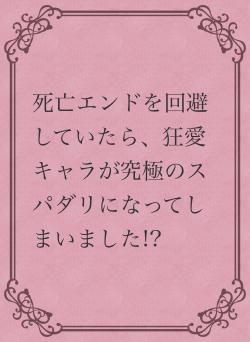私とルザークがいることに気づいていないのか、観葉植物を隔てたすぐ向こう側で気配がする。
「なんだか泣けてきちゃうわよね。健気というか何というか……公爵様に気に入られようと必死で」
「本当よねぇ」
それが嘲笑だとすぐにわかった。
言葉に労りの感情は一つもなく、分かりやすく言うならばすべての語尾に「(笑)」が付いている感じだ。
正直聞くに絶えないので省略するけれど、なんでも彼女たちは本館のメイドで、あわよくばクリストファーに見初められたいという期待を持っていたらしい。
そこに今まで放置されていた私が現れて、面白く思っていないようだ。
(……だからって、5歳児を妬むってどうなの)
呆れながら隣にいるルザークを見れば、とてつもなく冷めた目をして会話を耳にしていた。
横顔からでもわかる軽蔑をはらんだ瞳に不意をつかれ、私はぎょっとしてしまう。