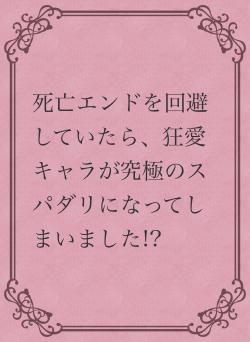「なんのようだ、ロザリン」
「遥々きた友人に歓待の言葉くらいくれよ。それとロザリンはやめろって何度言ったらわかる。リューカスだろ」
あろうことかロザリン侯と呼ばれたその人は、フレンドリーにクリストファーの肩を組んだ。
クリストファーの眉間が一瞬にしてにゅっと狭まる。珍しくわかりやすい顔だ。
(ロザリン……ロザリン……。どこかで聞いたことある気がするのに、思い出せない)
『リデルの歌声』に出てきた名前だっただろうか。今のところ聞き覚えがあるというだけで、それ以上は思い出せそうになかった。
それよりも、この人の存在の圧が凄まじい。
なんといえばいいのか。自信満々さが溢れていて、直射日光を浴びているような気分になる。
(クリストファーにここまで馴れ馴れしくできる人がいるなんて知らなかった。肩組んですぐに避けられてたけど)
謎の男リューカスの勢いに圧された私は、無意識のうちにクリストファーの脚の後ろに避難していた。
「…………」
そっと目の前の片脚に張り付くと、クリストファーがじっと私を見下ろす。
「ん? ……んん!? おい、まさかその子どもは……っ」
私を凝視する目は、驚愕と動揺を混ぜ込んだように忙しない。
(近い近い! 距離が近いなこの人!)
特に人見知りというわけではないけれど、見知らぬ男のどアップに慌てた私は、クリストファーの脚を片手できゅっと掴みながらも後ずさりをした。
いくらイケメンとはいえ、自分よりも遥かに体の大きい大人に迫られると反射的に飛び退いてしまいそうになる。
「暑苦しい、下がれ」
その時、私の頭に軽く手が添えられた。