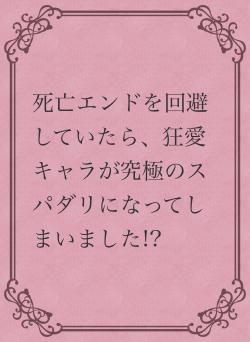気がしたというだけで、特になにかが起こることはなかった。
クリストファーは手に持っていたグラスを置いて、何気なく一呼吸を入れる。
そして天井に視線を流しながら背もたれに深く寄りかかった瞬間、聞こえた幻聴に耳を疑った。
『――お父様』
間違いなく、それはアリアの声だった。
すぐそばで発せられたような、妙に現実味のある声音に堪らず振り返る。
けれどそこには誰の姿もなく、クリストファーはゆっくりと瞬きを落とした。
「…………アリア」
なぜだろう。今朝はどうでもいいと思ったはずなのに、急に気になって仕方がない。
(…………風邪なんて、大したことないはずだ)
昼間にジェイドは言っていた。
アリアのことが心配ではないのかと。
たかが熱が高いだけで、何をそんなに心配する必要があるのかクリストファーには理解できなかった。
(死ぬわけじゃないだろう、あいつもいちいち大袈裟だ。…………そうだ、死ぬわけじゃ)
今も理解はできないのに、なぜかクリストファーの足は別館のほうへと向いていた。