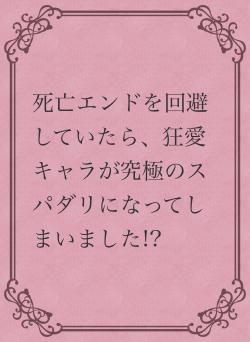(……なぜ、あの目は)
美しい紫の瞳。
今は亡き姉と瓜二つのその目を向けられるたびに、クリストファーは内側から湧き上がる焦燥感に苛まれた。
わからない。姉を蔑ろにした憎らしい侯爵の血を引くアリアを拒絶しているはずなのに、それとは別に生まれる感情の正体が。
『お父様、いい天気だね』
『今日もお父様に会えてアリア嬉しいな』
『お父様がお稽古してるところ見てみたいなぁ』
そのあどけない声は、心地よく響いている。
(高熱が続いているんだったな。医者は……)
ジェイドが出ていってから一貫して険しい表情を崩さなかったクリストファーが、ふとそれを和らげた瞬間。
"――お姉さま、お姉さま、どうして僕を置いて死んじゃったの……? うう、ううっ……そうだ、お前が産まれたからいけないんだ"
「……っ!」
アリアではない、子供の言葉。
小さな少年が涙声に囁いた途端、クリストファーの思考はひとつに染まる。
(…………いや。どうでもいい、はずだ。あれが、どうなろうと)
"そう、どうでもいいんだよ。だって、あの子は、僕の大切なお姉さまを奪ったんだから"