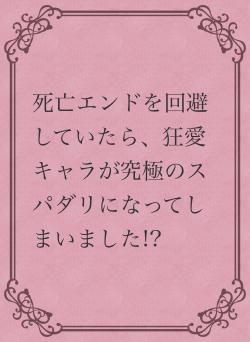シェリーにも悪いことしちゃったな。
こうなったのは私のせいなのに、責任は自分にあると頭を下げさせてしまったし。
「……。つらいのか?」
寝苦しさでうーうーと唸っていれば、突然サルヴァドールが人型になって顔を覗き込んできた。
「づらい……ずびっ」
「はは、ひでー顔」
「〜〜! って、いうか、人の姿……! もし、誰かに」
「大丈夫だって。誰か来たら、すぐにあのマヌケな姿に戻る」
途切れ途切れの言葉を汲み取ったサルヴァドールをじろっと睨む。
そんなに私の顔が面白いのか。だからって笑うことないのに。
(……でも、変なの。いつも通りでちょっと安心する)
シェリーも医者も凄まじい高熱だと顔面蒼白だったからか、少し不安になっていたみたいだ。
誰か一人でも普段通りの態度でいてくれると、精神的にも余裕が出てくる。
「……。なにか、してやろうか」
「へ……?」
不器用な声だけど、私を案じてくれるのがわかった。
自分のことを悪魔だなんだって言ってるけど、こちらを見つめる表情はとても人間味のあるもので。
私はサルヴァドールに向かって、笑みを浮かべた。
「じゃあ、ここにいて。誰かがくるまで、手も繋いでほしい」
「手って……ガキかよ」
「5歳、だもん」
「んな堂々と自分で言うかね」
そこから先は言い返す気力もなく、ぼんやりと見えるサルヴァドールにただへらりと笑うしかなかったけれど。
私が覚えている限りでは、意識を手放すまで右手に冷たい感触がずっとあった。