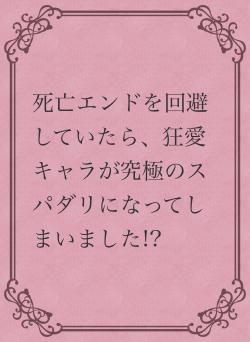***
愛嬌振りまき揺さぶり作戦を実行して二週間目の朝。
いくら苦言を漏らしたところで無駄だと悟ったのか、私が窓際で待ち伏せしていてもクリストファーは何も言わなくなっていた。
立ち止まる時間は相変わらず二分から三分前後と短いけれど、それでも私に関心を向けてくれている。
サルヴァドール曰く、その些細な意識こそが重要らしい。
「……」
「あっ、お父様、またねー! お稽古、頑張ってねー!」
少しの間立ち止まったあと、いつものようにクリストファーは無言で訓練所のほうへと去っていく。
私も慣れたと言わんばかりに遠ざかっていく背中に向かって手を振った。
「……ひっ、くしゅんっ」
シェリーに注意を受けてから暖かい格好で廊下に出るようにしているけれど、それでも外の空気に当てられれば体は冷えてしまう。
「お嬢様、お早く中に……」
朝の挨拶をやめない私を見て観念したシェリーは、自然とこの日課に付き添ってくれるようになっていた。
クリストファーへの挨拶が終わるとすかさず部屋の暖炉の前まで連れて行ってくれるのだ。
「シェリー、ありがとう……くっしゅん!」
「なかなかくしゃみが止まりませんね……さあ、こちらも羽織りましょうね」
「へへ、いっぱい着てるからアリアまん丸だね。なんか雪だるまみたい」
「ふふ、こんなに愛らしい雪だるまさんは見たことがありません。きっと公爵様もお嬢様の愛らしさに気づかれますわ」
父親に構って欲しくて必死になっている娘。
傍から見れば単純にそんな構図なのだろう。
だからシェリーも、私を無茶な行動を頭ごなしに止めることができないのだ。
「……ひっ、くしゅん! くしゅん!」
それにしても、なかなかしつこいくしゃみである。
心なしか頭がぼうっとして、体が火照ってきたような。
「……! お嬢様、失礼しますね」
不意にシェリーの手がおでこを包んだかと思うと、目の前の顔がサッと青ざめた。
「シェリー……?」
ぼやける視界。
名前を呼んだ声は、ひどくかすれていた。