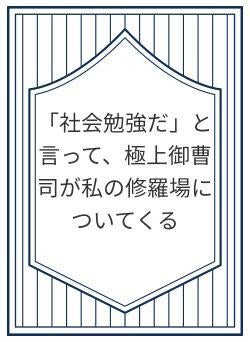「人が多くて疲れちゃいましたか?」
うわの空なのが丸わかりだったのか、琴子さんを心配させてしまった。
まだカートの中身は半分くらい。このままじゃ、今すぐに帰りましょうと気を使わせてしまう。
「このくらいなら、いつもホテルで見慣れてるよ。そうだ、夕飯作りは僕にも手伝わせて」
うまく話題をそらせただろうか。
琴子さんは、僕におかしな所がないか、確認するようにじっと見てくる。
目が合い続ける。まるで睨めっこだ。
ここが人が多く通る通路ではなく、あまり居ない缶詰めコーナーで良かった。
黙って見つめ合う僕たちの間には、さっき見た夫婦のような甘い雰囲気はないから。
ケンカだと思われても困ってしまう。
「それなら良かったです。じゃあ、せっかくだから二人で作ると楽しい料理にしようかな」
パッとさっきの不穏に似た空気は消えた。
二人で作って楽しいもの? 想像がつかないまま、キャベツを探しに行くという琴子さんの後をついていった。
日用品と食料品を買い込み外に出ると、じんっとしみるような寒さで身震いが起きる。
もうすぐにでも雪が降りだしそうだ。
「大雪って、大変ですけどわくわくします」
白い息を吐きながら、琴子さんが灰色の宙を見上げる。僕もつられて視線を上げる。
「小さい頃は、雪がシャーベットだったらいいのにって思ってました。それが学校に上がって、理科の勉強で雪には空気中のゴミが結構含まれてると知って……食べられないって知って落ち込みました」
小さい琴子さんが落ち込む姿。大人になって、物凄く落ち込んだ所で僕が声を掛けた日を思い出した。
雨上がり、夏の匂いのするぬるく湿った風が吹いていた。
あれから、二つ季節が過ぎた。
「僕は実際に、かき氷のシロップを雪の降った日に持ち出したことがある。夏に使った余りがずっと冷蔵庫に入っていたんだ」
夏の名残りのイチゴ味は、冬が到来しても冷蔵庫のドアポケットにしれっと並んでいた。
「えっ」と空から僕の顔に、琴子さんが視線を移す。
「それで、どうしたんですか。まさか本当に……」
「ここまできて食べない理由がない。新雪にドバドバとシロップを撒いて、思いっきり頬張った」
「あ、味は?」
「……強烈な久しぶりの甘みの中に、苦味も感じたよ。庭でそんなことをしたからすぐに母にバレて、しこたま叱られたけど」
真っ白な雪に撒いたショッキングピンクと、甘ったるい匂い。土の匂いに似た薄い苦い新雪の味。
いまでも鮮明に覚えている。
「なんだか、以前よりずっと、国治さんに親近感がわいてます……ふふっ、お義母さん大変だ」
くつくつと笑いを堪えている琴子さんの姿に、僕はやっぱりまた可愛いと思ってしまった。
うわの空なのが丸わかりだったのか、琴子さんを心配させてしまった。
まだカートの中身は半分くらい。このままじゃ、今すぐに帰りましょうと気を使わせてしまう。
「このくらいなら、いつもホテルで見慣れてるよ。そうだ、夕飯作りは僕にも手伝わせて」
うまく話題をそらせただろうか。
琴子さんは、僕におかしな所がないか、確認するようにじっと見てくる。
目が合い続ける。まるで睨めっこだ。
ここが人が多く通る通路ではなく、あまり居ない缶詰めコーナーで良かった。
黙って見つめ合う僕たちの間には、さっき見た夫婦のような甘い雰囲気はないから。
ケンカだと思われても困ってしまう。
「それなら良かったです。じゃあ、せっかくだから二人で作ると楽しい料理にしようかな」
パッとさっきの不穏に似た空気は消えた。
二人で作って楽しいもの? 想像がつかないまま、キャベツを探しに行くという琴子さんの後をついていった。
日用品と食料品を買い込み外に出ると、じんっとしみるような寒さで身震いが起きる。
もうすぐにでも雪が降りだしそうだ。
「大雪って、大変ですけどわくわくします」
白い息を吐きながら、琴子さんが灰色の宙を見上げる。僕もつられて視線を上げる。
「小さい頃は、雪がシャーベットだったらいいのにって思ってました。それが学校に上がって、理科の勉強で雪には空気中のゴミが結構含まれてると知って……食べられないって知って落ち込みました」
小さい琴子さんが落ち込む姿。大人になって、物凄く落ち込んだ所で僕が声を掛けた日を思い出した。
雨上がり、夏の匂いのするぬるく湿った風が吹いていた。
あれから、二つ季節が過ぎた。
「僕は実際に、かき氷のシロップを雪の降った日に持ち出したことがある。夏に使った余りがずっと冷蔵庫に入っていたんだ」
夏の名残りのイチゴ味は、冬が到来しても冷蔵庫のドアポケットにしれっと並んでいた。
「えっ」と空から僕の顔に、琴子さんが視線を移す。
「それで、どうしたんですか。まさか本当に……」
「ここまできて食べない理由がない。新雪にドバドバとシロップを撒いて、思いっきり頬張った」
「あ、味は?」
「……強烈な久しぶりの甘みの中に、苦味も感じたよ。庭でそんなことをしたからすぐに母にバレて、しこたま叱られたけど」
真っ白な雪に撒いたショッキングピンクと、甘ったるい匂い。土の匂いに似た薄い苦い新雪の味。
いまでも鮮明に覚えている。
「なんだか、以前よりずっと、国治さんに親近感がわいてます……ふふっ、お義母さん大変だ」
くつくつと笑いを堪えている琴子さんの姿に、僕はやっぱりまた可愛いと思ってしまった。