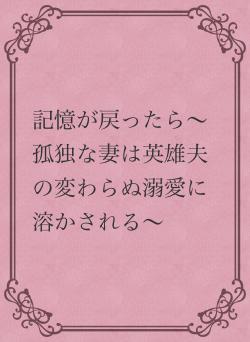子爵家令息の方と婚約を解消してから、私はすぐに隣国へ旅立った。
学園の手続きはお父様がして下さるそうだから、あとのことはお任せした。
隣国へは留学という形で行く。
その為、お父様の知り合いの伯爵家のお世話になる事にしていた。
まず伯爵家の方にご挨拶をすると、快く迎えて下さった。
その日のうちに新たな婚約者となる公爵様にも手紙で到着した事を伝えると、晩餐の前に速達でお返事が来た。
『来てくれてありがとう。すぐにでも会いたい。私はいつでも構わない。君の都合はどうだろうか?』
丁寧な文字で綴られたそれは簡素な内容なのに公爵様からの想いを感じた。
私は伯爵様とお話して、3日後に公爵様の元へ行く事にした。
『会えるのを楽しみにしている』
翌日返事を出して、その日のうちに届いたメッセージには、バラの花が添えられていた。
初めて誰かに貰ったバラの花は、私の気持ちを少しだけ慰めてくれた。
お会いした日、公爵様はとても喜んで下さった。
「待っていたよ、婚約者殿。早速俺の屋敷の中に案内するよ」
「ありがとうございます」
「じゃあ、行こうか」
にこにこ笑って、公爵様は当たり前のように手を差し出した。
私は躊躇って。
そっとその手を重ねた。
──家族では無い男性にエスコートされるのはいつ以来だろう。
あの方と夜会に行けたのは数える程。
社交界デビューは私のほうが先に産まれたから一緒に行けなかった。そのときはお父様がエスコートして下さった。
その後、年に一回の建国祭では流石に家族に説得されてエスコートして下さったけれど。
心ここに非ずのようでいつも何かを考えているようだった。
私を見て。
貴方の為に着飾ったの。
私を見て。
貴方の瞳の色のドレス、似合っているかしら?
合わない視線、開かない唇。
どうしたら私は貴方の瞳に映るのかしら?
「そう言えば、君の住む場所なんだけど」
公爵様の声にはっと意識を浮上させる。
公爵様のエスコートで、邸宅内のサロンに案内されたのだったわ。
いけないわ。
相手の話はちゃんと聞かなければいけないのに。
おろおろしてしまった私に、いつの間に隣に座っていた公爵様は穏やかに微笑む。
「君が良ければ、この公爵邸に来ないか?」
えっ?
「俺たちは婚約者になったんだし、将来結婚する為の花嫁修業として結婚前に一緒に住むことはよくあるし。
あ、部屋は勿論離すし、手は出さないと誓うから。
……どうかな?」
どうかな?と言われても……。
淑女として、はしたなくないかしら?
でも、彼は婚約者ではあるのだし、留学している間お世話になる予定の家が、婚約者の家に変わるだけ……になるのかしら?
「部屋は沢山余っているし。
結婚するまでまだ時間はあるけれど、少しでも君の事を知りたいし、一緒にいたいんだ」
思わず公爵様を見上げると、髪を一房取られて口付けられた。
「君が良ければ、だけど」
私は初めてされる行動、言われる言葉に戸惑いしか無かった。
だって、彼はこんな事しなかった。
こんな事言わなかった。
どんな顔をしたらいいか分からない。何て答えたらいいか分からない。
「滞在先の家の方に聞いてから……お返事してもよろしいでしょうか?」
駄目だと言われたらどうしよう。
拒絶されるのが怖かった。
けれど。
「もちろんだよ。滞在先は伯爵家だったよね。俺も一緒に挨拶に行こう」
何てこと無いように言うから、頭の中は『どうして』で埋められる。
「君はこの国に来たばかりで戸惑う事が多いだろう?
君には色々とこの国の事知ってほしいし、好きになってほしい。
だから俺が君にこの国を紹介したい。
この国の人たちにも、君を紹介したい」
その笑顔は眩しくて、私は後ろめたくなった。
私がここに来たのはあの方に絶対に会わないようにする為だったから。
母国に残っていたら、またあの方に迷惑をかけてしまう。
婚約を解消したと言うのに私の中に残るあの方への想いの残骸はまだ燻り続けていて、本当は今すぐ飛んで行きたい。
でも、彼が選んだのは私ではなかった。
それに、偶然にも会ってしまったら、また望まれない気持ちを押し付けてしまうんじゃないかと思うと否定できない自分が怖かった。
あの方から遠い場所に行きたかった。
遠い場所に行けるならどこでも良かったし誰でも良かった。
遠い場所に行きたい時に、タイミング良く現われたから縋っただけ。
……だから、公爵様をまっすぐ見れなかった。
「前向きに考えて。
じゃあ、お茶でも飲もう。
お菓子も君の為に色々用意したんだ。
どれか一つでも気に入るのがあると良いんだけど」
テーブルには様々なお菓子が沢山並んでいた。
公爵様が私を歓迎して下さっているのが伝わってくる。
「あの……ありがとう、ございます…、その……。
先日頂いたバラも、こうしてお菓子をご用意して下さったのも、とても…嬉しいです」
ここまで私をもてなして下さって戸惑う事しかできてないけれど。
公爵様はきっと、お優しい方なのだろう。
「どういたしまして。遠慮はいらないよ。君は俺の婚約者になったんだから、これからは君に沢山贈り物をしたいんだ」
「公爵様……」
「アイザックだよ」
公爵様は私の手を取り、見つめてくる。
「アイザック・カーティスだ。
これからは俺の名前を呼んでほしい」
公爵様──アイザック様は、愛おしそうにそう言った。
「わ、私はっ」
私も名前を言おうとしたけれど、アイザック様に人差し指で止られる。
「君の名前を呼ぶと、俺は一線を越えたくなってしまう。
まだ婚約者だった彼を忘れられないだろう?
君に無理強いはしたくないんだ。
だから、君が自然に俺の事を愛しいと、好きだと思えるようになったら、改めて名前を教えてほしい」
アイザック様は優しく、本当に優しく、微笑む。
どうして、こんなにも、私を考えてくれるのだろう。
どうして、こんなにも、初めての事を沢山くれるのだろう。
「分かり、ました…。
その時が来たら、呼んでください」
アイザック様は、いつの間にか私の頬を伝う雫を指で拭って下さった。
その指がとても温かくて。
でも、あの方とは違う指で。
どうしようもなく悲しい気持ちがあるのに。
どうしようもなくほのかに嬉しい気持ちが芽生えて。
私は、目の前にいる方から貰える沢山の初めてに、戸惑うしか無かった。