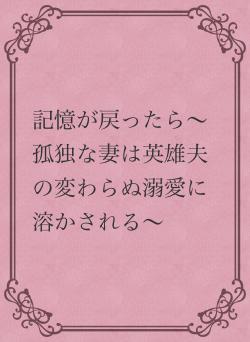「リロイが婚約したらしいよ。お相手は侯爵様からの紹介で、侯爵令嬢の従姉妹に当たる女性らしいよ。
結構仲良くやってるみたいだね」
「……そう」
何の感情も無く休日の義務として開かれる夫婦のティータイム。
お茶を飲んでいると、夫となった男が言った。
リロイとは幼馴染みの子爵家嫡男。
つまりあいつのお兄さんで、私の初恋の人。
あれを最後に会えてない。
結局、私は同級生だった男爵家嫡男と結婚した。
呆れた両親が持ってきた最初の縁談相手が夫だった。
初恋は終わったし、侯爵令嬢の婚約を駄目にした私を、初婚で貰ってくれる相手がいるのはマシな方だった。
正直、相手は誰でも良かった。
好きだった人からは「会いに来るな」と言われたから。
ちらりと相手を見てみる。
服はパツパツで今にもボタンが弾け飛びそう。
顔は白くてまんまる。まるでむきたての茹で卵みたい。
でも、髪はくるんくるんの金髪、瞳はきれいな紫色。
食べる事が何より好きだという彼は、学生時代から私の事を好きだったと言っていた。
「ばっかだねぇ、君も。同情と愛情を履き違えなければ、今頃リロイとどうにかなってたかもしれないのに」
「……ならないわよ」
最後に会った時の冷たい目を思い出してぶるりと震える。
心底軽蔑した、って顔してた。
私はあの人の信頼を裏切ってしまったのだ。
「……今だから言うけどね、リロイは君の事初恋だって言ってたんだよ」
「……え……」
目の前の夫は、不思議な事を言った。
「リロイも気持ちを伝えられてたら良かったのにね。
そしたら、君も弟クンを相手にしなかったんじゃない?」
「……そん、な……」
どうして、今更。
そんな、残酷な事実。
幼馴染みと侯爵令嬢がうまくいってたら、私は……。
「君は優しい。幼馴染みだからってだけで彼の逃げ場を作ってあげた。
でもそれって愛情から?それとも同情?」
「そ、れは……」
「幼馴染みが侯爵令嬢より君を優先してて、ちょっと優越感とか感じてたりして?」
「そ、んなわけ、ないじゃない!」
反論したいのに、喉が張り付いたみたいに気持ち悪い。
そんな、優越感とか、最低な考え、あるわけないと思うのに。
「ふうん。じゃあ、ただ純粋に幼馴染みだけを心配してたんだ。……君って優しいね。
その優しさが、時に残酷になるのにね」
そう言ったあと、紅茶の入ったカップを傾け、再びソーサーに戻してからお菓子に手を延ばした。
「……あまり食べ過ぎない方がいいんじゃない…」
何個目かのカップケーキに手を伸ばしかけた夫をチラリと見てから独り言のように呟いた。
「美味しいよ、これ。君も好きだろう?」
「好きだけど、食べ過ぎは良くないし……」
「ははっ、僕の事心配してくれるのかい?」
心底驚いた、みたいな顔をして、夫は笑う。
私が心配したのが信じられないとか失礼な。
私だって人並みに夫となった人を心配する事もある。例えそこに愛はなくても。
「まぁ、建前だけだよね。偽善でも何でも、とりあえず僕を気にしてくれてるんだね」
「偽善とかじゃ……」
「君は優しい。幼馴染みに対しても、僕に対しても。
誰彼構わず愛想を振り撒いて、良かれと思って押し付けて、そこに発生する感情には無責任」
夫の言葉にぞくりとした。
「酷いよね。それって善意の押し売りだよ。
自分が気持ち良くなりたいだけだ。
巻き込まれた方はたまらない」
穏やかに、優しく言ってるだけなのに。
何だか責められてるみたい……。
「どうして……責められないといけないの?
苦しんでた人を助けただけじゃない。
嫌だって言うから逃げ場を作ってあげた。
苦しいって言うから庇ってあげた。
頼って来たから、幼い頃にやってたみたいにしてあげただけよ。
それが駄目だって言うなら、どうしたら良かったのよ!
だいたいあの方だって、彼の事何も考えず一方的だったじゃない……」
巻き込まれたのは私の方じゃない。
二人で解決できなかった事を私が壊したみたいに言わないで欲しい。
「君たちはそれでいいかもしれないね。
でも、侯爵令嬢は誰かに辛いって言えたのかな」
「……っそんな、のっ、誰か、いるでしょ……」
「僕たち低位貴族と違って、国の顔としても社交に駆り出され、跡継ぎとして、淑女の手本として常に気を張ってなきゃいけなかった彼女が、唯一弱音を吐けるはずの婚約者は常に別の女性と一緒にいた。
愛を乞いたい相手が、自分じゃない人を抱き締める。
──辛いって言えたのかな」
「私たちはそんな関係じゃ……」
「それを知るのは本人たちだけ。
君たちは傍目から見たら侯爵令嬢に引き裂かれそうな愛し合う二人だったよ」
『事実はどうであれ』
夫はそう言った。
「君たちは、そうだね。依存関係だった。互いの利害が一致しただけ。
依存は何も産まないよ。互いに身を滅ぼすだけだ。
それに『自分がいなきゃ相手がかわいそう』って、それはただの同情。
作って#あげた__・__#、庇って#あげた__・__#、して#あげた__・__#。
君は優しい。
優しすぎて、二人の仲を壊してしまった」
夫の言葉に何も言い返せなかった。
優しくしたことが罪になるなんて思わなかった。
幼馴染みの婚約を壊し、侯爵家との繋がりが無くなった事でお兄さんは政略結婚をする事になった。
もし、ちゃんと彼を突っぱねられてたら。
婚約者と話し合えと説得できてたら。
──せめて、彼女にだけは誤解されずにいたならば。
私とお兄さんが結ばれる未来もあったのだろうか。
初恋を実らせる事も、できたのかな。
でも、もう全ては終わってしまったこと。
謝罪も懺悔もさせて貰えない。
どうして気付かなかったんだろう。
関係ないなんて言えなかった。
女である私が、男である幼馴染みの逃げ場になる事は、侯爵令嬢からしたら大好きな人を奪う存在でしかなかった。
彼に自分に向いて欲しくて、必死に頑張って。
それを微笑ましいなんて他人事みたいに捉えていた自分が恥ずかしくなった。
自分の存在が彼女からしたらどれだけ不安を与えているかなんて、考えられなかった私はどうしようもないバカだ。
同時に、否定できないある種の優越感にも気付き苦いものが押し寄せてくる。
低位貴族の私が高位貴族の彼女より選ばれる事に仄かな喜びを感じていたんだ。そんな醜い感情に気付きたくなかった。
『幸せに、なって』と潔く身を引いた彼女の方がよほど優しい。
ただ相手の幸せを願って最終的に己を戒めた彼女がどれだけ彼を好きだったのか思い知らされた気がした。
彼女からなんの咎めも無く、責められない事が苦しいなんて思ってもみなかった……。
「……まあ、君が壊してしまったことで、皮肉にも僕は君と結婚できたんだけどね」
そう言った夫の目が優しくて。
何だか泣きそうになった。
「僕はこんな見た目だろう?君だけだったんだ、優しくしてくれたの。
分け隔てなく接してくれたのは、君だけ」
「私は優しくなんてない……。あなたの言う通り、ただの偽善者だわ」
「僕は君が好きだよ。
優しくて、残酷で、愚かな君が。惚れてしまったから仕方ないね」
本当に優しいのは、あなたの方だ。
バカな私を悟してくれる。そっちの方がよほど思いやりを感じる。
「……それは愛情?それとも同情?」
「勿論愛情だよ。これからもよろしくね、奥さん」
夫がにっこり笑ってまたお菓子に手を延ばそうとしたので、私はその手を握った。
「愛情なら、お菓子は程々にして、長生きしてください」
きょとんとした夫は、やがて。
とても優しい笑顔を見せた。
今の私にはその笑顔が眩しくて、真正面から見る事ができなかった。