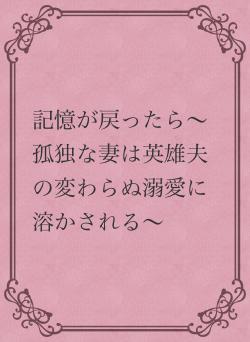一週間自領内を回って、そこかしこに感じた侯爵家からの恩恵を見て有り難さと申し訳無さがごちゃまぜになっていた。
作物の品種改良、農業用治水対策、河川の氾濫対策。
候爵家からの援助は領地内でしっかり活かされていた。
候爵様と、彼女の指示らしい。
「素晴らしい手腕だったよ。領民と話し合い、ぶつかり合い、結託して、次々と変えて下さった。おかげで生活に余裕ができて領民の表情が和らいだ。
侯爵様は今でも時折ご指導下さっている」
驚いた。
僕と彼女の婚約が解消されて、侯爵家とは疎遠になったとばかり思っていたから。
「ものすごく厳しい御方だ。だけど、ちゃんと道筋を示して下さる。気付くまで、辛抱強く」
一番尊敬している、と兄は言った。
……何だか。
「兄さんが彼女と婚約すれば良かったね……」
そうすれば、きっと、僕より彼女を尊重して、いい夫婦になれたんじゃないかな…と思うと胸が痛くなった。
「俺も心からそう思う。お互い跡取りだからというのもあったんだが、もし俺が婿入りしたらお前が子爵領を、と思うと、領民がな…。
……それに、侯爵令嬢が選んだのはお前だった。どこが良かったのかは分からん。俺の中でも永遠のテーマになりそうだ。
侯爵令嬢が10人いたら9人くらいは俺を選ぶんじゃないか?
……お前を選んだのは残りの1人だったんだよ」
何だその例えは、と思わず苦笑した。
だけど、そうか。
誰も僕を選ばない中で、唯一、彼女は僕がいいと言ってくれたんだ。
僕が幼馴染みに縋っても、それでも、僕を選んでくれていたんだ。
「……どこが、良かったのかな…」
「さあな。彼女にしか分からない何かが良かったんだろう。普通なら婚約者を無視する男なんか願い下げだろ。
……あ、そうか。だから婚約解消されたんだったな。すまんすまん」
本当にこの兄は傷口に塩を擦り込むのが好きだな。
でも、彼女に対して何もしなかった自分はやはり、彼女みたいな女性とは釣り合わない。
僕には勿体無さすぎる。
「解消されて、良かったんだよ、きっと」
言ったあとで、目元が霞む。
彼女を想って胸が痛むのは執着か、恋心か。
確かに好きだと思ったのに、それは愛では無かったのか。
自分の気持ちなのに曖昧で不確かで。
たった一つだけ、ここに彼女がいない事が辛いのは確かだった。
「ここは?」
「侯爵令嬢がよく来ていた孤児院だ」
視察の最終日。
僕たちは真新しい建物の前にいた。
「新しい建物だね」
「ああ、婚約解消で頂いた慰謝料で建て直したからな。侯爵令嬢が一番気にしていた場所だ」
中に入ると広いエントランスからいくつかの扉が見えた。
かすかに子ども達の声が聞こえる。
兄はつかつかと中に入り、迷わず扉に手を掛けた。
「失礼するぞ」
「まあまあ、いらっしゃいませ領主様。……そちらは、例の…」
「ああ、俺の弟だ。ジメ男とでも呼んでくれ」
「あらまあ」
流石に反論しようとしたけど、もう何だか半分諦めた。
「はじめまして、……ジメ男です」
「……どうも。ここの院長です」
戸惑いがちな院長さんと挨拶を交わす。
兄さんが変な事を言うから笑顔が強ばってるじゃないか。
僕たちは院長に案内されて、中を見て回った。
食堂、遊戯室、勉強する部屋、子どもたちの部屋。
子ども達が安全に自由に過ごせるように配慮がなされている。
「たまにここに来ては子どもたちに読み書きなどを教えてくれていたようだ。
まあ、侯爵令嬢も自領内の事があるから頻度は高くは無いがな」
そうだ。
彼女は侯爵家の跡取りで。
自領の事もあったはずなのに……。
「ねぇねぇ、あのお姉ちゃんもう来ないの?」
いつの間にか足元にいた小さな女の子が服の裾を引っ張っていた。
「あのお姉ちゃん……?」
「お空みたいなキレイなおめめのお姉ちゃん。
時々来てご本を読んでくれてたの。
……でも、こないだ来たとき、『約束したのにごめんね』って言ってたの」
「やく……そ、く……?」
小さな女の子はこくりと頷く。
「お姉ちゃん、領主様の弟と結婚するから、また時々はここで遊ぼうね、って言ってたの。
でも、もう、できなくなっちゃったって……。
ねえ、お姉ちゃんもうここに来ないの?」
僕は瞳の潤んだ小さな女の子に何も言えなかった。
僕が勝手だった事で、彼女だけじゃなく、見知らぬ誰かも悲しい思いをするなんて想像もしてなかった。
「……ごめん……、もう、お姉ちゃんは、遠い所に行って、来れないんだ……」
僕は震える声で女の子に告げた。
自分に対しての情けなさに涙が止まらない。
立っていられなくて、その場にしゃがみこんだ。
「お兄ちゃん、大丈夫?どこか痛い?」
女の子は必死に小さな手で頭を撫でてくる。
その仕草は拙いのに、温かな気持ちになる。
こんな小さな子でも、誰かを思いやれるのに。
僕はたった一人すら思いやれなかった。
もっと、彼女を見れば良かった。
彼女と話せば良かった。
自分が、自分が、ってそればかりで、何も見えてなかった。見てなかった。
ちゃんと会って話していたら、彼女が僕の分まで気を回してくれていた事に気付けたかもしれないのに。
侯爵家だけじゃなく、子爵家の事まで考えてくれていた彼女に感謝しこそすれ、無視していい訳が無かったんだと、今更ながら当たり前の事に気付く。
どれだけ彼女を傷付けた?
こんな僕をずっと好きでいてくれた彼女を、どれだけ裏切っていた?
彼女の言葉をいい様に解釈して、八つ当たりして。
それでも好きだと言ってくれてた。
そして、最後は。
『幸せに、なって、』
僕の、幸せを、
ただ、ねがって、、
身を引かせた。
彼女のせいじゃないのに。
自分のせいだと、思い込ませてしまった。
「ごめん……ごめん、……────…」
もう、届かない。
謝罪も、僕の気持ちも。
彼女は隣国に行ってしまった。
僕の後悔は、虚しく響くだけだった。
「兄さん、僕は、変わりたい」
帰りの馬車の中で、兄に告げる。
「……まあ、『保存しておけばいつかは使えるかもしれないゴミ』にまでは成長したのか。及第点はくれてやる」
「……ありがとう」
「お前が無駄に過ごした時間を必死に取り戻すんだな。
分からなかったら聞け。自分の足で学べ。
せめて、侯爵令嬢の見る目が無かったなんて言わせないくらいには成長しろ」
「……うん。彼女がいつか『好きでいて良かった』と思って貰えるように頑張る」
「まあ。一つだけ、何かに集中して取り組める事はお前の良い所じゃないか?
誰の言葉にも耳を貸さず、頑なに突っ走れる集中力だけは、……いや、良い所じゃないな、これは」
「これからはちゃんと聞きます」
「せいぜい頑張れ。
死んだら土に埋めるくらいはしてやるよ」
もう兄の言葉には苦笑いしか出ない。
でも、見捨てないでくれるだけありがたい。
僕には何の取り柄もない。
英雄でもないし、天才でもない。
欠点しかないし、良い所も少ない。
でもそれを逃げずに受け入れていくしかないんだ。
随分回り道をしたけど、これからはちゃんと、向き合おう。
そして、いつか。
いつになるか分からない。もしかしたら来ないかもしれない。
でも、いつか、もし彼女に出会えたら。
「ありがとう」と伝えたい。
「好きになってくれて、ありがとう」と。
その頃には彼女はもう、隣国の公爵と、幸せになっているかな……。
いまはまだ、その姿を想像すると鼻の奥がツンとする。
でも、いつかは思い出になるように。
僕は僕なりにあがいてみようと思う。
そして、いずれは幸運を体現できるように。
僕はスカーフに刺繍されたクローバーを、そっと撫でた。