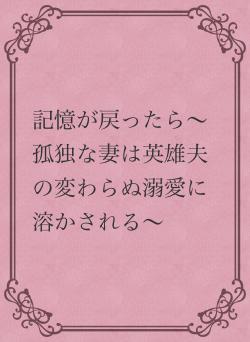結局僕は、卒業してから兄の仕事を手伝う事になった。
元婚約者の彼女が隣国に留学したと聞いて、ずっと無気力で。
何をするにも手が付かなくて、見かねた兄が手を差し伸べてくれたのだ。
少しずつ、少しずつ。
重しが付いた足を前に動かすように進んでいく毎日。
夢中で仕事をして、ふとした瞬間思い出す彼女の最後の笑顔。
夢に出てくるのは初めて会った頃のこと。
好きに振る舞う彼女をちょっと注意したら、顔を真っ赤に染め上げて。
『あなた、私を誰だと思ってるの』
強い口調なのに、その姿が可愛くて。
『可愛いな』
そう言ったら、一ヶ月後には婚約が整っていた。
ちょっと可愛いと思っていたし、彼女から「好き」「大好き」と笑顔で言われれば段々その気にもなってくる。
だけど、学園の勉強と並行して領地経営の勉強を始めると段々彼女といる時間も減っていった。
僕は頑張っているのに、彼女はいつもお茶会とか買い物とか気楽な事ばかり言って。
「私との時間も作ってくださいませ」
ぷぅと頬を膨らませてそんな事を言う。
最初は可愛いと思っていた。
「仕方ないなぁ」って、彼女のワガママを聞いていた。
だけど、段々勉強の内容が難しくなってくると理解するまでに時間がかかる。
次第に彼女のワガママが、責められてるように感じてしまうようになった。
友人たちでさえ。
「最近付き合い悪いよな。婚約者の相手が忙しいのか?羨ましい事だよ」
違う。相手にしているのは家庭教師だ。
「将来安泰だな!侯爵家の当主だろう?」
当主は僕じゃない。彼女だ。
「俺にも高位貴族令嬢を紹介してくれよ~。この際愛人でもいいから!」
愛人なんかに成り下がる奴なんか!!
ふざけるな!
「……僕は勉強で忙しいんだ。君の相手はしてられないんだ」
「えっ?でも、……結婚したら私が全部するからいいのよ?」
彼女が微笑む。
それって僕は
必要ないって事?
君にとって、僕は、ただの飾りなの?
僕の事、本当に好きなの……?
「大好きよ」
嘘つきじゃないか。
──また、同じ夢。
「酷い顔だな。眠れなかったのか」
兄が朝食を食べながら聞いてくる。
初めてじゃないし、もう何度もこんな状態があったから驚きもしてない。
「兄さん……僕は……どうしたら良かったんだろう」
婚約が解消されて、何度も自分に問い掛けた言葉。
最初は良かった。「好き」だけで頑張れた。
彼女の隣に立てるように、それだけが支えになった。
だけど、高位貴族との違いが明るみになる度、僕は押しつぶされて自信が無くなっていった。
だけど、兄の手伝いをするようになって。
実際に領地を経営する事、領民を守る事の難しさが分かってきて、生半可な気持ちじゃ無理だと思った。
同時に、自分がどれだけ甘い考えだったのか痛感した。
彼女は産まれた時から跡継ぎとして幼い頃から勉強していて。
その環境が当たり前だったから余裕そうに見えていただけだったんだ。
「……そうだな。お前が気付かなければならなかった事はいくつかある」
兄は持っていたフォークとナイフを一旦置き、ナフキンを口に当てた。
「まず、気安い関係だからと幼馴染みに……女性に縋ってはいけなかった」
「……それは」
彼女がいいと言ったし、当時の僕には同性の頼れる友人がいなかった。
だから幼馴染みに頼ったんだ。
元婚約者との婚約が整わなければ幼い頃の約束で……
いや、そう思っていたのは僕だけだったな。
幼馴染みは別の男の元へ嫁ぐ予定だ。
「お前たちが気安い、互いに友情以上のものを感じていなくても、周りはそうは見ない。
お前を好きだと言う婚約者を放っておいて別の女性と親しくする。
それは婚約者から見たら、どう映る」
「彼女はいいと言った!でも僕はそんな不誠実な男にはならないと……言ったし…」
「お前は誠実な男だったか?
いくら婚約者がいい、と言っても、それを鵜呑みにするのは愚か者のする事だ」
僕は顔を歪ませた。
だって、じゃあそれなら何故、彼女はそれを肯定したんだ……。
嫌だって、本当は嫌だって、言って、くれたら……。
「第三者から見たお前は、愛情を寄せる婚約者を蔑ろにし、別の女性と親しくしている男だった。
友人たちは何と言った?どうして離れた?」
『君は婚約者に対して不誠実な男だ。……見損なったよ』
『婚約者の事、好きじゃなかったのか?見てられないよ、ずっとお前を探してるんだ』
『ちゃんと話し合えよ。結婚するなら逃げるな』
「……………苦しかったんだ。何もかも。
彼女の想いも、友人たちの忠告も」
「一度でも、それを侯爵令嬢に言ったのか?」
「独りになりたいって言ってた!」
「相談しなかったのか?」
相談?
「──相談、なんか、したら……
情けないじゃないか……。僕は……それこそ彼女にとって、必要ない男になる……」
「夫婦になるなら向き合う事が大事だろう?
『健やかなるときも、病めるときも』
夫婦は、良いも悪いも分かち合う事を誓うものだ。
一人じゃ乗り越えられなくても、二人なら知恵を出し合って協力できるだろう。
そうするのが、夫婦になると誓った者ではないのか?
お前は、侯爵令嬢を信用してなかったのか?」
──ああ、そうだ。
僕はずっと彼女の想いを疑っていた。
信用できなかった。
全てを肯定してくれる彼女が怖かった。
相手の全てを許容できるなんて、僕には無理だったから。
同じ量の想いを返せる自信が無かった。
「それでも…………好きだったんだ…」
今でも変わらない。
彼女が隣国に行って僕じゃない男と結婚するとか想像しただけで苦しい。
「……忘れろ。お前は侯爵令嬢を手放したんだ。遠い場所から彼女の幸せを願え」
「願えるわけないじゃないか!!」
「……だから解消されたんだ。相手を思いやれない、信用もできない結婚なんかしてもお互い不幸になるだけだ」
兄の言葉が僕を抉る。
彼女に信用も、思いやりも無い。
僕たちの婚約は、彼女の気持ちだけで辛うじて繋がっているだけだった。
「苦しいんだ、兄さん。どうしたら……」
「苦しいのはお前だけじゃないだろう。
侯爵令嬢もきっと苦しんでる。だがお前の幸せを願って身を引いたんだろう?
ならば自分で幸せを探せ」
『幸せに、なって、』
彼女はそう言ったけれど。
なれるわけないじゃないか。
なぜなら僕の幸せは
彼女と笑い合っている事なのに。
だけど僕は
自分で手放したんだ。
だから、ずっと後悔し続けてる。
彼女の気持ちに応え無かった事に。
ずっと、無視して逃げ続けてしまった事に。
『好きだ』と言えずに終わってしまった恋を、ずっと手放せずにいる僕は、幸せになれるのだろうか。