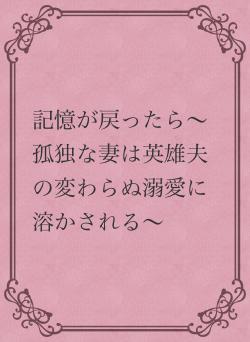【side 元婚約者幼馴染み】
結婚して数年が経過した。
案外私たちはうまくやっていると思う。
「ニコ、ホラ早く!始まっちゃうわよ」
「待って、待ってよアルマ」
どすどすと音を立てそうなくらいの大きな身体で夫が一生懸命に走ってくる。
ようやく追い付くと、膝に手を付いてぜいぜいと息を整えた。
「大丈夫?息整えて」
「はぁ、も、へき。ふぅ、本気で減量しなきゃかなぁ」
「えっ?本気なの?」
「君はどっちがいい?」
「どっちでもいいわよ。今のあなたに愛着湧いちゃったし。
……でも長生きはしてほしいから…」
「ははっ、そうか。あっ、そろそろ席に行かなきゃ」
「ええ、行きましょう、あなた」
そう言って、腕に手を添えると。
「今日の歌劇は隣国で何度も再演された演目らしいよ」
「それは楽しみね」
私たちはにこやかに劇場へと入って行った。
~~~~
【side エヴェリーナ】
「リーナ、お客さんだよ」
夫に呼ばれ、息子を乳母にお願いして簡単に身支度をした後、応接間に出向いた。
「お姉様、お久しぶりです!」
輝かんばかりの笑顔で迎えてくれたのは従姉妹のクレアだった。
クレアの弟が侯爵家を引き継いでくれたので縁も深まったのだ。
「久しぶりね。元気にしてた?先触れ貰ってから楽しみに待っていたのよ。今日はどうしたの?」
そう言うとクレアはソファに座った男性に目を向けた。
「お久しぶりです。覚えてらっしゃいますか?」
その男性は知っている。
若い頃に縁があった方だ。かつては彼の領地経営に色々と口を出してしまった。
クレアと結婚した──リロイ様。
私の婚約者だった方のお兄様。
こうして見ると、やはり兄弟だわ。彼が大人になったらこんな感じなのかな、でも少し違うような気もするわ、とぼんやり考えた。
「ええ。覚えていますわ。お久しぶりですね」
笑顔で応える。
夫の支えで笑えるようになった私は、これ以上彼の面影を探す事は無い。
私と夫、クレアとリロイ様は暫く談笑した。
何かを話したそうにしているクレア達の事は気になったけれど、言い出さないのは大した話では無いのかもしれない。
そんな中、応接室の扉がノックされる。
入室を促すと困り顔のメイドが申し訳無さそうにやって来た。
「奥様、すみません。坊っちゃまが泣きやまなくて」
「あら、すぐ行くわ」
もうすぐ一歳になる息子は寝る前に大泣きするのがお仕事だ。
時折乳母では手に負えない事があり、そういう時は私が抱くと泣きやんでうとうとしだす。
なのでこうして呼ばれる事はたまにあるのだ。
「ごめんなさいね、ゆっくりしててちょうだいね」
「ええ、……お姉様、幸せそうで良かったわ」
突然、クレアが感慨深そうに言った。
だから、私はとびきりの笑顔を見せる。
「ええ、とても幸せよ。愛する夫がいて、子どもたちもいるから。……と、行くわね」
「良かったわ。坊やたちによろしくね」
クレアたちが来てくれたのに退室するのは気が引けたけれど、息子が気になったので部屋をあとにした。
~~~~
【side アイザック】
「実は……今日は夫人に渡したい物がありまして」
妻が退室した後、リロイ様は躊躇いがちに口を開いた。
そして、差し出されたのは、手紙の束。
少し色褪せたものから、新しいものまで。
誰が、誰に宛てたものなのだろう?
「これは……弟が、夫人に宛てた手紙でした」
その言葉に息を飲む。
「今日、弟は……どうしても外せない用事で来れなくて。
なので、預かって来ました。
もし、不要であれば処分して下さい」
リロイ様と、奥方は緩く笑んだが、俺に捨てる事はできないだろう。
……本人が来たなら追い返してやるのに、全く。
「折を見て渡します。それでよろしいでしょうか?」
「ええ。……すみません」
何かを堪えるような彼の様子に、俺は一つの予感がした。
~~~~
【side エヴェリーナ】
「リーナ、っと、寝たかい?」
「あなた……、ええ、今ベッドに寝せたところよ。クレアたちは?」
「他に用事があるからって帰ったよ」
「そう。何だか申し訳無いわ」
「大丈夫だよ、子どもの事だから分かってくれるさ」
夫はそう言って、瞼に口付ける。
そうして抱き締めてきた。
私も自然な動作で背中に手を回す。
そうするととても幸せな気持ちになるのだ。
「リーナ、愛しているよ」
「ザック、私も愛しているわ……。
どうしたの?突然」
「突然かな?でも、言いたかったんだ。
これからもずっと、君を愛しているよ」
夫は一層、強く抱き締めると、ゆっくりと離れる。
見上げると、少し寂しそうな瞳をしていて、どきりとした。
「そうだ、君にって預かったよ」
「私に?」
そうして受け取ったのは手紙の束。
預かった、という事はクレア達から?
受け取ってみると、差出人の名前も宛名も何も無い青い封筒。
「リーナ、サロンに行こう」
「ええ……」
確かに息子が寝ているし、読むとしてもここじゃ落ち着かないわね。
乳母に息子をお願いして、私は夫のエスコートでサロンに移動した。
侍女にお茶を準備してもらい、早速手紙を開いた。
そこに書かれていたのは懐かしい文字。
もう見る事は無いと思っていた、あの方の。
その人柄が表すように力強く、かつ柔らかな文字を私はなぞっていく。
書かれていたのは日記のような報告書のような。
今日はどこに視察に行って何をしたとか、誰に何を言われてどう思ったとか。
彼がどう過ごして、どう感じたのかを感じ取れるものだった。
かつて私も行った子爵領の事で、読んでいると一緒に周っているような錯覚を起こす。
それは叶えられなかった夢。
今は遠い記憶となったもの。
読み進めて、最後の1通を開くと。
それまで読んだものとは違う、私宛の内容だった。
『侯爵令嬢様
貴女に届く事の無い手紙を書く事をお許し下さい。
僕は、貴女の事が好きでした。
僕と、婚約してくれて、本当は嬉しかった。
素直になれず、ごめんなさい。
僕は貴女を沢山傷付けました。
許されるとは思っていません。
僕を憎んでくれても構いません。
こんな僕を好きになってくれて、ありがとう。
出会ってくれて、ありがとう。
貴女に出逢えた事が、僕にとっての幸せでした。
貴女が、これから先ずっと幸せでありますように。
遠くから祈っています。
フェリクス
追伸
───────』
最後の文字は何かで濡れて滲んでいた。
少しだけしわになった便箋は、書いたあとで捨てようとした名残だろうか。
ぽたりと、手紙を持つ私の手を雫が濡らす。
夫は何も言わず、抱き寄せた。
優しく、私の頭を撫でる。
「あなた……、私、あなたに会えてよかったわ」
だから、私も、願うわ。
貴方の幸せを。
フェリクス様。
追伸の答えは──────
窓の外に広がる青空に、貴方の笑顔が見えた気がした。
~~~~
【side クレア】
その日の前からずっと雨が降り続いていた。
どんよりした雨雲を見上げていると、執事が慌てて手紙を持ってきた。
その内容は、領地で災害の恐れありというものだった。
災害が起きたのか、これからなのか。
領民は無事なのか。
確かめなければならないけれど、夫は王城へ報告書を提出に行って不在だった。
だから、弟であるフェリクス様が「自分が行って確かめてくる」と言い出したのだ。
「待って、危険よ。せめてリロイが帰って来るまで……」
「義姉さん、危険だからこそ、領主が把握して指示しなきゃ。兄さんがいない今、僕しかいない」
「もし貴方に何かあったら…!」
「ありがとう、義姉さん。でも僕は、領地を、領民を守りたいんだ。彼女が残していってくれたものを。だから、行くね」
ずっと、彼が領地の為に身を粉にして働く様を見てきた。
非常事態に、彼が行きたいと思う気持ちもよく分かる。
私には漠然とした予感があった。
妙な胸騒ぎがしている。
今ここで止めなければ、と何かが叫ぶのだ。
けれど、義弟を止める事はできなかった。
「帰って来なさい。リロイの為にも……、まだまだ貴方は必要な人よ」
「ええ、分かってます。じゃあ、行ってきます」
光の中に消えた義弟は、とても幸せそうに笑っていた。
~~~~
【side フェリクス】
真っ暗な中、僕は光を見付けた。
きっと、すぐ側にあった希望の光。
とても温かくて、満たされる、優しい陽の光。
灼熱の想いで焦がれ、手放してしまったそれが優しく僕を包み込む。
やがて形作られ、僕が求めていたものに変わった。
『はじめまして、私はエヴェリーナよ!』
『僕はフェリクス。よろしくね』
幼い僕たちは、無邪気に笑いながら手を取り合って。
一面の真っ白な花畑に駆け出した。