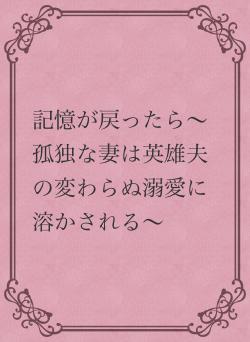「じゃあ、行ってくるよ」
「行ってらっしゃいませ、アイザック様」
エヴェリーナの頬に口付けを落とし、俺は玄関を出た。
晴れて両想いになった俺たちだが、相変わらず彼女の好きなもの探しを続けていた。
「ミルクティーも好きだけど、ストレートも好きだわ」
「気分やお菓子で変えるのもいいね」
「色は……青がいいわ。爽やかだし、ホラ、あなたの瞳の色」
そう言ってふわりと笑う。
俺を確実に仕留めに来てる。中々の手練だ。勝てない。
「甘いのが好きだからチョコレートケーキがいいわ。ほら、あなたの髪の色みたい」
想いを自覚した彼女の無自覚な口説きにたじろいでしまう。
幸せな中死ねるのは……
いや、まだ死ねない。
彼女を遺して逝くとか無理だ。
ただでさえ可愛くてふにゃふにゃした彼女だ。
生涯俺が守らねばならない。
「婚約者だけでなく俺の身体も守ってくれよ!」
ばん!と机を叩きながら、目の下に隈を作った王太子殿下が叫んだ。
「殿下、早く書類を捌いて下さい。でないと俺が新婚休暇取れないじゃないですか」
「誰が新婚休暇に一ヶ月も取るんだ!?」
「私、こと、アイザック・カーティスでございます」
「だからって一ヶ月分の仕事を今前倒しするのはおかしくないか!?」
「殿下が私がいないと捗らないと仰るからいるうちに、と思ったのですが…
お気に召しませんでしたか?」
「誰が召すかバカヤロー!!」
全く、ああ言えばこう言う。
でも悪態つきながら手は止めない。
だから殿下に期待してしまうのは仕方ない事なんだけど。
「でも、まぁ。お前が幸せになって良かったよ」
書類に記入しながらボソボソと言う。
思えば俺の恋が実ったのも、隣国の王太子殿下とやり取りして情報を教えてくれた殿下のおかげもあるかもしれない。
「王太子殿下のおかげでございます。その節はありがとうございました」
恭しく礼をすると、手を止めぽかんとして見られた。
「な、なんだ、気持ち悪いな、何か背筋がゾッとしたぞ」
ぶるりと震える殿下の顔が引き攣っている。
失礼な。
「ま、まあ、俺は公爵家が存続できるのかが気になったんだ。お前が結婚できて良かったよ。結果良ければ全て良しだな。ははっ……」
未だ顔をぴくぴくさせながら、再び手を動かし始めた。
「そう言えば殿下、俺達の結婚式には出席してくださるんですよね?」
「ああ、その予定だ」
「ではこちらの書類もお願いします」
ばさっと書類の束を追加すると、殿下は持っていたペンをばきりと折った。
「冷然!冷血!!この残虐公爵めー!!!」
うん、我が国は今日も平和である。
そんな仕事中の話を彼女にすると、口に手を当てて堪えきれないという風に笑う。
「ふふっ、アイザック様と王太子殿下は本当に仲良しですね。……ふくくっ」
「そうだなぁ。まぁ、けどどんなに厳しくしても結局ちゃんとやる事はやるからね。つい、どんどんやってしまうんだよね」
「信頼しあっているのですね。良い関係です」
「そうだね。信頼していないと悪態つけないからね」
最近の彼女はよく笑うようになった。
今ではもう、夜中に起きて泣く事も無い。
時折見せていた、憂いを帯びた表情も、遠くを見るような仕草も無い。
変わったと言えば、俺への好意を溢れんばかりに伝えてくれるようになった。
勿論俺は潰れる事も無く、遠慮なく愛を捧げられるのできっと俺たちは相性が良いのだろう。
誰かを愛し、愛される事は決して容易では無い。
出逢いのタイミングや想いの大きさも関わってくるだろう。
政略結婚が多い貴族なら尚の事、愛などに拘っている場合では無い。
けれど、一生を共に過ごすならば。
互いに向き合って、ケンカして、笑い合って。
沢山話して、そうして信頼を築き、愛を得られる関係になりたいと思うのは自然な事だろう。
最初から諦めて楽な方に逃げるのは簡単だ。
でも、望むのであれば辛くても足掻いてみるべきだと思う。
傷付くかもしれない。
望まない結果かもしれない。
──喜びをもたらすかもしれない。
未来は誰にも分からない。
何が起こるか決まってない。
行動しなければ何も起きない。
何かが起きるのは、自分の行動の結果なのだ。
「エヴェリーナ、きれいだよ」
真っ白なドレスに身を包んだ彼女は、女神かと思う程に美しい。
「アイザック様も素敵です」
はにかみながら、目を細めて笑う彼女が愛おしく、口付けたかったが堪えた。
抱き締めたいが止まらなくなりそうなのでこれも我慢した。
今日は待ちに待った結婚式。
ようやく夫婦になれるのだ。
「残酷公爵、祝いに来たぞ。休暇は一ヶ月、短縮は歓迎するが延長は許さん」
目の下の隈で幽鬼のような顔をした王太子殿下が祝いに来た。
「王太子殿下、ありがとうございます」
「そちらが嫁か。紹介しろ」
「何でですか。減るじゃないですか」
「紹介しただけで減るわけ無いだろう!?そろそろ不敬罪でぶち込むぞ!?」
言い合いしている俺達を目の当たりにしたエヴェリーナはふふふっ、と笑う。
ああ、もう、笑顔を王太子殿下に見られるとか勿体無さ過ぎる。
「遅くなりまして申し上げございません。王太子殿下にご挨拶申し上げます。
カーティス公爵の妻となるエヴェリーナと申します。
夫と共によろしくお願い致します」
エヴェリーナはカーテシーをし、ふわりと笑む。
「あ、ああ、どうも……、こちらこそ、よろしく頼む…。
お、おい、きれいな奥さんだな、オイ。あんなきれいな方だったか?」
殿下が顔を赤くしてボソボソ小突いてくる。
「殿下。休暇明けたら釣書を山程持って参りますね」
「え"っ、いや、それは、ははっ、じゃ、あ俺はあっち行くな!またな!休暇はゆっくりしてくれたまへよ!」
全く、人の妻になる女性に色目使おうとするからだ。
「本当に楽しそうですね。でも、何だかあなたの素を見た気もしますわ」
「幻滅したかい?」
「いいえ、ちっとも。逆に惚れ直しました」
その言葉に嬉しくなり、思わず頬に口付けた。
「なっ!」
「赤くなった君もかわいいよ。じゃあ、そろそろ行こうか、奥さん」
何か言いたげに口をパクパクしていたが、やがて俺が差し出した手にそっと重ねて来た。
「愛しているわ、アイザック様」
「愛しているよ、エヴェリーナ」
俺たちの結婚を、眩しい陽の光が祝福しているようだった。