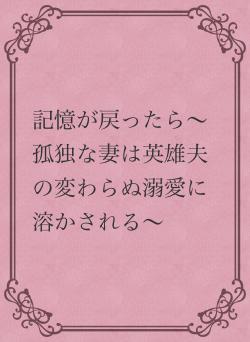隣国に来て、一年が経過した。
あれから私は少しずつ、前に進んでいると実感する。
それはきっと、アイザック様が側にいて支えてくれるおかげだ。
彼は私を否定しない。
ずっと、全てを受け入れてくれる。
一緒に考えて、一緒に悩んで。
悲しいも、苦しいも、楽しいも、分かちあってくれた。
彼にとって、嫌な事も言っただろう。
それでも笑って受け止めてくれる。
そして、諭してくれる。
そうして過ごすうち、段々とあの方よりもアイザック様の事を考える時間が増えたように思う。
きっと、私はあの方を忘れる事はないのだろう。
けれど、少しずつ、考える事もなくなる。
それが寂しいような、切ないような。
時と共に確実に変化していく。
一昨日より昨日。昨日より今日。
ゆっくりと、ゆっくりと。思い出に変わっていく。
今の私は留学先の学園を無事卒業して、将来の公爵夫人としての勉強を始めた。
とはいえ元々侯爵家跡取りとして、領地経営の勉強はしていたからその辺りはあまり心配はしていない。
社交も学園時代に親しくさせて頂いた方々と親交が続いている。
以前、王太子殿下に頂いたチケットで見た歌劇の再演を、友人の誘いで観劇した。
あの時はあの方を思い出して苦しかったけれど、今回は「友人の方と結ばれて良かった」と素直に思えた。
彼女を忘れ他に行く男性より、彼女を見て、ずっと悲しみごと受け入れてくれた男性の方がいいに決まっている。
『恋愛は一人でするもんじゃないから』
アイザック様はそう言っていた。
好きだからと想いを受け入れてほしいと囲い込むようにしてあの方を苦しめたのは、やはり一方的でわがままだった。
冷静になって見てみれば、申し訳無い事をしたと心底思う。
彼には幸せになってほしい。
もう会う機会は無いかもしれない。
傷付けた私がそう願ってしまうのは傲慢だろうか。
いつもの晩餐のあとのティータイム。
この時間が心地良くて、最近では時間が足りないと思うくらいになってきた。
自分が変わってきたな、と思ったのはこの国に伝わる『恋人の日』の出来事。
友人から教えてもらったその日は、お互いに感謝を告げようというものの他に、女性から想いを伝えてもいいと聞いた。
私は自然と、アイザック様に伝えたいと思った。
感謝だけではない想いを。
彼ともっと一緒にいたい。
色々な話をしたい。
名前を呼んでほしい。
誰でもない、アイザック様に。
今日は恋人の日では無いけれど。
伝えたいと思う気持ちは徐々に大きくなっていった。
だから、私は意を決してアイザック様を見た。
きっと、彼なら咎められないだろうと、期待して。
「アイザック様」
「なんだい?」
「私の名前を、呼んで下さいますか?」
ティーカップを持ったまま、アイザック様は笑顔で固まった。
唐突すぎたかしら。
でも、自然と、呼んでほしいと思ったの。
しばらく、二人の間に沈黙が流れた。
笑顔のまま固まったアイザック様は、やがてぎこちない動きのままカップをソーサーに置いた。
「その……婚約者殿」
「はい」
「もう一度、言ってくれる?」
あまりにも真剣な顔をしているから、段々と愛しさが芽生えてくる。
「アイザック様に、私の名前を呼んでほしいのです。
……ダメでしょうか」
「ダメじゃない!ダメじゃない、全然、全く!
……でも、いいのか?」
この方はどこまでも、私を思ってくれる。
ずっと待ってくれていた。
「あなたに、呼んでほしいのです」
だから、私も想いを返したい。
アイザック様は何度か咳払いして。
覚悟を決めたように口を開いた。
「エヴェリーナ」
呼ばれた瞬間、私の中に優しく温かなものが宿る。
名前を呼ばれただけで、芽吹いたものが花咲くように。
「もう一度、呼んで下さいますか?」
「エヴェリーナ……何度でも呼ぶよ」
アイザック様が口にする度、次々と花開く。
嬉しくて、切なくて、でも苦しくない。
「アイザック様、好きです」
自然に、口にした言葉にアイザック様は目を見開く。
「ずっと、私を見ていて下さったあなたが好きです。
待たせてしまってごめんなさい」
私は自然に、笑えているかしら。
アイザック様は目を見開いたまま、自身の頬をつねった。
「夢……じゃ、ない?」
「夢であって欲しいですか?」
「夢は嫌だ!……いや、夢なのか?」
目を瞬かせ、何度も頬をつねるアイザック様を見ていると、「ふふっ」と笑ってしまった。
「エヴェリーナ……、ようやく、自然に笑えるようになったんだね」
感慨深いような顔をして、アイザック様も微笑む。
「側に行ってもいいかな?」
「はい」
アイザック様は私の前に跪く。
そして私の手を取り、見上げた。
「エヴェリーナ。ありがとう。その……嬉しい。嬉しくて、夢みたいで」
「夢ではありません。
……でも、私の気持ちは重いかもしれません。それでも、いいですか?」
「大歓迎だよ。むしろ俺の方が重い……かも、あれ、もしかして、俺ちょっと、重い男……?」
いや、そんな、まさか、と眉間に皺を寄せてブツブツ言うアイザック様を見て、私は吹き出してしまった。
「ふふっ…、重い私と、アイザック様、お似合いかも、しれませんね……ふふふっ」
「……そうかもしれない。これからは遠慮なく君に愛を捧げていくよ」
そうして、アイザック様は私の手に口付け、再び真剣な表情で見上げた。
「エヴェリーナ・ソレイユ侯爵令嬢。
私はあなたを愛しています。
一生をかけて、あなたを愛し、幸せにすると誓います。
だから、私と結婚して下さい」
それは、求婚の言葉。
だから。
「アイザック・カーティス公爵様。
よろこんであなたの申し出をお受けします。
私もあなたを愛し、幸せにします。
ふつつかですが、よろしくお願い致します」
「ありがとう、エヴェリーナ」
アイザック様は嬉しさを隠しきれないという風に溢れんばかりの笑顔を見せた。
思えばこの方はずっと笑顔だった。
この笑顔に癒やされていたんだ。
そうして、私たちは見つめ合って。
どちらからともなく顔が近寄って。
初めての口付けを交わした。