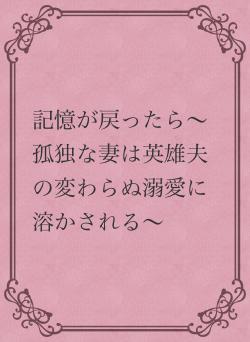彼女が来て数カ月が経過した。
普段、俺は王太子殿下の側近として働き、帰宅後は領地の事を家令から報告を聞いて当主印がいるものの書類を捌く。
彼女も学園に編入し、帰宅後は自由に過ごしているようだ。
同じ屋敷内で暮らすようになって、俺は帰宅するのが楽しみになった。
なぜなら。
「アイザック様、お帰りなさいませ」
使用人達の出迎えの中に、彼女が加わったからだ。
愛しい婚約者から出迎えられる。……幸せすぎるだろう。
おかげで俺の仕事はすこぶる捗り、毎日今までより多く書類を捌く為、王太子殿下から
「無慈悲!悪魔!!地獄の門番!!!」
などと悪態つかれている。
そんな中、二人で彼女の好きなもの探しが始まった。
主に、食事の時、食後のお茶を飲むとき、寝る前。
好きな食べ物、味付け、食器の柄、お茶の種類、読んだ本など、多岐にわたる。
肉より魚、トマトは少し苦手、明るい色より落ち着いた色、緑より青、ミルクティーよりストレート、推理物より恋愛物、など比べてみてどちらが良かったか、などを話している。
段々自分が求めるものが何か分かって表情は乏しいけれど、嬉しそうにわくわくしている姿を見るだけで幸せになれる。
好きそうだな、というものを話す時少しだけ綻ぶのだ。
そんな小さな発見で喜ぶ俺は単純だな。
俺の仕事が休みの日には積極的に出掛けた。
元婚約者は何をしていたんだ?と憤りたくなるほど彼女は色んな事に慣れていなかった。
エスコートされる事、何かをプレゼントされる事。
その度に戸惑い、驚く姿は新鮮で可愛くはあるけれど、それだけ元婚約者の彼から無視され続けていたのかと思うとやるせなくて、つい抱き締めてしまいたくなるのだ。
だけど、彼女は時折遠くを見てぼんやりしている。
まるで過ぎ去った日に想いを馳せているように。
ここから、どこか遠くへ行ってしまうのではないかと不安になる時があるのだ。
そんな時は手を繋ぐ。
言葉はいらない。
「俺はここにいる。いなくならない」と、想いを込めて。
最初は繋ぐ度にぴくりと反応していたが、段々慣れてくると彼女の方から握り返され、今度は俺がぴくりとした。
不意打ちは心臓に来る。
少しずつ、少しずつ。
ゆっくりと、確実に『彼女』が確立されていく。
元婚約者との境が、できていく。
色々選びながら、俺はある事に気付いた。
彼女が#意図的に選ばない__・__#ものがある。
ミルクティーや緑、冒険物の物語。
チーズケーキ、葉物野菜、りんごの果実水。
不自然に選ばない。
それしか無いなら諦める。
食べ物などは食べないわけでは無いが、好んで選ばない。
きっと、思い出すのだろう。
彼の名残を。
愛しい気持ち、忘れたい気持ち、ないまぜになるのは、きっと苦しいだろう。
時折夜中に起きて泣いていると使用人から聞いた。
婚約者とはいえ流石に夜中に行く事はできない。
本当なら一晩中慰めたいのをじっと堪える。
朝になったら挨拶と共に抱き締めて額にキスを送る。
少し腫れた瞼にも。
俺にはこんな事しかできないのがもどかしい。
そんな時、王太子殿下から歌劇のチケットを頂いた。
「おい悪魔公爵。よく聞け。お前は最近俺を働かせすぎだ。だからお前を強制的に俺から引き剥がす事にしたぞ。
見ろ!俺の権力を駆使して手に入れた最近話題の歌劇のチケットだ!
ふははははどうだこれで俺も休めるぞざまぁみろーはははは」
ああ、ちょっと働かせ過ぎたかな、反省。
「ありがとうございます、殿下。では捌く予定の書類を準備してお休みをいただきますね」
殿下の執務机にどんっと書類の束を置いて、チケットを有難く頂く。
お優しい主を持てて幸せだなぁ。早速彼女と行く事にしよう。
「冷徹!冷酷!!腹黒ー!!!」
殿下が何か吠えているが休みをくれたし、彼女が優先なので放っておこう。
「歌劇……ですか?」
「そう、殿下が休みと一緒にくれたんだ。行ってみないか?」
チケットを眺めたまま、不思議そうに見ている。
「……良いですね。行ってみます」
柔く微笑む彼女のそれは、まだ淑女としてのものだった。
「明日、学園は休みだったね。じゃあ朝食を食べてから出掛けよう」
「分かりました。楽しみにしています」
いつかは自然な笑みを見れるのだろうか。
…………焦ってはダメだ。
今はこうしていてくれる、それだけでいい。
翌日。
馬車で歌劇場に赴いた。
さすが王太子殿下手配のチケットで、専用のシートに案内される。
二人がゆったり座れるソファ、遠過ぎない距離だが個室になっているので気兼ね無く過ごせる。
「どんな劇かしら」
「ああ、そう言えば聞いてなかったな。楽しみにしていよう」
「ええ」
端的に言って、内容は今の彼女には辛い物だった。
最初は仲睦まじかった恋人同士が、男の心変わりによって破局してしまうという展開を見て、彼女に退室しようと促した。
だが、彼女は顔色を悪くしながらも席を離れなかった。
「せっかく下さったから……」
「君の顔色が悪い。すぐに帰ろう」
「いえ……、あ……ホラ、先程まで脇役だった男性が……」
ちょうど場面が変わる所だった。
時折出て来ていた如何にも脇役な男性が、彼女の手を取り愛を告白していた。
男は浮気男とは友人関係で、彼女の事を慰めていたのだ。
結局、最終的に浮気男は彼女に復縁を迫ったが友人と愛し合う関係になっていた彼女から
「もう、貴方はいらないのよ。さようなら」
と言われ、幕が閉じた。
「……こんな出逢いもあるのね…」
そう呟いた彼女の顔色は戻っていたけれど、元婚約者との事を思い出させるような展開に肝が冷えたものだった。
「序盤の展開は酷いものだった。……すまない、知っていたら連れては来なかったのに」
殿下の執務を五割増ししようと決めた。
「……アイザック様」
俯き、躊躇いがちに名前を呼ぶ。
何かを言いたそうに、何度も唇を噛んで。
だが、意思の強い瞳をした彼女は、真っ直ぐに俺を見た。
「帰ったら、聞いてほしい事があります」
「……分かった」
「……あまり、面白い話では無いかもしれません」
「いいよ。君から話したいと言ってくれる事なら全て聞くから」
彼女はホッとしたような、顔をした。
「元婚約者の方の話です。……それでも、いいですか?」
俺は真剣な表情をした。
そしてゆっくりと頷いた。
瞳に涙を溜めた彼女が、真っ直ぐ俺を見たから。