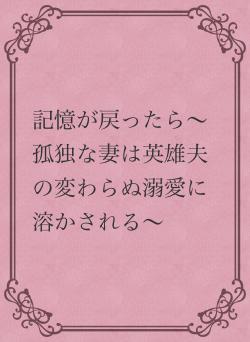婚約者である公爵様──アイザック様に提案されて、私は公爵邸に住むことにした。
「カーティス公爵邸ならば安心できます。
お嬢様をよろしくお願い致します」
お世話になった伯爵様に御礼をして、荷物と一緒に公爵邸に引っ越した。
「俺の部屋は階段登ってこっちの奥。
君に準備した部屋は反対側の奥。
離れているけど、警備はしっかりしてるから安心して」
アイザック様にエスコートされて辿り着いたお部屋は、とても過ごしやすそうなお部屋だった。
「過ごしやすそうなお部屋です。ありがとうございます」
「どういたしまして」
とても嬉しそうな笑顔。
どうしてこんなに笑えるのかしら。
「アイザック様はいつも笑ってらっしゃいますね」
言ったあとでしまった、と口を押さえた。
他意は無い。ふと気になったから。
「まいったな、俺そんなにニヤけてる?」
アイザック様は口を押さえて気まずそうにした。
「あ……いえ、すみません。その……いつも笑顔ですので……」
どうしよう。
気分を害されたかしら。
どうしよう。
また嫌がられたり無視されたら──。
私は俯いて、ドレスをぎゅっと握り締めた。
「俺がいつも笑えるのは、君がここにいるからだよ」
その言葉に思わず顔を上げると、アイザック様は優しく笑んでいる。
「君が子爵家の彼と婚約している時に、君に会った事があるんだ。
覚えてるかな?歓迎の夜会で、君と踊ったんだけど」
夜会で、踊った──?
そんな記憶──
私が何も言えなかったからか、アイザック様は苦笑した。
「大丈夫だよ。君がずっと彼を見ていたのを知っているから」
「すみません……」
ダンスに誘って下さったのに覚えていないなんて、貴族としてありえない失態だわ。
でも、アイザック様は私を責めず「大丈夫」だと仰って下さった。
「ずっと、忘れられなかったんだ。
君には婚約者がいて、君は彼の事が好きだと全身で表していて。
君からそういう風に好きだと言われたら、どんなにいいだろう、って。
でも、一度は諦めたんだ。
だから、今、君がここにいる事が嬉しくて仕方ない。自然に顔が緩むのは許してほしい」
照れたような、バツが悪そうな、そんな顔がとても新鮮だった。
異性のそんな表情、見た事が無かった。
「どうも格好つかないな。すまない」
「いえ……」
顔を赤らめているアイザック様を見て。
私はどうしたらいいか分からない。
どうして、ここまで喜んで下さるのかも分からない。
婚約者ってこんな態度になるものなの?
周りはどうだったのかしら。
そう思って気付いた。
私は、周りの方々を見ていなかった。
いつだって私の世界の中心はあの方で。
あの方に私を映してほしくて必死だった。
一日中あの方を想い、あの方の為に頑張る毎日を過ごしていた。
それが無くなった今、私に何が残るのだろう。
私がいる事を喜んで下さる方に何ができるのだろう。
「婚約者殿」
考えこんでしまった私に、アイザック様は優しく声をかける。
「まあ、そういうわけで、俺は君の事をこれから知っていきたいんだ。
君が好きな食べ物、花、色、興味がある事は勿論、君が許せない事、嫌な事、嫌いな食べ物、苦手な事、なんでも教えて欲しい」
私の、事。
私の、好きな、食べ物……。
「それは……」
好きな花
色
分からない。
好きな色はあの方の瞳の色。
好きな食べ物はあの方の好きな食べ物。
好きな、花なんて……
「……………」
口を開くけれど、声にできない。
今迄の私はあまりにも、彼を中心に置きすぎていて『自分』を失っていたのだ。
「分かり……ません……」
「うん?」
「今、まで……、婚約者だった…彼の、興味ある、事を……。彼が、好きな、もの、が……好きだったの、で…
自分が、何を好きで……興味があるか、なんて……」
考えもしなかった。
自分が分からないなんて、自己を持たないなんて、呆れられるかしら……。
「そっか。……じゃあ、これから俺と一緒に見つける、ってのはどう?」
「……っ」
「君の好きな彼と、君は違う人間だ。
もしかしたら、本当は苦手なものも、彼が好きだからって理由で無理に好きだと思い込んでいたのもあるかもしれない。
そういうのを、少しずつ、見つけていくのはどうだろう?」
その言葉に私は目を見開いた。
無理に、好きだと思い込んでいた……なんて、思ってもみなかった。
けれど、その提案は私に響いて。
やってみたい、と自然に思えた。
「分からない事だらけで、ご迷惑をかけるかもしれませんが……
でも、私も……探したいです。
あの……っ、嫌ならいいんです。でも、一緒に、探して……頂いても……、いいですか…?」
最後の方は自信が無くて、嫌だと言われたらどうしようが先に来て、か細くなってしまった。
怖くて、心臓がばくばくして、何かにつかまりたくて、手を動かしていたら。
「喜んで。言っただろう?
君と一緒に見つけたい、って。
君が何を好きか、何が苦手か。
二人で色々探してみよう。
色んな場所に行ったり、色んな物を見たり、沢山見つけた中で好きなもの、駄目なものを君の感じたままに教えて欲しい」
手を緩く握られて、優しい口調で仰った。
あまりにも真っ直ぐに私を見てくるから、また泣きそうになる。
「どうして……そんなに、あなたは……私を見て下さるのですか……?」
アイザック様は目を細めて笑う。
「君の事が好きだからだよ。
好きだから、一緒にいたいし、見ていたい」
私はその言葉に何も返せなかった。
アイザック様の言葉は、私が彼から欲しかった言葉。
欲しかったけど、貰えなかった言葉。
たった一言だけで良かった。
私は貴方に
「君が好きだ」と言ってほしかった。
だけど、もう、会うことは叶わない。
会いに行く事も無い。
私の好きなもの、苦手なものが分かるようになる頃には、彼を忘れる事ができるのかな。
そしていつか、目の前にいるアイザック様を好きになれるのかな。
全部、分からない。
未来の事まで見通せない。
けれど、私を見て、誠実に接して下さる方に、私も応えたいと。
今は無理だけど、少しずつ、一緒に歩んでいきたいと。
優しい笑顔を見てそう思った。