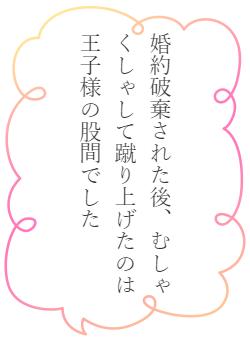「あ、あ、あなた、い、いったい……!」
「ね、レティ……ずっと僕は態度で示してきただろう? 冗談なんかじゃなく、僕は本気で——」
「ば、ばか……っ!」
いつの間にか握られていた手を無理矢理振りほどくと、レティシアはどんと彼を突き飛ばした。だが、さすが聖騎士候補にまでなった騎士だけのことはある。エルヴェはよろける様子すら見せず、再びレティシアの腕を掴んだ。
「ね、レティ——」
「……るわけ、ないでしょ!」
「え?」
突然大声を上げたレティシアに、エルヴェが目を丸くする。手の力が緩んだのを良いことに、レティシアは力一杯手を振り払うと大声で叫んだ。
「なれるわけないでしょ、って言ったのよ! 万が一……万が一なれたら考えてあげても良いわ!」
「本当に?」
「ええ、オービニエ家の娘としての誇りにかけて誓うわよ!」
そう宣言すると同時に、エルヴェがにやりと笑うのが見えた。はっとしたがもう遅い。口から出た言葉は戻ってこない。
「じゃあ——一ヶ月後を楽しみにしていて」
最後に手を取って、その甲に触れるか触れないかの口付けをそっと残すと、エルヴェは爽やかな笑顔を残して去って行った。
「ね、レティ……ずっと僕は態度で示してきただろう? 冗談なんかじゃなく、僕は本気で——」
「ば、ばか……っ!」
いつの間にか握られていた手を無理矢理振りほどくと、レティシアはどんと彼を突き飛ばした。だが、さすが聖騎士候補にまでなった騎士だけのことはある。エルヴェはよろける様子すら見せず、再びレティシアの腕を掴んだ。
「ね、レティ——」
「……るわけ、ないでしょ!」
「え?」
突然大声を上げたレティシアに、エルヴェが目を丸くする。手の力が緩んだのを良いことに、レティシアは力一杯手を振り払うと大声で叫んだ。
「なれるわけないでしょ、って言ったのよ! 万が一……万が一なれたら考えてあげても良いわ!」
「本当に?」
「ええ、オービニエ家の娘としての誇りにかけて誓うわよ!」
そう宣言すると同時に、エルヴェがにやりと笑うのが見えた。はっとしたがもう遅い。口から出た言葉は戻ってこない。
「じゃあ——一ヶ月後を楽しみにしていて」
最後に手を取って、その甲に触れるか触れないかの口付けをそっと残すと、エルヴェは爽やかな笑顔を残して去って行った。