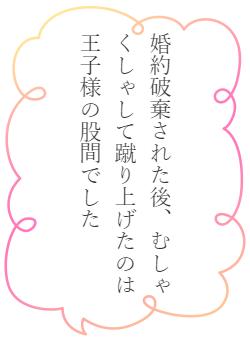「お、おめ……」
「だからレティシア、聖騎士に選ばれたら、結婚してくれ」
「は……?」
「聖騎士に選ばれたら、僕と結婚してくれ」
一瞬、言われたことの意味がわからず、レティシアは目を瞬かせた。だが、同じ言葉をもう一度繰り返されて、やっと彼が何を言っているのかを理解する。
——正気なの……?
祝いの言葉を遮られ、思いも寄らない言葉聞かされたレティシアは彼の正気を疑って、半眼になってしまう。
だが、エルヴェの顔は真剣そのもので、嘘や冗談を言っている雰囲気ではない。その空気に圧され、レティシアはごくりとつばを飲み込んだ。
「レティ」
「へっ……?」
戸惑っている間に、エルヴェがそっと肩に手を添える。夏物の薄い布地越しに彼の熱い手の感触が伝わってきて、一気に体温が上がる心地がした。影が差して思わず視線を上げると、彼の顔が近づいてくる。
「な、っちょ、ちょっと……!!」
唇がくっつきそうになる寸前で、レティシアは慌てて二人の間に手のひらをねじ込んだ。手のひらに感じるふよっとした生暖かい感触が、彼の唇だと思うと脳が破裂しそうなほどの羞恥が襲いかかってくる。
気のせいではなく、口付けられそうになったのだ——そう思うと、次に襲いかかってきたのは困惑だった。いや、困惑などという生やさしいものではない。大混乱だ。
「だからレティシア、聖騎士に選ばれたら、結婚してくれ」
「は……?」
「聖騎士に選ばれたら、僕と結婚してくれ」
一瞬、言われたことの意味がわからず、レティシアは目を瞬かせた。だが、同じ言葉をもう一度繰り返されて、やっと彼が何を言っているのかを理解する。
——正気なの……?
祝いの言葉を遮られ、思いも寄らない言葉聞かされたレティシアは彼の正気を疑って、半眼になってしまう。
だが、エルヴェの顔は真剣そのもので、嘘や冗談を言っている雰囲気ではない。その空気に圧され、レティシアはごくりとつばを飲み込んだ。
「レティ」
「へっ……?」
戸惑っている間に、エルヴェがそっと肩に手を添える。夏物の薄い布地越しに彼の熱い手の感触が伝わってきて、一気に体温が上がる心地がした。影が差して思わず視線を上げると、彼の顔が近づいてくる。
「な、っちょ、ちょっと……!!」
唇がくっつきそうになる寸前で、レティシアは慌てて二人の間に手のひらをねじ込んだ。手のひらに感じるふよっとした生暖かい感触が、彼の唇だと思うと脳が破裂しそうなほどの羞恥が襲いかかってくる。
気のせいではなく、口付けられそうになったのだ——そう思うと、次に襲いかかってきたのは困惑だった。いや、困惑などという生やさしいものではない。大混乱だ。