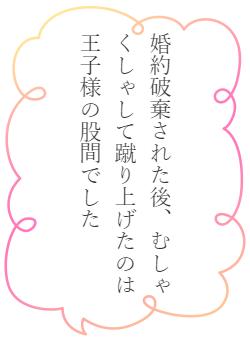目標があるから、それを達成するまでは結婚しないと言い張っているらしいので、それでも寄ってくるという女除けなのだろう。
——まったく、人をなんだと思っているのかしら。
ちらりと横目で睨むと、彼は眉を下げ、困ったように笑った。そうしてすっとレティシアの手に自分のものを重ねると、こう囁く。
「誤解じゃないよ、いつも言っているだろう、マイ・リトル・レティ」
「はいはい」
「つれないなあ……」
昔は、こうした一言に内心ドギマギしていたものだけれど——今ではだいぶ慣れてしまった自分が悲しい。おざなりな返答をすると、彼はすり、と指の腹で手の甲を撫でてきた。途端にぞくっとした感覚が背筋を這う。決して不快ではないものの——なんだか落ち着かない、そんな感覚だ。思わず振り払おうとするが、いつもならすぐに離れていくはずの手が、今日はかえってしっかりとレティシアの手を握り込む。
その力強さに、内心たじろいでしまう。それに気付かれたくなくて、レティシアはつばを飲み込むと震える唇を開いた。
——まったく、人をなんだと思っているのかしら。
ちらりと横目で睨むと、彼は眉を下げ、困ったように笑った。そうしてすっとレティシアの手に自分のものを重ねると、こう囁く。
「誤解じゃないよ、いつも言っているだろう、マイ・リトル・レティ」
「はいはい」
「つれないなあ……」
昔は、こうした一言に内心ドギマギしていたものだけれど——今ではだいぶ慣れてしまった自分が悲しい。おざなりな返答をすると、彼はすり、と指の腹で手の甲を撫でてきた。途端にぞくっとした感覚が背筋を這う。決して不快ではないものの——なんだか落ち着かない、そんな感覚だ。思わず振り払おうとするが、いつもならすぐに離れていくはずの手が、今日はかえってしっかりとレティシアの手を握り込む。
その力強さに、内心たじろいでしまう。それに気付かれたくなくて、レティシアはつばを飲み込むと震える唇を開いた。