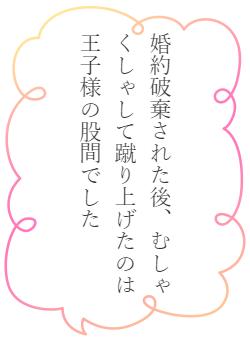花の盛りだけあって、庭には花々の馥郁とした香りが満ちていた。季節は初夏——オービニエ侯爵家自慢の庭園が、最も見頃を迎える季節だ。
レティシアが出て行くと、エルヴェはちょうどカップを傾けながら庭を眺めているところだった。その秀麗な横顔に、一瞬目を奪われる。
少し青みのある黒髪を撫でつけ、琥珀のような色合いの瞳を細めたその姿は、まるで一枚の絵画のよう。歴史あるグランジュ公爵家の嫡男にして騎士である彼は、細身ながらも鍛えられた均整の取れた体つきをしていて、まるで彫刻が歩いているようだと言われている。
天はいくつ彼に恩恵を与えれば気が済むのだろう。現在二十三歳の彼は、騎士団でも頭角を現していると聞いている。
社交界では、その凜々しさと将来性の高さからかなりの人気を博しているのだということを、レティシアでさえ知っていた。
まったく、ご立派に育ったものだ。小さな頃は、泣いてばかりいたくせに。
そう思いながら一歩踏み出すと、その気配に気付いたのかエルヴェがこちらを向いた。
「いらっしゃい、エルヴェ。約束もなしに押しかけてくるなんて珍しいわね」
「こんにちは、レティ。相変わらず元気そうで何より」
——ああ、またやってしまった……。
どうしても、彼のことになると嫌みな態度をやめられない。せめて表情だけでも、と思うものの、引きつったような笑顔しか作れない。これのせいで、人を小馬鹿にしていると言われてしまうのに。
だが、そんなレティシアに向かって、エルヴェはにこりと微笑んだ。完璧な優しい笑顔を向けられて、顔が一気に熱くなる。それを隠そうとして、レティシアはつんとそっぽを向いた。
すると、彼が小さく吹き出すのが聞こえて、むっときたレティシアはつっけんどんな態度になってしまう。
これも、毎度のパターンだ。
レティシアが出て行くと、エルヴェはちょうどカップを傾けながら庭を眺めているところだった。その秀麗な横顔に、一瞬目を奪われる。
少し青みのある黒髪を撫でつけ、琥珀のような色合いの瞳を細めたその姿は、まるで一枚の絵画のよう。歴史あるグランジュ公爵家の嫡男にして騎士である彼は、細身ながらも鍛えられた均整の取れた体つきをしていて、まるで彫刻が歩いているようだと言われている。
天はいくつ彼に恩恵を与えれば気が済むのだろう。現在二十三歳の彼は、騎士団でも頭角を現していると聞いている。
社交界では、その凜々しさと将来性の高さからかなりの人気を博しているのだということを、レティシアでさえ知っていた。
まったく、ご立派に育ったものだ。小さな頃は、泣いてばかりいたくせに。
そう思いながら一歩踏み出すと、その気配に気付いたのかエルヴェがこちらを向いた。
「いらっしゃい、エルヴェ。約束もなしに押しかけてくるなんて珍しいわね」
「こんにちは、レティ。相変わらず元気そうで何より」
——ああ、またやってしまった……。
どうしても、彼のことになると嫌みな態度をやめられない。せめて表情だけでも、と思うものの、引きつったような笑顔しか作れない。これのせいで、人を小馬鹿にしていると言われてしまうのに。
だが、そんなレティシアに向かって、エルヴェはにこりと微笑んだ。完璧な優しい笑顔を向けられて、顔が一気に熱くなる。それを隠そうとして、レティシアはつんとそっぽを向いた。
すると、彼が小さく吹き出すのが聞こえて、むっときたレティシアはつっけんどんな態度になってしまう。
これも、毎度のパターンだ。