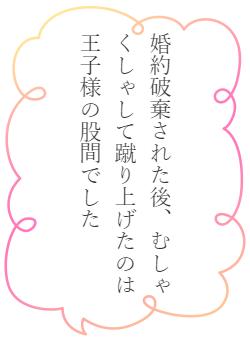一度目は、唇同士を軽く触れあわせただけ。それを何度か繰り返すうちに、だんだんと一度の時間が長くなっていく。ちゅっと吸い付かれ、唇を舐められるとぞくぞくした感覚が背筋を這った。その得体の知れなさに、思わず逃げようとするものの、机に置かれたのとは反対の手が、いつの間にかレティシアの後頭部をしっかりと掴んでいる。
「レティ、聞かせて」
口づけの合間に、エルヴェが囁く。酸素が足りなくなってぼうっとした頭で、レティシアは小さく頷いた。
「すきよ……」
ぽろりと口を突いて出たのは、素直な気持ちだ。
そうだ、本当はずっと彼のことが好きだった。幼い頃、一緒に本を読んでくれて——ちょっと押しに弱くて、それでいていざという時は頼りになる、そんな男の子のことが。
だからこそ、彼の変化が怖かった。自分一人だけのものだった背中が、どんどん逞しくなって他の人にも見つかってしまう。それが本当は嫌だった。
「レティ、聞かせて」
口づけの合間に、エルヴェが囁く。酸素が足りなくなってぼうっとした頭で、レティシアは小さく頷いた。
「すきよ……」
ぽろりと口を突いて出たのは、素直な気持ちだ。
そうだ、本当はずっと彼のことが好きだった。幼い頃、一緒に本を読んでくれて——ちょっと押しに弱くて、それでいていざという時は頼りになる、そんな男の子のことが。
だからこそ、彼の変化が怖かった。自分一人だけのものだった背中が、どんどん逞しくなって他の人にも見つかってしまう。それが本当は嫌だった。