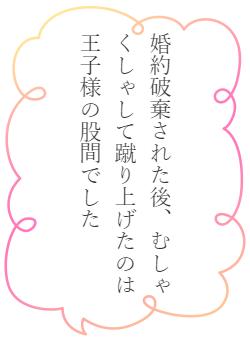口数の多いエルヴェにしてはめずらしいことだが、さすがに緊張しているのだろう。
何かを言おうと口を開きかけたとき、遠くで笛の鳴る音が響いた。集合の合図だ。
「……じゃあ、頑張って」
「……レティ、うん、頑張るよ……! きみが応援してくれたなら、百人力だ」
そう言うと、エルヴェは笑顔で手を振って、レティシアに背を向ける。その後ろ姿を見送って、レティシアはぎゅっと手を握りしめた。
ここから先は、見守ることもできない。観客が入れるのは、最後の決勝戦のみだ。
勝ち残ることを期待しているのか、そうでないのか——レティシアはもう、自分でも自分の気持ちが良く解らなくなっていた。
と、いうのに。
「う、うそでしょお……?」
「残念ながら、本当だよ」
結論から言うと、エルヴェは決勝戦まで見事勝ち残って見せた。その時点で二位以内になるため、聖騎士になることは確定だ。
だというのに、なんとその決勝戦でもエルヴェは勝利を収め——つまり、優勝してしまったのである。
応援席で固唾を呑んで見守っていたレティシアが、呆然とするほどの快勝ぶりだった。
何かを言おうと口を開きかけたとき、遠くで笛の鳴る音が響いた。集合の合図だ。
「……じゃあ、頑張って」
「……レティ、うん、頑張るよ……! きみが応援してくれたなら、百人力だ」
そう言うと、エルヴェは笑顔で手を振って、レティシアに背を向ける。その後ろ姿を見送って、レティシアはぎゅっと手を握りしめた。
ここから先は、見守ることもできない。観客が入れるのは、最後の決勝戦のみだ。
勝ち残ることを期待しているのか、そうでないのか——レティシアはもう、自分でも自分の気持ちが良く解らなくなっていた。
と、いうのに。
「う、うそでしょお……?」
「残念ながら、本当だよ」
結論から言うと、エルヴェは決勝戦まで見事勝ち残って見せた。その時点で二位以内になるため、聖騎士になることは確定だ。
だというのに、なんとその決勝戦でもエルヴェは勝利を収め——つまり、優勝してしまったのである。
応援席で固唾を呑んで見守っていたレティシアが、呆然とするほどの快勝ぶりだった。