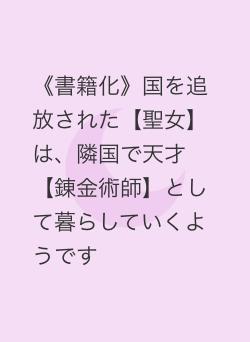戦闘の音が聞こえた瞬間、私は治療場へと走り出していた。
今外で戦っている兵士たちが負傷しても、すぐに治療に当たれるようにするためだ。
「聖女様! 大変です‼ 外に魔獣が‼」
「デイジー! 状況は⁉」
治療場に着くと、すでに怪我をした兵士たちが運ばれていた。
デイジーを始め、総勢で治癒に当たっているが、何しろ数が多い。
やっと安定的に治療ができるようになってきたと思っていたけれど、ここは戦場。
そう簡単にはいかないようだ。
「毒を受けた者は私のところに運んでちょうだい! デイジー! こっちへ来て! 簡単な毒についてはあなたに任せるわよ‼」
「はい‼」
どうやら思ったよりも魔獣の勢いは激しいようだ。
どんどん負傷兵が運ばれてくる。
中には少し前に回復したばかりの兵士の姿もあった。
みな、牙や爪などで四肢を切り裂かれた状態で運ばれてきて、痛々しい。
運んできた兵士もすぐに戦闘に戻り、そして怪我をして、別の兵士に運ばれるような状況だ。
運が悪いことに、この第五衛生兵部隊に運ばれる兵士のほとんどは、身分もそして戦闘能力も低い者ばかりだった。
「聖女様! このままでは間に合いません! こんなに次から次へと運ばれるだなんて!」
「諦めてはダメよ! 兵士たちが頑張っているの! それを助ける私たちが頑張らないでどうするの‼」
言葉はかけるものの、私自身いつ終わるか分からない戦闘と、負傷兵の多さにどうすればいいか分からなくなっていた。
今では同じ兵士が何度も運ばれ、傷を癒してはすぐ戦闘に戻って行くような有様だ。
衛生兵たちも、魔力枯渇と魔法酷使の症状が出始めている。
このまま今の状態が続けば、そのうち一人、また一人と衛生兵が先に倒れて行くだろう。
「なんてこと! こんな時に、魔石があれば‼」
魔石とは魔法の触媒となる石の総称で、魔鉱石を精製して作られる。
砕いて身体に取り込めば魔力の回復、魔法を唱える際にうまく使えば、普段使うことのできないような上級の魔法を使うことができる、まさに魔法の石だ。
「魔石……ですか? 昔、全ての部隊にそれなりの量の魔石を支給されたと聞いたことがありますが……」
「それは本当⁉」
私の泣き言を聞いたデイジーが一縷の望みがあることを告げる。
もしなければどのみち間に合わないのだ。
私はデイジーに私の分の治療も一時的に任せて、再び司令室であるアンバーの部屋に急いだ。
「失礼します‼」
「なんだ。君か。申し訳ないけど今は忙しいんだ。君も知っているだろう? 魔獣がこの陣営を襲ってきたんだよ。まったく、嫌になるよ」
「分かっています‼ 部隊長‼ 軍から魔石が支給されたとは本当ですか⁉」
「うん? よく知ってるね。ああ、本当だよ。ただ……それを当てにしようたって無駄さ」
アンバーは部屋の棚に置いてある錠のついた箱に目線を送った後、顔を横に振った。
私は急いで箱の前に行き開けようとするが、鍵がかかったままで開くことができなかった。
「すぐにこの箱を開け、魔石を使わせてください。でなれけば……大勢死にます‼」
「無駄と言っただろう。まったく軍ってのは嫌になるよ。その箱の鍵だけどね。開けるためには長官に報告書を上げて、承認を得ないといけない。そんなのしている間に数日経ってしまうさ」
「そんなバカなことが‼ 鍵は! 鍵はお持ちじゃないんですか⁉」
「無いんだよ。承認状と一緒に鍵が送られてくるって手筈さ。だから、諦めて持ち場へ戻りたまえ。ここは君のいる場所じゃ無いだろう?」
どうやらこれ以上話しても無駄なようだ。
しかし、ここにある魔石がどれだけあるか分からないけれど、手に入れなければ確実に治療場は瓦解する。
私は拳を作り、そこに魔力を込めた。
右手が淡く光り輝くのを確認した後、私は大きく頭上へ拳を振り上げた。
「おい……何をする気――」
アンバーの言葉など無視して、私は拳を錠のついた箱に勢いよく振り下ろす。
箱の蓋と錠は激しく歪み、すでに中の物を守るという役目を担えなくなっていた。
「開くじゃないですか。それでは、この魔石もらっていきますね」
「たまげたね。まさかそんなことするなんて。正気かい?」
「戦場で正気でいる者など居るはずがありません。居るとしたら、それは死人だけです」
「あっはっは! 君は僕が思っていた女性とは随分違うようだね。分かったよ。その魔石は君に全部あげよう。どうせ奴ら箱のことなんて確認しないんだ」
アンバーは白が多く混じった黒色の短髪を額から後に撫であげ、濃褐色の瞳を私に向けそう言った。
私は何が面白いのか分からず、しかし時間がないと、急いで箱から魔石を取り出して行く。
すると、アンバーが箱の方に近付き手を伸ばして来た。
まさか結局阻止されるのかと思い、私は身構える。
「ああ。そんな風に警戒しないで。持っていっていいって言ったのは本当さ。ただね、一つだけでいいから、僕にくれないかな? それ」
「部隊長が魔石など何に使うんですか?」
「いいから、いいから。ほら。急がないと手遅れになる子が出てくるかもしれないよ?」
「分かりました。それでは失礼します」
私は一礼をすると、魔石を落とさぬように気を付けながら、治療場へ急ぐ。
もともと体力がある方ではないので、息が上がる。
それでも少しでも早く治療に戻るために、息を弾ませながら懸命に両足を動かした。
「戻ったわ‼ 状況は⁉」
「聖女様! もう無理です‼ みんな、限界です‼」
見るとすでに衛生兵の何人かが、魔力枯渇により倒れていた。
その間にも負傷した兵は多く運ばれており、すでに全員が横になることができないほど、負傷兵で埋め尽くされていた。
「みんな! 聞いて! ここに魔石があるわ。魔力が尽きた者はこれを砕いて飲んで! 少量でいいわ。重傷者は優先して私の方に運んで‼」
「分かりました‼」
私の指示に、まだ動ける衛生兵たちは動き始める。
すでに倒れた人には、別の人が砕いて飲ませてあげていた。
「凄い……魔力が、魔力が満ちてきます」
「それが魔石の効果よ。さぁ! もうひと踏ん張りよ‼」
私も魔石を一つ砕きその全てを飲み干した。
身体中に魔力が満ちていくのが感じられる。
そして次々と私の元に運ばれてくる重傷者に、上級の回復魔法をかけては、その傷を癒していった。
どのくらいの人数を治したかすでに分からなくなっていたが、私はふと変化に気が付いた。
「負傷者が、運ばれて来なくなった?」
私の呟きにそれを聞き取った数人が顔を上げる。
すると、入口からどこにも怪我を負っていない兵士が一人飛び込んできた。
「みなさん! 無事に魔獣は殲滅しました‼ そして‼ あれだけ激しい戦闘だったにも関わらず、奇跡的に死者はゼロです‼」
その報告に、私も含め、その場にいる全ての人間が歓声を上げた。
今外で戦っている兵士たちが負傷しても、すぐに治療に当たれるようにするためだ。
「聖女様! 大変です‼ 外に魔獣が‼」
「デイジー! 状況は⁉」
治療場に着くと、すでに怪我をした兵士たちが運ばれていた。
デイジーを始め、総勢で治癒に当たっているが、何しろ数が多い。
やっと安定的に治療ができるようになってきたと思っていたけれど、ここは戦場。
そう簡単にはいかないようだ。
「毒を受けた者は私のところに運んでちょうだい! デイジー! こっちへ来て! 簡単な毒についてはあなたに任せるわよ‼」
「はい‼」
どうやら思ったよりも魔獣の勢いは激しいようだ。
どんどん負傷兵が運ばれてくる。
中には少し前に回復したばかりの兵士の姿もあった。
みな、牙や爪などで四肢を切り裂かれた状態で運ばれてきて、痛々しい。
運んできた兵士もすぐに戦闘に戻り、そして怪我をして、別の兵士に運ばれるような状況だ。
運が悪いことに、この第五衛生兵部隊に運ばれる兵士のほとんどは、身分もそして戦闘能力も低い者ばかりだった。
「聖女様! このままでは間に合いません! こんなに次から次へと運ばれるだなんて!」
「諦めてはダメよ! 兵士たちが頑張っているの! それを助ける私たちが頑張らないでどうするの‼」
言葉はかけるものの、私自身いつ終わるか分からない戦闘と、負傷兵の多さにどうすればいいか分からなくなっていた。
今では同じ兵士が何度も運ばれ、傷を癒してはすぐ戦闘に戻って行くような有様だ。
衛生兵たちも、魔力枯渇と魔法酷使の症状が出始めている。
このまま今の状態が続けば、そのうち一人、また一人と衛生兵が先に倒れて行くだろう。
「なんてこと! こんな時に、魔石があれば‼」
魔石とは魔法の触媒となる石の総称で、魔鉱石を精製して作られる。
砕いて身体に取り込めば魔力の回復、魔法を唱える際にうまく使えば、普段使うことのできないような上級の魔法を使うことができる、まさに魔法の石だ。
「魔石……ですか? 昔、全ての部隊にそれなりの量の魔石を支給されたと聞いたことがありますが……」
「それは本当⁉」
私の泣き言を聞いたデイジーが一縷の望みがあることを告げる。
もしなければどのみち間に合わないのだ。
私はデイジーに私の分の治療も一時的に任せて、再び司令室であるアンバーの部屋に急いだ。
「失礼します‼」
「なんだ。君か。申し訳ないけど今は忙しいんだ。君も知っているだろう? 魔獣がこの陣営を襲ってきたんだよ。まったく、嫌になるよ」
「分かっています‼ 部隊長‼ 軍から魔石が支給されたとは本当ですか⁉」
「うん? よく知ってるね。ああ、本当だよ。ただ……それを当てにしようたって無駄さ」
アンバーは部屋の棚に置いてある錠のついた箱に目線を送った後、顔を横に振った。
私は急いで箱の前に行き開けようとするが、鍵がかかったままで開くことができなかった。
「すぐにこの箱を開け、魔石を使わせてください。でなれけば……大勢死にます‼」
「無駄と言っただろう。まったく軍ってのは嫌になるよ。その箱の鍵だけどね。開けるためには長官に報告書を上げて、承認を得ないといけない。そんなのしている間に数日経ってしまうさ」
「そんなバカなことが‼ 鍵は! 鍵はお持ちじゃないんですか⁉」
「無いんだよ。承認状と一緒に鍵が送られてくるって手筈さ。だから、諦めて持ち場へ戻りたまえ。ここは君のいる場所じゃ無いだろう?」
どうやらこれ以上話しても無駄なようだ。
しかし、ここにある魔石がどれだけあるか分からないけれど、手に入れなければ確実に治療場は瓦解する。
私は拳を作り、そこに魔力を込めた。
右手が淡く光り輝くのを確認した後、私は大きく頭上へ拳を振り上げた。
「おい……何をする気――」
アンバーの言葉など無視して、私は拳を錠のついた箱に勢いよく振り下ろす。
箱の蓋と錠は激しく歪み、すでに中の物を守るという役目を担えなくなっていた。
「開くじゃないですか。それでは、この魔石もらっていきますね」
「たまげたね。まさかそんなことするなんて。正気かい?」
「戦場で正気でいる者など居るはずがありません。居るとしたら、それは死人だけです」
「あっはっは! 君は僕が思っていた女性とは随分違うようだね。分かったよ。その魔石は君に全部あげよう。どうせ奴ら箱のことなんて確認しないんだ」
アンバーは白が多く混じった黒色の短髪を額から後に撫であげ、濃褐色の瞳を私に向けそう言った。
私は何が面白いのか分からず、しかし時間がないと、急いで箱から魔石を取り出して行く。
すると、アンバーが箱の方に近付き手を伸ばして来た。
まさか結局阻止されるのかと思い、私は身構える。
「ああ。そんな風に警戒しないで。持っていっていいって言ったのは本当さ。ただね、一つだけでいいから、僕にくれないかな? それ」
「部隊長が魔石など何に使うんですか?」
「いいから、いいから。ほら。急がないと手遅れになる子が出てくるかもしれないよ?」
「分かりました。それでは失礼します」
私は一礼をすると、魔石を落とさぬように気を付けながら、治療場へ急ぐ。
もともと体力がある方ではないので、息が上がる。
それでも少しでも早く治療に戻るために、息を弾ませながら懸命に両足を動かした。
「戻ったわ‼ 状況は⁉」
「聖女様! もう無理です‼ みんな、限界です‼」
見るとすでに衛生兵の何人かが、魔力枯渇により倒れていた。
その間にも負傷した兵は多く運ばれており、すでに全員が横になることができないほど、負傷兵で埋め尽くされていた。
「みんな! 聞いて! ここに魔石があるわ。魔力が尽きた者はこれを砕いて飲んで! 少量でいいわ。重傷者は優先して私の方に運んで‼」
「分かりました‼」
私の指示に、まだ動ける衛生兵たちは動き始める。
すでに倒れた人には、別の人が砕いて飲ませてあげていた。
「凄い……魔力が、魔力が満ちてきます」
「それが魔石の効果よ。さぁ! もうひと踏ん張りよ‼」
私も魔石を一つ砕きその全てを飲み干した。
身体中に魔力が満ちていくのが感じられる。
そして次々と私の元に運ばれてくる重傷者に、上級の回復魔法をかけては、その傷を癒していった。
どのくらいの人数を治したかすでに分からなくなっていたが、私はふと変化に気が付いた。
「負傷者が、運ばれて来なくなった?」
私の呟きにそれを聞き取った数人が顔を上げる。
すると、入口からどこにも怪我を負っていない兵士が一人飛び込んできた。
「みなさん! 無事に魔獣は殲滅しました‼ そして‼ あれだけ激しい戦闘だったにも関わらず、奇跡的に死者はゼロです‼」
その報告に、私も含め、その場にいる全ての人間が歓声を上げた。
最後の一人の治療を終えた後、私はアンバーに報告するため司令室に向かった。
魔石の件は謝罪するべきか、それとも感謝すべきか迷いながら。
「失礼します」
「誰だ⁉ 誰も入れるなと厳命したはずだ‼」
私が司令室に入った途端、普段聞くことの無い、アンバーの荒げた声が聞こえた。
しかしその声は苦しみに耐えるようで、呼吸も速い。
「ああ……君か……すまんね。なんの用かな?」
「部隊長、どうされました? 顔色が優れないようですが。治療が必要なら――」
「無駄だよ。いいから出ていってくれ。さぁ! 今すぐに‼」
「……分かりました。失礼します」
珍しいアンバーの姿に若干戸惑い感じながらも、私は司令室を後にする。
治療場に行く途中、すれ違った兵士たちの言葉が自然と耳に入ってきた。
「それにしても凄かったな。部隊長の攻撃魔法。あんだけ苦戦した魔獣たちを一掃だぜ?」
「ほんと、凄かったよなぁ。それにしても、なんであんな強い人が、第五衛生兵部隊の部隊長なんかやってるんだ?」
五つある衛生兵部隊でも、この部隊は格でいえば一番下だ。
そもそもそんな攻撃魔法を使えるのならば、兵士が言う通り、攻撃部隊の、しかも上位の部隊に所属されていてもおかしくない。
「なんだ? 知らなかったのか? アンバー部隊長は以前は第二攻撃部隊の部隊長を務めていたんだぜ。なんでもその時戦った魔族から受けた傷が原因で前線から離れたんだとか」
「へー。知らなかったな。第二攻撃だなんて、エリート部隊じゃないか! そんな部隊の部隊長でも、満足に傷も治してもらえないんだなぁ」
「詳しくは知らないけどな。噂だよ。噂。怪我は治ったけど、呪いを受けてそれを取れなかったとか」
「呪いってあのずっと痛みを受けるってやつか? そりゃ嘘だろ。アンバー部隊長、いつもヘラヘラしてるじゃないか」
私はその言葉を聞いた瞬間、踵を返し、アンバーの部屋に戻った。
今の話と、アンバーの様子を見れば見当がつく。
そしてそれはできるだけ早くに対処しなければならない。
立ち入り禁止など聞いている場合ではなかった。
「失礼します‼」
「しつこいな……また君か。さっき出て行けと言ったはずだがね。なにか忘れ物でもしたかい?」
部屋に入ると、アンバーは既に立っているのが辛くなったようで、机に突っ伏すような格好でいた。
私が入ってきたのを確認しても動く様子はない。
「なんだい? 見ての通り、今動くのすらおっくうなんだ。忘れ物を見つけたら、今度こそさっさと出ていってくれ」
「ええ。大変な忘れ物をしていました。部隊長。あなた呪いに侵されていますね? しかも上位のものを含めて複数」
私の指摘にアンバーの眉が吊り上がる。
しかし、すでに言い返す気力と体力すら残っていないようだ。
「正直なところ、驚いています。じっとしているだけでも苦痛にさいなまれているはずです。それを他人に押し隠す努力、並大抵のものとは思えません」
私の言葉を聞いているのか分からないが、アンバーは一度だけゆっくりと瞬きをした。
「なぜ相談していただけなかったのですか? 就任直後に呪いを解く魔法を私が使えることはご存知だったはずです」
「無駄だよ……【痛み】を解けるくらいじゃ……もう何度も試したさ……高位の回復魔法の使い手に頼んでね……」
絞り出すような声でアンバーは答える。
おそらく今までは自分の魔力を総動員して、どうにか呪いを押さえ込んでいたに違いない。
それができたことも驚異だけれど、先ほどの戦闘で魔獣を一掃したという攻撃魔法。
それも驚異的な威力だったのだろう。
自身の魔力だけでは足りず、魔石を触媒にして使用した魔法。
魔力が尽きた今のアンバーは、無防備な身体で、恐ろしい呪いに襲われているのだ。
常人なら痛みで発狂したり、恐怖で自傷したり、多くの者は自分で命を絶つ選択をすると聞く。
それにも関わらず私になんとか弱みを見せぬよう、気丈に振舞おうとするアンバーの精神の強さに感服する。
「今すぐ患部を見せてください。まだ魔石も残っています。今やらなければ、最悪精神がやられますよ?」
「無駄だと……」
ここで押し問答をするつもりは無い。
私はアンバーが抵抗できないことを利用して、無理やり着ている軍服を脱がせた。
「これは……」
アンバーは私の二倍以上の年齢だろうか。
それにも関わらず、引き締まり無駄がない兵士の肉体を保っている。
その強靭な肉体を埋め尽くすかのように、呪いの紋様が描かれていた。
種類も複数あり、【痛み】、【恐怖】などはまだ優しい。
「まさか……【崩壊】まで……」
「それを知っているだけでも……大したもんだ……でも、これで無駄だということが……分かっただろ?」
【崩壊】は上位の魔族が使うとされる呪いで、それをかけられた者は、内部から腐敗し死に至る。
そして、呪いの厄介なところは、最も強い呪いを解ける解呪の魔法を使わなければ、初級の呪いすら解呪できない事だった。
「遅かったかもしれませんが、今気付けて良かった。少し時間はかかります。その格好では苦しいでしょう。横になってください」
「何を……する気だ……?」
「もちろん治療するんです! それ以外にありますか?」
私はアンバーを床に寝かせると、懐から魔石の最も質のいい物を選び取り出す。
それともうひとつ魔石を取ると、小さい方は砕いて飲み干した。
先ほどの治療で消耗した魔力が再び満たされる。
そして質のいい魔石を手に持つと、自分の使える最上級の解呪の魔法を唱え始めた。
私の両手からアンバーの全身に眩い光が伝わる。
その光に溶けるように、アンバーの身体に描かれていた紋様が消えていく。
やがて、光が収まる頃には、全身を埋め尽くしていた呪いの紋様は、跡形もなく綺麗に消え失せていた。
呪いから解放されたアンバーは瞬きを繰り返し私を見つめている。
「さぁ、あともうひと踏ん張りですよ。呪いは消えました。後は腐敗した内部を治療しましょう」
そして今度は治癒の魔法を唱える。
これでアンバーの身体は、健康的でどこにも問題のない肉体になったと言えるだろう。
魔石の件は謝罪するべきか、それとも感謝すべきか迷いながら。
「失礼します」
「誰だ⁉ 誰も入れるなと厳命したはずだ‼」
私が司令室に入った途端、普段聞くことの無い、アンバーの荒げた声が聞こえた。
しかしその声は苦しみに耐えるようで、呼吸も速い。
「ああ……君か……すまんね。なんの用かな?」
「部隊長、どうされました? 顔色が優れないようですが。治療が必要なら――」
「無駄だよ。いいから出ていってくれ。さぁ! 今すぐに‼」
「……分かりました。失礼します」
珍しいアンバーの姿に若干戸惑い感じながらも、私は司令室を後にする。
治療場に行く途中、すれ違った兵士たちの言葉が自然と耳に入ってきた。
「それにしても凄かったな。部隊長の攻撃魔法。あんだけ苦戦した魔獣たちを一掃だぜ?」
「ほんと、凄かったよなぁ。それにしても、なんであんな強い人が、第五衛生兵部隊の部隊長なんかやってるんだ?」
五つある衛生兵部隊でも、この部隊は格でいえば一番下だ。
そもそもそんな攻撃魔法を使えるのならば、兵士が言う通り、攻撃部隊の、しかも上位の部隊に所属されていてもおかしくない。
「なんだ? 知らなかったのか? アンバー部隊長は以前は第二攻撃部隊の部隊長を務めていたんだぜ。なんでもその時戦った魔族から受けた傷が原因で前線から離れたんだとか」
「へー。知らなかったな。第二攻撃だなんて、エリート部隊じゃないか! そんな部隊の部隊長でも、満足に傷も治してもらえないんだなぁ」
「詳しくは知らないけどな。噂だよ。噂。怪我は治ったけど、呪いを受けてそれを取れなかったとか」
「呪いってあのずっと痛みを受けるってやつか? そりゃ嘘だろ。アンバー部隊長、いつもヘラヘラしてるじゃないか」
私はその言葉を聞いた瞬間、踵を返し、アンバーの部屋に戻った。
今の話と、アンバーの様子を見れば見当がつく。
そしてそれはできるだけ早くに対処しなければならない。
立ち入り禁止など聞いている場合ではなかった。
「失礼します‼」
「しつこいな……また君か。さっき出て行けと言ったはずだがね。なにか忘れ物でもしたかい?」
部屋に入ると、アンバーは既に立っているのが辛くなったようで、机に突っ伏すような格好でいた。
私が入ってきたのを確認しても動く様子はない。
「なんだい? 見ての通り、今動くのすらおっくうなんだ。忘れ物を見つけたら、今度こそさっさと出ていってくれ」
「ええ。大変な忘れ物をしていました。部隊長。あなた呪いに侵されていますね? しかも上位のものを含めて複数」
私の指摘にアンバーの眉が吊り上がる。
しかし、すでに言い返す気力と体力すら残っていないようだ。
「正直なところ、驚いています。じっとしているだけでも苦痛にさいなまれているはずです。それを他人に押し隠す努力、並大抵のものとは思えません」
私の言葉を聞いているのか分からないが、アンバーは一度だけゆっくりと瞬きをした。
「なぜ相談していただけなかったのですか? 就任直後に呪いを解く魔法を私が使えることはご存知だったはずです」
「無駄だよ……【痛み】を解けるくらいじゃ……もう何度も試したさ……高位の回復魔法の使い手に頼んでね……」
絞り出すような声でアンバーは答える。
おそらく今までは自分の魔力を総動員して、どうにか呪いを押さえ込んでいたに違いない。
それができたことも驚異だけれど、先ほどの戦闘で魔獣を一掃したという攻撃魔法。
それも驚異的な威力だったのだろう。
自身の魔力だけでは足りず、魔石を触媒にして使用した魔法。
魔力が尽きた今のアンバーは、無防備な身体で、恐ろしい呪いに襲われているのだ。
常人なら痛みで発狂したり、恐怖で自傷したり、多くの者は自分で命を絶つ選択をすると聞く。
それにも関わらず私になんとか弱みを見せぬよう、気丈に振舞おうとするアンバーの精神の強さに感服する。
「今すぐ患部を見せてください。まだ魔石も残っています。今やらなければ、最悪精神がやられますよ?」
「無駄だと……」
ここで押し問答をするつもりは無い。
私はアンバーが抵抗できないことを利用して、無理やり着ている軍服を脱がせた。
「これは……」
アンバーは私の二倍以上の年齢だろうか。
それにも関わらず、引き締まり無駄がない兵士の肉体を保っている。
その強靭な肉体を埋め尽くすかのように、呪いの紋様が描かれていた。
種類も複数あり、【痛み】、【恐怖】などはまだ優しい。
「まさか……【崩壊】まで……」
「それを知っているだけでも……大したもんだ……でも、これで無駄だということが……分かっただろ?」
【崩壊】は上位の魔族が使うとされる呪いで、それをかけられた者は、内部から腐敗し死に至る。
そして、呪いの厄介なところは、最も強い呪いを解ける解呪の魔法を使わなければ、初級の呪いすら解呪できない事だった。
「遅かったかもしれませんが、今気付けて良かった。少し時間はかかります。その格好では苦しいでしょう。横になってください」
「何を……する気だ……?」
「もちろん治療するんです! それ以外にありますか?」
私はアンバーを床に寝かせると、懐から魔石の最も質のいい物を選び取り出す。
それともうひとつ魔石を取ると、小さい方は砕いて飲み干した。
先ほどの治療で消耗した魔力が再び満たされる。
そして質のいい魔石を手に持つと、自分の使える最上級の解呪の魔法を唱え始めた。
私の両手からアンバーの全身に眩い光が伝わる。
その光に溶けるように、アンバーの身体に描かれていた紋様が消えていく。
やがて、光が収まる頃には、全身を埋め尽くしていた呪いの紋様は、跡形もなく綺麗に消え失せていた。
呪いから解放されたアンバーは瞬きを繰り返し私を見つめている。
「さぁ、あともうひと踏ん張りですよ。呪いは消えました。後は腐敗した内部を治療しましょう」
そして今度は治癒の魔法を唱える。
これでアンバーの身体は、健康的でどこにも問題のない肉体になったと言えるだろう。
「まだ信じられないな……」
呪いも、呪いによる体の損傷も回復したアンバーが、自分の身体を触りながら感慨深げに呟く。
今は以前からの貼り付いたような笑みは消え失せ、より自然な表情を見せる。
おそらく呪いの苦しみを他人に悟られまいと、必死で隠していたゆえの笑みだったのだろう。
今のアンバーの顔付きの方が、個人的には好感が持てる。
「とにかくありがとう。礼を言うよ」
「いえ。当然のことをしたまでです。負傷兵を癒すのが私たち衛生兵の役目ですから」
「ふむ。それはそうとフローラ嬢。君に言っておかなくちゃいけないことがある」
「なんでしょうか?」
アンバーは以前の笑みを作る。
私は嫌な予感がした。
「君はゴール侯爵令嬢かもしれないが、今は軍属。私の部下だ。上官である私に二度背いたね。一度目の魔石は許すと言った。しかし、次はそうはいかない」
「確かに上官の命令は絶対だとは心得ています。その点については弁明しません」
「うん。僕は出て行けと再三言った。しかし君は命令を聞くどころか、それに背き私の呪いを解いた。きれいさっぱりだ」
どうも様子がおかしい。
命令違反の厳罰を申し渡される覚悟をしていたのだが、アンバーはやけに嬉しそうだ。
「明らかな命令違反だ。よって……僕も君を聖女様とこれから呼ぶことにしよう」
「な⁉ 何を言っているのですか‼」
アンバーはいたずらっぽく笑う。
私はアンバーの意図が分からず、困惑していた。
「だって。僕の呪いは誰も治せなかったんだよ。前聖女様以外ね。残念ながら僕がこの呪いを受けた時には、すでに彼女は亡くなっていた」
「それと、部隊長が私を聖女と呼ぶのと何の関係が?」
「だからさ。君は誰がなんと言おうと、僕にとっての聖女様なのさ。誰がなんと言おうとね。王都でふんぞり返ってるだけの青二才の顔色を疑うのはもうやめだ」
「しかし、それではご自身の立場が危ういのでは?」
聖女と呼ばれることについての問題は、つい先ほどアンバー本人から指摘されたことだ。
私が聖女と呼ばれて、マリーゴールドも、そしてルチル王子も面白くは思わないだろう。
「大丈夫だよ。呪いが無くなった今、実力で僕をどうこうできる相手なんて限られている。まぁ、それに。前線の些細なことなんて彼は気にしていないさ。気にしていたら少しはここの環境だって良くなってるはずだ」
よほど呪いから解放されたことが嬉しかったのだろう。
アンバーは両手を広げ、少年のように目を輝かせている。
聖女と呼ばれることについては、元々私はそこまで気にしていなかった。
今更部隊長からもそう呼ばれても些細なことだろう。
「分かりました。とりあえず、治癒に成功できて良かったです。それでは、失礼します」
「ああ。ありがとう。聖女様。これからもよろしく頼むよ。僕は君への援助は惜しまないつもりだ。何かあればなんでも言ってくれ」
一礼して、退出しようとした時、窓を叩く音が聞こえた。
木の板がはめられただけの窓のため、音の原因は分からない。
興味が湧いて見ていると、アンバーは警戒することも無く窓を開けた。
すると、全身真っ黒な鳥が中に入ってきて、アンバーの差し出した腕に器用にとまる。
「なんですか? それは」
「ん? ああ。これは僕の使い魔だよ。これで色々と情報を個人的に集めてるんだ。君のことも、こいつを使って調べたのさ」
そう言いながらにこやかな顔で、使い魔だという黒い鳥のクチバシを耳の方へ近付ける。
使い魔というのは話を聞いたことはあるけれど、実際に見るのは初めてだ。
上位の魔導士などが使役する動物で、ある程度自分の意思通りに動かすことができるらしい。
動物の種類は様々で、空を飛べる点から鳥や、街中では狭いところにも入れるという理由から、猫やネズミなどが使われることが多いと聞く。
私はついつい興味本位で、そのやりとりを見入ってしまった。
アンバーにやり方を習えば、私にも使い魔を持つことができるだろうか。
「うん? なんだって⁉」
「どうしました?」
驚いた声をあげるアンバーに、自然と私は問いかけてしまった。
ただ、出て行けと言われてはいないから、居ても問題はなかったのだろう。
「大変なことが起きたみたいだよ。さっきの魔獣の群れ、襲われたのはここだけじゃないようだ」
「なんですって⁉ それで! 被害は⁉」
「まぁ、慌てるな。順を追って話すから。まず、ここから西に向かった方角に、魔王討伐軍の本営があるのは知っているかい?」
「ええ。各部隊を取りまとめる長官などが居ると聞きます。まさか⁉ そこが襲われたのですか?」
アンバーは一度頷く。
「そのまさかさ。しかも、間が悪い、と言うのがいいのか、それを狙ってなのかは知らないけど。その場に軍の総司令官に当たる、ルチル王子がいたらしい。しかも新しい『聖女様』を連れてね」
「そんな! ルチル王子が戦場に出るだなんて聞いたことがありません‼」
「ああ。僕も初めてさ。総司令官だって名ばかりだしね。何を思ったか知らないけれど、とにかくいたらしい。そりゃ警護も厳重さ。ここよりも強力で大勢の魔獣が押し寄せたらしいけど、なんとか撃退したらしい」
「そうですか。それは良かった」
アンバーの言葉に胸を撫で下ろす。
ルチル王子が、というわけではないが、本営が落ちれば魔王との戦が立ち行かなくなるのは必至だからだ。
被害の程は分からないけれど、最小限ですんだことを願うばかりだ。
ほっとしている私に向かって、アンバーは神妙な顔を向ける。
その表情が、私の心をざわつかせた。
「まさか……それで終わりじゃないんですか?」
「ああ。続きがある。魔獣は撃退した。ところがだ、一体の魔族が後から現れたらしい。しかもルチル王子の目の前に」
私は無意識に唾を飲み込んだ。
「まさかの僕が最後に戦った同じ魔族だったようだよ。そして、王子に呪いをかけた」
「まさか⁉ その呪いは――」
「そう。【崩壊】だよ」
呪いも、呪いによる体の損傷も回復したアンバーが、自分の身体を触りながら感慨深げに呟く。
今は以前からの貼り付いたような笑みは消え失せ、より自然な表情を見せる。
おそらく呪いの苦しみを他人に悟られまいと、必死で隠していたゆえの笑みだったのだろう。
今のアンバーの顔付きの方が、個人的には好感が持てる。
「とにかくありがとう。礼を言うよ」
「いえ。当然のことをしたまでです。負傷兵を癒すのが私たち衛生兵の役目ですから」
「ふむ。それはそうとフローラ嬢。君に言っておかなくちゃいけないことがある」
「なんでしょうか?」
アンバーは以前の笑みを作る。
私は嫌な予感がした。
「君はゴール侯爵令嬢かもしれないが、今は軍属。私の部下だ。上官である私に二度背いたね。一度目の魔石は許すと言った。しかし、次はそうはいかない」
「確かに上官の命令は絶対だとは心得ています。その点については弁明しません」
「うん。僕は出て行けと再三言った。しかし君は命令を聞くどころか、それに背き私の呪いを解いた。きれいさっぱりだ」
どうも様子がおかしい。
命令違反の厳罰を申し渡される覚悟をしていたのだが、アンバーはやけに嬉しそうだ。
「明らかな命令違反だ。よって……僕も君を聖女様とこれから呼ぶことにしよう」
「な⁉ 何を言っているのですか‼」
アンバーはいたずらっぽく笑う。
私はアンバーの意図が分からず、困惑していた。
「だって。僕の呪いは誰も治せなかったんだよ。前聖女様以外ね。残念ながら僕がこの呪いを受けた時には、すでに彼女は亡くなっていた」
「それと、部隊長が私を聖女と呼ぶのと何の関係が?」
「だからさ。君は誰がなんと言おうと、僕にとっての聖女様なのさ。誰がなんと言おうとね。王都でふんぞり返ってるだけの青二才の顔色を疑うのはもうやめだ」
「しかし、それではご自身の立場が危ういのでは?」
聖女と呼ばれることについての問題は、つい先ほどアンバー本人から指摘されたことだ。
私が聖女と呼ばれて、マリーゴールドも、そしてルチル王子も面白くは思わないだろう。
「大丈夫だよ。呪いが無くなった今、実力で僕をどうこうできる相手なんて限られている。まぁ、それに。前線の些細なことなんて彼は気にしていないさ。気にしていたら少しはここの環境だって良くなってるはずだ」
よほど呪いから解放されたことが嬉しかったのだろう。
アンバーは両手を広げ、少年のように目を輝かせている。
聖女と呼ばれることについては、元々私はそこまで気にしていなかった。
今更部隊長からもそう呼ばれても些細なことだろう。
「分かりました。とりあえず、治癒に成功できて良かったです。それでは、失礼します」
「ああ。ありがとう。聖女様。これからもよろしく頼むよ。僕は君への援助は惜しまないつもりだ。何かあればなんでも言ってくれ」
一礼して、退出しようとした時、窓を叩く音が聞こえた。
木の板がはめられただけの窓のため、音の原因は分からない。
興味が湧いて見ていると、アンバーは警戒することも無く窓を開けた。
すると、全身真っ黒な鳥が中に入ってきて、アンバーの差し出した腕に器用にとまる。
「なんですか? それは」
「ん? ああ。これは僕の使い魔だよ。これで色々と情報を個人的に集めてるんだ。君のことも、こいつを使って調べたのさ」
そう言いながらにこやかな顔で、使い魔だという黒い鳥のクチバシを耳の方へ近付ける。
使い魔というのは話を聞いたことはあるけれど、実際に見るのは初めてだ。
上位の魔導士などが使役する動物で、ある程度自分の意思通りに動かすことができるらしい。
動物の種類は様々で、空を飛べる点から鳥や、街中では狭いところにも入れるという理由から、猫やネズミなどが使われることが多いと聞く。
私はついつい興味本位で、そのやりとりを見入ってしまった。
アンバーにやり方を習えば、私にも使い魔を持つことができるだろうか。
「うん? なんだって⁉」
「どうしました?」
驚いた声をあげるアンバーに、自然と私は問いかけてしまった。
ただ、出て行けと言われてはいないから、居ても問題はなかったのだろう。
「大変なことが起きたみたいだよ。さっきの魔獣の群れ、襲われたのはここだけじゃないようだ」
「なんですって⁉ それで! 被害は⁉」
「まぁ、慌てるな。順を追って話すから。まず、ここから西に向かった方角に、魔王討伐軍の本営があるのは知っているかい?」
「ええ。各部隊を取りまとめる長官などが居ると聞きます。まさか⁉ そこが襲われたのですか?」
アンバーは一度頷く。
「そのまさかさ。しかも、間が悪い、と言うのがいいのか、それを狙ってなのかは知らないけど。その場に軍の総司令官に当たる、ルチル王子がいたらしい。しかも新しい『聖女様』を連れてね」
「そんな! ルチル王子が戦場に出るだなんて聞いたことがありません‼」
「ああ。僕も初めてさ。総司令官だって名ばかりだしね。何を思ったか知らないけれど、とにかくいたらしい。そりゃ警護も厳重さ。ここよりも強力で大勢の魔獣が押し寄せたらしいけど、なんとか撃退したらしい」
「そうですか。それは良かった」
アンバーの言葉に胸を撫で下ろす。
ルチル王子が、というわけではないが、本営が落ちれば魔王との戦が立ち行かなくなるのは必至だからだ。
被害の程は分からないけれど、最小限ですんだことを願うばかりだ。
ほっとしている私に向かって、アンバーは神妙な顔を向ける。
その表情が、私の心をざわつかせた。
「まさか……それで終わりじゃないんですか?」
「ああ。続きがある。魔獣は撃退した。ところがだ、一体の魔族が後から現れたらしい。しかもルチル王子の目の前に」
私は無意識に唾を飲み込んだ。
「まさかの僕が最後に戦った同じ魔族だったようだよ。そして、王子に呪いをかけた」
「まさか⁉ その呪いは――」
「そう。【崩壊】だよ」
「どうするんだい? 今から本営に向かうなら、許可をしよう。君なら治せるのだろう?」
アンバーはそんなことを言い出した。
しかし、先ほどの話が本当だとしても、私の出る幕などないだろう。
「いいえ。マリーゴールドが一緒なのですよね。ルチル王子が承認した聖女がその場にいるというのに、他の者に治療させるとは思えません」
「王族の専属の『聖女様』、か。まぁ、確かにそうだね。しかし、僕はよくその『聖女様』を知らないけれど、君と同じくらい凄いのかい?」
聞かれて私はマリーゴールドのことを思い出す。
彼女は要領の良い子だった。もちろん悪い意味で。
彼女は努力という言葉が嫌いだった。
そんな彼女が上位の呪いを解くほどの解呪の魔法を使えるとは到底思えない。
私は一度だけ首を横に振る。
それを見たアンバーは深いため息をつく。
「まったく。ルチル王子には困ったもんだね。知ってるかい? 現国王からルチル王子に指揮権が移ってから、前線は徐々に後退してるのさ。一部を除いてね。ほとんど、彼の指揮があまりにも的を射ていないせいだって噂だよ」
「そうなんですね。ちなみに、前線を押し進めてる、その一部というのは?」
「気になるかい? 魔王討伐軍一の精鋭部隊、攻撃第一部隊さ。部隊長は僕の同期だけど、まぁ戦うために生まれたようなやつだね」
アンバーは旧友を思い懐かしんだのか、少し微笑む。
「彼女がさ、ルチル王子の言う無理難題を全て成し遂げちゃうから。困るんだよね。彼女の部隊だけ規格外なんだから。他の部隊に同じことができるはずないんだ」
「彼女? 第一部隊の部隊長は女性なんですか?」
「知らなかった? 有名なんだけどな。ダリアって言うんだ。ダリア・パルフェ。名前の通り、完璧ってやつだ」
「知りませんでした。覚えておきます」
その後、私はアンバーと二言三言話し、司令室を後にした。
治療場には戻らず、私は自室へと向かっていた。
自室に戻ると、飾ってあるリラの花が目に付く。
今も濃い紫の花を咲かせている。
私は自分の荷物から手紙に必要な一式を取り出すと、ベリル王子に向けて手紙を書き始めた。
内容はルチル王子の呪いについてだ。
アンバーの使い魔の件は伏せておくとして、この手紙はベリル王子以外に渡ることがないはずだから、ひとまずは呪いについて触れても良いだろう。
私は、ルチル王子がかかった呪いを魔石の力を借りたものの解けたことを書き、必要があれば治癒をすることを書き留めた。
恐らくルチル王子に伝えても一蹴されてお終いだろうが、ベリル王子はその点思慮深い。
私に対してどう言う感情を持っているかは知らないけれど、ルチル王子の呪いを解けるのが私だけだと分かれば、きっと申し出を断りはしないだろう。
正直なところ、私自身はルチル王子にいい印象は持っていない。
傲慢で、短絡的で、その上自信家。
下手に権力があるため、誰もとがめるものがいなかったのが原因でもあるかもしれないけれど、恐らく持って生まれたものだろう。
しかし、性格の良し悪しと、助けるか否かは関係がない。
命に貴賤はないが、身分が高いから助けなくて良いと言うわけでもないのだ。
助けられるものなら助けたい。
私のわがままかもしれないけれど、助けられるのに見て見ぬ振りをすることは出来なかった。
ベリル王子に定期的に教えるよう言われているリラの花の色と、ルチル王子の呪いについて書き終わると、私は専用の封をして、兵士に届けてもらうよう願った。
今までベリル王子から返信が来たのは一度だけ。
いつ来るかも分からない返信を、私は根気よく待つつもりだった。
しかし、返信は思いの外早く届いた。
私は急いでその返信の封を切り、中身を確認する。
するとこんなことが書かれていた。
『フローラへ。
手紙ありがとう。兄の容態についてすでに知っていることに驚いている。書いていないということは、聞いても理由を教えてくれはしないだろうから聞かないことにする。
俺は君に治してもらうよう兄にすぐに申し出たが、断られてしまった――』
こんな出だしで書かれていた手紙の中身を見て私は訝しがる。
何故なら、続く言葉で、ルチル王子の呪いはマリーゴールドによって解かれたと書いてあったからだ。
ベリル王子の手紙の内容を要約するとこういうことだった。
呪いを受けた時、マリーゴールドは十分な魔石がその場にあったにも関わらず、解呪出来なかった。
その間、ルチル王子は痛みなどから失神と覚醒を繰り返し、覚醒している間は発狂したように叫び続けていたらしい。
見る者にさえ恐怖を与える様相だったらしい。
その後、治癒に専念するためとマリーゴールドはルチル王子を隔離し、必要最低限の小間使い以外を近づかせなかったらしい。
しかし、治癒は難航したようで、毎日その一角から、ルチル王子の叫び声が途切れ途切れに聞こえてくるのだとか。
そこで、私の手紙を受け取ったベリル王子が、私にルチル王子の解呪をさせようと申し出た。
しかしそれが断られた。
断ったのはルチル王子ではなく、マリーゴールドだという。
そしてその後直ぐに、ルチル王子の解呪に成功したとマリーゴールドが言い出したというのだ。
不思議に思ったベリル王子は、面会を申し出たがこれも断られたのだとか。
確かに離れても聞こえてくるルチル王子の絶叫はその日から聞こえなくなったため、解呪が成功したのだろうという話になっているという。
「どうも釈然としないけれど、私がどうこうできる話でもないわね。助かったのなら良かったと思うべきね」
そう思いながら、私はベリル王子に返信と、リラの花の色を書いた手紙を再度送った。
リラの花は以前よりも更に濃い紫色の花を咲かせていた。
アンバーはそんなことを言い出した。
しかし、先ほどの話が本当だとしても、私の出る幕などないだろう。
「いいえ。マリーゴールドが一緒なのですよね。ルチル王子が承認した聖女がその場にいるというのに、他の者に治療させるとは思えません」
「王族の専属の『聖女様』、か。まぁ、確かにそうだね。しかし、僕はよくその『聖女様』を知らないけれど、君と同じくらい凄いのかい?」
聞かれて私はマリーゴールドのことを思い出す。
彼女は要領の良い子だった。もちろん悪い意味で。
彼女は努力という言葉が嫌いだった。
そんな彼女が上位の呪いを解くほどの解呪の魔法を使えるとは到底思えない。
私は一度だけ首を横に振る。
それを見たアンバーは深いため息をつく。
「まったく。ルチル王子には困ったもんだね。知ってるかい? 現国王からルチル王子に指揮権が移ってから、前線は徐々に後退してるのさ。一部を除いてね。ほとんど、彼の指揮があまりにも的を射ていないせいだって噂だよ」
「そうなんですね。ちなみに、前線を押し進めてる、その一部というのは?」
「気になるかい? 魔王討伐軍一の精鋭部隊、攻撃第一部隊さ。部隊長は僕の同期だけど、まぁ戦うために生まれたようなやつだね」
アンバーは旧友を思い懐かしんだのか、少し微笑む。
「彼女がさ、ルチル王子の言う無理難題を全て成し遂げちゃうから。困るんだよね。彼女の部隊だけ規格外なんだから。他の部隊に同じことができるはずないんだ」
「彼女? 第一部隊の部隊長は女性なんですか?」
「知らなかった? 有名なんだけどな。ダリアって言うんだ。ダリア・パルフェ。名前の通り、完璧ってやつだ」
「知りませんでした。覚えておきます」
その後、私はアンバーと二言三言話し、司令室を後にした。
治療場には戻らず、私は自室へと向かっていた。
自室に戻ると、飾ってあるリラの花が目に付く。
今も濃い紫の花を咲かせている。
私は自分の荷物から手紙に必要な一式を取り出すと、ベリル王子に向けて手紙を書き始めた。
内容はルチル王子の呪いについてだ。
アンバーの使い魔の件は伏せておくとして、この手紙はベリル王子以外に渡ることがないはずだから、ひとまずは呪いについて触れても良いだろう。
私は、ルチル王子がかかった呪いを魔石の力を借りたものの解けたことを書き、必要があれば治癒をすることを書き留めた。
恐らくルチル王子に伝えても一蹴されてお終いだろうが、ベリル王子はその点思慮深い。
私に対してどう言う感情を持っているかは知らないけれど、ルチル王子の呪いを解けるのが私だけだと分かれば、きっと申し出を断りはしないだろう。
正直なところ、私自身はルチル王子にいい印象は持っていない。
傲慢で、短絡的で、その上自信家。
下手に権力があるため、誰もとがめるものがいなかったのが原因でもあるかもしれないけれど、恐らく持って生まれたものだろう。
しかし、性格の良し悪しと、助けるか否かは関係がない。
命に貴賤はないが、身分が高いから助けなくて良いと言うわけでもないのだ。
助けられるものなら助けたい。
私のわがままかもしれないけれど、助けられるのに見て見ぬ振りをすることは出来なかった。
ベリル王子に定期的に教えるよう言われているリラの花の色と、ルチル王子の呪いについて書き終わると、私は専用の封をして、兵士に届けてもらうよう願った。
今までベリル王子から返信が来たのは一度だけ。
いつ来るかも分からない返信を、私は根気よく待つつもりだった。
しかし、返信は思いの外早く届いた。
私は急いでその返信の封を切り、中身を確認する。
するとこんなことが書かれていた。
『フローラへ。
手紙ありがとう。兄の容態についてすでに知っていることに驚いている。書いていないということは、聞いても理由を教えてくれはしないだろうから聞かないことにする。
俺は君に治してもらうよう兄にすぐに申し出たが、断られてしまった――』
こんな出だしで書かれていた手紙の中身を見て私は訝しがる。
何故なら、続く言葉で、ルチル王子の呪いはマリーゴールドによって解かれたと書いてあったからだ。
ベリル王子の手紙の内容を要約するとこういうことだった。
呪いを受けた時、マリーゴールドは十分な魔石がその場にあったにも関わらず、解呪出来なかった。
その間、ルチル王子は痛みなどから失神と覚醒を繰り返し、覚醒している間は発狂したように叫び続けていたらしい。
見る者にさえ恐怖を与える様相だったらしい。
その後、治癒に専念するためとマリーゴールドはルチル王子を隔離し、必要最低限の小間使い以外を近づかせなかったらしい。
しかし、治癒は難航したようで、毎日その一角から、ルチル王子の叫び声が途切れ途切れに聞こえてくるのだとか。
そこで、私の手紙を受け取ったベリル王子が、私にルチル王子の解呪をさせようと申し出た。
しかしそれが断られた。
断ったのはルチル王子ではなく、マリーゴールドだという。
そしてその後直ぐに、ルチル王子の解呪に成功したとマリーゴールドが言い出したというのだ。
不思議に思ったベリル王子は、面会を申し出たがこれも断られたのだとか。
確かに離れても聞こえてくるルチル王子の絶叫はその日から聞こえなくなったため、解呪が成功したのだろうという話になっているという。
「どうも釈然としないけれど、私がどうこうできる話でもないわね。助かったのなら良かったと思うべきね」
そう思いながら、私はベリル王子に返信と、リラの花の色を書いた手紙を再度送った。
リラの花は以前よりも更に濃い紫色の花を咲かせていた。
「今日の清掃終わりました‼」
デイジーが元気な声を出す。
清掃というのは治療場のことだ。
別に私は彼女の上官でもないので、いちいち報告する必要ない。
しかし、それぞれ持ち回りでやる様々な仕事の報告を、みな私にするようになっていた。
私が初めてここに来たときは、治療場は強い臭いと様々なもので汚れていて酷い有様だった。
今は、各チームで清掃をしているため、非常に清潔感あふれる場所に変わっている。
汚い所で治癒を行うと、思わぬ結果が現れることがあり、清潔になった今はその問題は鳴りを潜めた。
それでなくても、治療する側もされる側も汚いよりはきれいな場所の方が嬉しいだろう。
デイジーが入ってきた時、私はベリル王子から来た手紙を開いていた。
流石に人に見せるわけにもいかないため、私は慌てて手紙をしまった。
「あれ? 聖女様。なんですか? 手紙みたいなの読んでました?」
「なんでもないわ」
どう答えていいのか分からず、自分でも少しぶっきらぼうだと思う言い方で返してしまう。
その私の様子に、何を勘違いしたのか、デイジーは嬉しそうに目を輝かせた。
「もしかして! 恋文ですか⁉ わぁ。素敵ですねぇ。私も文通とかしてみたいなぁ」
「そんなんじゃないったら」
「はいはい。ふふ。良かった。聖女様も人の子なんですね。きっとお相手は高貴で素敵な方なんでしょうねぇ!」
「もう……用件が終わったのなら、出て行きなさい。まだ非番には早いでしょう?」
私の態度を面白がるように、デイジーは明らかな笑顔を作り、一礼して部屋を出ていった。
それを見送った後、私は一度ため息をついてから、読みかけの手紙を開き直した。
ベリル王子からの手紙の関心ごとは、最近はもっぱら陣営の中の問題の有無についてだった。
私は魔石の補充や、使用許可の簡略化、また衛生兵の増員や教育機関の設立など、思いつくままにベリル王子に手紙を書く際に綴った。
どうやら、呪いが解かれたというものの、ルチル王子は現在も療養中で、表には出てきていないらしい。
そのため、暫定的に総司令官の席が空席になっている、とアンバーから聞いた。
おそらくこのままルチル王子の容態が回復しなければ、総司令官は第二王子であり第二王位継承権を持つベリル王子になるのではないかとも言っていた。
それはベリル王子の手紙には書かれていないものの、もしそうだとしても、わざわざ手紙で私にそうだと教えるとは思えない。
ただ、仮にベリル王子が総司令官につけば、私の提案した改善要求も、いずれは実現してくれるかもしれない。
そんなことを思いながら、私は読み終わると、定例のリラの花の色と、最近の状況を書き、兵士を呼ぶと手紙を渡した。
何度もやりとりを繰り返すうちに、兵士も慣れてきたようで、今では私が兵士を部屋に呼ぶと手紙だと思われるようになっていた。
受け取りに来る兵士も固定化し、その兵士というのはここにきて最初に助けたクロムという青年だった。
「お呼びでしょうか!」
「クロム。いつも悪いわね。また、これを頼むわ」
「かしこまりました!」
そう言いながら、クロムは私から手紙を受け取る。
そして何か思案したような素振りを見せた後、私に質問を投げかけてきた。
「失礼なことを聞くようですが。これは聖女様の大切な方へのお手紙でしょうか?」
「まぁ。あなたまでそんなことを言うの? その手紙のことなら違うわよ。」
先ほどデイジーとのやり取りで十分だと思っていた私は、投げやりにそう答える。
それを聞いたクロムは、何故か嬉しそうな顔を見せた。
「そうですか! 不躾な質問。失礼しました! 確かにこの手紙、承りました‼」
「いいえ。いいわ。じゃあ、頼むわね」
手紙を書き終え、私は治療場へ向かう。
中ではいつものように、魔族や魔獣との戦闘で負傷した兵たちが、ここの衛生兵によって治療を受けていた。
私も自分の持ち場につき、負傷兵たちへの治療に当たる。
目の前にいる兵士は、どうやら脚を切り落とされたらしい。
出血を抑えるため、傷口は魔法か実際の炎か分からないが、焼き固められていた。
確かに上位の回復魔法を使えば、焼いた後も失った脚も綺麗に治るが、かなりの荒い応急処置だと言える。
「よく頑張ったわね。もう大丈夫よ。今から治すから」
「あぁ! 脚が! 脚が無いはずなのに、痛い! 無い脚が痛いんだ! どうにかしてくれ‼」
私の声に、今まで押し黙っていた兵士が声を荒げる。
どうやら必死で耐えていたものが、私に話しかけられるということで吹き出したのだろう。
無くなったはずの部位が痛むというのは幻肢痛というものらしい。
呪いでもそれを再現することができると聞くけれど、これは呪いではなく精神的なものだとか。
いずれにしろ、私がやることは決まっている。
目の前の兵士の無くなった方の脚の付け根あたりに手を当て、回復魔法を唱えた。
まず私の手が淡く光り、そしてその光は手を伝わって無くなった脚を形取るように広がっていく。
光が一瞬眩しいほどに光り輝き、その光がなくなると、そこには失った脚が元どおりについていた。
「お、俺の……俺の脚が‼ うわぁぁ! 俺の脚がある‼ ありがとう……ありがとう‼ あんたか! 聖女様っていうのは!」
先ほどまで弱音を言っていた兵士は、自分の脚が戻ったことを見ると、涙を流しながら私に感謝の念を言ってきた。
私はそんな兵士の頭を優しく撫でた後、次の負傷兵の治療へと向かった。
デイジーが元気な声を出す。
清掃というのは治療場のことだ。
別に私は彼女の上官でもないので、いちいち報告する必要ない。
しかし、それぞれ持ち回りでやる様々な仕事の報告を、みな私にするようになっていた。
私が初めてここに来たときは、治療場は強い臭いと様々なもので汚れていて酷い有様だった。
今は、各チームで清掃をしているため、非常に清潔感あふれる場所に変わっている。
汚い所で治癒を行うと、思わぬ結果が現れることがあり、清潔になった今はその問題は鳴りを潜めた。
それでなくても、治療する側もされる側も汚いよりはきれいな場所の方が嬉しいだろう。
デイジーが入ってきた時、私はベリル王子から来た手紙を開いていた。
流石に人に見せるわけにもいかないため、私は慌てて手紙をしまった。
「あれ? 聖女様。なんですか? 手紙みたいなの読んでました?」
「なんでもないわ」
どう答えていいのか分からず、自分でも少しぶっきらぼうだと思う言い方で返してしまう。
その私の様子に、何を勘違いしたのか、デイジーは嬉しそうに目を輝かせた。
「もしかして! 恋文ですか⁉ わぁ。素敵ですねぇ。私も文通とかしてみたいなぁ」
「そんなんじゃないったら」
「はいはい。ふふ。良かった。聖女様も人の子なんですね。きっとお相手は高貴で素敵な方なんでしょうねぇ!」
「もう……用件が終わったのなら、出て行きなさい。まだ非番には早いでしょう?」
私の態度を面白がるように、デイジーは明らかな笑顔を作り、一礼して部屋を出ていった。
それを見送った後、私は一度ため息をついてから、読みかけの手紙を開き直した。
ベリル王子からの手紙の関心ごとは、最近はもっぱら陣営の中の問題の有無についてだった。
私は魔石の補充や、使用許可の簡略化、また衛生兵の増員や教育機関の設立など、思いつくままにベリル王子に手紙を書く際に綴った。
どうやら、呪いが解かれたというものの、ルチル王子は現在も療養中で、表には出てきていないらしい。
そのため、暫定的に総司令官の席が空席になっている、とアンバーから聞いた。
おそらくこのままルチル王子の容態が回復しなければ、総司令官は第二王子であり第二王位継承権を持つベリル王子になるのではないかとも言っていた。
それはベリル王子の手紙には書かれていないものの、もしそうだとしても、わざわざ手紙で私にそうだと教えるとは思えない。
ただ、仮にベリル王子が総司令官につけば、私の提案した改善要求も、いずれは実現してくれるかもしれない。
そんなことを思いながら、私は読み終わると、定例のリラの花の色と、最近の状況を書き、兵士を呼ぶと手紙を渡した。
何度もやりとりを繰り返すうちに、兵士も慣れてきたようで、今では私が兵士を部屋に呼ぶと手紙だと思われるようになっていた。
受け取りに来る兵士も固定化し、その兵士というのはここにきて最初に助けたクロムという青年だった。
「お呼びでしょうか!」
「クロム。いつも悪いわね。また、これを頼むわ」
「かしこまりました!」
そう言いながら、クロムは私から手紙を受け取る。
そして何か思案したような素振りを見せた後、私に質問を投げかけてきた。
「失礼なことを聞くようですが。これは聖女様の大切な方へのお手紙でしょうか?」
「まぁ。あなたまでそんなことを言うの? その手紙のことなら違うわよ。」
先ほどデイジーとのやり取りで十分だと思っていた私は、投げやりにそう答える。
それを聞いたクロムは、何故か嬉しそうな顔を見せた。
「そうですか! 不躾な質問。失礼しました! 確かにこの手紙、承りました‼」
「いいえ。いいわ。じゃあ、頼むわね」
手紙を書き終え、私は治療場へ向かう。
中ではいつものように、魔族や魔獣との戦闘で負傷した兵たちが、ここの衛生兵によって治療を受けていた。
私も自分の持ち場につき、負傷兵たちへの治療に当たる。
目の前にいる兵士は、どうやら脚を切り落とされたらしい。
出血を抑えるため、傷口は魔法か実際の炎か分からないが、焼き固められていた。
確かに上位の回復魔法を使えば、焼いた後も失った脚も綺麗に治るが、かなりの荒い応急処置だと言える。
「よく頑張ったわね。もう大丈夫よ。今から治すから」
「あぁ! 脚が! 脚が無いはずなのに、痛い! 無い脚が痛いんだ! どうにかしてくれ‼」
私の声に、今まで押し黙っていた兵士が声を荒げる。
どうやら必死で耐えていたものが、私に話しかけられるということで吹き出したのだろう。
無くなったはずの部位が痛むというのは幻肢痛というものらしい。
呪いでもそれを再現することができると聞くけれど、これは呪いではなく精神的なものだとか。
いずれにしろ、私がやることは決まっている。
目の前の兵士の無くなった方の脚の付け根あたりに手を当て、回復魔法を唱えた。
まず私の手が淡く光り、そしてその光は手を伝わって無くなった脚を形取るように広がっていく。
光が一瞬眩しいほどに光り輝き、その光がなくなると、そこには失った脚が元どおりについていた。
「お、俺の……俺の脚が‼ うわぁぁ! 俺の脚がある‼ ありがとう……ありがとう‼ あんたか! 聖女様っていうのは!」
先ほどまで弱音を言っていた兵士は、自分の脚が戻ったことを見ると、涙を流しながら私に感謝の念を言ってきた。
私はそんな兵士の頭を優しく撫でた後、次の負傷兵の治療へと向かった。
「え? 王都への帰還命令ですか⁉」
「うん。そうだね」
司令室に突然呼び出され、最初にアンバーに告げられたのが、王都に戻れという話だった。
あまりの唐突な命令に、私は異議を申し出る。
「突然過ぎます! 帰還理由を教えてください。私の行動に問題があったとは思えませんが、何か理由があるなら改善します。やっと軌道に乗り始めている最中なのは部隊長もご存知のはずです‼」
一気にまくし立てる私に、アンバーは両手を前に出してなだめる仕草をする。
「まぁまぁ。今から説明するから。聖女様。いいね?」
アンバーの表情を見て、この命令が今目の前にいる人物の本意では無いと悟り、少し気持ちを落ち着かせる。
「まず、僕だって寝耳に水さ。実際君はよくやってくれている。知ってるかい? 君が来る前のここに運ばれた負傷兵の致死率は約四割だったんだ。それが、今では、ほぼゼロと言っていい」
「ええ。色々とやっていますからね。だけど、まだ足りません。今では衛生兵の質も量も十分とは言えません」
デイジーを始め、徐々に何人かは、初級の解毒魔法や中級の治癒魔法への足掛かりができ始めようとしていた。
しかし、それでも重傷の兵士の対応はほとんど私がしている。
もしここで私が抜ければ、瓦解する、とまではいかないものの、かなりの無理を強いることになるだろう。
そうすれば、緊急の場合に対応が難しくなる。
魔石が十分に確保できていない現状、無理をすれば衛生兵にも犠牲が出る危険性がある。
犠牲の上での奉仕ではいけないのだ。
「うんうん。そうだね。その点も聖女様はよくやってくれていると思うよ。彼女らがあそこまで回復魔法を使いこなすようになるとは。正直僕は思いもしなかったよ」
「運良く素質が高い人たちが多くいてくれたおかげです。また、彼女らも勤勉で、私も助かっています」
「ちょっと話が逸れたね。とにかく、君には王都に帰還してもらわないといけない。これは総司令官命令だからね」
「総司令官……ですか?」
総司令官と言われて私は首を傾げる。
国王は今も病に伏せているはずで、実権を任されているルチル王子もまだ療養中の身のはずだ。
「うん。ベリル王子直々の命令らしいよ。いやぁたまげたね。聖女様はさすが侯爵令嬢だけあるってことかな? ベリル王子と面識があるなんて」
「ベリル王子が総司令官ということは、正式に決まったのですか⁉」
「うん。どうやらそうみたい。この前僕の所にも伝令が来たよ。それでね、とにかく戻るしかない。寂しくなるけどね」
「分かりました……とりあえず、荷物の整理をして来ます。日時はいつでしょうか?」
前にアンバーが言っていたように、とうとうベリル王子が総司令官に就任したということは、今までに送っていた手紙の内容の実現の可能性も出て来たということだ。
そう考えれば考えるほど、今この状況で現場を後にするのが口惜しくてたまらなかった。
「いや。そんな暇はないんだ。今すぐに出発だ。とりあえず、最低限必要なものを持って行ってくれ。荷物は後から送る手配をすることになっている」
「なんですって⁉ それだけ緊急、ということでしょうか?」
「どうだろうね……正直お偉いさんの考えることなんて僕は分からないさ。とりあえず、すでに移動の用意は済ませてある。護衛もね。思えば短い間だったけど、寂しくなるよ……」
「分かりました。ありがとうございます。部隊長も……色々とありがとうございました」
私は衛生兵たちに簡単な伝言を頼み、また、伝えきれないことは後日手紙で送ることを伝えてその場を後にする。
前線の状況も気になるものの、すでに自分の力でどうすることもできないというのは理解していた。
それよりも、今は王都への帰還命令のことについて考えていた。
ベリル王子が思いつきで何かをする人物だとは思えない。
これだけ急かすということは、何かしらの重大な理由があるということだろう。
移動する間、私はこれから起こることが何なのかをぼんやりと考えていた。
「聖女様。考えことですか? でも、良かったですね。安全な場所に帰ることができて。俺としては正直、寂しいってのがありますけど」
「ああ……クロム。ええ、ちょっと何故突然呼び戻されたのかと考えていてね」
護衛として付けられたクロムが、私に話しかけて来た。
何でも、手紙のやり取りの際も、護衛の件も本人がアンバーに直に頼んでその役目を勝ち取ったのだとか。
手紙のやり取りはともかく、護衛という点ではクロムは第五衛生兵部隊に所属する者の中で、アンバーを除けば一番有能だと言えた。
逆に言えば、そんな彼が陣営を離れることを許可してくれたアンバーの、私に対する配慮も並々ならないと感謝している。
実際、陣営へ向かう最中に魔獣に襲われ戦線に辿り着くことなく命を失う、ということがないわけではない。
そのため、ある程度重要な人物の陣営から最寄りの街までの移動の際は、護衛が付くのがほとんどだった。
しかし、てっきりクロムも街までの護衛かと思っていたら、王都まで一緒に付いてくるとのことだった。
何でも、護衛を王都まで付けることも総司令官、つまりベリル王子の要求だったとか。
「もうすぐ王都に着きますよ。俺、王都に行くの初めてなんですよ。凄いですね……」
クロムの言葉に外の風景に目を向ける。
目の前には、生まれてからつい最近まで育った街並みが広がっていた。
「うん。そうだね」
司令室に突然呼び出され、最初にアンバーに告げられたのが、王都に戻れという話だった。
あまりの唐突な命令に、私は異議を申し出る。
「突然過ぎます! 帰還理由を教えてください。私の行動に問題があったとは思えませんが、何か理由があるなら改善します。やっと軌道に乗り始めている最中なのは部隊長もご存知のはずです‼」
一気にまくし立てる私に、アンバーは両手を前に出してなだめる仕草をする。
「まぁまぁ。今から説明するから。聖女様。いいね?」
アンバーの表情を見て、この命令が今目の前にいる人物の本意では無いと悟り、少し気持ちを落ち着かせる。
「まず、僕だって寝耳に水さ。実際君はよくやってくれている。知ってるかい? 君が来る前のここに運ばれた負傷兵の致死率は約四割だったんだ。それが、今では、ほぼゼロと言っていい」
「ええ。色々とやっていますからね。だけど、まだ足りません。今では衛生兵の質も量も十分とは言えません」
デイジーを始め、徐々に何人かは、初級の解毒魔法や中級の治癒魔法への足掛かりができ始めようとしていた。
しかし、それでも重傷の兵士の対応はほとんど私がしている。
もしここで私が抜ければ、瓦解する、とまではいかないものの、かなりの無理を強いることになるだろう。
そうすれば、緊急の場合に対応が難しくなる。
魔石が十分に確保できていない現状、無理をすれば衛生兵にも犠牲が出る危険性がある。
犠牲の上での奉仕ではいけないのだ。
「うんうん。そうだね。その点も聖女様はよくやってくれていると思うよ。彼女らがあそこまで回復魔法を使いこなすようになるとは。正直僕は思いもしなかったよ」
「運良く素質が高い人たちが多くいてくれたおかげです。また、彼女らも勤勉で、私も助かっています」
「ちょっと話が逸れたね。とにかく、君には王都に帰還してもらわないといけない。これは総司令官命令だからね」
「総司令官……ですか?」
総司令官と言われて私は首を傾げる。
国王は今も病に伏せているはずで、実権を任されているルチル王子もまだ療養中の身のはずだ。
「うん。ベリル王子直々の命令らしいよ。いやぁたまげたね。聖女様はさすが侯爵令嬢だけあるってことかな? ベリル王子と面識があるなんて」
「ベリル王子が総司令官ということは、正式に決まったのですか⁉」
「うん。どうやらそうみたい。この前僕の所にも伝令が来たよ。それでね、とにかく戻るしかない。寂しくなるけどね」
「分かりました……とりあえず、荷物の整理をして来ます。日時はいつでしょうか?」
前にアンバーが言っていたように、とうとうベリル王子が総司令官に就任したということは、今までに送っていた手紙の内容の実現の可能性も出て来たということだ。
そう考えれば考えるほど、今この状況で現場を後にするのが口惜しくてたまらなかった。
「いや。そんな暇はないんだ。今すぐに出発だ。とりあえず、最低限必要なものを持って行ってくれ。荷物は後から送る手配をすることになっている」
「なんですって⁉ それだけ緊急、ということでしょうか?」
「どうだろうね……正直お偉いさんの考えることなんて僕は分からないさ。とりあえず、すでに移動の用意は済ませてある。護衛もね。思えば短い間だったけど、寂しくなるよ……」
「分かりました。ありがとうございます。部隊長も……色々とありがとうございました」
私は衛生兵たちに簡単な伝言を頼み、また、伝えきれないことは後日手紙で送ることを伝えてその場を後にする。
前線の状況も気になるものの、すでに自分の力でどうすることもできないというのは理解していた。
それよりも、今は王都への帰還命令のことについて考えていた。
ベリル王子が思いつきで何かをする人物だとは思えない。
これだけ急かすということは、何かしらの重大な理由があるということだろう。
移動する間、私はこれから起こることが何なのかをぼんやりと考えていた。
「聖女様。考えことですか? でも、良かったですね。安全な場所に帰ることができて。俺としては正直、寂しいってのがありますけど」
「ああ……クロム。ええ、ちょっと何故突然呼び戻されたのかと考えていてね」
護衛として付けられたクロムが、私に話しかけて来た。
何でも、手紙のやり取りの際も、護衛の件も本人がアンバーに直に頼んでその役目を勝ち取ったのだとか。
手紙のやり取りはともかく、護衛という点ではクロムは第五衛生兵部隊に所属する者の中で、アンバーを除けば一番有能だと言えた。
逆に言えば、そんな彼が陣営を離れることを許可してくれたアンバーの、私に対する配慮も並々ならないと感謝している。
実際、陣営へ向かう最中に魔獣に襲われ戦線に辿り着くことなく命を失う、ということがないわけではない。
そのため、ある程度重要な人物の陣営から最寄りの街までの移動の際は、護衛が付くのがほとんどだった。
しかし、てっきりクロムも街までの護衛かと思っていたら、王都まで一緒に付いてくるとのことだった。
何でも、護衛を王都まで付けることも総司令官、つまりベリル王子の要求だったとか。
「もうすぐ王都に着きますよ。俺、王都に行くの初めてなんですよ。凄いですね……」
クロムの言葉に外の風景に目を向ける。
目の前には、生まれてからつい最近まで育った街並みが広がっていた。
「やあ、フローラ。よく戻って来てくれたね。急な命令で済まない」
王都に到着し、実家による暇も与えられず、私は王城へと向かった。
そこで、身支度を済ませ、ドレス姿に着替えた私は、その足でベリル王子に謁見する。
柔らかそうな金髪と蒼色の瞳を持った顔は、嬉しそうな笑みを浮かべていた。
私は王族に対する一礼を済ませた後、ここに呼ばれた用件を聞く。
「ご無沙汰しております。ベリル殿下。お元気そうで何よりです。と、挨拶はこれくらいにさせていただきます。私を帰還させるとはどういうことでしょうか?」
「ふふふ。君は変わらないね。大きくなり美しい女性になっても、昔のままだ。そうだね、私もそんなに時間の余裕があるわけじゃないんだ。お互いのため、さっさと本題に入ろうか」
ベリル王子は私を別室へと案内する。
他に付き添いの者は一人だけだ。
鋭い目つきをしたこの人物を私は初めて見る。
服装から見るに執事長か何かだろうか。
「こちらでございます」
移動の最中に名前を聞き、クリスと名乗った人物は、王城の一角になる部屋へ着くと、扉を開ける。
その中には、三人の人物が居た。
「フローラ‼ お願い‼ 助けて‼ 貴女と私の仲じゃない‼」
「…………‼」
三人のうち一人は、拘束されて身動きが取れないようになっているマリーゴールドだった。
私との仲と言っても、そこまで親しかった記憶はない。
もう一人は護衛だろうか。
私たちが入ってくるのを見ると、一礼をした。
そして最後の一人の様子に私は目を見開いた。
それはベッドに横たわり、今も痛みによる失神と覚醒を繰り返すルチル王子だった。
その顔は恐ろしいまでに苦悶の表情に支配されていて、何かを叫ぼうと口を大きく開いているが、聞こえるのは息が漏れ出る音だけだった。
恐らく喉を潰されて声が出ないようになっているのだろう。
「驚いたかい? 私もこの現状を目の当たりにした時には大層驚いたよ。ねぇ? マリーゴールド」
「ベリル王子‼ どうか! 私の話をお聞きください‼ これは! 私も本意では無かったのです‼」
必死の形相で弁明をするマリーゴールドを無視して、ベリル王子は私の方を向き、困った顔を見せる。
そしてルチル王子を指差し、こう言った。
「つまり、こういうことだったんだ。兄さんは、思った通り治癒などされていなかった。叫び声が消えたのはこの女に喉を潰されていたからだ」
「私にこれを見せたということは、治療してもよろしいんですね?」
「ああ。できるものなら、ね。正直なところ、私はこの女が聖女だとは思っていない。きっと、兄さんのことだ。聖女などという特別な力を持つ相手を娶るより、気に入った女性をと言ったところだろう。フローラにはひどい話だけどね」
「いえ。気にしていませんので」
正直なところ、私も同じように考えていたのだから、そこだけはルチル王子に悪い印象は持っていない。
ただ、ベリル王子の口添えが無ければ、この城に一生幽閉されていたのかもしれないと考えれば、そうとは言えないけれど。
「ただね。私もまだ半信半疑なんだよ。フローラも治せないのかもしれない。それまでは、この女の処遇も含めて保留にしてある。さあ、できるかい?」
「できるかどうかの保証はしません。それでも、やってみます」
そう答えると、ベリル王子は私に一つの魔石を手渡す。
受け取って確認すると、大きさ質ともに最高級のものと言っていいものだった。
私はその魔石を右手に持つと、アンバーにした様に解呪の魔法を唱え始める。
ルチル王子の身体が光に包まれ、そして光が消えると、痛みなどが消えたおかげか、安らかな顔に戻る。
続いて私は治癒の魔法を唱え、呪いによって傷付いた身体の内部も潰された喉も治した。
これで、身体の方は問題なく完治したはずだ。
しかし、恐らく精神の方は……。
「驚いたな……殺した訳じゃないよね?」
「寝ているだけです。近付けば寝息が聞こえるのが分かるはずです」
私の言葉にベリル王子はゆっくりとした足取りでルチル王子に近付き、口元に顔を持っていく。
そして、私の方を振り向いた。
「確かに息をしているね。ありがとう。これで、白黒はっきりしたね。聖女が誰なのかってことが」
そう言うと、ベリル王子は私に向けていた笑顔を消し、険しい顔付きをマリーゴールドに向け、クリスに強い口調で命令をする。
「こいつを連れて行け。処遇は追って決める」
「はっ! かしこまりました!」
「やめて! 助けて‼ 私が悪いんじゃないの‼ わ……むごもごっ‼」
移送中に声を出されない様にか、マリーゴールドは猿ぐつわをされ、護衛と共にクリスが連れ出す。
後に残った私に、ベリル王子は再び笑みを向けた。
「色々と済まなかったね。事が事なだけに、あの女の処遇も含めて色々と決めかねていたんだよ。下手な所に移送して、変なことを吹聴されても困るからね」
「それで、私の役目は終わりでしょうか?」
「ああ。これで兄さんも助かった事だしね。ただ、少しこの事件はきな臭いんだ。あの女が言う様に、一人で考えて行動したものではないのかもしれない」
「お言葉ですが、ルチル王子は療養が必要でしょう。傷も癒え、呪いも解けましたが、これだけの期間呪いに晒され続けていたのです。精神が病んでいる可能性が高いでしょう」
呪いについて学んだ時、多くはないものの、呪いを受けてから解かれるまでの期間が長かった者のその後が書かれていた。
その多くは、呪いによって生じていた痛みや恐怖により、精神が病み、まるで心が壊れた様な状態になるのだという。
残念ながら、少なくとも私が知りうる限りの回復魔法では、この状態を治癒させるものは無いという結論だった。
時間をかけ、ゆっくりと治していくしか方法は今のところない。
それでも、完治した例は少なく、多くはそのままの状態でいるらしい。
今寝ているルチル王子が覚醒した時にどういう状況か、もし心が壊れていても治るのかも私には分からない事だった。
王都に到着し、実家による暇も与えられず、私は王城へと向かった。
そこで、身支度を済ませ、ドレス姿に着替えた私は、その足でベリル王子に謁見する。
柔らかそうな金髪と蒼色の瞳を持った顔は、嬉しそうな笑みを浮かべていた。
私は王族に対する一礼を済ませた後、ここに呼ばれた用件を聞く。
「ご無沙汰しております。ベリル殿下。お元気そうで何よりです。と、挨拶はこれくらいにさせていただきます。私を帰還させるとはどういうことでしょうか?」
「ふふふ。君は変わらないね。大きくなり美しい女性になっても、昔のままだ。そうだね、私もそんなに時間の余裕があるわけじゃないんだ。お互いのため、さっさと本題に入ろうか」
ベリル王子は私を別室へと案内する。
他に付き添いの者は一人だけだ。
鋭い目つきをしたこの人物を私は初めて見る。
服装から見るに執事長か何かだろうか。
「こちらでございます」
移動の最中に名前を聞き、クリスと名乗った人物は、王城の一角になる部屋へ着くと、扉を開ける。
その中には、三人の人物が居た。
「フローラ‼ お願い‼ 助けて‼ 貴女と私の仲じゃない‼」
「…………‼」
三人のうち一人は、拘束されて身動きが取れないようになっているマリーゴールドだった。
私との仲と言っても、そこまで親しかった記憶はない。
もう一人は護衛だろうか。
私たちが入ってくるのを見ると、一礼をした。
そして最後の一人の様子に私は目を見開いた。
それはベッドに横たわり、今も痛みによる失神と覚醒を繰り返すルチル王子だった。
その顔は恐ろしいまでに苦悶の表情に支配されていて、何かを叫ぼうと口を大きく開いているが、聞こえるのは息が漏れ出る音だけだった。
恐らく喉を潰されて声が出ないようになっているのだろう。
「驚いたかい? 私もこの現状を目の当たりにした時には大層驚いたよ。ねぇ? マリーゴールド」
「ベリル王子‼ どうか! 私の話をお聞きください‼ これは! 私も本意では無かったのです‼」
必死の形相で弁明をするマリーゴールドを無視して、ベリル王子は私の方を向き、困った顔を見せる。
そしてルチル王子を指差し、こう言った。
「つまり、こういうことだったんだ。兄さんは、思った通り治癒などされていなかった。叫び声が消えたのはこの女に喉を潰されていたからだ」
「私にこれを見せたということは、治療してもよろしいんですね?」
「ああ。できるものなら、ね。正直なところ、私はこの女が聖女だとは思っていない。きっと、兄さんのことだ。聖女などという特別な力を持つ相手を娶るより、気に入った女性をと言ったところだろう。フローラにはひどい話だけどね」
「いえ。気にしていませんので」
正直なところ、私も同じように考えていたのだから、そこだけはルチル王子に悪い印象は持っていない。
ただ、ベリル王子の口添えが無ければ、この城に一生幽閉されていたのかもしれないと考えれば、そうとは言えないけれど。
「ただね。私もまだ半信半疑なんだよ。フローラも治せないのかもしれない。それまでは、この女の処遇も含めて保留にしてある。さあ、できるかい?」
「できるかどうかの保証はしません。それでも、やってみます」
そう答えると、ベリル王子は私に一つの魔石を手渡す。
受け取って確認すると、大きさ質ともに最高級のものと言っていいものだった。
私はその魔石を右手に持つと、アンバーにした様に解呪の魔法を唱え始める。
ルチル王子の身体が光に包まれ、そして光が消えると、痛みなどが消えたおかげか、安らかな顔に戻る。
続いて私は治癒の魔法を唱え、呪いによって傷付いた身体の内部も潰された喉も治した。
これで、身体の方は問題なく完治したはずだ。
しかし、恐らく精神の方は……。
「驚いたな……殺した訳じゃないよね?」
「寝ているだけです。近付けば寝息が聞こえるのが分かるはずです」
私の言葉にベリル王子はゆっくりとした足取りでルチル王子に近付き、口元に顔を持っていく。
そして、私の方を振り向いた。
「確かに息をしているね。ありがとう。これで、白黒はっきりしたね。聖女が誰なのかってことが」
そう言うと、ベリル王子は私に向けていた笑顔を消し、険しい顔付きをマリーゴールドに向け、クリスに強い口調で命令をする。
「こいつを連れて行け。処遇は追って決める」
「はっ! かしこまりました!」
「やめて! 助けて‼ 私が悪いんじゃないの‼ わ……むごもごっ‼」
移送中に声を出されない様にか、マリーゴールドは猿ぐつわをされ、護衛と共にクリスが連れ出す。
後に残った私に、ベリル王子は再び笑みを向けた。
「色々と済まなかったね。事が事なだけに、あの女の処遇も含めて色々と決めかねていたんだよ。下手な所に移送して、変なことを吹聴されても困るからね」
「それで、私の役目は終わりでしょうか?」
「ああ。これで兄さんも助かった事だしね。ただ、少しこの事件はきな臭いんだ。あの女が言う様に、一人で考えて行動したものではないのかもしれない」
「お言葉ですが、ルチル王子は療養が必要でしょう。傷も癒え、呪いも解けましたが、これだけの期間呪いに晒され続けていたのです。精神が病んでいる可能性が高いでしょう」
呪いについて学んだ時、多くはないものの、呪いを受けてから解かれるまでの期間が長かった者のその後が書かれていた。
その多くは、呪いによって生じていた痛みや恐怖により、精神が病み、まるで心が壊れた様な状態になるのだという。
残念ながら、少なくとも私が知りうる限りの回復魔法では、この状態を治癒させるものは無いという結論だった。
時間をかけ、ゆっくりと治していくしか方法は今のところない。
それでも、完治した例は少なく、多くはそのままの状態でいるらしい。
今寝ているルチル王子が覚醒した時にどういう状況か、もし心が壊れていても治るのかも私には分からない事だった。
ルチル王子の一件があった後、数日経って私は再び王城に呼び出された。
その間、父が「よく戻ってきた」とか「今からでも遅くない」とかを、毎日のように聞かせてくるので、若干うんざりしてしまった。
「やぁ。よく来てくれたね。座ってよ」
「失礼いたします」
今回通されたのは、ベリル王子の私室の一つだった。
ゆったりとしたソファが向かいあわせで置かれていて、奥の方にすでにベリル王子が座っている。
隣に佇むクリスが私に向かって会釈する。
私もベリル王子、そしてクリスにそれぞれ一礼してから、向かいあう形で空いているソファに座った。
「なんだい。こっちにも空きがあるんだから、こっちに座ればいいのに。そこじゃあ、遠いだろ?」
「ご冗談を。今日のご用件はなんでしょうか?」
私の言葉にベリル王子は笑みを強くする。
どうやら私にはこの人の考えを読むのは難しそうだ。
「ああ。そうだね。他でもない。兄さんのことさ」
ベリル王子は呪いが解けた後のルチル王子のことについては淡々と述べた。
その口調や表情からは、そのことを悲しんでいるのか喜んでいるのかは読み取れなかった。
ルチル王子は案の定、心を壊してしまったようだ。
身体に異常がないにもかかわらず、反応もいまいちで、一日中どこか遠くを見つめているだけらしい。
「それで、相談なんだけど。兄さんを元に戻すことはできるのかな?」
「分かりかねます。ただ、魔法の力で、ということでしたら、現時点で方法はありません」
「そうか……それは残念だね。本人の口から直接聞きたかったんだけどな」
「なんのことでしょうか?」
ベリル王子が困った顔でそんなことを言うので、思わず私は聞き返してしまった。
「どうやら、毒を盛られていたみたいなんだ。国王、つまり父がね」
「どういうことです⁉」
「そのまんまの意味さ。しかも困ったことに毒自体は既に解毒したのだけれど、衰弱してしまっていてね。もうそんなに長くないだろう。問題は、誰が毒を盛っていたか、ということなんだけど」
「ルチル王子が犯人だと?」
私のはっきりとした物言いに、ベリル王子の眉が一瞬跳ねた。
「状況的に一番怪しいのはね。私ですら、父にはそんなに近寄れなかったんだ。誰かを使おうにも、かなり難しいだろうね」
「それを話させるために、ルチル王子の治療が必要だと?」
「いや。それだけの気持ちではもちろんないさ。純粋に良くなって欲しいとは思っている。一応でも私の兄だからね。そうだ。話のついでに、あの女がどうなったか――」
「必要ありません」
ベリル王子にわざわざ聞かなくても、マリーゴールド、そしてその一族がどうなったかは簡単に想像できる。
家の使用人からマリーゴールドの家が取り潰しにあったと聞いた。
事が事なだけに理由は大っぴらにはなっていないが、そういう事なのだろう。
私は一瞬目を瞑り、マリーゴールドとその一族の安寧を祈った。
「そうか。それで、色々と処理をしないといけないことが多すぎて、君を正式に聖女だと言うことは当分難しそうなんだ。済まないね」
「いえ。構いません。なんでしたら今後も必要ありません」
元々聖女になどなる気はないのだ。
それは実際に戦地へ赴き、負傷兵たちの治療に従事して、より強い気持ちになった。
今さら聖女になりたい気持ちなど一切なかった。
むしろ王都に繋ぎ止められている今が、どうしようもなく感じられた。
今こう話している間にも、負傷兵の治癒は行われているだろう。
デイジーたちは問題なくこなせているだろうか。
「相変わらずだね。ただ、それでは王族としての威厳が保てない。私のできる範囲で、個人的にお礼をしたいと思っている。何か欲しいものはあるかな?」
「どんなことでもいいのでしょうか?」
「私ができる範囲ならね。どんなことでも叶えよう」
「それでは、私を衛生兵として戦場に戻してください。今すぐに」
私は考えるまでもなく、願いを言った。
それを聞いたベリル王子は目を見開き驚いた顔をした後、声を出して笑った。
「あっはっは。まさか、あの地獄から帰還して、それでもあそこに行きたいなんて言うとは思っていなかったよ」
「地獄だからこそ行くのです。そうしなければ、いつまでも地獄のままです」
「分かった。私が総司令官だということも知っての願いなのだろう。私から言い出したことだ。約束は守ろう」
「ありがとうございます」
これでやり残したことを再びできる。
しかし、ベリル王子から出た言葉は私が想像していない事だった。
「ただし。戻る部隊は別の部隊だ。未来の聖女に、それなりの席を用意しなくては。ちょうど、第二部隊の副隊長に空きが出来たところだったはずだ」
以前居た第五衛生兵部隊に戻れると思っていたところ、どうやらこれから向かうのは第二衛生兵部隊のようだ。
しかも、その部隊の副隊長として。
役に就けば自分のやりたいことも通しやすいだろう。
慣れ親しんだ彼女たちと一緒に働けないのは残念だけれど。
そんなことを思いながら、私は自分の信念を実現するために、戦地で自分がやるべきことに思いを馳せていた。
その間、父が「よく戻ってきた」とか「今からでも遅くない」とかを、毎日のように聞かせてくるので、若干うんざりしてしまった。
「やぁ。よく来てくれたね。座ってよ」
「失礼いたします」
今回通されたのは、ベリル王子の私室の一つだった。
ゆったりとしたソファが向かいあわせで置かれていて、奥の方にすでにベリル王子が座っている。
隣に佇むクリスが私に向かって会釈する。
私もベリル王子、そしてクリスにそれぞれ一礼してから、向かいあう形で空いているソファに座った。
「なんだい。こっちにも空きがあるんだから、こっちに座ればいいのに。そこじゃあ、遠いだろ?」
「ご冗談を。今日のご用件はなんでしょうか?」
私の言葉にベリル王子は笑みを強くする。
どうやら私にはこの人の考えを読むのは難しそうだ。
「ああ。そうだね。他でもない。兄さんのことさ」
ベリル王子は呪いが解けた後のルチル王子のことについては淡々と述べた。
その口調や表情からは、そのことを悲しんでいるのか喜んでいるのかは読み取れなかった。
ルチル王子は案の定、心を壊してしまったようだ。
身体に異常がないにもかかわらず、反応もいまいちで、一日中どこか遠くを見つめているだけらしい。
「それで、相談なんだけど。兄さんを元に戻すことはできるのかな?」
「分かりかねます。ただ、魔法の力で、ということでしたら、現時点で方法はありません」
「そうか……それは残念だね。本人の口から直接聞きたかったんだけどな」
「なんのことでしょうか?」
ベリル王子が困った顔でそんなことを言うので、思わず私は聞き返してしまった。
「どうやら、毒を盛られていたみたいなんだ。国王、つまり父がね」
「どういうことです⁉」
「そのまんまの意味さ。しかも困ったことに毒自体は既に解毒したのだけれど、衰弱してしまっていてね。もうそんなに長くないだろう。問題は、誰が毒を盛っていたか、ということなんだけど」
「ルチル王子が犯人だと?」
私のはっきりとした物言いに、ベリル王子の眉が一瞬跳ねた。
「状況的に一番怪しいのはね。私ですら、父にはそんなに近寄れなかったんだ。誰かを使おうにも、かなり難しいだろうね」
「それを話させるために、ルチル王子の治療が必要だと?」
「いや。それだけの気持ちではもちろんないさ。純粋に良くなって欲しいとは思っている。一応でも私の兄だからね。そうだ。話のついでに、あの女がどうなったか――」
「必要ありません」
ベリル王子にわざわざ聞かなくても、マリーゴールド、そしてその一族がどうなったかは簡単に想像できる。
家の使用人からマリーゴールドの家が取り潰しにあったと聞いた。
事が事なだけに理由は大っぴらにはなっていないが、そういう事なのだろう。
私は一瞬目を瞑り、マリーゴールドとその一族の安寧を祈った。
「そうか。それで、色々と処理をしないといけないことが多すぎて、君を正式に聖女だと言うことは当分難しそうなんだ。済まないね」
「いえ。構いません。なんでしたら今後も必要ありません」
元々聖女になどなる気はないのだ。
それは実際に戦地へ赴き、負傷兵たちの治療に従事して、より強い気持ちになった。
今さら聖女になりたい気持ちなど一切なかった。
むしろ王都に繋ぎ止められている今が、どうしようもなく感じられた。
今こう話している間にも、負傷兵の治癒は行われているだろう。
デイジーたちは問題なくこなせているだろうか。
「相変わらずだね。ただ、それでは王族としての威厳が保てない。私のできる範囲で、個人的にお礼をしたいと思っている。何か欲しいものはあるかな?」
「どんなことでもいいのでしょうか?」
「私ができる範囲ならね。どんなことでも叶えよう」
「それでは、私を衛生兵として戦場に戻してください。今すぐに」
私は考えるまでもなく、願いを言った。
それを聞いたベリル王子は目を見開き驚いた顔をした後、声を出して笑った。
「あっはっは。まさか、あの地獄から帰還して、それでもあそこに行きたいなんて言うとは思っていなかったよ」
「地獄だからこそ行くのです。そうしなければ、いつまでも地獄のままです」
「分かった。私が総司令官だということも知っての願いなのだろう。私から言い出したことだ。約束は守ろう」
「ありがとうございます」
これでやり残したことを再びできる。
しかし、ベリル王子から出た言葉は私が想像していない事だった。
「ただし。戻る部隊は別の部隊だ。未来の聖女に、それなりの席を用意しなくては。ちょうど、第二部隊の副隊長に空きが出来たところだったはずだ」
以前居た第五衛生兵部隊に戻れると思っていたところ、どうやらこれから向かうのは第二衛生兵部隊のようだ。
しかも、その部隊の副隊長として。
役に就けば自分のやりたいことも通しやすいだろう。
慣れ親しんだ彼女たちと一緒に働けないのは残念だけれど。
そんなことを思いながら、私は自分の信念を実現するために、戦地で自分がやるべきことに思いを馳せていた。
「本日よりこちらに配属されたフローラです。よろしくお願いします」
「ああ。いらっしゃい。まぁ、そんなに畏まらず、楽にやってよ」
ベリル王子に要望を出して、次の日には王都を出立して再び戦線へと向かった。
今回配属するのは第二衛生兵部隊。
そこに着くと、その足で司令室にいる部隊長のゾイスの元へ挨拶に向かった。
ゾイスは歳はアンバーより若く見えるが、軍属の割には緩んだ身体の持ち主だった。
初期のアンバーとはまた毛色の違った笑みを顔に貼り付け、右手に持つハンカチーフで額と首元の汗を拭いている。
人を見かけで判断してはいけないけれど、あまり好ましいと思うような相手には思えなかった。
「それでは、早速業務に携わりたいのですがよろしいでしょうか?」
「ん? ああ、ああ。まぁ、そんな気張らなくていいってば。えーっと、フローラ君だっけ? 君に会ったら聞きたい事があったんだ」
「なんでしょうか?」
「君さ。誰に取り入ったの? もし良かったら教えてよ。何? やっぱり女性の武器ってやつを使ったのかな? いいよねぇ」
そう言いながらゾイスはすでに上がっている口角を更に上げる。
どうやら侮辱を受けているようだ。
「なんのことだか分かりません。それでは、早く現場に慣れたいのでこれで失礼します」
「あ、そう。まぁいいや。所詮君は副隊長。部隊長の俺には逆らえないんだから、ちゃんと地位を弁えた行動を頼むね。それじゃ、行っていいよ」
そう言いながら、ゾイスは手に持つハンカチーフを前後に振る。
かなり良い性格の持ち主のようだが、私の目的は部隊長に気に入られることではない。
にやけ顔の上官を無視するように、最低限の礼をしてから司令官室を後にした。
そこではたと、この陣営の治療場の場所を聞くのを忘れたのに気付いた。
通りすがりの兵士に自己紹介をしてから、治療場の場所を聞く。
私が新しく配属された副隊長だと言った時には、かなり驚いた顔をしたが、胸につけてある徽章を見て納得したようだ。
改めて軍特有の礼を私にしてから、丁寧な口調で案内してくれた。
治療場に向かう間、私はその兵士に色々と聞いてみることにした。
「ここの衛生兵の人数を知っている?」
「はい。全部で三十名ほどだと思います」
「結構多いのね。それで、その中で回復魔法を使えるのは何人くらいいるのかしら?」
「回復魔法ですか? 誰がどのくらい使えるかまでは詳しく知りませんが、ここにいる衛生兵は全員使えるはずです。ご存知なかったのですか?」
返答を聞いて、私は驚いた顔をしてしまった。
以前いた第五衛生兵部隊の衛生兵は、今では全員が回復魔法を使えるものの、初めは数人しかいなかった。
それが、ここでは全員が使えるというのだ。
私は、この僥倖に思わず顔を緩めてしまう。
始めから使えるのであれば、それなりの素質を持つ者ばかりなのだろう。
うまく訓練を行えば、その内解呪の魔法すら使いこなす者も多く誕生するかもしれない。
私は喜び勇んで兵士に返答する。
「ごめんなさい。知らないの。ここの衛生兵が全員回復魔法を使えることに、何か理由があるの?」
私の言葉を聞いた兵士は、少し考え込み、そして戸惑いを見せながらこう答えた。
「ここに所属するためには最低限回復魔法を元々使えることが条件なのです。ですから――」
始めの言葉に、素晴らしいと思ったのも束の間、続く言葉は、あまり好ましいものではなかった。
兵士の話はこういうことだった。
衛生兵として送られる者は、回復魔法の適性を鑑みて女性、しかも危険な前線に送られるのは、一身上に様々な問題がある者ばかり。
夫を亡くした未亡人や、雇い先から解雇を告げられたメイドなどだ。
一方、回復魔法を教える施設などは一般的には無い。
私も、父が家庭教師を呼び、様々な書物を買い与えてくれたからこそ、学ぶ事ができた。
それにはそれなり以上の資金が必要だ。
そして、夫や職を失った女性が、簡単に払えるような額では無い。
人によってはその身を売った人もいるだろう。
そうやってなんとか捻出した資金で、ようやく回復魔法の教えを乞い、身に付けて配属されたのがここいる大半らしい。
彼女らの努力は買うが、そこまでしなければならない現状を再度理解し、私はベリル王子に再度教育機関の創設を打診することを心に決めた。
「着きました。ここが治療場です。今、呼び集めますのでお待ちください」
「いいえ。結構よ。挨拶なら作業をしながらでもできるわ。ありがとう。持ち場へ戻って大丈夫よ」
そう言うと、兵士はまた一礼をしてその場から去っていった。
一人残った私は、治療場の状況を確認するために一望する。
広さは第五部隊よりも少し広いがそこまで変わらず、多少臭いや汚れが気になるものの、そこまで酷い状況にはなっていなかった。
安心した気持ちで、治癒に当たっている人たちに目を移していく。
確かに兵士が言っていた通り、その場にいる全員が回復魔法を使えるようだ。
ほとんどが初級の回復魔法ではあるものの、手際よく負傷している兵士の傷を治していくのが見えた。
「なるほど。これならまずは大丈夫そうね――」
そう独り言を呟いた矢先、一人の衛生兵の行動が目に付いた。
その衛生兵は、右足を失った兵士の治癒に当たっている。
その女性は先ほどから初級の回復魔法しか使っていないように思える人物だった。
せいぜい出来ても傷口を塞ぐだけ、失った四肢を再生させるのには無理がある。
もしかしたら、そのような魔法も使えるのかもしれないと、注視していると、果たして使ったのは、やはり初級の治癒の魔法だった。
布で止血をしていた負傷兵の傷が光に包まれ、そして光が消える頃には傷口は塞がっていた。
そこまでやると、衛生兵は立ち上がり、別の負傷兵の方へと向かう。
もちろん、傷口は塞がったものの、脚は再生されておらず、失ったままだ。
負傷兵は悔しそうな顔をして起き上がると、別の者から渡された木の棒を杖代わりにその場を後にしようとしている。
他の衛生兵もその兵士に構う者は見当たらない。
「ちょっと! あなたたち! 何をしているの⁉」
思わず私は叫んでいた。
その声に、その場にいた全員が私の方を向く。
見ていた限り、ごく少数ではあるものの、四肢を再生させることのできる中級の治癒の魔法を使える者も中にはいた。
その衛生兵に任せれば、今目の前にいる杖を突いた兵士の脚を取り戻すことができたはずだ。
「なぜ、治せる者が治さないの⁉ この人の脚は⁉」
状況が掴めていないのか、誰も何も言わず、不思議そうな顔を私に向ける。
時間の無駄を感じ、私は目の前を通り過ぎようとしている脚を失った兵士に声をかける。
「その場に横になりなさい。やり直しよ。脚を、切るわね」
「ああ。いらっしゃい。まぁ、そんなに畏まらず、楽にやってよ」
ベリル王子に要望を出して、次の日には王都を出立して再び戦線へと向かった。
今回配属するのは第二衛生兵部隊。
そこに着くと、その足で司令室にいる部隊長のゾイスの元へ挨拶に向かった。
ゾイスは歳はアンバーより若く見えるが、軍属の割には緩んだ身体の持ち主だった。
初期のアンバーとはまた毛色の違った笑みを顔に貼り付け、右手に持つハンカチーフで額と首元の汗を拭いている。
人を見かけで判断してはいけないけれど、あまり好ましいと思うような相手には思えなかった。
「それでは、早速業務に携わりたいのですがよろしいでしょうか?」
「ん? ああ、ああ。まぁ、そんな気張らなくていいってば。えーっと、フローラ君だっけ? 君に会ったら聞きたい事があったんだ」
「なんでしょうか?」
「君さ。誰に取り入ったの? もし良かったら教えてよ。何? やっぱり女性の武器ってやつを使ったのかな? いいよねぇ」
そう言いながらゾイスはすでに上がっている口角を更に上げる。
どうやら侮辱を受けているようだ。
「なんのことだか分かりません。それでは、早く現場に慣れたいのでこれで失礼します」
「あ、そう。まぁいいや。所詮君は副隊長。部隊長の俺には逆らえないんだから、ちゃんと地位を弁えた行動を頼むね。それじゃ、行っていいよ」
そう言いながら、ゾイスは手に持つハンカチーフを前後に振る。
かなり良い性格の持ち主のようだが、私の目的は部隊長に気に入られることではない。
にやけ顔の上官を無視するように、最低限の礼をしてから司令官室を後にした。
そこではたと、この陣営の治療場の場所を聞くのを忘れたのに気付いた。
通りすがりの兵士に自己紹介をしてから、治療場の場所を聞く。
私が新しく配属された副隊長だと言った時には、かなり驚いた顔をしたが、胸につけてある徽章を見て納得したようだ。
改めて軍特有の礼を私にしてから、丁寧な口調で案内してくれた。
治療場に向かう間、私はその兵士に色々と聞いてみることにした。
「ここの衛生兵の人数を知っている?」
「はい。全部で三十名ほどだと思います」
「結構多いのね。それで、その中で回復魔法を使えるのは何人くらいいるのかしら?」
「回復魔法ですか? 誰がどのくらい使えるかまでは詳しく知りませんが、ここにいる衛生兵は全員使えるはずです。ご存知なかったのですか?」
返答を聞いて、私は驚いた顔をしてしまった。
以前いた第五衛生兵部隊の衛生兵は、今では全員が回復魔法を使えるものの、初めは数人しかいなかった。
それが、ここでは全員が使えるというのだ。
私は、この僥倖に思わず顔を緩めてしまう。
始めから使えるのであれば、それなりの素質を持つ者ばかりなのだろう。
うまく訓練を行えば、その内解呪の魔法すら使いこなす者も多く誕生するかもしれない。
私は喜び勇んで兵士に返答する。
「ごめんなさい。知らないの。ここの衛生兵が全員回復魔法を使えることに、何か理由があるの?」
私の言葉を聞いた兵士は、少し考え込み、そして戸惑いを見せながらこう答えた。
「ここに所属するためには最低限回復魔法を元々使えることが条件なのです。ですから――」
始めの言葉に、素晴らしいと思ったのも束の間、続く言葉は、あまり好ましいものではなかった。
兵士の話はこういうことだった。
衛生兵として送られる者は、回復魔法の適性を鑑みて女性、しかも危険な前線に送られるのは、一身上に様々な問題がある者ばかり。
夫を亡くした未亡人や、雇い先から解雇を告げられたメイドなどだ。
一方、回復魔法を教える施設などは一般的には無い。
私も、父が家庭教師を呼び、様々な書物を買い与えてくれたからこそ、学ぶ事ができた。
それにはそれなり以上の資金が必要だ。
そして、夫や職を失った女性が、簡単に払えるような額では無い。
人によってはその身を売った人もいるだろう。
そうやってなんとか捻出した資金で、ようやく回復魔法の教えを乞い、身に付けて配属されたのがここいる大半らしい。
彼女らの努力は買うが、そこまでしなければならない現状を再度理解し、私はベリル王子に再度教育機関の創設を打診することを心に決めた。
「着きました。ここが治療場です。今、呼び集めますのでお待ちください」
「いいえ。結構よ。挨拶なら作業をしながらでもできるわ。ありがとう。持ち場へ戻って大丈夫よ」
そう言うと、兵士はまた一礼をしてその場から去っていった。
一人残った私は、治療場の状況を確認するために一望する。
広さは第五部隊よりも少し広いがそこまで変わらず、多少臭いや汚れが気になるものの、そこまで酷い状況にはなっていなかった。
安心した気持ちで、治癒に当たっている人たちに目を移していく。
確かに兵士が言っていた通り、その場にいる全員が回復魔法を使えるようだ。
ほとんどが初級の回復魔法ではあるものの、手際よく負傷している兵士の傷を治していくのが見えた。
「なるほど。これならまずは大丈夫そうね――」
そう独り言を呟いた矢先、一人の衛生兵の行動が目に付いた。
その衛生兵は、右足を失った兵士の治癒に当たっている。
その女性は先ほどから初級の回復魔法しか使っていないように思える人物だった。
せいぜい出来ても傷口を塞ぐだけ、失った四肢を再生させるのには無理がある。
もしかしたら、そのような魔法も使えるのかもしれないと、注視していると、果たして使ったのは、やはり初級の治癒の魔法だった。
布で止血をしていた負傷兵の傷が光に包まれ、そして光が消える頃には傷口は塞がっていた。
そこまでやると、衛生兵は立ち上がり、別の負傷兵の方へと向かう。
もちろん、傷口は塞がったものの、脚は再生されておらず、失ったままだ。
負傷兵は悔しそうな顔をして起き上がると、別の者から渡された木の棒を杖代わりにその場を後にしようとしている。
他の衛生兵もその兵士に構う者は見当たらない。
「ちょっと! あなたたち! 何をしているの⁉」
思わず私は叫んでいた。
その声に、その場にいた全員が私の方を向く。
見ていた限り、ごく少数ではあるものの、四肢を再生させることのできる中級の治癒の魔法を使える者も中にはいた。
その衛生兵に任せれば、今目の前にいる杖を突いた兵士の脚を取り戻すことができたはずだ。
「なぜ、治せる者が治さないの⁉ この人の脚は⁉」
状況が掴めていないのか、誰も何も言わず、不思議そうな顔を私に向ける。
時間の無駄を感じ、私は目の前を通り過ぎようとしている脚を失った兵士に声をかける。
「その場に横になりなさい。やり直しよ。脚を、切るわね」
この作家の他の作品
表紙を見る
気付くと私は、発売から十年経った今も思い出してはプレイを続ける乙女ゲーム「イストワール〜星恋の七王子」のキャラクターに転生してしまった。
しかもそれはゲーム内でヒロインを執拗に陥れようと画策する悪役令嬢、ミザリー・マリア・ド・ゴール。
本来の主人公であるヒロインがどのルートを通ってもその前に立ちはだかり、最終的には己の行いが招いた破滅の結末を迎える。
私はそんな結末を回避しようと、三年間の学園生活を奔走する。
「王子を味方につける方法を考えなきゃ!」
表紙を見る
精霊に愛された少女は聖女として崇められる。私の住む国で古くからある習わしだ。
驚いたことに私も聖女だと、村の皆の期待を背に王都マーベラに迎えられた。
それなのに……。
「この者が聖女なはずはない! 穢らわしい!」
私よりも何年も前から聖女として称えられているローザ様の一言で、私は国を追放されることになってしまった。
「もし良かったら同行してくれないか?」
隣国に向かう途中で命を救ったやり手の商人アベルに色々と助けてもらうことに。
その隣国では精霊の力を利用する技術を使う者は【錬金術師】と呼ばれていて……。
第五元素エーテルの精霊に愛された私は、生まれた国を追放されたけれど、隣国で天才錬金術師として暮らしていくようです!!
この物語は、国を追放された聖女と、助けたやり手商人との恋愛話です。
追放ものなので、最初の方で3話毎にざまぁ描写があります。
薬の効果を示すためにたまに人が怪我をしますがグロ描写はありません。
作者が化学好きなので、少し趣味が出ますがファンタジー風味を壊すことは無いように気を使っています。
ベリーズファンタジー様から発売されました!!
書籍版は大ボリューム加筆修正しておりますので、ぜひぜひお手にお取りください!!
表紙を見る
勇者パーティの支援職だった私は、自己を超々強化する秘法と言われた魔法を使い、幼女になってしまった。
そんな私の姿を見て、パーティメンバーが決めたのは……
「アリシアちゃん。いい子だからお留守番しててね」
見た目は幼女でも、最強の肉体を手に入れた私は、付いてくるなと言われた手前、こっそりひっそりと陰から元仲間を支援することに決めた。
戦神の愛用していたという神器破城槌を振り回し、神の乗り物だと言うもふもふ神獣と旅を続ける珍道中!
主人公は元は立派な大人ですが、心も体も知能も子供です
基本的にコメディ色が強いです
毎日朝7時に一話分更新します
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…