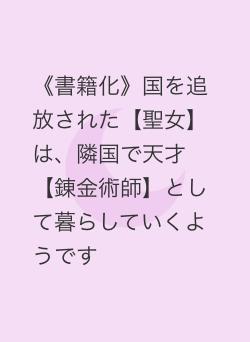魔法兵の放った光球が少し離れた場所にいる四足歩行の魔獣に炸裂する。
崩れ落ちる魔獣の横を駆け抜け、金属製の粗末な武器を持った魔獣が、前衛の攻撃兵に向かって横なぎに振るった。
「ぐぅ!」
鋭い魔獣の攻撃に反応が間に合わずに、攻撃を受けた兵士は血を吹き出しながら横へと体を流した。
おそらく骨と内蔵を損傷したのだろう。
兵士は苦悶の表情を抱えながら上段から下へと勢いに任せた一撃を振るう。
私は既に用意が終わった治癒の魔法を兵士にかけ、傷を癒す。
瞬間、驚いたような顔をしたまま放った兵士の一撃は、勢いを増し魔獣を絶命させる。
ひとまずの戦闘の終了に、私は胸を撫で下ろし息を吐く。
「ありがとう……本当に恐ろしいものね……魔獣というのは」
私は誰に話しかけるでもなく、そう呟く。
すると、後衛にいる私に向かって前衛の兵士が駆け寄って来た。
「ありがとう‼︎ 噂には聞いてたけど、衛生兵がすぐ後ろに控えているって安心感が段違いだね‼︎」
まだ若い兵士のようだ。
こんな若者が何人も戦場で命を失っているのだろう。
治療場でも正しく理解できない現場の肌の感覚を感じ、私はますます一人でも多くの命が救えるようこの身を捧げることを再度誓った。
それにしても、結果的にはカルザーに後押しされた形になってしまったが、衛生兵の同行は、私も考えていたことではあった。
いくら前線の陣営に治療場を設置したとしても、運ばれてくるまで生きているのは、むしろ運のいい方だといえる。
試合などではなく、殺し合いの戦争では、相手が傷つけば、トドメを刺しにいくのが至極当然の行為だろう。
傷を負えば負うほど戦闘の継続は難しくなる。
先ほども、私が治療を行わなければ、若い命が一つ散ってしまっていたかもしれない。
そう考えれば、現場ですぐに治療を行えるのは、救命という観点でいえば最良なのだ。
ただし、問題は同行する衛生兵の身の安全だ。
攻撃兵も、自分だけではなく、身体能力に劣る衛生兵を援護しながら戦わなければならない。
少なくとも、思いつきで実施して成功するような簡単なものではないだろう。
今だに私にキラキラとした視線を送る兵士に、私は静かな口調で伝える。
「ええ。でも慢心は余計な失敗を引き起こすわ。それに、今回は敵も少なく幸運なだけだったかもしれない。私たちの役目は本体が相手の拠点を制圧するまでに周囲の敵の殲滅でしょう? 休んでいるわけにもいかない。次へ進みましょう」
「ああ! それにしても衛生兵っていうのは凄いんだね‼︎ あんな怪我をたちどころに治しちゃうなんて。こんなことができるなら、各小隊に衛生兵を付ければいいのに」
興奮した様子でいう兵士の頭を、私の隣にいた魔法兵が拳で叩く。
こちらはアンバーほどではないが、それなりの年齢で、戦場での経験も目の前の若い兵士よりは豊富そうだ。
彼はこの小隊を指揮する小隊長で、名前はインディゴといった。
「痛い! ちょっと! 突然何するんですか⁉︎」
「うるせぇ! 戦闘中だってぇのに鼻の下伸ばしやがって。こんなことできるならだと? この人と同等かそれ以上の衛生兵なんて存在しねぇよ! そもそもこの聖女様は部隊長だぞ? 言葉遣い考えろ‼︎」
「え⁉︎」
インディゴの言葉に、その場にいた全員が頷く。
どうやら、私の立場を知らなかったのは、殴られた若い兵士だけのようだ。
そういえば、普段胸に付けている徽章は、気持ちばかりの防具に隠れて見えなくなっている。
若い兵士が気づかなくても仕方がないのかもしれない。
その他の兵士たちは、何度か見たことがある顔だ。
きっと、一度は第二衛生兵部隊の治療場に負傷兵として担ぎ込まれたのだろう。
「部隊長⁉︎ そんな偉い人が、現場に出て来てるんですか⁉︎」
「それが、そうなってるから、俺たちはみんな驚いてるんじゃねぇか。いいか? 絶対に、聖女様の身は守れ。自分の命に変えてもだ。それほどに、聖女様の命には価値がある」
インディゴの言葉に、再び他の兵たちも頷く。
それを聞いた私は、ついつい口を挟んでしまった。
「いいえ。命に価値の違いはないわ。一人一人、大切な命なのよ。命を投げ打ってまで助けようだなんて思わないでちょうだい」
「しかし……俺たちは傷ついても聖女様が治してくれますが、聖女様が瀕死になってしまったら、誰が治すんですか?」
そう問いかけられ、私は一瞬考え込んでしまった。
というのも、自分自身の回復魔法は、自分を治癒できないという問題があったからだ。
この問題については、少なくても私がこれまでに読んだ多くの文献に同様に記されていたから、間違いないのだろう。
実際に歴代の聖女様の中には、ご自身の怪我を治せずにいたという記録も残っていた。
また、そもそも回復魔法は、男性に比べて女性には効きづらいという事実もある。
これについては個人差があるようだが、少なくとも私は今までに回復魔法を受ける機会に恵まれなかったため、分からない。
私は、頼るべきところは頼った方が、それぞれの領分に専念した方が良いと理解し、インディゴに笑顔で答える。
「確かにそれもそうね。ただ、生きていれば救えるけれど、死んでしまっては無理なの。だから……死なないでちょうだい」
私の言葉に、インディゴや他の兵士、そして先ほどの若い兵士全員が、軍式の敬礼で応えてくれた。
崩れ落ちる魔獣の横を駆け抜け、金属製の粗末な武器を持った魔獣が、前衛の攻撃兵に向かって横なぎに振るった。
「ぐぅ!」
鋭い魔獣の攻撃に反応が間に合わずに、攻撃を受けた兵士は血を吹き出しながら横へと体を流した。
おそらく骨と内蔵を損傷したのだろう。
兵士は苦悶の表情を抱えながら上段から下へと勢いに任せた一撃を振るう。
私は既に用意が終わった治癒の魔法を兵士にかけ、傷を癒す。
瞬間、驚いたような顔をしたまま放った兵士の一撃は、勢いを増し魔獣を絶命させる。
ひとまずの戦闘の終了に、私は胸を撫で下ろし息を吐く。
「ありがとう……本当に恐ろしいものね……魔獣というのは」
私は誰に話しかけるでもなく、そう呟く。
すると、後衛にいる私に向かって前衛の兵士が駆け寄って来た。
「ありがとう‼︎ 噂には聞いてたけど、衛生兵がすぐ後ろに控えているって安心感が段違いだね‼︎」
まだ若い兵士のようだ。
こんな若者が何人も戦場で命を失っているのだろう。
治療場でも正しく理解できない現場の肌の感覚を感じ、私はますます一人でも多くの命が救えるようこの身を捧げることを再度誓った。
それにしても、結果的にはカルザーに後押しされた形になってしまったが、衛生兵の同行は、私も考えていたことではあった。
いくら前線の陣営に治療場を設置したとしても、運ばれてくるまで生きているのは、むしろ運のいい方だといえる。
試合などではなく、殺し合いの戦争では、相手が傷つけば、トドメを刺しにいくのが至極当然の行為だろう。
傷を負えば負うほど戦闘の継続は難しくなる。
先ほども、私が治療を行わなければ、若い命が一つ散ってしまっていたかもしれない。
そう考えれば、現場ですぐに治療を行えるのは、救命という観点でいえば最良なのだ。
ただし、問題は同行する衛生兵の身の安全だ。
攻撃兵も、自分だけではなく、身体能力に劣る衛生兵を援護しながら戦わなければならない。
少なくとも、思いつきで実施して成功するような簡単なものではないだろう。
今だに私にキラキラとした視線を送る兵士に、私は静かな口調で伝える。
「ええ。でも慢心は余計な失敗を引き起こすわ。それに、今回は敵も少なく幸運なだけだったかもしれない。私たちの役目は本体が相手の拠点を制圧するまでに周囲の敵の殲滅でしょう? 休んでいるわけにもいかない。次へ進みましょう」
「ああ! それにしても衛生兵っていうのは凄いんだね‼︎ あんな怪我をたちどころに治しちゃうなんて。こんなことができるなら、各小隊に衛生兵を付ければいいのに」
興奮した様子でいう兵士の頭を、私の隣にいた魔法兵が拳で叩く。
こちらはアンバーほどではないが、それなりの年齢で、戦場での経験も目の前の若い兵士よりは豊富そうだ。
彼はこの小隊を指揮する小隊長で、名前はインディゴといった。
「痛い! ちょっと! 突然何するんですか⁉︎」
「うるせぇ! 戦闘中だってぇのに鼻の下伸ばしやがって。こんなことできるならだと? この人と同等かそれ以上の衛生兵なんて存在しねぇよ! そもそもこの聖女様は部隊長だぞ? 言葉遣い考えろ‼︎」
「え⁉︎」
インディゴの言葉に、その場にいた全員が頷く。
どうやら、私の立場を知らなかったのは、殴られた若い兵士だけのようだ。
そういえば、普段胸に付けている徽章は、気持ちばかりの防具に隠れて見えなくなっている。
若い兵士が気づかなくても仕方がないのかもしれない。
その他の兵士たちは、何度か見たことがある顔だ。
きっと、一度は第二衛生兵部隊の治療場に負傷兵として担ぎ込まれたのだろう。
「部隊長⁉︎ そんな偉い人が、現場に出て来てるんですか⁉︎」
「それが、そうなってるから、俺たちはみんな驚いてるんじゃねぇか。いいか? 絶対に、聖女様の身は守れ。自分の命に変えてもだ。それほどに、聖女様の命には価値がある」
インディゴの言葉に、再び他の兵たちも頷く。
それを聞いた私は、ついつい口を挟んでしまった。
「いいえ。命に価値の違いはないわ。一人一人、大切な命なのよ。命を投げ打ってまで助けようだなんて思わないでちょうだい」
「しかし……俺たちは傷ついても聖女様が治してくれますが、聖女様が瀕死になってしまったら、誰が治すんですか?」
そう問いかけられ、私は一瞬考え込んでしまった。
というのも、自分自身の回復魔法は、自分を治癒できないという問題があったからだ。
この問題については、少なくても私がこれまでに読んだ多くの文献に同様に記されていたから、間違いないのだろう。
実際に歴代の聖女様の中には、ご自身の怪我を治せずにいたという記録も残っていた。
また、そもそも回復魔法は、男性に比べて女性には効きづらいという事実もある。
これについては個人差があるようだが、少なくとも私は今までに回復魔法を受ける機会に恵まれなかったため、分からない。
私は、頼るべきところは頼った方が、それぞれの領分に専念した方が良いと理解し、インディゴに笑顔で答える。
「確かにそれもそうね。ただ、生きていれば救えるけれど、死んでしまっては無理なの。だから……死なないでちょうだい」
私の言葉に、インディゴや他の兵士、そして先ほどの若い兵士全員が、軍式の敬礼で応えてくれた。
「うおぉぉぉぉ!!」
兵士たちの攻撃で、今日何度目か分からない戦闘の幕が閉じた。
激しい戦闘が続く中、みな活力の溢れた顔付きを保っている。
私は戦闘中にはするほどでもなかった、小さな傷の治療を始める。
いくつかに戦闘を経験した結果、致命傷や行動の制限に繋がりそうな怪我などは即座に治し、細かな治療は戦闘終了後にまとめて行うのが効率的という結論に至ったためだ。
治療を受けているインディゴが嬉しそうな顔をしながら話しかけてきた。
「それにしても、本当に聖女様が居てくれるおかげで、段違いですよ。いつもこんな感じだったら、どんなに楽か」
「そう。役に立てているなら、嬉しいわ」
私が答えると、インディゴは大袈裟な仕草をして、話を続けた。
「役に立ってるなんてもんじゃないですよ! もうさっきので七回目の戦闘をしてますが、まだ脱落者なし! こうやって毎回細かい傷まで治してもらえるから、毎回戦闘を万全の体制で行える。奇跡みたいなもんです」
「本当に。まだ誰も死者が出てなくて内心ホッとしているの」
「最初、衛生兵が同行するって話を聞いた時は、冗談じゃない! って思ったんです。自分の身体守るのにも精一杯なのに、他のやつまでなんか手を回せるかってね。それにこんな危険なところに来るのなんて、言っちゃ悪いですが、大したこともできないやつだと思ってたんで。まさか聖女様が来てくれるなんて……」
「どうせなら、初級の回復魔法だけしか使えないより、色んな魔法を使えた方がいいでしょう? それに、覚えたては、魔力の総量が少ないの。いつ休めるかも分からない戦闘に送り出すのは難しいわね」
実際、今までの戦闘で使用した回復魔法を考えれば、緑色どころか、黄色のリボンタイの衛生兵でもそろそろ難しいだろう。
怪我だけじゃなく、毒も受けたりするので、魔力以外にも使える魔法も問題になる。
「ところで、部隊長である聖女様が現場に出てくるなんて、何があったんです? こんなこと聞いていいのか分かりませんが、陣営の方の指揮は?」
「そちらは信頼出来る副隊長に任せているわ。彼女も一通りのことは既にできるようになっているし。もう一人、優秀な衛生兵もいるしね。さぁ、話が長くなってしまったわ。次の場所へ向かいましょう」
私が留守にしている間、デイジーとサルビアに陣営での治療は任せることにしている。
私が赴くと言い出した時、二人は強く反対したけれど、私はどうにか説得し、こうして現場に訪れたのだ。
「正確に現場を知らなければ、分からないことがあるからね……」
独り言を呟きながら、どうすれば衛生兵として貢献できるか、生き延びる可能性が高くなるかを考えとしてまとめていく。
私ができないことを他の衛生兵に求めるのは難しいだろうから、全ての行動や条件を様々な条件に落とし込んでいくことも忘れない。
「各小隊が連携をとりながら、どの隊にも衛生兵を置くのがいいのかしらね」
インディゴの言う通り、怪我をその場で治癒しながら戦闘できるというのは、大きな優位性を持つ。
戦闘続行の判断として、兵士たちの怪我の多寡を考慮に入れなくて済むため、物資や各人の体力、魔力だけが問題になる。
思っていた通り、傷付いた兵士を陣営での治すよりも、効率的なはずだ。
やはり問題は、衛生兵の質と数の問題と、安全を確保だろう。
「他の四人も無事だといいのだけれど」
私の他にも四名、志願してくれた衛生兵が今日の作戦に参加している。
彼女たち今回派遣したのは全員同じ中隊だ。
彼女たちの安全を祈りながら、私は前後を兵士に守られながら、次の目的地へと行進を続けた。
☆
「全員臨戦態勢!! 魔族だ!!」
しばらく歩き続けていたら、突然前衛の兵士の一人がそう叫んだ。
他の兵士はその声を聞いた瞬間、歩きやすいように収めていた各自の武器を構え、前方に意識を集中させた。
私の視線も前方に突如現れた、二足歩行の黒い影に釘付けになっていた。
それはまるで、野牛を擬人化したような見た目をしている。
頭から生えた二本のねじれたツノ、そして半裸の肉体は盛り上がった筋肉によって覆われていた。
手には大振りの曲刀を持ち、まるで、私たちがここに来ることを待ち構えていたかのように一人立ち尽くしている。
「くそっ! 識別名称【暴れ牛】だ!! 寄りにもよって!!」
インディゴが叫ぶ。
どうやら目の前の魔族は、軍の中では有名な相手らしい。
識別名称というのは、軍内で敵の個体勢力を呼称するために用いられる。
つまり、目の前の暴れ牛は、名前が付くほど戦果をあげているというわけだ。
インディゴが暴れ牛という言葉を発した瞬間、目の前の敵は、笑みを作ったように見えた。
相手が自分のことを知っていることへの喜びか、はたまた嘲りか。
そんな暴れ牛をしっかり見据えたまま、殿を務めていたインディゴは、私を庇うように少し前におどり出る。
そして、叫ぶように指示を出した。
「いいか? 俺は言ったな? 死んでも聖女様はお守りしろ!! ヤバくなったら誰でもいい! とにかく聖女様を逃がせ!!」
インディゴの言葉に兵士たちは短い返事を一斉に返した。
それが、私が初めて目の当たりにする魔族、暴れ牛との戦闘開始の合図だった。
兵士たちの攻撃で、今日何度目か分からない戦闘の幕が閉じた。
激しい戦闘が続く中、みな活力の溢れた顔付きを保っている。
私は戦闘中にはするほどでもなかった、小さな傷の治療を始める。
いくつかに戦闘を経験した結果、致命傷や行動の制限に繋がりそうな怪我などは即座に治し、細かな治療は戦闘終了後にまとめて行うのが効率的という結論に至ったためだ。
治療を受けているインディゴが嬉しそうな顔をしながら話しかけてきた。
「それにしても、本当に聖女様が居てくれるおかげで、段違いですよ。いつもこんな感じだったら、どんなに楽か」
「そう。役に立てているなら、嬉しいわ」
私が答えると、インディゴは大袈裟な仕草をして、話を続けた。
「役に立ってるなんてもんじゃないですよ! もうさっきので七回目の戦闘をしてますが、まだ脱落者なし! こうやって毎回細かい傷まで治してもらえるから、毎回戦闘を万全の体制で行える。奇跡みたいなもんです」
「本当に。まだ誰も死者が出てなくて内心ホッとしているの」
「最初、衛生兵が同行するって話を聞いた時は、冗談じゃない! って思ったんです。自分の身体守るのにも精一杯なのに、他のやつまでなんか手を回せるかってね。それにこんな危険なところに来るのなんて、言っちゃ悪いですが、大したこともできないやつだと思ってたんで。まさか聖女様が来てくれるなんて……」
「どうせなら、初級の回復魔法だけしか使えないより、色んな魔法を使えた方がいいでしょう? それに、覚えたては、魔力の総量が少ないの。いつ休めるかも分からない戦闘に送り出すのは難しいわね」
実際、今までの戦闘で使用した回復魔法を考えれば、緑色どころか、黄色のリボンタイの衛生兵でもそろそろ難しいだろう。
怪我だけじゃなく、毒も受けたりするので、魔力以外にも使える魔法も問題になる。
「ところで、部隊長である聖女様が現場に出てくるなんて、何があったんです? こんなこと聞いていいのか分かりませんが、陣営の方の指揮は?」
「そちらは信頼出来る副隊長に任せているわ。彼女も一通りのことは既にできるようになっているし。もう一人、優秀な衛生兵もいるしね。さぁ、話が長くなってしまったわ。次の場所へ向かいましょう」
私が留守にしている間、デイジーとサルビアに陣営での治療は任せることにしている。
私が赴くと言い出した時、二人は強く反対したけれど、私はどうにか説得し、こうして現場に訪れたのだ。
「正確に現場を知らなければ、分からないことがあるからね……」
独り言を呟きながら、どうすれば衛生兵として貢献できるか、生き延びる可能性が高くなるかを考えとしてまとめていく。
私ができないことを他の衛生兵に求めるのは難しいだろうから、全ての行動や条件を様々な条件に落とし込んでいくことも忘れない。
「各小隊が連携をとりながら、どの隊にも衛生兵を置くのがいいのかしらね」
インディゴの言う通り、怪我をその場で治癒しながら戦闘できるというのは、大きな優位性を持つ。
戦闘続行の判断として、兵士たちの怪我の多寡を考慮に入れなくて済むため、物資や各人の体力、魔力だけが問題になる。
思っていた通り、傷付いた兵士を陣営での治すよりも、効率的なはずだ。
やはり問題は、衛生兵の質と数の問題と、安全を確保だろう。
「他の四人も無事だといいのだけれど」
私の他にも四名、志願してくれた衛生兵が今日の作戦に参加している。
彼女たち今回派遣したのは全員同じ中隊だ。
彼女たちの安全を祈りながら、私は前後を兵士に守られながら、次の目的地へと行進を続けた。
☆
「全員臨戦態勢!! 魔族だ!!」
しばらく歩き続けていたら、突然前衛の兵士の一人がそう叫んだ。
他の兵士はその声を聞いた瞬間、歩きやすいように収めていた各自の武器を構え、前方に意識を集中させた。
私の視線も前方に突如現れた、二足歩行の黒い影に釘付けになっていた。
それはまるで、野牛を擬人化したような見た目をしている。
頭から生えた二本のねじれたツノ、そして半裸の肉体は盛り上がった筋肉によって覆われていた。
手には大振りの曲刀を持ち、まるで、私たちがここに来ることを待ち構えていたかのように一人立ち尽くしている。
「くそっ! 識別名称【暴れ牛】だ!! 寄りにもよって!!」
インディゴが叫ぶ。
どうやら目の前の魔族は、軍の中では有名な相手らしい。
識別名称というのは、軍内で敵の個体勢力を呼称するために用いられる。
つまり、目の前の暴れ牛は、名前が付くほど戦果をあげているというわけだ。
インディゴが暴れ牛という言葉を発した瞬間、目の前の敵は、笑みを作ったように見えた。
相手が自分のことを知っていることへの喜びか、はたまた嘲りか。
そんな暴れ牛をしっかり見据えたまま、殿を務めていたインディゴは、私を庇うように少し前におどり出る。
そして、叫ぶように指示を出した。
「いいか? 俺は言ったな? 死んでも聖女様はお守りしろ!! ヤバくなったら誰でもいい! とにかく聖女様を逃がせ!!」
インディゴの言葉に兵士たちは短い返事を一斉に返した。
それが、私が初めて目の当たりにする魔族、暴れ牛との戦闘開始の合図だった。
戦闘は劣勢が続いていた。
インディゴの指示で様々な攻撃が繰り広げられるが、そのことごとくが受け止められ、逆に誰かが負傷した。
「今、回復するわ‼︎」
私はそのたび、回復魔法をかけていた。
まだ死者は出ていないが、このまま打開策が見つからなければ、そう遅くない未来、全滅も覚悟しなければならないだろう。
「くそっ! こいつ‼︎ 俺らのことを弄んでやがる! 逃がす気もないみたいだし、このままじゃジリ貧だ‼︎」
誰かが吐き捨てるように叫ぶ。
彼の言う通り、暴れ牛は私たちとの戦闘を楽しんでいるような素振りを見せていた。
基本的に最初の場所から動かずに、こちらが近づいた場合のみ、返り討ちのように手に持った巨大な曲刀を振るった。
その勢いは凄まじく、受けた兵士は毎回死なないまでも致命傷を負わされている。
その間、インディゴの指示でも、それ以外の兵士自身の判断でも、何度も逃走を試みた。
しかし、暴れ牛は私たちを逃がす気はないらしく、逃げようとした兵士が出た瞬間、凄まじい速さでそれを阻止してくる。
「なんだかよォ。おかしいなァ。俺は何度も切ったんだぜェ? それなのによォ」
今まで一言も声を発していなかった暴れ牛が、突然私にも分かる言葉で、独り言のようなものを呟き始めた。
どうやら魔族というのは、私たちの使う言葉を理解し、扱うことができるらしい。
魔族が喋ること自体が珍しいのか、暴れ牛の声に、インディゴ、他の兵士たちも驚いた様子だ。
そんな私たちの様子など意に介さぬように、暴れ牛は独白を続けた。
「俺ァ切ったよなァ? ああ、切ったともォ。それなのにィ。なんで、テメェら死なねんだァ?」
そう言いながら、暴れ牛は自分の得物を素早く数度その場で振った。
そのたび風を切る音と、風圧がこちらまで飛んでくる。
「おかしいよなァ? ゼェーたい、おかしィ‼︎ テメェらァ! なんで俺が切っても、死なねんだァァ‼︎」
今まで能動的に場所の移動をしてこなかった暴れ牛が、突進の如く迫ってきた。
前衛の兵士が慌ててそれを受け止めようと、武器を構える。
「一人目ェ‼︎」
突進の勢いを殺さぬまま、暴れ牛は得物を横薙ぎに振るう。
辛うじて受け止めた兵士の持った剣は砕け、勢いは減ったものの、曲刀は兵士の横腹にぶつかる。
「ぐはぁ‼︎」
全てを吐き出すような呻き声を上げた兵士は、そのまま弾かれ横に吹き飛んでいく。
私はすでに用意していた上級の治癒魔法をまだ地面にたどり着く前に、負傷した兵士に唱えた。
突撃の勢いを緩めない暴れ牛に、横から襲うように別の前衛が剣を振るう。
「それェ! 二人目ェ‼︎」
「くっ! ぐ……うわぁぁ‼︎」
しかし、それをすでに読んでいたのか、下からすくい上げるように暴れ牛は剣撃を繰り出す。
逆に受け止める形になった兵士は、一瞬耐え切ったと思えたが、受け止めた剣ごと身体を縦に切り裂かれる。
これも準備しておいた治癒魔法を唱え、なんとか一命を取り留める。
しかし、このままの勢いで攻撃が続けば、すぐに私の魔法の速度が間に合わなくなっていってしまう。
焦りを感じていたところで、突然暴れ牛は突進を止め、その場で無造作に立ち尽くした。
それを見た、後衛の魔法兵が攻撃を繰り出すが、暴れ牛にぶつかる前に、曲刀で薙ぎ払われてしまった。
「テメェかァ……さっきからウザってェことしやがってるのはよォ……」
「まずい‼︎ 聖女様をお守りしろ‼︎」
私はこの瞬間、戦闘の現場に来てから、初めて恐怖に支配されるというのを理解した。
今まで私は、攻撃兵と同じ戦場に立っていると思っていたが、大きな間違いだったらしい。
今までの私は敵の攻撃の対象になっていなかった。
体がすくむ様な敵意を、自身に向けられることなどなかった。
危険に身を晒していると思っていたけれど、安全な場所に立っていたのだ。
そして今、明確な殺意が、私を殺そうとしている刺さる様な敵意が、私の身体に向けられている。
その時になって初めて、自分が死と隣り合わせの危険な場所に立ったのだと理解した。
「テメェらァ。みんな邪魔だァ……そいつが変なことしてるからァ、俺が切っても切ってもォ、テメェらは死なねんだろゥ?」
インディゴの一声で、その場にいる全ての兵士が、私と暴れ牛の間に割り込む。
全員が私の命を守ろうと、必死の形相だ。
「聖女様! ダメです‼︎ 逃げましょう‼︎」
小隊に派遣されてから、最初に治療を施した若い兵士が、私の手を握り、後ろに走り出した。
それを見届けた他の兵士たちは、なんとか暴れ牛の動きを止めようと、一斉に攻撃を繰り出し始めた。
「逃がすかよォ! まずはソイツをやってェ、テメェらもォ、全員皆殺しだァ」
どう動いたのか分からないが、兵士と共に後に走り出した私の目の前に、暴れ牛が姿を現した。
そのまま、曲刀を振るう。
魔族の表情など私には分かるはずもないのに、最初に出会った時と同じように、暴れ牛が笑みを浮かべた様に感じた。
「聖女様‼︎」
私の手を引いてた兵士の叫び声が耳を打つ。
その瞬間、私の身体は突き飛ばされ、横に流れた。
倒れていく中、私の視界は、私の代わりに切り付けられた兵士の血で、真っ赤に染まった。
インディゴの指示で様々な攻撃が繰り広げられるが、そのことごとくが受け止められ、逆に誰かが負傷した。
「今、回復するわ‼︎」
私はそのたび、回復魔法をかけていた。
まだ死者は出ていないが、このまま打開策が見つからなければ、そう遅くない未来、全滅も覚悟しなければならないだろう。
「くそっ! こいつ‼︎ 俺らのことを弄んでやがる! 逃がす気もないみたいだし、このままじゃジリ貧だ‼︎」
誰かが吐き捨てるように叫ぶ。
彼の言う通り、暴れ牛は私たちとの戦闘を楽しんでいるような素振りを見せていた。
基本的に最初の場所から動かずに、こちらが近づいた場合のみ、返り討ちのように手に持った巨大な曲刀を振るった。
その勢いは凄まじく、受けた兵士は毎回死なないまでも致命傷を負わされている。
その間、インディゴの指示でも、それ以外の兵士自身の判断でも、何度も逃走を試みた。
しかし、暴れ牛は私たちを逃がす気はないらしく、逃げようとした兵士が出た瞬間、凄まじい速さでそれを阻止してくる。
「なんだかよォ。おかしいなァ。俺は何度も切ったんだぜェ? それなのによォ」
今まで一言も声を発していなかった暴れ牛が、突然私にも分かる言葉で、独り言のようなものを呟き始めた。
どうやら魔族というのは、私たちの使う言葉を理解し、扱うことができるらしい。
魔族が喋ること自体が珍しいのか、暴れ牛の声に、インディゴ、他の兵士たちも驚いた様子だ。
そんな私たちの様子など意に介さぬように、暴れ牛は独白を続けた。
「俺ァ切ったよなァ? ああ、切ったともォ。それなのにィ。なんで、テメェら死なねんだァ?」
そう言いながら、暴れ牛は自分の得物を素早く数度その場で振った。
そのたび風を切る音と、風圧がこちらまで飛んでくる。
「おかしいよなァ? ゼェーたい、おかしィ‼︎ テメェらァ! なんで俺が切っても、死なねんだァァ‼︎」
今まで能動的に場所の移動をしてこなかった暴れ牛が、突進の如く迫ってきた。
前衛の兵士が慌ててそれを受け止めようと、武器を構える。
「一人目ェ‼︎」
突進の勢いを殺さぬまま、暴れ牛は得物を横薙ぎに振るう。
辛うじて受け止めた兵士の持った剣は砕け、勢いは減ったものの、曲刀は兵士の横腹にぶつかる。
「ぐはぁ‼︎」
全てを吐き出すような呻き声を上げた兵士は、そのまま弾かれ横に吹き飛んでいく。
私はすでに用意していた上級の治癒魔法をまだ地面にたどり着く前に、負傷した兵士に唱えた。
突撃の勢いを緩めない暴れ牛に、横から襲うように別の前衛が剣を振るう。
「それェ! 二人目ェ‼︎」
「くっ! ぐ……うわぁぁ‼︎」
しかし、それをすでに読んでいたのか、下からすくい上げるように暴れ牛は剣撃を繰り出す。
逆に受け止める形になった兵士は、一瞬耐え切ったと思えたが、受け止めた剣ごと身体を縦に切り裂かれる。
これも準備しておいた治癒魔法を唱え、なんとか一命を取り留める。
しかし、このままの勢いで攻撃が続けば、すぐに私の魔法の速度が間に合わなくなっていってしまう。
焦りを感じていたところで、突然暴れ牛は突進を止め、その場で無造作に立ち尽くした。
それを見た、後衛の魔法兵が攻撃を繰り出すが、暴れ牛にぶつかる前に、曲刀で薙ぎ払われてしまった。
「テメェかァ……さっきからウザってェことしやがってるのはよォ……」
「まずい‼︎ 聖女様をお守りしろ‼︎」
私はこの瞬間、戦闘の現場に来てから、初めて恐怖に支配されるというのを理解した。
今まで私は、攻撃兵と同じ戦場に立っていると思っていたが、大きな間違いだったらしい。
今までの私は敵の攻撃の対象になっていなかった。
体がすくむ様な敵意を、自身に向けられることなどなかった。
危険に身を晒していると思っていたけれど、安全な場所に立っていたのだ。
そして今、明確な殺意が、私を殺そうとしている刺さる様な敵意が、私の身体に向けられている。
その時になって初めて、自分が死と隣り合わせの危険な場所に立ったのだと理解した。
「テメェらァ。みんな邪魔だァ……そいつが変なことしてるからァ、俺が切っても切ってもォ、テメェらは死なねんだろゥ?」
インディゴの一声で、その場にいる全ての兵士が、私と暴れ牛の間に割り込む。
全員が私の命を守ろうと、必死の形相だ。
「聖女様! ダメです‼︎ 逃げましょう‼︎」
小隊に派遣されてから、最初に治療を施した若い兵士が、私の手を握り、後ろに走り出した。
それを見届けた他の兵士たちは、なんとか暴れ牛の動きを止めようと、一斉に攻撃を繰り出し始めた。
「逃がすかよォ! まずはソイツをやってェ、テメェらもォ、全員皆殺しだァ」
どう動いたのか分からないが、兵士と共に後に走り出した私の目の前に、暴れ牛が姿を現した。
そのまま、曲刀を振るう。
魔族の表情など私には分かるはずもないのに、最初に出会った時と同じように、暴れ牛が笑みを浮かべた様に感じた。
「聖女様‼︎」
私の手を引いてた兵士の叫び声が耳を打つ。
その瞬間、私の身体は突き飛ばされ、横に流れた。
倒れていく中、私の視界は、私の代わりに切り付けられた兵士の血で、真っ赤に染まった。
私は叫ぶよりも、倒れていく自分の身体を気遣うよりも先に、自分が使える最上級の治癒の魔法を唱える準備をした。
若い命を、私を庇ってくれた兵士の命を、失うわけにはいかなかった。
胴体を深く切り払われた兵士の体は、まるで糸が切れた人形のように崩れていく。
その体が地面に到達する直前に、私の魔法が完成した。
「私はあなたを! 死なせはしない!!」
気合いとともに放った治癒の魔法は、兵士の体全体を白く包み、まるで時間が戻るかのように、損傷した怪我を塞いでいく。
衝撃で意識を失ってしまったのかもしれないが、地面に倒れピクリともしない体は、削られた防具以外、元通りに戻っていた。
「テメェ……やっぱりウゼェなァ!!」
回復し、一命を取り留めたであろう兵士など目もくれず、暴れ牛はゆっくりとした足取りで私の元へと歩いてくる。
地面を踏み鳴らすその一歩一歩が、まるで死への秒読みのように感じた。
「くそぉ!! 喰らえぇ!!」
インディゴを始めとした魔法を扱える兵士たちが、暴れ牛に光弾を放つ。
しかし、何度も見てきた光景が繰り返され、兵士たちの放った魔法は、暴れ牛に傷を与えることはできなかった。
「ちくしょおォ、テメェらァ。邪魔だなァ。その邪魔な女がァ、殺れねェじゃねェかァ。まったくゥ、弱いくせによォ」
魔法兵が攻撃を放っている間に、再び兵士たちが暴れ牛と私の間に走りんでいた。
それを見た暴れ牛は、苛立った表情を見せ、そして何かを思いついたように、今度こそ明確にニヤリと笑った。
「そうかァ。傷つけても、傷つけてもォ。テメェが回復しやがるがァ。あそこに寝てる野郎みたいにィ、意識を刈り取ってやればァ、もう起きねェなァ!!」
その瞬間、一陣に風が吹き荒れたように感じた。
「ぐっ……!!」
「ぐぇ……!!」
小さなうめき声とともに、目の前の兵士たちが視界から消え、地面へと倒れ込んでいく。
兵士たちの体に目をやるが、目立った怪我はない。
どうやら暴れ牛は、傷を負わせても私が回復してしまうことが、失った意識までは回復できないことに気がついてしまったようだ。
回復魔法で再び立ち上がれぬよう、傷よりも意識を刈り取ることを重視した攻撃を繰り出しているのだろう。
何とか私の身を守ろうと必死に頑張る兵士たちは、次々と倒れ、とうとう立っているのは私一人になってしまった。
暴れ牛は満足したように、再び笑みを深め、そしてゆっくりと近づいてくる。
「テメェは、一瞬じゃあァ殺さねェ……イライラさせられたからよォ。自分で自分を治したって無駄だぜェ。今まで見てて知ってるんだァ。テメェの魔法よりィ、俺の方がはえェ」
私はここまでかと観念して、その場に立ち尽くし、目を閉じた。
闇に変わった視界の中に、これまでの出来事や人物が次々と映し出されていく。
デイジーは私が死んだことを聞いて泣くだろうか、それとも怒るだろうか。
きっと両方だ。
それでも彼女はこのまま訓練を続ければ、私以上の回復魔法の使い手になってくれるに違いない。
サルビアと共に、部隊を指揮し、後続の衛生兵の指導も問題なくこなしてくれるだろう。
クロムもきっと、人づてに聞くはずだ。
彼に死ぬなと言った私が先に死ぬんだから、世話がない。
アンバーやダリアはどうするだろうか。
ベリル王子は、忠告を聞いておけば、と嫌味の一言も言ってくるかもしれない。
思えば、いつからか、私は少し傲慢になっていたのかもしれない。
自分に治せないものはなく、自分がいれば大丈夫だと。
今までに数え切れないほどの兵士たちを治療し救ってきた。
それがいつしか、死なずに治癒できると、奢り昂っていたのだ。
私が治してきた兵士の後ろには、まだまだおびただしいほどの死が、紛れもない明確な死が、犠牲として横たわっていたというのに。
目をつぶってから、覚悟を決めてかどれほどの時間が経っただろうか。
すごく長い時間だったかもしれないし、ほんの一瞬だったかもしれない。
しかしとうとうその時が来たのを、私は頬に感じる風圧で理解した。
自分のこれまでの選択に、後悔してるわけではないが、やり残したことが数多くある。
それが心残りだった。
身体がこわばり、閉じていた目をさらにきつくつぶる。
おかしい……
私の脳裏に、異常を知らせる疑問が沸き起こっていた。
振り下ろされるはずの凶刃は、いつまで経っても私に身体に到達しなかった。
その代わりに、激しい動きを想像させる金属同士ぶつかる音と、風が周囲を舞っている。
私は何が起こっているのか、固く閉じた目を、ゆっくりと開く。
そこには、見知った一人の兵士、クロムが暴れ牛と互角以上に戦いを繰り広げていた。
暴れ牛は先ほどまでは全ての攻撃を弾き、逆に一撃の元に兵士に致命傷を与えていた。
しかし、クロムの攻撃を捌ききれずに、その黒い体からさらに黒い血のようなものを流している。
私のすぐ近くで繰り返されてた攻防は、暴れ牛が後ろに大きく退いたことで、一度途切れた。
その隙に、クロムは私の身体を守るように、私と暴れ牛の直線上に移動し、剣を構え直す。
「テメェ……何もんだァ?」
「魔族に名乗る名などない!!」
クロムは暴れ牛の問いに、短く言い放つ。
そして意識を暴れ牛から離さぬまま、背中越しに驚きで声を忘れている私に話しかけてきた。
「遅くなりました。聖女様! 間に合って良かったです!! あの時の約束、きちんと果たしますから!!」
若い命を、私を庇ってくれた兵士の命を、失うわけにはいかなかった。
胴体を深く切り払われた兵士の体は、まるで糸が切れた人形のように崩れていく。
その体が地面に到達する直前に、私の魔法が完成した。
「私はあなたを! 死なせはしない!!」
気合いとともに放った治癒の魔法は、兵士の体全体を白く包み、まるで時間が戻るかのように、損傷した怪我を塞いでいく。
衝撃で意識を失ってしまったのかもしれないが、地面に倒れピクリともしない体は、削られた防具以外、元通りに戻っていた。
「テメェ……やっぱりウゼェなァ!!」
回復し、一命を取り留めたであろう兵士など目もくれず、暴れ牛はゆっくりとした足取りで私の元へと歩いてくる。
地面を踏み鳴らすその一歩一歩が、まるで死への秒読みのように感じた。
「くそぉ!! 喰らえぇ!!」
インディゴを始めとした魔法を扱える兵士たちが、暴れ牛に光弾を放つ。
しかし、何度も見てきた光景が繰り返され、兵士たちの放った魔法は、暴れ牛に傷を与えることはできなかった。
「ちくしょおォ、テメェらァ。邪魔だなァ。その邪魔な女がァ、殺れねェじゃねェかァ。まったくゥ、弱いくせによォ」
魔法兵が攻撃を放っている間に、再び兵士たちが暴れ牛と私の間に走りんでいた。
それを見た暴れ牛は、苛立った表情を見せ、そして何かを思いついたように、今度こそ明確にニヤリと笑った。
「そうかァ。傷つけても、傷つけてもォ。テメェが回復しやがるがァ。あそこに寝てる野郎みたいにィ、意識を刈り取ってやればァ、もう起きねェなァ!!」
その瞬間、一陣に風が吹き荒れたように感じた。
「ぐっ……!!」
「ぐぇ……!!」
小さなうめき声とともに、目の前の兵士たちが視界から消え、地面へと倒れ込んでいく。
兵士たちの体に目をやるが、目立った怪我はない。
どうやら暴れ牛は、傷を負わせても私が回復してしまうことが、失った意識までは回復できないことに気がついてしまったようだ。
回復魔法で再び立ち上がれぬよう、傷よりも意識を刈り取ることを重視した攻撃を繰り出しているのだろう。
何とか私の身を守ろうと必死に頑張る兵士たちは、次々と倒れ、とうとう立っているのは私一人になってしまった。
暴れ牛は満足したように、再び笑みを深め、そしてゆっくりと近づいてくる。
「テメェは、一瞬じゃあァ殺さねェ……イライラさせられたからよォ。自分で自分を治したって無駄だぜェ。今まで見てて知ってるんだァ。テメェの魔法よりィ、俺の方がはえェ」
私はここまでかと観念して、その場に立ち尽くし、目を閉じた。
闇に変わった視界の中に、これまでの出来事や人物が次々と映し出されていく。
デイジーは私が死んだことを聞いて泣くだろうか、それとも怒るだろうか。
きっと両方だ。
それでも彼女はこのまま訓練を続ければ、私以上の回復魔法の使い手になってくれるに違いない。
サルビアと共に、部隊を指揮し、後続の衛生兵の指導も問題なくこなしてくれるだろう。
クロムもきっと、人づてに聞くはずだ。
彼に死ぬなと言った私が先に死ぬんだから、世話がない。
アンバーやダリアはどうするだろうか。
ベリル王子は、忠告を聞いておけば、と嫌味の一言も言ってくるかもしれない。
思えば、いつからか、私は少し傲慢になっていたのかもしれない。
自分に治せないものはなく、自分がいれば大丈夫だと。
今までに数え切れないほどの兵士たちを治療し救ってきた。
それがいつしか、死なずに治癒できると、奢り昂っていたのだ。
私が治してきた兵士の後ろには、まだまだおびただしいほどの死が、紛れもない明確な死が、犠牲として横たわっていたというのに。
目をつぶってから、覚悟を決めてかどれほどの時間が経っただろうか。
すごく長い時間だったかもしれないし、ほんの一瞬だったかもしれない。
しかしとうとうその時が来たのを、私は頬に感じる風圧で理解した。
自分のこれまでの選択に、後悔してるわけではないが、やり残したことが数多くある。
それが心残りだった。
身体がこわばり、閉じていた目をさらにきつくつぶる。
おかしい……
私の脳裏に、異常を知らせる疑問が沸き起こっていた。
振り下ろされるはずの凶刃は、いつまで経っても私に身体に到達しなかった。
その代わりに、激しい動きを想像させる金属同士ぶつかる音と、風が周囲を舞っている。
私は何が起こっているのか、固く閉じた目を、ゆっくりと開く。
そこには、見知った一人の兵士、クロムが暴れ牛と互角以上に戦いを繰り広げていた。
暴れ牛は先ほどまでは全ての攻撃を弾き、逆に一撃の元に兵士に致命傷を与えていた。
しかし、クロムの攻撃を捌ききれずに、その黒い体からさらに黒い血のようなものを流している。
私のすぐ近くで繰り返されてた攻防は、暴れ牛が後ろに大きく退いたことで、一度途切れた。
その隙に、クロムは私の身体を守るように、私と暴れ牛の直線上に移動し、剣を構え直す。
「テメェ……何もんだァ?」
「魔族に名乗る名などない!!」
クロムは暴れ牛の問いに、短く言い放つ。
そして意識を暴れ牛から離さぬまま、背中越しに驚きで声を忘れている私に話しかけてきた。
「遅くなりました。聖女様! 間に合って良かったです!! あの時の約束、きちんと果たしますから!!」
この作家の他の作品
表紙を見る
気付くと私は、発売から十年経った今も思い出してはプレイを続ける乙女ゲーム「イストワール〜星恋の七王子」のキャラクターに転生してしまった。
しかもそれはゲーム内でヒロインを執拗に陥れようと画策する悪役令嬢、ミザリー・マリア・ド・ゴール。
本来の主人公であるヒロインがどのルートを通ってもその前に立ちはだかり、最終的には己の行いが招いた破滅の結末を迎える。
私はそんな結末を回避しようと、三年間の学園生活を奔走する。
「王子を味方につける方法を考えなきゃ!」
表紙を見る
精霊に愛された少女は聖女として崇められる。私の住む国で古くからある習わしだ。
驚いたことに私も聖女だと、村の皆の期待を背に王都マーベラに迎えられた。
それなのに……。
「この者が聖女なはずはない! 穢らわしい!」
私よりも何年も前から聖女として称えられているローザ様の一言で、私は国を追放されることになってしまった。
「もし良かったら同行してくれないか?」
隣国に向かう途中で命を救ったやり手の商人アベルに色々と助けてもらうことに。
その隣国では精霊の力を利用する技術を使う者は【錬金術師】と呼ばれていて……。
第五元素エーテルの精霊に愛された私は、生まれた国を追放されたけれど、隣国で天才錬金術師として暮らしていくようです!!
この物語は、国を追放された聖女と、助けたやり手商人との恋愛話です。
追放ものなので、最初の方で3話毎にざまぁ描写があります。
薬の効果を示すためにたまに人が怪我をしますがグロ描写はありません。
作者が化学好きなので、少し趣味が出ますがファンタジー風味を壊すことは無いように気を使っています。
ベリーズファンタジー様から発売されました!!
書籍版は大ボリューム加筆修正しておりますので、ぜひぜひお手にお取りください!!
表紙を見る
勇者パーティの支援職だった私は、自己を超々強化する秘法と言われた魔法を使い、幼女になってしまった。
そんな私の姿を見て、パーティメンバーが決めたのは……
「アリシアちゃん。いい子だからお留守番しててね」
見た目は幼女でも、最強の肉体を手に入れた私は、付いてくるなと言われた手前、こっそりひっそりと陰から元仲間を支援することに決めた。
戦神の愛用していたという神器破城槌を振り回し、神の乗り物だと言うもふもふ神獣と旅を続ける珍道中!
主人公は元は立派な大人ですが、心も体も知能も子供です
基本的にコメディ色が強いです
毎日朝7時に一話分更新します
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…