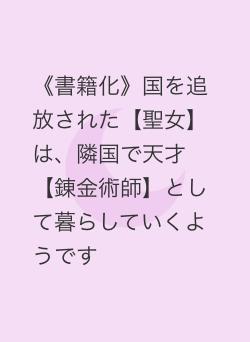「フローラが聖女ではないとは、どういうことですか⁉ ルチル王子!」
私の父、アルマン・ルイ・ド・ゴール侯爵が叫ぶ。
父と相対するのは、この国の第一王子であるルチル・ヘンリー・ド・シャルル王子。
柔らかな金髪と自らの力を象徴する紅い瞳を持つこの男性は、病弱な国王が療養中の今、実質的な権限を持つ王太子だ。
「どうもこうも、事実を述べただけだよ。アルマン。聖女と思ってフローラには尽くしてもらったが、真の聖女は他にいた、ということだ」
「そんなことは……! 現にフローラは【リラの花】を紫色に咲かせたのですから」
【リラの花】と言うのは聖女の証と呼ばれる花で、聖女が毎年育てている花だ。
聖女選定の際には、それがめぼしい候補者に配られる。
そして育てていくと、育てたものの魔力を吸い花を咲かせる。
普通は白色だが、聖女に選ばれるもの花は鮮やかな紫色に色付く。
私は父にプレゼントされたこの花をそうとは知らずに育て、見事に濃い紫色の花が咲いた。
「だからそれが偽物だったと言っておるのだ。白い花弁に丁寧に色を塗って騙そうとしたのだ」
「そ、そんな馬鹿なことが! では! 本当の聖女はどこにいると言うのですか⁉」
「ここにいる。このマリーゴールドこそが真の聖女だよ。なぁ? マリーゴールド」
「ば、馬鹿なことを! 聖女に選ばれると言うことがどれほど重要なことかお分かりにならぬのですか⁉」
父はなおも私を聖女にしようと言うのか。
今までも何度もご辞退すると伝えてきたと言うのに。
聖女というのは、回復魔法を習得した貴族の令嬢の中でも、一人だけがなることを許される特別な存在だ、と父は言う。
前聖女が亡くなり、次の聖女が誰になるかは父を含め、多くの貴族の関心ごとらしい。
しかし私にはそんなことはどうでもいいことだった。
聖女はその身を国に捧げる――これについてはなんの問題もない。
だけどその後が気に食わないのだ。
一日中平和のために祈りを捧げ、国王を始めとした王族が怪我をした時にだけその卓越した回復魔法を使う。
そんな物になるために私は回復魔法を学んだのではない。
私が回復魔法を学んだ理由。それは今も前線で傷つき倒れている兵士たちを癒すためだ。
兵士たちだけではない。
国民全体が怪我をしても十分な回復魔法を受けることができず、落とさなくてもいい命を落としている。
それを改善したいと、私は必死で回復魔法を学んだ。
それなのに、王族にしか使うことが許されず、それ以外は祈るだけの聖女などに、誰がなりたいと言うのだろうか。
また、聖女はその国の王太子と婚姻関係を結ばされる。
つまり、私が聖女になれば、ルチル王子の妻にならなくてはならない。
私がまるで他人事のようにルチル王子と父のやりとりを見ていると、ふとマリーゴールドと目が合う。
緩やかなカーブを持つ桃金色の髪と、緑藍色の瞳を持つ彼女は、非常にふくよかな肢体をしていた。
ルチル王子は物腰柔らかで、この少しお頭の弱いマリーゴールドのような女性が好みなのは知っていた。
私は直毛の灰銀色の髪と薄褐色の瞳、そしてスレンダーな肢体していて、聖女に選ばれたと伝えた時のルチル王子の落胆を見ると、残念ながら好みではなかったのだろう。
(胸はそれなりにある方だと思うのだけれど……)
そんなことを思いながら目線を自分の体に向けると、父が私の婚姻について話しているのが聞こえた。
「しかし! それでは王子と娘の! フローラとの婚姻は⁉」
「そんなものは当然破棄だ。もういいぞ。アルマン。これ以上俺に楯突くのであれば、いくらお前でも処罰せねばならなくなる。親子揃って戦場に行かせるのはさすがに忍びない」
「なっ! なんですと⁉ 娘を! 娘を戦地へと赴かせるとおっしゃるのですか‼」
「ああ。そうだ。本来ならば、国を欺こうとした罪で一生幽閉が妥当かと思ったのだがな。ベリルの進言で、せっかく使える回復魔法を国のために使ってもらう方が少しは役に立つ、と言うことになった」
ベリルというのはこの国の第二王子であるベリル王子のことだろう。
ベリル王子は兄のルチル王子と異なり合理的な考えの持ち主だ。
さらに昔一度だけ舞踏会でエスコートをしてくれた際に、私の考えを伝えたことがあり、賛同してくれた記憶がある。
ただ随分と昔のことで、そのことをベリル王子が覚えているかどうかは定かではない。
まさか、ベリル王子がその時の私の考え通りに進言してくれるとは思ってもいなかったので、私は目を見開き、続きを聴き入った。
「まぁ、さすがに死亡率が高い前線に行かせるわけじゃない。せいぜい陣営の指揮官付きの回復魔導士として重宝されるだろう」
これで話はお終いだというふうに、ルチル王子は手で合図を送った。
いくら私の父が侯爵だとはいえ、この国の王子であり実質的な第一権力者に歯向かうことなどできるはずもない。
父はルチル王子の合図に従いその場を離れようとする。
私もそれにならい、踵を返す。
ふと、振り返りもう一度だけルチル王子とマリーゴールドの顔を見ると、二人は満足そうな顔で笑っていた。
☆
「そうだ‼ 国王に! 国王に直訴すればよいのだ‼」
父は屋敷に戻ってから、落ち着きなく部屋中をうろうろと歩き回っていた。
そして名案を思いついたとばかりに手を打つと、そんなことを言い出す。
「お父様。それはできるはずがありません。国王様は病床に伏せております。前聖女様が亡くなった今、お会いできるのは次期聖女に選ばれた者だけです」
「だから! お前が行って国王の病を治してくれば良いのだ! そうすれば、国王もお前を聖女として認めるに違いない」
父はなおもこの案が素晴らしいと思ってやまないらしい。
しかしどう考えても、実権を握っているルチル王子の承諾を得ることなく王に会うことなど不可能だ。
「お父様。お父様が普段からは考えられないような思考をお持ちになるほど、私のことを愛していることは分かりました」
「そ、そうだぞ‼ 儂は何も変なことを考えているのではなく、お前のためを思って」
「ということで、これ以上お父様、この家にご迷惑をおかけするつもりはございません。もうじき使いの者が来るはずです。私はルチル王子のご指示通り、戦地で負傷兵のため、奉仕してきます」
「なぁ⁉ ならぬ! ならぬというのだ‼」
慌てる父を置き去りにして、私は自室に戻り、必要な荷造りを始めたのだった。
「魔王討伐軍第五衛生兵部隊フローラです。今日からよろしくお願いします」
「あー。例の……まぁ、ここは比較的安全だからさ。適当にやってよ。僕たちの邪魔だけはしないでくれよ?」
私が使いの者に連れられて来た戦場というのは、予想以上に酷いものだった。
衛生兵部隊、つまり負傷兵の治癒を担う部隊の長は女性ですらなかった。
どういうわけか分からないけれど、回復魔法を使えるのはもっぱら女性だけ。
男性は魔族や魔獣を打ち倒すための攻撃魔法の適性が高い。
それなのに聞けば、五つある衛生兵部隊の部隊長も、それを統率する長官も、全て男だった。
長官に至っては魔道士ですらなく、コネでなったとしか思えないような実績だ。
「邪魔……とは、どういう意味でしょうか?」
「言葉の通りだよ。ここでは大勢死ぬ。女性のしかも今までは貴族の生活を楽しんでたアンタには辛いだろうが、泣いたり喚いたりしないでくれ」
どうやらこの部隊長、アンバーは私をお荷物だと思っているようだ。
白が混じった短髪の黒髪をわしわしと撫でながら、濃褐色の目をこちらに向ける。
しかしそれは仕方のないことなのかもしれない。
私のことがどのように伝わっているのかは知らないけれど、前線に送られる回復魔法の使い手は、未亡人かクビになったメイドくらいだと聞いている。
前線に来てから簡単な魔法を学ぶ者がほとんどだということも。
そもそも回復魔法を体系的に教える場所がないのだから、質も量も増えはしない。
質のいい担い手は、王族専属の聖女とまではいかなくても、貴族たちが囲っているのだ。
「お言葉ですが、お邪魔をするつもりはありません。できるだけ多くの人を助けたいと思って――」
「あー、そういうのいいから。どうせ死ぬときゃ死ぬんだし。あんまり気張らないで。ほんと……邪魔だけはしないでね?」
アンバーは面倒くさそうに手を振る。
どうやら歓迎もされていないし、私を有効に使おうと言う気持ちも無いようだ。
言葉で何を言っても意味が無いと感じた私は、その場を後にして、治療を行う場所へ向かった。
そして、その現場を一目見て、私は目眩を起こしそうになる。
「ここが治療場ですって⁉ 冗談じゃないわ‼」
思わす叫んだ私に、その場にいた人たちから目線が降り注ぐ。
そんなものも構わず、私はどうするか頭を悩ませていた。
まずは臭い。
怪我や魔族の呪い、魔獣の毒などが原因で寝たきりになっている人たちは、排泄物をその場で垂れ流していた。
他に血や様々な臭いが混じり、吐き気を誘う。
とてもではないけれど、治療に適した場所とは言いがたかった。
更に治療とは名ばかりで、ほとんどが回復魔法も使えずに傷口を布で覆う処置をしているような有様だ。
痛みや熱に苛まれ、『殺してください』と呻く人も多い。
「どいてください! 今助けます‼」
「な、なんですか。あなたは⁉ この人はもう無理です。苦しみを長引かせるくらいならいっそのこと――」
私は明らかに重傷な人の前に立ち、回復魔法を矢継ぎ早に唱える。
「助けて……まだ、死ねない……助けて……ください……」
「今助けるから‼」
私は苦痛に顔を歪ませながらも生への執着を絞り出す男性に向かって励ましの声をかける。
焦げ茶色の髪は自身の流した血で固まり、色を失いかけつつある青緑色の瞳は涙に濡れていた。
死ぬ気が無い者をこちらの事情で殺すことなんて以ての外だ。
まずはもっと大きな肉体の損傷の治癒、失った片腕と片脚が戻る。
次に解毒、おそらく魔獣に受けたと思われる毒は既に半身に回っていた。
土気色だった顔に赤みがさすが、そこまでやってもこの若い兵士は苦悶に満ちた表情をしている。
それはきっとこの呪いのせいだろう。
身体に刻まれた紋様を見て私は舌を打つ。
下等魔族が使う【痛み】という呪いで、文字通り全身に激痛を与える。
下等といっても、魔族は一体で魔獣何体分もの強さを誇ると聞いている。
そんなものと戦って生き延びただけでもこの兵士は優秀なのだろう。
私は解呪の魔法を使うため、今一度意識を集中させる。
解呪の魔法は回復魔法の中でも特に難度が高く、私も気軽に扱えるものではなかった。
かざした手から眩しいほどの光が放たれ、青年兵士の呪いを解く。
痛みに悶えていた顔が安堵へと変わる。
「ああ……痛みが嘘のように消えました! ありがとうございます。ありがとうございます‼」
感謝の念を述べた青年兵士は、ようやく得た安息の中、意識を失うように眠りへ落ちた。
それを見届けると、休むことなく次の重傷者へと向かう。
「なんてこと……クロムが治るなんて……奇跡よ……」
「今の見たか⁉ 解毒だけじゃなく解呪まで‼」
後ろでは、クロム――青年兵の名前だろう、を安楽死させようとしていた女性が驚きの声を上げていた。
事態に気付いた周りの人々も歓声を上げる。
「人手が足りない! 回復魔法を使える者は名乗りなさい‼」
その場に居る全員を回復させるには、私だけでは魔力が足りない。
ひとまず命に関わる人たちから治癒を施していくけれど、負傷兵はその間にもどんどん増えていく。
私の叫びに数人がおずおずと手を挙げた。
名前と何ができるか聞き、それぞれに役目を振る。
と言っても、彼女たちができるのは初級の傷の治癒くらいで、ここに居る者を治すためには、一人に何度も回復魔法をかけなければならないような状況だ。
それでも少しずつではあるけれど、回復した者が運ばれる負傷者よりも増えていく。
回復魔法が使えない者には、回復魔法を使える者の補佐をするようにも頼んだ。
寝たきりの兵士の患部を見せるのが補佐の役で、そこを治癒することによって効率的になる。
疲労から来る倦怠感と、回復魔法の酷使による頭痛と戦いながら治癒した結果、危篤状態の負傷兵の数はゼロとなった。
「みな峠は越えました‼ 聖女様‼ あなたのおかげです‼」
「みんなやったぞ‼ 奇跡だ‼ 戦場に舞い降りた聖女様の起こした奇跡だ‼」
「私は……聖女なんかじゃ……ないわ……」
ことを終えたあと、その場に居る兵士も含めてみんなが再び歓声を上げ、その声を聞き届けた私はそのまま倒れるように眠りについた。
私が目を覚ますと、そこは陣営の休息所だった。
一応他の人々と別室を用意してもらってはいるものの、汚れたこの姿で運び入れていいのか悩んでここに運んだと、始めに助けた青年兵士が言った。
「確か……クロムだったわね。ありがとう。起きるまで私をずっと見ていたの?」
「名前を覚えていただき光栄です‼ 聖女様。魔王討伐軍第三攻撃部隊所属のクロムと申します! 失礼ながら、そうであります‼」
「そう……そんなに畏まらなくてもいいのよ。それと、その『聖女』というのはどうにかならないかしら」
「お気に召しませんか? 貴女のことは奇跡を起こした聖女様とみんな呼んでいますが……」
みながそう呼んでいるのなら今から止めるのも無理があるだろう。
まぁ呼び方などより実態が大事なのだから問題とするほどでもない。
「いえ、いいわ。私のことは好きに呼んでちょうだい。それで、どのくらい私は寝てたのかしら?」
「ちょうど半日、つまり十時間ほど寝てらっしゃいました」
一日が二十時間、あの時既に日をまたいでいたから、今は正午過ぎということだろう。
いくら魔力を使い切ったからといって、少し寝すぎてしまったようだ。
「ありがとう。それにしても……さすがに臭うわね。水浴びをして着替えたいのだけれど、場所を知っているかしら?」
「分かりました! 今聞いてきます‼」
そう言うとクロムは私の役に立つのが嬉しいのか、喜び勇んで駆け出していった。
その後陣営の一角で水を使い臭いと汚れを洗い流し、新しい服へと着替える。
「あら? まだ居たのね。クロムも少し休んで、本隊に戻ったら?」
「いえ。実は……恥ずかしながら自分は既に部隊から除名扱いされていたようで……」
そう言いながらクロムは右手の人差し指で頬をかく。
どうやら水浴びをしている間にそのことを知ったらしい。
「まぁ! 何故? あなたはまだ生きているのに」
「まさかあの状態で助かるなどと、誰も思っていなかったようです。自分ですらそう思っていますから。仕方ありません」
部隊は除名されたけれど、本人たっての希望で、ここ第五衛生兵部隊の守衛兵として任を受けることにしたらしい。
戦場から少し離れたこの陣営でも、はぐれの魔獣などが現れるため、それを討伐する者が何人かは必要なのだ。
「せっかく助かった命だし、除名されたのなら軍役は終わるのでしょう? 故郷に戻っても良かったんじゃない?」
「いえ! 自分は、聖女様に救っていただいたこの命、聖女様をお守りするために使うと決めましたから‼」
どうやらこれ以上何を言っても仕方がないようだ。
いずれにしろ軍官に昇進しなければ、長くても数年で軍役は終えるのだ。
それまでは彼の好きなようにさせてあげるのが、彼のためだろう。
もしまた傷つくことがあっても、死んでなければ助けてあげられるかもしれない。
「分かったわ。ありがとう。でも、無理をしないでね。死んでしまっては、私も助けられないから」
「分かりました‼ 肝に銘じます‼」
「それはそうと、今、治療場はどうなっているの?」
「聖女様が眠りに就かれてからも、何人かは重篤な兵が運ばれてきましたが、みなで力を合わせて無事回復しています。今は命に別状がある者は居ないかと」
私はそれを聞いて安心した。
寝ている間に誰か死んでしまったというのでは、さすがに寝覚めが悪い。
不可抗力はあるとはいえ、私が寝すぎていたのは確かだ。
おそらく初めての戦場の雰囲気に、死と隣合わせの現実に、気付かぬうちに緊張していたのだろう。
私はクロムに治療場に向かうと伝え、その場を後にした。
クロムは名残惜しそうな顔をしていたが、本来の業務である陣営周辺の警備にあたると言い私とは別の方へ去っていく。
治療場に足を踏み入れた私は、その場の雰囲気が昨日と打って変わっていたことに驚きを隠せなかった。
昨日見たここに居る人たちは、負傷兵もその治癒に当たる人々も悲壮と諦めに満ちていた。
しかし、今は希望とやる気が見える。
兵士たちは怪我を治し生きる気力を、治す側は死んでいなければ治すのだという自信を持ち始めたようだ。
「あ! 聖女様‼ みんな! 聖女様がお越しになられた!」
「聖女様! この兵はデススコーピオの毒にやられているのです。どうか解毒をお願いします! 私たちに解毒の魔法を使える者がいなくて……」
私は指さされた兵に目を向ける。
確かに腕が青紫色に腫れ上がり、そこから手先と肩に向けて毒が回っているのが分かった。
「分かったわ。ところで、そんなに畏まらなくても……いえ、いいわ。好きにしてちょうだい。さて、と。今治すわね」
私は毒を受けた兵に近寄ると、解毒の魔法を唱え始める。
一言で解毒といっても、簡単な毒しか治すことのできない初級から、大抵の毒を治すことができる上級までいくつか種類がある。
デススコーピオの毒を治すのには中級以上の解毒の魔法が必要だ。
そこで私は中級の魔法を使い解毒を完了させた。
「おお! さすがです! デススコーピオの毒をいとも簡単に‼」
「ありがたい。俺たちには聖女様がついている‼ こんな怪我なんかに負けずに魔王をぶっ飛ばしてやる‼」
「他に解毒が必要な人はいるかしら?」
「いえ、昨日あらかた治していただいたので、今居るのは毒も呪いも無い者ばかりです」
どうやら少し時間をとることができそうだ。
そこで私は昨日回復魔法を唱えることができないと言っていた人たちに声をかける。
「あなたたち。回復魔法を覚える気はないかしら?」
目の前に集まったのは数名の衛生兵。
いずれも回復魔法の担い手となることを期待され、戦線に送られてきた女性たちだ。
しかし、話によるとここに着いた時に行われた簡単な訓練の結果、回復魔法を覚えられなかった者はそのままにされてしまっているらしい。
私はその話に憤りを感じながらも、無駄な時間など一秒もないため、胸の中にしまって、今は自分のすべきことをすることを決めた。
「それじゃあ、まずは初歩の初歩、魔力操作についてやるわね」
私が教える側なので、並んで女性たちに向かい合わせで立ち、みんなの顔に向かってそう言う。
しかし、誰もがなんのことだか分からないような顔をして、互いに顔を見合わせている。
「どうしたの? 回復魔法について一応とはいえ、習ったのでしょう? それなら魔力操作は知っているはずよね?」
私がそう言うが、やはり誰もが分からないと首を横にふった。
そして、その中の一人がおずおずと手を挙げる。
明るめの赤茶色の緩やかなカーブを持つ長髪の女性は、深い藍色の瞳で私を探るように見ながら口を開いた。
「すいません。聖女様。私たちみたいな者のためにせっかく時間を使っていただいているのに。あの……魔力操作って……なんでしょうか?」
「まぁ! 魔力操作の概念を知らずに回復魔法を使わせようとするだなんて! それじゃあ、ほとんどの人ができずに終わるはずだわ‼」
私はその質問と、今のみんなの態度で、何故学べば多くの人ができるはずの初歩の回復魔法すら使えないのか合点がいった。
回復魔法を使える一般人はほぼいないと言っていいが、それは単に学ぶ機会がなかっただけで、能力が足りないわけではない。
まがりなりにも学んだのに、使えない者が多くいる理由。
それは単に教える側の問題だったのだ。
「貴方名前は?」
「すいません。デイジーと申します」
「謝る必要はないわ。デイジー。勇気を出してよく質問してくれたわね」
魔法を唱えるためには、自分の中に流れている魔力を操作できないといけない。
持っている魔力の量はそれぞれだし、使えば使っただけ増えるものだけれど、全く持っていない人はほとんどいないはずだ。
私はまずその自身の持つ魔力の操作方法を懇切丁寧に教えることにした。
得手不得手があり、やり方を学んでもできない人もいるらしいが、幸いなことに時間がかかる者はいたけれど、その場にいる全員が使えるようになった。
「これが魔力操作……なんだか身体の芯がポカポカしてきますね」
「ええ。この感覚を覚えて、暇な時には常に魔力を操作してみることをおすすめするわ。魔力は使えば使うほど鍛えられるものなのだから」
次に私は初歩の回復魔法である傷を治す魔法を教え始める。
魔力操作も初めて学んだような相手に、少し急がせている気もするけれど、ここの状況を考えれば悠長なことは言っていられない。
まずはここにいる全員が最低限、回復魔法を使えるようになってもらわなくては。
今はたまたま重篤な人が少ないけれど、負傷兵は今こうしている間にも生まれている。
回復魔法を使うのは体力を著しく消耗するし、魔力だって使えば無くなる。
今のままでは、いつか崩壊しまた以前のように死者が大勢出るだろう。
そうならないように今のうちにできる限りの準備はしなくてければ。
「デイジー。あなた、筋がいいわね。十分に魔力を操作できているし、回復魔法もできているわ」
「ありがとうございます‼ 聖女様のおかげです! 前に習った時はこんなに分かりやすくなかったですし……」
五つあるという衛生兵部隊のここの様子を見れば、他の部隊も同じようなものだろう。
私が新しく配属されてくる新人も含めて、全員に都度指導をするというのも無理がある。
しかるべき時期に教育機関を作らねばならないと私は胸に刻む。
やがて、デイジーを筆頭に数人が回復魔法を習得した。
残念ながら今日はこの場の全員が習得というわけにはいかなかった。
またの機会を作って指導を続けるとして、回復魔法が使えない人はまだたくさん居るのだ。
交代で時間を作っている以上、一人につきっきりになるわけにもいかない。
衛生兵たちに回復魔法の指導を始めてからしばらく経った。
試行錯誤しながら、いくつかのチームに分け、一つのチームを私が指導、残りのチームで治療に当たるというの体制をとっていた。
「聖女様‼ 毒に侵された兵が複数名運ばれています! どうか、お願いします‼」
しかし、まだ解毒までできるようになった者はおらず、こうやって指導を中断されるのもしばしばだった。
「分かったわ。今行く!」
私は呼びに来た者の後に続き治療場へと急ぐ。
みると腕や脚を腫れ上がられた兵士たちが、何人も治療場に並べられていた。
患部を確認すると、ポイズントードという魔獣から受けた毒らしい。
「これなら初級の解毒魔法でできるわね」
そう言いながら、私は次々と魔法を唱えて行く。
すると、隣でそれを見ていたデイジーがおずおずと申し出てきた。
「あの……聖女様。もし良かったら、私にやらせてもらえませんか?」
「どういうこと? あなたにはまだ解毒魔法を教えていないはずだけれど」
最初から回復魔法を使えた人たちは、教えなくても魔力操作を感覚的に行うことのできた人たちで、上達も他の人より早かった。
その人たちに混じって、デイジーも他の人よりも上級な回復魔法の指導を受けていたのは知っている。
デイジーは私の指導を、水を吸う乾いた土のように吸収し、そして水を得た魚のように巧みに使った。
しかし、そもそもそのチームにすらまだ解毒魔法は教えてすらいないのだ。
それは先により上級の傷を癒す魔法を習得してもらった方が良いと考えたからでもある。
つまり、デイジーが解毒魔法を使えるはずはない。
「あの……聖女様の魔法を横で何度も見ていて、覚えました。私……きっとできます!」
「なんてこと……分かったわ。何事もやらせてみないと上達しない。そして、私はあなたを信じるわ」
目の前の負傷兵はそのやり取りを少し不安げに見ていた。
おそらく私が治療をすると思っていたところに、初めてだと分かるデイジーが代わったことが不安なのだろう。
「大丈夫よ。失敗しても今より悪くなることはないわ。もし失敗しても私がきちんと治してあげる。ただ、この子の成長に、少しだけ協力してちょうだい?」
「分かりました……お願いします!」
そう言うと負傷兵は目をつぶる。
場所を譲ると、デイジーはゆっくりと丁寧に、解毒の魔法を使い始めた。
淡い白い光がデイジーの手の平に現れる。
そしてそれを毒に侵された患部に当て、魔法を唱えた。
力強い言葉の後に、負傷兵の腕が一瞬輝きを放つ。
光が収まると、紫色に腫れ上がっていた腕は、もとの色と太さに戻っていた。
「やったわね。ちゃんとできたじゃない」
「やった……やりました! 聖女様! 私できましたよ‼」
喜ぶデイジーに優しく微笑みかける。
何故かデイジーは私の顔を見て頬を紅潮させた。
「ありがとう。助かりましたよ。凄いですね。聖女様も、デイジーさんも」
「ええ。ここ自慢の衛生兵よ」
腕の毒の治療を終えお礼を述べた兵士に、私は笑顔でそう答えた。
「聖女様。この美しい花は?」
ある日、用事があり私の居室を訪れたデイジーが部屋に飾ってあるリラの花を見つけ聞いてきた。
それは自分で入れた記憶が無いのにも関わらず、気付くと居室にあった。
綺麗な紫色の花を咲かせるその木は、間違いなく私が育てたリラの花だ。
誰が持ってきて置いたのか知らないけれど、ここにある以上は世話をしている。
無視をして枯らすことなど考えもしなかった。
聖女に選ばれるために育てさせられたと今では知っていたけれど、この花自体に罪はない。
「それリラの花よ」
聖女に関することはわざわざ話す気になれず、素っ気なく私はそうとだけ答えた。
「素敵な色の花ですね。小さくても、色に深みがあって。凛として美しい」
「そうかしら。そう言ってもらえると嬉しいわ。ありがとう」
「私もこんな素敵な花育ててみたいなって思いました。私の方こそありがとうございます」
「あら。じゃあ、少し分けてあげるから、デイジーの部屋でも育ててみたら?」
私の申し出にデイジーは驚いた顔をする。
しかし、どうもその後の表情を見ると、よほど花が好きなのだろう、断ることがないということが既に分かった。
「本当ですか⁉ ありがとうございます‼ 大切に育てますね‼」
「ええ。少し育てるのが難しい木だけれど、丁寧に育ててあげればきれいな花が咲くと思うわ」
そう言って私は枝を数本切り落とし、デイジーに手渡す。
デイジーは嬉しそうにそれを受け取り、お礼を言って一度頭を下げてから部屋を出ていった。
「さて……デイジーはどの色の花を咲かせるかしら……」
そんなことを考えていたら一人の兵士が書簡を持ってやってきた。
厳重に封がされていて、持ってきた兵士も誰から送られてきたのか分からないという。
「変ね……普通は中身の検閲があるはずだと聞いているけれど……」
前線に送られるものも、前線から送るものも、ほとんどは中身に問題がないか確認されるはずだった。
しかし、封が切られていないということは、これは検閲を免れたということだ。
よほど権力のある人物からの書簡だと見て間違いはないだろう。
父からだろうか……そう思いながら、私は封を切る。
始めに、書かれている署名に目をやり、予想していなかった人物のものだと分かり驚愕する。
確かに、彼ならば検閲を免れるだろう。
「ベリル王子が私に手紙だなんて……」
この戦場に送る直接の原因となった人物の顔を思い浮かべる。
紅い目の兄のルチル王子とは異なり、思慮と慈愛に満ちた蒼色の瞳を始めに思い出す。
髪は兄弟揃って金色に輝き、柔らかな物腰ながらも王族としての威厳を醸し出す人物だ。
結果的にベリル王子のおかげで私は昔からの夢の実現へと邁進できていると言える。
ただ、直接何か関係を持った記憶は本当に一度しか思い浮かべられない。
そんなベリル王子が私に手紙などどういうことだろうか。
そこには私への労いの言葉と、そしてリラの花を運ばせたのがベリル王子だということが書かれていた。
さらに花の色は何色か定期的に手紙を送るようにとも。
「一体どういうつもりかしら。まぁ、嘘を言うつもりも、王子の命令に背くつもりもないけれど」
私は落ち着いたら家に手紙を書くために持ってきていた用紙を取り出し、ベリル王子に近況と花の色が紫色だと書いた。
封は手紙に同封されていた印を打つ。
手紙にはベリル王子への手紙は全てこの印を使って封をするようにと書かれていたからだ。
そしてそれを、手紙を持ってきた兵士に渡した。
数日経って、ベリル王子から返信が届いた。
この陣営から王都まではかなりの距離がある。
どんなに急いでも数日で往復できる距離ではない。
ということはベリル王子は王都を離れ、陣営の近くに来ているのだろうか。
「もしくは誰かのイタズラかしら。こんな手の込んだイタズラをする相手も、する理由も思いつかないけれど」
そんな独り言を言いながら、返信の封を切り中を確認する。
そこには『分かった』とだけ書かれていた。
「本当にどういうことかしら……定期的に手紙を送れば、いずれは何か分かるのかしら」
私は再び近況とリラの花の色を書き、手紙を送り返した。
☆
「やぁ。フローラ嬢。なかなかの活躍らしいじゃないか。まぁ、そこに座っておくれよ」
ある日、第五衛生兵部隊の部隊長であるアンバーが、私を自室に呼び出した。
随分と自由に動き回っていた自覚はあるので、そのお小言だろうか。
「それで、聖女様? だっけ。兵士たちは君のことをそんな名前で呼ばせているみたいだけど?」
「私から呼ばせた記憶はありません。勝手に呼び始め、あまりに多いので訂正ができない状況です」
私の言葉を聞いたアンバーは、こめかみを揉みほぐす仕草をしてからこう言った。
「困るんだよねぇ。君だって、聖女という意味を知らないわけじゃないだろう? ここだけで呼ばれるならまだいいけれど、ねぇ」
「それは私に呼ばれる度に否定しろと言う命令でしょうか? 先ほども言いましたが、数が多すぎて対処しきれません。私の預かり知らぬところで呼ぶ人たちもいます」
「とにかくさ。僕の立場も考えてよ。困るだろう? 誰とは言わないが、ある人の耳にこのことが入ったりしたら」
「分かりました。善処します」
ある人、というのはルチル王子のことだろう。
アンバーは見かけによらず情報通のようだ。
私がルチル王子に偽の聖女だと言われてここに送られてきていることを知っているらしい。
しかし、ここに来てからすでにある程度の日数が経つが、このアンバーという人物が何を考えているのかは分かりかねた。
いつも気だるそうに、やる気のなさを隠す素振りもせず、そのくせ笑顔を絶やさずに任に当たっている。
ただ、その発言や行動には何かを隠しているような不自然さが時折見え隠れしていた。
「ま、ということで、ひとつ頼むよ。それで――」
「大変です‼ 魔獣の群れが‼ この陣営に迫ってきています‼」
アンバーの言葉を遮るように、一人の兵士が司令室であるアンバーの部屋に入って急を告げた。
それを合図にするかのように、戦闘が始まったことが分かる騒音が外から聞こえてきた。
戦闘の音が聞こえた瞬間、私は治療場へと走り出していた。
今外で戦っている兵士たちが負傷しても、すぐに治療に当たれるようにするためだ。
「聖女様! 大変です‼ 外に魔獣が‼」
「デイジー! 状況は⁉」
治療場に着くと、すでに怪我をした兵士たちが運ばれていた。
デイジーを始め、総勢で治癒に当たっているが、何しろ数が多い。
やっと安定的に治療ができるようになってきたと思っていたけれど、ここは戦場。
そう簡単にはいかないようだ。
「毒を受けた者は私のところに運んでちょうだい! デイジー! こっちへ来て! 簡単な毒についてはあなたに任せるわよ‼」
「はい‼」
どうやら思ったよりも魔獣の勢いは激しいようだ。
どんどん負傷兵が運ばれてくる。
中には少し前に回復したばかりの兵士の姿もあった。
みな、牙や爪などで四肢を切り裂かれた状態で運ばれてきて、痛々しい。
運んできた兵士もすぐに戦闘に戻り、そして怪我をして、別の兵士に運ばれるような状況だ。
運が悪いことに、この第五衛生兵部隊に運ばれる兵士のほとんどは、身分もそして戦闘能力も低い者ばかりだった。
「聖女様! このままでは間に合いません! こんなに次から次へと運ばれるだなんて!」
「諦めてはダメよ! 兵士たちが頑張っているの! それを助ける私たちが頑張らないでどうするの‼」
言葉はかけるものの、私自身いつ終わるか分からない戦闘と、負傷兵の多さにどうすればいいか分からなくなっていた。
今では同じ兵士が何度も運ばれ、傷を癒してはすぐ戦闘に戻って行くような有様だ。
衛生兵たちも、魔力枯渇と魔法酷使の症状が出始めている。
このまま今の状態が続けば、そのうち一人、また一人と衛生兵が先に倒れて行くだろう。
「なんてこと! こんな時に、魔石があれば‼」
魔石とは魔法の触媒となる石の総称で、魔鉱石を精製して作られる。
砕いて身体に取り込めば魔力の回復、魔法を唱える際にうまく使えば、普段使うことのできないような上級の魔法を使うことができる、まさに魔法の石だ。
「魔石……ですか? 昔、全ての部隊にそれなりの量の魔石を支給されたと聞いたことがありますが……」
「それは本当⁉」
私の泣き言を聞いたデイジーが一縷の望みがあることを告げる。
もしなければどのみち間に合わないのだ。
私はデイジーに私の分の治療も一時的に任せて、再び司令室であるアンバーの部屋に急いだ。
「失礼します‼」
「なんだ。君か。申し訳ないけど今は忙しいんだ。君も知っているだろう? 魔獣がこの陣営を襲ってきたんだよ。まったく、嫌になるよ」
「分かっています‼ 部隊長‼ 軍から魔石が支給されたとは本当ですか⁉」
「うん? よく知ってるね。ああ、本当だよ。ただ……それを当てにしようたって無駄さ」
アンバーは部屋の棚に置いてある錠のついた箱に目線を送った後、顔を横に振った。
私は急いで箱の前に行き開けようとするが、鍵がかかったままで開くことができなかった。
「すぐにこの箱を開け、魔石を使わせてください。でなれけば……大勢死にます‼」
「無駄と言っただろう。まったく軍ってのは嫌になるよ。その箱の鍵だけどね。開けるためには長官に報告書を上げて、承認を得ないといけない。そんなのしている間に数日経ってしまうさ」
「そんなバカなことが‼ 鍵は! 鍵はお持ちじゃないんですか⁉」
「無いんだよ。承認状と一緒に鍵が送られてくるって手筈さ。だから、諦めて持ち場へ戻りたまえ。ここは君のいる場所じゃ無いだろう?」
どうやらこれ以上話しても無駄なようだ。
しかし、ここにある魔石がどれだけあるか分からないけれど、手に入れなければ確実に治療場は瓦解する。
私は拳を作り、そこに魔力を込めた。
右手が淡く光り輝くのを確認した後、私は大きく頭上へ拳を振り上げた。
「おい……何をする気――」
アンバーの言葉など無視して、私は拳を錠のついた箱に勢いよく振り下ろす。
箱の蓋と錠は激しく歪み、すでに中の物を守るという役目を担えなくなっていた。
「開くじゃないですか。それでは、この魔石もらっていきますね」
「たまげたね。まさかそんなことするなんて。正気かい?」
「戦場で正気でいる者など居るはずがありません。居るとしたら、それは死人だけです」
「あっはっは! 君は僕が思っていた女性とは随分違うようだね。分かったよ。その魔石は君に全部あげよう。どうせ奴ら箱のことなんて確認しないんだ」
アンバーは白が多く混じった黒色の短髪を額から後に撫であげ、濃褐色の瞳を私に向けそう言った。
私は何が面白いのか分からず、しかし時間がないと、急いで箱から魔石を取り出して行く。
すると、アンバーが箱の方に近付き手を伸ばして来た。
まさか結局阻止されるのかと思い、私は身構える。
「ああ。そんな風に警戒しないで。持っていっていいって言ったのは本当さ。ただね、一つだけでいいから、僕にくれないかな? それ」
「部隊長が魔石など何に使うんですか?」
「いいから、いいから。ほら。急がないと手遅れになる子が出てくるかもしれないよ?」
「分かりました。それでは失礼します」
私は一礼をすると、魔石を落とさぬように気を付けながら、治療場へ急ぐ。
もともと体力がある方ではないので、息が上がる。
それでも少しでも早く治療に戻るために、息を弾ませながら懸命に両足を動かした。
「戻ったわ‼ 状況は⁉」
「聖女様! もう無理です‼ みんな、限界です‼」
見るとすでに衛生兵の何人かが、魔力枯渇により倒れていた。
その間にも負傷した兵は多く運ばれており、すでに全員が横になることができないほど、負傷兵で埋め尽くされていた。
「みんな! 聞いて! ここに魔石があるわ。魔力が尽きた者はこれを砕いて飲んで! 少量でいいわ。重傷者は優先して私の方に運んで‼」
「分かりました‼」
私の指示に、まだ動ける衛生兵たちは動き始める。
すでに倒れた人には、別の人が砕いて飲ませてあげていた。
「凄い……魔力が、魔力が満ちてきます」
「それが魔石の効果よ。さぁ! もうひと踏ん張りよ‼」
私も魔石を一つ砕きその全てを飲み干した。
身体中に魔力が満ちていくのが感じられる。
そして次々と私の元に運ばれてくる重傷者に、上級の回復魔法をかけては、その傷を癒していった。
どのくらいの人数を治したかすでに分からなくなっていたが、私はふと変化に気が付いた。
「負傷者が、運ばれて来なくなった?」
私の呟きにそれを聞き取った数人が顔を上げる。
すると、入口からどこにも怪我を負っていない兵士が一人飛び込んできた。
「みなさん! 無事に魔獣は殲滅しました‼ そして‼ あれだけ激しい戦闘だったにも関わらず、奇跡的に死者はゼロです‼」
その報告に、私も含め、その場にいる全ての人間が歓声を上げた。
最後の一人の治療を終えた後、私はアンバーに報告するため司令室に向かった。
魔石の件は謝罪するべきか、それとも感謝すべきか迷いながら。
「失礼します」
「誰だ⁉ 誰も入れるなと厳命したはずだ‼」
私が司令室に入った途端、普段聞くことの無い、アンバーの荒げた声が聞こえた。
しかしその声は苦しみに耐えるようで、呼吸も速い。
「ああ……君か……すまんね。なんの用かな?」
「部隊長、どうされました? 顔色が優れないようですが。治療が必要なら――」
「無駄だよ。いいから出ていってくれ。さぁ! 今すぐに‼」
「……分かりました。失礼します」
珍しいアンバーの姿に若干戸惑い感じながらも、私は司令室を後にする。
治療場に行く途中、すれ違った兵士たちの言葉が自然と耳に入ってきた。
「それにしても凄かったな。部隊長の攻撃魔法。あんだけ苦戦した魔獣たちを一掃だぜ?」
「ほんと、凄かったよなぁ。それにしても、なんであんな強い人が、第五衛生兵部隊の部隊長なんかやってるんだ?」
五つある衛生兵部隊でも、この部隊は格でいえば一番下だ。
そもそもそんな攻撃魔法を使えるのならば、兵士が言う通り、攻撃部隊の、しかも上位の部隊に所属されていてもおかしくない。
「なんだ? 知らなかったのか? アンバー部隊長は以前は第二攻撃部隊の部隊長を務めていたんだぜ。なんでもその時戦った魔族から受けた傷が原因で前線から離れたんだとか」
「へー。知らなかったな。第二攻撃だなんて、エリート部隊じゃないか! そんな部隊の部隊長でも、満足に傷も治してもらえないんだなぁ」
「詳しくは知らないけどな。噂だよ。噂。怪我は治ったけど、呪いを受けてそれを取れなかったとか」
「呪いってあのずっと痛みを受けるってやつか? そりゃ嘘だろ。アンバー部隊長、いつもヘラヘラしてるじゃないか」
私はその言葉を聞いた瞬間、踵を返し、アンバーの部屋に戻った。
今の話と、アンバーの様子を見れば見当がつく。
そしてそれはできるだけ早くに対処しなければならない。
立ち入り禁止など聞いている場合ではなかった。
「失礼します‼」
「しつこいな……また君か。さっき出て行けと言ったはずだがね。なにか忘れ物でもしたかい?」
部屋に入ると、アンバーは既に立っているのが辛くなったようで、机に突っ伏すような格好でいた。
私が入ってきたのを確認しても動く様子はない。
「なんだい? 見ての通り、今動くのすらおっくうなんだ。忘れ物を見つけたら、今度こそさっさと出ていってくれ」
「ええ。大変な忘れ物をしていました。部隊長。あなた呪いに侵されていますね? しかも上位のものを含めて複数」
私の指摘にアンバーの眉が吊り上がる。
しかし、すでに言い返す気力と体力すら残っていないようだ。
「正直なところ、驚いています。じっとしているだけでも苦痛にさいなまれているはずです。それを他人に押し隠す努力、並大抵のものとは思えません」
私の言葉を聞いているのか分からないが、アンバーは一度だけゆっくりと瞬きをした。
「なぜ相談していただけなかったのですか? 就任直後に呪いを解く魔法を私が使えることはご存知だったはずです」
「無駄だよ……【痛み】を解けるくらいじゃ……もう何度も試したさ……高位の回復魔法の使い手に頼んでね……」
絞り出すような声でアンバーは答える。
おそらく今までは自分の魔力を総動員して、どうにか呪いを押さえ込んでいたに違いない。
それができたことも驚異だけれど、先ほどの戦闘で魔獣を一掃したという攻撃魔法。
それも驚異的な威力だったのだろう。
自身の魔力だけでは足りず、魔石を触媒にして使用した魔法。
魔力が尽きた今のアンバーは、無防備な身体で、恐ろしい呪いに襲われているのだ。
常人なら痛みで発狂したり、恐怖で自傷したり、多くの者は自分で命を絶つ選択をすると聞く。
それにも関わらず私になんとか弱みを見せぬよう、気丈に振舞おうとするアンバーの精神の強さに感服する。
「今すぐ患部を見せてください。まだ魔石も残っています。今やらなければ、最悪精神がやられますよ?」
「無駄だと……」
ここで押し問答をするつもりは無い。
私はアンバーが抵抗できないことを利用して、無理やり着ている軍服を脱がせた。
「これは……」
アンバーは私の二倍以上の年齢だろうか。
それにも関わらず、引き締まり無駄がない兵士の肉体を保っている。
その強靭な肉体を埋め尽くすかのように、呪いの紋様が描かれていた。
種類も複数あり、【痛み】、【恐怖】などはまだ優しい。
「まさか……【崩壊】まで……」
「それを知っているだけでも……大したもんだ……でも、これで無駄だということが……分かっただろ?」
【崩壊】は上位の魔族が使うとされる呪いで、それをかけられた者は、内部から腐敗し死に至る。
そして、呪いの厄介なところは、最も強い呪いを解ける解呪の魔法を使わなければ、初級の呪いすら解呪できない事だった。
「遅かったかもしれませんが、今気付けて良かった。少し時間はかかります。その格好では苦しいでしょう。横になってください」
「何を……する気だ……?」
「もちろん治療するんです! それ以外にありますか?」
私はアンバーを床に寝かせると、懐から魔石の最も質のいい物を選び取り出す。
それともうひとつ魔石を取ると、小さい方は砕いて飲み干した。
先ほどの治療で消耗した魔力が再び満たされる。
そして質のいい魔石を手に持つと、自分の使える最上級の解呪の魔法を唱え始めた。
私の両手からアンバーの全身に眩い光が伝わる。
その光に溶けるように、アンバーの身体に描かれていた紋様が消えていく。
やがて、光が収まる頃には、全身を埋め尽くしていた呪いの紋様は、跡形もなく綺麗に消え失せていた。
呪いから解放されたアンバーは瞬きを繰り返し私を見つめている。
「さぁ、あともうひと踏ん張りですよ。呪いは消えました。後は腐敗した内部を治療しましょう」
そして今度は治癒の魔法を唱える。
これでアンバーの身体は、健康的でどこにも問題のない肉体になったと言えるだろう。
「まだ信じられないな……」
呪いも、呪いによる体の損傷も回復したアンバーが、自分の身体を触りながら感慨深げに呟く。
今は以前からの貼り付いたような笑みは消え失せ、より自然な表情を見せる。
おそらく呪いの苦しみを他人に悟られまいと、必死で隠していたゆえの笑みだったのだろう。
今のアンバーの顔付きの方が、個人的には好感が持てる。
「とにかくありがとう。礼を言うよ」
「いえ。当然のことをしたまでです。負傷兵を癒すのが私たち衛生兵の役目ですから」
「ふむ。それはそうとフローラ嬢。君に言っておかなくちゃいけないことがある」
「なんでしょうか?」
アンバーは以前の笑みを作る。
私は嫌な予感がした。
「君はゴール侯爵令嬢かもしれないが、今は軍属。私の部下だ。上官である私に二度背いたね。一度目の魔石は許すと言った。しかし、次はそうはいかない」
「確かに上官の命令は絶対だとは心得ています。その点については弁明しません」
「うん。僕は出て行けと再三言った。しかし君は命令を聞くどころか、それに背き私の呪いを解いた。きれいさっぱりだ」
どうも様子がおかしい。
命令違反の厳罰を申し渡される覚悟をしていたのだが、アンバーはやけに嬉しそうだ。
「明らかな命令違反だ。よって……僕も君を聖女様とこれから呼ぶことにしよう」
「な⁉ 何を言っているのですか‼」
アンバーはいたずらっぽく笑う。
私はアンバーの意図が分からず、困惑していた。
「だって。僕の呪いは誰も治せなかったんだよ。前聖女様以外ね。残念ながら僕がこの呪いを受けた時には、すでに彼女は亡くなっていた」
「それと、部隊長が私を聖女と呼ぶのと何の関係が?」
「だからさ。君は誰がなんと言おうと、僕にとっての聖女様なのさ。誰がなんと言おうとね。王都でふんぞり返ってるだけの青二才の顔色を疑うのはもうやめだ」
「しかし、それではご自身の立場が危ういのでは?」
聖女と呼ばれることについての問題は、つい先ほどアンバー本人から指摘されたことだ。
私が聖女と呼ばれて、マリーゴールドも、そしてルチル王子も面白くは思わないだろう。
「大丈夫だよ。呪いが無くなった今、実力で僕をどうこうできる相手なんて限られている。まぁ、それに。前線の些細なことなんて彼は気にしていないさ。気にしていたら少しはここの環境だって良くなってるはずだ」
よほど呪いから解放されたことが嬉しかったのだろう。
アンバーは両手を広げ、少年のように目を輝かせている。
聖女と呼ばれることについては、元々私はそこまで気にしていなかった。
今更部隊長からもそう呼ばれても些細なことだろう。
「分かりました。とりあえず、治癒に成功できて良かったです。それでは、失礼します」
「ああ。ありがとう。聖女様。これからもよろしく頼むよ。僕は君への援助は惜しまないつもりだ。何かあればなんでも言ってくれ」
一礼して、退出しようとした時、窓を叩く音が聞こえた。
木の板がはめられただけの窓のため、音の原因は分からない。
興味が湧いて見ていると、アンバーは警戒することも無く窓を開けた。
すると、全身真っ黒な鳥が中に入ってきて、アンバーの差し出した腕に器用にとまる。
「なんですか? それは」
「ん? ああ。これは僕の使い魔だよ。これで色々と情報を個人的に集めてるんだ。君のことも、こいつを使って調べたのさ」
そう言いながらにこやかな顔で、使い魔だという黒い鳥のクチバシを耳の方へ近付ける。
使い魔というのは話を聞いたことはあるけれど、実際に見るのは初めてだ。
上位の魔導士などが使役する動物で、ある程度自分の意思通りに動かすことができるらしい。
動物の種類は様々で、空を飛べる点から鳥や、街中では狭いところにも入れるという理由から、猫やネズミなどが使われることが多いと聞く。
私はついつい興味本位で、そのやりとりを見入ってしまった。
アンバーにやり方を習えば、私にも使い魔を持つことができるだろうか。
「うん? なんだって⁉」
「どうしました?」
驚いた声をあげるアンバーに、自然と私は問いかけてしまった。
ただ、出て行けと言われてはいないから、居ても問題はなかったのだろう。
「大変なことが起きたみたいだよ。さっきの魔獣の群れ、襲われたのはここだけじゃないようだ」
「なんですって⁉ それで! 被害は⁉」
「まぁ、慌てるな。順を追って話すから。まず、ここから西に向かった方角に、魔王討伐軍の本営があるのは知っているかい?」
「ええ。各部隊を取りまとめる長官などが居ると聞きます。まさか⁉ そこが襲われたのですか?」
アンバーは一度頷く。
「そのまさかさ。しかも、間が悪い、と言うのがいいのか、それを狙ってなのかは知らないけど。その場に軍の総司令官に当たる、ルチル王子がいたらしい。しかも新しい『聖女様』を連れてね」
「そんな! ルチル王子が戦場に出るだなんて聞いたことがありません‼」
「ああ。僕も初めてさ。総司令官だって名ばかりだしね。何を思ったか知らないけれど、とにかくいたらしい。そりゃ警護も厳重さ。ここよりも強力で大勢の魔獣が押し寄せたらしいけど、なんとか撃退したらしい」
「そうですか。それは良かった」
アンバーの言葉に胸を撫で下ろす。
ルチル王子が、というわけではないが、本営が落ちれば魔王との戦が立ち行かなくなるのは必至だからだ。
被害の程は分からないけれど、最小限ですんだことを願うばかりだ。
ほっとしている私に向かって、アンバーは神妙な顔を向ける。
その表情が、私の心をざわつかせた。
「まさか……それで終わりじゃないんですか?」
「ああ。続きがある。魔獣は撃退した。ところがだ、一体の魔族が後から現れたらしい。しかもルチル王子の目の前に」
私は無意識に唾を飲み込んだ。
「まさかの僕が最後に戦った同じ魔族だったようだよ。そして、王子に呪いをかけた」
「まさか⁉ その呪いは――」
「そう。【崩壊】だよ」
「どうするんだい? 今から本営に向かうなら、許可をしよう。君なら治せるのだろう?」
アンバーはそんなことを言い出した。
しかし、先ほどの話が本当だとしても、私の出る幕などないだろう。
「いいえ。マリーゴールドが一緒なのですよね。ルチル王子が承認した聖女がその場にいるというのに、他の者に治療させるとは思えません」
「王族の専属の『聖女様』、か。まぁ、確かにそうだね。しかし、僕はよくその『聖女様』を知らないけれど、君と同じくらい凄いのかい?」
聞かれて私はマリーゴールドのことを思い出す。
彼女は要領の良い子だった。もちろん悪い意味で。
彼女は努力という言葉が嫌いだった。
そんな彼女が上位の呪いを解くほどの解呪の魔法を使えるとは到底思えない。
私は一度だけ首を横に振る。
それを見たアンバーは深いため息をつく。
「まったく。ルチル王子には困ったもんだね。知ってるかい? 現国王からルチル王子に指揮権が移ってから、前線は徐々に後退してるのさ。一部を除いてね。ほとんど、彼の指揮があまりにも的を射ていないせいだって噂だよ」
「そうなんですね。ちなみに、前線を押し進めてる、その一部というのは?」
「気になるかい? 魔王討伐軍一の精鋭部隊、攻撃第一部隊さ。部隊長は僕の同期だけど、まぁ戦うために生まれたようなやつだね」
アンバーは旧友を思い懐かしんだのか、少し微笑む。
「彼女がさ、ルチル王子の言う無理難題を全て成し遂げちゃうから。困るんだよね。彼女の部隊だけ規格外なんだから。他の部隊に同じことができるはずないんだ」
「彼女? 第一部隊の部隊長は女性なんですか?」
「知らなかった? 有名なんだけどな。ダリアって言うんだ。ダリア・パルフェ。名前の通り、完璧ってやつだ」
「知りませんでした。覚えておきます」
その後、私はアンバーと二言三言話し、司令室を後にした。
治療場には戻らず、私は自室へと向かっていた。
自室に戻ると、飾ってあるリラの花が目に付く。
今も濃い紫の花を咲かせている。
私は自分の荷物から手紙に必要な一式を取り出すと、ベリル王子に向けて手紙を書き始めた。
内容はルチル王子の呪いについてだ。
アンバーの使い魔の件は伏せておくとして、この手紙はベリル王子以外に渡ることがないはずだから、ひとまずは呪いについて触れても良いだろう。
私は、ルチル王子がかかった呪いを魔石の力を借りたものの解けたことを書き、必要があれば治癒をすることを書き留めた。
恐らくルチル王子に伝えても一蹴されてお終いだろうが、ベリル王子はその点思慮深い。
私に対してどう言う感情を持っているかは知らないけれど、ルチル王子の呪いを解けるのが私だけだと分かれば、きっと申し出を断りはしないだろう。
正直なところ、私自身はルチル王子にいい印象は持っていない。
傲慢で、短絡的で、その上自信家。
下手に権力があるため、誰もとがめるものがいなかったのが原因でもあるかもしれないけれど、恐らく持って生まれたものだろう。
しかし、性格の良し悪しと、助けるか否かは関係がない。
命に貴賤はないが、身分が高いから助けなくて良いと言うわけでもないのだ。
助けられるものなら助けたい。
私のわがままかもしれないけれど、助けられるのに見て見ぬ振りをすることは出来なかった。
ベリル王子に定期的に教えるよう言われているリラの花の色と、ルチル王子の呪いについて書き終わると、私は専用の封をして、兵士に届けてもらうよう願った。
今までベリル王子から返信が来たのは一度だけ。
いつ来るかも分からない返信を、私は根気よく待つつもりだった。
しかし、返信は思いの外早く届いた。
私は急いでその返信の封を切り、中身を確認する。
するとこんなことが書かれていた。
『フローラへ。
手紙ありがとう。兄の容態についてすでに知っていることに驚いている。書いていないということは、聞いても理由を教えてくれはしないだろうから聞かないことにする。
俺は君に治してもらうよう兄にすぐに申し出たが、断られてしまった――』
こんな出だしで書かれていた手紙の中身を見て私は訝しがる。
何故なら、続く言葉で、ルチル王子の呪いはマリーゴールドによって解かれたと書いてあったからだ。
ベリル王子の手紙の内容を要約するとこういうことだった。
呪いを受けた時、マリーゴールドは十分な魔石がその場にあったにも関わらず、解呪出来なかった。
その間、ルチル王子は痛みなどから失神と覚醒を繰り返し、覚醒している間は発狂したように叫び続けていたらしい。
見る者にさえ恐怖を与える様相だったらしい。
その後、治癒に専念するためとマリーゴールドはルチル王子を隔離し、必要最低限の小間使い以外を近づかせなかったらしい。
しかし、治癒は難航したようで、毎日その一角から、ルチル王子の叫び声が途切れ途切れに聞こえてくるのだとか。
そこで、私の手紙を受け取ったベリル王子が、私にルチル王子の解呪をさせようと申し出た。
しかしそれが断られた。
断ったのはルチル王子ではなく、マリーゴールドだという。
そしてその後直ぐに、ルチル王子の解呪に成功したとマリーゴールドが言い出したというのだ。
不思議に思ったベリル王子は、面会を申し出たがこれも断られたのだとか。
確かに離れても聞こえてくるルチル王子の絶叫はその日から聞こえなくなったため、解呪が成功したのだろうという話になっているという。
「どうも釈然としないけれど、私がどうこうできる話でもないわね。助かったのなら良かったと思うべきね」
そう思いながら、私はベリル王子に返信と、リラの花の色を書いた手紙を再度送った。
リラの花は以前よりも更に濃い紫色の花を咲かせていた。