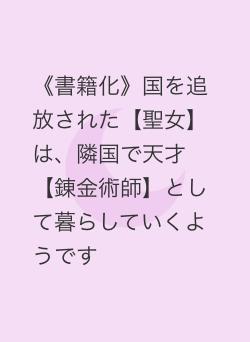私の声を待たずに、ロベリアは辺りを見渡し、はっと息を飲んだ。
視線の先にはたった今治療を受けている一人の青年がいる。
「兄さん! アイオラ兄さん‼」
「その声は……ロベリアかい?」
ロベリアが走り寄り声をかけるが、アイオラはロベリアが見えていないようだ。
よく見ると、ロベリアに向けた目は光を失っていた。
「兄さん! まさか。見えないの⁉ ああ、神様‼」
「大丈夫。心配しないで。きっとここの人たちが治してくれるさ」
ロベリアとよく似た顔をしたアイオラが、微笑みながらそう答えた。
しかし、無理をして笑っているのがはっきりと分かる。
「部隊長! 損傷した目を再生させたはずなのですが、上手くいきません!」
「なんですって? 状況を出来るだけ詳しく説明して」
アイオラの腕に巻かれている布の色は黄色。
再生が必要な傷を受けた者に付けられる色で、治療に当たっている者のリボンタイを見れば、問題ないはずだ。
「それが……間違いなく治療し、傷も癒えているはずなのですが……」
説明によれば、アイオラは両目に大きな傷を負って運ばれて来たらしい。
それ以外の傷も多くあったが、それは後回しにして一番重度な目の治療を最初に行った。
これまでにも目の再生を経験したことはあるらしく、特に心配もせずに回復魔法を使い、無事に目は再生した。
その後身体の傷を治療している間に異変に気付いたという。
『衛生兵さん。僕の目は、治ったのですか? 何も見えないのですが』
アイオラがそんなことを言い出したのだという。
慌てて確認したが、問題なく目は再生し、傷も跡形もなく消えていた。
それでも視力を取り戻さないアイオラに、彼女は再度回復魔法をかけてみた。
しかし結果は変わらず、一向に視力を取り戻す様子がないアイオラに困っていたところ、ロベリアが来たのだとか。
「そんな! 部隊長! お願いです‼ 兄を! アイオラ兄さんを治してください‼」
「落ち着いて。あなたに言われなくてもそのつもりよ。アイオラというのね。ちょっとその目をよく見せてもらうわよ」
確かに治療に当たった衛生兵の言う通り、外から見た限りは問題なく治療されているように見える。
私は試しに、魔力で目の内部に問題がないかを確認してみることにした。
純粋な魔力の流れ方は、物によって様々で、片方の手から放出させた魔力をもう片方の手で受け取るように流すと、間に挟んだ物の様子が内部まで見られるのだ。
私は右手でアイオラの両眼を押さえ、後頭部に左手を当て、魔力を流した。
魔力の強さをいくつか変え、流れやすさで内部を立体的に確認していく。
すると、アイオラの目に重大な問題があることが分かった。
「こんなことが……アイオラの目の裏側辺りに、小さな魔獣が潜んでいるわ。恐らくアイオラの目が見えないのは、その魔獣のせいね……」
「魔獣が⁉ ああ、兄さん‼ どうすれば‼」
魔獣を駆除しなければ、アイオラの視力が戻ることはないだろう。
しかし問題はその場所だった。
これがもし腕や足ならば、切除して回復魔法で再生すると言うこともできる。
もちろん目も治療できるのだが、よほどうまくやらなければ、治療する前にアイオラを殺しかねない。
生きていれば救えるが、死んでしまった者を生き返らすことは、どんな回復魔法を以てしても不可能だ。
しかし、思い悩んでいる暇もそんなにないだろう。
目の裏に潜んでいる魔獣が、そのまま大人しくしている保証はない。
もしかしたら、魔獣自身がアイオラを傷付け、死に至らしめてしまう可能性も高い。
「魔獣だなんて……ああ、私に魔獣を倒す力があったらどんなに良かったか。回復魔法すらろくに使うことのできない私は肝心な時に役に立てない!」
ロベリアは私の話を聞いて再び嘆き始めた。
しかし、その一言が、私にある可能性を示唆した。
「魔獣を倒す力。攻撃魔法。そうよ。もし、そんな力が使えれば……」
ロベリアが回復魔法を使えない理由は、魔力を練る方法が間違っているからだ。
しかし、それはある可能性を示していた。
確かに女性は回復魔法を、男性は攻撃魔法を扱うことに長けると言われている。
私もなんの疑問を持たずに、回復魔法だけに専念してきた。
だけどロベリアが実際に見せてくれたように、女性でも攻撃魔法用の魔力を練ることは可能なのだ。
私は頭の中で、ロベリアの魔力を感じた時のことを思い出す。
そして、学んだ知識を総動員して、腹部の下側で魔力を練ることを試してみた。
いつもと違う感覚に、強いもどかしさを感じながらも、頑張ってみたができない。
やはりロベリアが回復魔法に必要な魔力を練ることが未だにできないように、私も一朝一夕でできることではないらしい。
諦めかけた時、目の前のアイオラが不思議そうな顔をしながら声をかけてきた。
「衛生兵さんは魔力を練ろうとしているのですか? 何故だか知りませんが、酷く苦戦しているように思いますが」
「あなた、分かるの?」
「いい方法を知っています。妹も、ロベリアもこれで魔力を練ることができるようになりました。手を。私の両手をそれぞれ握ってください」
そう言ってアイオラは、自分の手を前に差し出す。
私は一瞬戸惑ったが、アイオラの手を握った。
ちょうど二人の腕で輪を作るような形になった私は、アイオラが何をするのか見逃すことの無いように、全神経を集中する。
ロベリアが学んだ方法、つまり、攻撃魔法に必要な魔力を練る方法をアイオラが教えてくれる可能性にかけた。
「それじゃあ、行きますよ? 力を抜いて。楽にしてください。徐々に暖かくなる場所がありますから、そこを意識するんです」
「暖かくなる場所……」
アイオラが言った途端、繋いだ右手を通じて、アイオラの魔力の波動が流れ込んで来るのを感じた。
それは私の身体を通り、やがて左手からアイオラへと戻っていく。
その魔力の波動によって、私は腹部が温かくなるのを徐々に感じた。
本で学んだ、攻撃魔法にための魔力を練るための器官があると言われる場所だった。
「すごいわ! アイオラ!! ありがとう! もう大丈夫。あとは一人でやるわね!!」
私は先ほど熱を帯びた場所に意識を集中し、魔力を練り始めた。
やがて普段とは異なる波動を持つ魔力を手の平に集めることに成功した。
問題はこの新しい魔力を上手く扱えるかどうかだ。
上手くいった喜びを押し殺し、真面目な口調でアイオラに話しかける。
「アイオラ。はっきりと言うわ。よく聞いてちょうだい。今あなたの頭の中には魔獣が潜んでいる。その魔獣は放っておけばやがてあなたを内部から殺すかもしれない」
アイオラはその見えない視線を私に向け、じっと聞いていた。
隣ではロベリアがすすり泣きをしている。
「回復魔法は魔獣を倒す力はない。もし物理的に排除しようとしても場所が悪い。最悪その行動があなたを死なせてしまうかもしれない」
「つまり、僕が助かる手段はない。と言うことですね」
「いいえ。可能性はあるわ。でも、今からやることは私も初めての試み。上手くいく保証も失敗した時にどうなるかも分からない。それでも、私はあなたを救いたいと思っている。受け入れる覚悟はあるかしら」
「どうせ死ぬかもしれないのなら。何にだってすがってみたい。僕は死にたくない。ロベリアを、妹を悲しませたくないんです」
アイオラははっきりと強い口調でそう答えた。
視線の先にはたった今治療を受けている一人の青年がいる。
「兄さん! アイオラ兄さん‼」
「その声は……ロベリアかい?」
ロベリアが走り寄り声をかけるが、アイオラはロベリアが見えていないようだ。
よく見ると、ロベリアに向けた目は光を失っていた。
「兄さん! まさか。見えないの⁉ ああ、神様‼」
「大丈夫。心配しないで。きっとここの人たちが治してくれるさ」
ロベリアとよく似た顔をしたアイオラが、微笑みながらそう答えた。
しかし、無理をして笑っているのがはっきりと分かる。
「部隊長! 損傷した目を再生させたはずなのですが、上手くいきません!」
「なんですって? 状況を出来るだけ詳しく説明して」
アイオラの腕に巻かれている布の色は黄色。
再生が必要な傷を受けた者に付けられる色で、治療に当たっている者のリボンタイを見れば、問題ないはずだ。
「それが……間違いなく治療し、傷も癒えているはずなのですが……」
説明によれば、アイオラは両目に大きな傷を負って運ばれて来たらしい。
それ以外の傷も多くあったが、それは後回しにして一番重度な目の治療を最初に行った。
これまでにも目の再生を経験したことはあるらしく、特に心配もせずに回復魔法を使い、無事に目は再生した。
その後身体の傷を治療している間に異変に気付いたという。
『衛生兵さん。僕の目は、治ったのですか? 何も見えないのですが』
アイオラがそんなことを言い出したのだという。
慌てて確認したが、問題なく目は再生し、傷も跡形もなく消えていた。
それでも視力を取り戻さないアイオラに、彼女は再度回復魔法をかけてみた。
しかし結果は変わらず、一向に視力を取り戻す様子がないアイオラに困っていたところ、ロベリアが来たのだとか。
「そんな! 部隊長! お願いです‼ 兄を! アイオラ兄さんを治してください‼」
「落ち着いて。あなたに言われなくてもそのつもりよ。アイオラというのね。ちょっとその目をよく見せてもらうわよ」
確かに治療に当たった衛生兵の言う通り、外から見た限りは問題なく治療されているように見える。
私は試しに、魔力で目の内部に問題がないかを確認してみることにした。
純粋な魔力の流れ方は、物によって様々で、片方の手から放出させた魔力をもう片方の手で受け取るように流すと、間に挟んだ物の様子が内部まで見られるのだ。
私は右手でアイオラの両眼を押さえ、後頭部に左手を当て、魔力を流した。
魔力の強さをいくつか変え、流れやすさで内部を立体的に確認していく。
すると、アイオラの目に重大な問題があることが分かった。
「こんなことが……アイオラの目の裏側辺りに、小さな魔獣が潜んでいるわ。恐らくアイオラの目が見えないのは、その魔獣のせいね……」
「魔獣が⁉ ああ、兄さん‼ どうすれば‼」
魔獣を駆除しなければ、アイオラの視力が戻ることはないだろう。
しかし問題はその場所だった。
これがもし腕や足ならば、切除して回復魔法で再生すると言うこともできる。
もちろん目も治療できるのだが、よほどうまくやらなければ、治療する前にアイオラを殺しかねない。
生きていれば救えるが、死んでしまった者を生き返らすことは、どんな回復魔法を以てしても不可能だ。
しかし、思い悩んでいる暇もそんなにないだろう。
目の裏に潜んでいる魔獣が、そのまま大人しくしている保証はない。
もしかしたら、魔獣自身がアイオラを傷付け、死に至らしめてしまう可能性も高い。
「魔獣だなんて……ああ、私に魔獣を倒す力があったらどんなに良かったか。回復魔法すらろくに使うことのできない私は肝心な時に役に立てない!」
ロベリアは私の話を聞いて再び嘆き始めた。
しかし、その一言が、私にある可能性を示唆した。
「魔獣を倒す力。攻撃魔法。そうよ。もし、そんな力が使えれば……」
ロベリアが回復魔法を使えない理由は、魔力を練る方法が間違っているからだ。
しかし、それはある可能性を示していた。
確かに女性は回復魔法を、男性は攻撃魔法を扱うことに長けると言われている。
私もなんの疑問を持たずに、回復魔法だけに専念してきた。
だけどロベリアが実際に見せてくれたように、女性でも攻撃魔法用の魔力を練ることは可能なのだ。
私は頭の中で、ロベリアの魔力を感じた時のことを思い出す。
そして、学んだ知識を総動員して、腹部の下側で魔力を練ることを試してみた。
いつもと違う感覚に、強いもどかしさを感じながらも、頑張ってみたができない。
やはりロベリアが回復魔法に必要な魔力を練ることが未だにできないように、私も一朝一夕でできることではないらしい。
諦めかけた時、目の前のアイオラが不思議そうな顔をしながら声をかけてきた。
「衛生兵さんは魔力を練ろうとしているのですか? 何故だか知りませんが、酷く苦戦しているように思いますが」
「あなた、分かるの?」
「いい方法を知っています。妹も、ロベリアもこれで魔力を練ることができるようになりました。手を。私の両手をそれぞれ握ってください」
そう言ってアイオラは、自分の手を前に差し出す。
私は一瞬戸惑ったが、アイオラの手を握った。
ちょうど二人の腕で輪を作るような形になった私は、アイオラが何をするのか見逃すことの無いように、全神経を集中する。
ロベリアが学んだ方法、つまり、攻撃魔法に必要な魔力を練る方法をアイオラが教えてくれる可能性にかけた。
「それじゃあ、行きますよ? 力を抜いて。楽にしてください。徐々に暖かくなる場所がありますから、そこを意識するんです」
「暖かくなる場所……」
アイオラが言った途端、繋いだ右手を通じて、アイオラの魔力の波動が流れ込んで来るのを感じた。
それは私の身体を通り、やがて左手からアイオラへと戻っていく。
その魔力の波動によって、私は腹部が温かくなるのを徐々に感じた。
本で学んだ、攻撃魔法にための魔力を練るための器官があると言われる場所だった。
「すごいわ! アイオラ!! ありがとう! もう大丈夫。あとは一人でやるわね!!」
私は先ほど熱を帯びた場所に意識を集中し、魔力を練り始めた。
やがて普段とは異なる波動を持つ魔力を手の平に集めることに成功した。
問題はこの新しい魔力を上手く扱えるかどうかだ。
上手くいった喜びを押し殺し、真面目な口調でアイオラに話しかける。
「アイオラ。はっきりと言うわ。よく聞いてちょうだい。今あなたの頭の中には魔獣が潜んでいる。その魔獣は放っておけばやがてあなたを内部から殺すかもしれない」
アイオラはその見えない視線を私に向け、じっと聞いていた。
隣ではロベリアがすすり泣きをしている。
「回復魔法は魔獣を倒す力はない。もし物理的に排除しようとしても場所が悪い。最悪その行動があなたを死なせてしまうかもしれない」
「つまり、僕が助かる手段はない。と言うことですね」
「いいえ。可能性はあるわ。でも、今からやることは私も初めての試み。上手くいく保証も失敗した時にどうなるかも分からない。それでも、私はあなたを救いたいと思っている。受け入れる覚悟はあるかしら」
「どうせ死ぬかもしれないのなら。何にだってすがってみたい。僕は死にたくない。ロベリアを、妹を悲しませたくないんです」
アイオラははっきりと強い口調でそう答えた。
アイオラの承諾を得て、私はおそらく人類で初めてとなる試みを行う。
頭の中に先ほど魔力で読み取った、アイオラの頭の中に居る魔獣の位置を思い浮かべる。
右手を正面から当て、後頭部に当てた左手に向け、攻撃魔法に適した魔力を流し込む。
問題は加減だ。
強過ぎればアイオラの頭の中を損傷し下手をすれば死に至らしめてしまう。
弱過ぎれば魔獣を殺すことが出来ずに、下手をすれば余計な刺激を魔獣に与えてしまうことになるかもしれない。
私は慣れない操作ながらも、まずは極力弱い力から、徐々にその出力を上げていく。
上げていく間に、初めはじっとしていたアイオラの顔が苦痛に歪む。
「これ以上は無理なようね」
私は慌てて出力を弱める。
そしてもう一度従来の魔力を練り直し、アイオラの頭の中を覗く。
魔獣は何事もなかったかのように、先ほどと同じ場所に居た。
刺激で動き出さなかっただけでも幸いと思うべきか。
「これじゃあダメだわ。魔獣を殺す前にアイオラの身体がまいってしまう。何かいい方法は無いかしら……」
「部隊長! 兄は、アイオラは助かるんでしょうか⁉」
悩んでる私に、堪えきれなくなったのか、ロベリアが話しかけてくる。
心配なのは分かる。
私だってどうにかして助けてやりたい。
だけど、この魔獣を倒すには私一人では無理なようだ。
「私一人では……? ロベリア‼ あなた、元の魔力の練り方は、まだ覚えているわね⁉」
「え……? 元の魔力ですか? 覚えているも何も、どんなに頑張ってもあれ以外出来なくて……」
「それでいいの。あなたに手伝って欲しいことがあるわ。あなたの力で、アイオラを救えるかもしれない!」
「本当ですか⁉ わたしに出来ることなら、なんでもやります‼ やらせてください‼」
私はロベリアに魔力を練るように伝える。
そして練った魔力を右手に集めさせた。
私の指示に従い、ロベリアは器用に魔力を操作する。
回復魔法に適した魔力ではないが、魔力操作については優秀なようだ。
魔力を溜めた右手を、こめかみの位置に当てさせ、反対側から挟むように左手を添えさせた。
私が手を当ててる位置から、ちょうど交差するようになっている。
「そこから決して手の位置を動かさないでね。ロベリア、右手から左手にかけて、アイオラの頭を通して、その魔力を移動させてみて。一度に流し過ぎないよう、注意してね」
「こうですか?」
アイオラに当てた私の手を通じて、ロベリアの魔力の波動が伝わってくる。
どうやら上手くいっているようだ。
「上手よ。そのまま少しずつ出力を上げていってちょうだい。待って! これ以上は危険。少しだけ出力を下げた状態で続けてちょうだい」
「分かりました……あの、これで本当に兄が助かるんですか?」
「確証はないわ。でも、やらなければ確実に助けられない。だったら、やるべきでしょう?」
そう言って、私も自分の右手から左手にかけて、魔力を流し込む。
少し扱いが慣れてきたのか、攻撃魔法に適した魔力でも、中の様子が分かるようになってきた。
私の時同様、ロベリア一人では、アイオラに危害を与えない程度の出力しか出せず、魔獣を倒すことは出来ない。
では二人なら?
交差するように魔力を当てて、その交わる点に魔獣が居たら?
二人分の魔力を受け、耐えられないのではないだろうか。
私は徐々に出力を上げていく。
すると、アイオラの中にいる魔獣に異変が生じ始めた。
明らかに苦しそうに、その小さな体を小刻みに震わせている。
アイオラもその様子が自分の体内で分かるのか、顔をしかめている。
そして、先ほど確認したアイオラの耐えられるぎりぎりの所まで出力を上げた時、魔獣は動くのを止めた。
念の為しばらく様子を見てみたが、どうやら完全に息絶えたようだ。
「ロベリア。もう止めて大丈夫よ。あなたのおかげで、無事にアイオラの中の魔獣は倒せたわ。お礼を言うわね。ありがとう」
「本当ですか⁉ ああ、兄さん‼ 良かった……本当に良かった‼ ありがとうございます‼ ありがとうございます‼」
「何がどうなったんです? 私は……本当に助かったのですか?」
「ええ。間違いなく、あなたの目の裏の魔獣は倒したわ。さぁ、もう一度目の治療をしましょう。今度こそ視界が取り戻せるはずよ」
私は再び本来の回復魔法のための魔力を練り始める。
そして、アイオラに回復魔法を唱えた。
白い光が私の手を伝わり、アイオラの両目の周りを包み込む。
やがて光が消えると、アイオラの目に光が点っていた。
「ああ……ああ。見えます。ああ! ロベリア! こうやって再びお前の顔を見ることが出来るなんて‼」
「兄さん‼ 本当に良かった‼」
「あなたのおかげで、これからの治療の新しい可能性が見いだせたわ。ありがとう」
「そんな! お礼を言うのは俺の方です‼ ありがとうございました‼」
アイオラは見えるようになった目で私をしっかり見つめ、そして深々と頭を下げた。
ロベリアも隣で兄と同じように頭を下げている。
「ふふ。兄妹というのはいいものね。ところで……ロベリアは回復魔法を使えるようにならないと、ここに残ることが出来ないというのは覚えているかしら?」
「あ……あの! もう少しだけ時間をください‼ なんとか、何とかしてみせますから‼」
「いいえ。きっと一人では無理よ。でもね。両方使うことが出来るようになった私のアドバイスを受けながらなら、直ぐにできるようになると思うわ。あなたの魔力操作の実力があればね」
「え⁉ お願いします‼ 私、頑張りますから‼」
もう一度下げたロベリアの頭を私は優しく撫でる。
「さぁ。頭を上げなさい。下げている暇があったら、訓練するわよ!」
「はい‼」
数日後、練る魔力の感覚の違いや、気を付ける所はどこかを私から教わったロベリアは、回復魔法に必要な魔力を練ることが出来るようになった。
こうして、第一期訓練生の全員が、無事に回復魔法を習得した。
頭の中に先ほど魔力で読み取った、アイオラの頭の中に居る魔獣の位置を思い浮かべる。
右手を正面から当て、後頭部に当てた左手に向け、攻撃魔法に適した魔力を流し込む。
問題は加減だ。
強過ぎればアイオラの頭の中を損傷し下手をすれば死に至らしめてしまう。
弱過ぎれば魔獣を殺すことが出来ずに、下手をすれば余計な刺激を魔獣に与えてしまうことになるかもしれない。
私は慣れない操作ながらも、まずは極力弱い力から、徐々にその出力を上げていく。
上げていく間に、初めはじっとしていたアイオラの顔が苦痛に歪む。
「これ以上は無理なようね」
私は慌てて出力を弱める。
そしてもう一度従来の魔力を練り直し、アイオラの頭の中を覗く。
魔獣は何事もなかったかのように、先ほどと同じ場所に居た。
刺激で動き出さなかっただけでも幸いと思うべきか。
「これじゃあダメだわ。魔獣を殺す前にアイオラの身体がまいってしまう。何かいい方法は無いかしら……」
「部隊長! 兄は、アイオラは助かるんでしょうか⁉」
悩んでる私に、堪えきれなくなったのか、ロベリアが話しかけてくる。
心配なのは分かる。
私だってどうにかして助けてやりたい。
だけど、この魔獣を倒すには私一人では無理なようだ。
「私一人では……? ロベリア‼ あなた、元の魔力の練り方は、まだ覚えているわね⁉」
「え……? 元の魔力ですか? 覚えているも何も、どんなに頑張ってもあれ以外出来なくて……」
「それでいいの。あなたに手伝って欲しいことがあるわ。あなたの力で、アイオラを救えるかもしれない!」
「本当ですか⁉ わたしに出来ることなら、なんでもやります‼ やらせてください‼」
私はロベリアに魔力を練るように伝える。
そして練った魔力を右手に集めさせた。
私の指示に従い、ロベリアは器用に魔力を操作する。
回復魔法に適した魔力ではないが、魔力操作については優秀なようだ。
魔力を溜めた右手を、こめかみの位置に当てさせ、反対側から挟むように左手を添えさせた。
私が手を当ててる位置から、ちょうど交差するようになっている。
「そこから決して手の位置を動かさないでね。ロベリア、右手から左手にかけて、アイオラの頭を通して、その魔力を移動させてみて。一度に流し過ぎないよう、注意してね」
「こうですか?」
アイオラに当てた私の手を通じて、ロベリアの魔力の波動が伝わってくる。
どうやら上手くいっているようだ。
「上手よ。そのまま少しずつ出力を上げていってちょうだい。待って! これ以上は危険。少しだけ出力を下げた状態で続けてちょうだい」
「分かりました……あの、これで本当に兄が助かるんですか?」
「確証はないわ。でも、やらなければ確実に助けられない。だったら、やるべきでしょう?」
そう言って、私も自分の右手から左手にかけて、魔力を流し込む。
少し扱いが慣れてきたのか、攻撃魔法に適した魔力でも、中の様子が分かるようになってきた。
私の時同様、ロベリア一人では、アイオラに危害を与えない程度の出力しか出せず、魔獣を倒すことは出来ない。
では二人なら?
交差するように魔力を当てて、その交わる点に魔獣が居たら?
二人分の魔力を受け、耐えられないのではないだろうか。
私は徐々に出力を上げていく。
すると、アイオラの中にいる魔獣に異変が生じ始めた。
明らかに苦しそうに、その小さな体を小刻みに震わせている。
アイオラもその様子が自分の体内で分かるのか、顔をしかめている。
そして、先ほど確認したアイオラの耐えられるぎりぎりの所まで出力を上げた時、魔獣は動くのを止めた。
念の為しばらく様子を見てみたが、どうやら完全に息絶えたようだ。
「ロベリア。もう止めて大丈夫よ。あなたのおかげで、無事にアイオラの中の魔獣は倒せたわ。お礼を言うわね。ありがとう」
「本当ですか⁉ ああ、兄さん‼ 良かった……本当に良かった‼ ありがとうございます‼ ありがとうございます‼」
「何がどうなったんです? 私は……本当に助かったのですか?」
「ええ。間違いなく、あなたの目の裏の魔獣は倒したわ。さぁ、もう一度目の治療をしましょう。今度こそ視界が取り戻せるはずよ」
私は再び本来の回復魔法のための魔力を練り始める。
そして、アイオラに回復魔法を唱えた。
白い光が私の手を伝わり、アイオラの両目の周りを包み込む。
やがて光が消えると、アイオラの目に光が点っていた。
「ああ……ああ。見えます。ああ! ロベリア! こうやって再びお前の顔を見ることが出来るなんて‼」
「兄さん‼ 本当に良かった‼」
「あなたのおかげで、これからの治療の新しい可能性が見いだせたわ。ありがとう」
「そんな! お礼を言うのは俺の方です‼ ありがとうございました‼」
アイオラは見えるようになった目で私をしっかり見つめ、そして深々と頭を下げた。
ロベリアも隣で兄と同じように頭を下げている。
「ふふ。兄妹というのはいいものね。ところで……ロベリアは回復魔法を使えるようにならないと、ここに残ることが出来ないというのは覚えているかしら?」
「あ……あの! もう少しだけ時間をください‼ なんとか、何とかしてみせますから‼」
「いいえ。きっと一人では無理よ。でもね。両方使うことが出来るようになった私のアドバイスを受けながらなら、直ぐにできるようになると思うわ。あなたの魔力操作の実力があればね」
「え⁉ お願いします‼ 私、頑張りますから‼」
もう一度下げたロベリアの頭を私は優しく撫でる。
「さぁ。頭を上げなさい。下げている暇があったら、訓練するわよ!」
「はい‼」
数日後、練る魔力の感覚の違いや、気を付ける所はどこかを私から教わったロベリアは、回復魔法に必要な魔力を練ることが出来るようになった。
こうして、第一期訓練生の全員が、無事に回復魔法を習得した。
ロベリアとアイオラの出来事からしばらく経ったある日のこと、私に一通の通達が届いた。
差出人はカルザー、衛生兵部隊の長官で現在部隊長を務める私の直属の上官にあたる。
内容は『可能な限り至急、本部に出向くこと』。
几帳面な字面の直筆で、そうとだけ書かれていた。
「長官に呼ばれるとは、何かあったかな?」
私は思考をめぐらせるが、特に思い当たることはなかった。
カルザーとは、部隊長に任命された時に挨拶で顔を見せたきりだ。
アンバーの話によると、カルザーはモスアゲート伯爵と懇意らしい。
つまり警戒すべき相手と言うわけだ。
しかし、表向き私はベリル王子とモスアゲート伯爵の確執など知らないことになっている。
変に警戒を見せる訳にもいかない。
「ちょうど第一期が無事全員回復魔法を習得したところだし、行くなら今かな」
ベリル王子が送ると言っていた第二期訓練生はもう少し先になるらしい。
もし訓練生が来たら忙しくなるだろうから、行くなら今がちょうどいい。
いずれにしろ上官が可能な限り至急と言っているのだから、今すぐ行くに越したことはないだろう。
私はそう思い、早速本部へ向かう支度をして、副隊長のデイジーに留守を頼んだ。
「行ってらっしゃいませ。聖女様。いくら護衛が付くとはいえ、道中はお気を付けくださいね」
「ええ。気を付けるわ。と言っても、私が出来ることはないけれど」
こうして私は、数名の護衛を引き連れ、本部のある陣営に向かった。
「第二衛生兵部隊、部隊長フローラ、長官の命令により、参上しました」
「ああ。よく来てくれたね。まぁ、固くならずに、ゆっくりしてくれたまえよ」
長い口ひげを生やした白髪の老人。
これが私は初めて会った時のカルザー長官の印象だった。
確かに見た目は間違いはない。
ただ、挨拶の時目を合わせてから、私はその認識を改めた。
歳は確かにとってはいるが、カルザーは老人などという生易しいものではない。
一癖も二癖もあるその本当の顔を、シワが刻まれた笑みを浮かべるその顔の裏に隠し持っていると確信した。
「それで……忙しいところ呼び寄せたのは他でもない。部隊のことで大きな変更があってね。流石に書面で伝えるだけでは悪いだろうと思い、ここへ呼んだというわけなんだ」
「大きな変更ですか? それはどのような?」
「うん。今、第二衛生兵部隊は魔王討伐部隊の前線から見たら、かなり後方に位置しているね?」
「そうですね。そもそも衛生兵部隊はどの部隊も、治療中の襲撃を危惧し、前線から離れた所にあると聞いていますが……」
カルザーは私の答えに嬉しそうな顔をして頷く。
この嬉しそうな、という表情が、私にとって吉なのか凶なのかは不明だ。
「その通り! だからね。前線で怪我をした兵士たちはそれぞれ階級や症状などで、各衛生兵部隊へ振り分けられるんだけど、今のままじゃ時間がかかる。そうだろう?」
「おっしゃる通りですね。移動中に怪我を悪化させる兵士も多いと聞きます」
「そこでだ! 君の部隊を、まるまる最前線に移動しようと思ってね。どうだい? 素敵な考えだろう?」
「最前線にですか⁉」
またもやカルザーは嬉しそうな顔をして頷いた。
どうやらカルザーの嬉しそうな顔は、私にとっては凶だったようだ。
確かに私も言った通り、負傷兵の移動時間の問題は気付いていた。
カルザーの言うように、最前線に衛生兵部隊があれば、より早く治療が受けられ、無用な苦しみは避けられる。
しかし逆を言うと、今まで以上に負傷兵がひっきりなしに治療場へ訪れることになるだろう。
第一期訓練生を指導していて分かったことだけれど、指導を行えば行うほど、自分の時間が少なくなっていく。
もし最前線に部隊を移動したら、本来の治療が忙しすぎて、指導を行う余裕は大きく制限されるだろう。
そうすれば、第二期訓練生を育てることは難しいだろう。
確かに未来のために今を切り捨てるという考えは好きではないが、これは明らかに訓練生の訓練の阻害を目的としたものだと見ていいだろう。
そうでなければ、私たち第二衛生兵部隊だけを最前線に送るというのは無理がある。
「君は分け隔てなく苦しむ負傷兵を治癒してくれる人物だと聞いているよ。まさか断りはしないだろうね?」
「ベリル王子、いえベリル総司令官には既に話は通ってるのですか?」
「うん? 何故ここで総司令官の名前を君が口にするのかね。君の直属の上官は私だ。私とその上のやり取りの是非を君が気にする事はない」
「失礼しました。忘れてください」
ベリル王子に許可を取っているかどうか。
確かに私が口に出していい問題ではない。
それを分かった上でカルザーは、許可を取っているかどうかをうやむやにした。
もし仮に私がこのことをベリル王子に直接伝えでもしたら、情報系統を乱したとして罰を受ける可能性まである。
いずれにしろ、ここで断るという選択肢は私には無い。
一度目をつぶると、今後の動きを瞬時に思い浮かべる。
「分かりました。このフローラ。長官の期待に添えるよう、精一杯頑張らせていただきます」
差出人はカルザー、衛生兵部隊の長官で現在部隊長を務める私の直属の上官にあたる。
内容は『可能な限り至急、本部に出向くこと』。
几帳面な字面の直筆で、そうとだけ書かれていた。
「長官に呼ばれるとは、何かあったかな?」
私は思考をめぐらせるが、特に思い当たることはなかった。
カルザーとは、部隊長に任命された時に挨拶で顔を見せたきりだ。
アンバーの話によると、カルザーはモスアゲート伯爵と懇意らしい。
つまり警戒すべき相手と言うわけだ。
しかし、表向き私はベリル王子とモスアゲート伯爵の確執など知らないことになっている。
変に警戒を見せる訳にもいかない。
「ちょうど第一期が無事全員回復魔法を習得したところだし、行くなら今かな」
ベリル王子が送ると言っていた第二期訓練生はもう少し先になるらしい。
もし訓練生が来たら忙しくなるだろうから、行くなら今がちょうどいい。
いずれにしろ上官が可能な限り至急と言っているのだから、今すぐ行くに越したことはないだろう。
私はそう思い、早速本部へ向かう支度をして、副隊長のデイジーに留守を頼んだ。
「行ってらっしゃいませ。聖女様。いくら護衛が付くとはいえ、道中はお気を付けくださいね」
「ええ。気を付けるわ。と言っても、私が出来ることはないけれど」
こうして私は、数名の護衛を引き連れ、本部のある陣営に向かった。
「第二衛生兵部隊、部隊長フローラ、長官の命令により、参上しました」
「ああ。よく来てくれたね。まぁ、固くならずに、ゆっくりしてくれたまえよ」
長い口ひげを生やした白髪の老人。
これが私は初めて会った時のカルザー長官の印象だった。
確かに見た目は間違いはない。
ただ、挨拶の時目を合わせてから、私はその認識を改めた。
歳は確かにとってはいるが、カルザーは老人などという生易しいものではない。
一癖も二癖もあるその本当の顔を、シワが刻まれた笑みを浮かべるその顔の裏に隠し持っていると確信した。
「それで……忙しいところ呼び寄せたのは他でもない。部隊のことで大きな変更があってね。流石に書面で伝えるだけでは悪いだろうと思い、ここへ呼んだというわけなんだ」
「大きな変更ですか? それはどのような?」
「うん。今、第二衛生兵部隊は魔王討伐部隊の前線から見たら、かなり後方に位置しているね?」
「そうですね。そもそも衛生兵部隊はどの部隊も、治療中の襲撃を危惧し、前線から離れた所にあると聞いていますが……」
カルザーは私の答えに嬉しそうな顔をして頷く。
この嬉しそうな、という表情が、私にとって吉なのか凶なのかは不明だ。
「その通り! だからね。前線で怪我をした兵士たちはそれぞれ階級や症状などで、各衛生兵部隊へ振り分けられるんだけど、今のままじゃ時間がかかる。そうだろう?」
「おっしゃる通りですね。移動中に怪我を悪化させる兵士も多いと聞きます」
「そこでだ! 君の部隊を、まるまる最前線に移動しようと思ってね。どうだい? 素敵な考えだろう?」
「最前線にですか⁉」
またもやカルザーは嬉しそうな顔をして頷いた。
どうやらカルザーの嬉しそうな顔は、私にとっては凶だったようだ。
確かに私も言った通り、負傷兵の移動時間の問題は気付いていた。
カルザーの言うように、最前線に衛生兵部隊があれば、より早く治療が受けられ、無用な苦しみは避けられる。
しかし逆を言うと、今まで以上に負傷兵がひっきりなしに治療場へ訪れることになるだろう。
第一期訓練生を指導していて分かったことだけれど、指導を行えば行うほど、自分の時間が少なくなっていく。
もし最前線に部隊を移動したら、本来の治療が忙しすぎて、指導を行う余裕は大きく制限されるだろう。
そうすれば、第二期訓練生を育てることは難しいだろう。
確かに未来のために今を切り捨てるという考えは好きではないが、これは明らかに訓練生の訓練の阻害を目的としたものだと見ていいだろう。
そうでなければ、私たち第二衛生兵部隊だけを最前線に送るというのは無理がある。
「君は分け隔てなく苦しむ負傷兵を治癒してくれる人物だと聞いているよ。まさか断りはしないだろうね?」
「ベリル王子、いえベリル総司令官には既に話は通ってるのですか?」
「うん? 何故ここで総司令官の名前を君が口にするのかね。君の直属の上官は私だ。私とその上のやり取りの是非を君が気にする事はない」
「失礼しました。忘れてください」
ベリル王子に許可を取っているかどうか。
確かに私が口に出していい問題ではない。
それを分かった上でカルザーは、許可を取っているかどうかをうやむやにした。
もし仮に私がこのことをベリル王子に直接伝えでもしたら、情報系統を乱したとして罰を受ける可能性まである。
いずれにしろ、ここで断るという選択肢は私には無い。
一度目をつぶると、今後の動きを瞬時に思い浮かべる。
「分かりました。このフローラ。長官の期待に添えるよう、精一杯頑張らせていただきます」
「赤い布が足りないわ‼ もっと持ってきてちょうだい‼」
「黄色の患者! こっちです! そっちはもっと重篤な患者用です!!」
狭い治療場の至る所で悲鳴に似た叫び声が飛び交う。
私は額に流れる汗を拭う暇すらなく、ひたすらに運ばれてくる兵士たちの治療に専念していた。
「いてぇ! いてぇよぉ‼」
「うわぁぁぁ!! こっちに来るなぁ!! あぁぁぁ!! ああああ!!」
目の間に運ばれてくるのは呪いを受けた兵士たち。
弱い【痛み】だけならまだデイジーも対応できるが、【恐怖】に侵されている者までいる。
隣では【痛み】の呪いを受けた兵士を何とか落ち着かせようと優しく声をかけるデイジーが、悪戦苦闘していた。
「大丈夫よ。落ち着いて。深呼吸を。動いていたらうまく治療できないわ」
「いやだぁあぁぁ! 痛いぃぃぃ!! 痛いんだよぉぉ!! 助けてくれ! 殺してくれー!!」
痛みのせいで、屈強な兵士すら、気が狂ったように叫び続けている。
今思えば、クロムが瀕死の状況で【痛み】に侵されていたのに、あれだけ自制心を保っていたのは凄いことだったのだろう。
呪いを受けた兵士たちの多くは泣き、叫び、そして暴れまわった。
なんとか数人がかりで押さえつけ、その隙に治療を施すのだが、これが一苦労だった。
「ロベリアが魔力枯渇です! 休ませます!!」
「分かったわ! 他の人も無理をしないで! 休むのも立派な仕事よ!」
同期の休憩を代わりに告げてきた衛生兵に私は視線を動かすことなく叫んで返す。
治療が忙しすぎて、横を振り向く暇すら惜しいのだ。
数週間前に戦闘の最前線に繰り出された私たち第二衛生兵部隊は、苦戦を強いられていた。
とにかく負傷兵が多すぎるのだ。
前線ではこれほどまでに負傷兵がいたのかと驚くほどの数が、休むことなく運ばれてくる。
その中には猛毒や呪いを受けた兵士も少なくない。
「きっと、前線から後衛の衛生兵部隊まで運ばれる間に、助からなかったのね……」
猛毒は速やかに全身の周り、患者を死に追いやる。
そして止むことのない痛みや恐怖は、受けた本人を自死へと誘っていたのだろう。
「もう少しだけ辛抱して! 今治すから‼︎」
「聖女様! 布なしです! 毒と呪いの複合です‼︎」
「すぐに運んで‼︎ 順番に並べるのよ‼︎ デイジー! 代わりにこっちをお願い‼︎」
「分かりました‼︎」
初期の解呪を覚えたデイジーがいてくれたおかげでなんとかなっている。
しかし、私たちも万能ではなく、すでに間に合わなかった犠牲者も出始めていた。
「人手が! 人手がまるで足りないわ‼︎」
「部隊長! 本部からの伝達ですがどうしますか⁉︎」
休む間もなく回復魔法を施していた私の元に、衛兵が一人駆け寄ってくる。
その表情はどうすればいいか分からず、オロオロとした様子だ。
「読んでる暇なんてないわ! あなた! そこで読み上げなさい‼︎ 私に聞こえるようはっきりと!」
「し、しかし……軍の重要機密の印が押されていますが……」
「構わないわ。この問答すら時間の無駄だと言うのが分からないの? 早く読みなさい!」
「わ、分かりましたァ‼︎」
私に促されて衛兵は手に持った伝達の封を切り、中から紙を取り出すとはっきりとした声で読み始めた。
「第二衛生兵部隊長フローラに告げる。本日より、衛生兵の増員を送ることとする。衛生兵部隊長官カルザー」
文章はたったそれだけだった。
しかし、その分の意味を私はしっかりと理解した。
「まさか! このタイミングで訓練兵を⁉︎」
元々は私の部隊、第二衛生兵部隊には回復魔法を使うことのできない衛生兵を、訓練兵として集める予定だった。
その訓練兵たちは表向きはみな、既に回復魔法を使える立派な衛生兵ということになっている。
モスアゲート伯爵にバレずに前線の戦力を増強するための、ベリル王子主導の戦略のはずだが、その訓練兵が今送られてきたと言うのだ。
足りない人員を補う戦力として。
これがもし、ベリル王子の名で出された伝達や、ダリアもしくはアンバーだったら話が違っていただろう。
しかし、書かれていたのは長官カルザー。
彼がモスアゲート伯爵の息がかかった人物だと言うことは間違いない。
その彼が増員という形で訓練兵を送ってきたということは……
私が、どうするか思案していたところに、窓から一匹の黒い鳥が飛び込んできた。
突然の闖入に驚きの声をあげる者もいる。
しかし私はこの鳥に見覚えがあったので、驚くことなく、私の肩にとまった黒い鳥に耳を傾ける。
すると黒い鳥の嘴から、聞き覚えのある男性の声、アンバーの声が聞こえてきた。
「大変だよ。聖女様。どうやら奴さんに計画がバレたらしい。僕やダリアのところは元々実戦で鍛える計画だったから問題ないけど、問題は聖女様のところだ」
私は治療を続けながら、黒い鳥を介して伝達されるアンバーの言葉に注意深く聞き入った。
「そっちも今最前線でてんやわんやだろ? そんなところにろくに使えない訓練兵さ。しかも名目上は増員って話でね。鍛える暇もなく、増員したのに成果は変わらず。奴ら聖女様を戦場から追い出すつもりだよ!」
予想通りの展開に、私は一度深い息を吐く。
確かに人手は足りず、増員が欲しいと願ったが、それは回復魔法が使える衛生兵、つまり使い物になる人物としてだ。
ここでの訓練兵は、足手まといとまでは言わないが、期待する援助にはならないだろう。
しかも名目上はきちんとした衛生兵を送ったというのに、状況が改善しないとなれば、部隊長である私に何らかの罰を与えることもできる。
流石に命に関わることはないだろうが、これ以上戦地に関わりの持てないような処遇を受けることだってできるかもしれない。
そこまで考えて、もう一度、息を強く吐き出した。
「思い通りにさせるもんですかっ! 訓練兵の訓練の時間が取れないなら、私たちも実地で訓練させてあげればいいのよ!」
私が意気込んでいる間に、件の訓練兵たちがぞろぞろと治療場へと訪れてきた。
みな、困ったような、不安そうな顔をしている。
彼女らは事情をほとんど知らないはずだ。
回復魔法の訓練を無償で行え、衛生兵として職を持つことができるとだけ聞き、この戦場に来たのだろう。
そんな彼女らが最初に訪れた場所が、最も危険で過酷な最前線の治療場だとは夢にも思わなかったに違いない。
しかし、私も彼女らも泣き言を漏らしても事態は一向に改善しないのだ。
いまだにオロオロと、どうすればいいのか分からないまま立ち尽くす白いリボンタイを付けた訓練兵たち。
彼女らに私は立ち上がり大声で今後のことを手短に伝えた。
「ようこそ! 第二衛生兵部隊へ! 部隊長のフローラよ! 見て分かる通り、一人でも手助けが必要な状態なの。ただし、手取り足取り教えている暇は残念ながら無いわ。一人ずつ、緑色のリボンタイをしている衛生兵の元に行き、実際に治療しながら、回復魔法を覚えなさい‼︎」
「黄色の患者! こっちです! そっちはもっと重篤な患者用です!!」
狭い治療場の至る所で悲鳴に似た叫び声が飛び交う。
私は額に流れる汗を拭う暇すらなく、ひたすらに運ばれてくる兵士たちの治療に専念していた。
「いてぇ! いてぇよぉ‼」
「うわぁぁぁ!! こっちに来るなぁ!! あぁぁぁ!! ああああ!!」
目の間に運ばれてくるのは呪いを受けた兵士たち。
弱い【痛み】だけならまだデイジーも対応できるが、【恐怖】に侵されている者までいる。
隣では【痛み】の呪いを受けた兵士を何とか落ち着かせようと優しく声をかけるデイジーが、悪戦苦闘していた。
「大丈夫よ。落ち着いて。深呼吸を。動いていたらうまく治療できないわ」
「いやだぁあぁぁ! 痛いぃぃぃ!! 痛いんだよぉぉ!! 助けてくれ! 殺してくれー!!」
痛みのせいで、屈強な兵士すら、気が狂ったように叫び続けている。
今思えば、クロムが瀕死の状況で【痛み】に侵されていたのに、あれだけ自制心を保っていたのは凄いことだったのだろう。
呪いを受けた兵士たちの多くは泣き、叫び、そして暴れまわった。
なんとか数人がかりで押さえつけ、その隙に治療を施すのだが、これが一苦労だった。
「ロベリアが魔力枯渇です! 休ませます!!」
「分かったわ! 他の人も無理をしないで! 休むのも立派な仕事よ!」
同期の休憩を代わりに告げてきた衛生兵に私は視線を動かすことなく叫んで返す。
治療が忙しすぎて、横を振り向く暇すら惜しいのだ。
数週間前に戦闘の最前線に繰り出された私たち第二衛生兵部隊は、苦戦を強いられていた。
とにかく負傷兵が多すぎるのだ。
前線ではこれほどまでに負傷兵がいたのかと驚くほどの数が、休むことなく運ばれてくる。
その中には猛毒や呪いを受けた兵士も少なくない。
「きっと、前線から後衛の衛生兵部隊まで運ばれる間に、助からなかったのね……」
猛毒は速やかに全身の周り、患者を死に追いやる。
そして止むことのない痛みや恐怖は、受けた本人を自死へと誘っていたのだろう。
「もう少しだけ辛抱して! 今治すから‼︎」
「聖女様! 布なしです! 毒と呪いの複合です‼︎」
「すぐに運んで‼︎ 順番に並べるのよ‼︎ デイジー! 代わりにこっちをお願い‼︎」
「分かりました‼︎」
初期の解呪を覚えたデイジーがいてくれたおかげでなんとかなっている。
しかし、私たちも万能ではなく、すでに間に合わなかった犠牲者も出始めていた。
「人手が! 人手がまるで足りないわ‼︎」
「部隊長! 本部からの伝達ですがどうしますか⁉︎」
休む間もなく回復魔法を施していた私の元に、衛兵が一人駆け寄ってくる。
その表情はどうすればいいか分からず、オロオロとした様子だ。
「読んでる暇なんてないわ! あなた! そこで読み上げなさい‼︎ 私に聞こえるようはっきりと!」
「し、しかし……軍の重要機密の印が押されていますが……」
「構わないわ。この問答すら時間の無駄だと言うのが分からないの? 早く読みなさい!」
「わ、分かりましたァ‼︎」
私に促されて衛兵は手に持った伝達の封を切り、中から紙を取り出すとはっきりとした声で読み始めた。
「第二衛生兵部隊長フローラに告げる。本日より、衛生兵の増員を送ることとする。衛生兵部隊長官カルザー」
文章はたったそれだけだった。
しかし、その分の意味を私はしっかりと理解した。
「まさか! このタイミングで訓練兵を⁉︎」
元々は私の部隊、第二衛生兵部隊には回復魔法を使うことのできない衛生兵を、訓練兵として集める予定だった。
その訓練兵たちは表向きはみな、既に回復魔法を使える立派な衛生兵ということになっている。
モスアゲート伯爵にバレずに前線の戦力を増強するための、ベリル王子主導の戦略のはずだが、その訓練兵が今送られてきたと言うのだ。
足りない人員を補う戦力として。
これがもし、ベリル王子の名で出された伝達や、ダリアもしくはアンバーだったら話が違っていただろう。
しかし、書かれていたのは長官カルザー。
彼がモスアゲート伯爵の息がかかった人物だと言うことは間違いない。
その彼が増員という形で訓練兵を送ってきたということは……
私が、どうするか思案していたところに、窓から一匹の黒い鳥が飛び込んできた。
突然の闖入に驚きの声をあげる者もいる。
しかし私はこの鳥に見覚えがあったので、驚くことなく、私の肩にとまった黒い鳥に耳を傾ける。
すると黒い鳥の嘴から、聞き覚えのある男性の声、アンバーの声が聞こえてきた。
「大変だよ。聖女様。どうやら奴さんに計画がバレたらしい。僕やダリアのところは元々実戦で鍛える計画だったから問題ないけど、問題は聖女様のところだ」
私は治療を続けながら、黒い鳥を介して伝達されるアンバーの言葉に注意深く聞き入った。
「そっちも今最前線でてんやわんやだろ? そんなところにろくに使えない訓練兵さ。しかも名目上は増員って話でね。鍛える暇もなく、増員したのに成果は変わらず。奴ら聖女様を戦場から追い出すつもりだよ!」
予想通りの展開に、私は一度深い息を吐く。
確かに人手は足りず、増員が欲しいと願ったが、それは回復魔法が使える衛生兵、つまり使い物になる人物としてだ。
ここでの訓練兵は、足手まといとまでは言わないが、期待する援助にはならないだろう。
しかも名目上はきちんとした衛生兵を送ったというのに、状況が改善しないとなれば、部隊長である私に何らかの罰を与えることもできる。
流石に命に関わることはないだろうが、これ以上戦地に関わりの持てないような処遇を受けることだってできるかもしれない。
そこまで考えて、もう一度、息を強く吐き出した。
「思い通りにさせるもんですかっ! 訓練兵の訓練の時間が取れないなら、私たちも実地で訓練させてあげればいいのよ!」
私が意気込んでいる間に、件の訓練兵たちがぞろぞろと治療場へと訪れてきた。
みな、困ったような、不安そうな顔をしている。
彼女らは事情をほとんど知らないはずだ。
回復魔法の訓練を無償で行え、衛生兵として職を持つことができるとだけ聞き、この戦場に来たのだろう。
そんな彼女らが最初に訪れた場所が、最も危険で過酷な最前線の治療場だとは夢にも思わなかったに違いない。
しかし、私も彼女らも泣き言を漏らしても事態は一向に改善しないのだ。
いまだにオロオロと、どうすればいいのか分からないまま立ち尽くす白いリボンタイを付けた訓練兵たち。
彼女らに私は立ち上がり大声で今後のことを手短に伝えた。
「ようこそ! 第二衛生兵部隊へ! 部隊長のフローラよ! 見て分かる通り、一人でも手助けが必要な状態なの。ただし、手取り足取り教えている暇は残念ながら無いわ。一人ずつ、緑色のリボンタイをしている衛生兵の元に行き、実際に治療しながら、回復魔法を覚えなさい‼︎」
訓練兵が来てから一週間が経った。
初めは教える側も教えられる側も戸惑っていたものの、少しずつ慣れてきたようだ。
第二衛生兵部隊にいる緑色のリボンタイをしている衛生兵は、全員が私やデイジーから訓練を受けている。
どうすれば回復魔法を使えるようになれるか、一から知っているという訳だ。
何も知らない訓練兵に、一から教えるとしても、問題はないだろう。
逆に初めから回復魔法が使えた者だと、使えない者の感覚というの理解できず、そこでつまずく危険性があった。
また、緑色の負傷兵は時間的余裕もある。
中には早くしろと怒鳴り出す兵士もいたが、私が気に食わないなら治療しないと言うと、誰もが大人しくなった。
少し大人気ない言い方かもしれないが、いちいち時間をかける余裕もない。
前線に来てから、今までより精神的に強くなったようにも思う。
そうやって先輩の仕事を見ながら、都度練習し、訓練兵は実地で訓練を行っていく。
魔力操作をし、回復魔法を唱える様子を実際に見ていた方が、実感が湧きやすいのか、今までよりも習得が早いようにも見えた。
少しだけある休憩時間、隊長用の執務室で魔力を回復させるために休んでいると、サルビアが報告しにきた。
私が休んでいる間はデイジーが必ず治療場にいるので、訓練兵の伝言はサルビアに頼んでいる。
「回復魔法を使えるようになってきた者も増えてきたようです」
「思いつきの方法だったけれど、なかなかうまくいっているみたいね。これからは、上の方にも取り入れるわよ。まずはサルビア、あなたも紫色を付けれるようになりなさい」
既に毒の治癒を行える赤色のリボンタイを付けれられる衛生兵は、サルビアだけではなくなっていた。
しかし、初級の呪いを解呪できる者が付けることが許された紫色のリボンタイは、いまだにデイジーだけだった。
ちなみに、元々は紫は強い毒の解毒だけで、呪いの解呪は私だけしかできない布なしだった。
しかし、部隊の能力が向上するにつれ、黄色以上の要求はそれぞれ変わっていった。
初めは色を増やすことも検討したけれど、あまり増やすと負傷兵に布を巻く際に、煩雑だということで、色の数はそのままにすることにしたのだ。
「紫色のリボンタイですか……本心としてはすぐにでも付けられるようになりたいところですが……」
「あなたには付けられる才能があるわ。自信を持ちなさい。以前よりも扱える魔力は格段に増えているはずよ。あとはきっかけだけ」
「ありがとうございます。しかし……その……コツと言いますか。限られた時間ですが、暇がある時には訓練をしていますが一向に」
「ええ。分かっているわ。あなたは努力をしている。だから、今日から私と一緒に布なしの対処をしてもらうわ」
伝えた瞬間、サルビアの目が見開いた。
驚きと興奮の様子だ。
「本当ですか⁉︎ 聖女様の治癒を近くで見ることができるなんて! ありがとうございます‼︎」
「お礼を言っている場合じゃないのよ。サルビア。治療はできるだけあなたが担当するの。もちろんできないことをやらせるつもりはないけれど」
「どういうことですか?」
「訓練兵と一緒よ。治療場で治療を施しながら、あなたに解呪の魔法を教えるわ。つまり実地訓練ね」
「え⁉︎ でも、呪いを受けた兵士たちは、みんな気が狂いそうな状態ですよ? 私が失敗したら……」
「少なくとも呪いですぐに死ぬことはないわ。長期間放置されてしまえば精神が病んでしまうこともあるけれど。治療場で過ごす時間程度では、そんなことも起きないでしょうね」
私が今からやろうとしていることは、やられる負傷兵からみれば、たまったものではないことは十分理解している。
しかし、今のままではデイジーと私のどちらも手を空けることができない。
もしサルビアがデイジーの負担を減らすことができれば、少なくとも私かデイジーの手が空く時間を捻出することができるかもしれない。
訓練兵が白色から緑色になるための訓練ならば、今のやり方で問題がない。
しかし、黄色や赤色になるためには適さない。
時間経過の結果、出血や毒によって命を落とす危険が圧倒的に高くなるからだ。
どうしても次の段階に行くためには、実地ではない、これまで通りの訓練も必要だ。
つまり、逼迫していない状況での訓練だ。
それを実現しなければ、求めた増員にはなりえない。
もしここが以前のような後衛に設置された陣営だったのであれば、緑色でも十分戦力になっただろう。
しかし、前線は予想していた以上に、重篤な負傷兵が多い。
小さな傷を治すことしかできない衛生兵では不十分なのだ。
サルビアが解呪の魔法を習得するまで、負傷兵には今よりも多少の痛みが伴う。
それは必要な痛みだと思うしかない。
私は神ではないのだ。
今この瞬間、全ての衛生兵を私と同じ程度の回復魔法の使い手にする方法があるのなら、喜んでこの身すら投げ出そう。
しかしそれは起こり得ない。
ならば、着実に一歩一歩進んでいくしかない。
「あなたが解呪の魔法を習得することは、今後の第二衛生兵部隊全体にとって、とても重要なことなの。サルビア、やってくれるわね?」
「……分かりました! できるだけ早く習得するように、精一杯頑張らせていただきます‼︎」
初めは教える側も教えられる側も戸惑っていたものの、少しずつ慣れてきたようだ。
第二衛生兵部隊にいる緑色のリボンタイをしている衛生兵は、全員が私やデイジーから訓練を受けている。
どうすれば回復魔法を使えるようになれるか、一から知っているという訳だ。
何も知らない訓練兵に、一から教えるとしても、問題はないだろう。
逆に初めから回復魔法が使えた者だと、使えない者の感覚というの理解できず、そこでつまずく危険性があった。
また、緑色の負傷兵は時間的余裕もある。
中には早くしろと怒鳴り出す兵士もいたが、私が気に食わないなら治療しないと言うと、誰もが大人しくなった。
少し大人気ない言い方かもしれないが、いちいち時間をかける余裕もない。
前線に来てから、今までより精神的に強くなったようにも思う。
そうやって先輩の仕事を見ながら、都度練習し、訓練兵は実地で訓練を行っていく。
魔力操作をし、回復魔法を唱える様子を実際に見ていた方が、実感が湧きやすいのか、今までよりも習得が早いようにも見えた。
少しだけある休憩時間、隊長用の執務室で魔力を回復させるために休んでいると、サルビアが報告しにきた。
私が休んでいる間はデイジーが必ず治療場にいるので、訓練兵の伝言はサルビアに頼んでいる。
「回復魔法を使えるようになってきた者も増えてきたようです」
「思いつきの方法だったけれど、なかなかうまくいっているみたいね。これからは、上の方にも取り入れるわよ。まずはサルビア、あなたも紫色を付けれるようになりなさい」
既に毒の治癒を行える赤色のリボンタイを付けれられる衛生兵は、サルビアだけではなくなっていた。
しかし、初級の呪いを解呪できる者が付けることが許された紫色のリボンタイは、いまだにデイジーだけだった。
ちなみに、元々は紫は強い毒の解毒だけで、呪いの解呪は私だけしかできない布なしだった。
しかし、部隊の能力が向上するにつれ、黄色以上の要求はそれぞれ変わっていった。
初めは色を増やすことも検討したけれど、あまり増やすと負傷兵に布を巻く際に、煩雑だということで、色の数はそのままにすることにしたのだ。
「紫色のリボンタイですか……本心としてはすぐにでも付けられるようになりたいところですが……」
「あなたには付けられる才能があるわ。自信を持ちなさい。以前よりも扱える魔力は格段に増えているはずよ。あとはきっかけだけ」
「ありがとうございます。しかし……その……コツと言いますか。限られた時間ですが、暇がある時には訓練をしていますが一向に」
「ええ。分かっているわ。あなたは努力をしている。だから、今日から私と一緒に布なしの対処をしてもらうわ」
伝えた瞬間、サルビアの目が見開いた。
驚きと興奮の様子だ。
「本当ですか⁉︎ 聖女様の治癒を近くで見ることができるなんて! ありがとうございます‼︎」
「お礼を言っている場合じゃないのよ。サルビア。治療はできるだけあなたが担当するの。もちろんできないことをやらせるつもりはないけれど」
「どういうことですか?」
「訓練兵と一緒よ。治療場で治療を施しながら、あなたに解呪の魔法を教えるわ。つまり実地訓練ね」
「え⁉︎ でも、呪いを受けた兵士たちは、みんな気が狂いそうな状態ですよ? 私が失敗したら……」
「少なくとも呪いですぐに死ぬことはないわ。長期間放置されてしまえば精神が病んでしまうこともあるけれど。治療場で過ごす時間程度では、そんなことも起きないでしょうね」
私が今からやろうとしていることは、やられる負傷兵からみれば、たまったものではないことは十分理解している。
しかし、今のままではデイジーと私のどちらも手を空けることができない。
もしサルビアがデイジーの負担を減らすことができれば、少なくとも私かデイジーの手が空く時間を捻出することができるかもしれない。
訓練兵が白色から緑色になるための訓練ならば、今のやり方で問題がない。
しかし、黄色や赤色になるためには適さない。
時間経過の結果、出血や毒によって命を落とす危険が圧倒的に高くなるからだ。
どうしても次の段階に行くためには、実地ではない、これまで通りの訓練も必要だ。
つまり、逼迫していない状況での訓練だ。
それを実現しなければ、求めた増員にはなりえない。
もしここが以前のような後衛に設置された陣営だったのであれば、緑色でも十分戦力になっただろう。
しかし、前線は予想していた以上に、重篤な負傷兵が多い。
小さな傷を治すことしかできない衛生兵では不十分なのだ。
サルビアが解呪の魔法を習得するまで、負傷兵には今よりも多少の痛みが伴う。
それは必要な痛みだと思うしかない。
私は神ではないのだ。
今この瞬間、全ての衛生兵を私と同じ程度の回復魔法の使い手にする方法があるのなら、喜んでこの身すら投げ出そう。
しかしそれは起こり得ない。
ならば、着実に一歩一歩進んでいくしかない。
「あなたが解呪の魔法を習得することは、今後の第二衛生兵部隊全体にとって、とても重要なことなの。サルビア、やってくれるわね?」
「……分かりました! できるだけ早く習得するように、精一杯頑張らせていただきます‼︎」
次の日から、サルビアの実地訓練による私からの直接指導が始まった。
と言っても、すぐに解呪の魔法が使えるようになるわけではないので、最初は隣でやり方を見てもらっている。
「いい? 通常の怪我を治すための治癒の魔法と、毒を直す解毒の魔法の違いは感覚でわかっているわね?」
「はい。うまく言葉に表せられないですけど、治癒はほわーって感じで、解毒はじわーって感じですね。全然違います」
思わずサルビアの説明に小さな微笑みを抱いてしまう。
彼女の言う通り、魔法の感覚というのを口で説明するのは非常に難しい。
さらに、同じ魔法を唱える場合にも、使用者の感覚はそれぞれだ。
私の場合も、あえて擬音で感覚を表すとしたら、治癒魔法は同じほわーだが、解毒魔法はしゅって感じになる。
「そう。いいわね。その擬音で感覚を表すの。今度使わせてもらうわ」
「はい! 気に入ってもらえて恐縮です!」
こんな会話をしているところだが、目の前には【痛み】の呪いを受け、先ほどから痛みを訴えている紫色の布を巻いた負傷兵がいる。
呪いの範囲はまだ狭く、痛みも耐えられるようだが、これ以上放っておくのも可哀想だろう。
「それじゃあ、まずは見せるわね」
「うぅぅぅ‼︎」
痛みに耐えかねたのか、負傷兵から声が漏れる。
私はできるだけ素早く、かつ必要最低限の魔力を練って、解呪の魔法を唱えた。
以前より魔力の総量は格段に増えたものの、使用する魔力の量もこの前線では桁違いで、できるだけ節約する必要がある。
おかげで、魔力量を操る力も、以前とは比べ物にならないほど繊細な扱いが可能にになった。
両手に光が集まり、眩く輝く。
その光に負傷兵の体に刻まれた呪いの紋様が呼応し、墨が水に溶け流れるように、徐々に消えていった。
「やっぱり聖女様の魔法はすごいです! こんな近くで見られて、私、感激です‼︎」
「喜んでいる場合じゃないわよ? これをサルビアにはできるようになってもらわないければならないのだから」
痛みが消えたおかげで、顔の歪みが取れた負傷兵に、私は告げる。
「これで呪いは消えたわ。残りの怪我については、サルビアが看るわね。そして、治療に時間がかかってごめんなさいね。今彼女の訓練中なの」
「あぁ……そうでしたか。お気になさらないでください。あなた方はこうして私を救ってくださったのですから。それに、聖女様と兵士たちから呼ばれるあなたに治療されて、私は運が良かった。ありがとうございます」
「消失した大腿部、治癒完了しました!」
「あぁ……魔族の攻撃を受けた時はもうダメかと思いましたが、まさか再び五体満足に戻れるとは。本当にありがとうございます。ありがとうございます」
何度もお礼を言いながら、兵士は去っていった。
確かに彼の言う通り、前線では未だに死者が後を絶たない。
その多くは、治療場に運ばれてくる前に手遅れになっていた。
今は運ばれてくる負傷兵の治癒で手がいっぱいだが、いずれ訓練兵たちが成長し、他の衛生兵たちの能力の底上げも済めば、何か改善策を練りたいと思っているところだ。
そんなことを考えている間に呪いを受けた他の負傷兵が運ばれてくる。
「それじゃあ早速。サルビアに解呪の魔法を使ってもらうわね」
「え⁉︎ そんな! 無理ですよ! いきなりなんて‼︎」
サルビアの叫び声に、負傷兵は不安そうな顔をこちらに向ける。
私は大丈夫だと諭すように、微笑みを負傷兵に向けて、説明を始めた。
「ごめんなさいね。辛いのはよく分かっているの。でも、少しだけこの子の成長の手伝いをしてちょうだい。大丈夫。必ず良くなるから。そこは安心して」
そう言った後、サルビアへの説明を続ける。
「いきなりできるようになるだなんて、私も思っていないわ。でも、やらなければ、いつまで経ってもいきなりから卒業できないわよ?」
「そ、そうですね。分かりました。やります! やらせてください!」
既にサルビアは知識としての解呪の魔法については習得済みだ。
必要なのは感覚。
しかし、その感覚は自分だけのもの。
さらに、攻撃魔法と違い、回復魔法は実際の怪我や毒、呪いを受けた人に使ってみないと、その効果が出ているのか判断が難しい。
同じ系統の上位の魔法を使う分には、同じ感覚を利用できるため、わざわざ実際の怪我などに唱える必要がない。
しかし、新しい感覚を身に付ける時は、確認として必須だった。
今回の場合で言えば、サルビアが解呪の魔法を使えるようになったかどうか確認するためには、実際に呪いを受けた人物への治療が必要だ。
まずはダメもとでやらせてみる。
「いきます!」
サルビアが目を瞑り、解呪の魔法を唱え始める。
差し出した両手に私の時と同じように光が集まり始めた。
サルビアは瞑っていた目を開き、両手の光で呪いの紋様を照らすように近づける。
しばしの沈黙。サルビアの表情は真剣そのものだ。
「うまく……いっていないようね」
私の声にサルビアは明らかな落胆の表情を見せる。
サルビアが光を呪いの紋様に当ててからしばらく経っても、紋様の色は一向に薄まったり消えたりすることはなかった。
つまり――失敗だ。
急いで私は解呪の魔法を唱え始めた。
私の挙動に気づいたサルビアは、かざした手を引っ込める。
先ほどサルビアの手がかざされていた場所に、私の手をかざす。
今度は、ほとんど時間を置くことなく、呪いの紋様は溶けて消えていった。
「すいません……やっぱりうまくいかなかったみたいです……」
サルビアは申し訳なさそうに謝ってきた。
私は首を横に振り、問題ないことを告げる。
「大丈夫よ。言ったでしょう? これは訓練だって。初めからできるのなら、訓練は必要ないのよ。できないからこその訓練なの。さぁ、いちいち失敗に落ち込んでる暇はないわよ! 負傷兵はどんどん運ばれてくるのだから!」
「そうですね……はい!」
サルビアは元来の明るさを取り戻し、再び呪いを解くために、新たな負傷兵に向かって、解呪の魔法を唱え始めた。
と言っても、すぐに解呪の魔法が使えるようになるわけではないので、最初は隣でやり方を見てもらっている。
「いい? 通常の怪我を治すための治癒の魔法と、毒を直す解毒の魔法の違いは感覚でわかっているわね?」
「はい。うまく言葉に表せられないですけど、治癒はほわーって感じで、解毒はじわーって感じですね。全然違います」
思わずサルビアの説明に小さな微笑みを抱いてしまう。
彼女の言う通り、魔法の感覚というのを口で説明するのは非常に難しい。
さらに、同じ魔法を唱える場合にも、使用者の感覚はそれぞれだ。
私の場合も、あえて擬音で感覚を表すとしたら、治癒魔法は同じほわーだが、解毒魔法はしゅって感じになる。
「そう。いいわね。その擬音で感覚を表すの。今度使わせてもらうわ」
「はい! 気に入ってもらえて恐縮です!」
こんな会話をしているところだが、目の前には【痛み】の呪いを受け、先ほどから痛みを訴えている紫色の布を巻いた負傷兵がいる。
呪いの範囲はまだ狭く、痛みも耐えられるようだが、これ以上放っておくのも可哀想だろう。
「それじゃあ、まずは見せるわね」
「うぅぅぅ‼︎」
痛みに耐えかねたのか、負傷兵から声が漏れる。
私はできるだけ素早く、かつ必要最低限の魔力を練って、解呪の魔法を唱えた。
以前より魔力の総量は格段に増えたものの、使用する魔力の量もこの前線では桁違いで、できるだけ節約する必要がある。
おかげで、魔力量を操る力も、以前とは比べ物にならないほど繊細な扱いが可能にになった。
両手に光が集まり、眩く輝く。
その光に負傷兵の体に刻まれた呪いの紋様が呼応し、墨が水に溶け流れるように、徐々に消えていった。
「やっぱり聖女様の魔法はすごいです! こんな近くで見られて、私、感激です‼︎」
「喜んでいる場合じゃないわよ? これをサルビアにはできるようになってもらわないければならないのだから」
痛みが消えたおかげで、顔の歪みが取れた負傷兵に、私は告げる。
「これで呪いは消えたわ。残りの怪我については、サルビアが看るわね。そして、治療に時間がかかってごめんなさいね。今彼女の訓練中なの」
「あぁ……そうでしたか。お気になさらないでください。あなた方はこうして私を救ってくださったのですから。それに、聖女様と兵士たちから呼ばれるあなたに治療されて、私は運が良かった。ありがとうございます」
「消失した大腿部、治癒完了しました!」
「あぁ……魔族の攻撃を受けた時はもうダメかと思いましたが、まさか再び五体満足に戻れるとは。本当にありがとうございます。ありがとうございます」
何度もお礼を言いながら、兵士は去っていった。
確かに彼の言う通り、前線では未だに死者が後を絶たない。
その多くは、治療場に運ばれてくる前に手遅れになっていた。
今は運ばれてくる負傷兵の治癒で手がいっぱいだが、いずれ訓練兵たちが成長し、他の衛生兵たちの能力の底上げも済めば、何か改善策を練りたいと思っているところだ。
そんなことを考えている間に呪いを受けた他の負傷兵が運ばれてくる。
「それじゃあ早速。サルビアに解呪の魔法を使ってもらうわね」
「え⁉︎ そんな! 無理ですよ! いきなりなんて‼︎」
サルビアの叫び声に、負傷兵は不安そうな顔をこちらに向ける。
私は大丈夫だと諭すように、微笑みを負傷兵に向けて、説明を始めた。
「ごめんなさいね。辛いのはよく分かっているの。でも、少しだけこの子の成長の手伝いをしてちょうだい。大丈夫。必ず良くなるから。そこは安心して」
そう言った後、サルビアへの説明を続ける。
「いきなりできるようになるだなんて、私も思っていないわ。でも、やらなければ、いつまで経ってもいきなりから卒業できないわよ?」
「そ、そうですね。分かりました。やります! やらせてください!」
既にサルビアは知識としての解呪の魔法については習得済みだ。
必要なのは感覚。
しかし、その感覚は自分だけのもの。
さらに、攻撃魔法と違い、回復魔法は実際の怪我や毒、呪いを受けた人に使ってみないと、その効果が出ているのか判断が難しい。
同じ系統の上位の魔法を使う分には、同じ感覚を利用できるため、わざわざ実際の怪我などに唱える必要がない。
しかし、新しい感覚を身に付ける時は、確認として必須だった。
今回の場合で言えば、サルビアが解呪の魔法を使えるようになったかどうか確認するためには、実際に呪いを受けた人物への治療が必要だ。
まずはダメもとでやらせてみる。
「いきます!」
サルビアが目を瞑り、解呪の魔法を唱え始める。
差し出した両手に私の時と同じように光が集まり始めた。
サルビアは瞑っていた目を開き、両手の光で呪いの紋様を照らすように近づける。
しばしの沈黙。サルビアの表情は真剣そのものだ。
「うまく……いっていないようね」
私の声にサルビアは明らかな落胆の表情を見せる。
サルビアが光を呪いの紋様に当ててからしばらく経っても、紋様の色は一向に薄まったり消えたりすることはなかった。
つまり――失敗だ。
急いで私は解呪の魔法を唱え始めた。
私の挙動に気づいたサルビアは、かざした手を引っ込める。
先ほどサルビアの手がかざされていた場所に、私の手をかざす。
今度は、ほとんど時間を置くことなく、呪いの紋様は溶けて消えていった。
「すいません……やっぱりうまくいかなかったみたいです……」
サルビアは申し訳なさそうに謝ってきた。
私は首を横に振り、問題ないことを告げる。
「大丈夫よ。言ったでしょう? これは訓練だって。初めからできるのなら、訓練は必要ないのよ。できないからこその訓練なの。さぁ、いちいち失敗に落ち込んでる暇はないわよ! 負傷兵はどんどん運ばれてくるのだから!」
「そうですね……はい!」
サルビアは元来の明るさを取り戻し、再び呪いを解くために、新たな負傷兵に向かって、解呪の魔法を唱え始めた。
「すいません! 今回もダメです‼︎」
「大丈夫! そろそろ魔力が消えかかっているようね。少し休みなさい。でも、私の治療を見ているのよ」
かなりの時間、互いに試行錯誤をしながらサルビアの訓練を続けていたものの、結果は芳しくはなかった。
その主な理由は感覚の違い。
デイジーに解呪の魔法を指導する際には、私の感覚とデイジーの感覚がたまたま似通っていたおかげか、時間はかかったものの、何とか習得してもらうことができた。
しかし、先ほどの解毒の魔法の感覚が大きく違ったように、私とサルビアの感覚には大きな隔たりがあるようだ。
「ごめんなさい。何かいい方法があればいいのだけれど……」
「そんな! 聖女様は一つも悪くありません! こんなに時間を割いて指導いただいているのに、できない私が悪いんです‼︎」
その場に座り込みながら、消耗した魔力を回復させるサルビアがそう言う。
私は首を横に振り、どうにかならないかと思案していた。
やはり一番重要なのは、感覚だ。
デイジーが解呪の魔法を覚えた時も、口頭でだが私が解呪の魔法を使う時の感覚を伝えたことがきっかけだった。
それまで何度やっても失敗していたデイジーだったが、感覚を伝えた途端、何か気づきがあったようで、数日間独自に訓練をしていた。
その後、再び解呪に挑戦し、完全に解呪するまではいかなかったものの、使う際に必要な感覚が掴めたと、喜んでいた。
悩みで気が疎かになっていた矢先、聞き覚えのある声同士の会話がふと耳に入った。
声のする方を見ると、ロベリアが負傷兵として運ばれてきたアイオラと話している。
「兄さん! また怪我をしたの?」
「あはは。そりゃあ、戦闘をしているんだから怪我はいつだってするさ。それに今回は前回みたいな酷いものじゃない。大丈夫だよ」
「そうよね……安心して! 兄さんや他の兵士さんがいくら傷ついたって、聖女様のいるこの部隊がたちまち綺麗さっぱり治しちゃうんだから!」
「そりゃあ頼もしいなぁ。ロベリアも頑張っているみたいだね。さぁさ、仕事中だろう? いつまでも油を売ってないで持ち場に戻るんだよ」
「残念でした! 今は休憩時間ですー。あ、でも他の人に邪魔になるから、そろそろいくわね。兄さんも無茶しないでね」
「ああ。今回の怪我はアンバー部隊長を庇って受けた傷でね。僕としては敬愛する部隊長を守れて、誇りに思っているんだけど、案の定、本人にこってり怒られたよ」
珍しく明るい雰囲気に私はついつい聴き入ってしまっていた。
そこで、あることを思い出す。
「ちょっと、一瞬だけ外すわね」
そう言って、私はアイオラの方へと向かい、声をかけた。
「久しぶりね。アイオラ。ロベリアはその後しっかりやってくれているわ。ところで、あなたに少しだけ教えて欲しいことがあるの」
「これは聖女様。あの節は本当にありがとうございました。おかげでこうしてあなたやロベリアの顔を見ることもできますし、未だに生きています」
「時間があまりないから単刀直入に言うわね。前に私に魔力の練り方を教えてくれたでしょう? あれは、どうやってやるの?」
「え? ああ、あの方法ですか……すいません。まさか聖女様だとはあの時は分からず、生意気を言ってしまって」
アイオラは一瞬驚いた顔をして、それから頭を下げた。
あの時は目が見えなかったし、そもそもアイオラが攻撃魔法用の魔力の練る場所を教えてくれたおかげで、彼を助けることができたのだから、感謝しかない。
「いいのよ。それで、あれは誰でもできるのかしら?」
「ええ。魔力をすでに練ることができる人なら誰でも。練った魔力を、繋いだ手を通して相手に送るんです。相手が力を抜いていれば、その魔力は最も通りやすい場所を通ってから、反対の手に流れます。昔、ロベリアと遊んでいる時に気づいたんですが……」
「ありがとう! 分かったわ。ちょっとやってみるわね。手を貸してくれるかしら?」
「え? ええ。でも、私はもう既に魔力の練り方を知っていますから、今さら……ああ、通すことができるかの確認ですね。それなら知っている相手にやってみた方が間違いが少ない」
そう言いながら、アイオラは私の差し出した両手を握り返した。
さっそく回復魔法を使うための魔力を練り、右手からアイオラの手に通すようイメージする。
すると、確かに手を通してアイオラの身体に私の魔力が流れていく。
よく考えれば、私自身も、魔力を右手から左手へとアイオラの頭の中を通したことがある。
あれは意識的に魔力の流れを制御して、まっすぐ手の間を流していたけれど、今回は送った後のことは、分からない。
少しの時間の差があってから、右手に送った魔力と同じものが、アイオラの手から私の左手へと流れ込んできた。
「どう? できているかしら?」
「え、ええ……できている、と思うんですが。何故か経路も、熱を帯びる場所も違うように思います。普通だとへその下辺りが暖かくなるんですが、今は胸の辺りが暖かくなりました」
「本当? それでいいの。成功よ。ありがとう!」
「え? そうなんですか? なんだか分かりませんが、お役に立てて良かったです。それでは、僕もいつまでもここで休んでいるわけにはいかないので失礼しますね。部隊長を心配させるといけませんから」
そう言うとアイオラは軍式の敬礼をしてから、治療場を後にした。
私は、すぐに戻り治療を再開する。
それを見ていたサルビアが不思議そうな顔を私に向け、質問を投げかけてきた。
「聖女様。あの人ってロベリアのお兄さんですよね? いきなり手を握りしめたりして、どうしたんですか? まさか、聖女様のいい人ですか⁉︎」
「何を馬鹿なこと言っているの。違うわよ。それはそうと、サルビア。魔力が回復したら、ちょっと試したいことがあるの」
不思議そうな顔のままのサルビアに向かって、私は笑みを送った。
「大丈夫! そろそろ魔力が消えかかっているようね。少し休みなさい。でも、私の治療を見ているのよ」
かなりの時間、互いに試行錯誤をしながらサルビアの訓練を続けていたものの、結果は芳しくはなかった。
その主な理由は感覚の違い。
デイジーに解呪の魔法を指導する際には、私の感覚とデイジーの感覚がたまたま似通っていたおかげか、時間はかかったものの、何とか習得してもらうことができた。
しかし、先ほどの解毒の魔法の感覚が大きく違ったように、私とサルビアの感覚には大きな隔たりがあるようだ。
「ごめんなさい。何かいい方法があればいいのだけれど……」
「そんな! 聖女様は一つも悪くありません! こんなに時間を割いて指導いただいているのに、できない私が悪いんです‼︎」
その場に座り込みながら、消耗した魔力を回復させるサルビアがそう言う。
私は首を横に振り、どうにかならないかと思案していた。
やはり一番重要なのは、感覚だ。
デイジーが解呪の魔法を覚えた時も、口頭でだが私が解呪の魔法を使う時の感覚を伝えたことがきっかけだった。
それまで何度やっても失敗していたデイジーだったが、感覚を伝えた途端、何か気づきがあったようで、数日間独自に訓練をしていた。
その後、再び解呪に挑戦し、完全に解呪するまではいかなかったものの、使う際に必要な感覚が掴めたと、喜んでいた。
悩みで気が疎かになっていた矢先、聞き覚えのある声同士の会話がふと耳に入った。
声のする方を見ると、ロベリアが負傷兵として運ばれてきたアイオラと話している。
「兄さん! また怪我をしたの?」
「あはは。そりゃあ、戦闘をしているんだから怪我はいつだってするさ。それに今回は前回みたいな酷いものじゃない。大丈夫だよ」
「そうよね……安心して! 兄さんや他の兵士さんがいくら傷ついたって、聖女様のいるこの部隊がたちまち綺麗さっぱり治しちゃうんだから!」
「そりゃあ頼もしいなぁ。ロベリアも頑張っているみたいだね。さぁさ、仕事中だろう? いつまでも油を売ってないで持ち場に戻るんだよ」
「残念でした! 今は休憩時間ですー。あ、でも他の人に邪魔になるから、そろそろいくわね。兄さんも無茶しないでね」
「ああ。今回の怪我はアンバー部隊長を庇って受けた傷でね。僕としては敬愛する部隊長を守れて、誇りに思っているんだけど、案の定、本人にこってり怒られたよ」
珍しく明るい雰囲気に私はついつい聴き入ってしまっていた。
そこで、あることを思い出す。
「ちょっと、一瞬だけ外すわね」
そう言って、私はアイオラの方へと向かい、声をかけた。
「久しぶりね。アイオラ。ロベリアはその後しっかりやってくれているわ。ところで、あなたに少しだけ教えて欲しいことがあるの」
「これは聖女様。あの節は本当にありがとうございました。おかげでこうしてあなたやロベリアの顔を見ることもできますし、未だに生きています」
「時間があまりないから単刀直入に言うわね。前に私に魔力の練り方を教えてくれたでしょう? あれは、どうやってやるの?」
「え? ああ、あの方法ですか……すいません。まさか聖女様だとはあの時は分からず、生意気を言ってしまって」
アイオラは一瞬驚いた顔をして、それから頭を下げた。
あの時は目が見えなかったし、そもそもアイオラが攻撃魔法用の魔力の練る場所を教えてくれたおかげで、彼を助けることができたのだから、感謝しかない。
「いいのよ。それで、あれは誰でもできるのかしら?」
「ええ。魔力をすでに練ることができる人なら誰でも。練った魔力を、繋いだ手を通して相手に送るんです。相手が力を抜いていれば、その魔力は最も通りやすい場所を通ってから、反対の手に流れます。昔、ロベリアと遊んでいる時に気づいたんですが……」
「ありがとう! 分かったわ。ちょっとやってみるわね。手を貸してくれるかしら?」
「え? ええ。でも、私はもう既に魔力の練り方を知っていますから、今さら……ああ、通すことができるかの確認ですね。それなら知っている相手にやってみた方が間違いが少ない」
そう言いながら、アイオラは私の差し出した両手を握り返した。
さっそく回復魔法を使うための魔力を練り、右手からアイオラの手に通すようイメージする。
すると、確かに手を通してアイオラの身体に私の魔力が流れていく。
よく考えれば、私自身も、魔力を右手から左手へとアイオラの頭の中を通したことがある。
あれは意識的に魔力の流れを制御して、まっすぐ手の間を流していたけれど、今回は送った後のことは、分からない。
少しの時間の差があってから、右手に送った魔力と同じものが、アイオラの手から私の左手へと流れ込んできた。
「どう? できているかしら?」
「え、ええ……できている、と思うんですが。何故か経路も、熱を帯びる場所も違うように思います。普通だとへその下辺りが暖かくなるんですが、今は胸の辺りが暖かくなりました」
「本当? それでいいの。成功よ。ありがとう!」
「え? そうなんですか? なんだか分かりませんが、お役に立てて良かったです。それでは、僕もいつまでもここで休んでいるわけにはいかないので失礼しますね。部隊長を心配させるといけませんから」
そう言うとアイオラは軍式の敬礼をしてから、治療場を後にした。
私は、すぐに戻り治療を再開する。
それを見ていたサルビアが不思議そうな顔を私に向け、質問を投げかけてきた。
「聖女様。あの人ってロベリアのお兄さんですよね? いきなり手を握りしめたりして、どうしたんですか? まさか、聖女様のいい人ですか⁉︎」
「何を馬鹿なこと言っているの。違うわよ。それはそうと、サルビア。魔力が回復したら、ちょっと試したいことがあるの」
不思議そうな顔のままのサルビアに向かって、私は笑みを送った。
しばらくしてから、床に座りながら私の治療を眺めていたサルビアが、立ち上がり、休憩終了を告げる。
「すいません、聖女様。お待たせしました。それにしても……あんなに治療をしたのに、まだ魔力が尽きないなんて。聖女様の魔力の総量は恐ろしいですね……」
「そうかしら? でも、魔力って使っていると自然と増えるでしょう? だから、ここの部隊のみんなだって、前よりもずっと増えているはずよ」
「それでもいつまで経っても聖女様に及ぶ未来が見えません。私が少し増えている間に、聖女はずっと増えてそうな気がして」
「魔力の総量を簡便に測る方法があればいいのだけれど。そうすれば、衛生兵の配備だってもう少し効率よくできる気がするの」
「聖女様は本当にいつも、より良くすることを考えてらっしゃるんですね。頭が下がります。それで、魔力が回復したらやることとはなんでしょうか?」
「ああ! そうだったわ。ごめんなさい。また、少し治療を止めるわね」
私はサルビアの方を向き、先ほどと同じように両手を差し出す。
サルビアはなんだかよく分からないといった顔を見せたが、私が伝えるより前に私の手を握り返してきた。
「さっきと同じことやるんですね? 握りましたが、何をするんです?」
「ええ。そうなの。解呪の魔法の感覚がどうしても口で伝えられないでしょう? だったら、直接身体に教えたらどうかと思って」
「え? 直接身体にですか? どういうことです?」
「今から私が練った解呪の魔法用の魔力をサルビアの身体に送るわ。全身の力を抜いて、楽にしてちょうだい。呼吸を深く。きっと魔力が、胸の辺りを通るはず。その時の感覚を掴んでちょうだい」
私は先ほどのアイオラの時とは違い、解呪の魔法に適した魔力を練り始める。
その魔力を先ほどと同じように右手からサルビアの繋いだ手へと流し込んだ。
少し緊張しているのか、若干抵抗を感じながら、私の魔力がサルビアに流れていくの感じていた。
その瞬間、サルビアの表情が驚いた顔になった。
「わ、わ! なんですか、これ? なんだか、すごく……え、え⁉︎」
私からは分からないけれど、サルビアの身体の中を、私の魔力が流れているのだろう。
左手に魔力が流れてくるの感じ、私は繋いだ手を解いた。
「もういいわ。どう? 何か感じたかしら?」
「え? え、ええ! え……と、ちょっと恥ずかしいんですけど……その……」
「どう感じたかはあなたしか分からないでしょうから無理に説明しなくていいわ。とにかく、それが解呪の魔法のあなたの感覚よ。それを自分でもできるようになれば、解呪の魔法が使えるようになるはず」
「え⁉︎ そうなんですね! 分かりました! 忘れないようにしないと!」
「それじゃあ、後は自主訓練でいいわ。同じ感覚で魔力が練れるようになったら、戻ってきなさい。その時、試すわね」
「分かりました! 失礼します‼︎」
サルビアも軍式の敬礼をすると、駆け足で訓練場へと駆けていった。
それを見送る暇もなく、私は再び治療を開始する。
「待たせたわね。今から治療を開始するわ」
「あ? ああ……お願いします」
【痛み】の呪いを受けて、痛みに苛まれているはずの若い兵士の顔は、何故だか少し紅潮していたように見えた。
☆
「戻りました! 多分……できます‼︎」
しばらくして、再びサルビアが治療場に姿を現した。
満足に満ちた笑顔を見せるサルビアに、私は期待を寄せる。
「それじゃあ、次に来た呪いを受けた負傷兵に、もう一度治療を行ってちょうだい」
「分かりました!」
ほどなくして、【痛み】の呪いを受けた負傷兵が運ばれてきた。
「痛い、痛い痛い痛い‼︎」
「もう少しの辛抱よ。さぁ、サルビア。やってみせて!」
「はい! 分かりました‼︎」
横になる兵士に向かって、サルビアはこれまでと同じように魔力を練り上げ、手に灯った光で呪いの紋様を照らす。
すると、完全にではないが、徐々に呪いの紋様が薄くなっていった。
「痛……けど、そんなに痛くなくなった?」
「よくやったわ! サルビア! これであなたも解呪の魔法を習得したのよ! 後はその感覚を忘れずに、徐々に慣れていくだけだわ!」
「やったぁ! よかったぁ……私、本当にもう無理だと……聖女様にこんなに見てもらってるのに、全然できなくて。才能ないんだって……」
サルビアは目に涙を溜めて、今にも泣き出しそうだ。
今にも抱きしめてあげたいけれど、それは後に取っておくことにした。
「さぁ! まだ完全に治ってないわよ。もう一度」
「はい! 分かりました‼︎」
袖で涙を拭った後、サルビアは再び魔力を練り、呪いの紋様に光を当てる。
二度目の魔法に晒された呪いは、今度こそ跡形もなく消え失せた。
「痛みが……消えた! ありがとう! ありがとうございます‼︎」
「こちらこそ、ありがとう‼︎ 聖女様! 私……私……」
再び目に涙を溜めるサルビアを、今度こそ私は両腕でしっかりと包み込み抱きしめた。
魔力を練ったわけでもないのに、私の胸のあたりに熱を感じた。
「すいません、聖女様。お待たせしました。それにしても……あんなに治療をしたのに、まだ魔力が尽きないなんて。聖女様の魔力の総量は恐ろしいですね……」
「そうかしら? でも、魔力って使っていると自然と増えるでしょう? だから、ここの部隊のみんなだって、前よりもずっと増えているはずよ」
「それでもいつまで経っても聖女様に及ぶ未来が見えません。私が少し増えている間に、聖女はずっと増えてそうな気がして」
「魔力の総量を簡便に測る方法があればいいのだけれど。そうすれば、衛生兵の配備だってもう少し効率よくできる気がするの」
「聖女様は本当にいつも、より良くすることを考えてらっしゃるんですね。頭が下がります。それで、魔力が回復したらやることとはなんでしょうか?」
「ああ! そうだったわ。ごめんなさい。また、少し治療を止めるわね」
私はサルビアの方を向き、先ほどと同じように両手を差し出す。
サルビアはなんだかよく分からないといった顔を見せたが、私が伝えるより前に私の手を握り返してきた。
「さっきと同じことやるんですね? 握りましたが、何をするんです?」
「ええ。そうなの。解呪の魔法の感覚がどうしても口で伝えられないでしょう? だったら、直接身体に教えたらどうかと思って」
「え? 直接身体にですか? どういうことです?」
「今から私が練った解呪の魔法用の魔力をサルビアの身体に送るわ。全身の力を抜いて、楽にしてちょうだい。呼吸を深く。きっと魔力が、胸の辺りを通るはず。その時の感覚を掴んでちょうだい」
私は先ほどのアイオラの時とは違い、解呪の魔法に適した魔力を練り始める。
その魔力を先ほどと同じように右手からサルビアの繋いだ手へと流し込んだ。
少し緊張しているのか、若干抵抗を感じながら、私の魔力がサルビアに流れていくの感じていた。
その瞬間、サルビアの表情が驚いた顔になった。
「わ、わ! なんですか、これ? なんだか、すごく……え、え⁉︎」
私からは分からないけれど、サルビアの身体の中を、私の魔力が流れているのだろう。
左手に魔力が流れてくるの感じ、私は繋いだ手を解いた。
「もういいわ。どう? 何か感じたかしら?」
「え? え、ええ! え……と、ちょっと恥ずかしいんですけど……その……」
「どう感じたかはあなたしか分からないでしょうから無理に説明しなくていいわ。とにかく、それが解呪の魔法のあなたの感覚よ。それを自分でもできるようになれば、解呪の魔法が使えるようになるはず」
「え⁉︎ そうなんですね! 分かりました! 忘れないようにしないと!」
「それじゃあ、後は自主訓練でいいわ。同じ感覚で魔力が練れるようになったら、戻ってきなさい。その時、試すわね」
「分かりました! 失礼します‼︎」
サルビアも軍式の敬礼をすると、駆け足で訓練場へと駆けていった。
それを見送る暇もなく、私は再び治療を開始する。
「待たせたわね。今から治療を開始するわ」
「あ? ああ……お願いします」
【痛み】の呪いを受けて、痛みに苛まれているはずの若い兵士の顔は、何故だか少し紅潮していたように見えた。
☆
「戻りました! 多分……できます‼︎」
しばらくして、再びサルビアが治療場に姿を現した。
満足に満ちた笑顔を見せるサルビアに、私は期待を寄せる。
「それじゃあ、次に来た呪いを受けた負傷兵に、もう一度治療を行ってちょうだい」
「分かりました!」
ほどなくして、【痛み】の呪いを受けた負傷兵が運ばれてきた。
「痛い、痛い痛い痛い‼︎」
「もう少しの辛抱よ。さぁ、サルビア。やってみせて!」
「はい! 分かりました‼︎」
横になる兵士に向かって、サルビアはこれまでと同じように魔力を練り上げ、手に灯った光で呪いの紋様を照らす。
すると、完全にではないが、徐々に呪いの紋様が薄くなっていった。
「痛……けど、そんなに痛くなくなった?」
「よくやったわ! サルビア! これであなたも解呪の魔法を習得したのよ! 後はその感覚を忘れずに、徐々に慣れていくだけだわ!」
「やったぁ! よかったぁ……私、本当にもう無理だと……聖女様にこんなに見てもらってるのに、全然できなくて。才能ないんだって……」
サルビアは目に涙を溜めて、今にも泣き出しそうだ。
今にも抱きしめてあげたいけれど、それは後に取っておくことにした。
「さぁ! まだ完全に治ってないわよ。もう一度」
「はい! 分かりました‼︎」
袖で涙を拭った後、サルビアは再び魔力を練り、呪いの紋様に光を当てる。
二度目の魔法に晒された呪いは、今度こそ跡形もなく消え失せた。
「痛みが……消えた! ありがとう! ありがとうございます‼︎」
「こちらこそ、ありがとう‼︎ 聖女様! 私……私……」
再び目に涙を溜めるサルビアを、今度こそ私は両腕でしっかりと包み込み抱きしめた。
魔力を練ったわけでもないのに、私の胸のあたりに熱を感じた。
サルビアが解呪の魔法を使えるようになり、デイジーと同じ紫色のリボンタイを付けるようになってから、数日経った。
様子を見るための数日だったけれど、どうやら少しくらいなら私の身体も自由になりそうだ。
そこで、計画していた訓練兵たちをさらに鍛え上げる訓練を開始することにした。
ただ、今回は以前よりも上手く、そして早く習得が達成できる確信がある。
アイオラに習い、サルビアで実践した感覚の共有。
これができれば、最も困難な種々の回復魔法の感覚を正確に伝えることができる。
ただ、デイジーやサルビアに試してもらったところ、上手くいかなかった。
どうやら私は苦労なくできたが、人によっては他人に自分の魔力を通すということが極めて困難らしい。
これも練習を繰り返せばそのうち徐々にできるようになると思うが、二人ができるのを悠長に待っている時間の余裕もない。
唯一私以外にできるのはロベリアだったが、彼女は最近回復魔法を使えるようになったばかりで、自身もまだ緑色のリボン帯を巻いている。
「つまり……私がやるのが一番手っ取り早いということね」
私は独り言を呟きながら、訓練兵の待つ訓練場へと向かった。
訓練場には、今回新しく配属された訓練兵の他に、緑色のリボンタイを巻いている衛生兵たちも参加してもらっている。
一列に並んだ彼女たちに、私は一人ずつ目を合わせながら話し始めた。
「今日からあなたたちにはより上位の治癒の魔法、それに解毒の魔法を習得していってもらうわ。ここにいる全員が黄色のリボンタイを付けられるよう、期待しているから頑張ってちょうだい!」
「はい‼︎」
一斉に元気な返事が返ってくる。
私はそれに一度頷き、訓練の具体的な方法を伝える。
「これから一人一人、私と手を握ってもらうわ。私がそれぞれの回復魔法に必要な魔力の感覚を直接身体に伝えていくの。口で説明するより実際にやってみた方が分かるわね。ロベリア。こっちにいらっしゃい」
「はい!」
私に名を呼ばれたロベリアは、少し嬉しそうな顔をして、前に出てきた。
すでに兄のアイオラと魔力循環を遊びとして繰り返し行なっていたロベリアは、十分に慣れている。
受け取る側がどういうふうにすれば良いのか、説明をしなくてもよく分かっているだろうから、見本としては一番適しているだろう。
既に私の前に差し出されている両手を握り返し、説明を続ける。
「あなたたちは、ロベリアと同じように、両手を差し出して、身体の力はできるだけ抜いて。そしてこうやって私があなたたちの両手を握るわ。それじゃあ、ロベリア。今から流すわね。これが、解毒の魔法を扱うときに練る魔力の感覚よ」
「はい……あ、感じます。確かに治癒の魔法とは全然違いますね……それに、さすが聖女様です。私は、こんな大きな魔力、自分では練られせん」
「魔力の総量と同じで、一度に練られる魔力の量も、訓練していけば徐々にだけど増えていくから心配しないで。今は、感覚を覚えることだけに専念してちょうだい」
「はい! 分かりました‼︎」
魔力循環が終わり、私は手を離してから再び訓練兵たちの方を向く。
全員、よく分からないといった顔だが、何をすれば良いのかは伝わっただろう。
「実際に経験しないとこれ以上は上手く伝えることができないけれど、やることはわかったでしょう? ただ私と手を握って身体の力を抜くだけ。さぁ、一人ずついらっしゃい」
「はい!」
向かって右の方から、一人の衛生兵が前に出てくる。
先ほどと同じように、手を差し出させ、それを握りかえす。
「良いかしら? 今から魔力を送るわ。普段魔力を練る感覚と、何が違うのか、しっかり感じてね」
「分かりました。あの、このまま黙っていれば良いんですか? 何もせずに」
「ええ。むしろ何もしないのが最良よ。緊張したりすると上手くいきにくくなるの。一度深呼吸をしましょうか」
「す、すいません! 部隊長と手を握るだなんて! 光栄で緊張しています‼︎」
彼女は結局何度も深呼吸を繰り返し、なんとか自分を落ち着かせようとしていた。
なんだかその仕草がおかしかったが、いつまで経っても緊張は解れないようなので、諦めてこのまま開始する。
「もういいわ。このまま始めましょう」
「す、すいません! わぁ! 私ったら!」
「良いのよ。今回一度きりで全てが分からなくても、できるまで続けましょう。それじゃあ、今度こそ行くわね」
「はい!」
私はロベリアにしたのと同じように解毒の魔法に必要な魔力を練り、彼女の手へと流し込む。
やはり相手が緊張していればしているほど、魔力を流し込むのに抵抗が生じるようだ。
「わ! え⁉︎ なんですかこれ⁉︎ すごっ! うわ?」
「落ち着いて。今あなたの手を通して、私の練った魔力をあなたの身体に流しているの。胸の辺りに熱を帯びるでしょう? それ以外にも、全身で感じる感覚を覚えて」
慣れているロベリアとは違い、初めて人に魔力を流されると、彼女のように驚くのは仕方がないことだと思う。
私も初めて経験した時は、表には出さなかったけれど、奇妙さに驚いたものだ。
少し長めに流した後、私は魔力の循環を止めた。
私が手を離そうとしても、いつまでも手を離さない彼女に、私は優しい口調で言う。
「もう手は離していいのよ」
「え? あ、す、すいません‼︎」
「うふふ。それで、感覚は掴めたかしら?」
「はい! と言いたいところですが、普段自分が練っている魔力とは違うのは分かったんですが、これを自分ですぐ練ろって言われると、できないと思います……」
彼女は少し申し訳なさそうに、答えた。
「大丈夫よ。感覚さえ掴められれば、後は練習でなんとかなるわ。誰もすぐにできるだなんて思ってもいないのよ。さぁ、次に行くわね。代わりなさい」
「はい! ありがとうございました」
こうして、私は一人一人に魔力循環を実施していった。
様子を見るための数日だったけれど、どうやら少しくらいなら私の身体も自由になりそうだ。
そこで、計画していた訓練兵たちをさらに鍛え上げる訓練を開始することにした。
ただ、今回は以前よりも上手く、そして早く習得が達成できる確信がある。
アイオラに習い、サルビアで実践した感覚の共有。
これができれば、最も困難な種々の回復魔法の感覚を正確に伝えることができる。
ただ、デイジーやサルビアに試してもらったところ、上手くいかなかった。
どうやら私は苦労なくできたが、人によっては他人に自分の魔力を通すということが極めて困難らしい。
これも練習を繰り返せばそのうち徐々にできるようになると思うが、二人ができるのを悠長に待っている時間の余裕もない。
唯一私以外にできるのはロベリアだったが、彼女は最近回復魔法を使えるようになったばかりで、自身もまだ緑色のリボン帯を巻いている。
「つまり……私がやるのが一番手っ取り早いということね」
私は独り言を呟きながら、訓練兵の待つ訓練場へと向かった。
訓練場には、今回新しく配属された訓練兵の他に、緑色のリボンタイを巻いている衛生兵たちも参加してもらっている。
一列に並んだ彼女たちに、私は一人ずつ目を合わせながら話し始めた。
「今日からあなたたちにはより上位の治癒の魔法、それに解毒の魔法を習得していってもらうわ。ここにいる全員が黄色のリボンタイを付けられるよう、期待しているから頑張ってちょうだい!」
「はい‼︎」
一斉に元気な返事が返ってくる。
私はそれに一度頷き、訓練の具体的な方法を伝える。
「これから一人一人、私と手を握ってもらうわ。私がそれぞれの回復魔法に必要な魔力の感覚を直接身体に伝えていくの。口で説明するより実際にやってみた方が分かるわね。ロベリア。こっちにいらっしゃい」
「はい!」
私に名を呼ばれたロベリアは、少し嬉しそうな顔をして、前に出てきた。
すでに兄のアイオラと魔力循環を遊びとして繰り返し行なっていたロベリアは、十分に慣れている。
受け取る側がどういうふうにすれば良いのか、説明をしなくてもよく分かっているだろうから、見本としては一番適しているだろう。
既に私の前に差し出されている両手を握り返し、説明を続ける。
「あなたたちは、ロベリアと同じように、両手を差し出して、身体の力はできるだけ抜いて。そしてこうやって私があなたたちの両手を握るわ。それじゃあ、ロベリア。今から流すわね。これが、解毒の魔法を扱うときに練る魔力の感覚よ」
「はい……あ、感じます。確かに治癒の魔法とは全然違いますね……それに、さすが聖女様です。私は、こんな大きな魔力、自分では練られせん」
「魔力の総量と同じで、一度に練られる魔力の量も、訓練していけば徐々にだけど増えていくから心配しないで。今は、感覚を覚えることだけに専念してちょうだい」
「はい! 分かりました‼︎」
魔力循環が終わり、私は手を離してから再び訓練兵たちの方を向く。
全員、よく分からないといった顔だが、何をすれば良いのかは伝わっただろう。
「実際に経験しないとこれ以上は上手く伝えることができないけれど、やることはわかったでしょう? ただ私と手を握って身体の力を抜くだけ。さぁ、一人ずついらっしゃい」
「はい!」
向かって右の方から、一人の衛生兵が前に出てくる。
先ほどと同じように、手を差し出させ、それを握りかえす。
「良いかしら? 今から魔力を送るわ。普段魔力を練る感覚と、何が違うのか、しっかり感じてね」
「分かりました。あの、このまま黙っていれば良いんですか? 何もせずに」
「ええ。むしろ何もしないのが最良よ。緊張したりすると上手くいきにくくなるの。一度深呼吸をしましょうか」
「す、すいません! 部隊長と手を握るだなんて! 光栄で緊張しています‼︎」
彼女は結局何度も深呼吸を繰り返し、なんとか自分を落ち着かせようとしていた。
なんだかその仕草がおかしかったが、いつまで経っても緊張は解れないようなので、諦めてこのまま開始する。
「もういいわ。このまま始めましょう」
「す、すいません! わぁ! 私ったら!」
「良いのよ。今回一度きりで全てが分からなくても、できるまで続けましょう。それじゃあ、今度こそ行くわね」
「はい!」
私はロベリアにしたのと同じように解毒の魔法に必要な魔力を練り、彼女の手へと流し込む。
やはり相手が緊張していればしているほど、魔力を流し込むのに抵抗が生じるようだ。
「わ! え⁉︎ なんですかこれ⁉︎ すごっ! うわ?」
「落ち着いて。今あなたの手を通して、私の練った魔力をあなたの身体に流しているの。胸の辺りに熱を帯びるでしょう? それ以外にも、全身で感じる感覚を覚えて」
慣れているロベリアとは違い、初めて人に魔力を流されると、彼女のように驚くのは仕方がないことだと思う。
私も初めて経験した時は、表には出さなかったけれど、奇妙さに驚いたものだ。
少し長めに流した後、私は魔力の循環を止めた。
私が手を離そうとしても、いつまでも手を離さない彼女に、私は優しい口調で言う。
「もう手は離していいのよ」
「え? あ、す、すいません‼︎」
「うふふ。それで、感覚は掴めたかしら?」
「はい! と言いたいところですが、普段自分が練っている魔力とは違うのは分かったんですが、これを自分ですぐ練ろって言われると、できないと思います……」
彼女は少し申し訳なさそうに、答えた。
「大丈夫よ。感覚さえ掴められれば、後は練習でなんとかなるわ。誰もすぐにできるだなんて思ってもいないのよ。さぁ、次に行くわね。代わりなさい」
「はい! ありがとうございました」
こうして、私は一人一人に魔力循環を実施していった。
この作家の他の作品
表紙を見る
気付くと私は、発売から十年経った今も思い出してはプレイを続ける乙女ゲーム「イストワール〜星恋の七王子」のキャラクターに転生してしまった。
しかもそれはゲーム内でヒロインを執拗に陥れようと画策する悪役令嬢、ミザリー・マリア・ド・ゴール。
本来の主人公であるヒロインがどのルートを通ってもその前に立ちはだかり、最終的には己の行いが招いた破滅の結末を迎える。
私はそんな結末を回避しようと、三年間の学園生活を奔走する。
「王子を味方につける方法を考えなきゃ!」
表紙を見る
精霊に愛された少女は聖女として崇められる。私の住む国で古くからある習わしだ。
驚いたことに私も聖女だと、村の皆の期待を背に王都マーベラに迎えられた。
それなのに……。
「この者が聖女なはずはない! 穢らわしい!」
私よりも何年も前から聖女として称えられているローザ様の一言で、私は国を追放されることになってしまった。
「もし良かったら同行してくれないか?」
隣国に向かう途中で命を救ったやり手の商人アベルに色々と助けてもらうことに。
その隣国では精霊の力を利用する技術を使う者は【錬金術師】と呼ばれていて……。
第五元素エーテルの精霊に愛された私は、生まれた国を追放されたけれど、隣国で天才錬金術師として暮らしていくようです!!
この物語は、国を追放された聖女と、助けたやり手商人との恋愛話です。
追放ものなので、最初の方で3話毎にざまぁ描写があります。
薬の効果を示すためにたまに人が怪我をしますがグロ描写はありません。
作者が化学好きなので、少し趣味が出ますがファンタジー風味を壊すことは無いように気を使っています。
ベリーズファンタジー様から発売されました!!
書籍版は大ボリューム加筆修正しておりますので、ぜひぜひお手にお取りください!!
表紙を見る
勇者パーティの支援職だった私は、自己を超々強化する秘法と言われた魔法を使い、幼女になってしまった。
そんな私の姿を見て、パーティメンバーが決めたのは……
「アリシアちゃん。いい子だからお留守番しててね」
見た目は幼女でも、最強の肉体を手に入れた私は、付いてくるなと言われた手前、こっそりひっそりと陰から元仲間を支援することに決めた。
戦神の愛用していたという神器破城槌を振り回し、神の乗り物だと言うもふもふ神獣と旅を続ける珍道中!
主人公は元は立派な大人ですが、心も体も知能も子供です
基本的にコメディ色が強いです
毎日朝7時に一話分更新します
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…