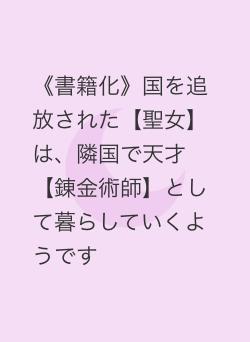「――という訳で、無事に全員の治療を完了しました。死者はゼロです」
運ばれてきた大量の毒に侵された兵士たちの治療を終え、私は司令室に向かい、中でうろうろと歩き回っていたゾイスにそう報告した。
私の報告を聞いたゾイスは、唾を撒き散らしながら私に叫ぶ。
「何が、無事に、だ‼ 無事なんかじゃないよ‼」
「しかし、部隊長の言う、致死率も延べ人数も十分だと認識していますが」
私は平然と述べる。
次に続く言葉は、予想ができた。
「実績を作ってしまったのが問題だ‼ できないことをできないことに文句を言う者はいないが、一度できてしまったことが、次にできなければまずいだろうが‼」
「仰ってる意味が、よく分かりません」
実際のところ、ゾイスが何を考え心配しているかは、理解出来ている。
今回はたまたま私とデイジーが配属された後だったから、解毒が間に合ったのだ。
もし、元々いたサルビアだけでは全員を回復することはできず、対応できなかっただろう。
つまり、もうゾイスは、どんなに私やデイジーが目障りになったとしても、新しい解毒の魔法の使い手が配属されなければ、私たちの治療を拒むことはできない。
「今は幸い解毒をできる者が複数います。今後も積極的に治療に当たれば問題ないかと」
「う……だが! もし君たちに何かあったらどうするつもりだ! 一度受け入れてしまった者を移送するのは出来んのだぞ‼」
正確に言えば、治療不可での別部隊への移送は評価として悪くなるから、できないということだろう。
もっとも、私はそんなことをするつもりは毛頭ない。
かといって、このままずっと三人だけで解毒の治療に専念するつもりもない。
これは布石だった。
「お言葉ですが、実はデイジーはつい最近まで回復魔法を唱えることができませんでした。しかし、今は中級の解毒魔法まで扱うことができます」
「は! そんな馬鹿な話があるわけないだろう! そんな魔法を使えるやつがホイホイ戦場に送られる訳がない。今頃どこかの貴族のお抱えになってるよ」
「信じてもらえないなら、今日一緒に治療に当たったサルビアに聞いてもらっても構いません。彼女は確か初級の解毒魔法しか扱えませんでしたね? それ以上の魔法が必要な兵士が一人も居なかったとでも?」
「ぬ……おい! 誰か‼ 衛生兵のサルビアを呼んでこい! 今すぐにだ‼」
ゾイスが叫ぶと、司令室の外に居た一人の兵士が、慌ててサルビアを呼びに向かった。
その間に、私は話を続ける。
「それで、提案があります。ここの他の衛生兵にも才能がある者がまだいるかもしれません。その者たちに、訓練を行い、解毒魔法を習得させるのはいかがでしょうか?」
「はっ! 何を言い出すかと思えば。誰が教えるっていうんだい。都から使い手を呼んで教鞭でも取ってもらうつもりかい? 一体いくらかかると思っている。そもそもこんな所に来ようと思う物好きなんて居ないさ!」
そんなやり取りをしている間に、呼ばれたサルビアが司令室へと入ってきた。
部隊長のゾイスと副隊長である私が同席している司令室に一人だけ呼び出され、何事かと心配そうな顔をしている。
「ああ。来たようだね。さて。まずは君の嘘をサルビアに証明してもらおうか。サルビア、正直に答えたまえ。これは部隊長命令だ。今日新しく配属されたデイジーとかいう衛生兵が、君より上級な回復魔法を使ったというのは嘘だね?」
「いえ。本当です」
何を聞かれるのかと身構えていたサルビアは、予想外の質問に拍子抜けしたのか、率直にそう答えた。
「うんうん。そうだろう。嘘だっ……なんだって⁉」
「ですから。本当です。デイジーさんと、そこにいらっしゃる副隊長は、私には到底治療できない毒を受けた兵士たちを治療しておりました。間違いありません」
「ば、馬鹿な⁉ もし嘘を言っていたら、ただじゃおかないぞ⁉」
「いえ。私に嘘をつく理由はありせんので」
うろたえるゾイスを一瞥し、私は口を挟む。
これ以上は時間の無駄だ。
「私の話が嘘ではないとこれで証明されたようですね。それで、先ほどの話ですが、衛生兵の訓練を許可いただけるでしょうか?」
「しかし! 誰が教える⁉ 訓練の間、治療の手が足りなくなるだろう!」
「私とデイジーが交代で教えます。治療が疎かにならないよう、そこも私に考えがあります。さあ、どうか許可を」
「ぐぬぬ……もし! 何か問題があれば、君が全ての責任を取りたまえ‼ それが条件だ‼」
私は笑みを作り、一度だけ頷く。
「問題ありません。では、すぐにでも。これで話は終わりですね? 失礼します。サルビアも。あなたには、別の用があるの。一緒に来てくれるかしら?」
「は、はい!」
私はそのまま司令室を出ていく。
サルビアは慌てた様子で、出る際にゾイスに一礼をしてから私の後を追ってくる。
「あ、あの。副隊長。私に用とはなんでしょうか?」
「ええ。今空いている人を集めて、ある物を作ってほしいの。そうね、色は……四つもあれば最初は足りるかしら。必要だったらその時に増やしましょう」
「色、ですか?」
「ええ。さぁ、始めるわよ! 人を集めたら、私の部屋に来てちょうだい。その時、四つの色が異なる布を、できるだけ持ってきて」
私の言葉に、サルビアは戸惑いをにじませた返ことをしてから、他の衛生兵を呼びに行く。
こうして、休憩中や非番だった衛生兵数人が私の部屋に集まった。
「よく来てくれたわね。休んでいるところ申し訳ないけれど、少し手伝って欲しいの」
私の説明で、集まった衛生兵たちは布を細く切り裂いていく。
やがて、色様々な何本もの細い布が出来上がった。
「さぁ。準備はこれで十分よ。ありがとう。これの使い方を説明するから。他のみんなにも説明したいから、治療場に移動しましょう」
運ばれてきた大量の毒に侵された兵士たちの治療を終え、私は司令室に向かい、中でうろうろと歩き回っていたゾイスにそう報告した。
私の報告を聞いたゾイスは、唾を撒き散らしながら私に叫ぶ。
「何が、無事に、だ‼ 無事なんかじゃないよ‼」
「しかし、部隊長の言う、致死率も延べ人数も十分だと認識していますが」
私は平然と述べる。
次に続く言葉は、予想ができた。
「実績を作ってしまったのが問題だ‼ できないことをできないことに文句を言う者はいないが、一度できてしまったことが、次にできなければまずいだろうが‼」
「仰ってる意味が、よく分かりません」
実際のところ、ゾイスが何を考え心配しているかは、理解出来ている。
今回はたまたま私とデイジーが配属された後だったから、解毒が間に合ったのだ。
もし、元々いたサルビアだけでは全員を回復することはできず、対応できなかっただろう。
つまり、もうゾイスは、どんなに私やデイジーが目障りになったとしても、新しい解毒の魔法の使い手が配属されなければ、私たちの治療を拒むことはできない。
「今は幸い解毒をできる者が複数います。今後も積極的に治療に当たれば問題ないかと」
「う……だが! もし君たちに何かあったらどうするつもりだ! 一度受け入れてしまった者を移送するのは出来んのだぞ‼」
正確に言えば、治療不可での別部隊への移送は評価として悪くなるから、できないということだろう。
もっとも、私はそんなことをするつもりは毛頭ない。
かといって、このままずっと三人だけで解毒の治療に専念するつもりもない。
これは布石だった。
「お言葉ですが、実はデイジーはつい最近まで回復魔法を唱えることができませんでした。しかし、今は中級の解毒魔法まで扱うことができます」
「は! そんな馬鹿な話があるわけないだろう! そんな魔法を使えるやつがホイホイ戦場に送られる訳がない。今頃どこかの貴族のお抱えになってるよ」
「信じてもらえないなら、今日一緒に治療に当たったサルビアに聞いてもらっても構いません。彼女は確か初級の解毒魔法しか扱えませんでしたね? それ以上の魔法が必要な兵士が一人も居なかったとでも?」
「ぬ……おい! 誰か‼ 衛生兵のサルビアを呼んでこい! 今すぐにだ‼」
ゾイスが叫ぶと、司令室の外に居た一人の兵士が、慌ててサルビアを呼びに向かった。
その間に、私は話を続ける。
「それで、提案があります。ここの他の衛生兵にも才能がある者がまだいるかもしれません。その者たちに、訓練を行い、解毒魔法を習得させるのはいかがでしょうか?」
「はっ! 何を言い出すかと思えば。誰が教えるっていうんだい。都から使い手を呼んで教鞭でも取ってもらうつもりかい? 一体いくらかかると思っている。そもそもこんな所に来ようと思う物好きなんて居ないさ!」
そんなやり取りをしている間に、呼ばれたサルビアが司令室へと入ってきた。
部隊長のゾイスと副隊長である私が同席している司令室に一人だけ呼び出され、何事かと心配そうな顔をしている。
「ああ。来たようだね。さて。まずは君の嘘をサルビアに証明してもらおうか。サルビア、正直に答えたまえ。これは部隊長命令だ。今日新しく配属されたデイジーとかいう衛生兵が、君より上級な回復魔法を使ったというのは嘘だね?」
「いえ。本当です」
何を聞かれるのかと身構えていたサルビアは、予想外の質問に拍子抜けしたのか、率直にそう答えた。
「うんうん。そうだろう。嘘だっ……なんだって⁉」
「ですから。本当です。デイジーさんと、そこにいらっしゃる副隊長は、私には到底治療できない毒を受けた兵士たちを治療しておりました。間違いありません」
「ば、馬鹿な⁉ もし嘘を言っていたら、ただじゃおかないぞ⁉」
「いえ。私に嘘をつく理由はありせんので」
うろたえるゾイスを一瞥し、私は口を挟む。
これ以上は時間の無駄だ。
「私の話が嘘ではないとこれで証明されたようですね。それで、先ほどの話ですが、衛生兵の訓練を許可いただけるでしょうか?」
「しかし! 誰が教える⁉ 訓練の間、治療の手が足りなくなるだろう!」
「私とデイジーが交代で教えます。治療が疎かにならないよう、そこも私に考えがあります。さあ、どうか許可を」
「ぐぬぬ……もし! 何か問題があれば、君が全ての責任を取りたまえ‼ それが条件だ‼」
私は笑みを作り、一度だけ頷く。
「問題ありません。では、すぐにでも。これで話は終わりですね? 失礼します。サルビアも。あなたには、別の用があるの。一緒に来てくれるかしら?」
「は、はい!」
私はそのまま司令室を出ていく。
サルビアは慌てた様子で、出る際にゾイスに一礼をしてから私の後を追ってくる。
「あ、あの。副隊長。私に用とはなんでしょうか?」
「ええ。今空いている人を集めて、ある物を作ってほしいの。そうね、色は……四つもあれば最初は足りるかしら。必要だったらその時に増やしましょう」
「色、ですか?」
「ええ。さぁ、始めるわよ! 人を集めたら、私の部屋に来てちょうだい。その時、四つの色が異なる布を、できるだけ持ってきて」
私の言葉に、サルビアは戸惑いをにじませた返ことをしてから、他の衛生兵を呼びに行く。
こうして、休憩中や非番だった衛生兵数人が私の部屋に集まった。
「よく来てくれたわね。休んでいるところ申し訳ないけれど、少し手伝って欲しいの」
私の説明で、集まった衛生兵たちは布を細く切り裂いていく。
やがて、色様々な何本もの細い布が出来上がった。
「さぁ。準備はこれで十分よ。ありがとう。これの使い方を説明するから。他のみんなにも説明したいから、治療場に移動しましょう」
「みんな少しだけ手を止めて。聞いてちょうだい」
私はその場にいる全員に聞こえるように声を張る。
指示通り、衛生兵たちは治療を止め、私と四つの色の細く切り裂かれた布を大量に持っている同僚たちに目を向けた。
「なるべく早く済ませるわ。今から私の前に一列に並んで、自分の使うことのできる回復魔法の種類を教えてちょうだい。正直に答えること。いいわね?」
何が始まるのかと、不安げな顔を見せながらも、副隊長の私の命令に従い、一列に並ぶ。
それぞれの申告に応じた色の布を手渡し、私は更に説明を続ける。
「今渡した布を、身体のよく見えるところに巻きつけてちょうだい。分かったと思うけれど、それぞれの色は自分の使える回復魔法の種類、つまり治すことのできる負傷の程度を示しているわ」
今回用意された布の色は、緑、黄、赤、そして紫だ。
緑色は初級の治癒魔法のみ使える者。
黄色は四肢の再生なども可能な者。
赤色はサルビア、紫色はデイジーのみが付けている。
手渡された布を思い思いの場所に付けながら、色の意味は分かったものの、衛生兵たちはまだ釈然としていない顔をしている。
全員に布が行き渡った後、布作りに携わった一人の衛生兵が、私に質問を投げかけてきた。
「副隊長。配り終わりましたが、まだこんなに布が余っています。こんなに作ってどうするんですか?」
「それはね。こうするのよ」
私は、いくつかの布を受け取ると、その場で治療を今かと待ちながら、ことの成り行きを訝しげに見つめる負傷兵たちの元へ向かった。
そして、その傷の程度や、毒の有無によって、布を巻きつけていく。
「さぁ。今つけた色と同じ兵の所へ向かって、治療を再開してちょうだい」
その言葉に多くの者が私の意図を理解できたようで、各々自分が付けた布の色と同じ色を持つ兵の元へと向かい治療を始めた。
それを見ながら、私は残りの兵士にも順に布を巻いていく。
「一体全体。これはなんの意味があるってんだ? あんたが考えたのか? 良かったら教えてくれ」
布を巻きつけ終わる頃、一人の兵士が私に質問してきた。
この兵士の布の色は緑色だ。
「誰が誰に回復魔法をかければいいか。それを分かるための印よ。あなたの色は緑。初級の回復魔法で十分。逆にあっちの彼は赤色。この場で治せる者が少ないから、それができる衛生兵に優先的に見させるの」
「へぇ! そりゃいいや。考えたもんだねぇ。あいつは俺のダチなんだ。どうか、助けてやってくれ。俺は独身だが、あいつにゃ帰りを待つ人が居るんだよ」
私は兵士に微笑みを向けると、次の準備のため、治療場に兵士を受け入れる者たちの元へと足を運ぶ。
そして、今私がしたように、負傷兵の怪我や毒の程度に応じて、受入れの際にそれに応じた色の布を巻くよう指示した。
初めは戸惑っていたものの、しばらく指示を出してどの色を巻くべきか教えていると、私が指示を出さなくても適切な色の布を巻けるようになった。
そして、私は一言だけ付け加える。
「もし、どの色よりも困難な兵士が居たら、布を巻かずにできるだけ速く私の元へ連れてきてちょうだい。いいわね?」
これでひとまずの下地は出来た。
治療の効率は上がり、また、治せる者が治すことが徹底できるだろう。
私は再び治療場に戻ると、治療を続ける衛生兵たちにまた声をかけた。
「今度は手を休めずに聞いてちょうだい。あなたたちに伝えたいことがあるの。今日から、空き時間を使って、回復魔法の訓練を実施するわ。参加は任意。希望する者は、夕方、私の部屋へいらっしゃい」
それだけ言うと、私は赤や紫の布を巻かれた兵士を優先的に治療を始めた。
☆
「副隊長。失礼します」
「入りなさい」
夕方、私の部屋に数人の衛生兵たちが訪れた。
三十人全員が休憩時間な訳ではないが、思っていたより更に少ない。
「よく来たわね。嬉しいわ」
「あ、あの。副隊長。回復魔法の訓練って、本当ですか? あの、私、今より上手になりたい気持ちはあるんですが……あの、お金が無くて……」
その一言に、私は自分のうっかりに気付いた。
人が思ったより少ないのは、恐らく訓練に金が必要だと思ったからだろう。
ここに居る者はほとんどが来る前に自費で回復魔法をなんらかの方法で学んだ者ばかりだ。
無料で教わることができるなどと思いもよらないのだろう。
「説明が不足していたわね。後でみんなにも伝えてくれるかしら。訓練を受けるのに、費用は一切かからないわ」
「ほ、本当ですか⁉ それなら、今すぐにでも習いたいです! 私、初級の魔法しか使えなくて……」
よく見ると、彼女は私が来た時に脚を失った兵士に回復魔法をかけた衛生兵だった。
恐らく本人も、あの行動は本意ではなかったのだろう。
「ええ、もちろんいいわよ。あなたたちもいいのね?」
私の問いに、この部屋に訪れた全員が頷く。
「それじゃあ、早速始めましょう。夕方と、朝方に訓練をするつもりだから出られる方に出て。まずは魔力操作から――」
こうして、この第二衛生兵部隊での回復魔法の訓練が始まった。
初めは数人の参加だったが、緑色だった者が次々に黄色の布に変わるのを見たせいか、徐々に参加者が増えていった。
こうして、いつしか全員が治療の合間を縫って訓練に参加し、布の色を変えていく。
自分や相手の今の状況や、成長が目に見えるからか、第五衛生兵部隊で訓練を実施していたよりも、やる気に満ちているようにも思えた。
私もこの成果に満足しながら、日々の訓練をこなし、また毎日運ばれてくる兵士たちの治療に専念していた。
☆
そんなある日、夜眠れなかったため、外気にあたろうと建物の外に出た時のことだった。
見回りの業務をちょうど終えたクロムと偶然出会した。
クロムは私に気付くと、その人懐っこい顔に笑みを作り、声をかけてくる。
「聖女様! こんな遅くにどうしたんですか?」
「クロム。ご苦労様。少し夜風に当たろうと思ってね。今戻り?」
「ええ。これから戻って寝る所です。陣営の中とはいえ、外は危ないですよ。ましてこんな夜は、魔獣たちの天下ですからね」
「そうね。気を付けないとね。でも、そこら辺を少し歩くだけだから。クロムはおやすみなさい。ゆっくり休んでね」
挨拶をしてその場を去ろうとしたところ、クロムが呼び止めるように声をかけてきた。
私はその声に振り返り、もう一度クロムを見る。
「そんなに長くならないんですよね? それなら、部屋に戻られるまで、俺もお供しますよ」
「あら。悪いわ。本当に大丈夫だから」
「いいえ! 大丈夫なことなんてちっともないですから! ダメって言ってもついて行きますからね。それなら、始めから良いって言ってくれた方がいいと思いませんか?」
「うふふ。分かったわ。それじゃあ、少しの間だけ。よろしく頼むわね」
護衛をお願いした途端、クロムは嬉しそうに握り拳を作ったのが見えた。
私はなんだかその仕草が妙に可笑しくて、声を出して笑ってしまった。
私はその場にいる全員に聞こえるように声を張る。
指示通り、衛生兵たちは治療を止め、私と四つの色の細く切り裂かれた布を大量に持っている同僚たちに目を向けた。
「なるべく早く済ませるわ。今から私の前に一列に並んで、自分の使うことのできる回復魔法の種類を教えてちょうだい。正直に答えること。いいわね?」
何が始まるのかと、不安げな顔を見せながらも、副隊長の私の命令に従い、一列に並ぶ。
それぞれの申告に応じた色の布を手渡し、私は更に説明を続ける。
「今渡した布を、身体のよく見えるところに巻きつけてちょうだい。分かったと思うけれど、それぞれの色は自分の使える回復魔法の種類、つまり治すことのできる負傷の程度を示しているわ」
今回用意された布の色は、緑、黄、赤、そして紫だ。
緑色は初級の治癒魔法のみ使える者。
黄色は四肢の再生なども可能な者。
赤色はサルビア、紫色はデイジーのみが付けている。
手渡された布を思い思いの場所に付けながら、色の意味は分かったものの、衛生兵たちはまだ釈然としていない顔をしている。
全員に布が行き渡った後、布作りに携わった一人の衛生兵が、私に質問を投げかけてきた。
「副隊長。配り終わりましたが、まだこんなに布が余っています。こんなに作ってどうするんですか?」
「それはね。こうするのよ」
私は、いくつかの布を受け取ると、その場で治療を今かと待ちながら、ことの成り行きを訝しげに見つめる負傷兵たちの元へ向かった。
そして、その傷の程度や、毒の有無によって、布を巻きつけていく。
「さぁ。今つけた色と同じ兵の所へ向かって、治療を再開してちょうだい」
その言葉に多くの者が私の意図を理解できたようで、各々自分が付けた布の色と同じ色を持つ兵の元へと向かい治療を始めた。
それを見ながら、私は残りの兵士にも順に布を巻いていく。
「一体全体。これはなんの意味があるってんだ? あんたが考えたのか? 良かったら教えてくれ」
布を巻きつけ終わる頃、一人の兵士が私に質問してきた。
この兵士の布の色は緑色だ。
「誰が誰に回復魔法をかければいいか。それを分かるための印よ。あなたの色は緑。初級の回復魔法で十分。逆にあっちの彼は赤色。この場で治せる者が少ないから、それができる衛生兵に優先的に見させるの」
「へぇ! そりゃいいや。考えたもんだねぇ。あいつは俺のダチなんだ。どうか、助けてやってくれ。俺は独身だが、あいつにゃ帰りを待つ人が居るんだよ」
私は兵士に微笑みを向けると、次の準備のため、治療場に兵士を受け入れる者たちの元へと足を運ぶ。
そして、今私がしたように、負傷兵の怪我や毒の程度に応じて、受入れの際にそれに応じた色の布を巻くよう指示した。
初めは戸惑っていたものの、しばらく指示を出してどの色を巻くべきか教えていると、私が指示を出さなくても適切な色の布を巻けるようになった。
そして、私は一言だけ付け加える。
「もし、どの色よりも困難な兵士が居たら、布を巻かずにできるだけ速く私の元へ連れてきてちょうだい。いいわね?」
これでひとまずの下地は出来た。
治療の効率は上がり、また、治せる者が治すことが徹底できるだろう。
私は再び治療場に戻ると、治療を続ける衛生兵たちにまた声をかけた。
「今度は手を休めずに聞いてちょうだい。あなたたちに伝えたいことがあるの。今日から、空き時間を使って、回復魔法の訓練を実施するわ。参加は任意。希望する者は、夕方、私の部屋へいらっしゃい」
それだけ言うと、私は赤や紫の布を巻かれた兵士を優先的に治療を始めた。
☆
「副隊長。失礼します」
「入りなさい」
夕方、私の部屋に数人の衛生兵たちが訪れた。
三十人全員が休憩時間な訳ではないが、思っていたより更に少ない。
「よく来たわね。嬉しいわ」
「あ、あの。副隊長。回復魔法の訓練って、本当ですか? あの、私、今より上手になりたい気持ちはあるんですが……あの、お金が無くて……」
その一言に、私は自分のうっかりに気付いた。
人が思ったより少ないのは、恐らく訓練に金が必要だと思ったからだろう。
ここに居る者はほとんどが来る前に自費で回復魔法をなんらかの方法で学んだ者ばかりだ。
無料で教わることができるなどと思いもよらないのだろう。
「説明が不足していたわね。後でみんなにも伝えてくれるかしら。訓練を受けるのに、費用は一切かからないわ」
「ほ、本当ですか⁉ それなら、今すぐにでも習いたいです! 私、初級の魔法しか使えなくて……」
よく見ると、彼女は私が来た時に脚を失った兵士に回復魔法をかけた衛生兵だった。
恐らく本人も、あの行動は本意ではなかったのだろう。
「ええ、もちろんいいわよ。あなたたちもいいのね?」
私の問いに、この部屋に訪れた全員が頷く。
「それじゃあ、早速始めましょう。夕方と、朝方に訓練をするつもりだから出られる方に出て。まずは魔力操作から――」
こうして、この第二衛生兵部隊での回復魔法の訓練が始まった。
初めは数人の参加だったが、緑色だった者が次々に黄色の布に変わるのを見たせいか、徐々に参加者が増えていった。
こうして、いつしか全員が治療の合間を縫って訓練に参加し、布の色を変えていく。
自分や相手の今の状況や、成長が目に見えるからか、第五衛生兵部隊で訓練を実施していたよりも、やる気に満ちているようにも思えた。
私もこの成果に満足しながら、日々の訓練をこなし、また毎日運ばれてくる兵士たちの治療に専念していた。
☆
そんなある日、夜眠れなかったため、外気にあたろうと建物の外に出た時のことだった。
見回りの業務をちょうど終えたクロムと偶然出会した。
クロムは私に気付くと、その人懐っこい顔に笑みを作り、声をかけてくる。
「聖女様! こんな遅くにどうしたんですか?」
「クロム。ご苦労様。少し夜風に当たろうと思ってね。今戻り?」
「ええ。これから戻って寝る所です。陣営の中とはいえ、外は危ないですよ。ましてこんな夜は、魔獣たちの天下ですからね」
「そうね。気を付けないとね。でも、そこら辺を少し歩くだけだから。クロムはおやすみなさい。ゆっくり休んでね」
挨拶をしてその場を去ろうとしたところ、クロムが呼び止めるように声をかけてきた。
私はその声に振り返り、もう一度クロムを見る。
「そんなに長くならないんですよね? それなら、部屋に戻られるまで、俺もお供しますよ」
「あら。悪いわ。本当に大丈夫だから」
「いいえ! 大丈夫なことなんてちっともないですから! ダメって言ってもついて行きますからね。それなら、始めから良いって言ってくれた方がいいと思いませんか?」
「うふふ。分かったわ。それじゃあ、少しの間だけ。よろしく頼むわね」
護衛をお願いした途端、クロムは嬉しそうに握り拳を作ったのが見えた。
私はなんだかその仕草が妙に可笑しくて、声を出して笑ってしまった。
「月が綺麗ですねー」
クロムと並び、陣営の中を当てもなく歩いていると、突然空を見上げたクロムがそう言い出した。
釣られて私も目線を上げると、確かに雲ひとつない夜空に、月が煌々と浮かんでいた。
「そうね。ねぇ。クロムは出身はどの辺りなの?」
無言で歩き続けるのもなんだと、思い付いた話題を口に出してみる。
私からの質問に、聞かれた本人は驚いたのか、目を見開いた。
「お、俺ですか。えっと、知っているかどうかわかりませんが、ロメル村っていう小さな村です。ここから北の方にあるマッカーブ山脈の麓にあるんです」
「あら。随分と寒い地域に住んでいたのね」
マッカーブ山脈というのは、この国の最北に連なる山脈で、一年中冠雪している山も多いと聞く。
今は辺りが暗く分かりにくいが、確かに北出身に多い、色白で透き通るような肌と、淡い青緑の瞳をしていたことが記憶から呼び起こされた。
「寒いですよ。冬は村から出ることもできないほどです。そんな暮らしが嫌で、村を飛び出したんですよ。俺」
「まぁ! それは大変だったわね。じゃあ、ここへは志願で?」
「はは。実はそうなんです。本当は街で暮らすつもりだったんですが、上手くいかなくて」
クロムはバツが悪そうに頬をかく。
そこで私は、こんな風に誰かの身の上を聞くのは初めての経験だと気付いた。
私は改めてクロムを見つめる。
それに気付いたのか、クロムは長いまつ毛が生え揃った大きな瞳を瞬かせた。
「あ、あの! 聖女様は、慕っている男性とかはいらっしゃらないんですか⁉」
一瞬の間を置いて、クロムは少し身体を強ばらせながら、上擦った声でそんなことを聞いてきた。
思わぬ質問に、私は少し考え込んでしまう。
慕っている男性というのは、どういう意味の質問だろうか。
会ったことはないが、攻撃や回復魔法の基礎となる魔力に関する著書を書いたオルマン伯爵には、尊敬の念を抱いてる。
しかし、今までの話の流れで、そんなことを聞くような話はあっただろうか。
適切な答えが分からず黙っていると、クロムは痺れを切らしたように、先ほどの自分の言葉を否定し始めた。
「ああ! 今の話は忘れてください! なんでもないんです。俺、何を聞いてるんだろ!」
「あら。そう? ごめんなさいね。いい答えが思い付かなくて――」
そういい切ろうとした瞬間、陣営の見張り台から、敵襲を知らせる合図が鳴り響いた。
私は驚き動きを止めるが、クロムはそんな私を自分の方に引き寄せ、辺りに警戒を向ける。
「聖女様! どうやら敵襲です! 早く建物の中へお戻りください‼」
「え、ええ! クロム、あなたは⁉」
「私は衛兵。この時のために私は居るのです。入口まで送りましょう。さぁ、早く‼」
クロムに手を引かれる形で、私は建物の入口へと走る。
もうすぐ入口へと辿り着くといったところで、目の前に何かが降りてきた。
私は思わず声を上げる。
目に入ったのは、黒い羽を持つ魔獣だった。
「くそっ! ガーゴイルか‼ こいつ、空を飛んで陣営の壁を越えやがった‼」
「クロム! 無理はしないで‼ 増援をっ‼」
しかし、辺りを見渡しても近くに他の兵士の姿はなく、どうにか二人だけで切り抜けなくてはいけなさそうだ。
ガーゴイルと呼ばれる、身体が石のような見た目をした魔獣は、牙が生え揃った裂けた口で威嚇の鳴き声を上げる。
次の瞬間、鋭い爪が生えた腕を突き出し、私を庇うように前に立ったクロムに向かって、身体ごと突進してきた。
しかし、クロムは動じることなく、両手で構えた剣を器用に振るって、ガーゴイルの腕を、そして羽の付け根を切り落とした。
思わぬ反撃をくらいうろたえた様子のガーゴイルを、クロムは縦一文字に切り伏せる。
初めて目の当たりにするクロムの実力に、私は目を白黒させてしまった。
「ふぅ……もう大丈夫です。さぁ、今のうちに中へ‼ 俺は、戻ります。あっちの塀の外に沢山群がって来ているようですから」
「ありがとう、クロム。助かったわ。本当に。でも無理はしないでね。死んでしまってはいくら私でも助けられないわ」
私の言葉にクロムは目を細め、そして軍式の礼をする。
「承知しました‼ 副隊長の命令、必ずや守ってみせます‼」
「ええ。そうしてちょうだい。命令違反は、しないでね」
クロムは一度頷くと、大量の魔獣が押し寄せているであろう、戦闘音が響く方へと走り出した。
私はそれを見送ると、建物の中へと入り、寝ている衛生兵を起こしながら治療場へと向かう。
「聖女様、一体何事ですか?」
今まで寝ていたのか、目を擦りながらデイジーが聞いてくる。
「敵襲よ! 前のようにここが襲われているわ。負傷兵が大量に運ばれる可能性が高いわ。心してちょうだい‼」
「わ、分かりましたぁ‼」
状況が飲み込めたのか、デイジーは一気に目が覚めたようで、治療場へと向かう足を速めた。
私は受入係に布をできるだけ速く、かつ正確に負傷兵に付ける様に指示を出した後、気を引き締め運ばれてくるであろう負傷兵を待ち構えた。
クロムと並び、陣営の中を当てもなく歩いていると、突然空を見上げたクロムがそう言い出した。
釣られて私も目線を上げると、確かに雲ひとつない夜空に、月が煌々と浮かんでいた。
「そうね。ねぇ。クロムは出身はどの辺りなの?」
無言で歩き続けるのもなんだと、思い付いた話題を口に出してみる。
私からの質問に、聞かれた本人は驚いたのか、目を見開いた。
「お、俺ですか。えっと、知っているかどうかわかりませんが、ロメル村っていう小さな村です。ここから北の方にあるマッカーブ山脈の麓にあるんです」
「あら。随分と寒い地域に住んでいたのね」
マッカーブ山脈というのは、この国の最北に連なる山脈で、一年中冠雪している山も多いと聞く。
今は辺りが暗く分かりにくいが、確かに北出身に多い、色白で透き通るような肌と、淡い青緑の瞳をしていたことが記憶から呼び起こされた。
「寒いですよ。冬は村から出ることもできないほどです。そんな暮らしが嫌で、村を飛び出したんですよ。俺」
「まぁ! それは大変だったわね。じゃあ、ここへは志願で?」
「はは。実はそうなんです。本当は街で暮らすつもりだったんですが、上手くいかなくて」
クロムはバツが悪そうに頬をかく。
そこで私は、こんな風に誰かの身の上を聞くのは初めての経験だと気付いた。
私は改めてクロムを見つめる。
それに気付いたのか、クロムは長いまつ毛が生え揃った大きな瞳を瞬かせた。
「あ、あの! 聖女様は、慕っている男性とかはいらっしゃらないんですか⁉」
一瞬の間を置いて、クロムは少し身体を強ばらせながら、上擦った声でそんなことを聞いてきた。
思わぬ質問に、私は少し考え込んでしまう。
慕っている男性というのは、どういう意味の質問だろうか。
会ったことはないが、攻撃や回復魔法の基礎となる魔力に関する著書を書いたオルマン伯爵には、尊敬の念を抱いてる。
しかし、今までの話の流れで、そんなことを聞くような話はあっただろうか。
適切な答えが分からず黙っていると、クロムは痺れを切らしたように、先ほどの自分の言葉を否定し始めた。
「ああ! 今の話は忘れてください! なんでもないんです。俺、何を聞いてるんだろ!」
「あら。そう? ごめんなさいね。いい答えが思い付かなくて――」
そういい切ろうとした瞬間、陣営の見張り台から、敵襲を知らせる合図が鳴り響いた。
私は驚き動きを止めるが、クロムはそんな私を自分の方に引き寄せ、辺りに警戒を向ける。
「聖女様! どうやら敵襲です! 早く建物の中へお戻りください‼」
「え、ええ! クロム、あなたは⁉」
「私は衛兵。この時のために私は居るのです。入口まで送りましょう。さぁ、早く‼」
クロムに手を引かれる形で、私は建物の入口へと走る。
もうすぐ入口へと辿り着くといったところで、目の前に何かが降りてきた。
私は思わず声を上げる。
目に入ったのは、黒い羽を持つ魔獣だった。
「くそっ! ガーゴイルか‼ こいつ、空を飛んで陣営の壁を越えやがった‼」
「クロム! 無理はしないで‼ 増援をっ‼」
しかし、辺りを見渡しても近くに他の兵士の姿はなく、どうにか二人だけで切り抜けなくてはいけなさそうだ。
ガーゴイルと呼ばれる、身体が石のような見た目をした魔獣は、牙が生え揃った裂けた口で威嚇の鳴き声を上げる。
次の瞬間、鋭い爪が生えた腕を突き出し、私を庇うように前に立ったクロムに向かって、身体ごと突進してきた。
しかし、クロムは動じることなく、両手で構えた剣を器用に振るって、ガーゴイルの腕を、そして羽の付け根を切り落とした。
思わぬ反撃をくらいうろたえた様子のガーゴイルを、クロムは縦一文字に切り伏せる。
初めて目の当たりにするクロムの実力に、私は目を白黒させてしまった。
「ふぅ……もう大丈夫です。さぁ、今のうちに中へ‼ 俺は、戻ります。あっちの塀の外に沢山群がって来ているようですから」
「ありがとう、クロム。助かったわ。本当に。でも無理はしないでね。死んでしまってはいくら私でも助けられないわ」
私の言葉にクロムは目を細め、そして軍式の礼をする。
「承知しました‼ 副隊長の命令、必ずや守ってみせます‼」
「ええ。そうしてちょうだい。命令違反は、しないでね」
クロムは一度頷くと、大量の魔獣が押し寄せているであろう、戦闘音が響く方へと走り出した。
私はそれを見送ると、建物の中へと入り、寝ている衛生兵を起こしながら治療場へと向かう。
「聖女様、一体何事ですか?」
今まで寝ていたのか、目を擦りながらデイジーが聞いてくる。
「敵襲よ! 前のようにここが襲われているわ。負傷兵が大量に運ばれる可能性が高いわ。心してちょうだい‼」
「わ、分かりましたぁ‼」
状況が飲み込めたのか、デイジーは一気に目が覚めたようで、治療場へと向かう足を速めた。
私は受入係に布をできるだけ速く、かつ正確に負傷兵に付ける様に指示を出した後、気を引き締め運ばれてくるであろう負傷兵を待ち構えた。
「焦らないで! 今まで通りにやればいいのよ‼」
私は目の前の毒に侵された兵士の治療をしながら、誰にともなくそう叫んだ。
予想していた通り、負傷する兵の数は多く、休んでいた者も含めて全員が対応に当たっていた。
特に今回は大怪我をしたり、毒を受けたりしている兵士が多いため、一定以上の衛生兵に負担が集中していた。
もし訓練を行うのが遅かったり、やっていなかったりすれば、状況はかなり悪くなっていただろう。
「副隊長! 急患です‼ 布なしです‼」
「分かったわ! すぐに行くわ‼」
デイジーでも難しい、瀕死の負傷兵も何人か運ばれてきている。
私がすぐに対応してなんとか一命を取り留めているものの、一度に来たらかなり難しい判断に迫られることになるだろう。
どうやら、負傷した兵士たちのぼやきを聞いていると、兵士の質が悪い訳ではなく、統率がうまくできていないようだ。
衛兵たちの指揮もここの司令官である部隊長の役目なはずだが、司令室にゾイスの姿が見つからないらしい。
それでも、クロムを始め優秀な衛兵のおかげで、徐々に敵勢力の殲滅へと向かってはいるらしい。
幸い、ここの部隊には衛生兵が多く、希望的観測ではあるものの、こちらが潰れるよりも早く事態の収束に向かいそうだ。
「副隊長! また布なしです‼ お願いします‼」
「今いく‼ デイジー‼ こっち代わってちょうだい‼」
それでも今忙しいのには変わりなく、他の衛生兵たちも、次々と運ばれる目の前の兵士たちの治療を必死に行っていた。
治療場は痛みで叫ぶ兵士の声と、治療にあたる私たちの声で満ち、周囲で起きていることには意識を向けることも難しい状態だった。
そんな中、ある事件が起きてしまった。
☆
――陣営内、某所――
「部隊長‼ 今までどこへ⁉」
「そんなことはどうでもいい‼ 腕を切られた! くそっ‼ 忌々しい魔獣め‼」
部隊長の行方を探していた兵士の一人が、目的であるゾイスを見かけて声を上げた。
それに対し、ゾイスは自分の右手を庇いながら叫ぶ。
「何をしておる‼ 早く俺を治療場へ運べ‼ 腕を切られたと言っているだろうが‼」
「は、はい! こちらへ‼」
どうやら、ゾイスは敵襲があった際に建物の外に居たようで、ここへ向かう際に右手の手首から先を切り落とされてしまったようだ。
止血は済んでいるものの、痛みのためか、額には脂汗が滲んでいた。
「部隊長が負傷した! 受け入れを頼む‼」
「何⁉ 分かった! 部隊長。怪我の程度を確認しますから、ひとまずこちらへ」
「確認するまでもないだろう‼ 腕を切られたのが見て分からんのか‼ さっさと治療を始めろ‼ 今すぐにだ‼」
切り落とされた手首の先が無く、受付の判断で再生が必要な黄色の布を無事な左腕に巻かれたゾイスは更に声を上げる。
「なんだこれは‼ そんな訳の分からんことをしている暇があったらさっさと俺を運べ‼ いや! ここに衛生兵を呼んでこい‼ 今すぐにだ! 俺が誰だか分かっているだろうが‼」
「そ、それは……中では今も全員がそれぞれ治療に当たっています。呼ぶとなると時間がかかるかと……」
「馬鹿なことを言うな‼ お前、上官の命令に背くつもりか! 口答えは許さん! さっさと行け‼」
「は、はいぃ‼」
ゾイスの言葉に受付の一人が慌てた様子で治療場に向かい、黄色の布をした衛生兵を探す。
しかし、何処を見ても衛生兵の前には、同じ色を付けた負傷兵が多く運ばれていて、手が空いていそうな者は皆無だった。
運が悪いことに、この時ゾイスの命令を受けた者は、どちらかと言えば気の弱い人間だった。
ゾイスの言葉に逆らい、この治療場に連れてくることもできなければ、大勢の治療を待つ兵士を押し除けて、誰かをゾイスの元へとすぐに連れてくることもできなかった。
そんなことなど知らずに、ゾイスは苦々しい顔をしながら、自分を治療する衛生兵が来るのを待っていた。
しかし、ゾイスの思いとは裏腹に、なかなか衛生兵は訪れない。
そんな中、一人の衛生兵が治療場から出てきた。
それを見つけたゾイスは、怒鳴り声でその衛生兵に叫んだ。
「一体何をしていた‼ いつまで待たせる気だ‼ さっさと俺を治さんか‼」
「え……?」
部隊長であるゾイスに怒鳴られた衛生兵は驚いて動きを止める。
その腕には緑色の布が巻かれていた。
彼女は最近この部隊に配属されてきたばかりの衛生兵で、訓練を積んだ他の衛生兵とは違い、早々に魔力枯渇が訪れ、休憩に向かう途中だった。
不幸は重なり、この時彼女は魔力枯渇に起因する頭痛があり、平常時に比べて思考が緩慢になっていた。
「何を呆けている! お前は衛生兵だろう! さっさと俺の手を治療しろ‼」
「は、はい‼」
怒鳴り声による部隊長命令を受けた新人の彼女は、緊張のあまり深く考えることなく、指示通りに回復魔法を唱えた。
ゾイスの手首の先が淡い光に包まれ、そしてすぐにその光は消えていく。
苛んでいた痛みが無くなったことに満足しながら、ゾイスは自分の右手を目線まで上げた。
そこにはきちんと傷口が塞がれた状態の、手を失ったままの腕先があった。
私は目の前の毒に侵された兵士の治療をしながら、誰にともなくそう叫んだ。
予想していた通り、負傷する兵の数は多く、休んでいた者も含めて全員が対応に当たっていた。
特に今回は大怪我をしたり、毒を受けたりしている兵士が多いため、一定以上の衛生兵に負担が集中していた。
もし訓練を行うのが遅かったり、やっていなかったりすれば、状況はかなり悪くなっていただろう。
「副隊長! 急患です‼ 布なしです‼」
「分かったわ! すぐに行くわ‼」
デイジーでも難しい、瀕死の負傷兵も何人か運ばれてきている。
私がすぐに対応してなんとか一命を取り留めているものの、一度に来たらかなり難しい判断に迫られることになるだろう。
どうやら、負傷した兵士たちのぼやきを聞いていると、兵士の質が悪い訳ではなく、統率がうまくできていないようだ。
衛兵たちの指揮もここの司令官である部隊長の役目なはずだが、司令室にゾイスの姿が見つからないらしい。
それでも、クロムを始め優秀な衛兵のおかげで、徐々に敵勢力の殲滅へと向かってはいるらしい。
幸い、ここの部隊には衛生兵が多く、希望的観測ではあるものの、こちらが潰れるよりも早く事態の収束に向かいそうだ。
「副隊長! また布なしです‼ お願いします‼」
「今いく‼ デイジー‼ こっち代わってちょうだい‼」
それでも今忙しいのには変わりなく、他の衛生兵たちも、次々と運ばれる目の前の兵士たちの治療を必死に行っていた。
治療場は痛みで叫ぶ兵士の声と、治療にあたる私たちの声で満ち、周囲で起きていることには意識を向けることも難しい状態だった。
そんな中、ある事件が起きてしまった。
☆
――陣営内、某所――
「部隊長‼ 今までどこへ⁉」
「そんなことはどうでもいい‼ 腕を切られた! くそっ‼ 忌々しい魔獣め‼」
部隊長の行方を探していた兵士の一人が、目的であるゾイスを見かけて声を上げた。
それに対し、ゾイスは自分の右手を庇いながら叫ぶ。
「何をしておる‼ 早く俺を治療場へ運べ‼ 腕を切られたと言っているだろうが‼」
「は、はい! こちらへ‼」
どうやら、ゾイスは敵襲があった際に建物の外に居たようで、ここへ向かう際に右手の手首から先を切り落とされてしまったようだ。
止血は済んでいるものの、痛みのためか、額には脂汗が滲んでいた。
「部隊長が負傷した! 受け入れを頼む‼」
「何⁉ 分かった! 部隊長。怪我の程度を確認しますから、ひとまずこちらへ」
「確認するまでもないだろう‼ 腕を切られたのが見て分からんのか‼ さっさと治療を始めろ‼ 今すぐにだ‼」
切り落とされた手首の先が無く、受付の判断で再生が必要な黄色の布を無事な左腕に巻かれたゾイスは更に声を上げる。
「なんだこれは‼ そんな訳の分からんことをしている暇があったらさっさと俺を運べ‼ いや! ここに衛生兵を呼んでこい‼ 今すぐにだ! 俺が誰だか分かっているだろうが‼」
「そ、それは……中では今も全員がそれぞれ治療に当たっています。呼ぶとなると時間がかかるかと……」
「馬鹿なことを言うな‼ お前、上官の命令に背くつもりか! 口答えは許さん! さっさと行け‼」
「は、はいぃ‼」
ゾイスの言葉に受付の一人が慌てた様子で治療場に向かい、黄色の布をした衛生兵を探す。
しかし、何処を見ても衛生兵の前には、同じ色を付けた負傷兵が多く運ばれていて、手が空いていそうな者は皆無だった。
運が悪いことに、この時ゾイスの命令を受けた者は、どちらかと言えば気の弱い人間だった。
ゾイスの言葉に逆らい、この治療場に連れてくることもできなければ、大勢の治療を待つ兵士を押し除けて、誰かをゾイスの元へとすぐに連れてくることもできなかった。
そんなことなど知らずに、ゾイスは苦々しい顔をしながら、自分を治療する衛生兵が来るのを待っていた。
しかし、ゾイスの思いとは裏腹に、なかなか衛生兵は訪れない。
そんな中、一人の衛生兵が治療場から出てきた。
それを見つけたゾイスは、怒鳴り声でその衛生兵に叫んだ。
「一体何をしていた‼ いつまで待たせる気だ‼ さっさと俺を治さんか‼」
「え……?」
部隊長であるゾイスに怒鳴られた衛生兵は驚いて動きを止める。
その腕には緑色の布が巻かれていた。
彼女は最近この部隊に配属されてきたばかりの衛生兵で、訓練を積んだ他の衛生兵とは違い、早々に魔力枯渇が訪れ、休憩に向かう途中だった。
不幸は重なり、この時彼女は魔力枯渇に起因する頭痛があり、平常時に比べて思考が緩慢になっていた。
「何を呆けている! お前は衛生兵だろう! さっさと俺の手を治療しろ‼」
「は、はい‼」
怒鳴り声による部隊長命令を受けた新人の彼女は、緊張のあまり深く考えることなく、指示通りに回復魔法を唱えた。
ゾイスの手首の先が淡い光に包まれ、そしてすぐにその光は消えていく。
苛んでいた痛みが無くなったことに満足しながら、ゾイスは自分の右手を目線まで上げた。
そこにはきちんと傷口が塞がれた状態の、手を失ったままの腕先があった。
――治療場――
「おい‼ この腕を治せる奴‼ さっさとこっちへ来て治せ‼」
突然治療場に男の叫び声が響き渡り、私は何事かと声のした方に目を向けた。
声の主は部隊長のゾイスのようで、先がなくなった右手を振り上げ、喚き散らしている。
「部隊長。どうしました? 怪我をしたのなら、並んでいただければ順に治療します……それは……?」
私はゾイスを無視するわけにもいかず、治療の手を休めることなくゾイスに声をかけた。
しかし、振り上げている右手の先がすでに塞がれていることに気付く。
「馬鹿を言うな! そこら辺の雑兵と俺を同格に扱う気か⁉ そもそも、見ろ‼ 馬鹿で無能な衛生兵に治療を任せたら、この様だ」
「回復魔法を……すでにお受けになったのですか? そんなはずは……」
私は目の前の兵士の治療を終え、ゾイスの方へと歩み寄る。
見ればきちんと黄色の布が巻かれている。
この色の衛生兵に治療を任せていれば、再生されずに治療を終えるなどはないはずだ。
しかし、現実はすでに治療を終えていて、再生されぬまま傷口は塞がってしまっている。
問題はこの治療がどれほど前に行われたかだ。
もし十分な時間が過ぎてしまっていては、いかに私でも元に戻すことはできない。
「副隊長。そういえばお前は回復魔法に長けていると言っていたな? 気に食わんが、お前でいい。さっさと俺の腕を元に戻せ!」
「失礼ですが、部隊長。その腕の治療は誰が?」
「知るか! あんな無能の名前など。部隊長である俺の治療もろくにできない無能なら、さっきしこたましごいてやったから、外でぶっ倒れているだろう」
「なんですって⁉ 誰か‼ すぐに見に行って‼」
私の叫び声を聞き、デイジーが真っ先に治療場の外へ向かった。
私はそれを見届けてから、ゾイスの方へと向き合い語気を強めて言い放つ。
「あなたは一体何様のつもりですか⁉ 治療をした兵に暴力を振るうなど‼ そもそも、何故治療場に来なかったのですか⁉ その布の色についても報告書を何度も上げたはずです‼ お読みにならなかったのですか⁉」
「うるさい! 俺に口答えする気か⁉ お前が一体誰に取り入ったのか知らんが、俺を怒らせるとただじゃ済まないぞ⁉ 俺の後ろにはモリアゲート伯爵様がついているんだからな⁉」
モリアゲート伯爵と聞いて、私は記憶の隅にある貴族たちの名前を思い出す。
確か、モリアゲート伯爵は戦線から最も近い所に領地を持つ辺境伯で、随分な野心家だと知られている人物だ。
この魔王討伐軍の中でもかなりの役職についていて発言権がある人物だというのは間違い無いだろう。
だがそれがなんだというのだろう。
「後ろに誰が居ようと関係ありません。残念ながら、もうその腕の再生は不可能です」
「な、なんだと⁉ ふざけるな‼ いい加減なことをぬかしおって‼ もういい! おい! 誰でもいい‼ この腕を治した者には報奨金を出すぞ‼」
ゾイスが右腕を上にかざしながらそう叫ぶが、誰も前に出る者は居ない。
すでに固定化が済んでしまった傷を治すことなど誰にとっても不可能なのだ。
もし、ゾイスが治療の不備に気付いた時に、すぐここへ向かっていれば可能だったかもしれない。
しかしその最後の機会を、この男はあろう事か治療に当たった衛生兵の折檻の時間に費やしてしまった。
同情の余地はもはやないだろう。
自らの行いが招いた結果だ。
いずれにしろ、私にできることはない。
これ以上、ゾイスに付き合って他の兵士の治療の邪魔をするわけにもいかない。
「お分かりいただけましたか? ここに居る、いえ。世界中どこを探したとしても、一度固定化した傷を元に戻せる者は居ないのです。さぁ、部隊長へできる治療は済んでいます。お言葉ですが、他の兵の治療の妨げになるので。お引き取りを」
「ぐぬぬ……ふざけるなっ! お前たちも‼ 俺に逆らってどうなるか。思い知らせてやるかな‼ 覚えておけ‼」
「誰が、何を思い知らせてやるのかな? ゾイス部隊長殿」
激昂したゾイスに向かって、凛とした女性の声が響いた。
私も含め多くの者が、その聞く者に強制力を持つような声の主へと目を向けた。
そこには数々の勲章を付けた、凛々しい顔付きの女性が立っていた。
ふと、面識がないにも関わらず、私の頭の中に一人の女性の名前が浮かんだ。
「お前は、ダリア‼ こんな所に何故お前が⁉」
「おいおい。お前に呼び捨てされるほど仲が良かった覚えはないんだけどな。何故こんな所に居るかだと? 部隊長のお前がここに居ると聞いたから、わざわざ足を運んだのではないか」
ダリアと呼ばれた女性は流れるような動きでゾイスの元まで近付くと、ゾイスを一瞥してため息をつく。
恐らくこの女性はダリア・パルフェ。
アンバーから聞いた第一攻撃部隊の部隊長だろう。
にこやかな笑みを浮かべているが、薄寒いような圧力を感じる。
「最近後衛の陣営を魔獣が襲う事態が多発している。新しい総司令官がそのことを気にしていてな。私が良い案があると古い友人を紹介した所、採用され、襲われた陣営には即座に近い部隊が救援に向かうようになったのだがな」
「そ、そんな報告は聞いていないぞ⁉ そもそも! 主戦力であるお前の部隊がわざわざここに赴くとはどういうことだ⁉」
ダリアの説明にゾイスはうろたえながら、疑問を投げかける。
確かに最前線で戦いを繰り広げているはずの部隊の長が来るのは不思議だった。
「まぁ、聴け。私の古い友人なんだが、重い怪我を患っていてな。ああ。心配はいらない。もうすでに完治したらしい。喜ばしいことだ」
「なんの話だ! 何を言っている?」
「その友人の怪我を治してくれた聖女様が、この部隊に配属になったようだ。友人の恩人だ。放っておけずに来てしまった。という訳だ」
「聖女様だと⁉」
ダリアの話を聞いて、アンバーのことを思い出す。
恐らく、使い魔を伝令代わりに使っているのだろう。
その後もダリアはゾイスに状況を説明していた。
指揮を執るはずのゾイスの行方が分からなかったせいで、多くの兵士が無駄な負傷を受けたこと。
ダリアの指揮と活躍により、すでに魔獣の群れの討伐は完了していること。
その言葉を聞いた時には、その場にいる多くの兵が安堵の表情になった。
そして、最後にダリアの口から、とんでもないことが発せられた。
それを聞いた時、衛生兵の何人かは心当たりがあるのか、視線を下げていた。
「以上のように、危機はあったものの、魔獣は撃退した。しかしだ。ゾイス殿。お前は何をしていたのだ? いや、答えなくて良い。どうせ答えられないだろう。ここに証人が居る。この娘だ。見覚えが無い、とは言わせないぞ?」
ダリアはそう言いながら一人の衛生兵を指差した。
彼女は少し身をこわばらせている。
「どうやら他にもいるようだが……この娘に、立場を利用して暴行を働こうとしていたらしいな? しかも、魔獣が現れた時は、この娘を置き去りにして逃げ出したのだとか。まったく。どこまでもクズめ」
「し、知らん‼ 俺はそんなこと知らんぞ‼」
「見苦しいぞ。今回のことも含めてお前が今までやって来たことは報告済みだ。使い魔というのは便利なものでな。すでにお前の処遇については決定されている」
「ふ、ふざけるなぁ! そうだ! これは罠だ‼ 誰かが俺を陥れようとした罠だぁ‼ うぉぉぉおおお‼」
支離滅裂なことを言いながら、ゾイスはダリアに向かって突進をした。
しかし、ダリアはそんな突然の出来ことに眉一つ動かさず、一撃の元にゾイスを地に伏せさせた。
「おい‼ この腕を治せる奴‼ さっさとこっちへ来て治せ‼」
突然治療場に男の叫び声が響き渡り、私は何事かと声のした方に目を向けた。
声の主は部隊長のゾイスのようで、先がなくなった右手を振り上げ、喚き散らしている。
「部隊長。どうしました? 怪我をしたのなら、並んでいただければ順に治療します……それは……?」
私はゾイスを無視するわけにもいかず、治療の手を休めることなくゾイスに声をかけた。
しかし、振り上げている右手の先がすでに塞がれていることに気付く。
「馬鹿を言うな! そこら辺の雑兵と俺を同格に扱う気か⁉ そもそも、見ろ‼ 馬鹿で無能な衛生兵に治療を任せたら、この様だ」
「回復魔法を……すでにお受けになったのですか? そんなはずは……」
私は目の前の兵士の治療を終え、ゾイスの方へと歩み寄る。
見ればきちんと黄色の布が巻かれている。
この色の衛生兵に治療を任せていれば、再生されずに治療を終えるなどはないはずだ。
しかし、現実はすでに治療を終えていて、再生されぬまま傷口は塞がってしまっている。
問題はこの治療がどれほど前に行われたかだ。
もし十分な時間が過ぎてしまっていては、いかに私でも元に戻すことはできない。
「副隊長。そういえばお前は回復魔法に長けていると言っていたな? 気に食わんが、お前でいい。さっさと俺の腕を元に戻せ!」
「失礼ですが、部隊長。その腕の治療は誰が?」
「知るか! あんな無能の名前など。部隊長である俺の治療もろくにできない無能なら、さっきしこたましごいてやったから、外でぶっ倒れているだろう」
「なんですって⁉ 誰か‼ すぐに見に行って‼」
私の叫び声を聞き、デイジーが真っ先に治療場の外へ向かった。
私はそれを見届けてから、ゾイスの方へと向き合い語気を強めて言い放つ。
「あなたは一体何様のつもりですか⁉ 治療をした兵に暴力を振るうなど‼ そもそも、何故治療場に来なかったのですか⁉ その布の色についても報告書を何度も上げたはずです‼ お読みにならなかったのですか⁉」
「うるさい! 俺に口答えする気か⁉ お前が一体誰に取り入ったのか知らんが、俺を怒らせるとただじゃ済まないぞ⁉ 俺の後ろにはモリアゲート伯爵様がついているんだからな⁉」
モリアゲート伯爵と聞いて、私は記憶の隅にある貴族たちの名前を思い出す。
確か、モリアゲート伯爵は戦線から最も近い所に領地を持つ辺境伯で、随分な野心家だと知られている人物だ。
この魔王討伐軍の中でもかなりの役職についていて発言権がある人物だというのは間違い無いだろう。
だがそれがなんだというのだろう。
「後ろに誰が居ようと関係ありません。残念ながら、もうその腕の再生は不可能です」
「な、なんだと⁉ ふざけるな‼ いい加減なことをぬかしおって‼ もういい! おい! 誰でもいい‼ この腕を治した者には報奨金を出すぞ‼」
ゾイスが右腕を上にかざしながらそう叫ぶが、誰も前に出る者は居ない。
すでに固定化が済んでしまった傷を治すことなど誰にとっても不可能なのだ。
もし、ゾイスが治療の不備に気付いた時に、すぐここへ向かっていれば可能だったかもしれない。
しかしその最後の機会を、この男はあろう事か治療に当たった衛生兵の折檻の時間に費やしてしまった。
同情の余地はもはやないだろう。
自らの行いが招いた結果だ。
いずれにしろ、私にできることはない。
これ以上、ゾイスに付き合って他の兵士の治療の邪魔をするわけにもいかない。
「お分かりいただけましたか? ここに居る、いえ。世界中どこを探したとしても、一度固定化した傷を元に戻せる者は居ないのです。さぁ、部隊長へできる治療は済んでいます。お言葉ですが、他の兵の治療の妨げになるので。お引き取りを」
「ぐぬぬ……ふざけるなっ! お前たちも‼ 俺に逆らってどうなるか。思い知らせてやるかな‼ 覚えておけ‼」
「誰が、何を思い知らせてやるのかな? ゾイス部隊長殿」
激昂したゾイスに向かって、凛とした女性の声が響いた。
私も含め多くの者が、その聞く者に強制力を持つような声の主へと目を向けた。
そこには数々の勲章を付けた、凛々しい顔付きの女性が立っていた。
ふと、面識がないにも関わらず、私の頭の中に一人の女性の名前が浮かんだ。
「お前は、ダリア‼ こんな所に何故お前が⁉」
「おいおい。お前に呼び捨てされるほど仲が良かった覚えはないんだけどな。何故こんな所に居るかだと? 部隊長のお前がここに居ると聞いたから、わざわざ足を運んだのではないか」
ダリアと呼ばれた女性は流れるような動きでゾイスの元まで近付くと、ゾイスを一瞥してため息をつく。
恐らくこの女性はダリア・パルフェ。
アンバーから聞いた第一攻撃部隊の部隊長だろう。
にこやかな笑みを浮かべているが、薄寒いような圧力を感じる。
「最近後衛の陣営を魔獣が襲う事態が多発している。新しい総司令官がそのことを気にしていてな。私が良い案があると古い友人を紹介した所、採用され、襲われた陣営には即座に近い部隊が救援に向かうようになったのだがな」
「そ、そんな報告は聞いていないぞ⁉ そもそも! 主戦力であるお前の部隊がわざわざここに赴くとはどういうことだ⁉」
ダリアの説明にゾイスはうろたえながら、疑問を投げかける。
確かに最前線で戦いを繰り広げているはずの部隊の長が来るのは不思議だった。
「まぁ、聴け。私の古い友人なんだが、重い怪我を患っていてな。ああ。心配はいらない。もうすでに完治したらしい。喜ばしいことだ」
「なんの話だ! 何を言っている?」
「その友人の怪我を治してくれた聖女様が、この部隊に配属になったようだ。友人の恩人だ。放っておけずに来てしまった。という訳だ」
「聖女様だと⁉」
ダリアの話を聞いて、アンバーのことを思い出す。
恐らく、使い魔を伝令代わりに使っているのだろう。
その後もダリアはゾイスに状況を説明していた。
指揮を執るはずのゾイスの行方が分からなかったせいで、多くの兵士が無駄な負傷を受けたこと。
ダリアの指揮と活躍により、すでに魔獣の群れの討伐は完了していること。
その言葉を聞いた時には、その場にいる多くの兵が安堵の表情になった。
そして、最後にダリアの口から、とんでもないことが発せられた。
それを聞いた時、衛生兵の何人かは心当たりがあるのか、視線を下げていた。
「以上のように、危機はあったものの、魔獣は撃退した。しかしだ。ゾイス殿。お前は何をしていたのだ? いや、答えなくて良い。どうせ答えられないだろう。ここに証人が居る。この娘だ。見覚えが無い、とは言わせないぞ?」
ダリアはそう言いながら一人の衛生兵を指差した。
彼女は少し身をこわばらせている。
「どうやら他にもいるようだが……この娘に、立場を利用して暴行を働こうとしていたらしいな? しかも、魔獣が現れた時は、この娘を置き去りにして逃げ出したのだとか。まったく。どこまでもクズめ」
「し、知らん‼ 俺はそんなこと知らんぞ‼」
「見苦しいぞ。今回のことも含めてお前が今までやって来たことは報告済みだ。使い魔というのは便利なものでな。すでにお前の処遇については決定されている」
「ふ、ふざけるなぁ! そうだ! これは罠だ‼ 誰かが俺を陥れようとした罠だぁ‼ うぉぉぉおおお‼」
支離滅裂なことを言いながら、ゾイスはダリアに向かって突進をした。
しかし、ダリアはそんな突然の出来ことに眉一つ動かさず、一撃の元にゾイスを地に伏せさせた。
「色々騒がせて済まなかったな」
ゾイスの取り押さえなどで、一時治療場は神妙な雰囲気に包まれた。
そんな中、その間も負傷兵の治療を続けていた私の元に、再びダリアがやって来た。
「いえ。こちらこそ。事態の収拾、感謝します」
「ふむ。一応確認したい。アンバーの呪いを君が解いたというのは間違いないか?」
ダリアの口から以前の上官の名前が出て、改めて私の予想が正しかったのが証明された。
残念なことに使い魔については結局教わることが出来なかったが、確かにあの能力は伝達には有用だろう。
別の部隊とはいえ、上位に当たる者に対して失礼と思うものの、治療の最中だったため顔だけを向けて私は答えた。
「はい。もし、おっしゃる方が第五衛生兵部隊の部隊長のことならば、間違いありません」
「そうか。あいつも私も半ば諦めていたんだ。旧友を救ってくれて私も感謝している。ありがとう。それにしても、よくあいつが治療を依頼するほどの信頼を得られたな?」
「いえ。アンバー部隊長から依頼された訳ではありません。私が無理やり治療を行いました」
「なんだと?」
私の返答を聞いた途端、ダリアは目を丸くした。
「あっはっは! これは良い! あいつを無理やりにか! それはさぞ見ものだっただろう。私もその場で見ていたかったものだな」
「部隊長は……ゾイスは今度どうなるのですか?」
盛大に笑って涙を滲ませるダリアに向かって、私は気になっていることを素直に聞いてみた。
その途端、ダリアの顔から笑みが消え、険しい怒気のようなものが発せられた。
「ひとまず、色々と調べ上げたことに間違いが無いか取り調べを行う」
「そうですか……次の部隊長がまともな方であれば良いのですが……」
恐らくゾイスは私の思いもよらぬことを色々としていたのだろう。
ダリアがここに来たというのも、口では私のことを言っていたが、本当は最初からゾイスが目当てだったに違いない。
ただ、前線の英雄たる彼女がわざわざ出向くほどの大それたことをゾイスがしていたとも考えにくい。
彼女が来たという理由に、私に用があったというのもあながち嘘ではないのかもしれない。
「何を言っている? 自分で自分の心配をしてもしょうがないだろう」
「それは、どういう意味でしょうか?」
「言葉通りの意味だ。自分がまともかどうかは、自分が一番よく分かっているだろう」
そう言いながら、ダリアは笑みを私に向けながら話を続けた。
「さっき言った通り、ゾイスは今回の件で正式に任を解かれた。部隊長不在の際は、副隊長がその任を代理するとは知らなかったのか?」
そういえば、この部隊に来る際に目を通した資料の中にそんな内容が書かれていたのを思い出す。
まさかそんな事態が実際に起こるとは思っていなかったから、頭の片隅に追いやってしまっていた。
「ところで、だ。実は今回私が来たのは他にも用件があるのだ。少し込み入った話になる。君も今は忙しいだろう。私はもう少しだけここに滞在する予定だ。手が空いたら、司令室に来てくれ」
「分かりました。あなたのおかげで既に新しく運ばれてくる兵士はほとんどいないようです。できるだけすぐに向かいますので」
私のその返ことを聞くと、ダリアは再び笑みを私に向け、治療場から去っていった。
治療場に残った私は、緊急性の高い負傷兵の治療を終えると、デイジーたちに後を託して司令室に向かった。
☆
「お待たせしました」
「思ったより早かったな。入ってくれ」
私は司令室に入ると、ダリアの他に思いもよらない見知った人物が居たことに目を止めた。
「アンバー部隊長! どうしてここに⁉」
「やぁ。久しぶりだね。聖女様。元気そうで何よりだ」
「なんだ、アンバー。本当に彼女を聖女様と呼んでいるのだな。私も呼ばなければ失礼に当たるか?」
「とんでもない。ダリア部隊長。お戯れを」
いたずらっぽく笑みを浮かべながらそう言うダリアを否定しながら、私はアンバーに顔を向け、質問の返事を待つ。
アンバーは髪を撫でつけながら、ダリアの方に一度顔を向け、口を開いた。
「どうしてもこうしてもさ。めんどくさい仕事を頼まれちゃったんだよ。聖女様も関係するんだけどね」
「アンバー。お前と違って未だに私は忙しいんだ。私の方から簡潔に説明させてもらうぞ」
そう言いながら、ダリアは説明を始めた。
ダリアの説明を聞き、私はこの決定の裏にはベリル王子が深く絡んでいるのだろうと考えていた。
なんと、私とアンバー、そしてダリアでそれぞれの訓練部隊の育成を命じられたというのだ。
ダリアは近接主体の戦闘を、アンバーは攻撃魔法をそれぞれ育成するらしい。
そして、私は回復魔法の使い手、つまり衛生兵の育成の任を与えられた。
それも、前線で実際の負傷兵の治療を行いながら訓練を行うとのことだった。
「衛生兵の育成に関しては異存ありませんが、色々と疑問点があります」
「何故、育成を前線で行うか、私やアンバーも育成に当たるのかか?」
ダリアは私の疑問にこう答えた。
どうやら、ゾイスが負傷兵に不完全な治療を施していたのは、本人は知らずとも狙いがあってのことだったらしい。
実戦を積んだ兵士は、模擬戦などで訓練をした兵士よりも速く成長する。
しかしいずれは怪我を負い、もし適切な治療が受けられなければ、兵士としては使い物にならなくなる。
せっかく育った兵士が戦場を去っていく。
このことが魔王軍との戦争が長引いている理由の一つだった。
つまり、戦争を長引かせることを望んでいる者が居たのだ。
その人物は、先ほどゾイスから聞いたばかりだった。
「モリアゲート伯爵に疑いの目を向けられぬよう、そして邪魔をされぬよう。私たち三人で精鋭部隊を作り上げるのだよ」
そう答えたダリアの目には怒りの火が燃えていた。
ゾイスの取り押さえなどで、一時治療場は神妙な雰囲気に包まれた。
そんな中、その間も負傷兵の治療を続けていた私の元に、再びダリアがやって来た。
「いえ。こちらこそ。事態の収拾、感謝します」
「ふむ。一応確認したい。アンバーの呪いを君が解いたというのは間違いないか?」
ダリアの口から以前の上官の名前が出て、改めて私の予想が正しかったのが証明された。
残念なことに使い魔については結局教わることが出来なかったが、確かにあの能力は伝達には有用だろう。
別の部隊とはいえ、上位に当たる者に対して失礼と思うものの、治療の最中だったため顔だけを向けて私は答えた。
「はい。もし、おっしゃる方が第五衛生兵部隊の部隊長のことならば、間違いありません」
「そうか。あいつも私も半ば諦めていたんだ。旧友を救ってくれて私も感謝している。ありがとう。それにしても、よくあいつが治療を依頼するほどの信頼を得られたな?」
「いえ。アンバー部隊長から依頼された訳ではありません。私が無理やり治療を行いました」
「なんだと?」
私の返答を聞いた途端、ダリアは目を丸くした。
「あっはっは! これは良い! あいつを無理やりにか! それはさぞ見ものだっただろう。私もその場で見ていたかったものだな」
「部隊長は……ゾイスは今度どうなるのですか?」
盛大に笑って涙を滲ませるダリアに向かって、私は気になっていることを素直に聞いてみた。
その途端、ダリアの顔から笑みが消え、険しい怒気のようなものが発せられた。
「ひとまず、色々と調べ上げたことに間違いが無いか取り調べを行う」
「そうですか……次の部隊長がまともな方であれば良いのですが……」
恐らくゾイスは私の思いもよらぬことを色々としていたのだろう。
ダリアがここに来たというのも、口では私のことを言っていたが、本当は最初からゾイスが目当てだったに違いない。
ただ、前線の英雄たる彼女がわざわざ出向くほどの大それたことをゾイスがしていたとも考えにくい。
彼女が来たという理由に、私に用があったというのもあながち嘘ではないのかもしれない。
「何を言っている? 自分で自分の心配をしてもしょうがないだろう」
「それは、どういう意味でしょうか?」
「言葉通りの意味だ。自分がまともかどうかは、自分が一番よく分かっているだろう」
そう言いながら、ダリアは笑みを私に向けながら話を続けた。
「さっき言った通り、ゾイスは今回の件で正式に任を解かれた。部隊長不在の際は、副隊長がその任を代理するとは知らなかったのか?」
そういえば、この部隊に来る際に目を通した資料の中にそんな内容が書かれていたのを思い出す。
まさかそんな事態が実際に起こるとは思っていなかったから、頭の片隅に追いやってしまっていた。
「ところで、だ。実は今回私が来たのは他にも用件があるのだ。少し込み入った話になる。君も今は忙しいだろう。私はもう少しだけここに滞在する予定だ。手が空いたら、司令室に来てくれ」
「分かりました。あなたのおかげで既に新しく運ばれてくる兵士はほとんどいないようです。できるだけすぐに向かいますので」
私のその返ことを聞くと、ダリアは再び笑みを私に向け、治療場から去っていった。
治療場に残った私は、緊急性の高い負傷兵の治療を終えると、デイジーたちに後を託して司令室に向かった。
☆
「お待たせしました」
「思ったより早かったな。入ってくれ」
私は司令室に入ると、ダリアの他に思いもよらない見知った人物が居たことに目を止めた。
「アンバー部隊長! どうしてここに⁉」
「やぁ。久しぶりだね。聖女様。元気そうで何よりだ」
「なんだ、アンバー。本当に彼女を聖女様と呼んでいるのだな。私も呼ばなければ失礼に当たるか?」
「とんでもない。ダリア部隊長。お戯れを」
いたずらっぽく笑みを浮かべながらそう言うダリアを否定しながら、私はアンバーに顔を向け、質問の返事を待つ。
アンバーは髪を撫でつけながら、ダリアの方に一度顔を向け、口を開いた。
「どうしてもこうしてもさ。めんどくさい仕事を頼まれちゃったんだよ。聖女様も関係するんだけどね」
「アンバー。お前と違って未だに私は忙しいんだ。私の方から簡潔に説明させてもらうぞ」
そう言いながら、ダリアは説明を始めた。
ダリアの説明を聞き、私はこの決定の裏にはベリル王子が深く絡んでいるのだろうと考えていた。
なんと、私とアンバー、そしてダリアでそれぞれの訓練部隊の育成を命じられたというのだ。
ダリアは近接主体の戦闘を、アンバーは攻撃魔法をそれぞれ育成するらしい。
そして、私は回復魔法の使い手、つまり衛生兵の育成の任を与えられた。
それも、前線で実際の負傷兵の治療を行いながら訓練を行うとのことだった。
「衛生兵の育成に関しては異存ありませんが、色々と疑問点があります」
「何故、育成を前線で行うか、私やアンバーも育成に当たるのかか?」
ダリアは私の疑問にこう答えた。
どうやら、ゾイスが負傷兵に不完全な治療を施していたのは、本人は知らずとも狙いがあってのことだったらしい。
実戦を積んだ兵士は、模擬戦などで訓練をした兵士よりも速く成長する。
しかしいずれは怪我を負い、もし適切な治療が受けられなければ、兵士としては使い物にならなくなる。
せっかく育った兵士が戦場を去っていく。
このことが魔王軍との戦争が長引いている理由の一つだった。
つまり、戦争を長引かせることを望んでいる者が居たのだ。
その人物は、先ほどゾイスから聞いたばかりだった。
「モリアゲート伯爵に疑いの目を向けられぬよう、そして邪魔をされぬよう。私たち三人で精鋭部隊を作り上げるのだよ」
そう答えたダリアの目には怒りの火が燃えていた。
「それじゃあ、今日からよろしく頼むわね」
「はいっ! よろしくお願いします‼」
私は目の前に並ぶ女性たち、新しく配属された衛生兵の卵たちに向かって声をかける。
彼女たちは、みな首元に白いスカーフをリボンタイの様に巻いている。
腕に巻いていた布を、ある衛生兵がスカーフにして首元に巻いたらどうかと提案したのが始めだった。
その案はその場に居た衛生兵全員に支持され、やがて裁縫が得意な者たちが切れ端を綺麗に形取りスカーフにした。
それが、ここで回復魔法を学ぶために集まった彼女たちにも普及したのだ。
白はまだ回復魔法を扱うことの出来ない、訓練生を意味した。
「これから、あなたたちは先輩の元につき、実際の治療に携わりながら、自身も回復魔法を使えるように訓練を受けてもらいます。何か質問は?」
「あの……部隊長。もし回復魔法を扱うことが出来なかったらどうなるのでしょうか……?」
訓練生の一人がおずおずと手を挙げ、心配そうに質問を口にした。
私はその衛生兵の方に目を向ける。
栗色の真っ直ぐな髪の毛を肩ほどまで伸ばし、深緑色の瞳で私を恥ずかしそうに見返していた。
他の衛生兵もその質問に興味津々らしく、彼女と私の間で目を動かしている。
「そうね。もし、規定の期間で初期の回復魔法も習得できなければ。その時は除隊。帰還してもらうわ」
私の返答に場がざわつく。
誰も好き好んでこの戦場へ奉仕しに来た者は居ないだろう。
止むに止まれぬ事情で、来た者がほとんどだ。
別の言い方で言えば、彼女らにここ以外に居場所は無いのだ。
「そんな! 今までは例え習得できなくても多くの人が、その人なりに勤めていたと聞きました!」
質問した衛生兵が声を上げる。
確かに彼女の言う通り、今まではむしろ習得している者の方が少ないのが現状だった。
だが、それではいけないと、この訓練が実施されるのだ。
目的を持ってやる以上はある程度厳しくするのは止むを得ないだろう。
「あなた、名前は?」
「ロベリアです……」
「そう、ロベリア。一つ問題を出しましょう。私がこの部隊に配属される前、別の部隊に居たの。そこではあなたの言う通り、回復魔法を使えない衛生兵が多く従事していたわ」
「は、はぁ……」
「配属初期に回復魔法の指導はあったのだけれど、使えたのは……そうね。全体の二割くらいだったかしら。残りは全く使えなかった。それで、その衛生兵たちに今からあなたたちにも行う訓練を実施したのだけれど、回復魔法を使えるようになったのは、その内どのくらいだと思う?」
「え……指導ではダメで、その後に訓練、ですか……?」
ロベリアは困った顔をしながら、考えを巡らすような素振りを見せ、そして回答した。
「多分、残りの二割、多くても三割くらいだと思います。指導でもダメだったってことは、落ちこぼれってことですもの」
「そう。他のみんなは? どのくらいだと思う?」
声を上げる者は居なかったが、思い思いにみな自分なりの割合を頭の中に浮かべているようだ。
少し間を置いた後、私は正解を告げる。
「答えは、全員。第五衛生兵部隊なのだけれど、そこに居た全員が回復魔法を使えるようになったわ」
「え⁉ そんなことが⁉」
私の告げた答えを聞き、訓練兵たちはざわつき、互いに顔を見合わせる者たちも居た。
それを見ながら私は話を続ける。
「もちろん人によって才能は違う。時間がかかる者も早い者も居たわ。それと、ここで今唯一紫色のタイを付けているデイジーは、元第五衛生兵部隊の出身よ。そして、彼女は訓練を行う前、回復魔法を一切使えなかったわ。あなたの言う落ちこぼれね」
私の隣に立つデイジーはバツが悪そうに頬をかく。
訓練兵の目が一斉にデイジーへと向けられている。
「デイジーは真面目に訓練し、今はこの第二衛生兵部隊の副隊長を務めるようになったわ。さぁ、あなたたちはどうかしら? 真面目に訓練する気がある?」
「あります‼ 私、頑張ります‼」
ロベリアは元気に返事を返す。
その言葉に釣られて、他の訓練生たちも次々と良い返事を出した。
「良かったわ。それじゃあ、訓練の指導は、私とこのデイジーが主に行う。その他の細かいことについては、自分がついた先輩にそれぞれ聞いてちょうだい。あなたたちが一日も早く緑色のタイをその首に巻けることを祈ってるわ」
「はい! 部隊長‼ ありがとうございました‼」
こうして、ダリアから聞いた、訓練兵の受け入れの初日が無事に始まった。
少なくとも表向きは彼女たちは立派な衛生兵として、負傷兵の治療のためにこの第二衛生兵部隊に所属されたことになっている。
目標は、回復魔法を習得し、一人前になるまで育て、他の部隊へと転属させること。
転属の理由については、上で考えるから私は関与しなくても良いらしい。
問題は、直ぐには気付かれないだろうが、モスアゲート伯爵に勘づかれると、横槍を入れられる危険性があると言うこと。
ダリアの話では、この戦争で最も潤っているのは、前線に様々な補給物質を提供しているモスアゲート伯爵らしい。
もちろん負けてしまえば自分の領土にも害が及ぶのだが。
いずれにしろ、怪しまれずに優秀な衛生兵を育て上げるのが私の仕事だ。
ダリアもアンバーもそれぞれの部隊で今頃様々な実地訓練を行っていることだろう。
そういえば、クロムはダリアにその才能を見出され第一攻撃部隊へと転属が決まった。
アンバーも本人が望んだかどうかは知らないけれど、再び第二攻撃部隊の部隊長に復帰したらしい。
私はふと、飾ってあるリラの花に目を向ける。
初めて咲いた時は薄紫色という表現が合っていた花は、今や濃紫色に染っていた。
「はいっ! よろしくお願いします‼」
私は目の前に並ぶ女性たち、新しく配属された衛生兵の卵たちに向かって声をかける。
彼女たちは、みな首元に白いスカーフをリボンタイの様に巻いている。
腕に巻いていた布を、ある衛生兵がスカーフにして首元に巻いたらどうかと提案したのが始めだった。
その案はその場に居た衛生兵全員に支持され、やがて裁縫が得意な者たちが切れ端を綺麗に形取りスカーフにした。
それが、ここで回復魔法を学ぶために集まった彼女たちにも普及したのだ。
白はまだ回復魔法を扱うことの出来ない、訓練生を意味した。
「これから、あなたたちは先輩の元につき、実際の治療に携わりながら、自身も回復魔法を使えるように訓練を受けてもらいます。何か質問は?」
「あの……部隊長。もし回復魔法を扱うことが出来なかったらどうなるのでしょうか……?」
訓練生の一人がおずおずと手を挙げ、心配そうに質問を口にした。
私はその衛生兵の方に目を向ける。
栗色の真っ直ぐな髪の毛を肩ほどまで伸ばし、深緑色の瞳で私を恥ずかしそうに見返していた。
他の衛生兵もその質問に興味津々らしく、彼女と私の間で目を動かしている。
「そうね。もし、規定の期間で初期の回復魔法も習得できなければ。その時は除隊。帰還してもらうわ」
私の返答に場がざわつく。
誰も好き好んでこの戦場へ奉仕しに来た者は居ないだろう。
止むに止まれぬ事情で、来た者がほとんどだ。
別の言い方で言えば、彼女らにここ以外に居場所は無いのだ。
「そんな! 今までは例え習得できなくても多くの人が、その人なりに勤めていたと聞きました!」
質問した衛生兵が声を上げる。
確かに彼女の言う通り、今まではむしろ習得している者の方が少ないのが現状だった。
だが、それではいけないと、この訓練が実施されるのだ。
目的を持ってやる以上はある程度厳しくするのは止むを得ないだろう。
「あなた、名前は?」
「ロベリアです……」
「そう、ロベリア。一つ問題を出しましょう。私がこの部隊に配属される前、別の部隊に居たの。そこではあなたの言う通り、回復魔法を使えない衛生兵が多く従事していたわ」
「は、はぁ……」
「配属初期に回復魔法の指導はあったのだけれど、使えたのは……そうね。全体の二割くらいだったかしら。残りは全く使えなかった。それで、その衛生兵たちに今からあなたたちにも行う訓練を実施したのだけれど、回復魔法を使えるようになったのは、その内どのくらいだと思う?」
「え……指導ではダメで、その後に訓練、ですか……?」
ロベリアは困った顔をしながら、考えを巡らすような素振りを見せ、そして回答した。
「多分、残りの二割、多くても三割くらいだと思います。指導でもダメだったってことは、落ちこぼれってことですもの」
「そう。他のみんなは? どのくらいだと思う?」
声を上げる者は居なかったが、思い思いにみな自分なりの割合を頭の中に浮かべているようだ。
少し間を置いた後、私は正解を告げる。
「答えは、全員。第五衛生兵部隊なのだけれど、そこに居た全員が回復魔法を使えるようになったわ」
「え⁉ そんなことが⁉」
私の告げた答えを聞き、訓練兵たちはざわつき、互いに顔を見合わせる者たちも居た。
それを見ながら私は話を続ける。
「もちろん人によって才能は違う。時間がかかる者も早い者も居たわ。それと、ここで今唯一紫色のタイを付けているデイジーは、元第五衛生兵部隊の出身よ。そして、彼女は訓練を行う前、回復魔法を一切使えなかったわ。あなたの言う落ちこぼれね」
私の隣に立つデイジーはバツが悪そうに頬をかく。
訓練兵の目が一斉にデイジーへと向けられている。
「デイジーは真面目に訓練し、今はこの第二衛生兵部隊の副隊長を務めるようになったわ。さぁ、あなたたちはどうかしら? 真面目に訓練する気がある?」
「あります‼ 私、頑張ります‼」
ロベリアは元気に返事を返す。
その言葉に釣られて、他の訓練生たちも次々と良い返事を出した。
「良かったわ。それじゃあ、訓練の指導は、私とこのデイジーが主に行う。その他の細かいことについては、自分がついた先輩にそれぞれ聞いてちょうだい。あなたたちが一日も早く緑色のタイをその首に巻けることを祈ってるわ」
「はい! 部隊長‼ ありがとうございました‼」
こうして、ダリアから聞いた、訓練兵の受け入れの初日が無事に始まった。
少なくとも表向きは彼女たちは立派な衛生兵として、負傷兵の治療のためにこの第二衛生兵部隊に所属されたことになっている。
目標は、回復魔法を習得し、一人前になるまで育て、他の部隊へと転属させること。
転属の理由については、上で考えるから私は関与しなくても良いらしい。
問題は、直ぐには気付かれないだろうが、モスアゲート伯爵に勘づかれると、横槍を入れられる危険性があると言うこと。
ダリアの話では、この戦争で最も潤っているのは、前線に様々な補給物質を提供しているモスアゲート伯爵らしい。
もちろん負けてしまえば自分の領土にも害が及ぶのだが。
いずれにしろ、怪しまれずに優秀な衛生兵を育て上げるのが私の仕事だ。
ダリアもアンバーもそれぞれの部隊で今頃様々な実地訓練を行っていることだろう。
そういえば、クロムはダリアにその才能を見出され第一攻撃部隊へと転属が決まった。
アンバーも本人が望んだかどうかは知らないけれど、再び第二攻撃部隊の部隊長に復帰したらしい。
私はふと、飾ってあるリラの花に目を向ける。
初めて咲いた時は薄紫色という表現が合っていた花は、今や濃紫色に染っていた。
「問題が?」
訓練兵の訓練が始まりしばらく経ったある日のこと、デイジーが私の部屋を訪れ、開口一番に報告した内容に私は疑問を投げかける。
「はい。ある一人の訓練兵なのですが、魔力操作は誰よりも早く、いえ、正確に言うと指導する前にできていたのですが、そこから全く成長を見せません」
「なんですって? ちなみに名前は?」
「ロベリア、という子です。聖女様が覚えているか分かりませんが、初日に――」
「ああ。あの子ね」
私は訓練兵が配属された初日に質問をした女性を思い出す。
衛生兵部隊に配属されるにしては珍しく若く、私とそこまで歳が変わらないように見えた。
いずれにしろ、魔力操作が出来たのに、その先に進めないというのは気になるところだ。
第五衛生兵部隊で目の当たりにしたが、魔力操作についてきちんと学んでいなくても、回復魔法を使える者が居たのだ。
魔法の基礎となる魔力操作が出来て、かつ回復魔法が使えないということがあり得るのだろうか?
ロベリアの治療業務の時間帯のせいで、いつもは私ではなくデイジーが担当しているため、実際に何が原因かはよく分からない。
しかし、デイジーの教え方に問題があるとも思えない。
実際、すでに訓練兵の何人かは、緑色のリボンタイになっている。
「分かったわ。私が個別に見てみましょう。直接見れば何か原因が分かるかもしれないから」
「すいません。聖女様。私が不甲斐ないばっかりに」
「いいえ、いいのよ。そうだ。デイジー、良かったらお願いがあるのだけれど」
「はい。なんでしょう?」
頭を下げるデイジーに向かって私は声をかける。
その声に反応し、デイジーは頭を上げ、期待に満ちた目を私に向ける。
どうやらデイジーは心底私を敬愛してくれているらしい。
私の役に立つのが嬉しくてしょうがないという顔だ。
「この花なのだけれど」
「ああ! 以前から育てているリラの花ですね。あぁ、やっぱり聖女様が育てている花は色が濃くて素敵です‼」
「うふふ。ありがとう。実はね。少し育ちすぎてしまって。少し切り落とそうと思っているの。それで、デイジーの他にも欲しい人が居るかどうか、聞いておいてくれないかしら」
「ええ‼ みんな欲しいと言うと思いますよ! 早速みんなに声をかけてきます‼」
デイジーは私に一礼した後、嬉しそうに身体を弾ませながら部屋を出て行った。
一人残された私は大きく育ったリラの花を見る。
最近特に成長が早い気がする。
鉢植えから枝が大きく迫り出し、所構わず花が咲き乱れている。
「みんな欲しいと言い出したら、無くなってしまうかしら……うふふ。そうしたら、また一から育てなくてはね」
私は一度帰宅した際に買い足しておいた便箋に筆を走らせる。
いまだに定期的にベリル王子には花の色や、部隊での出来事を報告している。
少し形は違うものの、訓練兵のことについてもお礼を書いたばかりだ。
そろそろその返信も返ってくる頃だろうか。
私は魔力を口に込め、口笛を鳴らす。
すると、一羽の白い鳥が空から舞い降りて、開けた窓から部屋へと入ってくる。
純白の柔らかそうな羽毛に包まれたその鳥は、首を真横に傾けて私の方を向いている。
丸みを帯びたその身体から突き出た、獰猛な爪が生えた足の付け根に、筒が括り付けられていた。
「良かった。ちょうど返信が来たようね。ありがとうピート」
私は使い魔であるピートの頭を撫でながら、空いている手で筒を取り外す。
頭を撫でられている間、ピートは気持ちよさそうに目を細めてじっとしていた。
このピートは、この間アンバーと再会を果たした時に教えてもらった使い魔だ。
私の魔力を込めた口笛で、ある程度の命令を聞いてくれる。
アンバーは使い魔と意思疎通ができるほどらしいが、残念ながら私にはそこまではまだ無理だった。
今のところ、ベリル王子との手紙のやり取りを専門にやってもらっている。
さすが空を自由に駆け回る鳥だけあって、以前よりも速く手紙のやり取りが出来るようになった。
ベリル王子も、検閲を毎回気にせずにやり取りが出来ると満足した様子だ。
「そういえば、クロムへの返信がまだだったわね。ごめんねピート。ベリル王子の所から帰ったら、次はクロムの所へ手紙を運んでちょうだい」
第一攻撃部隊に転属となったクロムは、去り際に私に手紙を書くと言い出した。
返信をもらえなくても手紙を書かせて欲しいというクロムのあまりの勢いに私は笑いながら、返信を送る約束をした。
その時の嬉しそうなクロムの顔は今でも忘れられない。
横で見ていたダリアが私に笑顔を向けていたが、それも忘れられない。
そんなことを思いながら、私は再び口に魔力を込め、口笛を吹く。
ベリル王子へ手紙を届ける命令をしたのだ。
ピートは一声鳴くと、再び括り付け直した筒と共に空へと飛び立つ。
身体を窓から乗り出し空を見上げると、ピートは一度大きくその場で旋回した後、ベリル王子が居る王都の方角へと飛んでいった。
それを見届けた私は、デイジーから相談されたロベリアのことに思考を戻す。
私は部屋の扉を開け、近くに居た兵に声をかけた。
「訓練兵のロベリアを部屋へ呼んでちょうだい」
訓練兵の訓練が始まりしばらく経ったある日のこと、デイジーが私の部屋を訪れ、開口一番に報告した内容に私は疑問を投げかける。
「はい。ある一人の訓練兵なのですが、魔力操作は誰よりも早く、いえ、正確に言うと指導する前にできていたのですが、そこから全く成長を見せません」
「なんですって? ちなみに名前は?」
「ロベリア、という子です。聖女様が覚えているか分かりませんが、初日に――」
「ああ。あの子ね」
私は訓練兵が配属された初日に質問をした女性を思い出す。
衛生兵部隊に配属されるにしては珍しく若く、私とそこまで歳が変わらないように見えた。
いずれにしろ、魔力操作が出来たのに、その先に進めないというのは気になるところだ。
第五衛生兵部隊で目の当たりにしたが、魔力操作についてきちんと学んでいなくても、回復魔法を使える者が居たのだ。
魔法の基礎となる魔力操作が出来て、かつ回復魔法が使えないということがあり得るのだろうか?
ロベリアの治療業務の時間帯のせいで、いつもは私ではなくデイジーが担当しているため、実際に何が原因かはよく分からない。
しかし、デイジーの教え方に問題があるとも思えない。
実際、すでに訓練兵の何人かは、緑色のリボンタイになっている。
「分かったわ。私が個別に見てみましょう。直接見れば何か原因が分かるかもしれないから」
「すいません。聖女様。私が不甲斐ないばっかりに」
「いいえ、いいのよ。そうだ。デイジー、良かったらお願いがあるのだけれど」
「はい。なんでしょう?」
頭を下げるデイジーに向かって私は声をかける。
その声に反応し、デイジーは頭を上げ、期待に満ちた目を私に向ける。
どうやらデイジーは心底私を敬愛してくれているらしい。
私の役に立つのが嬉しくてしょうがないという顔だ。
「この花なのだけれど」
「ああ! 以前から育てているリラの花ですね。あぁ、やっぱり聖女様が育てている花は色が濃くて素敵です‼」
「うふふ。ありがとう。実はね。少し育ちすぎてしまって。少し切り落とそうと思っているの。それで、デイジーの他にも欲しい人が居るかどうか、聞いておいてくれないかしら」
「ええ‼ みんな欲しいと言うと思いますよ! 早速みんなに声をかけてきます‼」
デイジーは私に一礼した後、嬉しそうに身体を弾ませながら部屋を出て行った。
一人残された私は大きく育ったリラの花を見る。
最近特に成長が早い気がする。
鉢植えから枝が大きく迫り出し、所構わず花が咲き乱れている。
「みんな欲しいと言い出したら、無くなってしまうかしら……うふふ。そうしたら、また一から育てなくてはね」
私は一度帰宅した際に買い足しておいた便箋に筆を走らせる。
いまだに定期的にベリル王子には花の色や、部隊での出来事を報告している。
少し形は違うものの、訓練兵のことについてもお礼を書いたばかりだ。
そろそろその返信も返ってくる頃だろうか。
私は魔力を口に込め、口笛を鳴らす。
すると、一羽の白い鳥が空から舞い降りて、開けた窓から部屋へと入ってくる。
純白の柔らかそうな羽毛に包まれたその鳥は、首を真横に傾けて私の方を向いている。
丸みを帯びたその身体から突き出た、獰猛な爪が生えた足の付け根に、筒が括り付けられていた。
「良かった。ちょうど返信が来たようね。ありがとうピート」
私は使い魔であるピートの頭を撫でながら、空いている手で筒を取り外す。
頭を撫でられている間、ピートは気持ちよさそうに目を細めてじっとしていた。
このピートは、この間アンバーと再会を果たした時に教えてもらった使い魔だ。
私の魔力を込めた口笛で、ある程度の命令を聞いてくれる。
アンバーは使い魔と意思疎通ができるほどらしいが、残念ながら私にはそこまではまだ無理だった。
今のところ、ベリル王子との手紙のやり取りを専門にやってもらっている。
さすが空を自由に駆け回る鳥だけあって、以前よりも速く手紙のやり取りが出来るようになった。
ベリル王子も、検閲を毎回気にせずにやり取りが出来ると満足した様子だ。
「そういえば、クロムへの返信がまだだったわね。ごめんねピート。ベリル王子の所から帰ったら、次はクロムの所へ手紙を運んでちょうだい」
第一攻撃部隊に転属となったクロムは、去り際に私に手紙を書くと言い出した。
返信をもらえなくても手紙を書かせて欲しいというクロムのあまりの勢いに私は笑いながら、返信を送る約束をした。
その時の嬉しそうなクロムの顔は今でも忘れられない。
横で見ていたダリアが私に笑顔を向けていたが、それも忘れられない。
そんなことを思いながら、私は再び口に魔力を込め、口笛を吹く。
ベリル王子へ手紙を届ける命令をしたのだ。
ピートは一声鳴くと、再び括り付け直した筒と共に空へと飛び立つ。
身体を窓から乗り出し空を見上げると、ピートは一度大きくその場で旋回した後、ベリル王子が居る王都の方角へと飛んでいった。
それを見届けた私は、デイジーから相談されたロベリアのことに思考を戻す。
私は部屋の扉を開け、近くに居た兵に声をかけた。
「訓練兵のロベリアを部屋へ呼んでちょうだい」
「お呼びでしょうか? 部隊長」
「ええ。少し話を聞いてみたいと思ってね」
私に呼び出されたロベリアは、何事かと心配そうな様子で部屋に入ってきた。
ただでさえ新米の訓練兵と、年は近いとは言ってもその部隊の部隊長。
この若さで緊張するなというのは、無理というものだろう。
私はそんなロベリアに目を向けると、早速本題に入った。
「ロベリア。あなたは魔力操作には問題が見られない。けれど、一向に回復魔法を覚えられない。と聞いているわ。間違いない?」
「え⁉ あ、あの……それは……」
「違うの?」
「……違いません」
ロベリアの反応を見て、私は配属当初のやり取りを思い出す。
そういえば、ロベリアは回復魔法が取得できなければどうなるか、と質問をしていた。
「安心してちょうだい。まだ、帰還命令を出すまでには時間があるわ。これはあなたが回復魔法を使えるようになるために必要なことだと理解してちょうだい」
「え? あ、そうなんですね。よかったぁ。わたし、てっきり……」
「それで、魔力操作が既にできていたにも関わらず、回復魔法が使えないというのが、どうしてなのか。調べたいと思うの。いいわね?」
「はい! わたしもどうすればいいのか全然分からなくて……」
私はロベリアにまずは魔力操作を実演させてみる。
魔力操作は、身体で練った魔力を手先に持ってくることを意味する。
ロベリアは私に一度だけ返事をすると、その場で目をつぶり、魔力を練り上げ始めた。
魔力の総量自体も人それそれだけれど、いかに効率良く練り上げられるかも、回復魔法を使うには重要になってくる。
しかしその感覚は本人しか分からず、次の手先に持ってくるという行為を通してからしか、できているのかどうかは他人には分からない。
やがて、ロベリアは練り上げたであろう魔力を手先に移動させようと、右手を胸の辺りに持ち上げ、両目でしっかりと見据えた。
「出来ました」
「分かったわ。それじゃあ、確かめるわね」
私はロベリアの右手に自分の手を置く。
魔力の波動とそれに応じた熱を感じ、確かにロベリアは魔力操作はできていることが確認できた。
しかし、量が少ないこともあるけれど、それ以外にも何か違和感を感じた私は、ロベリアに基本的なことについて質問を投げかけた。
私の考えが正しいのなら、回復魔法が使えない理由がそこにあるかもしれない。
「ロベリア。魔力操作は出来ているようだわ。ところで、基礎的な質問なのだけれど、魔力を練る時、身体のどこを意識してる?」
「えーっと、この辺りですね……」
ロベリアはそう言いながら、自分の腹部、へその下辺りを右手で撫でた。
それを見た私は、考えが正しかったと確信する。
「ロベリア、誰か。そうね。親しい人に攻撃魔法を使う人が居るかしら?」
「え⁉ なんで分かったんですか⁉ 兄が、歳の離れた兄がいます。第二攻撃部隊に所属しています」
「魔力操作は、そのお兄さんから学んだのかしら?」
「部隊長はなんでも分かるんですね。その通りです。兄は独学で攻撃魔法を学び扱えるようになった人でした。そんな兄について回っているうちに私も興味を持って……それが何か?」
私は一度息を吐く。
ロベリアが回復魔法を使えない理由はここにあるのは確定したものの、それを直すのはなかなかに骨が折れることだった。
右手を自分の胸の中心に当て、私はロベリアが絶望しないように言葉を選んで説明を始めた。
「実はね、ロベリア。男性が得意な攻撃魔法。そして女性が得意な回復魔法。どちらも魔力操作を伴うのだけれど」
「はい」
「あなたが魔力を練っている場所。それは攻撃魔法を使うための場所なの。回復魔法はここで練るのよ」
「え⁉」
そう言いながら私は右手で胸を軽く叩く。
それを見たロベリアは驚きのあまり目を見開いている。
「回復魔法はね、心で魔力を練るの。言葉では上手く説明が難しいけれど、普通の人は考えずにそうしているのよ」
「それじゃあ、私はどうすれば?」
「あなたが回復魔法を使えない理由は、魔力の質が違うから。攻撃を目的とした魔力と、回復を目的とした魔力とでは質が全く違うの」
私の説明を聞きながら、ロベリアは困惑した表情をこちらに向ける。
それを見た私は悲しい気持ちになる。
魔力を練る感覚は、人によって違う。
そして、それは他人が教えて分かるものではないのだ。
一度癖としてついてしまったことを忘れて、別の方法を正しく身につけるのは、新しく始めるよりはるかに難易度の高いことだった。
正直なところ、私も書物で知識として知ってはいるものの、実際にへその下で魔力を練ってみろと言われても、実現することはできない。
「心苦しいけれど、ロベリア。あなたが、魔力の練り方を自力で直さなければ、あなたは一生回復魔法を使うことはできないわ」
「そんな! それは、困ります……私、衛生兵になって、兄を……アイオラにもしものことがあれば助けたい一心で!」
ロベリアはこの戦場に赴くには若いとは思っていたが、なるほど、どうやら志願兵だったようだ。
できるかどうかも定かではないのに、衛生兵を志願したということは、よほど兄が心配なのだろう。
しかし、私にできるのはここまでだ。
あとは、自分で魔力の練り方を直すしか方法はない。
「冷たいことを言うようだけれど、ロベリア。間違っていることは教えられても、どうすれば正しい方法で出来るのかは、あなたにしか分からないわ」
「はい……」
「そうね……今日から、治療場での業務は休止しなさい。そして、どうすれば魔力の練り方を変えられるか、それを試行錯誤しなさい」
「分かりました……でも、どうやったら違いが分かるんですか?」
聞かれて私は頭を回転させた。
私も違和感を感じただけで、魔力に触れたとしても、正確にどちらの魔力の質なのかまでは自信がない。
「そうね。実際に回復魔法を使ってみるしかないでしょうね。出来るようになったと思ったら、治療場に顔を出しなさい。実際に負傷兵に回復魔法をかけて確認する他ないわ」
「分かりました。それでは……失礼します」
こうしてロベリアは間違って身に付けてしまった魔力操作を修整するために、ひたすら自己訓練にあけくれていた。
しかし、しばらく経ってもロベリアが治療場に顔を出すことはなかった。
そんなある日のこと、いつも通りひっきりなしに負傷兵が運ばれてきていた治療場に、血相を変えたロベリアが飛び込んできた。
その形相は、成功した喜びを持っているようにはとても見えない。
ロベリアは辺りを見渡した後、私を見つけて、駆けつけてくる。
そして開口一番にこう言った。
「部隊長‼ 兄が‼ アイオラがここに運ばれたって本当ですか⁉」
「ええ。少し話を聞いてみたいと思ってね」
私に呼び出されたロベリアは、何事かと心配そうな様子で部屋に入ってきた。
ただでさえ新米の訓練兵と、年は近いとは言ってもその部隊の部隊長。
この若さで緊張するなというのは、無理というものだろう。
私はそんなロベリアに目を向けると、早速本題に入った。
「ロベリア。あなたは魔力操作には問題が見られない。けれど、一向に回復魔法を覚えられない。と聞いているわ。間違いない?」
「え⁉ あ、あの……それは……」
「違うの?」
「……違いません」
ロベリアの反応を見て、私は配属当初のやり取りを思い出す。
そういえば、ロベリアは回復魔法が取得できなければどうなるか、と質問をしていた。
「安心してちょうだい。まだ、帰還命令を出すまでには時間があるわ。これはあなたが回復魔法を使えるようになるために必要なことだと理解してちょうだい」
「え? あ、そうなんですね。よかったぁ。わたし、てっきり……」
「それで、魔力操作が既にできていたにも関わらず、回復魔法が使えないというのが、どうしてなのか。調べたいと思うの。いいわね?」
「はい! わたしもどうすればいいのか全然分からなくて……」
私はロベリアにまずは魔力操作を実演させてみる。
魔力操作は、身体で練った魔力を手先に持ってくることを意味する。
ロベリアは私に一度だけ返事をすると、その場で目をつぶり、魔力を練り上げ始めた。
魔力の総量自体も人それそれだけれど、いかに効率良く練り上げられるかも、回復魔法を使うには重要になってくる。
しかしその感覚は本人しか分からず、次の手先に持ってくるという行為を通してからしか、できているのかどうかは他人には分からない。
やがて、ロベリアは練り上げたであろう魔力を手先に移動させようと、右手を胸の辺りに持ち上げ、両目でしっかりと見据えた。
「出来ました」
「分かったわ。それじゃあ、確かめるわね」
私はロベリアの右手に自分の手を置く。
魔力の波動とそれに応じた熱を感じ、確かにロベリアは魔力操作はできていることが確認できた。
しかし、量が少ないこともあるけれど、それ以外にも何か違和感を感じた私は、ロベリアに基本的なことについて質問を投げかけた。
私の考えが正しいのなら、回復魔法が使えない理由がそこにあるかもしれない。
「ロベリア。魔力操作は出来ているようだわ。ところで、基礎的な質問なのだけれど、魔力を練る時、身体のどこを意識してる?」
「えーっと、この辺りですね……」
ロベリアはそう言いながら、自分の腹部、へその下辺りを右手で撫でた。
それを見た私は、考えが正しかったと確信する。
「ロベリア、誰か。そうね。親しい人に攻撃魔法を使う人が居るかしら?」
「え⁉ なんで分かったんですか⁉ 兄が、歳の離れた兄がいます。第二攻撃部隊に所属しています」
「魔力操作は、そのお兄さんから学んだのかしら?」
「部隊長はなんでも分かるんですね。その通りです。兄は独学で攻撃魔法を学び扱えるようになった人でした。そんな兄について回っているうちに私も興味を持って……それが何か?」
私は一度息を吐く。
ロベリアが回復魔法を使えない理由はここにあるのは確定したものの、それを直すのはなかなかに骨が折れることだった。
右手を自分の胸の中心に当て、私はロベリアが絶望しないように言葉を選んで説明を始めた。
「実はね、ロベリア。男性が得意な攻撃魔法。そして女性が得意な回復魔法。どちらも魔力操作を伴うのだけれど」
「はい」
「あなたが魔力を練っている場所。それは攻撃魔法を使うための場所なの。回復魔法はここで練るのよ」
「え⁉」
そう言いながら私は右手で胸を軽く叩く。
それを見たロベリアは驚きのあまり目を見開いている。
「回復魔法はね、心で魔力を練るの。言葉では上手く説明が難しいけれど、普通の人は考えずにそうしているのよ」
「それじゃあ、私はどうすれば?」
「あなたが回復魔法を使えない理由は、魔力の質が違うから。攻撃を目的とした魔力と、回復を目的とした魔力とでは質が全く違うの」
私の説明を聞きながら、ロベリアは困惑した表情をこちらに向ける。
それを見た私は悲しい気持ちになる。
魔力を練る感覚は、人によって違う。
そして、それは他人が教えて分かるものではないのだ。
一度癖としてついてしまったことを忘れて、別の方法を正しく身につけるのは、新しく始めるよりはるかに難易度の高いことだった。
正直なところ、私も書物で知識として知ってはいるものの、実際にへその下で魔力を練ってみろと言われても、実現することはできない。
「心苦しいけれど、ロベリア。あなたが、魔力の練り方を自力で直さなければ、あなたは一生回復魔法を使うことはできないわ」
「そんな! それは、困ります……私、衛生兵になって、兄を……アイオラにもしものことがあれば助けたい一心で!」
ロベリアはこの戦場に赴くには若いとは思っていたが、なるほど、どうやら志願兵だったようだ。
できるかどうかも定かではないのに、衛生兵を志願したということは、よほど兄が心配なのだろう。
しかし、私にできるのはここまでだ。
あとは、自分で魔力の練り方を直すしか方法はない。
「冷たいことを言うようだけれど、ロベリア。間違っていることは教えられても、どうすれば正しい方法で出来るのかは、あなたにしか分からないわ」
「はい……」
「そうね……今日から、治療場での業務は休止しなさい。そして、どうすれば魔力の練り方を変えられるか、それを試行錯誤しなさい」
「分かりました……でも、どうやったら違いが分かるんですか?」
聞かれて私は頭を回転させた。
私も違和感を感じただけで、魔力に触れたとしても、正確にどちらの魔力の質なのかまでは自信がない。
「そうね。実際に回復魔法を使ってみるしかないでしょうね。出来るようになったと思ったら、治療場に顔を出しなさい。実際に負傷兵に回復魔法をかけて確認する他ないわ」
「分かりました。それでは……失礼します」
こうしてロベリアは間違って身に付けてしまった魔力操作を修整するために、ひたすら自己訓練にあけくれていた。
しかし、しばらく経ってもロベリアが治療場に顔を出すことはなかった。
そんなある日のこと、いつも通りひっきりなしに負傷兵が運ばれてきていた治療場に、血相を変えたロベリアが飛び込んできた。
その形相は、成功した喜びを持っているようにはとても見えない。
ロベリアは辺りを見渡した後、私を見つけて、駆けつけてくる。
そして開口一番にこう言った。
「部隊長‼ 兄が‼ アイオラがここに運ばれたって本当ですか⁉」
この作家の他の作品
表紙を見る
気付くと私は、発売から十年経った今も思い出してはプレイを続ける乙女ゲーム「イストワール〜星恋の七王子」のキャラクターに転生してしまった。
しかもそれはゲーム内でヒロインを執拗に陥れようと画策する悪役令嬢、ミザリー・マリア・ド・ゴール。
本来の主人公であるヒロインがどのルートを通ってもその前に立ちはだかり、最終的には己の行いが招いた破滅の結末を迎える。
私はそんな結末を回避しようと、三年間の学園生活を奔走する。
「王子を味方につける方法を考えなきゃ!」
表紙を見る
精霊に愛された少女は聖女として崇められる。私の住む国で古くからある習わしだ。
驚いたことに私も聖女だと、村の皆の期待を背に王都マーベラに迎えられた。
それなのに……。
「この者が聖女なはずはない! 穢らわしい!」
私よりも何年も前から聖女として称えられているローザ様の一言で、私は国を追放されることになってしまった。
「もし良かったら同行してくれないか?」
隣国に向かう途中で命を救ったやり手の商人アベルに色々と助けてもらうことに。
その隣国では精霊の力を利用する技術を使う者は【錬金術師】と呼ばれていて……。
第五元素エーテルの精霊に愛された私は、生まれた国を追放されたけれど、隣国で天才錬金術師として暮らしていくようです!!
この物語は、国を追放された聖女と、助けたやり手商人との恋愛話です。
追放ものなので、最初の方で3話毎にざまぁ描写があります。
薬の効果を示すためにたまに人が怪我をしますがグロ描写はありません。
作者が化学好きなので、少し趣味が出ますがファンタジー風味を壊すことは無いように気を使っています。
ベリーズファンタジー様から発売されました!!
書籍版は大ボリューム加筆修正しておりますので、ぜひぜひお手にお取りください!!
表紙を見る
勇者パーティの支援職だった私は、自己を超々強化する秘法と言われた魔法を使い、幼女になってしまった。
そんな私の姿を見て、パーティメンバーが決めたのは……
「アリシアちゃん。いい子だからお留守番しててね」
見た目は幼女でも、最強の肉体を手に入れた私は、付いてくるなと言われた手前、こっそりひっそりと陰から元仲間を支援することに決めた。
戦神の愛用していたという神器破城槌を振り回し、神の乗り物だと言うもふもふ神獣と旅を続ける珍道中!
主人公は元は立派な大人ですが、心も体も知能も子供です
基本的にコメディ色が強いです
毎日朝7時に一話分更新します
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…