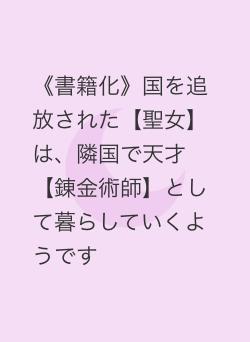「え? 王都への帰還命令ですか⁉」
「うん。そうだね」
司令室に突然呼び出され、最初にアンバーに告げられたのが、王都に戻れという話だった。
あまりの唐突な命令に、私は異議を申し出る。
「突然過ぎます! 帰還理由を教えてください。私の行動に問題があったとは思えませんが、何か理由があるなら改善します。やっと軌道に乗り始めている最中なのは部隊長もご存知のはずです‼」
一気にまくし立てる私に、アンバーは両手を前に出してなだめる仕草をする。
「まぁまぁ。今から説明するから。聖女様。いいね?」
アンバーの表情を見て、この命令が今目の前にいる人物の本意では無いと悟り、少し気持ちを落ち着かせる。
「まず、僕だって寝耳に水さ。実際君はよくやってくれている。知ってるかい? 君が来る前のここに運ばれた負傷兵の致死率は約四割だったんだ。それが、今では、ほぼゼロと言っていい」
「ええ。色々とやっていますからね。だけど、まだ足りません。今では衛生兵の質も量も十分とは言えません」
デイジーを始め、徐々に何人かは、初級の解毒魔法や中級の治癒魔法への足掛かりができ始めようとしていた。
しかし、それでも重傷の兵士の対応はほとんど私がしている。
もしここで私が抜ければ、瓦解する、とまではいかないものの、かなりの無理を強いることになるだろう。
そうすれば、緊急の場合に対応が難しくなる。
魔石が十分に確保できていない現状、無理をすれば衛生兵にも犠牲が出る危険性がある。
犠牲の上での奉仕ではいけないのだ。
「うんうん。そうだね。その点も聖女様はよくやってくれていると思うよ。彼女らがあそこまで回復魔法を使いこなすようになるとは。正直僕は思いもしなかったよ」
「運良く素質が高い人たちが多くいてくれたおかげです。また、彼女らも勤勉で、私も助かっています」
「ちょっと話が逸れたね。とにかく、君には王都に帰還してもらわないといけない。これは総司令官命令だからね」
「総司令官……ですか?」
総司令官と言われて私は首を傾げる。
国王は今も病に伏せているはずで、実権を任されているルチル王子もまだ療養中の身のはずだ。
「うん。ベリル王子直々の命令らしいよ。いやぁたまげたね。聖女様はさすが侯爵令嬢だけあるってことかな? ベリル王子と面識があるなんて」
「ベリル王子が総司令官ということは、正式に決まったのですか⁉」
「うん。どうやらそうみたい。この前僕の所にも伝令が来たよ。それでね、とにかく戻るしかない。寂しくなるけどね」
「分かりました……とりあえず、荷物の整理をして来ます。日時はいつでしょうか?」
前にアンバーが言っていたように、とうとうベリル王子が総司令官に就任したということは、今までに送っていた手紙の内容の実現の可能性も出て来たということだ。
そう考えれば考えるほど、今この状況で現場を後にするのが口惜しくてたまらなかった。
「いや。そんな暇はないんだ。今すぐに出発だ。とりあえず、最低限必要なものを持って行ってくれ。荷物は後から送る手配をすることになっている」
「なんですって⁉ それだけ緊急、ということでしょうか?」
「どうだろうね……正直お偉いさんの考えることなんて僕は分からないさ。とりあえず、すでに移動の用意は済ませてある。護衛もね。思えば短い間だったけど、寂しくなるよ……」
「分かりました。ありがとうございます。部隊長も……色々とありがとうございました」
私は衛生兵たちに簡単な伝言を頼み、また、伝えきれないことは後日手紙で送ることを伝えてその場を後にする。
前線の状況も気になるものの、すでに自分の力でどうすることもできないというのは理解していた。
それよりも、今は王都への帰還命令のことについて考えていた。
ベリル王子が思いつきで何かをする人物だとは思えない。
これだけ急かすということは、何かしらの重大な理由があるということだろう。
移動する間、私はこれから起こることが何なのかをぼんやりと考えていた。
「聖女様。考えことですか? でも、良かったですね。安全な場所に帰ることができて。俺としては正直、寂しいってのがありますけど」
「ああ……クロム。ええ、ちょっと何故突然呼び戻されたのかと考えていてね」
護衛として付けられたクロムが、私に話しかけて来た。
何でも、手紙のやり取りの際も、護衛の件も本人がアンバーに直に頼んでその役目を勝ち取ったのだとか。
手紙のやり取りはともかく、護衛という点ではクロムは第五衛生兵部隊に所属する者の中で、アンバーを除けば一番有能だと言えた。
逆に言えば、そんな彼が陣営を離れることを許可してくれたアンバーの、私に対する配慮も並々ならないと感謝している。
実際、陣営へ向かう最中に魔獣に襲われ戦線に辿り着くことなく命を失う、ということがないわけではない。
そのため、ある程度重要な人物の陣営から最寄りの街までの移動の際は、護衛が付くのがほとんどだった。
しかし、てっきりクロムも街までの護衛かと思っていたら、王都まで一緒に付いてくるとのことだった。
何でも、護衛を王都まで付けることも総司令官、つまりベリル王子の要求だったとか。
「もうすぐ王都に着きますよ。俺、王都に行くの初めてなんですよ。凄いですね……」
クロムの言葉に外の風景に目を向ける。
目の前には、生まれてからつい最近まで育った街並みが広がっていた。
「うん。そうだね」
司令室に突然呼び出され、最初にアンバーに告げられたのが、王都に戻れという話だった。
あまりの唐突な命令に、私は異議を申し出る。
「突然過ぎます! 帰還理由を教えてください。私の行動に問題があったとは思えませんが、何か理由があるなら改善します。やっと軌道に乗り始めている最中なのは部隊長もご存知のはずです‼」
一気にまくし立てる私に、アンバーは両手を前に出してなだめる仕草をする。
「まぁまぁ。今から説明するから。聖女様。いいね?」
アンバーの表情を見て、この命令が今目の前にいる人物の本意では無いと悟り、少し気持ちを落ち着かせる。
「まず、僕だって寝耳に水さ。実際君はよくやってくれている。知ってるかい? 君が来る前のここに運ばれた負傷兵の致死率は約四割だったんだ。それが、今では、ほぼゼロと言っていい」
「ええ。色々とやっていますからね。だけど、まだ足りません。今では衛生兵の質も量も十分とは言えません」
デイジーを始め、徐々に何人かは、初級の解毒魔法や中級の治癒魔法への足掛かりができ始めようとしていた。
しかし、それでも重傷の兵士の対応はほとんど私がしている。
もしここで私が抜ければ、瓦解する、とまではいかないものの、かなりの無理を強いることになるだろう。
そうすれば、緊急の場合に対応が難しくなる。
魔石が十分に確保できていない現状、無理をすれば衛生兵にも犠牲が出る危険性がある。
犠牲の上での奉仕ではいけないのだ。
「うんうん。そうだね。その点も聖女様はよくやってくれていると思うよ。彼女らがあそこまで回復魔法を使いこなすようになるとは。正直僕は思いもしなかったよ」
「運良く素質が高い人たちが多くいてくれたおかげです。また、彼女らも勤勉で、私も助かっています」
「ちょっと話が逸れたね。とにかく、君には王都に帰還してもらわないといけない。これは総司令官命令だからね」
「総司令官……ですか?」
総司令官と言われて私は首を傾げる。
国王は今も病に伏せているはずで、実権を任されているルチル王子もまだ療養中の身のはずだ。
「うん。ベリル王子直々の命令らしいよ。いやぁたまげたね。聖女様はさすが侯爵令嬢だけあるってことかな? ベリル王子と面識があるなんて」
「ベリル王子が総司令官ということは、正式に決まったのですか⁉」
「うん。どうやらそうみたい。この前僕の所にも伝令が来たよ。それでね、とにかく戻るしかない。寂しくなるけどね」
「分かりました……とりあえず、荷物の整理をして来ます。日時はいつでしょうか?」
前にアンバーが言っていたように、とうとうベリル王子が総司令官に就任したということは、今までに送っていた手紙の内容の実現の可能性も出て来たということだ。
そう考えれば考えるほど、今この状況で現場を後にするのが口惜しくてたまらなかった。
「いや。そんな暇はないんだ。今すぐに出発だ。とりあえず、最低限必要なものを持って行ってくれ。荷物は後から送る手配をすることになっている」
「なんですって⁉ それだけ緊急、ということでしょうか?」
「どうだろうね……正直お偉いさんの考えることなんて僕は分からないさ。とりあえず、すでに移動の用意は済ませてある。護衛もね。思えば短い間だったけど、寂しくなるよ……」
「分かりました。ありがとうございます。部隊長も……色々とありがとうございました」
私は衛生兵たちに簡単な伝言を頼み、また、伝えきれないことは後日手紙で送ることを伝えてその場を後にする。
前線の状況も気になるものの、すでに自分の力でどうすることもできないというのは理解していた。
それよりも、今は王都への帰還命令のことについて考えていた。
ベリル王子が思いつきで何かをする人物だとは思えない。
これだけ急かすということは、何かしらの重大な理由があるということだろう。
移動する間、私はこれから起こることが何なのかをぼんやりと考えていた。
「聖女様。考えことですか? でも、良かったですね。安全な場所に帰ることができて。俺としては正直、寂しいってのがありますけど」
「ああ……クロム。ええ、ちょっと何故突然呼び戻されたのかと考えていてね」
護衛として付けられたクロムが、私に話しかけて来た。
何でも、手紙のやり取りの際も、護衛の件も本人がアンバーに直に頼んでその役目を勝ち取ったのだとか。
手紙のやり取りはともかく、護衛という点ではクロムは第五衛生兵部隊に所属する者の中で、アンバーを除けば一番有能だと言えた。
逆に言えば、そんな彼が陣営を離れることを許可してくれたアンバーの、私に対する配慮も並々ならないと感謝している。
実際、陣営へ向かう最中に魔獣に襲われ戦線に辿り着くことなく命を失う、ということがないわけではない。
そのため、ある程度重要な人物の陣営から最寄りの街までの移動の際は、護衛が付くのがほとんどだった。
しかし、てっきりクロムも街までの護衛かと思っていたら、王都まで一緒に付いてくるとのことだった。
何でも、護衛を王都まで付けることも総司令官、つまりベリル王子の要求だったとか。
「もうすぐ王都に着きますよ。俺、王都に行くの初めてなんですよ。凄いですね……」
クロムの言葉に外の風景に目を向ける。
目の前には、生まれてからつい最近まで育った街並みが広がっていた。
「やあ、フローラ。よく戻って来てくれたね。急な命令で済まない」
王都に到着し、実家による暇も与えられず、私は王城へと向かった。
そこで、身支度を済ませ、ドレス姿に着替えた私は、その足でベリル王子に謁見する。
柔らかそうな金髪と蒼色の瞳を持った顔は、嬉しそうな笑みを浮かべていた。
私は王族に対する一礼を済ませた後、ここに呼ばれた用件を聞く。
「ご無沙汰しております。ベリル殿下。お元気そうで何よりです。と、挨拶はこれくらいにさせていただきます。私を帰還させるとはどういうことでしょうか?」
「ふふふ。君は変わらないね。大きくなり美しい女性になっても、昔のままだ。そうだね、私もそんなに時間の余裕があるわけじゃないんだ。お互いのため、さっさと本題に入ろうか」
ベリル王子は私を別室へと案内する。
他に付き添いの者は一人だけだ。
鋭い目つきをしたこの人物を私は初めて見る。
服装から見るに執事長か何かだろうか。
「こちらでございます」
移動の最中に名前を聞き、クリスと名乗った人物は、王城の一角になる部屋へ着くと、扉を開ける。
その中には、三人の人物が居た。
「フローラ‼ お願い‼ 助けて‼ 貴女と私の仲じゃない‼」
「…………‼」
三人のうち一人は、拘束されて身動きが取れないようになっているマリーゴールドだった。
私との仲と言っても、そこまで親しかった記憶はない。
もう一人は護衛だろうか。
私たちが入ってくるのを見ると、一礼をした。
そして最後の一人の様子に私は目を見開いた。
それはベッドに横たわり、今も痛みによる失神と覚醒を繰り返すルチル王子だった。
その顔は恐ろしいまでに苦悶の表情に支配されていて、何かを叫ぼうと口を大きく開いているが、聞こえるのは息が漏れ出る音だけだった。
恐らく喉を潰されて声が出ないようになっているのだろう。
「驚いたかい? 私もこの現状を目の当たりにした時には大層驚いたよ。ねぇ? マリーゴールド」
「ベリル王子‼ どうか! 私の話をお聞きください‼ これは! 私も本意では無かったのです‼」
必死の形相で弁明をするマリーゴールドを無視して、ベリル王子は私の方を向き、困った顔を見せる。
そしてルチル王子を指差し、こう言った。
「つまり、こういうことだったんだ。兄さんは、思った通り治癒などされていなかった。叫び声が消えたのはこの女に喉を潰されていたからだ」
「私にこれを見せたということは、治療してもよろしいんですね?」
「ああ。できるものなら、ね。正直なところ、私はこの女が聖女だとは思っていない。きっと、兄さんのことだ。聖女などという特別な力を持つ相手を娶るより、気に入った女性をと言ったところだろう。フローラにはひどい話だけどね」
「いえ。気にしていませんので」
正直なところ、私も同じように考えていたのだから、そこだけはルチル王子に悪い印象は持っていない。
ただ、ベリル王子の口添えが無ければ、この城に一生幽閉されていたのかもしれないと考えれば、そうとは言えないけれど。
「ただね。私もまだ半信半疑なんだよ。フローラも治せないのかもしれない。それまでは、この女の処遇も含めて保留にしてある。さあ、できるかい?」
「できるかどうかの保証はしません。それでも、やってみます」
そう答えると、ベリル王子は私に一つの魔石を手渡す。
受け取って確認すると、大きさ質ともに最高級のものと言っていいものだった。
私はその魔石を右手に持つと、アンバーにした様に解呪の魔法を唱え始める。
ルチル王子の身体が光に包まれ、そして光が消えると、痛みなどが消えたおかげか、安らかな顔に戻る。
続いて私は治癒の魔法を唱え、呪いによって傷付いた身体の内部も潰された喉も治した。
これで、身体の方は問題なく完治したはずだ。
しかし、恐らく精神の方は……。
「驚いたな……殺した訳じゃないよね?」
「寝ているだけです。近付けば寝息が聞こえるのが分かるはずです」
私の言葉にベリル王子はゆっくりとした足取りでルチル王子に近付き、口元に顔を持っていく。
そして、私の方を振り向いた。
「確かに息をしているね。ありがとう。これで、白黒はっきりしたね。聖女が誰なのかってことが」
そう言うと、ベリル王子は私に向けていた笑顔を消し、険しい顔付きをマリーゴールドに向け、クリスに強い口調で命令をする。
「こいつを連れて行け。処遇は追って決める」
「はっ! かしこまりました!」
「やめて! 助けて‼ 私が悪いんじゃないの‼ わ……むごもごっ‼」
移送中に声を出されない様にか、マリーゴールドは猿ぐつわをされ、護衛と共にクリスが連れ出す。
後に残った私に、ベリル王子は再び笑みを向けた。
「色々と済まなかったね。事が事なだけに、あの女の処遇も含めて色々と決めかねていたんだよ。下手な所に移送して、変なことを吹聴されても困るからね」
「それで、私の役目は終わりでしょうか?」
「ああ。これで兄さんも助かった事だしね。ただ、少しこの事件はきな臭いんだ。あの女が言う様に、一人で考えて行動したものではないのかもしれない」
「お言葉ですが、ルチル王子は療養が必要でしょう。傷も癒え、呪いも解けましたが、これだけの期間呪いに晒され続けていたのです。精神が病んでいる可能性が高いでしょう」
呪いについて学んだ時、多くはないものの、呪いを受けてから解かれるまでの期間が長かった者のその後が書かれていた。
その多くは、呪いによって生じていた痛みや恐怖により、精神が病み、まるで心が壊れた様な状態になるのだという。
残念ながら、少なくとも私が知りうる限りの回復魔法では、この状態を治癒させるものは無いという結論だった。
時間をかけ、ゆっくりと治していくしか方法は今のところない。
それでも、完治した例は少なく、多くはそのままの状態でいるらしい。
今寝ているルチル王子が覚醒した時にどういう状況か、もし心が壊れていても治るのかも私には分からない事だった。
王都に到着し、実家による暇も与えられず、私は王城へと向かった。
そこで、身支度を済ませ、ドレス姿に着替えた私は、その足でベリル王子に謁見する。
柔らかそうな金髪と蒼色の瞳を持った顔は、嬉しそうな笑みを浮かべていた。
私は王族に対する一礼を済ませた後、ここに呼ばれた用件を聞く。
「ご無沙汰しております。ベリル殿下。お元気そうで何よりです。と、挨拶はこれくらいにさせていただきます。私を帰還させるとはどういうことでしょうか?」
「ふふふ。君は変わらないね。大きくなり美しい女性になっても、昔のままだ。そうだね、私もそんなに時間の余裕があるわけじゃないんだ。お互いのため、さっさと本題に入ろうか」
ベリル王子は私を別室へと案内する。
他に付き添いの者は一人だけだ。
鋭い目つきをしたこの人物を私は初めて見る。
服装から見るに執事長か何かだろうか。
「こちらでございます」
移動の最中に名前を聞き、クリスと名乗った人物は、王城の一角になる部屋へ着くと、扉を開ける。
その中には、三人の人物が居た。
「フローラ‼ お願い‼ 助けて‼ 貴女と私の仲じゃない‼」
「…………‼」
三人のうち一人は、拘束されて身動きが取れないようになっているマリーゴールドだった。
私との仲と言っても、そこまで親しかった記憶はない。
もう一人は護衛だろうか。
私たちが入ってくるのを見ると、一礼をした。
そして最後の一人の様子に私は目を見開いた。
それはベッドに横たわり、今も痛みによる失神と覚醒を繰り返すルチル王子だった。
その顔は恐ろしいまでに苦悶の表情に支配されていて、何かを叫ぼうと口を大きく開いているが、聞こえるのは息が漏れ出る音だけだった。
恐らく喉を潰されて声が出ないようになっているのだろう。
「驚いたかい? 私もこの現状を目の当たりにした時には大層驚いたよ。ねぇ? マリーゴールド」
「ベリル王子‼ どうか! 私の話をお聞きください‼ これは! 私も本意では無かったのです‼」
必死の形相で弁明をするマリーゴールドを無視して、ベリル王子は私の方を向き、困った顔を見せる。
そしてルチル王子を指差し、こう言った。
「つまり、こういうことだったんだ。兄さんは、思った通り治癒などされていなかった。叫び声が消えたのはこの女に喉を潰されていたからだ」
「私にこれを見せたということは、治療してもよろしいんですね?」
「ああ。できるものなら、ね。正直なところ、私はこの女が聖女だとは思っていない。きっと、兄さんのことだ。聖女などという特別な力を持つ相手を娶るより、気に入った女性をと言ったところだろう。フローラにはひどい話だけどね」
「いえ。気にしていませんので」
正直なところ、私も同じように考えていたのだから、そこだけはルチル王子に悪い印象は持っていない。
ただ、ベリル王子の口添えが無ければ、この城に一生幽閉されていたのかもしれないと考えれば、そうとは言えないけれど。
「ただね。私もまだ半信半疑なんだよ。フローラも治せないのかもしれない。それまでは、この女の処遇も含めて保留にしてある。さあ、できるかい?」
「できるかどうかの保証はしません。それでも、やってみます」
そう答えると、ベリル王子は私に一つの魔石を手渡す。
受け取って確認すると、大きさ質ともに最高級のものと言っていいものだった。
私はその魔石を右手に持つと、アンバーにした様に解呪の魔法を唱え始める。
ルチル王子の身体が光に包まれ、そして光が消えると、痛みなどが消えたおかげか、安らかな顔に戻る。
続いて私は治癒の魔法を唱え、呪いによって傷付いた身体の内部も潰された喉も治した。
これで、身体の方は問題なく完治したはずだ。
しかし、恐らく精神の方は……。
「驚いたな……殺した訳じゃないよね?」
「寝ているだけです。近付けば寝息が聞こえるのが分かるはずです」
私の言葉にベリル王子はゆっくりとした足取りでルチル王子に近付き、口元に顔を持っていく。
そして、私の方を振り向いた。
「確かに息をしているね。ありがとう。これで、白黒はっきりしたね。聖女が誰なのかってことが」
そう言うと、ベリル王子は私に向けていた笑顔を消し、険しい顔付きをマリーゴールドに向け、クリスに強い口調で命令をする。
「こいつを連れて行け。処遇は追って決める」
「はっ! かしこまりました!」
「やめて! 助けて‼ 私が悪いんじゃないの‼ わ……むごもごっ‼」
移送中に声を出されない様にか、マリーゴールドは猿ぐつわをされ、護衛と共にクリスが連れ出す。
後に残った私に、ベリル王子は再び笑みを向けた。
「色々と済まなかったね。事が事なだけに、あの女の処遇も含めて色々と決めかねていたんだよ。下手な所に移送して、変なことを吹聴されても困るからね」
「それで、私の役目は終わりでしょうか?」
「ああ。これで兄さんも助かった事だしね。ただ、少しこの事件はきな臭いんだ。あの女が言う様に、一人で考えて行動したものではないのかもしれない」
「お言葉ですが、ルチル王子は療養が必要でしょう。傷も癒え、呪いも解けましたが、これだけの期間呪いに晒され続けていたのです。精神が病んでいる可能性が高いでしょう」
呪いについて学んだ時、多くはないものの、呪いを受けてから解かれるまでの期間が長かった者のその後が書かれていた。
その多くは、呪いによって生じていた痛みや恐怖により、精神が病み、まるで心が壊れた様な状態になるのだという。
残念ながら、少なくとも私が知りうる限りの回復魔法では、この状態を治癒させるものは無いという結論だった。
時間をかけ、ゆっくりと治していくしか方法は今のところない。
それでも、完治した例は少なく、多くはそのままの状態でいるらしい。
今寝ているルチル王子が覚醒した時にどういう状況か、もし心が壊れていても治るのかも私には分からない事だった。
ルチル王子の一件があった後、数日経って私は再び王城に呼び出された。
その間、父が「よく戻ってきた」とか「今からでも遅くない」とかを、毎日のように聞かせてくるので、若干うんざりしてしまった。
「やぁ。よく来てくれたね。座ってよ」
「失礼いたします」
今回通されたのは、ベリル王子の私室の一つだった。
ゆったりとしたソファが向かいあわせで置かれていて、奥の方にすでにベリル王子が座っている。
隣に佇むクリスが私に向かって会釈する。
私もベリル王子、そしてクリスにそれぞれ一礼してから、向かいあう形で空いているソファに座った。
「なんだい。こっちにも空きがあるんだから、こっちに座ればいいのに。そこじゃあ、遠いだろ?」
「ご冗談を。今日のご用件はなんでしょうか?」
私の言葉にベリル王子は笑みを強くする。
どうやら私にはこの人の考えを読むのは難しそうだ。
「ああ。そうだね。他でもない。兄さんのことさ」
ベリル王子は呪いが解けた後のルチル王子のことについては淡々と述べた。
その口調や表情からは、そのことを悲しんでいるのか喜んでいるのかは読み取れなかった。
ルチル王子は案の定、心を壊してしまったようだ。
身体に異常がないにもかかわらず、反応もいまいちで、一日中どこか遠くを見つめているだけらしい。
「それで、相談なんだけど。兄さんを元に戻すことはできるのかな?」
「分かりかねます。ただ、魔法の力で、ということでしたら、現時点で方法はありません」
「そうか……それは残念だね。本人の口から直接聞きたかったんだけどな」
「なんのことでしょうか?」
ベリル王子が困った顔でそんなことを言うので、思わず私は聞き返してしまった。
「どうやら、毒を盛られていたみたいなんだ。国王、つまり父がね」
「どういうことです⁉」
「そのまんまの意味さ。しかも困ったことに毒自体は既に解毒したのだけれど、衰弱してしまっていてね。もうそんなに長くないだろう。問題は、誰が毒を盛っていたか、ということなんだけど」
「ルチル王子が犯人だと?」
私のはっきりとした物言いに、ベリル王子の眉が一瞬跳ねた。
「状況的に一番怪しいのはね。私ですら、父にはそんなに近寄れなかったんだ。誰かを使おうにも、かなり難しいだろうね」
「それを話させるために、ルチル王子の治療が必要だと?」
「いや。それだけの気持ちではもちろんないさ。純粋に良くなって欲しいとは思っている。一応でも私の兄だからね。そうだ。話のついでに、あの女がどうなったか――」
「必要ありません」
ベリル王子にわざわざ聞かなくても、マリーゴールド、そしてその一族がどうなったかは簡単に想像できる。
家の使用人からマリーゴールドの家が取り潰しにあったと聞いた。
事が事なだけに理由は大っぴらにはなっていないが、そういう事なのだろう。
私は一瞬目を瞑り、マリーゴールドとその一族の安寧を祈った。
「そうか。それで、色々と処理をしないといけないことが多すぎて、君を正式に聖女だと言うことは当分難しそうなんだ。済まないね」
「いえ。構いません。なんでしたら今後も必要ありません」
元々聖女になどなる気はないのだ。
それは実際に戦地へ赴き、負傷兵たちの治療に従事して、より強い気持ちになった。
今さら聖女になりたい気持ちなど一切なかった。
むしろ王都に繋ぎ止められている今が、どうしようもなく感じられた。
今こう話している間にも、負傷兵の治癒は行われているだろう。
デイジーたちは問題なくこなせているだろうか。
「相変わらずだね。ただ、それでは王族としての威厳が保てない。私のできる範囲で、個人的にお礼をしたいと思っている。何か欲しいものはあるかな?」
「どんなことでもいいのでしょうか?」
「私ができる範囲ならね。どんなことでも叶えよう」
「それでは、私を衛生兵として戦場に戻してください。今すぐに」
私は考えるまでもなく、願いを言った。
それを聞いたベリル王子は目を見開き驚いた顔をした後、声を出して笑った。
「あっはっは。まさか、あの地獄から帰還して、それでもあそこに行きたいなんて言うとは思っていなかったよ」
「地獄だからこそ行くのです。そうしなければ、いつまでも地獄のままです」
「分かった。私が総司令官だということも知っての願いなのだろう。私から言い出したことだ。約束は守ろう」
「ありがとうございます」
これでやり残したことを再びできる。
しかし、ベリル王子から出た言葉は私が想像していない事だった。
「ただし。戻る部隊は別の部隊だ。未来の聖女に、それなりの席を用意しなくては。ちょうど、第二部隊の副隊長に空きが出来たところだったはずだ」
以前居た第五衛生兵部隊に戻れると思っていたところ、どうやらこれから向かうのは第二衛生兵部隊のようだ。
しかも、その部隊の副隊長として。
役に就けば自分のやりたいことも通しやすいだろう。
慣れ親しんだ彼女たちと一緒に働けないのは残念だけれど。
そんなことを思いながら、私は自分の信念を実現するために、戦地で自分がやるべきことに思いを馳せていた。
その間、父が「よく戻ってきた」とか「今からでも遅くない」とかを、毎日のように聞かせてくるので、若干うんざりしてしまった。
「やぁ。よく来てくれたね。座ってよ」
「失礼いたします」
今回通されたのは、ベリル王子の私室の一つだった。
ゆったりとしたソファが向かいあわせで置かれていて、奥の方にすでにベリル王子が座っている。
隣に佇むクリスが私に向かって会釈する。
私もベリル王子、そしてクリスにそれぞれ一礼してから、向かいあう形で空いているソファに座った。
「なんだい。こっちにも空きがあるんだから、こっちに座ればいいのに。そこじゃあ、遠いだろ?」
「ご冗談を。今日のご用件はなんでしょうか?」
私の言葉にベリル王子は笑みを強くする。
どうやら私にはこの人の考えを読むのは難しそうだ。
「ああ。そうだね。他でもない。兄さんのことさ」
ベリル王子は呪いが解けた後のルチル王子のことについては淡々と述べた。
その口調や表情からは、そのことを悲しんでいるのか喜んでいるのかは読み取れなかった。
ルチル王子は案の定、心を壊してしまったようだ。
身体に異常がないにもかかわらず、反応もいまいちで、一日中どこか遠くを見つめているだけらしい。
「それで、相談なんだけど。兄さんを元に戻すことはできるのかな?」
「分かりかねます。ただ、魔法の力で、ということでしたら、現時点で方法はありません」
「そうか……それは残念だね。本人の口から直接聞きたかったんだけどな」
「なんのことでしょうか?」
ベリル王子が困った顔でそんなことを言うので、思わず私は聞き返してしまった。
「どうやら、毒を盛られていたみたいなんだ。国王、つまり父がね」
「どういうことです⁉」
「そのまんまの意味さ。しかも困ったことに毒自体は既に解毒したのだけれど、衰弱してしまっていてね。もうそんなに長くないだろう。問題は、誰が毒を盛っていたか、ということなんだけど」
「ルチル王子が犯人だと?」
私のはっきりとした物言いに、ベリル王子の眉が一瞬跳ねた。
「状況的に一番怪しいのはね。私ですら、父にはそんなに近寄れなかったんだ。誰かを使おうにも、かなり難しいだろうね」
「それを話させるために、ルチル王子の治療が必要だと?」
「いや。それだけの気持ちではもちろんないさ。純粋に良くなって欲しいとは思っている。一応でも私の兄だからね。そうだ。話のついでに、あの女がどうなったか――」
「必要ありません」
ベリル王子にわざわざ聞かなくても、マリーゴールド、そしてその一族がどうなったかは簡単に想像できる。
家の使用人からマリーゴールドの家が取り潰しにあったと聞いた。
事が事なだけに理由は大っぴらにはなっていないが、そういう事なのだろう。
私は一瞬目を瞑り、マリーゴールドとその一族の安寧を祈った。
「そうか。それで、色々と処理をしないといけないことが多すぎて、君を正式に聖女だと言うことは当分難しそうなんだ。済まないね」
「いえ。構いません。なんでしたら今後も必要ありません」
元々聖女になどなる気はないのだ。
それは実際に戦地へ赴き、負傷兵たちの治療に従事して、より強い気持ちになった。
今さら聖女になりたい気持ちなど一切なかった。
むしろ王都に繋ぎ止められている今が、どうしようもなく感じられた。
今こう話している間にも、負傷兵の治癒は行われているだろう。
デイジーたちは問題なくこなせているだろうか。
「相変わらずだね。ただ、それでは王族としての威厳が保てない。私のできる範囲で、個人的にお礼をしたいと思っている。何か欲しいものはあるかな?」
「どんなことでもいいのでしょうか?」
「私ができる範囲ならね。どんなことでも叶えよう」
「それでは、私を衛生兵として戦場に戻してください。今すぐに」
私は考えるまでもなく、願いを言った。
それを聞いたベリル王子は目を見開き驚いた顔をした後、声を出して笑った。
「あっはっは。まさか、あの地獄から帰還して、それでもあそこに行きたいなんて言うとは思っていなかったよ」
「地獄だからこそ行くのです。そうしなければ、いつまでも地獄のままです」
「分かった。私が総司令官だということも知っての願いなのだろう。私から言い出したことだ。約束は守ろう」
「ありがとうございます」
これでやり残したことを再びできる。
しかし、ベリル王子から出た言葉は私が想像していない事だった。
「ただし。戻る部隊は別の部隊だ。未来の聖女に、それなりの席を用意しなくては。ちょうど、第二部隊の副隊長に空きが出来たところだったはずだ」
以前居た第五衛生兵部隊に戻れると思っていたところ、どうやらこれから向かうのは第二衛生兵部隊のようだ。
しかも、その部隊の副隊長として。
役に就けば自分のやりたいことも通しやすいだろう。
慣れ親しんだ彼女たちと一緒に働けないのは残念だけれど。
そんなことを思いながら、私は自分の信念を実現するために、戦地で自分がやるべきことに思いを馳せていた。
「本日よりこちらに配属されたフローラです。よろしくお願いします」
「ああ。いらっしゃい。まぁ、そんなに畏まらず、楽にやってよ」
ベリル王子に要望を出して、次の日には王都を出立して再び戦線へと向かった。
今回配属するのは第二衛生兵部隊。
そこに着くと、その足で司令室にいる部隊長のゾイスの元へ挨拶に向かった。
ゾイスは歳はアンバーより若く見えるが、軍属の割には緩んだ身体の持ち主だった。
初期のアンバーとはまた毛色の違った笑みを顔に貼り付け、右手に持つハンカチーフで額と首元の汗を拭いている。
人を見かけで判断してはいけないけれど、あまり好ましいと思うような相手には思えなかった。
「それでは、早速業務に携わりたいのですがよろしいでしょうか?」
「ん? ああ、ああ。まぁ、そんな気張らなくていいってば。えーっと、フローラ君だっけ? 君に会ったら聞きたい事があったんだ」
「なんでしょうか?」
「君さ。誰に取り入ったの? もし良かったら教えてよ。何? やっぱり女性の武器ってやつを使ったのかな? いいよねぇ」
そう言いながらゾイスはすでに上がっている口角を更に上げる。
どうやら侮辱を受けているようだ。
「なんのことだか分かりません。それでは、早く現場に慣れたいのでこれで失礼します」
「あ、そう。まぁいいや。所詮君は副隊長。部隊長の俺には逆らえないんだから、ちゃんと地位を弁えた行動を頼むね。それじゃ、行っていいよ」
そう言いながら、ゾイスは手に持つハンカチーフを前後に振る。
かなり良い性格の持ち主のようだが、私の目的は部隊長に気に入られることではない。
にやけ顔の上官を無視するように、最低限の礼をしてから司令官室を後にした。
そこではたと、この陣営の治療場の場所を聞くのを忘れたのに気付いた。
通りすがりの兵士に自己紹介をしてから、治療場の場所を聞く。
私が新しく配属された副隊長だと言った時には、かなり驚いた顔をしたが、胸につけてある徽章を見て納得したようだ。
改めて軍特有の礼を私にしてから、丁寧な口調で案内してくれた。
治療場に向かう間、私はその兵士に色々と聞いてみることにした。
「ここの衛生兵の人数を知っている?」
「はい。全部で三十名ほどだと思います」
「結構多いのね。それで、その中で回復魔法を使えるのは何人くらいいるのかしら?」
「回復魔法ですか? 誰がどのくらい使えるかまでは詳しく知りませんが、ここにいる衛生兵は全員使えるはずです。ご存知なかったのですか?」
返答を聞いて、私は驚いた顔をしてしまった。
以前いた第五衛生兵部隊の衛生兵は、今では全員が回復魔法を使えるものの、初めは数人しかいなかった。
それが、ここでは全員が使えるというのだ。
私は、この僥倖に思わず顔を緩めてしまう。
始めから使えるのであれば、それなりの素質を持つ者ばかりなのだろう。
うまく訓練を行えば、その内解呪の魔法すら使いこなす者も多く誕生するかもしれない。
私は喜び勇んで兵士に返答する。
「ごめんなさい。知らないの。ここの衛生兵が全員回復魔法を使えることに、何か理由があるの?」
私の言葉を聞いた兵士は、少し考え込み、そして戸惑いを見せながらこう答えた。
「ここに所属するためには最低限回復魔法を元々使えることが条件なのです。ですから――」
始めの言葉に、素晴らしいと思ったのも束の間、続く言葉は、あまり好ましいものではなかった。
兵士の話はこういうことだった。
衛生兵として送られる者は、回復魔法の適性を鑑みて女性、しかも危険な前線に送られるのは、一身上に様々な問題がある者ばかり。
夫を亡くした未亡人や、雇い先から解雇を告げられたメイドなどだ。
一方、回復魔法を教える施設などは一般的には無い。
私も、父が家庭教師を呼び、様々な書物を買い与えてくれたからこそ、学ぶ事ができた。
それにはそれなり以上の資金が必要だ。
そして、夫や職を失った女性が、簡単に払えるような額では無い。
人によってはその身を売った人もいるだろう。
そうやってなんとか捻出した資金で、ようやく回復魔法の教えを乞い、身に付けて配属されたのがここいる大半らしい。
彼女らの努力は買うが、そこまでしなければならない現状を再度理解し、私はベリル王子に再度教育機関の創設を打診することを心に決めた。
「着きました。ここが治療場です。今、呼び集めますのでお待ちください」
「いいえ。結構よ。挨拶なら作業をしながらでもできるわ。ありがとう。持ち場へ戻って大丈夫よ」
そう言うと、兵士はまた一礼をしてその場から去っていった。
一人残った私は、治療場の状況を確認するために一望する。
広さは第五部隊よりも少し広いがそこまで変わらず、多少臭いや汚れが気になるものの、そこまで酷い状況にはなっていなかった。
安心した気持ちで、治癒に当たっている人たちに目を移していく。
確かに兵士が言っていた通り、その場にいる全員が回復魔法を使えるようだ。
ほとんどが初級の回復魔法ではあるものの、手際よく負傷している兵士の傷を治していくのが見えた。
「なるほど。これならまずは大丈夫そうね――」
そう独り言を呟いた矢先、一人の衛生兵の行動が目に付いた。
その衛生兵は、右足を失った兵士の治癒に当たっている。
その女性は先ほどから初級の回復魔法しか使っていないように思える人物だった。
せいぜい出来ても傷口を塞ぐだけ、失った四肢を再生させるのには無理がある。
もしかしたら、そのような魔法も使えるのかもしれないと、注視していると、果たして使ったのは、やはり初級の治癒の魔法だった。
布で止血をしていた負傷兵の傷が光に包まれ、そして光が消える頃には傷口は塞がっていた。
そこまでやると、衛生兵は立ち上がり、別の負傷兵の方へと向かう。
もちろん、傷口は塞がったものの、脚は再生されておらず、失ったままだ。
負傷兵は悔しそうな顔をして起き上がると、別の者から渡された木の棒を杖代わりにその場を後にしようとしている。
他の衛生兵もその兵士に構う者は見当たらない。
「ちょっと! あなたたち! 何をしているの⁉」
思わず私は叫んでいた。
その声に、その場にいた全員が私の方を向く。
見ていた限り、ごく少数ではあるものの、四肢を再生させることのできる中級の治癒の魔法を使える者も中にはいた。
その衛生兵に任せれば、今目の前にいる杖を突いた兵士の脚を取り戻すことができたはずだ。
「なぜ、治せる者が治さないの⁉ この人の脚は⁉」
状況が掴めていないのか、誰も何も言わず、不思議そうな顔を私に向ける。
時間の無駄を感じ、私は目の前を通り過ぎようとしている脚を失った兵士に声をかける。
「その場に横になりなさい。やり直しよ。脚を、切るわね」
「ああ。いらっしゃい。まぁ、そんなに畏まらず、楽にやってよ」
ベリル王子に要望を出して、次の日には王都を出立して再び戦線へと向かった。
今回配属するのは第二衛生兵部隊。
そこに着くと、その足で司令室にいる部隊長のゾイスの元へ挨拶に向かった。
ゾイスは歳はアンバーより若く見えるが、軍属の割には緩んだ身体の持ち主だった。
初期のアンバーとはまた毛色の違った笑みを顔に貼り付け、右手に持つハンカチーフで額と首元の汗を拭いている。
人を見かけで判断してはいけないけれど、あまり好ましいと思うような相手には思えなかった。
「それでは、早速業務に携わりたいのですがよろしいでしょうか?」
「ん? ああ、ああ。まぁ、そんな気張らなくていいってば。えーっと、フローラ君だっけ? 君に会ったら聞きたい事があったんだ」
「なんでしょうか?」
「君さ。誰に取り入ったの? もし良かったら教えてよ。何? やっぱり女性の武器ってやつを使ったのかな? いいよねぇ」
そう言いながらゾイスはすでに上がっている口角を更に上げる。
どうやら侮辱を受けているようだ。
「なんのことだか分かりません。それでは、早く現場に慣れたいのでこれで失礼します」
「あ、そう。まぁいいや。所詮君は副隊長。部隊長の俺には逆らえないんだから、ちゃんと地位を弁えた行動を頼むね。それじゃ、行っていいよ」
そう言いながら、ゾイスは手に持つハンカチーフを前後に振る。
かなり良い性格の持ち主のようだが、私の目的は部隊長に気に入られることではない。
にやけ顔の上官を無視するように、最低限の礼をしてから司令官室を後にした。
そこではたと、この陣営の治療場の場所を聞くのを忘れたのに気付いた。
通りすがりの兵士に自己紹介をしてから、治療場の場所を聞く。
私が新しく配属された副隊長だと言った時には、かなり驚いた顔をしたが、胸につけてある徽章を見て納得したようだ。
改めて軍特有の礼を私にしてから、丁寧な口調で案内してくれた。
治療場に向かう間、私はその兵士に色々と聞いてみることにした。
「ここの衛生兵の人数を知っている?」
「はい。全部で三十名ほどだと思います」
「結構多いのね。それで、その中で回復魔法を使えるのは何人くらいいるのかしら?」
「回復魔法ですか? 誰がどのくらい使えるかまでは詳しく知りませんが、ここにいる衛生兵は全員使えるはずです。ご存知なかったのですか?」
返答を聞いて、私は驚いた顔をしてしまった。
以前いた第五衛生兵部隊の衛生兵は、今では全員が回復魔法を使えるものの、初めは数人しかいなかった。
それが、ここでは全員が使えるというのだ。
私は、この僥倖に思わず顔を緩めてしまう。
始めから使えるのであれば、それなりの素質を持つ者ばかりなのだろう。
うまく訓練を行えば、その内解呪の魔法すら使いこなす者も多く誕生するかもしれない。
私は喜び勇んで兵士に返答する。
「ごめんなさい。知らないの。ここの衛生兵が全員回復魔法を使えることに、何か理由があるの?」
私の言葉を聞いた兵士は、少し考え込み、そして戸惑いを見せながらこう答えた。
「ここに所属するためには最低限回復魔法を元々使えることが条件なのです。ですから――」
始めの言葉に、素晴らしいと思ったのも束の間、続く言葉は、あまり好ましいものではなかった。
兵士の話はこういうことだった。
衛生兵として送られる者は、回復魔法の適性を鑑みて女性、しかも危険な前線に送られるのは、一身上に様々な問題がある者ばかり。
夫を亡くした未亡人や、雇い先から解雇を告げられたメイドなどだ。
一方、回復魔法を教える施設などは一般的には無い。
私も、父が家庭教師を呼び、様々な書物を買い与えてくれたからこそ、学ぶ事ができた。
それにはそれなり以上の資金が必要だ。
そして、夫や職を失った女性が、簡単に払えるような額では無い。
人によってはその身を売った人もいるだろう。
そうやってなんとか捻出した資金で、ようやく回復魔法の教えを乞い、身に付けて配属されたのがここいる大半らしい。
彼女らの努力は買うが、そこまでしなければならない現状を再度理解し、私はベリル王子に再度教育機関の創設を打診することを心に決めた。
「着きました。ここが治療場です。今、呼び集めますのでお待ちください」
「いいえ。結構よ。挨拶なら作業をしながらでもできるわ。ありがとう。持ち場へ戻って大丈夫よ」
そう言うと、兵士はまた一礼をしてその場から去っていった。
一人残った私は、治療場の状況を確認するために一望する。
広さは第五部隊よりも少し広いがそこまで変わらず、多少臭いや汚れが気になるものの、そこまで酷い状況にはなっていなかった。
安心した気持ちで、治癒に当たっている人たちに目を移していく。
確かに兵士が言っていた通り、その場にいる全員が回復魔法を使えるようだ。
ほとんどが初級の回復魔法ではあるものの、手際よく負傷している兵士の傷を治していくのが見えた。
「なるほど。これならまずは大丈夫そうね――」
そう独り言を呟いた矢先、一人の衛生兵の行動が目に付いた。
その衛生兵は、右足を失った兵士の治癒に当たっている。
その女性は先ほどから初級の回復魔法しか使っていないように思える人物だった。
せいぜい出来ても傷口を塞ぐだけ、失った四肢を再生させるのには無理がある。
もしかしたら、そのような魔法も使えるのかもしれないと、注視していると、果たして使ったのは、やはり初級の治癒の魔法だった。
布で止血をしていた負傷兵の傷が光に包まれ、そして光が消える頃には傷口は塞がっていた。
そこまでやると、衛生兵は立ち上がり、別の負傷兵の方へと向かう。
もちろん、傷口は塞がったものの、脚は再生されておらず、失ったままだ。
負傷兵は悔しそうな顔をして起き上がると、別の者から渡された木の棒を杖代わりにその場を後にしようとしている。
他の衛生兵もその兵士に構う者は見当たらない。
「ちょっと! あなたたち! 何をしているの⁉」
思わず私は叫んでいた。
その声に、その場にいた全員が私の方を向く。
見ていた限り、ごく少数ではあるものの、四肢を再生させることのできる中級の治癒の魔法を使える者も中にはいた。
その衛生兵に任せれば、今目の前にいる杖を突いた兵士の脚を取り戻すことができたはずだ。
「なぜ、治せる者が治さないの⁉ この人の脚は⁉」
状況が掴めていないのか、誰も何も言わず、不思議そうな顔を私に向ける。
時間の無駄を感じ、私は目の前を通り過ぎようとしている脚を失った兵士に声をかける。
「その場に横になりなさい。やり直しよ。脚を、切るわね」
「あ、脚を切る? 何を言ってるんだ⁉」
「いいから、早くそこに横になりなさい。手遅れになりますよ」
私は理解していないだろう兵士を無理やり横にさせる。
そして、兵士の腰に差してある剣を抜き取り、刃を先ほど塞がれた脚の傷に当てる。
「な、何をする気だ⁉ 止めろ‼」
「私はあなたを、傷付けてでも治します!」
説明している暇がないというわけではないが、説明したところでそれを受け入れる心の準備を待つほどの余裕がない。
塞がった傷口が、固定化される前に早く治療しなければ。
失った脚や腕すら再生できる治癒の魔法でも、一度回復魔法によって傷口を塞がれ、それを身体が覚えてしまった後には治すことができない。
つまり、一度傷口を塞いでしまった彼の脚を取り戻すためには、再び傷口を開いてから再生させるしかないのだ。
それも早くしないとこの兵士の身体がこれを自然だと認識してしまい、いくら傷口を開いても、再生することは困難になる。
そのため、なるべく早くの処置が必要なのだ。
私は兵士が制止しようとする前に、脚の傷口を取った剣で斬りつけた。
一度は塞がった傷口から血が噴き出し、辺りを赤く染める。
「ぐぁぁああ‼」
「きゃあああ‼」
兵士と、それを見ていた者たちが叫び声を上げる。
私は構うことなく、脚を再生するための魔法を唱え、兵士に使った。
魔法の光が兵士のあったはずの脚の形を作り、そして輝きを強めた後に消える。
後には元の脚が、きちんと生えていた。
「な⁉ 俺の! 俺の脚が‼ ああ‼ ありがとう! ありがとうございます‼」
何が起きたのか理解した兵士が、泣き顔でお礼を言ってきた。
私は立ち上がると、剣についた血を布で拭うと兵士に返す。
「私は! 本日この部隊に配属された副隊長のフローラです! ここの状況の詳しい話は後で聞きます! 自分で治せないと判断した兵士は、全て私に任せなさい! 以上、自分の仕事に専念しなさい‼」
私の言葉に、そして胸の徽章に状況を理解したのか、衛生兵たちは慌てた様子で治療に戻る。
その内、一人がおずおずと私の元にやってきて小さな声を出した。
「あの……副隊長。私に彼は治せません……あの、それで……その……」
「分かったわ。自分のできる兵士の治療に専念なさい。そっちは私がやります」
見ると、彼女が担当した兵士は、腹部に大きな傷を受けていた。
外から見ただけでははっきりしないが、おそらく内部まで傷を受けているだろう。
これを初級の治癒魔法で回復するには、何度も魔法をかけ、内部から外へかけて回復をする必要がある。
それはある程度魔力操作ができないと難しく、それが出来ずに魔法をかけると、表層だけ傷が癒え、後から内部をきちんと治すのが逆に難しくなる。
私は全体を一度に回復させる治癒の魔法を使い、腹部の傷を癒していく。
絶望の顔を見せていた兵士は、先ほどのやり取りを見ていたのだろうか、私が癒すことを知ると、安堵の表情に変わった。
結局、魔力枯渇で倒れるぎりぎりまで、多くの兵士を私が治癒することになった。
☆
一通りの治癒を終え、一度休憩するために自室に戻ろうとした途中で、兵士にゾイスが私を呼んでいると報告があった。
私は頭痛を抱えながら、ゾイスの居る司令室へと足を運んだ。
「お呼びでしょうか?」
「ああ、君か。まったく。フローラ君、だっけ? 面倒なことをしてくれたね」
「面倒なこと……? とは、何のことでしょうか?」
「はぁ……君ね。この部隊の負傷兵の致死率がどれくらいか知ってる?」
何のことを言いたいのか分からないが、王都からここに来る道中、この部隊のことを知ろうと報告書には目を通してある。
確か記憶では、ここの致死率は極端に低く、5パーセント程度だったはずだ。
私はそれを見て、大したものだと感心した記憶があるから、数値に間違いはないはずだ。
「確か、5パーセント程だったと記憶していますが……それが何か?」
「4.876パーセントだよ。君、これがどれだけ凄いか分かる?」
確かに、私が配属されたばかりの時の第五部隊の致死率は40パーセントを超えていた。
それから見れば、この数値がいかに低いかは言われなくても分かる。
「何でも君、他の衛生兵から負傷兵を奪っては治していったそうじゃないか。一体どう言うつもりだい?」
「同じ衛生兵でも、技能に未熟な者が居ます。治せない者に治療させては、完治はできません」
「完治したかどうかなんて関係ないんだよ! 生きてるか死んだかが重要なんだ! 君、報告書に完治率なんてどこにもないんだよ⁉ そんなこと気にしてどうすんのさ」
「仰っている意味が分かりませんが……?」
私の返答にゾイスは一度息を吐き出し、更にまくし立てる。
「必要なのは、低い致死率と! それと延べ人数だよ! 君一人じゃ、人数増やせないだろ⁉ 何? 一人で三十人分働くの⁉ 働けないだろ‼ 余計なことしてないで、兵士なんて生きてりゃいいんだよ。生きてりゃ。腕が無かろうが、脚が無かろうが生きてりゃね!」
私は唾を飛ばしながら喚くこの生き物を、目を細めて一言も返さずに見ていた。
どうやらゾイスは、兵士の生き死にや健全な肉体を取り戻すことよりも、この部隊の成績、しかも上官に報告するための数値だけに興味があるようだ。
私は冷めた目でゾイスを見つめる。
その目線に気が付いたのか、少したじろいた後、ゾイスは更に言葉を発した。
「と、とにかく。余計なことは許さないよ。これは部隊長命令だ。君はそれを守る義務がある。分かったね? 分かったら、もう、行ってよし!」
「分かりました。失礼します」
私は礼をせず、司令室を後にした。
そして痛む頭に手を当て、思考にふける。
ゾイスが言う通り、致死率を下げることには私も異存はない。
治療できた兵士の人数が多いことが良いことなのも、問題はない。
しかし目的が違う。
おそらくゾイスは、自分の評価を上げることが目的なのだろう。
私の考え方とは、根本的に違うのだ。
そんな生き物が部隊長だというこの部隊を、今後どうすればいいか、私は深く考えていた。
「いいから、早くそこに横になりなさい。手遅れになりますよ」
私は理解していないだろう兵士を無理やり横にさせる。
そして、兵士の腰に差してある剣を抜き取り、刃を先ほど塞がれた脚の傷に当てる。
「な、何をする気だ⁉ 止めろ‼」
「私はあなたを、傷付けてでも治します!」
説明している暇がないというわけではないが、説明したところでそれを受け入れる心の準備を待つほどの余裕がない。
塞がった傷口が、固定化される前に早く治療しなければ。
失った脚や腕すら再生できる治癒の魔法でも、一度回復魔法によって傷口を塞がれ、それを身体が覚えてしまった後には治すことができない。
つまり、一度傷口を塞いでしまった彼の脚を取り戻すためには、再び傷口を開いてから再生させるしかないのだ。
それも早くしないとこの兵士の身体がこれを自然だと認識してしまい、いくら傷口を開いても、再生することは困難になる。
そのため、なるべく早くの処置が必要なのだ。
私は兵士が制止しようとする前に、脚の傷口を取った剣で斬りつけた。
一度は塞がった傷口から血が噴き出し、辺りを赤く染める。
「ぐぁぁああ‼」
「きゃあああ‼」
兵士と、それを見ていた者たちが叫び声を上げる。
私は構うことなく、脚を再生するための魔法を唱え、兵士に使った。
魔法の光が兵士のあったはずの脚の形を作り、そして輝きを強めた後に消える。
後には元の脚が、きちんと生えていた。
「な⁉ 俺の! 俺の脚が‼ ああ‼ ありがとう! ありがとうございます‼」
何が起きたのか理解した兵士が、泣き顔でお礼を言ってきた。
私は立ち上がると、剣についた血を布で拭うと兵士に返す。
「私は! 本日この部隊に配属された副隊長のフローラです! ここの状況の詳しい話は後で聞きます! 自分で治せないと判断した兵士は、全て私に任せなさい! 以上、自分の仕事に専念しなさい‼」
私の言葉に、そして胸の徽章に状況を理解したのか、衛生兵たちは慌てた様子で治療に戻る。
その内、一人がおずおずと私の元にやってきて小さな声を出した。
「あの……副隊長。私に彼は治せません……あの、それで……その……」
「分かったわ。自分のできる兵士の治療に専念なさい。そっちは私がやります」
見ると、彼女が担当した兵士は、腹部に大きな傷を受けていた。
外から見ただけでははっきりしないが、おそらく内部まで傷を受けているだろう。
これを初級の治癒魔法で回復するには、何度も魔法をかけ、内部から外へかけて回復をする必要がある。
それはある程度魔力操作ができないと難しく、それが出来ずに魔法をかけると、表層だけ傷が癒え、後から内部をきちんと治すのが逆に難しくなる。
私は全体を一度に回復させる治癒の魔法を使い、腹部の傷を癒していく。
絶望の顔を見せていた兵士は、先ほどのやり取りを見ていたのだろうか、私が癒すことを知ると、安堵の表情に変わった。
結局、魔力枯渇で倒れるぎりぎりまで、多くの兵士を私が治癒することになった。
☆
一通りの治癒を終え、一度休憩するために自室に戻ろうとした途中で、兵士にゾイスが私を呼んでいると報告があった。
私は頭痛を抱えながら、ゾイスの居る司令室へと足を運んだ。
「お呼びでしょうか?」
「ああ、君か。まったく。フローラ君、だっけ? 面倒なことをしてくれたね」
「面倒なこと……? とは、何のことでしょうか?」
「はぁ……君ね。この部隊の負傷兵の致死率がどれくらいか知ってる?」
何のことを言いたいのか分からないが、王都からここに来る道中、この部隊のことを知ろうと報告書には目を通してある。
確か記憶では、ここの致死率は極端に低く、5パーセント程度だったはずだ。
私はそれを見て、大したものだと感心した記憶があるから、数値に間違いはないはずだ。
「確か、5パーセント程だったと記憶していますが……それが何か?」
「4.876パーセントだよ。君、これがどれだけ凄いか分かる?」
確かに、私が配属されたばかりの時の第五部隊の致死率は40パーセントを超えていた。
それから見れば、この数値がいかに低いかは言われなくても分かる。
「何でも君、他の衛生兵から負傷兵を奪っては治していったそうじゃないか。一体どう言うつもりだい?」
「同じ衛生兵でも、技能に未熟な者が居ます。治せない者に治療させては、完治はできません」
「完治したかどうかなんて関係ないんだよ! 生きてるか死んだかが重要なんだ! 君、報告書に完治率なんてどこにもないんだよ⁉ そんなこと気にしてどうすんのさ」
「仰っている意味が分かりませんが……?」
私の返答にゾイスは一度息を吐き出し、更にまくし立てる。
「必要なのは、低い致死率と! それと延べ人数だよ! 君一人じゃ、人数増やせないだろ⁉ 何? 一人で三十人分働くの⁉ 働けないだろ‼ 余計なことしてないで、兵士なんて生きてりゃいいんだよ。生きてりゃ。腕が無かろうが、脚が無かろうが生きてりゃね!」
私は唾を飛ばしながら喚くこの生き物を、目を細めて一言も返さずに見ていた。
どうやらゾイスは、兵士の生き死にや健全な肉体を取り戻すことよりも、この部隊の成績、しかも上官に報告するための数値だけに興味があるようだ。
私は冷めた目でゾイスを見つめる。
その目線に気が付いたのか、少したじろいた後、ゾイスは更に言葉を発した。
「と、とにかく。余計なことは許さないよ。これは部隊長命令だ。君はそれを守る義務がある。分かったね? 分かったら、もう、行ってよし!」
「分かりました。失礼します」
私は礼をせず、司令室を後にした。
そして痛む頭に手を当て、思考にふける。
ゾイスが言う通り、致死率を下げることには私も異存はない。
治療できた兵士の人数が多いことが良いことなのも、問題はない。
しかし目的が違う。
おそらくゾイスは、自分の評価を上げることが目的なのだろう。
私の考え方とは、根本的に違うのだ。
そんな生き物が部隊長だというこの部隊を、今後どうすればいいか、私は深く考えていた。
結局いい案が思い浮かばず、私は頭痛を抱えて自室へ戻ることにした。
尽きた魔力を回復させるため休んでいると、扉を叩く音が聞こえ身を起こす。
「聖女様! こちらでしょうか?」
「開いているわ。入りなさい」
ここに居るはずのない懐かしい声が聞こえ、私は不思議に思いながらも声の主を招き入れる。
扉が開き、そこに立っていたのは第五衛生兵部隊で一緒に働いていたデイジーだった。
「聖女様‼」
「デイジー! 何故ここにいるの? あなた一人?」
「いいえ。私の他に、ここまでの護衛でクロムがおります」
「聖女様! またお会いできて嬉しいです‼」
私の言葉に、デイジーが後ろに控えていたクロムを見せる。
クロムは私の部屋に入っていいのか悩んでいるのか、外から身体を乗り出している。
「二人とも入っていいわ。よく来たわね。それで? どういうことか説明してちょうだい」
「実は、私たち。ここに転属になったんです」
デイジーの言葉に私は驚く。
別の部隊に転属というのはないことはないだろうが、私がここに配属された初日に、となると何らかの意図を感じる。
「実は、私たちも理由は詳しくは知らないんです」
「アンバー部隊長に、理由は聞くな。これは絶対命令だ。とだけ言われていまして」
アンバーが本人たちにそう言うということは、かなり上の者から直接命令だったのだろう。
私の脳裏には、身分をわざわざ隠さなければいけない、上位の者の顔が、一人だけ浮かんだ。
「でも! こうしてまた聖女様と一緒に働けるのが、私嬉しいです!」
「俺も、張り切って警護に当たりますよ‼ 魔獣なんてドンと来いです‼」
「ええ。私も嬉しいわ。デイジー。魔獣は来なければ、来ない方がいいのよ。クロム」
私の言葉にデイジーは両手を胸の辺りで組んで、嬉しそうな顔を見せる。
クロムは人差し指で頬をかいた。
「まぁ。それは言葉のあやと言いますか。でも! 聖女様のこと、全力でお守りしますので‼」
「ええ。ありがとう」
おそらくベリル王子がこの二人をここに送ってくれたのは間違いないだろう。
と、すればここの現状も知っていて、私を配属させたのだろうか。
思えば、そもそも私がこの戦場に配属できたのも、ベリル王子の口添えだとルチル王子が言っていた。
その時は、深く考えもしなかったが、ベリル王子の評判を考えると、考え無しにそんなことを言うはずがない。
実際に、私は希望通りに前線に赴き、私の考えで第五衛生兵部隊の状況の改善に務めた。
その結果、まだやり残したところはあるものの、私が居なくても、多くの負傷兵を助けることができる体制作りが出来たといえる。
そんな中の帰還命令。
そしてルチル王子の解呪と今回の配属先を変えられ、副隊長という任を与えられての配属。
どれもベリル王子の考えあっての事のように思えて来て仕方がない。
具体的に何か言われた訳ではないけれど、問題のある部隊に配属され、悩んでいたところにこうして助けとなる人物を送ってきたのだ。
「デイジー、あなたに頼みがあるの。お願いできるかしら」
「聖女様からのお願いを断るわけがありません‼ なんでも仰ってください‼」
私の問いかけに、デイジーは喜色ばった表情を向ける。
それを見たクロムは、自分も何かできることがないのかと物欲しそうな顔を見せている。
「そんな顔しないで。クロム。あなたにも、やって欲しいことがあるのよ。お願いできるかしら?」
「はい‼ もちろん。喜んで‼」
二人の顔を見て思いついたことを、それぞれ伝える。
この部隊の現状を聞いて驚いた顔をする二人だったが、私の要望を聞くと、二つ返事で早速動き始めた。
私はできるだけ早く魔力を回復させるため、一度横になり仮眠を取った。
☆
「一体どういうことだね⁉」
誰かが叫ぶ声に目を覚ます。
どのくらい寝ていたか分からないけれど、魔力枯渇による頭痛はすでに消えていた。
「何故、こんな兵士たちが俺の部隊に集まるんだ‼ 毒や呪いを受けた兵士はできるだけ受け入れないようにと言ったはずだ‼」
「しかし……今日からはそのような兵士も積極的に受け入れるようにと伝達があったはずですが……」
どうやら叫んでいるのは部隊長のゾイスのようだ。
おそらく、クロムに頼んだことがもう効果として現れたのだろう。
「どうしました? 何か騒がしいようですが、問題でも?」
「君か⁉ ふん‼ 今までどこへ行っていたんだ! いいご身分だな! 緊急事態だよ! 毒にやられた兵士がわんさかここに運ばれているんだ‼」
「それに何か問題が? 治せばいいではありませんか」
「馬鹿を言うな! ここにいる衛生兵で解毒の魔法なんて高等な魔法を使えるのは一人しかいないんだよ‼ 全員助けるなんて到底無理だ! せっかくの低い致死率に傷がつく‼」
相変わらずの態度に、私は胸にムカつきを感じながらも、表情を変えることなく答える。
「問題ありません。その解毒の魔法を使える衛生兵の名は?」
「あ⁉ えーっと、そうだ‼ サルビアだよ! それがどうした‼」
「いえ。とにかく。問題ありません。私はこれから現場に行きますので、部隊長はどうぞ司令室へお戻りください」
「何が問題ないんだ‼ あー! どうすればいいんだ‼ 今まであんなに――」
まだ喚き続けている生き物を置いて、私は治療場へと向かう。
ゾイスの言う通り、先ほどまではほとんど見かけなかった、魔獣の毒を受けた兵士たちが多く居た。
「聖女様! こちらです‼」
すでにデイジーは、兵士たちの解毒に当たっている。
それを、一人を除いて他の衛生兵たちが遠巻きに戸惑いながら見つめていた。
「あなたがサルビアね。解毒の魔法はどのくらい?」
「新しくきた副隊長ですね? そうです。サルビアと申します。恥ずかしながら、解毒の魔法は初級がやっとです」
長い黒髪を一つ、後ろで三つ編みにした女性に話しかける。
サルビアはデイジーと共に、兵士の解毒に当たっていた。
「十分よ。今から私が選んだ兵士だけ解毒しなさい。それと、治癒は他の人に任せて。あなたは解毒だけに専念するのよ。いいわね?」
「はい。分かりました」
「これから私たち三人は解毒作業に専念するわ! 他の衛生兵は、解毒が済んだ兵の治癒に当たりなさい! ただし! 自分が完全に治せる傷だけを選ぶの! いいわね‼」
私の言葉に、やっと自分たちがどうすればいいのか、方針が決まり安堵したように傍観していた衛生兵たちも動きだす。
私はそれを見届けた後、腫れ上がった腕を押さえながら、苦しげな表情をする兵士へ解毒の魔法を唱えた。
尽きた魔力を回復させるため休んでいると、扉を叩く音が聞こえ身を起こす。
「聖女様! こちらでしょうか?」
「開いているわ。入りなさい」
ここに居るはずのない懐かしい声が聞こえ、私は不思議に思いながらも声の主を招き入れる。
扉が開き、そこに立っていたのは第五衛生兵部隊で一緒に働いていたデイジーだった。
「聖女様‼」
「デイジー! 何故ここにいるの? あなた一人?」
「いいえ。私の他に、ここまでの護衛でクロムがおります」
「聖女様! またお会いできて嬉しいです‼」
私の言葉に、デイジーが後ろに控えていたクロムを見せる。
クロムは私の部屋に入っていいのか悩んでいるのか、外から身体を乗り出している。
「二人とも入っていいわ。よく来たわね。それで? どういうことか説明してちょうだい」
「実は、私たち。ここに転属になったんです」
デイジーの言葉に私は驚く。
別の部隊に転属というのはないことはないだろうが、私がここに配属された初日に、となると何らかの意図を感じる。
「実は、私たちも理由は詳しくは知らないんです」
「アンバー部隊長に、理由は聞くな。これは絶対命令だ。とだけ言われていまして」
アンバーが本人たちにそう言うということは、かなり上の者から直接命令だったのだろう。
私の脳裏には、身分をわざわざ隠さなければいけない、上位の者の顔が、一人だけ浮かんだ。
「でも! こうしてまた聖女様と一緒に働けるのが、私嬉しいです!」
「俺も、張り切って警護に当たりますよ‼ 魔獣なんてドンと来いです‼」
「ええ。私も嬉しいわ。デイジー。魔獣は来なければ、来ない方がいいのよ。クロム」
私の言葉にデイジーは両手を胸の辺りで組んで、嬉しそうな顔を見せる。
クロムは人差し指で頬をかいた。
「まぁ。それは言葉のあやと言いますか。でも! 聖女様のこと、全力でお守りしますので‼」
「ええ。ありがとう」
おそらくベリル王子がこの二人をここに送ってくれたのは間違いないだろう。
と、すればここの現状も知っていて、私を配属させたのだろうか。
思えば、そもそも私がこの戦場に配属できたのも、ベリル王子の口添えだとルチル王子が言っていた。
その時は、深く考えもしなかったが、ベリル王子の評判を考えると、考え無しにそんなことを言うはずがない。
実際に、私は希望通りに前線に赴き、私の考えで第五衛生兵部隊の状況の改善に務めた。
その結果、まだやり残したところはあるものの、私が居なくても、多くの負傷兵を助けることができる体制作りが出来たといえる。
そんな中の帰還命令。
そしてルチル王子の解呪と今回の配属先を変えられ、副隊長という任を与えられての配属。
どれもベリル王子の考えあっての事のように思えて来て仕方がない。
具体的に何か言われた訳ではないけれど、問題のある部隊に配属され、悩んでいたところにこうして助けとなる人物を送ってきたのだ。
「デイジー、あなたに頼みがあるの。お願いできるかしら」
「聖女様からのお願いを断るわけがありません‼ なんでも仰ってください‼」
私の問いかけに、デイジーは喜色ばった表情を向ける。
それを見たクロムは、自分も何かできることがないのかと物欲しそうな顔を見せている。
「そんな顔しないで。クロム。あなたにも、やって欲しいことがあるのよ。お願いできるかしら?」
「はい‼ もちろん。喜んで‼」
二人の顔を見て思いついたことを、それぞれ伝える。
この部隊の現状を聞いて驚いた顔をする二人だったが、私の要望を聞くと、二つ返事で早速動き始めた。
私はできるだけ早く魔力を回復させるため、一度横になり仮眠を取った。
☆
「一体どういうことだね⁉」
誰かが叫ぶ声に目を覚ます。
どのくらい寝ていたか分からないけれど、魔力枯渇による頭痛はすでに消えていた。
「何故、こんな兵士たちが俺の部隊に集まるんだ‼ 毒や呪いを受けた兵士はできるだけ受け入れないようにと言ったはずだ‼」
「しかし……今日からはそのような兵士も積極的に受け入れるようにと伝達があったはずですが……」
どうやら叫んでいるのは部隊長のゾイスのようだ。
おそらく、クロムに頼んだことがもう効果として現れたのだろう。
「どうしました? 何か騒がしいようですが、問題でも?」
「君か⁉ ふん‼ 今までどこへ行っていたんだ! いいご身分だな! 緊急事態だよ! 毒にやられた兵士がわんさかここに運ばれているんだ‼」
「それに何か問題が? 治せばいいではありませんか」
「馬鹿を言うな! ここにいる衛生兵で解毒の魔法なんて高等な魔法を使えるのは一人しかいないんだよ‼ 全員助けるなんて到底無理だ! せっかくの低い致死率に傷がつく‼」
相変わらずの態度に、私は胸にムカつきを感じながらも、表情を変えることなく答える。
「問題ありません。その解毒の魔法を使える衛生兵の名は?」
「あ⁉ えーっと、そうだ‼ サルビアだよ! それがどうした‼」
「いえ。とにかく。問題ありません。私はこれから現場に行きますので、部隊長はどうぞ司令室へお戻りください」
「何が問題ないんだ‼ あー! どうすればいいんだ‼ 今まであんなに――」
まだ喚き続けている生き物を置いて、私は治療場へと向かう。
ゾイスの言う通り、先ほどまではほとんど見かけなかった、魔獣の毒を受けた兵士たちが多く居た。
「聖女様! こちらです‼」
すでにデイジーは、兵士たちの解毒に当たっている。
それを、一人を除いて他の衛生兵たちが遠巻きに戸惑いながら見つめていた。
「あなたがサルビアね。解毒の魔法はどのくらい?」
「新しくきた副隊長ですね? そうです。サルビアと申します。恥ずかしながら、解毒の魔法は初級がやっとです」
長い黒髪を一つ、後ろで三つ編みにした女性に話しかける。
サルビアはデイジーと共に、兵士の解毒に当たっていた。
「十分よ。今から私が選んだ兵士だけ解毒しなさい。それと、治癒は他の人に任せて。あなたは解毒だけに専念するのよ。いいわね?」
「はい。分かりました」
「これから私たち三人は解毒作業に専念するわ! 他の衛生兵は、解毒が済んだ兵の治癒に当たりなさい! ただし! 自分が完全に治せる傷だけを選ぶの! いいわね‼」
私の言葉に、やっと自分たちがどうすればいいのか、方針が決まり安堵したように傍観していた衛生兵たちも動きだす。
私はそれを見届けた後、腫れ上がった腕を押さえながら、苦しげな表情をする兵士へ解毒の魔法を唱えた。
「――という訳で、無事に全員の治療を完了しました。死者はゼロです」
運ばれてきた大量の毒に侵された兵士たちの治療を終え、私は司令室に向かい、中でうろうろと歩き回っていたゾイスにそう報告した。
私の報告を聞いたゾイスは、唾を撒き散らしながら私に叫ぶ。
「何が、無事に、だ‼ 無事なんかじゃないよ‼」
「しかし、部隊長の言う、致死率も延べ人数も十分だと認識していますが」
私は平然と述べる。
次に続く言葉は、予想ができた。
「実績を作ってしまったのが問題だ‼ できないことをできないことに文句を言う者はいないが、一度できてしまったことが、次にできなければまずいだろうが‼」
「仰ってる意味が、よく分かりません」
実際のところ、ゾイスが何を考え心配しているかは、理解出来ている。
今回はたまたま私とデイジーが配属された後だったから、解毒が間に合ったのだ。
もし、元々いたサルビアだけでは全員を回復することはできず、対応できなかっただろう。
つまり、もうゾイスは、どんなに私やデイジーが目障りになったとしても、新しい解毒の魔法の使い手が配属されなければ、私たちの治療を拒むことはできない。
「今は幸い解毒をできる者が複数います。今後も積極的に治療に当たれば問題ないかと」
「う……だが! もし君たちに何かあったらどうするつもりだ! 一度受け入れてしまった者を移送するのは出来んのだぞ‼」
正確に言えば、治療不可での別部隊への移送は評価として悪くなるから、できないということだろう。
もっとも、私はそんなことをするつもりは毛頭ない。
かといって、このままずっと三人だけで解毒の治療に専念するつもりもない。
これは布石だった。
「お言葉ですが、実はデイジーはつい最近まで回復魔法を唱えることができませんでした。しかし、今は中級の解毒魔法まで扱うことができます」
「は! そんな馬鹿な話があるわけないだろう! そんな魔法を使えるやつがホイホイ戦場に送られる訳がない。今頃どこかの貴族のお抱えになってるよ」
「信じてもらえないなら、今日一緒に治療に当たったサルビアに聞いてもらっても構いません。彼女は確か初級の解毒魔法しか扱えませんでしたね? それ以上の魔法が必要な兵士が一人も居なかったとでも?」
「ぬ……おい! 誰か‼ 衛生兵のサルビアを呼んでこい! 今すぐにだ‼」
ゾイスが叫ぶと、司令室の外に居た一人の兵士が、慌ててサルビアを呼びに向かった。
その間に、私は話を続ける。
「それで、提案があります。ここの他の衛生兵にも才能がある者がまだいるかもしれません。その者たちに、訓練を行い、解毒魔法を習得させるのはいかがでしょうか?」
「はっ! 何を言い出すかと思えば。誰が教えるっていうんだい。都から使い手を呼んで教鞭でも取ってもらうつもりかい? 一体いくらかかると思っている。そもそもこんな所に来ようと思う物好きなんて居ないさ!」
そんなやり取りをしている間に、呼ばれたサルビアが司令室へと入ってきた。
部隊長のゾイスと副隊長である私が同席している司令室に一人だけ呼び出され、何事かと心配そうな顔をしている。
「ああ。来たようだね。さて。まずは君の嘘をサルビアに証明してもらおうか。サルビア、正直に答えたまえ。これは部隊長命令だ。今日新しく配属されたデイジーとかいう衛生兵が、君より上級な回復魔法を使ったというのは嘘だね?」
「いえ。本当です」
何を聞かれるのかと身構えていたサルビアは、予想外の質問に拍子抜けしたのか、率直にそう答えた。
「うんうん。そうだろう。嘘だっ……なんだって⁉」
「ですから。本当です。デイジーさんと、そこにいらっしゃる副隊長は、私には到底治療できない毒を受けた兵士たちを治療しておりました。間違いありません」
「ば、馬鹿な⁉ もし嘘を言っていたら、ただじゃおかないぞ⁉」
「いえ。私に嘘をつく理由はありせんので」
うろたえるゾイスを一瞥し、私は口を挟む。
これ以上は時間の無駄だ。
「私の話が嘘ではないとこれで証明されたようですね。それで、先ほどの話ですが、衛生兵の訓練を許可いただけるでしょうか?」
「しかし! 誰が教える⁉ 訓練の間、治療の手が足りなくなるだろう!」
「私とデイジーが交代で教えます。治療が疎かにならないよう、そこも私に考えがあります。さあ、どうか許可を」
「ぐぬぬ……もし! 何か問題があれば、君が全ての責任を取りたまえ‼ それが条件だ‼」
私は笑みを作り、一度だけ頷く。
「問題ありません。では、すぐにでも。これで話は終わりですね? 失礼します。サルビアも。あなたには、別の用があるの。一緒に来てくれるかしら?」
「は、はい!」
私はそのまま司令室を出ていく。
サルビアは慌てた様子で、出る際にゾイスに一礼をしてから私の後を追ってくる。
「あ、あの。副隊長。私に用とはなんでしょうか?」
「ええ。今空いている人を集めて、ある物を作ってほしいの。そうね、色は……四つもあれば最初は足りるかしら。必要だったらその時に増やしましょう」
「色、ですか?」
「ええ。さぁ、始めるわよ! 人を集めたら、私の部屋に来てちょうだい。その時、四つの色が異なる布を、できるだけ持ってきて」
私の言葉に、サルビアは戸惑いをにじませた返ことをしてから、他の衛生兵を呼びに行く。
こうして、休憩中や非番だった衛生兵数人が私の部屋に集まった。
「よく来てくれたわね。休んでいるところ申し訳ないけれど、少し手伝って欲しいの」
私の説明で、集まった衛生兵たちは布を細く切り裂いていく。
やがて、色様々な何本もの細い布が出来上がった。
「さぁ。準備はこれで十分よ。ありがとう。これの使い方を説明するから。他のみんなにも説明したいから、治療場に移動しましょう」
運ばれてきた大量の毒に侵された兵士たちの治療を終え、私は司令室に向かい、中でうろうろと歩き回っていたゾイスにそう報告した。
私の報告を聞いたゾイスは、唾を撒き散らしながら私に叫ぶ。
「何が、無事に、だ‼ 無事なんかじゃないよ‼」
「しかし、部隊長の言う、致死率も延べ人数も十分だと認識していますが」
私は平然と述べる。
次に続く言葉は、予想ができた。
「実績を作ってしまったのが問題だ‼ できないことをできないことに文句を言う者はいないが、一度できてしまったことが、次にできなければまずいだろうが‼」
「仰ってる意味が、よく分かりません」
実際のところ、ゾイスが何を考え心配しているかは、理解出来ている。
今回はたまたま私とデイジーが配属された後だったから、解毒が間に合ったのだ。
もし、元々いたサルビアだけでは全員を回復することはできず、対応できなかっただろう。
つまり、もうゾイスは、どんなに私やデイジーが目障りになったとしても、新しい解毒の魔法の使い手が配属されなければ、私たちの治療を拒むことはできない。
「今は幸い解毒をできる者が複数います。今後も積極的に治療に当たれば問題ないかと」
「う……だが! もし君たちに何かあったらどうするつもりだ! 一度受け入れてしまった者を移送するのは出来んのだぞ‼」
正確に言えば、治療不可での別部隊への移送は評価として悪くなるから、できないということだろう。
もっとも、私はそんなことをするつもりは毛頭ない。
かといって、このままずっと三人だけで解毒の治療に専念するつもりもない。
これは布石だった。
「お言葉ですが、実はデイジーはつい最近まで回復魔法を唱えることができませんでした。しかし、今は中級の解毒魔法まで扱うことができます」
「は! そんな馬鹿な話があるわけないだろう! そんな魔法を使えるやつがホイホイ戦場に送られる訳がない。今頃どこかの貴族のお抱えになってるよ」
「信じてもらえないなら、今日一緒に治療に当たったサルビアに聞いてもらっても構いません。彼女は確か初級の解毒魔法しか扱えませんでしたね? それ以上の魔法が必要な兵士が一人も居なかったとでも?」
「ぬ……おい! 誰か‼ 衛生兵のサルビアを呼んでこい! 今すぐにだ‼」
ゾイスが叫ぶと、司令室の外に居た一人の兵士が、慌ててサルビアを呼びに向かった。
その間に、私は話を続ける。
「それで、提案があります。ここの他の衛生兵にも才能がある者がまだいるかもしれません。その者たちに、訓練を行い、解毒魔法を習得させるのはいかがでしょうか?」
「はっ! 何を言い出すかと思えば。誰が教えるっていうんだい。都から使い手を呼んで教鞭でも取ってもらうつもりかい? 一体いくらかかると思っている。そもそもこんな所に来ようと思う物好きなんて居ないさ!」
そんなやり取りをしている間に、呼ばれたサルビアが司令室へと入ってきた。
部隊長のゾイスと副隊長である私が同席している司令室に一人だけ呼び出され、何事かと心配そうな顔をしている。
「ああ。来たようだね。さて。まずは君の嘘をサルビアに証明してもらおうか。サルビア、正直に答えたまえ。これは部隊長命令だ。今日新しく配属されたデイジーとかいう衛生兵が、君より上級な回復魔法を使ったというのは嘘だね?」
「いえ。本当です」
何を聞かれるのかと身構えていたサルビアは、予想外の質問に拍子抜けしたのか、率直にそう答えた。
「うんうん。そうだろう。嘘だっ……なんだって⁉」
「ですから。本当です。デイジーさんと、そこにいらっしゃる副隊長は、私には到底治療できない毒を受けた兵士たちを治療しておりました。間違いありません」
「ば、馬鹿な⁉ もし嘘を言っていたら、ただじゃおかないぞ⁉」
「いえ。私に嘘をつく理由はありせんので」
うろたえるゾイスを一瞥し、私は口を挟む。
これ以上は時間の無駄だ。
「私の話が嘘ではないとこれで証明されたようですね。それで、先ほどの話ですが、衛生兵の訓練を許可いただけるでしょうか?」
「しかし! 誰が教える⁉ 訓練の間、治療の手が足りなくなるだろう!」
「私とデイジーが交代で教えます。治療が疎かにならないよう、そこも私に考えがあります。さあ、どうか許可を」
「ぐぬぬ……もし! 何か問題があれば、君が全ての責任を取りたまえ‼ それが条件だ‼」
私は笑みを作り、一度だけ頷く。
「問題ありません。では、すぐにでも。これで話は終わりですね? 失礼します。サルビアも。あなたには、別の用があるの。一緒に来てくれるかしら?」
「は、はい!」
私はそのまま司令室を出ていく。
サルビアは慌てた様子で、出る際にゾイスに一礼をしてから私の後を追ってくる。
「あ、あの。副隊長。私に用とはなんでしょうか?」
「ええ。今空いている人を集めて、ある物を作ってほしいの。そうね、色は……四つもあれば最初は足りるかしら。必要だったらその時に増やしましょう」
「色、ですか?」
「ええ。さぁ、始めるわよ! 人を集めたら、私の部屋に来てちょうだい。その時、四つの色が異なる布を、できるだけ持ってきて」
私の言葉に、サルビアは戸惑いをにじませた返ことをしてから、他の衛生兵を呼びに行く。
こうして、休憩中や非番だった衛生兵数人が私の部屋に集まった。
「よく来てくれたわね。休んでいるところ申し訳ないけれど、少し手伝って欲しいの」
私の説明で、集まった衛生兵たちは布を細く切り裂いていく。
やがて、色様々な何本もの細い布が出来上がった。
「さぁ。準備はこれで十分よ。ありがとう。これの使い方を説明するから。他のみんなにも説明したいから、治療場に移動しましょう」
「みんな少しだけ手を止めて。聞いてちょうだい」
私はその場にいる全員に聞こえるように声を張る。
指示通り、衛生兵たちは治療を止め、私と四つの色の細く切り裂かれた布を大量に持っている同僚たちに目を向けた。
「なるべく早く済ませるわ。今から私の前に一列に並んで、自分の使うことのできる回復魔法の種類を教えてちょうだい。正直に答えること。いいわね?」
何が始まるのかと、不安げな顔を見せながらも、副隊長の私の命令に従い、一列に並ぶ。
それぞれの申告に応じた色の布を手渡し、私は更に説明を続ける。
「今渡した布を、身体のよく見えるところに巻きつけてちょうだい。分かったと思うけれど、それぞれの色は自分の使える回復魔法の種類、つまり治すことのできる負傷の程度を示しているわ」
今回用意された布の色は、緑、黄、赤、そして紫だ。
緑色は初級の治癒魔法のみ使える者。
黄色は四肢の再生なども可能な者。
赤色はサルビア、紫色はデイジーのみが付けている。
手渡された布を思い思いの場所に付けながら、色の意味は分かったものの、衛生兵たちはまだ釈然としていない顔をしている。
全員に布が行き渡った後、布作りに携わった一人の衛生兵が、私に質問を投げかけてきた。
「副隊長。配り終わりましたが、まだこんなに布が余っています。こんなに作ってどうするんですか?」
「それはね。こうするのよ」
私は、いくつかの布を受け取ると、その場で治療を今かと待ちながら、ことの成り行きを訝しげに見つめる負傷兵たちの元へ向かった。
そして、その傷の程度や、毒の有無によって、布を巻きつけていく。
「さぁ。今つけた色と同じ兵の所へ向かって、治療を再開してちょうだい」
その言葉に多くの者が私の意図を理解できたようで、各々自分が付けた布の色と同じ色を持つ兵の元へと向かい治療を始めた。
それを見ながら、私は残りの兵士にも順に布を巻いていく。
「一体全体。これはなんの意味があるってんだ? あんたが考えたのか? 良かったら教えてくれ」
布を巻きつけ終わる頃、一人の兵士が私に質問してきた。
この兵士の布の色は緑色だ。
「誰が誰に回復魔法をかければいいか。それを分かるための印よ。あなたの色は緑。初級の回復魔法で十分。逆にあっちの彼は赤色。この場で治せる者が少ないから、それができる衛生兵に優先的に見させるの」
「へぇ! そりゃいいや。考えたもんだねぇ。あいつは俺のダチなんだ。どうか、助けてやってくれ。俺は独身だが、あいつにゃ帰りを待つ人が居るんだよ」
私は兵士に微笑みを向けると、次の準備のため、治療場に兵士を受け入れる者たちの元へと足を運ぶ。
そして、今私がしたように、負傷兵の怪我や毒の程度に応じて、受入れの際にそれに応じた色の布を巻くよう指示した。
初めは戸惑っていたものの、しばらく指示を出してどの色を巻くべきか教えていると、私が指示を出さなくても適切な色の布を巻けるようになった。
そして、私は一言だけ付け加える。
「もし、どの色よりも困難な兵士が居たら、布を巻かずにできるだけ速く私の元へ連れてきてちょうだい。いいわね?」
これでひとまずの下地は出来た。
治療の効率は上がり、また、治せる者が治すことが徹底できるだろう。
私は再び治療場に戻ると、治療を続ける衛生兵たちにまた声をかけた。
「今度は手を休めずに聞いてちょうだい。あなたたちに伝えたいことがあるの。今日から、空き時間を使って、回復魔法の訓練を実施するわ。参加は任意。希望する者は、夕方、私の部屋へいらっしゃい」
それだけ言うと、私は赤や紫の布を巻かれた兵士を優先的に治療を始めた。
☆
「副隊長。失礼します」
「入りなさい」
夕方、私の部屋に数人の衛生兵たちが訪れた。
三十人全員が休憩時間な訳ではないが、思っていたより更に少ない。
「よく来たわね。嬉しいわ」
「あ、あの。副隊長。回復魔法の訓練って、本当ですか? あの、私、今より上手になりたい気持ちはあるんですが……あの、お金が無くて……」
その一言に、私は自分のうっかりに気付いた。
人が思ったより少ないのは、恐らく訓練に金が必要だと思ったからだろう。
ここに居る者はほとんどが来る前に自費で回復魔法をなんらかの方法で学んだ者ばかりだ。
無料で教わることができるなどと思いもよらないのだろう。
「説明が不足していたわね。後でみんなにも伝えてくれるかしら。訓練を受けるのに、費用は一切かからないわ」
「ほ、本当ですか⁉ それなら、今すぐにでも習いたいです! 私、初級の魔法しか使えなくて……」
よく見ると、彼女は私が来た時に脚を失った兵士に回復魔法をかけた衛生兵だった。
恐らく本人も、あの行動は本意ではなかったのだろう。
「ええ、もちろんいいわよ。あなたたちもいいのね?」
私の問いに、この部屋に訪れた全員が頷く。
「それじゃあ、早速始めましょう。夕方と、朝方に訓練をするつもりだから出られる方に出て。まずは魔力操作から――」
こうして、この第二衛生兵部隊での回復魔法の訓練が始まった。
初めは数人の参加だったが、緑色だった者が次々に黄色の布に変わるのを見たせいか、徐々に参加者が増えていった。
こうして、いつしか全員が治療の合間を縫って訓練に参加し、布の色を変えていく。
自分や相手の今の状況や、成長が目に見えるからか、第五衛生兵部隊で訓練を実施していたよりも、やる気に満ちているようにも思えた。
私もこの成果に満足しながら、日々の訓練をこなし、また毎日運ばれてくる兵士たちの治療に専念していた。
☆
そんなある日、夜眠れなかったため、外気にあたろうと建物の外に出た時のことだった。
見回りの業務をちょうど終えたクロムと偶然出会した。
クロムは私に気付くと、その人懐っこい顔に笑みを作り、声をかけてくる。
「聖女様! こんな遅くにどうしたんですか?」
「クロム。ご苦労様。少し夜風に当たろうと思ってね。今戻り?」
「ええ。これから戻って寝る所です。陣営の中とはいえ、外は危ないですよ。ましてこんな夜は、魔獣たちの天下ですからね」
「そうね。気を付けないとね。でも、そこら辺を少し歩くだけだから。クロムはおやすみなさい。ゆっくり休んでね」
挨拶をしてその場を去ろうとしたところ、クロムが呼び止めるように声をかけてきた。
私はその声に振り返り、もう一度クロムを見る。
「そんなに長くならないんですよね? それなら、部屋に戻られるまで、俺もお供しますよ」
「あら。悪いわ。本当に大丈夫だから」
「いいえ! 大丈夫なことなんてちっともないですから! ダメって言ってもついて行きますからね。それなら、始めから良いって言ってくれた方がいいと思いませんか?」
「うふふ。分かったわ。それじゃあ、少しの間だけ。よろしく頼むわね」
護衛をお願いした途端、クロムは嬉しそうに握り拳を作ったのが見えた。
私はなんだかその仕草が妙に可笑しくて、声を出して笑ってしまった。
私はその場にいる全員に聞こえるように声を張る。
指示通り、衛生兵たちは治療を止め、私と四つの色の細く切り裂かれた布を大量に持っている同僚たちに目を向けた。
「なるべく早く済ませるわ。今から私の前に一列に並んで、自分の使うことのできる回復魔法の種類を教えてちょうだい。正直に答えること。いいわね?」
何が始まるのかと、不安げな顔を見せながらも、副隊長の私の命令に従い、一列に並ぶ。
それぞれの申告に応じた色の布を手渡し、私は更に説明を続ける。
「今渡した布を、身体のよく見えるところに巻きつけてちょうだい。分かったと思うけれど、それぞれの色は自分の使える回復魔法の種類、つまり治すことのできる負傷の程度を示しているわ」
今回用意された布の色は、緑、黄、赤、そして紫だ。
緑色は初級の治癒魔法のみ使える者。
黄色は四肢の再生なども可能な者。
赤色はサルビア、紫色はデイジーのみが付けている。
手渡された布を思い思いの場所に付けながら、色の意味は分かったものの、衛生兵たちはまだ釈然としていない顔をしている。
全員に布が行き渡った後、布作りに携わった一人の衛生兵が、私に質問を投げかけてきた。
「副隊長。配り終わりましたが、まだこんなに布が余っています。こんなに作ってどうするんですか?」
「それはね。こうするのよ」
私は、いくつかの布を受け取ると、その場で治療を今かと待ちながら、ことの成り行きを訝しげに見つめる負傷兵たちの元へ向かった。
そして、その傷の程度や、毒の有無によって、布を巻きつけていく。
「さぁ。今つけた色と同じ兵の所へ向かって、治療を再開してちょうだい」
その言葉に多くの者が私の意図を理解できたようで、各々自分が付けた布の色と同じ色を持つ兵の元へと向かい治療を始めた。
それを見ながら、私は残りの兵士にも順に布を巻いていく。
「一体全体。これはなんの意味があるってんだ? あんたが考えたのか? 良かったら教えてくれ」
布を巻きつけ終わる頃、一人の兵士が私に質問してきた。
この兵士の布の色は緑色だ。
「誰が誰に回復魔法をかければいいか。それを分かるための印よ。あなたの色は緑。初級の回復魔法で十分。逆にあっちの彼は赤色。この場で治せる者が少ないから、それができる衛生兵に優先的に見させるの」
「へぇ! そりゃいいや。考えたもんだねぇ。あいつは俺のダチなんだ。どうか、助けてやってくれ。俺は独身だが、あいつにゃ帰りを待つ人が居るんだよ」
私は兵士に微笑みを向けると、次の準備のため、治療場に兵士を受け入れる者たちの元へと足を運ぶ。
そして、今私がしたように、負傷兵の怪我や毒の程度に応じて、受入れの際にそれに応じた色の布を巻くよう指示した。
初めは戸惑っていたものの、しばらく指示を出してどの色を巻くべきか教えていると、私が指示を出さなくても適切な色の布を巻けるようになった。
そして、私は一言だけ付け加える。
「もし、どの色よりも困難な兵士が居たら、布を巻かずにできるだけ速く私の元へ連れてきてちょうだい。いいわね?」
これでひとまずの下地は出来た。
治療の効率は上がり、また、治せる者が治すことが徹底できるだろう。
私は再び治療場に戻ると、治療を続ける衛生兵たちにまた声をかけた。
「今度は手を休めずに聞いてちょうだい。あなたたちに伝えたいことがあるの。今日から、空き時間を使って、回復魔法の訓練を実施するわ。参加は任意。希望する者は、夕方、私の部屋へいらっしゃい」
それだけ言うと、私は赤や紫の布を巻かれた兵士を優先的に治療を始めた。
☆
「副隊長。失礼します」
「入りなさい」
夕方、私の部屋に数人の衛生兵たちが訪れた。
三十人全員が休憩時間な訳ではないが、思っていたより更に少ない。
「よく来たわね。嬉しいわ」
「あ、あの。副隊長。回復魔法の訓練って、本当ですか? あの、私、今より上手になりたい気持ちはあるんですが……あの、お金が無くて……」
その一言に、私は自分のうっかりに気付いた。
人が思ったより少ないのは、恐らく訓練に金が必要だと思ったからだろう。
ここに居る者はほとんどが来る前に自費で回復魔法をなんらかの方法で学んだ者ばかりだ。
無料で教わることができるなどと思いもよらないのだろう。
「説明が不足していたわね。後でみんなにも伝えてくれるかしら。訓練を受けるのに、費用は一切かからないわ」
「ほ、本当ですか⁉ それなら、今すぐにでも習いたいです! 私、初級の魔法しか使えなくて……」
よく見ると、彼女は私が来た時に脚を失った兵士に回復魔法をかけた衛生兵だった。
恐らく本人も、あの行動は本意ではなかったのだろう。
「ええ、もちろんいいわよ。あなたたちもいいのね?」
私の問いに、この部屋に訪れた全員が頷く。
「それじゃあ、早速始めましょう。夕方と、朝方に訓練をするつもりだから出られる方に出て。まずは魔力操作から――」
こうして、この第二衛生兵部隊での回復魔法の訓練が始まった。
初めは数人の参加だったが、緑色だった者が次々に黄色の布に変わるのを見たせいか、徐々に参加者が増えていった。
こうして、いつしか全員が治療の合間を縫って訓練に参加し、布の色を変えていく。
自分や相手の今の状況や、成長が目に見えるからか、第五衛生兵部隊で訓練を実施していたよりも、やる気に満ちているようにも思えた。
私もこの成果に満足しながら、日々の訓練をこなし、また毎日運ばれてくる兵士たちの治療に専念していた。
☆
そんなある日、夜眠れなかったため、外気にあたろうと建物の外に出た時のことだった。
見回りの業務をちょうど終えたクロムと偶然出会した。
クロムは私に気付くと、その人懐っこい顔に笑みを作り、声をかけてくる。
「聖女様! こんな遅くにどうしたんですか?」
「クロム。ご苦労様。少し夜風に当たろうと思ってね。今戻り?」
「ええ。これから戻って寝る所です。陣営の中とはいえ、外は危ないですよ。ましてこんな夜は、魔獣たちの天下ですからね」
「そうね。気を付けないとね。でも、そこら辺を少し歩くだけだから。クロムはおやすみなさい。ゆっくり休んでね」
挨拶をしてその場を去ろうとしたところ、クロムが呼び止めるように声をかけてきた。
私はその声に振り返り、もう一度クロムを見る。
「そんなに長くならないんですよね? それなら、部屋に戻られるまで、俺もお供しますよ」
「あら。悪いわ。本当に大丈夫だから」
「いいえ! 大丈夫なことなんてちっともないですから! ダメって言ってもついて行きますからね。それなら、始めから良いって言ってくれた方がいいと思いませんか?」
「うふふ。分かったわ。それじゃあ、少しの間だけ。よろしく頼むわね」
護衛をお願いした途端、クロムは嬉しそうに握り拳を作ったのが見えた。
私はなんだかその仕草が妙に可笑しくて、声を出して笑ってしまった。
「月が綺麗ですねー」
クロムと並び、陣営の中を当てもなく歩いていると、突然空を見上げたクロムがそう言い出した。
釣られて私も目線を上げると、確かに雲ひとつない夜空に、月が煌々と浮かんでいた。
「そうね。ねぇ。クロムは出身はどの辺りなの?」
無言で歩き続けるのもなんだと、思い付いた話題を口に出してみる。
私からの質問に、聞かれた本人は驚いたのか、目を見開いた。
「お、俺ですか。えっと、知っているかどうかわかりませんが、ロメル村っていう小さな村です。ここから北の方にあるマッカーブ山脈の麓にあるんです」
「あら。随分と寒い地域に住んでいたのね」
マッカーブ山脈というのは、この国の最北に連なる山脈で、一年中冠雪している山も多いと聞く。
今は辺りが暗く分かりにくいが、確かに北出身に多い、色白で透き通るような肌と、淡い青緑の瞳をしていたことが記憶から呼び起こされた。
「寒いですよ。冬は村から出ることもできないほどです。そんな暮らしが嫌で、村を飛び出したんですよ。俺」
「まぁ! それは大変だったわね。じゃあ、ここへは志願で?」
「はは。実はそうなんです。本当は街で暮らすつもりだったんですが、上手くいかなくて」
クロムはバツが悪そうに頬をかく。
そこで私は、こんな風に誰かの身の上を聞くのは初めての経験だと気付いた。
私は改めてクロムを見つめる。
それに気付いたのか、クロムは長いまつ毛が生え揃った大きな瞳を瞬かせた。
「あ、あの! 聖女様は、慕っている男性とかはいらっしゃらないんですか⁉」
一瞬の間を置いて、クロムは少し身体を強ばらせながら、上擦った声でそんなことを聞いてきた。
思わぬ質問に、私は少し考え込んでしまう。
慕っている男性というのは、どういう意味の質問だろうか。
会ったことはないが、攻撃や回復魔法の基礎となる魔力に関する著書を書いたオルマン伯爵には、尊敬の念を抱いてる。
しかし、今までの話の流れで、そんなことを聞くような話はあっただろうか。
適切な答えが分からず黙っていると、クロムは痺れを切らしたように、先ほどの自分の言葉を否定し始めた。
「ああ! 今の話は忘れてください! なんでもないんです。俺、何を聞いてるんだろ!」
「あら。そう? ごめんなさいね。いい答えが思い付かなくて――」
そういい切ろうとした瞬間、陣営の見張り台から、敵襲を知らせる合図が鳴り響いた。
私は驚き動きを止めるが、クロムはそんな私を自分の方に引き寄せ、辺りに警戒を向ける。
「聖女様! どうやら敵襲です! 早く建物の中へお戻りください‼」
「え、ええ! クロム、あなたは⁉」
「私は衛兵。この時のために私は居るのです。入口まで送りましょう。さぁ、早く‼」
クロムに手を引かれる形で、私は建物の入口へと走る。
もうすぐ入口へと辿り着くといったところで、目の前に何かが降りてきた。
私は思わず声を上げる。
目に入ったのは、黒い羽を持つ魔獣だった。
「くそっ! ガーゴイルか‼ こいつ、空を飛んで陣営の壁を越えやがった‼」
「クロム! 無理はしないで‼ 増援をっ‼」
しかし、辺りを見渡しても近くに他の兵士の姿はなく、どうにか二人だけで切り抜けなくてはいけなさそうだ。
ガーゴイルと呼ばれる、身体が石のような見た目をした魔獣は、牙が生え揃った裂けた口で威嚇の鳴き声を上げる。
次の瞬間、鋭い爪が生えた腕を突き出し、私を庇うように前に立ったクロムに向かって、身体ごと突進してきた。
しかし、クロムは動じることなく、両手で構えた剣を器用に振るって、ガーゴイルの腕を、そして羽の付け根を切り落とした。
思わぬ反撃をくらいうろたえた様子のガーゴイルを、クロムは縦一文字に切り伏せる。
初めて目の当たりにするクロムの実力に、私は目を白黒させてしまった。
「ふぅ……もう大丈夫です。さぁ、今のうちに中へ‼ 俺は、戻ります。あっちの塀の外に沢山群がって来ているようですから」
「ありがとう、クロム。助かったわ。本当に。でも無理はしないでね。死んでしまってはいくら私でも助けられないわ」
私の言葉にクロムは目を細め、そして軍式の礼をする。
「承知しました‼ 副隊長の命令、必ずや守ってみせます‼」
「ええ。そうしてちょうだい。命令違反は、しないでね」
クロムは一度頷くと、大量の魔獣が押し寄せているであろう、戦闘音が響く方へと走り出した。
私はそれを見送ると、建物の中へと入り、寝ている衛生兵を起こしながら治療場へと向かう。
「聖女様、一体何事ですか?」
今まで寝ていたのか、目を擦りながらデイジーが聞いてくる。
「敵襲よ! 前のようにここが襲われているわ。負傷兵が大量に運ばれる可能性が高いわ。心してちょうだい‼」
「わ、分かりましたぁ‼」
状況が飲み込めたのか、デイジーは一気に目が覚めたようで、治療場へと向かう足を速めた。
私は受入係に布をできるだけ速く、かつ正確に負傷兵に付ける様に指示を出した後、気を引き締め運ばれてくるであろう負傷兵を待ち構えた。
クロムと並び、陣営の中を当てもなく歩いていると、突然空を見上げたクロムがそう言い出した。
釣られて私も目線を上げると、確かに雲ひとつない夜空に、月が煌々と浮かんでいた。
「そうね。ねぇ。クロムは出身はどの辺りなの?」
無言で歩き続けるのもなんだと、思い付いた話題を口に出してみる。
私からの質問に、聞かれた本人は驚いたのか、目を見開いた。
「お、俺ですか。えっと、知っているかどうかわかりませんが、ロメル村っていう小さな村です。ここから北の方にあるマッカーブ山脈の麓にあるんです」
「あら。随分と寒い地域に住んでいたのね」
マッカーブ山脈というのは、この国の最北に連なる山脈で、一年中冠雪している山も多いと聞く。
今は辺りが暗く分かりにくいが、確かに北出身に多い、色白で透き通るような肌と、淡い青緑の瞳をしていたことが記憶から呼び起こされた。
「寒いですよ。冬は村から出ることもできないほどです。そんな暮らしが嫌で、村を飛び出したんですよ。俺」
「まぁ! それは大変だったわね。じゃあ、ここへは志願で?」
「はは。実はそうなんです。本当は街で暮らすつもりだったんですが、上手くいかなくて」
クロムはバツが悪そうに頬をかく。
そこで私は、こんな風に誰かの身の上を聞くのは初めての経験だと気付いた。
私は改めてクロムを見つめる。
それに気付いたのか、クロムは長いまつ毛が生え揃った大きな瞳を瞬かせた。
「あ、あの! 聖女様は、慕っている男性とかはいらっしゃらないんですか⁉」
一瞬の間を置いて、クロムは少し身体を強ばらせながら、上擦った声でそんなことを聞いてきた。
思わぬ質問に、私は少し考え込んでしまう。
慕っている男性というのは、どういう意味の質問だろうか。
会ったことはないが、攻撃や回復魔法の基礎となる魔力に関する著書を書いたオルマン伯爵には、尊敬の念を抱いてる。
しかし、今までの話の流れで、そんなことを聞くような話はあっただろうか。
適切な答えが分からず黙っていると、クロムは痺れを切らしたように、先ほどの自分の言葉を否定し始めた。
「ああ! 今の話は忘れてください! なんでもないんです。俺、何を聞いてるんだろ!」
「あら。そう? ごめんなさいね。いい答えが思い付かなくて――」
そういい切ろうとした瞬間、陣営の見張り台から、敵襲を知らせる合図が鳴り響いた。
私は驚き動きを止めるが、クロムはそんな私を自分の方に引き寄せ、辺りに警戒を向ける。
「聖女様! どうやら敵襲です! 早く建物の中へお戻りください‼」
「え、ええ! クロム、あなたは⁉」
「私は衛兵。この時のために私は居るのです。入口まで送りましょう。さぁ、早く‼」
クロムに手を引かれる形で、私は建物の入口へと走る。
もうすぐ入口へと辿り着くといったところで、目の前に何かが降りてきた。
私は思わず声を上げる。
目に入ったのは、黒い羽を持つ魔獣だった。
「くそっ! ガーゴイルか‼ こいつ、空を飛んで陣営の壁を越えやがった‼」
「クロム! 無理はしないで‼ 増援をっ‼」
しかし、辺りを見渡しても近くに他の兵士の姿はなく、どうにか二人だけで切り抜けなくてはいけなさそうだ。
ガーゴイルと呼ばれる、身体が石のような見た目をした魔獣は、牙が生え揃った裂けた口で威嚇の鳴き声を上げる。
次の瞬間、鋭い爪が生えた腕を突き出し、私を庇うように前に立ったクロムに向かって、身体ごと突進してきた。
しかし、クロムは動じることなく、両手で構えた剣を器用に振るって、ガーゴイルの腕を、そして羽の付け根を切り落とした。
思わぬ反撃をくらいうろたえた様子のガーゴイルを、クロムは縦一文字に切り伏せる。
初めて目の当たりにするクロムの実力に、私は目を白黒させてしまった。
「ふぅ……もう大丈夫です。さぁ、今のうちに中へ‼ 俺は、戻ります。あっちの塀の外に沢山群がって来ているようですから」
「ありがとう、クロム。助かったわ。本当に。でも無理はしないでね。死んでしまってはいくら私でも助けられないわ」
私の言葉にクロムは目を細め、そして軍式の礼をする。
「承知しました‼ 副隊長の命令、必ずや守ってみせます‼」
「ええ。そうしてちょうだい。命令違反は、しないでね」
クロムは一度頷くと、大量の魔獣が押し寄せているであろう、戦闘音が響く方へと走り出した。
私はそれを見送ると、建物の中へと入り、寝ている衛生兵を起こしながら治療場へと向かう。
「聖女様、一体何事ですか?」
今まで寝ていたのか、目を擦りながらデイジーが聞いてくる。
「敵襲よ! 前のようにここが襲われているわ。負傷兵が大量に運ばれる可能性が高いわ。心してちょうだい‼」
「わ、分かりましたぁ‼」
状況が飲み込めたのか、デイジーは一気に目が覚めたようで、治療場へと向かう足を速めた。
私は受入係に布をできるだけ速く、かつ正確に負傷兵に付ける様に指示を出した後、気を引き締め運ばれてくるであろう負傷兵を待ち構えた。
この作家の他の作品
表紙を見る
気付くと私は、発売から十年経った今も思い出してはプレイを続ける乙女ゲーム「イストワール〜星恋の七王子」のキャラクターに転生してしまった。
しかもそれはゲーム内でヒロインを執拗に陥れようと画策する悪役令嬢、ミザリー・マリア・ド・ゴール。
本来の主人公であるヒロインがどのルートを通ってもその前に立ちはだかり、最終的には己の行いが招いた破滅の結末を迎える。
私はそんな結末を回避しようと、三年間の学園生活を奔走する。
「王子を味方につける方法を考えなきゃ!」
表紙を見る
精霊に愛された少女は聖女として崇められる。私の住む国で古くからある習わしだ。
驚いたことに私も聖女だと、村の皆の期待を背に王都マーベラに迎えられた。
それなのに……。
「この者が聖女なはずはない! 穢らわしい!」
私よりも何年も前から聖女として称えられているローザ様の一言で、私は国を追放されることになってしまった。
「もし良かったら同行してくれないか?」
隣国に向かう途中で命を救ったやり手の商人アベルに色々と助けてもらうことに。
その隣国では精霊の力を利用する技術を使う者は【錬金術師】と呼ばれていて……。
第五元素エーテルの精霊に愛された私は、生まれた国を追放されたけれど、隣国で天才錬金術師として暮らしていくようです!!
この物語は、国を追放された聖女と、助けたやり手商人との恋愛話です。
追放ものなので、最初の方で3話毎にざまぁ描写があります。
薬の効果を示すためにたまに人が怪我をしますがグロ描写はありません。
作者が化学好きなので、少し趣味が出ますがファンタジー風味を壊すことは無いように気を使っています。
ベリーズファンタジー様から発売されました!!
書籍版は大ボリューム加筆修正しておりますので、ぜひぜひお手にお取りください!!
表紙を見る
勇者パーティの支援職だった私は、自己を超々強化する秘法と言われた魔法を使い、幼女になってしまった。
そんな私の姿を見て、パーティメンバーが決めたのは……
「アリシアちゃん。いい子だからお留守番しててね」
見た目は幼女でも、最強の肉体を手に入れた私は、付いてくるなと言われた手前、こっそりひっそりと陰から元仲間を支援することに決めた。
戦神の愛用していたという神器破城槌を振り回し、神の乗り物だと言うもふもふ神獣と旅を続ける珍道中!
主人公は元は立派な大人ですが、心も体も知能も子供です
基本的にコメディ色が強いです
毎日朝7時に一話分更新します
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…