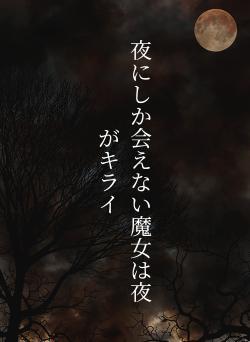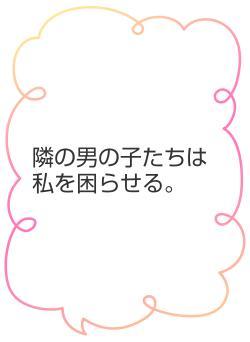そよそよと風が吹く公園のベンチ、日差しが照り付けるだだっ広い草や木が生い茂るその中でそこだけは木陰になっていて涼しくて気持ちいい。
目を閉じて横になり、ベンチの上で寝ていた。
「…悠」
「……。」
隣にあったもうひとつのベンチに座った。
じーっと上から覗き込むようにして、眠る悠の顔を見ていた。
「何?」
「起きてたんだ!?」
「起きてるだろ、さっきお前電話して来たんだから」
勢い余って電話しちゃったら一応は出てくれて、どこにいるかを聞けば答えてくれて今ここにいる。
一度は開いた瞳を再び閉じて、体ごと横を向いた。
「何か用?」
「用っていうか…、悠は何してるのかなって思って」
「別に見ての通り何もしてないけど」
「……。」
淡々とした声で話す悠は今日別れた時と同じだった。
感情の読み取りにくい悠は今どう思ってるのかあたしにはよくわからなくて、今日だって楽しみだったかどうかは本当のところはわからなかったから。
「…さっき真菜さんに会った」
「へぇ」
だからね、この話をした時悠の気持ちも、わかってあげられなかった。
「………。」
悠を傷付けない言葉を探した。
何を言ってもダメに思えて、でもあたしが言いたかったのはそんなことじゃないんだけど。
「あんなんいつものことだから」
「え?」
話し出したのは悠の方だった。
「彼氏と別れると誘いに来るんだよ、それで新しい彼氏が出来るとそっち行って…その繰り返し。いつものことだから」
ズキンって胸が重くなった。
鉛が降って来たみたい。
「昨日彼氏出来たんだってさ、じゃあその時言えよって話だよ」
横を向いたまま頭の下に右手を入れて枕代わりにし、ずっと目は閉じたままだった。
キラキラの髪が顔にかかる、時折風が吹けばふわっと揺れる。
なんで、どうして、声が震える。
「…そんなの、ひどいよ…っ」
きゅっとTシャツの裾を握った。
どこにぶつけたらいいかわからない気持ちをぎゅーっと握った手に込めて、俯いたまま鼻をすすった。
「いいんだよ、俺もそれわかって利用してるだけだし」
「でも…っ」
どうしてあたしの方が泣いてるのかな。
「あいつ金持ちなんだよ、実家大富豪だから」
「そんなのおかしいよ…!」
でも悲しかったから。
勝手な真菜さんもそんな風に言う悠も、悲しくて涙がこぼれた。
ひどいとかおかしいとか、そんな言葉しか出て来ない自分にも。
「いい暇つぶしにはなるし」
あたしが言いたかったのはそんなことじゃなかったでしょ。
あたしがここへ来たのは真菜さんを悪く言うためじゃない。
もっと言いたいことがあったから。
「悠!」
「ん」
「あたしと遊ぼ!今日はあたしと一緒にいて!」
目を閉じて横になり、ベンチの上で寝ていた。
「…悠」
「……。」
隣にあったもうひとつのベンチに座った。
じーっと上から覗き込むようにして、眠る悠の顔を見ていた。
「何?」
「起きてたんだ!?」
「起きてるだろ、さっきお前電話して来たんだから」
勢い余って電話しちゃったら一応は出てくれて、どこにいるかを聞けば答えてくれて今ここにいる。
一度は開いた瞳を再び閉じて、体ごと横を向いた。
「何か用?」
「用っていうか…、悠は何してるのかなって思って」
「別に見ての通り何もしてないけど」
「……。」
淡々とした声で話す悠は今日別れた時と同じだった。
感情の読み取りにくい悠は今どう思ってるのかあたしにはよくわからなくて、今日だって楽しみだったかどうかは本当のところはわからなかったから。
「…さっき真菜さんに会った」
「へぇ」
だからね、この話をした時悠の気持ちも、わかってあげられなかった。
「………。」
悠を傷付けない言葉を探した。
何を言ってもダメに思えて、でもあたしが言いたかったのはそんなことじゃないんだけど。
「あんなんいつものことだから」
「え?」
話し出したのは悠の方だった。
「彼氏と別れると誘いに来るんだよ、それで新しい彼氏が出来るとそっち行って…その繰り返し。いつものことだから」
ズキンって胸が重くなった。
鉛が降って来たみたい。
「昨日彼氏出来たんだってさ、じゃあその時言えよって話だよ」
横を向いたまま頭の下に右手を入れて枕代わりにし、ずっと目は閉じたままだった。
キラキラの髪が顔にかかる、時折風が吹けばふわっと揺れる。
なんで、どうして、声が震える。
「…そんなの、ひどいよ…っ」
きゅっとTシャツの裾を握った。
どこにぶつけたらいいかわからない気持ちをぎゅーっと握った手に込めて、俯いたまま鼻をすすった。
「いいんだよ、俺もそれわかって利用してるだけだし」
「でも…っ」
どうしてあたしの方が泣いてるのかな。
「あいつ金持ちなんだよ、実家大富豪だから」
「そんなのおかしいよ…!」
でも悲しかったから。
勝手な真菜さんもそんな風に言う悠も、悲しくて涙がこぼれた。
ひどいとかおかしいとか、そんな言葉しか出て来ない自分にも。
「いい暇つぶしにはなるし」
あたしが言いたかったのはそんなことじゃなかったでしょ。
あたしがここへ来たのは真菜さんを悪く言うためじゃない。
もっと言いたいことがあったから。
「悠!」
「ん」
「あたしと遊ぼ!今日はあたしと一緒にいて!」