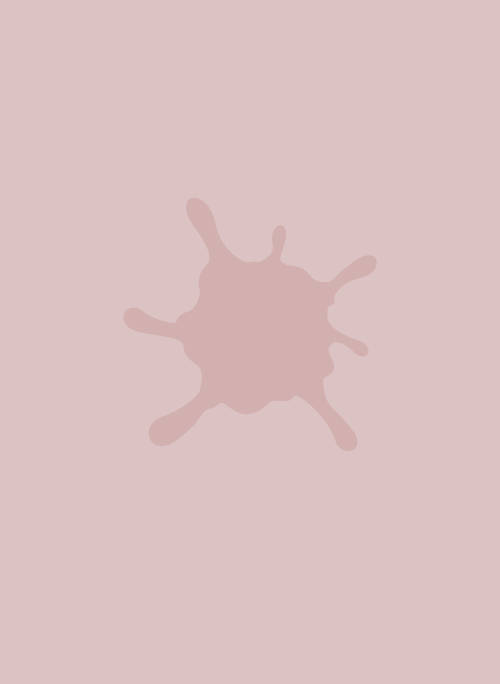「ごめんね!はい、これは大丈夫だから。はい、これチョコ」
シルナが、急いでケーキの代わりに詫びチョコを出す。
が、
「…何だかこれ、一口齧られてるんですが…」
「えぇぇ!?」
クュルナが摘んだチョコは、何故か端っこがちょこっと欠けていた。
ネズミに齧られたみたいに。
更に、エリュティアは。
「もごっ…!?げほっ、げほっ!」
また噎せてる。
「大丈夫かエリュティア。しっかりしろ、何があった?」
「からっ…。辛い、これ…辛いっ…ごほっ」
辛い?チョコレートが?
よく確かめてみると、エリュティアの齧ったチョコレートの中には。
いつぞや、元暗殺者組が仕込んでいた、例のデスソースが。
まさかそんな。いつの間に、誰がこんな陰湿な悪戯を?
やっぱり、これは…。
よもやと思って、小人共を見ると。
奴らは、にやにやしながらこちらを見ていた。
よく見たら、それぞれの小瓶の底に、それぞれ赤い液体と、青い液体が溜まり始めていた。
あれが…奴らの感情ゲージなのか。
「お前らの仕業なのか?これ…」
「うん」
「そうだよ」
この野郎、悪びれもせず。
つまりこれは、全部この小人共の仕業で。
意図的に、クュルナとエリュティアに不運が起きるよう、操作しているのか。
クュルナは怒りを、エリュティアは悲しみを感じるように。
「この調子で、七日間じっくりかけて、僕は怒りを…」
「僕は悲しみを、君達に教えてもらうからね」
…最低だ。
そして陰湿だ。
もう、既にこの時点で怒りも悲しみも感じてるよ。
「大丈夫。瓶がいっぱいになったら、ちゃんと解放してあげるからさ」
「そうそう。君達は、ただ感じてくれるだけで良い。楽なものでしょ?」
この小人、もう何回もぶん殴ってやりたいと思ったことだが。
やっぱりぶん殴ってやりたい。
何が楽なもんだ。ふざけるのもいい加減にしろ。
「この調子で、あと七日間…頑張ってね〜」
小人共に、へらへらと笑われ。
俺はこいつらをぶん殴りたい衝動を、必死に堪えるのだった。
シルナが、急いでケーキの代わりに詫びチョコを出す。
が、
「…何だかこれ、一口齧られてるんですが…」
「えぇぇ!?」
クュルナが摘んだチョコは、何故か端っこがちょこっと欠けていた。
ネズミに齧られたみたいに。
更に、エリュティアは。
「もごっ…!?げほっ、げほっ!」
また噎せてる。
「大丈夫かエリュティア。しっかりしろ、何があった?」
「からっ…。辛い、これ…辛いっ…ごほっ」
辛い?チョコレートが?
よく確かめてみると、エリュティアの齧ったチョコレートの中には。
いつぞや、元暗殺者組が仕込んでいた、例のデスソースが。
まさかそんな。いつの間に、誰がこんな陰湿な悪戯を?
やっぱり、これは…。
よもやと思って、小人共を見ると。
奴らは、にやにやしながらこちらを見ていた。
よく見たら、それぞれの小瓶の底に、それぞれ赤い液体と、青い液体が溜まり始めていた。
あれが…奴らの感情ゲージなのか。
「お前らの仕業なのか?これ…」
「うん」
「そうだよ」
この野郎、悪びれもせず。
つまりこれは、全部この小人共の仕業で。
意図的に、クュルナとエリュティアに不運が起きるよう、操作しているのか。
クュルナは怒りを、エリュティアは悲しみを感じるように。
「この調子で、七日間じっくりかけて、僕は怒りを…」
「僕は悲しみを、君達に教えてもらうからね」
…最低だ。
そして陰湿だ。
もう、既にこの時点で怒りも悲しみも感じてるよ。
「大丈夫。瓶がいっぱいになったら、ちゃんと解放してあげるからさ」
「そうそう。君達は、ただ感じてくれるだけで良い。楽なものでしょ?」
この小人、もう何回もぶん殴ってやりたいと思ったことだが。
やっぱりぶん殴ってやりたい。
何が楽なもんだ。ふざけるのもいい加減にしろ。
「この調子で、あと七日間…頑張ってね〜」
小人共に、へらへらと笑われ。
俺はこいつらをぶん殴りたい衝動を、必死に堪えるのだった。
――――――それから、クュルナとエリュティアに不幸が始まった。
…と、思ったのだが。
「…羽久、頭にガムついてる」
「…あぁ、知ってる」
さっき外の通路を歩いていたら、何処かから頭に、ベチャッ、と飛んできたんだよ。
もう、いちいちリアクションするのも面倒だから、知らない振りをしてたんだよ。
クュルナに、不幸が見舞われると思っていたら。
何故か、俺に不幸が降り掛かるようになった。
…と、思ったのだが。
「…羽久、頭にガムついてる」
「…あぁ、知ってる」
さっき外の通路を歩いていたら、何処かから頭に、ベチャッ、と飛んできたんだよ。
もう、いちいちリアクションするのも面倒だから、知らない振りをしてたんだよ。
クュルナに、不幸が見舞われると思っていたら。
何故か、俺に不幸が降り掛かるようになった。
怒り、悲しみの小人と、クュルナとエリュティアがそれぞれ契約してから、今日で三日目。
俺は、数々の不幸に見舞われるようになっていた。
「髪に絡まってるよ、ガム」
「陰湿ないじめだねー」
「…別にいじめではないけど…」
頭の後ろに手を回してみると、ガムのベタベタが髪に貼り付いていた。
気持ち悪っ…。
無視していようと思ったけど、さすがに無視出来ない。
「あぁ…。あぁぁ〜…羽久…大丈夫?」
シルナが、あわあわしながら聞いてきた。
「大丈夫ではないだろ…」
一昨日、昨日と、こんなことばかりだ。
いや、日に日に酷くなっている。
「羽久、足元汚れてるよ」
令月が、俺の足元を眺めながら呟いた。
そうだよ。知ってる。
「さっき歩いてたら、突き飛ばされて水溜りに足突っ込んだんだよ」
「背中も汚れてるよ」
「さっき外で、泥団子が飛んできた」
もう、いっそコントなんじゃないかと思うよな。
不運とか、そういう次元を越えてるよ。
「可哀想だねー。ガム、俺の糸で取ってあげるよ」
「おぉ…ありがとう」
すぐりが得意の糸魔法を使って、俺の髪の毛にへばりついたガムを、こそげ取ってくれた。
ありがとう。
これで、少しはベタベタが何とかなるだろう。
「元気出して、羽久…!ほら、これ。私の秘蔵のチョコあげるから」
シルナが、お宝のチョコレートをくれた。
「あぁ、ありがとう…」
有り難くチョコレートを受け取って、口に放り込む。
が。
「…!?」
甘いはずのチョコレートは、何故か一口噛むなり、信じられない苦味を感じた。
漢方薬みたいな味がする。何だこれ?
「げほっ…がはっ…」
「え、だ、大丈夫!?」
「にっが…!何だこれ…!?」
一体、何が仕込まれてるんだ?
更に、俺の不幸はこれだけに留まらない。
俺は、数々の不幸に見舞われるようになっていた。
「髪に絡まってるよ、ガム」
「陰湿ないじめだねー」
「…別にいじめではないけど…」
頭の後ろに手を回してみると、ガムのベタベタが髪に貼り付いていた。
気持ち悪っ…。
無視していようと思ったけど、さすがに無視出来ない。
「あぁ…。あぁぁ〜…羽久…大丈夫?」
シルナが、あわあわしながら聞いてきた。
「大丈夫ではないだろ…」
一昨日、昨日と、こんなことばかりだ。
いや、日に日に酷くなっている。
「羽久、足元汚れてるよ」
令月が、俺の足元を眺めながら呟いた。
そうだよ。知ってる。
「さっき歩いてたら、突き飛ばされて水溜りに足突っ込んだんだよ」
「背中も汚れてるよ」
「さっき外で、泥団子が飛んできた」
もう、いっそコントなんじゃないかと思うよな。
不運とか、そういう次元を越えてるよ。
「可哀想だねー。ガム、俺の糸で取ってあげるよ」
「おぉ…ありがとう」
すぐりが得意の糸魔法を使って、俺の髪の毛にへばりついたガムを、こそげ取ってくれた。
ありがとう。
これで、少しはベタベタが何とかなるだろう。
「元気出して、羽久…!ほら、これ。私の秘蔵のチョコあげるから」
シルナが、お宝のチョコレートをくれた。
「あぁ、ありがとう…」
有り難くチョコレートを受け取って、口に放り込む。
が。
「…!?」
甘いはずのチョコレートは、何故か一口噛むなり、信じられない苦味を感じた。
漢方薬みたいな味がする。何だこれ?
「げほっ…がはっ…」
「え、だ、大丈夫!?」
「にっが…!何だこれ…!?」
一体、何が仕込まれてるんだ?
更に、俺の不幸はこれだけに留まらない。
「だ、大丈夫羽久!?ほらっ…せめてこれ、ホットチョコレート飲んで。美味しいから」
シルナが、ホットチョコレートの入ったマグカップを渡してくれた。
「あぁ、ありが…」
マグカップを受け取った、その瞬間。
何もしてないのに、マグカップの持ち手が、バキッと音を立てて壊れ。
そのまま、マグカップが俺の膝の上に落下。
同時に、カップに入っていた熱々のホットチョコレートが膝を汚した。
「あっつ!!」
「あわあわあわ。羽久大丈夫!?」
もう、何をしても全く上手く行かない。
どころか、何をしても、不幸しか生まない。
慌てて、シルナと天音が、ホットチョコレートで火傷した膝に、回復魔法をかけてくれた。
申し訳なくて泣きたい。
すると、天音があることに気づいた。
「…!…羽久さん、その頭の瘤…どうしたの?」
おぉ…天音。よく気づいてくれたな。
「あぁ、これな…。今朝、授業の為に教室に行こうとしたら…階段から…椅子が落ちてきて…」
「階段から…椅子…!?」
信じられない事態だと思うだろう?
俺も信じられなかったよ。
でも、実際転げ落ちてきた椅子が、脳天を直撃したら…信じない訳にはいかないだろう?
めちゃくちゃ痛かった。
「そ、そんな不幸なことが…何で羽久さんに…」
「あぁ…うん。それなぁ…」
俺も、この三日間、ずっと考えてるんだけど…。
「とはいえ、エリュティアさんも負けてないですよ」
俺が不幸に見舞われるのを見ながら、ナジュがそう言った。
あぁ、そうだな。
悲しみの青い小人と、契約してからというもの。
不幸の度合いで言うなら、エリュティアも俺と負けてないのだ。
その証拠に。
「…エリュティアさん…その、何でびしょびしょなんですか?」
天音が、恐る恐る尋ねると。
エリュティアは遠い目をして、悲しげに答えた。
「うん…実は、僕の頭上にだけ、ピンポイントで雨雲が発生してて…」
雨に打たれて、びしょ濡れだと。
空、快晴なのにな。
エリュティアの頭上だけに雨雲とか、どんなギャグ漫画だよ。
「しかも…拭こうと思って持ってきたタオルに…いつの間にか穴が空いてて…」
そう言って、エリュティアは巨大な穴の空いた、穴開きタオルを広げて見せてくれた。
これは切ない。
「いっそもう…傘を持って歩こうかと思ってるんだ…」
「…そうか…」
それは…悲しいな。
シルナが、ホットチョコレートの入ったマグカップを渡してくれた。
「あぁ、ありが…」
マグカップを受け取った、その瞬間。
何もしてないのに、マグカップの持ち手が、バキッと音を立てて壊れ。
そのまま、マグカップが俺の膝の上に落下。
同時に、カップに入っていた熱々のホットチョコレートが膝を汚した。
「あっつ!!」
「あわあわあわ。羽久大丈夫!?」
もう、何をしても全く上手く行かない。
どころか、何をしても、不幸しか生まない。
慌てて、シルナと天音が、ホットチョコレートで火傷した膝に、回復魔法をかけてくれた。
申し訳なくて泣きたい。
すると、天音があることに気づいた。
「…!…羽久さん、その頭の瘤…どうしたの?」
おぉ…天音。よく気づいてくれたな。
「あぁ、これな…。今朝、授業の為に教室に行こうとしたら…階段から…椅子が落ちてきて…」
「階段から…椅子…!?」
信じられない事態だと思うだろう?
俺も信じられなかったよ。
でも、実際転げ落ちてきた椅子が、脳天を直撃したら…信じない訳にはいかないだろう?
めちゃくちゃ痛かった。
「そ、そんな不幸なことが…何で羽久さんに…」
「あぁ…うん。それなぁ…」
俺も、この三日間、ずっと考えてるんだけど…。
「とはいえ、エリュティアさんも負けてないですよ」
俺が不幸に見舞われるのを見ながら、ナジュがそう言った。
あぁ、そうだな。
悲しみの青い小人と、契約してからというもの。
不幸の度合いで言うなら、エリュティアも俺と負けてないのだ。
その証拠に。
「…エリュティアさん…その、何でびしょびしょなんですか?」
天音が、恐る恐る尋ねると。
エリュティアは遠い目をして、悲しげに答えた。
「うん…実は、僕の頭上にだけ、ピンポイントで雨雲が発生してて…」
雨に打たれて、びしょ濡れだと。
空、快晴なのにな。
エリュティアの頭上だけに雨雲とか、どんなギャグ漫画だよ。
「しかも…拭こうと思って持ってきたタオルに…いつの間にか穴が空いてて…」
そう言って、エリュティアは巨大な穴の空いた、穴開きタオルを広げて見せてくれた。
これは切ない。
「いっそもう…傘を持って歩こうかと思ってるんだ…」
「…そうか…」
それは…悲しいな。
この三日間、俺もエリュティアも、ずっとこんな感じだ。
エリュティアは、まだ分かる。
悲しい出来事が、エリュティアの身に次々と降り注ぐ。
そりゃ悲しいだろう。
その証拠に、青い小人の感情の小瓶は、じわじわと、着実に中身が溜まってきていた。
一方、クュルナが契約した赤い小人の、感情の小瓶。
こちらも、同じくじわじわと中身が溜まっているのだが。
何故かクュルナが受けるべき(?)不幸は、全て俺に降り掛かってきている。
てっきり、契約者本人に不幸が起きるのかと思っていたのだが。
赤い小人の不幸の矛先は、何故か常に俺である。
意味分かんねぇ、と最初は思ったものだが。
何のことはない。
クュルナが契約したのは、怒りの小人だ。
契約者本人に不幸が降り注げば、それは契約者を悲しませるだけ。
怒らせることは出来ない。
でも、本人じゃなかったら?
自分の代わりに、親しい他人が不幸を被ることになったら?
その感情は、悲しみではなく、怒りに変わる。
その証拠に。
「…」
見てみろ。この、クュルナの眉間の皺。
美人が台無し。
クュルナも最初は、自分の身に不幸が襲って、それによって怒りを蓄積させられるもの、と思っていたらしいが。
蓋を開けてみれば、不幸な目に遭うのは自分ではなく俺だったと知って、今ではこの不機嫌っぷり。
見事に小人の策に嵌まり、じわじわと怒りゲージが溜まっている。
そりゃまぁ、気持ちは分かる。
自分が不幸な目に遭うだけなら、自分一人の責任でどうとでもなるけど。
自分のせいで他人が不幸な目に遭うと来たら、見過ごせない。
あの赤い小人も、それを分かっててやってるのだ。
で、それが何で俺の集中砲火に繋がるのかは、分からないが。
他の人間が不幸になるだけなら、俺でなくても良いのでは?
何故頑なに、俺ばかりが不幸に見舞われるのか…それは分からないけども。
見たところクュルナには効果抜群なので、小人の策は上手く行っていると言わざるを得ない。
腹立たしいことに。
エリュティアは、まだ分かる。
悲しい出来事が、エリュティアの身に次々と降り注ぐ。
そりゃ悲しいだろう。
その証拠に、青い小人の感情の小瓶は、じわじわと、着実に中身が溜まってきていた。
一方、クュルナが契約した赤い小人の、感情の小瓶。
こちらも、同じくじわじわと中身が溜まっているのだが。
何故かクュルナが受けるべき(?)不幸は、全て俺に降り掛かってきている。
てっきり、契約者本人に不幸が起きるのかと思っていたのだが。
赤い小人の不幸の矛先は、何故か常に俺である。
意味分かんねぇ、と最初は思ったものだが。
何のことはない。
クュルナが契約したのは、怒りの小人だ。
契約者本人に不幸が降り注げば、それは契約者を悲しませるだけ。
怒らせることは出来ない。
でも、本人じゃなかったら?
自分の代わりに、親しい他人が不幸を被ることになったら?
その感情は、悲しみではなく、怒りに変わる。
その証拠に。
「…」
見てみろ。この、クュルナの眉間の皺。
美人が台無し。
クュルナも最初は、自分の身に不幸が襲って、それによって怒りを蓄積させられるもの、と思っていたらしいが。
蓋を開けてみれば、不幸な目に遭うのは自分ではなく俺だったと知って、今ではこの不機嫌っぷり。
見事に小人の策に嵌まり、じわじわと怒りゲージが溜まっている。
そりゃまぁ、気持ちは分かる。
自分が不幸な目に遭うだけなら、自分一人の責任でどうとでもなるけど。
自分のせいで他人が不幸な目に遭うと来たら、見過ごせない。
あの赤い小人も、それを分かっててやってるのだ。
で、それが何で俺の集中砲火に繋がるのかは、分からないが。
他の人間が不幸になるだけなら、俺でなくても良いのでは?
何故頑なに、俺ばかりが不幸に見舞われるのか…それは分からないけども。
見たところクュルナには効果抜群なので、小人の策は上手く行っていると言わざるを得ない。
腹立たしいことに。
「あー、もう駄目だ…。やめとこう。何かするのは駄目だ」
と、俺は呟いて、ただソファにもたれ掛かった。
何かをしようとすれば、必ず失敗して不幸な目に遭う。
何なら、職員室で書類仕事しようとしただけで、インクの瓶を書類の上にぶちまけ、ついでに窓から突風が入ってきて、書類を撒き散らす有様だから。
何をやっても裏目に出るなら、何もやらない方がマシ。
…なのだが。
「…わっ!?」
「は、羽久!?」
ただ、ソファにもたれていただけなのに。
突然ソファの背もたれが、ベキッ、と音を立てて壊れ。
俺は、背中から床に真っ逆さま。
ドスン、頭と背中を強打。
ついでに。
「羽久さん、だいじょ…うわっ!?」
エリュティアも、エリュティアで。
ただ俺を心配して、駆け寄ろうとしただけなのに。
突然、壁際に設置してある本棚の本が雪崩を起こし、エリュティアに直撃した。
二人して、床に沈没。
俺達は…もう、何をやっても駄目だな。
何もやらなくても駄目じゃん。
「…何だかコントみたいで、見てる分には面白いですね」
と、ナジュが他人事のようにポツリと言った。
…面白いですね、じゃねーよ。
こっちは、何も面白くないわ。
「…いい加減にしてください、この陰険小人」
とうとう、業を煮やしたクュルナが、赤い小人に食って掛かった。
そうなる気持ちは分かる。
「私を怒らせたいなら、私の身に何かして怒らせなさい。何で羽久さんを巻き込むんです」
クュルナ…ありがとうな。
しかし、赤い小人は、
「え?だって、この方が君を怒らせられるんだから、しょうがないでしょ?」
悪びれもせず、この態度。
「僕は君を怒らせるのが仕事なんだから、僕のやってることは間違ってないんだ。今だってそのお陰で、ほら。君は怒ってる」
あぁ、怒ってるな。
かつてないほどに、クュルナは怒りの炎を燃やしている。
「その調子で、どんどん怒ってよ。あー次は何をしようかな〜。空から金ダライとか落ちてきたら、面白いだろうな〜!」
そして、この挑発するような小人の態度。
クュルナでなくても腹が立つというものだ。
空から金ダライって、いつの時代だよ。
本当に起きそうだな。洒落にならんからやめろ。
相変わらずだが、この小人の舐めきった態度。
めちゃくちゃムカつくよな。
それに、青い小人も。
「もっともっと不幸な目に遭って、もっともっと悲しんでよ。悲しみっぷりが足りないよ」
何故か呆れたように、エリュティアにそんな我儘を言っている。
何だこの態度は。
「君はちゃんと悲しんで、僕に悲しみを教えるのが仕事なんだから。それすら満足に出来ないなんて、君は本当に駄目な人間だなぁ」
…こ、の、野郎…。
エリュティアを悲しませるのが目的の発言だと、分かってはいるものの。
それでも、ムカつくものはムカつく。
ふざけんなよ小人共。黙って聞いてりゃ。
「こいつら…いっぺん捕まえて、逆さに振ってやろうか。そうしたら、怒りも悲しみも分か…」
るだろう、と言ってやろうとしたら。
「あ!羽久さん、避けて!」
「え?」
天音が咄嗟に叫んだが、しかしあまりの怒りで我を忘れていた俺は、気が付かなかった。
気付いたときには、何処から現れたのか、金ダライが脳天を直撃。
ぐわんぐわんぐわん、と世界が数回回転し、そのままバタッ、と床に倒れた。
…今のは…効いたよ。
「あ、あぁぁ〜!羽久〜!しっかりして…」
シルナが駆け寄ってきたが、あまりの衝撃に、それさえ気づかなかった。
ただ、混濁した意識の中で、これだけは聞こえた。
「…本当にコントですね」
という、ナジュの呟きだけは。
コントじゃねーんだよ。ふざけんな。
と、言い返したかったが、もうそんな言葉も出てこなかった。
と、俺は呟いて、ただソファにもたれ掛かった。
何かをしようとすれば、必ず失敗して不幸な目に遭う。
何なら、職員室で書類仕事しようとしただけで、インクの瓶を書類の上にぶちまけ、ついでに窓から突風が入ってきて、書類を撒き散らす有様だから。
何をやっても裏目に出るなら、何もやらない方がマシ。
…なのだが。
「…わっ!?」
「は、羽久!?」
ただ、ソファにもたれていただけなのに。
突然ソファの背もたれが、ベキッ、と音を立てて壊れ。
俺は、背中から床に真っ逆さま。
ドスン、頭と背中を強打。
ついでに。
「羽久さん、だいじょ…うわっ!?」
エリュティアも、エリュティアで。
ただ俺を心配して、駆け寄ろうとしただけなのに。
突然、壁際に設置してある本棚の本が雪崩を起こし、エリュティアに直撃した。
二人して、床に沈没。
俺達は…もう、何をやっても駄目だな。
何もやらなくても駄目じゃん。
「…何だかコントみたいで、見てる分には面白いですね」
と、ナジュが他人事のようにポツリと言った。
…面白いですね、じゃねーよ。
こっちは、何も面白くないわ。
「…いい加減にしてください、この陰険小人」
とうとう、業を煮やしたクュルナが、赤い小人に食って掛かった。
そうなる気持ちは分かる。
「私を怒らせたいなら、私の身に何かして怒らせなさい。何で羽久さんを巻き込むんです」
クュルナ…ありがとうな。
しかし、赤い小人は、
「え?だって、この方が君を怒らせられるんだから、しょうがないでしょ?」
悪びれもせず、この態度。
「僕は君を怒らせるのが仕事なんだから、僕のやってることは間違ってないんだ。今だってそのお陰で、ほら。君は怒ってる」
あぁ、怒ってるな。
かつてないほどに、クュルナは怒りの炎を燃やしている。
「その調子で、どんどん怒ってよ。あー次は何をしようかな〜。空から金ダライとか落ちてきたら、面白いだろうな〜!」
そして、この挑発するような小人の態度。
クュルナでなくても腹が立つというものだ。
空から金ダライって、いつの時代だよ。
本当に起きそうだな。洒落にならんからやめろ。
相変わらずだが、この小人の舐めきった態度。
めちゃくちゃムカつくよな。
それに、青い小人も。
「もっともっと不幸な目に遭って、もっともっと悲しんでよ。悲しみっぷりが足りないよ」
何故か呆れたように、エリュティアにそんな我儘を言っている。
何だこの態度は。
「君はちゃんと悲しんで、僕に悲しみを教えるのが仕事なんだから。それすら満足に出来ないなんて、君は本当に駄目な人間だなぁ」
…こ、の、野郎…。
エリュティアを悲しませるのが目的の発言だと、分かってはいるものの。
それでも、ムカつくものはムカつく。
ふざけんなよ小人共。黙って聞いてりゃ。
「こいつら…いっぺん捕まえて、逆さに振ってやろうか。そうしたら、怒りも悲しみも分か…」
るだろう、と言ってやろうとしたら。
「あ!羽久さん、避けて!」
「え?」
天音が咄嗟に叫んだが、しかしあまりの怒りで我を忘れていた俺は、気が付かなかった。
気付いたときには、何処から現れたのか、金ダライが脳天を直撃。
ぐわんぐわんぐわん、と世界が数回回転し、そのままバタッ、と床に倒れた。
…今のは…効いたよ。
「あ、あぁぁ〜!羽久〜!しっかりして…」
シルナが駆け寄ってきたが、あまりの衝撃に、それさえ気づかなかった。
ただ、混濁した意識の中で、これだけは聞こえた。
「…本当にコントですね」
という、ナジュの呟きだけは。
コントじゃねーんだよ。ふざけんな。
と、言い返したかったが、もうそんな言葉も出てこなかった。
――――――…『白雪姫と七人の小人』から出てきた、赤い小人と契約してから、今日で五日目。
私の怒りゲージは、もう既に、臨界点を突破しつつあった。
叶うならば今すぐに、あの人の神経を逆撫でする天才である小人を、引き裂いてやりたいくらいに。
それなのに。
「いや〜、君は優秀だなー。まさか五日間で、こんなに溜まるとは」
怒りの小人は、赤い液体で満たされた小瓶を、満足げに揺らしながらそう言った。
私の怒りゲージは、もう既に、臨界点を突破しつつあった。
叶うならば今すぐに、あの人の神経を逆撫でする天才である小人を、引き裂いてやりたいくらいに。
それなのに。
「いや〜、君は優秀だなー。まさか五日間で、こんなに溜まるとは」
怒りの小人は、赤い液体で満たされた小瓶を、満足げに揺らしながらそう言った。
その小瓶は、既に満タンに近いほどに液体が満たされていた。
あと二日と半分残っているのに、である。
「こんなに優秀だとは思わなかったな〜。七日かかると思ってたのに、この調子だと今日中にでも終わりそうだね!」
「…」
私は返事をする代わりに、赤い小人を睨みつけた。
この小人だけは、どうやっても許せないし、何回引き裂いても飽き足らない。
「何々?怒ってるの〜?」
この、終始人を小馬鹿にしたような、生意気な態度と言い。
「良いことじゃないか。早く終わるんだから。何で怒ってるのかな〜」
にまにまと、思わず殴りたくなるほどのにやけ顔と言い。
「あ、それとも〜?君のご執心の彼?が不幸な目に遭うのが、そんなに気に入らないのかな〜?」
「…黙りなさい」
私は、思わずそう言い返していた。
言い返しても無駄だし、逆に挑発させる原因となるだけだと分かっていても。
言い返さずにはいられなかった。
すると、案の定。
「あ、何だ図星か〜。そうだよね〜?自分のせいで自分のお気に入りの人が傷つくなんて、そんなの黙って見てられないもんね〜。でも、君は黙って見てるしかないんだもんね〜。不甲斐ない自分が嫌になるよね〜」
「…」
そう、その通りだ。
語尾をいちいち伸ばして喋る、この独特な言い回しが、非常に癪に障るけれど。
でも、言ってることは間違ってない。むしろ大正解だ。
自分の身に何か不幸が起きるなら、それは別に構わない。
どんな目に遭っても良い。私は。
でも…だけれど…羽久さんは。
私のせいで、羽久さんの身に不幸が起きるのは…黙って見過ごすことは出来なかった。
これだけは、五日間たっても、どうしても慣れない。
慣れてたまるものか。
私の怒りゲージが、小人の予想より早く溜まっているのはそのせいだろう。
私はどうしても、私のせいで羽久さんが不幸になるのが、耐えられないのである。
あと二日と半分残っているのに、である。
「こんなに優秀だとは思わなかったな〜。七日かかると思ってたのに、この調子だと今日中にでも終わりそうだね!」
「…」
私は返事をする代わりに、赤い小人を睨みつけた。
この小人だけは、どうやっても許せないし、何回引き裂いても飽き足らない。
「何々?怒ってるの〜?」
この、終始人を小馬鹿にしたような、生意気な態度と言い。
「良いことじゃないか。早く終わるんだから。何で怒ってるのかな〜」
にまにまと、思わず殴りたくなるほどのにやけ顔と言い。
「あ、それとも〜?君のご執心の彼?が不幸な目に遭うのが、そんなに気に入らないのかな〜?」
「…黙りなさい」
私は、思わずそう言い返していた。
言い返しても無駄だし、逆に挑発させる原因となるだけだと分かっていても。
言い返さずにはいられなかった。
すると、案の定。
「あ、何だ図星か〜。そうだよね〜?自分のせいで自分のお気に入りの人が傷つくなんて、そんなの黙って見てられないもんね〜。でも、君は黙って見てるしかないんだもんね〜。不甲斐ない自分が嫌になるよね〜」
「…」
そう、その通りだ。
語尾をいちいち伸ばして喋る、この独特な言い回しが、非常に癪に障るけれど。
でも、言ってることは間違ってない。むしろ大正解だ。
自分の身に何か不幸が起きるなら、それは別に構わない。
どんな目に遭っても良い。私は。
でも…だけれど…羽久さんは。
私のせいで、羽久さんの身に不幸が起きるのは…黙って見過ごすことは出来なかった。
これだけは、五日間たっても、どうしても慣れない。
慣れてたまるものか。
私の怒りゲージが、小人の予想より早く溜まっているのはそのせいだろう。
私はどうしても、私のせいで羽久さんが不幸になるのが、耐えられないのである。
この五日間で、羽久さんがどんな不幸に遭ったと思う?
それはもう、数え切れないほど、計り知れないほどだ。
不幸な目、とは言っても、起きる事象は大小様々だ。
髪にガムがくっつくとか、ホットチョコレートを膝の上にぶちまけるとか。
それだけでも、私は非常に腹立たしかったけれど。
最近では、そういうことはなくなった。
今の羽久さんは、もっと悲惨だ。
見るに耐えない。
というのも、三日目を境に、羽久さんの身に起きる不幸のレベルが上がっている。
髪の毛にガムとか、頭に金ダライが落ちていたのが、可愛く見えるほど。
最初は「コントみたいだ」と笑っていたナジュさんも(実はこれにもちょっと苛ついていた)、笑えなくなってきているほどに。
最近の羽久さんは、不幸に遭う頻度がもっと上がっている。
もう、安全に校舎内を歩くことも出来ないほどに。
「…いたたたた…」
「あぁぁ…あぅあぅわー…。羽久大丈夫…?」
「あぁ…死ぬかと思った…」
今日の、羽久さんは。
頭と足に包帯を巻き、片腕にギプスを嵌めて、もう片方の腕で松葉杖をついていた。
何処からどう見ても…重傷者である。
こんな傷を作った原因は、勿論赤い小人にある。
全ては、私の怒りを駆り立てる為だ。
「頭は?頭どうしたの、羽久。その傷は」
「階段…の下を通りかかったとき、机が降ってきた…」
それに直撃したと。
最初の頃もそんなこと言ってたけど、あのとき降ってきたのは椅子だった。
今では、椅子から机にバージョンアップしている。
一体何があったら、どんなシチュエーションで、階段から机が降ってくるようなことがあるのだ。
このまま七日目を迎えたら、もう落ちてくるのは机じゃ済まないんじゃないだろうか。
と、思っていたら。
「それから…外を歩いてたら、上から煉瓦が落ちてきて…追撃された」
やっぱり、既に机どころではないものが落ちてきている。
煉瓦って。それはもう凶器だ。
ナイフが落ちてきても、何ら驚くことはない。
「何とか避けられないんですか?いつもの羽久さんの反射神経なら、容易に躱せるはずでは?」
と、尋ねるナジュさん。
その通りだ。
いつもの羽久さんなら、空から槍が降ってきたって、躱してみせることだろう。
あるいは、迎撃するか。
しかし。
「それが、何て言うか…避けられないんだよ、これだけは」
羽久さんは、痛みに顔をしかめながら言った。
それはもう、数え切れないほど、計り知れないほどだ。
不幸な目、とは言っても、起きる事象は大小様々だ。
髪にガムがくっつくとか、ホットチョコレートを膝の上にぶちまけるとか。
それだけでも、私は非常に腹立たしかったけれど。
最近では、そういうことはなくなった。
今の羽久さんは、もっと悲惨だ。
見るに耐えない。
というのも、三日目を境に、羽久さんの身に起きる不幸のレベルが上がっている。
髪の毛にガムとか、頭に金ダライが落ちていたのが、可愛く見えるほど。
最初は「コントみたいだ」と笑っていたナジュさんも(実はこれにもちょっと苛ついていた)、笑えなくなってきているほどに。
最近の羽久さんは、不幸に遭う頻度がもっと上がっている。
もう、安全に校舎内を歩くことも出来ないほどに。
「…いたたたた…」
「あぁぁ…あぅあぅわー…。羽久大丈夫…?」
「あぁ…死ぬかと思った…」
今日の、羽久さんは。
頭と足に包帯を巻き、片腕にギプスを嵌めて、もう片方の腕で松葉杖をついていた。
何処からどう見ても…重傷者である。
こんな傷を作った原因は、勿論赤い小人にある。
全ては、私の怒りを駆り立てる為だ。
「頭は?頭どうしたの、羽久。その傷は」
「階段…の下を通りかかったとき、机が降ってきた…」
それに直撃したと。
最初の頃もそんなこと言ってたけど、あのとき降ってきたのは椅子だった。
今では、椅子から机にバージョンアップしている。
一体何があったら、どんなシチュエーションで、階段から机が降ってくるようなことがあるのだ。
このまま七日目を迎えたら、もう落ちてくるのは机じゃ済まないんじゃないだろうか。
と、思っていたら。
「それから…外を歩いてたら、上から煉瓦が落ちてきて…追撃された」
やっぱり、既に机どころではないものが落ちてきている。
煉瓦って。それはもう凶器だ。
ナイフが落ちてきても、何ら驚くことはない。
「何とか避けられないんですか?いつもの羽久さんの反射神経なら、容易に躱せるはずでは?」
と、尋ねるナジュさん。
その通りだ。
いつもの羽久さんなら、空から槍が降ってきたって、躱してみせることだろう。
あるいは、迎撃するか。
しかし。
「それが、何て言うか…避けられないんだよ、これだけは」
羽久さんは、痛みに顔をしかめながら言った。
この作家の他の作品
表紙を見る
彼らは夢を見る。毎晩、バケモノに襲われる悪夢を。
彼らは生贄。罪を犯した人間達が生み出したバケモノを、その手で殺すことを宿命付けられた生贄。
彼らは選ばれた。「普通」であることに選ばれなかった彼ら。
裁定者たる天使が振った賽に、選ばれてしまった彼らが辿る運命は。
そして、生贄に選ばれた彼らの抱える、辛く、苦しみに満ちた過去の記憶とは…。
表紙を見る
2019年に作者が携帯小説モバスペbookに投稿した作品を移植しました。
彼らの迎えた夜明けに、祝福の歌を。
表紙を見る
2021年にモバスペbookに投稿した作品を移植しました。
エロマフィア、記念すべき第5弾。
最果てにあるレゾンデートルを、お楽しみください。
※この作品に登場する宗教、教義、宗教組織は全てフィクションです。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…