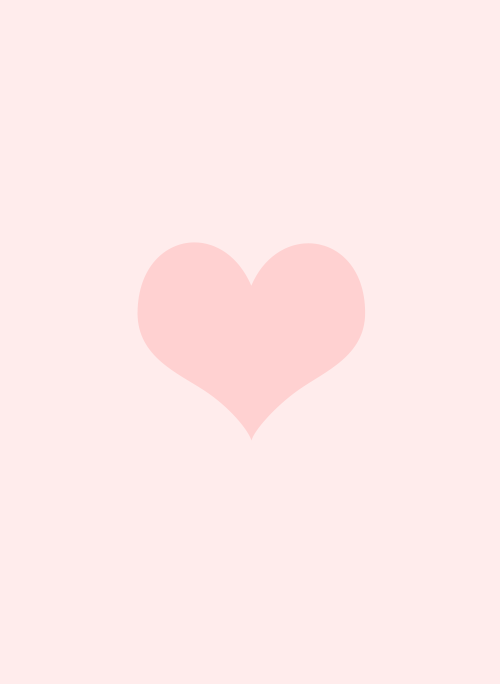「あの、」
「私は、自由が欲しいわけではないのです。このたびの自分を不甲斐ないとは思いますが、お役目を不満に思ったことはございません」
「……はい」
「あなたさまは素晴らしい巫女です。懸命で、誠実で、前向きで、明るく、歌に長けた巫女です。選ばれる理由が、私などにもわかります」
あなたさまの歌まもりでいられることを、たいへん光栄に存じます、と微笑まれて、くらりと目眩がした。
「あり、がとう、ございます……?」
すごい褒められている。
褒めに褒められている。それはだれのことですか、と首を傾げたいくらい褒められている。
「巫女さま。私の気持ちは、あなたに花を差し上げた夜から変わりません」
巫女さま。歌うたいさま。
「ただ、あなたが笑っていてくれたらと。笑ってくれたらと、願っています」
ですから、四年でなくても、自由になれなくても、構いません。
「……以前、娯楽費の話をしたとき、私は金があなたに似合うと答えましたが」
「ええ」
あなたに似合うと言われたあの日からずっと、いまも、わたくしの爪は金色をしている。
「ほんとうは、紫を選びたかったと申し上げたら、お困りになりますか」
「私は、自由が欲しいわけではないのです。このたびの自分を不甲斐ないとは思いますが、お役目を不満に思ったことはございません」
「……はい」
「あなたさまは素晴らしい巫女です。懸命で、誠実で、前向きで、明るく、歌に長けた巫女です。選ばれる理由が、私などにもわかります」
あなたさまの歌まもりでいられることを、たいへん光栄に存じます、と微笑まれて、くらりと目眩がした。
「あり、がとう、ございます……?」
すごい褒められている。
褒めに褒められている。それはだれのことですか、と首を傾げたいくらい褒められている。
「巫女さま。私の気持ちは、あなたに花を差し上げた夜から変わりません」
巫女さま。歌うたいさま。
「ただ、あなたが笑っていてくれたらと。笑ってくれたらと、願っています」
ですから、四年でなくても、自由になれなくても、構いません。
「……以前、娯楽費の話をしたとき、私は金があなたに似合うと答えましたが」
「ええ」
あなたに似合うと言われたあの日からずっと、いまも、わたくしの爪は金色をしている。
「ほんとうは、紫を選びたかったと申し上げたら、お困りになりますか」
「っ」
すみれ色の目に射抜かれて、胸が熱くて、頭が真っ白で、どうしたらいいかわからなかった。
「それは、その、歌うたいに選ばれたら、紫の包みが届くからですか」
「……はぐらかされてます?」
「いえ、だって、」
この後に及んではぐらかしてはいない。いないのだけれど、でも、そんなわけが。そんな都合のいいことが起こるわけがない。
現実逃避をしようとするこちらに言い含めるように、巫女さま、と呼ばれた。
低く、甘やかで、嗄れた声音。
折り目正しい距離を守ってきたこのひとには珍しい、熱をはらんだ音。
どうしてそんな呼び方をするのか考えて、やっぱり都合のいい理由を思い浮かべてしまって。
混乱している間に、歌まもりさまが一歩こちらに詰めた。少しだけ、距離が近くなる。
「あなたは金色がよくお似合いです。ほんとうにおきれいだ」
また一歩、近くなる。
「でも、私が選んだ色がいいと言われて、それが慰めになるなんて言われて」
近くなる。
「選んだ色を、身につけたいなんて」
ベッドのそば、先ほど座っていた椅子を越えた。
「その意味が、わからないとでもお思いですか」
一歩。
節度ある距離はすっかり縮まり、大きな体躯がもう目の前にある。
一歩ずつ確かめるように足を進めたのは、こちらが断れるようにするためだ。少しでも怯えたら、きっとやめてくれるつもりだった。
わたくしはこのひとの、そういうこまやかな配慮が好きなのだった。
すみれ色の目に射抜かれて、胸が熱くて、頭が真っ白で、どうしたらいいかわからなかった。
「それは、その、歌うたいに選ばれたら、紫の包みが届くからですか」
「……はぐらかされてます?」
「いえ、だって、」
この後に及んではぐらかしてはいない。いないのだけれど、でも、そんなわけが。そんな都合のいいことが起こるわけがない。
現実逃避をしようとするこちらに言い含めるように、巫女さま、と呼ばれた。
低く、甘やかで、嗄れた声音。
折り目正しい距離を守ってきたこのひとには珍しい、熱をはらんだ音。
どうしてそんな呼び方をするのか考えて、やっぱり都合のいい理由を思い浮かべてしまって。
混乱している間に、歌まもりさまが一歩こちらに詰めた。少しだけ、距離が近くなる。
「あなたは金色がよくお似合いです。ほんとうにおきれいだ」
また一歩、近くなる。
「でも、私が選んだ色がいいと言われて、それが慰めになるなんて言われて」
近くなる。
「選んだ色を、身につけたいなんて」
ベッドのそば、先ほど座っていた椅子を越えた。
「その意味が、わからないとでもお思いですか」
一歩。
節度ある距離はすっかり縮まり、大きな体躯がもう目の前にある。
一歩ずつ確かめるように足を進めたのは、こちらが断れるようにするためだ。少しでも怯えたら、きっとやめてくれるつもりだった。
わたくしはこのひとの、そういうこまやかな配慮が好きなのだった。
寝台に横たわったまま見上げると、歌まもりさまはこちらを覗き込んだ。
光の関係で顔全体に薄い影ができて、額を縁取る髪がいつもより濃い茶色になっている。すみれ色の目が、宝石みたいにきれいだった。
するりと手を取られて、冷え切った爪の上を、太い指先が優しく撫ぜた。
あんまり予想外すぎて、思わずびくりと盛大に手が跳ねる。
だって、歌まもりとしての距離を保ってきたこのひとに、エスコートではなく触れられるとは思わなかったんだもの。
「……おいやですか」
いいえ、と答えたはずの声は音にならなかった。慌ててぶんぶん首を振る。
いやではないけれど、恥ずかしいというか、びっくりするというか、変な感じがしますね。うん。
緊張しすぎて指は冷えているのに、顔は沸騰しそうに熱い。
「あのとき、よほど、紫と言おうかと思いました」
歌うたいさまが歌まもりの色を身につけていたら、そういうことでしょう。
「それはちょっと、卑怯かと思いまして」
「いえ、その、卑怯だなんて」
むしろ喜んで身につけましたけれど。
「でもいまは、金にしてよかったと思っています。どんなに飾られてもあなたは変わらず清廉で、金がそれを際立せる。金がこれほど厳かに似合う方を、私は他に知りません」
あああ、だめ、もう顔が熱すぎてだめ。
「巫女さま」
「はい」
役名を呼ばれた。聞き慣れた、優しい声色。
お役目を言われただけなのに、甘やかな響きをしていた。
「これから先も、あなたに笑いかけたいと思っては、いけませんか」
光の関係で顔全体に薄い影ができて、額を縁取る髪がいつもより濃い茶色になっている。すみれ色の目が、宝石みたいにきれいだった。
するりと手を取られて、冷え切った爪の上を、太い指先が優しく撫ぜた。
あんまり予想外すぎて、思わずびくりと盛大に手が跳ねる。
だって、歌まもりとしての距離を保ってきたこのひとに、エスコートではなく触れられるとは思わなかったんだもの。
「……おいやですか」
いいえ、と答えたはずの声は音にならなかった。慌ててぶんぶん首を振る。
いやではないけれど、恥ずかしいというか、びっくりするというか、変な感じがしますね。うん。
緊張しすぎて指は冷えているのに、顔は沸騰しそうに熱い。
「あのとき、よほど、紫と言おうかと思いました」
歌うたいさまが歌まもりの色を身につけていたら、そういうことでしょう。
「それはちょっと、卑怯かと思いまして」
「いえ、その、卑怯だなんて」
むしろ喜んで身につけましたけれど。
「でもいまは、金にしてよかったと思っています。どんなに飾られてもあなたは変わらず清廉で、金がそれを際立せる。金がこれほど厳かに似合う方を、私は他に知りません」
あああ、だめ、もう顔が熱すぎてだめ。
「巫女さま」
「はい」
役名を呼ばれた。聞き慣れた、優しい声色。
お役目を言われただけなのに、甘やかな響きをしていた。
「これから先も、あなたに笑いかけたいと思っては、いけませんか」
「いいえ」
よく考える前に、否定がこぼれ落ちる。
「いいえ。……あの、四年経っても、そばにいてくださるの、ですか」
「ええ。私などでもよろしければ」
「あなたがいい」
丁寧な口調が吹き飛んだ。はっとして言い直す。
ええと。
「一緒になるなら、あなたがいい、です」
ごめんなさい、うまく言葉が出なくて、と慌てると、歌まもりさまはやわらかく微笑んだ。
「かつてあなたさまは、ご自分をわたしと言っていましたね。あの頃も、うまく言葉が出なくてお困りだった。それを、可愛らしく思い出します」
うっ、ずるい。いまは可愛くないですか、なんていじけたことさえ言えない。
ええと、では。
「わたくしが二十五になったら、きっと歌まもりさまのお名前を教えてください」
わたくしは巫女。歌うたい。お役目の名前以外では呼ばれない。
このひとも同じく、歌まもり以外の名前では呼ばれない。
かつての同僚も、先輩も、上司と思われるひとも、この神殿に出入りする騎士たちはみな、このひとを歌まもりと呼ぶ。
お役目が終わったら、普通のひとに戻ったら、その証に、教えてもらった名前であなたを呼びたい。
堂々と、大手を振って、だれに遠慮することもなく、あなたに好きですと伝えたい。
「ええ。きっとお教えします」
でも、その前に。
「次は必ずお守りします。いえ、同じことは起こさせません」
「みなで気をつけてまいりましょう。まず手始めに、お花の本を取り寄せませんか?」
「はい」
それから、お花の勉強が始まった。
夜、持ってきてもらったお花を窓辺に飾る。
月明かりに照らされたそれを見ながら一緒に勉強する時間は、花売りになりたいと思っていたわたくしには、嬉しいものだった。
よく考える前に、否定がこぼれ落ちる。
「いいえ。……あの、四年経っても、そばにいてくださるの、ですか」
「ええ。私などでもよろしければ」
「あなたがいい」
丁寧な口調が吹き飛んだ。はっとして言い直す。
ええと。
「一緒になるなら、あなたがいい、です」
ごめんなさい、うまく言葉が出なくて、と慌てると、歌まもりさまはやわらかく微笑んだ。
「かつてあなたさまは、ご自分をわたしと言っていましたね。あの頃も、うまく言葉が出なくてお困りだった。それを、可愛らしく思い出します」
うっ、ずるい。いまは可愛くないですか、なんていじけたことさえ言えない。
ええと、では。
「わたくしが二十五になったら、きっと歌まもりさまのお名前を教えてください」
わたくしは巫女。歌うたい。お役目の名前以外では呼ばれない。
このひとも同じく、歌まもり以外の名前では呼ばれない。
かつての同僚も、先輩も、上司と思われるひとも、この神殿に出入りする騎士たちはみな、このひとを歌まもりと呼ぶ。
お役目が終わったら、普通のひとに戻ったら、その証に、教えてもらった名前であなたを呼びたい。
堂々と、大手を振って、だれに遠慮することもなく、あなたに好きですと伝えたい。
「ええ。きっとお教えします」
でも、その前に。
「次は必ずお守りします。いえ、同じことは起こさせません」
「みなで気をつけてまいりましょう。まず手始めに、お花の本を取り寄せませんか?」
「はい」
それから、お花の勉強が始まった。
夜、持ってきてもらったお花を窓辺に飾る。
月明かりに照らされたそれを見ながら一緒に勉強する時間は、花売りになりたいと思っていたわたくしには、嬉しいものだった。
いつものように明かりを消しにきた歌まもりさまを引き留める。
「わたくし、明日には二十五になります」
「はい」
「次の巫女の担い手が見つかれば、お役目は終わり。……夢のお告げで、次代を探すのでしたね」
「はい」
神が、選んだ巫女の名を教えると、初めに聞いた。わたくしもそうして選ばれた。
「わたくしは普段、夢を見ません。いいえ、見るのかもしれないけれど、覚えていたことがありません。……大丈夫でしょうか」
悪い予感がする。
最後だと思ってどきどきしていたからかもしれないけれど、今日は化粧筆やカトラリーやいろいろなものを落としたし、一部声がうまく出なかったし、天気が悪かった。
黒雲が立ち込める空が最後を飾るなんて、おどろおどろしいというもの。
「きっと大丈夫です」
「……そうだと、いいのですけれど……」
その晩、夢に、お告げはなかった。
「わたくし、明日には二十五になります」
「はい」
「次の巫女の担い手が見つかれば、お役目は終わり。……夢のお告げで、次代を探すのでしたね」
「はい」
神が、選んだ巫女の名を教えると、初めに聞いた。わたくしもそうして選ばれた。
「わたくしは普段、夢を見ません。いいえ、見るのかもしれないけれど、覚えていたことがありません。……大丈夫でしょうか」
悪い予感がする。
最後だと思ってどきどきしていたからかもしれないけれど、今日は化粧筆やカトラリーやいろいろなものを落としたし、一部声がうまく出なかったし、天気が悪かった。
黒雲が立ち込める空が最後を飾るなんて、おどろおどろしいというもの。
「きっと大丈夫です」
「……そうだと、いいのですけれど……」
その晩、夢に、お告げはなかった。
うそ。
夢を見逃した? 忘れた?
そうだ、まだ目が覚めていないんだわ。ここは夢のなか、だからお告げがないのよ。うそ、うそ、うそ——
「珍しくお寝坊ですね、歌うたいさま。おはようございます、よい朝ですよ」
からかうような軽やかで穏やかな世話係の声は、聞こえないふりをした。
母のような年齢の彼女の、十年間お世話になって慣れ親しんだ声が、いまだけ耳につく。
大丈夫、まだ夢うつつ、起きていないわ。大丈夫、大丈夫。
「歌うたいさま、歌うたいさま。朝にございますよ」
悪気なく繰り返す声に、起きないわけにはいかなかった。無理矢理笑顔を作る。
「おはよう、よい朝ね」
「はい、おはようございます」
「……朝餉の前に、歌まもりさまをお呼びして」
はい、と返事をした世話係が、なにも言わずに部屋を出た。
いくら歌まもりさまとはいえ、支度もしないで呼ぶなど初めてのこと。
きっとお告げがあったと勘違いしているのね。急いで呼んできてくれるのでしょう。
申し訳なさがひたひた喉を迫り上げる。
起きたばかりでひどい顔をしているに違いないけれど、相談しなければ。
これはわたくしひとりのことではないのだもの。わたくしたち、ひいてはこの国の未来がかかっているのだもの。
泣きそうに震える体を叱咤して、じっと歌まもりさまを待つ。
じりじりと長く感じられた数分後、控えめなノックが響いた。
夢を見逃した? 忘れた?
そうだ、まだ目が覚めていないんだわ。ここは夢のなか、だからお告げがないのよ。うそ、うそ、うそ——
「珍しくお寝坊ですね、歌うたいさま。おはようございます、よい朝ですよ」
からかうような軽やかで穏やかな世話係の声は、聞こえないふりをした。
母のような年齢の彼女の、十年間お世話になって慣れ親しんだ声が、いまだけ耳につく。
大丈夫、まだ夢うつつ、起きていないわ。大丈夫、大丈夫。
「歌うたいさま、歌うたいさま。朝にございますよ」
悪気なく繰り返す声に、起きないわけにはいかなかった。無理矢理笑顔を作る。
「おはよう、よい朝ね」
「はい、おはようございます」
「……朝餉の前に、歌まもりさまをお呼びして」
はい、と返事をした世話係が、なにも言わずに部屋を出た。
いくら歌まもりさまとはいえ、支度もしないで呼ぶなど初めてのこと。
きっとお告げがあったと勘違いしているのね。急いで呼んできてくれるのでしょう。
申し訳なさがひたひた喉を迫り上げる。
起きたばかりでひどい顔をしているに違いないけれど、相談しなければ。
これはわたくしひとりのことではないのだもの。わたくしたち、ひいてはこの国の未来がかかっているのだもの。
泣きそうに震える体を叱咤して、じっと歌まもりさまを待つ。
じりじりと長く感じられた数分後、控えめなノックが響いた。
「巫女さま、歌まもりにございます。お呼びと伺い、まいりました」
「開いています。お入りください」
「失礼します」
そばに控えようとした世話係には、「ふたりでお話したいの」と伝えて出てもらう。
厳重な警戒に、「防音の道具を置きますか」と低い声で短く聞かれる。
その手にはメモがある。きっと、次の巫女の名前を控えるためのメモ。
お告げはふたりきりでなくてもいいのだから、ふたりでと念押ししたことに疑問が浮かんだだろうに、なにも言わないでくれたのだ。
「お告げのことですか」とも、「どうしたのですか」とも聞かずに、真っ先に防音が必要かどうかを聞いてくれた。
「ええ、ぜひ」
こういうとき、このひとは順番を間違えない。
それは歌まもりとしての訓練と、このひとの性質がそうさせるんでしょうね。
思慮深く、誠実で、落ち着いているひと。
「かしこまりました」
節の高い指が、小さな水晶を寝台のそばに置く。
これでわたくしたち以外には会話が聞こえなくなる。全員扉の外にいてもらっているけれど、念のため。
……ほんとうのことを伝えたら、たいへんな騒ぎになるに決まっているもの。
もちろん今日中に話をしないといけないけれど、どうしたらいいか相談してからにしたい。
「開いています。お入りください」
「失礼します」
そばに控えようとした世話係には、「ふたりでお話したいの」と伝えて出てもらう。
厳重な警戒に、「防音の道具を置きますか」と低い声で短く聞かれる。
その手にはメモがある。きっと、次の巫女の名前を控えるためのメモ。
お告げはふたりきりでなくてもいいのだから、ふたりでと念押ししたことに疑問が浮かんだだろうに、なにも言わないでくれたのだ。
「お告げのことですか」とも、「どうしたのですか」とも聞かずに、真っ先に防音が必要かどうかを聞いてくれた。
「ええ、ぜひ」
こういうとき、このひとは順番を間違えない。
それは歌まもりとしての訓練と、このひとの性質がそうさせるんでしょうね。
思慮深く、誠実で、落ち着いているひと。
「かしこまりました」
節の高い指が、小さな水晶を寝台のそばに置く。
これでわたくしたち以外には会話が聞こえなくなる。全員扉の外にいてもらっているけれど、念のため。
……ほんとうのことを伝えたら、たいへんな騒ぎになるに決まっているもの。
もちろん今日中に話をしないといけないけれど、どうしたらいいか相談してからにしたい。
「どうなさいましたか。朝餉をとらぬなど、あなたさまらしくないこと。なにかありましたか」
歌まもりさまは、朝早いというのに、きちんと服を着込んでいた。身だしなみも整っている。
そんなぴしりと決まったひとに、こんな情けないことを言わなくてはいけないなんて、恥ずかしくてたまらない。
震える唇を、ゆっくり開く。
「歌まもりさま。わたくし、まだ、あなたさまのお名前を教えていただけないようです」
ひとつ、まばたき。
「なん、ですって?」
歌まもりさまの声が、珍しくひっくり返った。
「……お告げが、ございませんでした」
尻すぼみに消えそうな言葉を、必死で繰り返す。
「いえ、覚えていないのかもしれません。でもいま確かなことは、わたくしの次の巫女がどなたになるのか、まだわからないということです」
申し訳ない。泣いてしまいたい。
「巫女さま、失礼ながら復唱いたします。お告げが、なかったんですね?」
「お、お告げが、ございませんでした」
耐えきれず、ぽろ、と涙が落ちた。
「わたし、わたし、聞き逃してしまったのでしょうか。不信心なわたしに、お怒りなのでしょうか。わたし、なにか、間違えてしまったのでしょうか」
それとも。
「それともわたし、お告げを忘れてしまったのでしょうか……」
歌まもりさまは、朝早いというのに、きちんと服を着込んでいた。身だしなみも整っている。
そんなぴしりと決まったひとに、こんな情けないことを言わなくてはいけないなんて、恥ずかしくてたまらない。
震える唇を、ゆっくり開く。
「歌まもりさま。わたくし、まだ、あなたさまのお名前を教えていただけないようです」
ひとつ、まばたき。
「なん、ですって?」
歌まもりさまの声が、珍しくひっくり返った。
「……お告げが、ございませんでした」
尻すぼみに消えそうな言葉を、必死で繰り返す。
「いえ、覚えていないのかもしれません。でもいま確かなことは、わたくしの次の巫女がどなたになるのか、まだわからないということです」
申し訳ない。泣いてしまいたい。
「巫女さま、失礼ながら復唱いたします。お告げが、なかったんですね?」
「お、お告げが、ございませんでした」
耐えきれず、ぽろ、と涙が落ちた。
「わたし、わたし、聞き逃してしまったのでしょうか。不信心なわたしに、お怒りなのでしょうか。わたし、なにか、間違えてしまったのでしょうか」
それとも。
「それともわたし、お告げを忘れてしまったのでしょうか……」
忘れたのか、そもそもお告げがなかったのか、定かでないことが問題だ。
いままでは、その代の巫女の誕生日が過ぎたら、きちんとお告げがあった。
その内容も、巫女がきちんと伝えていた。
だから、お告げがないかもしれないとか、忘れる巫女がいるかもしれないとかなんて、だれも思いもしなかった。
そんな愚かな可能性は、わたしの番になるまで、万に一つもなかったのだ。
「どう、どうしたら、どうしたらいいのでしょう。みなお告げがあるものと、準備ももうすっかりしてあるのに、こんな前例は聞いたことがありません」
嗄れて引きつれる声を、必死に絞り出す。
「……わたし、だめな巫女ですか」
ばかな問いかけだった。
わかっていて、それでもこぼれ落ちた。だめな巫女でしたか、とは聞けなかった。
「いいえ」
歌まもりさまは優しい。即答は短く、穏やかだった。
「わたし、なにか、力不足で、おつとめができていなかったのでしょうか」
「いいえ、あなたさまのお力は確かです。あなたさまが着任されてから、わが国の守りは揺るぎません」
「では、ではなぜ、」
「巫女さま」
「わたし、」
「巫女さま。ご体調が優れないご様子。おやすみなさいませ」
「いいえ、おつとめをしなければ。こんなときこそしなければ。わたしは巫女ですもの。この国を守るが役目」
「いいえ、おやすみください」
歌まもりさまは頑として引かなかった。大人として、こちらを尊重してくれる歌まもりさまに珍しい頑なさだった。
思わず涙で濡れた視界を上げる。
いままでは、その代の巫女の誕生日が過ぎたら、きちんとお告げがあった。
その内容も、巫女がきちんと伝えていた。
だから、お告げがないかもしれないとか、忘れる巫女がいるかもしれないとかなんて、だれも思いもしなかった。
そんな愚かな可能性は、わたしの番になるまで、万に一つもなかったのだ。
「どう、どうしたら、どうしたらいいのでしょう。みなお告げがあるものと、準備ももうすっかりしてあるのに、こんな前例は聞いたことがありません」
嗄れて引きつれる声を、必死に絞り出す。
「……わたし、だめな巫女ですか」
ばかな問いかけだった。
わかっていて、それでもこぼれ落ちた。だめな巫女でしたか、とは聞けなかった。
「いいえ」
歌まもりさまは優しい。即答は短く、穏やかだった。
「わたし、なにか、力不足で、おつとめができていなかったのでしょうか」
「いいえ、あなたさまのお力は確かです。あなたさまが着任されてから、わが国の守りは揺るぎません」
「では、ではなぜ、」
「巫女さま」
「わたし、」
「巫女さま。ご体調が優れないご様子。おやすみなさいませ」
「いいえ、おつとめをしなければ。こんなときこそしなければ。わたしは巫女ですもの。この国を守るが役目」
「いいえ、おやすみください」
歌まもりさまは頑として引かなかった。大人として、こちらを尊重してくれる歌まもりさまに珍しい頑なさだった。
思わず涙で濡れた視界を上げる。
この作家の他の作品
表紙を見る
彼女はひどく淡白で
彼はひどく冷静で
二人はひどく、もどかしい
*
「ねえ、妬こうよ、そこはさ。」
「……え、なんで?」
*
似た者同士
淡々としすぎな大人たち
あの手この手で仕掛けてみても
無反応、無頓着、
何だかさらっと流される
——ねえ、旦那さん。
——なあ、奥さん。
……ヤキモチとか、
独占欲とか、
少しはないんですか。
((……馬鹿))
*
頂いたリクエストをもとに
番外編を書きました。
よろしければそちらも併せてどうぞ。
表紙を見る
あなたが二百年後に生まれたなら、
きっと小説を書いたでしょう。
あなたが百年前に生まれたなら、
きっと何も書けなかったでしょう。
しかしあなたはこの時代に生まれたゆえに、
あなたの文才は書簡で花開いたのです。
*
「わたくしの薔薇と、呼ばせてくれるわね?」
女王に書き物を見初められた、
ある女性の話
表紙を見る
あの夕暮れどきから、わたしは
この場所とこの人を推している。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…