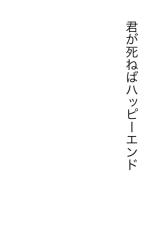二〇二三年。三月十日。金曜日。
先日、三月三日に三年生の卒業式があって、一学年丸々の人数が学校から消えた。
たまに進路の件か、部活動のOBなのか、卒業生を校舎内で見かけたけれど、部活もやっていない私には関係無い。
二時間目が始まって、九時五十分。
人生で最期の、担任の国語の授業中。
担任にはお世話になったから、最期に教壇に立つ姿を見ておこうという話で、私達の意見は一致した。
時計の秒針がゆっくりと回る。
もっとゆっくりしたスピードで、長針と短針がほんの少しずつ時間を刻む。
九時五十九分。
「先生。」
私はスッと右手を挙げた。
黒板に向かってチョークで文字を書いていた先生は、黄色いチョークをつまんだまま、私を振り返った。
「楠さん?どうかした?珍しく質問かしら?」
担任はにこにこと微笑む。
国語の授業…に関わらず、授業中に私が自ら挙手したことなんて一度も無い。
よっぽど嬉しかったのか、担任は目をキラキラさせている。
ごめんね。先生。違うんだよ。さよならの時間。
私はわざとらしく弱々しく椅子を押し引いて立った。
「すみません…。ちょっと具合悪くて。吐きそうかも…。」
「まぁ!大丈夫?ごめんね、気付かなくて!」
「先生!私、保健室に連れていきます!」
深春が大きな声を上げて、私に駆け寄った。
周りのクラスメイトが心配そうに私を見ている。
「棗さんなら安心だわ。お願いね。」
私と深春は担任に頭を下げて、深春が私を支えながら、教室を出た。
階段がある曲がり角まではそのスタイルを崩さない。
隣のクラスの窓から、生き生きと歩く姿を見られるわけにはいかないから。
先生。最期に最悪な嘘をついてごめんなさい。
一番最期に受けた大人の優しさは、先生でした。
先生も学校も、簡単に私達を見逃してしまって、これからが地獄かもしれない。
恩を仇で返した私達を先生はきっと許してはくれないでしょう。
恨みなんか一つも無いのに。
身勝手に産み落とされた私達の、最期のアンチテーゼ。
許されなくてもいい。
どうか解って。
先日、三月三日に三年生の卒業式があって、一学年丸々の人数が学校から消えた。
たまに進路の件か、部活動のOBなのか、卒業生を校舎内で見かけたけれど、部活もやっていない私には関係無い。
二時間目が始まって、九時五十分。
人生で最期の、担任の国語の授業中。
担任にはお世話になったから、最期に教壇に立つ姿を見ておこうという話で、私達の意見は一致した。
時計の秒針がゆっくりと回る。
もっとゆっくりしたスピードで、長針と短針がほんの少しずつ時間を刻む。
九時五十九分。
「先生。」
私はスッと右手を挙げた。
黒板に向かってチョークで文字を書いていた先生は、黄色いチョークをつまんだまま、私を振り返った。
「楠さん?どうかした?珍しく質問かしら?」
担任はにこにこと微笑む。
国語の授業…に関わらず、授業中に私が自ら挙手したことなんて一度も無い。
よっぽど嬉しかったのか、担任は目をキラキラさせている。
ごめんね。先生。違うんだよ。さよならの時間。
私はわざとらしく弱々しく椅子を押し引いて立った。
「すみません…。ちょっと具合悪くて。吐きそうかも…。」
「まぁ!大丈夫?ごめんね、気付かなくて!」
「先生!私、保健室に連れていきます!」
深春が大きな声を上げて、私に駆け寄った。
周りのクラスメイトが心配そうに私を見ている。
「棗さんなら安心だわ。お願いね。」
私と深春は担任に頭を下げて、深春が私を支えながら、教室を出た。
階段がある曲がり角まではそのスタイルを崩さない。
隣のクラスの窓から、生き生きと歩く姿を見られるわけにはいかないから。
先生。最期に最悪な嘘をついてごめんなさい。
一番最期に受けた大人の優しさは、先生でした。
先生も学校も、簡単に私達を見逃してしまって、これからが地獄かもしれない。
恩を仇で返した私達を先生はきっと許してはくれないでしょう。
恨みなんか一つも無いのに。
身勝手に産み落とされた私達の、最期のアンチテーゼ。
許されなくてもいい。
どうか解って。