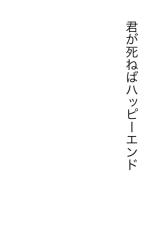「ごめんね。まふゆの誕生日はお祝い出来なくて。」
「今してくれたじゃん。」
「7のろうそくも買えば良かったかな。」
「それじゃあ百六十七歳みたいだね。」
うーん、と深春は唸った。
食べ終わったケーキの箱とフォークをまとめて片付けながら、私は空を見上げていた。
「三月になったらもう少し暖かくなるかなぁ。」
「今よりは、多分ね。」
「凍えながら死ぬのはさすがに嫌だもんね。」
深春は頷いて、私をギュッとした。
「あったかい?」
「うん。」
深春が首筋に口付ける。
マフラーの隙間から深春の吐息が入り込んできて、熱を感じた。
「やっぱり四月まで待つ?」
「何で?」
「まふゆの誕生日まで。一度もまふゆの誕生日におめでとうって言えてない。」
「今のままがいいよ。」
「今のまま?」
「やっと同じ年齢になれた。“同級生”なのに、深春、遅いんだもん。」
「ふふ。うん。そうだね。」
あと一ヶ月。
深春の熱を感じられるのも、声が聴けるのも、手を繋いだりキスをしたり、好きだよって何度も伝えたり。
全部があと一ヶ月でゼロになる。
命の期限が目の前まで来ている。
実感が無いからなのか、全然怖くもないし、引き返したいとも思わない。
心配事と言えば、来世なんて本当にあるのかってこと。
もう一度深春に逢えるのなら何度転生したって構わない。
「うまくいくといいね。リセット。」
「リセット?」
「うん。命のリセット。」
深春の頭を撫でた。
相変わらずツヤツヤの髪の毛。甘い香りがする。
私の髪も肩につくくらいまで伸びた。
もう脱色したりもしていないし、少しは髪質も改善されたと思う。
そんなことにすら、死んだら全て意味の無いこと。
あの世まで、来世まで持っていく物は、深春への想いだけでいい。
今世の苦しかったこと、報われなかったこと全部が救われなくてもいい。
たった一つだけ。
深春のことだけは絶対に憶えていてね、来世の私。
「深春。愛してるよ。」
「知ってるよ。」
「今してくれたじゃん。」
「7のろうそくも買えば良かったかな。」
「それじゃあ百六十七歳みたいだね。」
うーん、と深春は唸った。
食べ終わったケーキの箱とフォークをまとめて片付けながら、私は空を見上げていた。
「三月になったらもう少し暖かくなるかなぁ。」
「今よりは、多分ね。」
「凍えながら死ぬのはさすがに嫌だもんね。」
深春は頷いて、私をギュッとした。
「あったかい?」
「うん。」
深春が首筋に口付ける。
マフラーの隙間から深春の吐息が入り込んできて、熱を感じた。
「やっぱり四月まで待つ?」
「何で?」
「まふゆの誕生日まで。一度もまふゆの誕生日におめでとうって言えてない。」
「今のままがいいよ。」
「今のまま?」
「やっと同じ年齢になれた。“同級生”なのに、深春、遅いんだもん。」
「ふふ。うん。そうだね。」
あと一ヶ月。
深春の熱を感じられるのも、声が聴けるのも、手を繋いだりキスをしたり、好きだよって何度も伝えたり。
全部があと一ヶ月でゼロになる。
命の期限が目の前まで来ている。
実感が無いからなのか、全然怖くもないし、引き返したいとも思わない。
心配事と言えば、来世なんて本当にあるのかってこと。
もう一度深春に逢えるのなら何度転生したって構わない。
「うまくいくといいね。リセット。」
「リセット?」
「うん。命のリセット。」
深春の頭を撫でた。
相変わらずツヤツヤの髪の毛。甘い香りがする。
私の髪も肩につくくらいまで伸びた。
もう脱色したりもしていないし、少しは髪質も改善されたと思う。
そんなことにすら、死んだら全て意味の無いこと。
あの世まで、来世まで持っていく物は、深春への想いだけでいい。
今世の苦しかったこと、報われなかったこと全部が救われなくてもいい。
たった一つだけ。
深春のことだけは絶対に憶えていてね、来世の私。
「深春。愛してるよ。」
「知ってるよ。」