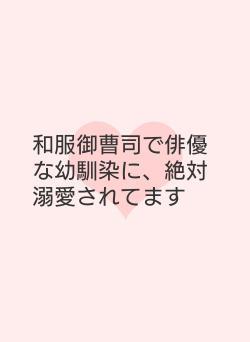彼女はシーリンと名乗った。
「不思議な名前ね」
わたしがそう言うと、彼女は首を傾げて微笑んだ。
「よく言われます」
(本当に綺麗な女の子だわ)
シーリンも貴族の令嬢らしいのだけれど、髪結いをしていたことなんかも含めて、詳しいことは教えてくれなかった。
彼女はわたしの愚痴を聞きながら、最先端のネイルやメイク、立ち居振舞い、礼儀作法に流行りのファッション……女性なら知っておいて損はない情報を教えてくれる。
――気づけば、わたしは別人のように綺麗な令嬢に生まれ変わっていた。
(本当に私……?)
艶やかな黒髪に、白い陶器のような肌、薔薇色の頬に桜色の唇。
流行の桃色のドレスに身を包んだわたしは、童話に出てくる花の妖精のようだった。
「ありがとう、シーリン! こんなに別人のように生まれ変われるなんて……! すごく嬉しいわ……!」
お礼を言いながら、彼女の元に向かおうとしたところ――。
「きゃっ……!」
ドレスの裾を靴で踏んでしまい、わたしは前のめりに倒れてしまった。
そんなわたしの身体を、シーリンは受け止める。
彼女に抱き着く格好になってしまったわたしが、彼女の顔を見上げると、深い海のように煌めく蒼い瞳と出会った。
なぜだか、わたしの心臓がどきんと跳ねる。
「スピカは、相変わらずおっちょこちょいだね。うっかり変な男に騙されるぐらい、とても純粋で可愛らしい。奪い返そうとは言ったけれど、元婚約者の侯爵に手渡すのはなんだか癪だな」
シーリンの言い方がなぜだか、男らしく聞こえてしまった。
(わたしったら、女性相手に胸がドキドキしてしまうなんて……)
「シーリンに相談するし、もう変な男には騙されたりはしません」
「本当かな?」
そう言いながら、彼女はわたしの耳にちゅっと口づけてきた。
男女問わず、初めてそんなことをされてしまい、どんどん心臓の音がうるさくなる。
そんな胸の内をごまかすように、わたしは彼女に向かって話しかけた。
「もし、シーリンが男性だったら、話しやすくて優しくて……恋をしてしまっていたかもしれないわ」
わたしがそんな軽口を叩くと、彼女はふんわりと笑った。
「それは良いことを聞いた。嬉しいよ、スピカ」
彼女の微笑みに、心臓が落ち着く暇もない。
「ああ、スピカ、そう言えば――」
そうして彼女はにっこりと微笑みながら、わたしに告げる。
「今度、私の親戚の屋敷で舞踏会があって、そこにデネブ侯と件のご令嬢も来るんだけど……一緒に奪い返しに行こうか――?」
こうして、わたしはシーリンと一緒に、デネブを取り返しに向かうことになったのだった。