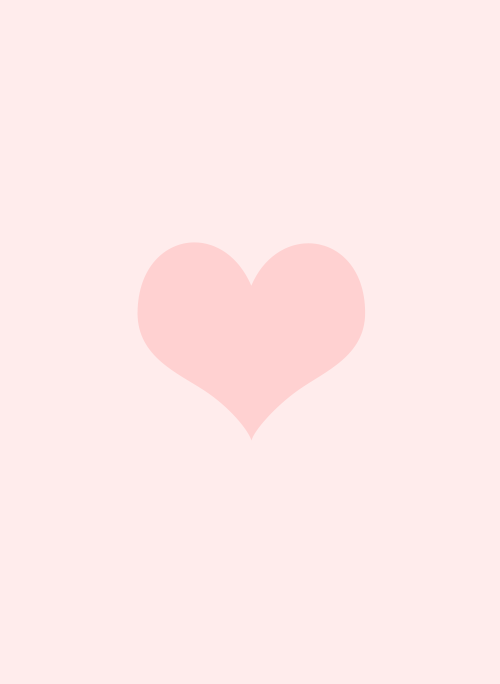「ねえ、笹山さん、また人の彼氏を横取りしたんだって」
「で、飽きたらポイ捨てでしょ?」
「ほんと悪女だね。中学時代気に入らない女子をいじめ倒したらしいよ」
「ああ、知ってる! 自分の手は汚さず取り巻きを使ってたんでしょ?」
「性格わっる〜!」
耳に届いた陰口に、思わず溜息を零してしまいそうになる。
私、笹山響は。
高校入学してすぐにデタラメな噂のせいで孤立している。
噂上の私は、人の彼氏を略奪しては何股もかけたり、気に入らない子を手を汚さずに虐める悪逆非道な人間らしい。
初めは違うと潔白を主張したけど、誰も信じてくれず、悪評は尾びれが付いて酷くなるばかりだ。
真っ暗な気分を抱いて教室に入ると談笑して賑わっていたクラスメイト達の声が静まり、私に視線が向けられる。
その視線から逃れるように、そそくさと自分の席へ向かった。
次の授業まであと十五分。教科書を眺めながら、昼休みが早く終われと祈っている。
私と同じ列の前方に視線を向けると、一人の女の子がクラスメイトに囲まれてお喋りをしていた。
桐谷真菜さん。
クラスメイトで私が個人的に理想としている女の子だ。
一五〇センチと小柄で、ぱっちりな丸っこい瞳、ピンク色の唇。ふんわりしたミルクティーブラウンのボブヘアー。
彼女はまるで大好きな恋愛小説のヒロイン像そのものだ。
実際、かなりの美少女で朗らかな性格で、男女問わず人気者だ。
対する私は一六七センチ、少し目尻が上がった瞳、パーマがかからない真っ直ぐな黒髪のショートボブ。
実年齢より少し上に見られ、気が強い、もしくは冷たい性格と思われがちだ。
恋愛小説に例えるなら、私はヒロインの恋路を邪魔するライバルだ。
噂上の私は邪魔どころか略奪しているけど。
本当の私は、他の男子なんか微塵も興味がないのに……。
放課後、甘いものを食べに行こうかな……。
私は現実逃避を始め、頭の中で放課後の計画を立てていた。
甘いものは大好き。
食べるもの、作るのも。
孤立する前の中学時代は、よく作ってはクラスメイトと食べていたり、放課後、一緒にカフェに寄ってお喋りをしながらスイーツを堪能した。
今はすっかりおひとり様も慣れてしまった。
カフェに限るけれどね。
せめてだれかと共有したくて、青い鳥のSNSに撮ったスイーツの画像を投稿している。
作ったお菓子も投稿すると、ありがたいことにいいねや「美味しそう」と言ったコメントを頂いたり。
何にしようかなぁ。
フロマージュにしようかな。それともパフェにしようかな。
何を食べようか考えていると、少しだけ憂鬱な気分は消えて楽しさが出てきた。
この時の私は知らなかった。
運命的な出会いを果たすことになるなんて────
実年齢より少し上に見られ、気が強い、もしくは冷たい性格と思われがちだ。
恋愛小説に例えるなら、私はヒロインの恋路を邪魔するライバルだ。
噂上の私は邪魔どころか略奪しているけど。
本当の私は、他の男子なんか微塵も興味がないのに……。
放課後、甘いものを食べに行こうかな……。
私は現実逃避を始め、頭の中で放課後の計画を立てていた。
甘いものは大好き。
食べるもの、作るのも。
孤立する前の中学時代は、よく作ってはクラスメイトと食べていたり、放課後、一緒にカフェに寄ってお喋りをしながらスイーツを堪能した。
今はすっかりおひとり様も慣れてしまった。
カフェに限るけれどね。
せめてだれかと共有したくて、青い鳥のSNSに撮ったスイーツの画像を投稿している。
作ったお菓子も投稿すると、ありがたいことにいいねや「美味しそう」と言ったコメントを頂いたり。
何にしようかなぁ。
フロマージュにしようかな。それともパフェにしようかな。
何を食べようか考えていると、少しだけ憂鬱な気分は消えて楽しさが出てきた。
この時の私は知らなかった。
運命的な出会いを果たすことになるなんて────
憂鬱な授業を終えて、待ちに待った放課後がやって来た。
部活動に入っていない。
保健委員会に入っていて、時々集まりや活動に参加するくらい。
爪弾きされている私は、どこにいたって針のむしろに座らされるんだから。
学校を出て、久し振りにお気に入りのカフェを目指すことに決めた。
担任の先生に捕まると、雑用を押し付け……頼まれるので、目立たないようにそそくさと教室を後にした。
目当てのカフェは、学校と自宅の中間に位置している。
学校の最寄り駅から二つ目の駅から降りて、十分程歩く。
スイーツは後でゆっくり決めるとして、飲み物は冷たい紅茶? 甘いカフェラテ? ハーブティーもいいな。
そんなことを考えながらわくわくしながら歩いていた時だった。
「ねえ、あんたが笹山響?」
誰?
私に近寄り声を掛けてきたのは、知らない三人の他校の女の子だった。
自分が通う誠稜高校では見られない膝上二十センチほどの短いスカートを履いてる。
シャツはガッツリ開いていて目のやり場に困ってしまう。
声を掛けた一人の女の子は、眉を寄せて私に睨み付けている。
「黙ってないで返事しなよ!」
立ち尽くす私に苛立ったのか、声を荒らげる。
「そう、です……」
慌てて頷くと、彼女達は「着いてきて」と言って私をどこかへ連れて行った。
部活動に入っていない。
保健委員会に入っていて、時々集まりや活動に参加するくらい。
爪弾きされている私は、どこにいたって針のむしろに座らされるんだから。
学校を出て、久し振りにお気に入りのカフェを目指すことに決めた。
担任の先生に捕まると、雑用を押し付け……頼まれるので、目立たないようにそそくさと教室を後にした。
目当てのカフェは、学校と自宅の中間に位置している。
学校の最寄り駅から二つ目の駅から降りて、十分程歩く。
スイーツは後でゆっくり決めるとして、飲み物は冷たい紅茶? 甘いカフェラテ? ハーブティーもいいな。
そんなことを考えながらわくわくしながら歩いていた時だった。
「ねえ、あんたが笹山響?」
誰?
私に近寄り声を掛けてきたのは、知らない三人の他校の女の子だった。
自分が通う誠稜高校では見られない膝上二十センチほどの短いスカートを履いてる。
シャツはガッツリ開いていて目のやり場に困ってしまう。
声を掛けた一人の女の子は、眉を寄せて私に睨み付けている。
「黙ってないで返事しなよ!」
立ち尽くす私に苛立ったのか、声を荒らげる。
「そう、です……」
慌てて頷くと、彼女達は「着いてきて」と言って私をどこかへ連れて行った。
辿り着いた先は、大通りから外れた人っけのない細い路地裏だった。
私は、彼女達になにか恨まれるようなことをした記憶はない、はず……。
金に近い明るい髪を靡かせる彼女は
「あんたのせいでアタシ振られたんだけど! どう責任取ってくれるの!?」
「人の彼氏を誑かすなんてどういう神経してるの?」
誑かした記憶はないです。
だって、あなたの彼氏と話したことも無ければ顔も知らないんだから。
「誑かした? 私はその人を知りません」
誤解に違いない、話せば分かるよ。
詳しく聞かせてください。
なるべく彼女を刺激しないように穏便に答え、尋ねるつもりだったけど。
「しらばっくれるなよ!」
どう答えても導火線に火がついてしまったみたい。
激昂した彼女に思い切り頬をぶたれていた。
鮮やかに彩られた長い爪が頬に引っかかって痛みが走っている。
「あー傷付いちゃった!」
「もっとやっちゃえって!」
彼女のお友達だろう二人は囃し立てるように大声をあげている。
彼女は私の胸倉を掴み、背後にあるフェンスに思い切り押し付けた。
殺意に似た憎しみを込めた眼差しを向けられて、ぞくりと背すじが凍るのを感じた。
手先が少し震えている。
そして、彼女は右手を思い切り振り上げた。
あ、殴られる……っ!
私は瞼を閉ざすことなく、これから来る痛みを覚悟した。
私は、彼女達になにか恨まれるようなことをした記憶はない、はず……。
金に近い明るい髪を靡かせる彼女は
「あんたのせいでアタシ振られたんだけど! どう責任取ってくれるの!?」
「人の彼氏を誑かすなんてどういう神経してるの?」
誑かした記憶はないです。
だって、あなたの彼氏と話したことも無ければ顔も知らないんだから。
「誑かした? 私はその人を知りません」
誤解に違いない、話せば分かるよ。
詳しく聞かせてください。
なるべく彼女を刺激しないように穏便に答え、尋ねるつもりだったけど。
「しらばっくれるなよ!」
どう答えても導火線に火がついてしまったみたい。
激昂した彼女に思い切り頬をぶたれていた。
鮮やかに彩られた長い爪が頬に引っかかって痛みが走っている。
「あー傷付いちゃった!」
「もっとやっちゃえって!」
彼女のお友達だろう二人は囃し立てるように大声をあげている。
彼女は私の胸倉を掴み、背後にあるフェンスに思い切り押し付けた。
殺意に似た憎しみを込めた眼差しを向けられて、ぞくりと背すじが凍るのを感じた。
手先が少し震えている。
そして、彼女は右手を思い切り振り上げた。
あ、殴られる……っ!
私は瞼を閉ざすことなく、これから来る痛みを覚悟した。
頬に走る痛みはいつまで経ってもくることはなかった。
彼女の背後から、背の高い男の人が振り下ろそうとした右手を掴んでいたから。
「痛い! 痛いいいーっ!」
ううん、掴んだというか捻り上げているが正しいかもしれない。
金髪の女の子は痛そうに眉をひそめて金切り声のような悲鳴を上げている。
私は目の前で繰り広げられている光景を飲み込むことが出来ず、呆然となっていた。
男の人はすぐに掴んだ腕を離した。
「強く掴んでごめんね。この子、俺の親戚なんだよ。だからこういう真似は辞めて欲しいな」
柔和な声音で謝る彼に、三人の女の子達はぼーっと見とれていた。
私も同じ状態になっていた。
だって……私は彼を知っている。
栗色の柔らかそうなショートヘア、私と彼女達に向けている大きなアーモンド形の双眸は澄んだ琥珀色。
王子様みたいに稀なほど整った甘めの顔立ちも、物腰柔らかな声も、ずっと前から忘れることなく覚えている。
……これは夢ですか?
「ごめんなさーい。私らちょっと喧嘩しただけなんですー」
彼女達は先程とは打って変わって笑顔で腰を低くしながらその場から去って行った。
彼女達が居なくなって、彼と二人きりになった時、私の体は脱力してへなへなと座り込んでしまった。
この体の震えは先程の恐怖からだろうか。
彼と遭遇したことによる緊張から来るものだろうか。
とりあえず、お礼を言わなきゃ。
「ありがとう、ございました……」
震えた情けない声だった。目がじーんと熱くなっている。
頬を伝ったのは、涙が汗か、私には判別が付かなかった。
「立てそう?」
そう言われて立ち上がろうとするけれど、足に力が入らず立ち上がることが出来なかった。
そんな私に彼は手差しのべた。
私は緊張しながら手を伸ばし、彼の手を握った。
とても大きな手。
あの頃と変わらない……。
私は当時のことを思い出してしまい、高鳴る鼓動を自覚した。
「すみません……」
「結構血が出てる。痕が残るといけないから今から病院に行こう」
「あの……」
頬に伝っていたのは涙や汗でもなく血だったんだ……。
思っていたより引っ掻き傷は酷かったみたい。
女の子の爪は結構鋭かったなぁ……でも、お洒落だったなぁ。
私の爪なんて、お菓子作りをするから常に短くてなにも塗られていない。
……女子力が低いや。
そうやってあさっての方向な思考をしていると、彼にぐいっと手を引かれていた。
まだ繋がれている!?
繋がれたままの手に、私の脳内は混乱していた。
大丈夫だと振りほどこうとしてもしっかり繋がれていて、病院に辿り着くまでその手が離れることはなかった。
彼の後ろ姿を見ていると、身長の高さに驚かされる。
私も平均より高めだというのに私より十五センチくらいは高そうだ。
駆け込んだ午後の病院で、診察と手当を受けた。
頬の傷は痕が残ることはないだろうと診断された。
万が一残れば形成外科を紹介してくれると言ってくれた。
そう言われて立ち上がろうとするけれど、足に力が入らず立ち上がることが出来なかった。
そんな私に彼は手差しのべた。
私は緊張しながら手を伸ばし、彼の手を握った。
とても大きな手。
あの頃と変わらない……。
私は当時のことを思い出してしまい、高鳴る鼓動を自覚した。
「すみません……」
「結構血が出てる。痕が残るといけないから今から病院に行こう」
「あの……」
頬に伝っていたのは涙や汗でもなく血だったんだ……。
思っていたより引っ掻き傷は酷かったみたい。
女の子の爪は結構鋭かったなぁ……でも、お洒落だったなぁ。
私の爪なんて、お菓子作りをするから常に短くてなにも塗られていない。
……女子力が低いや。
そうやってあさっての方向な思考をしていると、彼にぐいっと手を引かれていた。
まだ繋がれている!?
繋がれたままの手に、私の脳内は混乱していた。
大丈夫だと振りほどこうとしてもしっかり繋がれていて、病院に辿り着くまでその手が離れることはなかった。
彼の後ろ姿を見ていると、身長の高さに驚かされる。
私も平均より高めだというのに私より十五センチくらいは高そうだ。
駆け込んだ午後の病院で、診察と手当を受けた。
頬の傷は痕が残ることはないだろうと診断された。
万が一残れば形成外科を紹介してくれると言ってくれた。
診察室を出て、待合室のソファーで待つ彼に話しかけた。
「傷は多分消えるそうです。万が一残ったらいい形成外科を紹介してくれると言っていました」
「消えるといいね」
頬にテープで留められているガーゼを一瞥した彼の表情は、不安げに見えた。
気にしなくてもいいのに。
むしろ、助けてくれなかったらもっと酷い状態になっていたかもしれない。
あの女の子は相当私を恨んでいたようだった。
会計を済ませた頃には、待合室は診察待ちの人でいっぱいになっていた。
私と彼は病院を後にすることに。
こっそりと彼の横顔を盗み見る。
私が隣に並ぶことが烏滸がましいほどの綺麗な顔立ちをしている。
不意に何か考え事を始めたのか真剣な顔付きに変わり、胸の中がぎゅっと締め付けられた。
あの頃のように、ううん、それ以上に格好いい。
惜しむらくは、私のことを覚えていないことだ。
私はあの頃より十センチ以上背が伸びているから無理もないと思う。
「あの……」
私は邪魔にならないか不安になりながら、声を掛けた。
私の声に気付き、琥珀色の双眸を私に向ける。また鼓動が高鳴ったけど、平静を装ってみせる。
「見ず知らずなのに助けて頂いてありがとうございました」
「あんなに怖がっていたら放って置けないよ」
「……助かりました」
私は彼を一瞥すると、目を伏せた。
「良かったら駅前まで送ろうか? あの人達、近くにいてまた絡まれるかも知れない」
まだ一緒にいてくれるの?
予想外の申し出に私は動揺してしまい、辺りをきょろきょろと視線をさまよわせしまった。
どう見ても挙動不審の怪しい女です……。
私を覚えていなくても、関わるのがこれっきりだとしても、少しでも一緒にいたくて。
「お願いします……」
小さい声だったけど、厚意に甘えることにしたの。
駅まで向かう間無言だった。
まあ、話したくても私が緊張しているせいだけどね。私はヘタレです。
噂上の私か、桐谷さんならもっと上手に会話が出来たんだろうな……。
けれど、不思議と居心地は悪くなかった。
もう少しこうしていたいと願わずにいられなかったけれど、駅はあっという間に着いてしまった。
ああ、これっきりか……。
私は彼と別れることに残念な気持ちでいっぱいだった。
「ありがとうございました。さようなら」
ぎこちないながらもお礼を告げ、駅構内に入って改札口を通り抜けた。
電車に乗り、空いていたロングシートに腰掛けては、ため息をついた。
緊張した……。
今でも心臓が暴れている。
もしかすると、神様が私を哀れんで会わせてくれたのかもしれない。
少しだけ言葉を交わした日の思い出があれば、憂鬱な学校もしばらく頑張れそう……。
まだ、心臓がドキドキしてる。
「小説読もうっと」
私は緊張を紛らわせようと、リュックサックのサイドポケットを探りスマートフォンを取り出そうとした。
……あれ?
あるはずのスマートフォンが見当たらない。
私、落としちゃったの?
反対側のサイドポケットやリュックサックの中身も探ってみたけれど、一向に見つからなかった。
私のばか! 高校に入学した時に買ってもらったばかりなのに!
うっかりどこかに落とした自分が間抜けで情けなくて仕方ない。
友達は寂しいことにゼロだから連絡に困ることはないけど……。
暇つぶしでウェブ小説を読んだり、SNSでお菓子の画像を投稿したり……あと、愚痴を零すのに欠かせないのだ。
駅か病院のどこかで落としたのかもしれない。
私はがっくしと項垂れながら、帰ったら家の電話から問い合わせようと心の中で決めた。
この作家の他の作品
表紙を見る
初めての恋は
ただ甘くて
あたしの心臓を
壊していくのです
※一話完結、三人称です
完結
2017.8.31
表紙を見る
ずっと離ればなれだった初恋のいとこと
私の家で一緒に住むことになりました
かっこよくて、クールで
近寄りがたくなったと思ったけど…
「あと、ごふんだけ……」
寝ぼけまなこできつく抱き締めたり
「絢芽を一人で帰らせるなんてむり」
ぎゅっと繋いだ手を離してくれなかったり
いとこだから諦めなきゃだめなのに
甘すぎて“好き”がどんどん大きくなっちゃうよ
立花 伊織(たちばな いおり)
クールだけど、絢芽にだけ甘えたなイケメン
×
葦名 絢芽(あしな あやめ)
引っ込み思案だけど癒し系な美少女
「わたしのこと、きらわ、ないで……」
この恋は禁忌?
「絢芽のぜんぶ、受け止めるよ」
それとも…?
ちょっぴりこじれた
ピュアで極甘なおはなし
表紙を見る
エアラブに投稿した掌編のまとめです。
※付いているタイトルはヤンデレ要素があります。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…