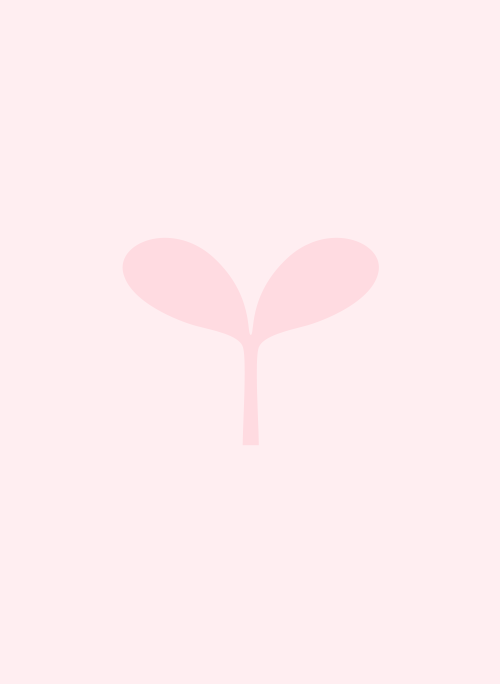この作家の他の作品
表紙を見る
日が経つにつれて、子どもたちは、体も心もだんだん成長していった。これまではぼくと妻猫がいつもそばについていて、しっかり守ってあげなければならなかったが、これからは誰かいい友だちを見つけて、友だちとの交流の中から、立派な成猫となれるような性格形成を自分でおこなっていかなければならない。
ぼくたちが住んでいる翠湖公園の中には、公園の近くに住んでいる猫たちがたくさん集まってくる場所があり、うちの子どもたちも気が合う友だちを見つけようと思って、毎日その場所に出かけていって、いろいろな猫と交流していた。でもまだ、心から好きになれるような友だちには出会えないでいる。
秋が深まり、木々の葉が風にひらひらと舞うころ、一番下の子どものサンパオが、この公園から出ていって、猫ではなくて黒騎士と呼ばれるラブラドル・レトリバー犬を探して、友だちになりたいと急に言い出した。唐突な考えに、ぼくはびっくりした。しかし災害救助犬として、これまで大活躍してきた黒騎士を探して、友だちになることができたら、サンパオの性格形成においてプラスになるだろうと思ったので、ぼくは力を貸すことにした。サンパオだけで探しに行かせることには不安を感じたので、ぼくはサンパオに付き添って、一緒に行くことにした。ぼくの友だちである老いらくさんも、一緒についてきてくれることになった。老いらくさんはネズミだが、思慮に富んでいて、適切な助言を与えてくれることが多いので、心強く思った。家をしばらく留守にすることになるが、パントーとアーヤーのことは妻猫がきちんと面倒をみてくれるだろう。
サンパオの決意を聞いてからまもまく、ぼくとサンパオは、家族にしばしの別れを告げて旅に出た。老いらくさんもスイカボールの中に入って転がりながらついてきた。
道中、いろいろなラブラドル・レトリバー犬と出会った。いい犬もいれば、悪い犬もいた。黒騎士ではないかと思われるような犬もいた。外見とは裏腹に、心の中は陰険で恐ろしい犬もいた。ぼくがそばにいなかったら、純粋で疑うことを知らないサンパオは、うっかりして悪い犬にだまされて、狡猾なわなにはまっていたかもしれない。何度も何度も期待と失望を繰り返しながら、ぼくたちは、町の郊外を方々、探し回った。そしてついに、ある日ようやく黒騎士と出会うことができた。災害救助犬として活躍していた黒騎士は今は盲導犬として活躍していた。
表紙を見る
黄色く色づいたイチョウの葉が、ひらひらと地に舞って、秋が深まってきたころ、子猫のアーヤーの心のなかに、ひそかな願いが生じた。
(言葉が話せない障害者のおじいさんを手伝って新聞を売ってあげよう)
アーヤーはそう思ったので、人の声真似ができる九官鳥を訪ねて行った。昼も夜も練習を重ねて、アーヤーはついに人の声真似ができるようになった。
「人民日報、ローカル新聞、ビジネス新聞」
新聞を売る猫を見て、町の人たちはびっくりして、町じゅうの話題となった。
その年も暮れてクリスマスイブの日。アーヤーは夜寝ているときに、不思議な夢を見た。夢のなかにサンタクロースが現れて、アーヤーを病院に連れて行った。病院のなかには、
植物人間となって、こんこんと眠っている人がいた。そのそばには七歳ぐらいの女の子がいて、植物人間に歌を歌ってあげていた。……
アーヤーが見た夢の内容は、このようなものだった。
夢からさめたアーヤーは自分も心に響く歌を歌って、意識を失っている人の意識を取り戻してあげたいと思うようになった。
九官鳥に歌い方を習って、血のにじむような練習を毎日おこなったアーヤーは、のどを痛めてしまった。それでもアーヤーはめげないで歌の練習に励んだ。それからまもなく、町の郊外にある病院のなかから、深夜になると、『鲁冰花(ルピナス)の花』という歌が聞こえてくるようになった。哀愁にみちた旋律は、たゆたうように病棟のなかを流れていった。まるで天使が歌っているかのように優しくてきれいな歌声だった。
表紙を見る
佐倉かおり。母が脳卒中で倒れたのを機に、25歳のときに高校教師の仕事を辞めて、長崎の自宅に帰り、15年近く母の介護をしていた。ひきこもり的な性格ではなかったが、高校教師を辞めたときに、周囲からは「もったいない」と言われて誰からも理解されず、変わり者とみなされて孤立無援の状態になった。周囲の冷たい視線に耐えられなくなったかおりは、母の介護の傍ら、アルバイトをすることを思い立ったが、どこに面接に行っても、ことごとく、はねられ、そのため、やむをえず、母の年金で生活させてもらっていた。年が上がるにつれて、日々の生活に虚しさを感じたり、このような生活でいいのだろうかと思って、これからの生き方を模索するようになった。39歳のときに母が永眠し、日本ではもう生活できないと思ったかおりは、一念発起して中国へ行き、長沙、南京、ハルピンの高校や大学で日本語を教えるようになった。日本では母以外の人から必要とされなかった喜びを中国に来て感じることができるようになったかおりは、日々充実した生活を送っていた。結婚してほしいという男性も現れた。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…
この作品をシェア
宇宙からきた子
を読み込んでいます