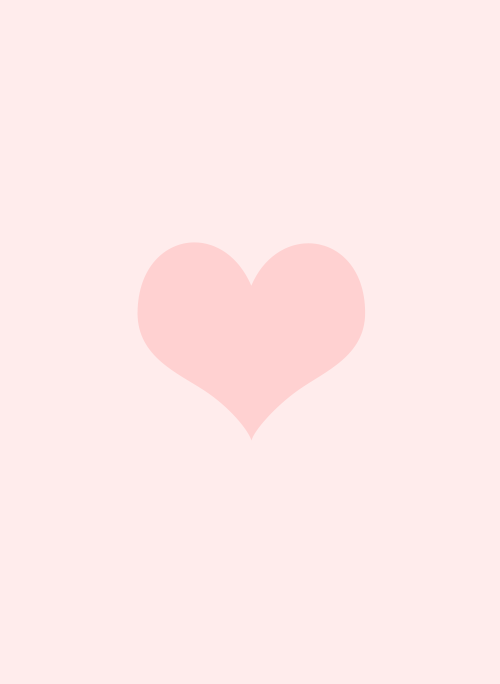「あははは、ごめんね、急に話しかけて。
びっくりしちゃったよね」
驚いた。
話しかけられたときはとても驚いたが、今の反応の方が数倍も衝撃が強かった。
初見で私の言動に笑った人は、この人が初めてだった。
私に対する反応の種類は、敵意を表すか、そそくさと離れていく人がほとんどだから。
たまに、笑顔を崩さない人はいるけど、こんなに無邪気に私の前で笑った人はいない。
そして、その無邪気な笑顔を崩さずに先輩は話し続けた。
「いやね、近くを通りがかったらおいしそうな弁当食べてるなって思ってさ。
いつもここで食べてんの?」
何とも不思議な理由で話しかけてくる人だと思った。
弁当がおいしそうという理由で話しかけてくる人がいるんだろうか。
今までない話しかけられ方と、人見知りが相まって怖さが倍増した。
何で私なんかに話しかけてくるんだろう、この人。
早くどっか行ってくれないかな。
「そうだとしても、先輩に関係あるんですか?
特に用ないなら話しかけないでもらえますか」
先輩はまた、無邪気に笑った。
さっきは驚いたが、改めて考えるとなんで笑っているのかに心当たりがなく、ここまでくるとほんとに怖い。
「怖がらせてごめんね、僕2年の東堂洸っていうんだ。
よろしく。名前覚えてくれると嬉しいな」
なんだろう、この、人の話を聞かない系のコミュ力お化けは。
変な人過ぎて、恐怖が一周回って冷静になってくる。
そこでふと思った。
あれ、もしかしてここでお昼食べたいのかな?と。
晴れの日はだいたい私がここ使っちゃってるし。
教室にいるといたたまれなくてここに来てるけど、ここ使いたいなら譲ろうかな。
ここ快適だから好きだけど、私だけの場所じゃないし。
広げていたお弁当をパパッと畳み、この場から去る準備する。
「もしかしてここ使いたいんですか?
だったら私、違うところで食べるので失礼します」
立ち上がり、この場から離れようとしたら、後ろからパッと腕をつかまれた。
「待って!」
「っ……!」
家族以外の他人から触られることが、小学生の集団下校から止まっている私は、その腕をとっさに振りほどいた。
「あ……急につかんでごめんね。びっくりしちゃったよね」
ずっと笑顔を崩さなかった顔が初めて変わり少し焦りを含む。
「ただ、君と仲良くなりたかっただけなんだ。
……嫌な思いさせたならごめん。
君はこのままここでお昼食べて、僕もう行くから」
今度は、先輩が立ち上がり私に背を向けて歩き出した。
去っていく後ろ姿に、なんとなく哀愁を感じた。
『仲良くなりたかった』
その言葉が頭の中をこだまする。
それは今まで生きてきて言われたことのない言葉だった。
そっか、私と仲良くなりたかったのか……そっか……。
『仲良くなりたい』
それは、私が今までいろんな人に言いたくて言えなかった言葉。
今まで他人から言われた言葉の代表例は、睨まれたとか酷いこと言われたとかだった私には、こそばゆくて、なんだか嬉しい。
他人から言われると嬉しいものなんだな。
「仲良くなりたかった……」
自分にだけ聞こえる声で、つぶやいた。
さっきまで怖かったのに、今は温かい気持ちでいっぱいだった。
言われたかった言葉を言ってもらえて、自分の顔が少し緩んでいくのが分かる。
今までに経験ない温かい感情に夢中になっていた私は、歩き去っていく後ろ姿が止まって振り返ったことに気付かなかった。
「あのさ」と話しかけられて初めて気づく。
緩んでいた頬は瞬時に引き締まり、いつもの無表情に戻った。
「君さえよければまた……ここで、話しかけていいかな?」
今までとは違い、こちらに選択権を与えている言い方だった。
そして、まるで懇願が含まれているような言い方だった。
「お、お好きに」
いつもなら嫌と言っていたかもしれないが、少し緩んでいたのと先輩の様子とで珍しく、鋭い言い方にはならなかった。
かといって、柔らかい言い方でもないのだが。
私の返事を聞くと先輩は破顔して笑った。
「ありがとう!
じゃあ、明日晴れたらまたここに来るね! 」
急な破顔に驚いて、反射的に頷いてしまった。
先輩は言いたいことを言い切ったのか、そそくさといなくなってしまった。
あした、また、か。
ん?明日?
「明日!?」
珍しい自分の大きな声が、耳と辺りに響いた。
自分の見た目の良さを自覚したのは、小学生の頃だった。
確かに小さい頃から良くかわいがってもらえているという印象はあったが、異性にモテ始めたのは小学校中学年くらいの時からで、その頃から女子がよく周りにいた。
望んでもないのに、周りにいつも女子が侍るのにうんざりしたのは思春期の中学二年。
その頃から、一人になる時間がほしくて、空き教室や人目につかないところで休むのが習慣になった。
そして、その習慣は高校に入学してからも続いた。
その場所を見つけたのは、入学して一か月半がたった頃だった。
校舎からは死角になっていて、かつ日の当たる場所。
すぐ近くの倉庫のような建物の裏にはベンチが置いてあるが、そこは校舎から少し見えてしまう。
この快適な場所に人が集まってしまう可能性を避けたかったのと、日陰よりも日向の方が僕には心地よかったことからベンチではなく、コンクリートに直接腰を下ろしている。
まあ、野外だから年中快適とは言えない。
夏は、周りに木など緑がたくさん生えているから虫が出るし蚊にも刺される。
そんで、コンクリートだから太陽光に熱せられて熱くなる。
もちろん冬の野外は寒くて快適とは言えない。
春などちょうどいい時期にはその場所は僕にとって最高の場所だ。
高校2年になっても、天気が良くてちょうどいいときにはこの場所に通っている。
その日も、春になり程よい温かさが心地よくてごろごろしていた。
遠くから聞こえる生徒の笑い声や鳥の鳴き声など、静かだからこそ心地よく感じるこの場所に、足音が近づいていると気づいた。
その足跡は、僕と倉庫を挟んだ反対側で止まった。
あのベンチが置いてある方だ。
「え、ここにベンチがあるんだ。
静かで落ち着く場所だなぁ。今日はここで食べよう」
その声にドキリとする。
高めの声で、明らかに女子の声だ。
自分だけの場所ではないのは分かっているが、自分のお気に入りの場所を害されたような気持になり、心の中で舌打ちをした。
しかも、女子から逃げたくてこの場所を見つけたのに、その元凶の女子にこのお気に入りの場所を見つけられてしまったのだからたまったもんじゃない。
ああ早くどこか行ってくれないか。
または、僕がどこかへ行きたい。
でもここから立ち去るにしても、移動するには彼女に僕の存在を知られてしまうしなぁ。
この場所が気に入ったなら、明日もこの子は来るのだろうか。
ああもうこの場所に来るのやめようかな。
などと悪態ついていた僕の思考を止めたのは、裏側のベンチに座っているであろう“顔も知らない女子”だった。
「どうしたら友達ってできるのぉぉぉおお……!」
我慢していた思いを吐き出すように、そして唸るように言うのを聞いて、思わず吹き出しそうになった。
吹き出さずに、我慢できた僕をほめてほしい。
「高校に入ったら友達頑張って作ろうって思っていたのに……!」
“顔も知らない女子“のため込んでいたであろう独り言は止まらない。
「ああ、せっかく話しかけてくれたのに!
せっかく話しかけてくれたのにぃぃぃ……!
あんな言い方したら誰だって『あ、この子とは関わるのやめよう。顔も怖いし』
って思うに決まっているじゃない!
緊張すると言葉の選択が辛辣になるの直したいっ……!!」
悲痛な思いがあって言っているのは分かる。
分かるが……。
今までこんなに切実に自分の思いを吐き出している人は、見たことが(正確には聞いたことだが)なかったから、他人の何も取り繕っていない願望を聞くことはこれほど面白いとは思わなかった。
セリフのようなところは声色を変えて話すのが、さらに面白くて必死に笑い声を抑える。
ああどうしよう!
腹筋が痛すぎてどうにかなりそう。
さっきとは違う意味でどこかへ行ってほしい。
「違うの!
私はただ仲良くなりたくて、見てただけなの。
『あ、そのキャラクターかわいいよね』って言いたかっただけなのに、
私の目つきが悪いせいで『あ、うるさかった? ごめんね』って謝らせちゃったぁ。
いや、せめて、その後に『んーん。そのキャラクターかわいいよね』って言えていればっ……」
ごめん。
さっき『早くどっか行って』って思ったの謝るから、もう許して。
笑いすぎて、お腹苦しくてちょっと痙攣起こしてるから。
この後も“友達が欲しい女子“は、どうして自分には友達ができないのか、
そして、どうしたら友達ができるのかを一人で話しながら、
おそらく弁当を食べ終え「友達が欲しい……!」という切実な思いのこもった言葉を残して去っていった。
“友達が欲しい女子”がいた時間は20分くらいだったが、終始笑うのをこらえていて、僕の腹は限界突破をしていた。
その子が立ち去るときに、痛い腹を必死に抑えながら、去っていく後ろ姿を見た。
肩よりも少し長い黒髪で、きれいなストレート。
言っていた言葉には自信のなさを感じたが、歩く姿は背筋がピンとしていて、
先ほどまで「友達が欲しい」と言っていた人物とは思えないほどの気品を感じた。
後ろ姿からは学年などは分からないが、
「高校に入ったら友達頑張って作ろうって思っていたのに……!」
と言っていたことから、新入生だろう。
今まで、僕の周りには自分を取り繕って、僕に気に入られようと寄ってくる女子ばかりだったから、「友達が欲しい」と切実に思うあの子は、まぶしいくらいだった。
あの子は明日もここに来るのだろうか。
先ほどまで、自分の気に入っている場所を壊されると悪態ついていたにもかかわらず、明日も来てほしいと願っている自分に驚いた。
そして、特定の人と会うのを楽しみにするという感情も初めてだった。
明日も、今日のようにいい天気だといいな。
そうすれば、あの子も来てくれるかもしれない。
ほのかな期待とともに、午後の授業を受けるべく教室に向かった。
次の日。
この日も、春らしい日和で、外で過ごすにはちょうどいい日だった。
今は、お腹のすく4時間目の半ば。
今日の数学の授業は、急遽自習の時間になっていた。
先生が急な出張らしい。
僕は午前中の授業の内容が全く頭に入らない状態だった。
なぜなら、1つのことをずっと考えていたから。
……あの子は今日も来るのかな?
今日は昨日と同じく良い天気だから、昨日あの子があの場所を気に入ったのなら来るかもしれない。
昼休みになったらすぐにいつもの場所へ行こう。
来るとははっきりしていないのに、勝手に待つなんてバカみたいだ。
バカみたいと思っているのに待ちたいと思ってしまうのは、昨日のあの子の言葉が耳から離れないからだろうか。
ぼうっと考えていると、僕の前の席に座る友達が話しかけてきた。
「なあなあ、さっき聞いたんだけど一年に美人な子いるらしい!
ちょっと近寄りがたい雰囲気あって、高値の花って感じなんだってー!
見てみたくね!?」
目をキラキラさせながら話しかけてくる友人。
コミュ力が高く多くの友達がいるこの友人は、またどこかから情報を仕入れてきたらしい。
特にその美人に対して興味のない僕は、「別に」と即答で返した。
「クッソ~イケメンはこれだから!
僕は女に困ってないってか?
嫌味か、嫌味なのか!」
悔しそうに顔を歪めて、僕を睨みつけながら言う。
僕をねめつけていたと思ったら、その表情から一転あきれ顔になり、「でも」と続けた。
この作家の他の作品
表紙を見る
幼なじみの美咲と亮。
赤ちゃんの頃から一緒で、家族ぐるみの仲。
優しくて可愛い
そんな亮が美咲は好きだった。
亮が小学校4年生の時に転校してから
初恋の思いはずっと残ってるものの
疎遠になってしまった。
……………………
高2の春。
初恋の人が戻ってきた!
「美咲ちゃん久しぶり」
……いや、誰?!
目の前に現れたのは昔の面影を全く残さない
暗い系イモ男子!
いやいや、なにがどうしてそうなったわけ?!
昔と全く違うあいつにもう恋心なんて微塵も感じない!
って思ってるのに……
「美咲ちゃん、綺麗になったね」
「なんで待たなかったんだ……!」
「心配した……」
こんなやつに何も感じないはずなのに
なんでこんなに胸が高鳴るんだろ……
……………………
イモ男子なのに時々見せる昔の面影と
昔とは違う力強い男子の片鱗。
……あいつには何やら裏がありそうです……
....................................
4作品目!
ラブコメです。
楽しんで読んでいただけたら幸いです!
書式が途中から変わったりしてます。
読みづらかったらすみません!
表紙を見る
小さな頃から一緒にいる2人。
でもその2人は
宮原千紗(ミヤハラ チサ)
→高身長女子(171cm)
×
高城陽介(タカギ ヨウスケ)
→低身長男子(161cm)
まさかの身長差逆!?
いっぷう変わったラブストーリー!
この身長差の恋
ヤミツキになるかも!?
3作品目!!
2019.6.4
“野いちご編集部オススメ小説”に掲載していただけました!
ありがとうございますっ
もう、感謝感謝です!!
これからもよろしくお願いします。
表紙を見る
高2の春、好きな人ができた。
運命の人であればいいと初めて思った人。
あなたが私の幸せ。
……でも好きになった人は親友の元彼だった。
そして、まだ親友を想っている。
私にとっての幸せをとるか
あなたにとっての幸せをとるか
さぁどっちをとる?
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…