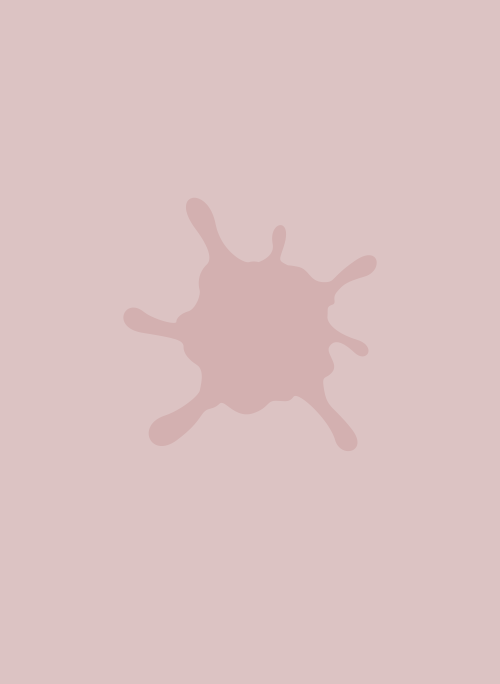更に。
「それにさー、あいつら。あの『帝国の光』って」
「ん?」
「皆平等〜とか言いながら、あれ…白い塔造ろうとしてるんだろ?」
あぁ、『白亜の塔』な。
「そんなもんで平等になって、皆喜ぶと思ってんのかね?」
「…さぁ…」
少なくとも、シェルドニア王国の人々は、皆幸せそうだが。
それが本当の幸せなのかどうかは、分からないな。
偽りだろうが、押し付けられたものだろうが、本人が幸せだと感じているなら、それは本物の幸せだ、と。
そう考えることも出来るし、偽物でも良いから幸福感を感じたいと思う人は、大勢いるだろう。
その証拠に裏社会では、そういった類の薬物が、いくらでも横行している。
手に入れた幸せが、自分の力で手にしたのではなくても。
それを自分が幸福と感じるなら、それで良い。
分からなくはない。
少なくとも、不幸であるよりずっとマシだろう。
「変な電波でアヘ顔晒すくらいなら、ゴキブリ生活してた方がよっぽどマシだぜ」
…まぁ、アリューシャみたいな考え方の人間もいる。
こればかりは、人の価値基準によって様々だろうな。
ヒイラは分かっているのだろうか。アリューシャみたいな考え方の人間もいるんだってこと。
いくら貧しいからって、そんな救われ方をされたいと、誰もが望むと思っているのだろうか。
幸福であれば、その形が何であろうと構わないのだろうか。
それともお前は、本当は平等な世の中なんて、どうでも良くて…。
…と、そこまで考えていると。
「ふわぁ〜…。ルル公が難しい話ばっかするから、アリューシャ眠くなってきたよ」
そう言って、アリューシャはばふっ、とベッドに大の字に寝そべった。
「あ、うん。いきなり変なこと聞いて悪かっ…」
「…zzz…」
「…寝てるし…」
早くね?
最後に会話してから、今、10秒もたってなかったんだけど?
しかも。
「毛布かけろよ、馬鹿…」
アリューシャが掛け布団なしで寝ようが、床で寝ようが、好きにすれば良いが。
そのせいでアリューシャが風邪を引いたら、俺がアイズに責められそうなので。
仕方なく、へそ出して寝てるアリューシャの上に、毛布をかけてやったのだった。
その無邪気な寝顔は、決してゴキブリなどと罵るようなものではなかった。
…良い夢見ろよ、アリューシャ。
「それにさー、あいつら。あの『帝国の光』って」
「ん?」
「皆平等〜とか言いながら、あれ…白い塔造ろうとしてるんだろ?」
あぁ、『白亜の塔』な。
「そんなもんで平等になって、皆喜ぶと思ってんのかね?」
「…さぁ…」
少なくとも、シェルドニア王国の人々は、皆幸せそうだが。
それが本当の幸せなのかどうかは、分からないな。
偽りだろうが、押し付けられたものだろうが、本人が幸せだと感じているなら、それは本物の幸せだ、と。
そう考えることも出来るし、偽物でも良いから幸福感を感じたいと思う人は、大勢いるだろう。
その証拠に裏社会では、そういった類の薬物が、いくらでも横行している。
手に入れた幸せが、自分の力で手にしたのではなくても。
それを自分が幸福と感じるなら、それで良い。
分からなくはない。
少なくとも、不幸であるよりずっとマシだろう。
「変な電波でアヘ顔晒すくらいなら、ゴキブリ生活してた方がよっぽどマシだぜ」
…まぁ、アリューシャみたいな考え方の人間もいる。
こればかりは、人の価値基準によって様々だろうな。
ヒイラは分かっているのだろうか。アリューシャみたいな考え方の人間もいるんだってこと。
いくら貧しいからって、そんな救われ方をされたいと、誰もが望むと思っているのだろうか。
幸福であれば、その形が何であろうと構わないのだろうか。
それともお前は、本当は平等な世の中なんて、どうでも良くて…。
…と、そこまで考えていると。
「ふわぁ〜…。ルル公が難しい話ばっかするから、アリューシャ眠くなってきたよ」
そう言って、アリューシャはばふっ、とベッドに大の字に寝そべった。
「あ、うん。いきなり変なこと聞いて悪かっ…」
「…zzz…」
「…寝てるし…」
早くね?
最後に会話してから、今、10秒もたってなかったんだけど?
しかも。
「毛布かけろよ、馬鹿…」
アリューシャが掛け布団なしで寝ようが、床で寝ようが、好きにすれば良いが。
そのせいでアリューシャが風邪を引いたら、俺がアイズに責められそうなので。
仕方なく、へそ出して寝てるアリューシャの上に、毛布をかけてやったのだった。
その無邪気な寝顔は、決してゴキブリなどと罵るようなものではなかった。
…良い夢見ろよ、アリューシャ。
翌朝。
「…」
俺はベッドから起き上がって、身体の調子を確かめた。
…よし。
胃腸は元気そうだ。
昨日、とんでもないものを食べさせられたからな。
食べさせられたって言うか、俺が知らずに食っただけなんだけど。
どうやら俺の胃腸は、カエルの卵パンに適応してくれたようだ。
良かった。
…。
…良かったのか?
まぁ、具合が悪くならなくて良かったよ。
それで。
隣のベッドに寝ているであろうアリューシャを、起こそうとしたら。
「…うわっ」
思わず、びっくりして声を上げてしまった。
アリューシャはうつ伏せになって、上半身をだらりと垂らしてぶら下がり。
下半身の方は、かろうじてベッドの上に留まっていた。
かけてやったはずの毛布は、アリューシャの身体にぐるぐる巻きになっており。
さながら、アリューシャ巻き寿司みたいになってる。
どうやったら、そんな体勢になるんだ?
「どうなってんだよ、お前…」
寝相が悪いとか、そういう次元じゃないぞ。
しかも。
「おい、アリューシャ起きろ」
「…zzz…」
俺にはこれから、まず「アリューシャを起こす」という、最大の難関を突破しなければならないのである。
「…」
俺はベッドから起き上がって、身体の調子を確かめた。
…よし。
胃腸は元気そうだ。
昨日、とんでもないものを食べさせられたからな。
食べさせられたって言うか、俺が知らずに食っただけなんだけど。
どうやら俺の胃腸は、カエルの卵パンに適応してくれたようだ。
良かった。
…。
…良かったのか?
まぁ、具合が悪くならなくて良かったよ。
それで。
隣のベッドに寝ているであろうアリューシャを、起こそうとしたら。
「…うわっ」
思わず、びっくりして声を上げてしまった。
アリューシャはうつ伏せになって、上半身をだらりと垂らしてぶら下がり。
下半身の方は、かろうじてベッドの上に留まっていた。
かけてやったはずの毛布は、アリューシャの身体にぐるぐる巻きになっており。
さながら、アリューシャ巻き寿司みたいになってる。
どうやったら、そんな体勢になるんだ?
「どうなってんだよ、お前…」
寝相が悪いとか、そういう次元じゃないぞ。
しかも。
「おい、アリューシャ起きろ」
「…zzz…」
俺にはこれから、まず「アリューシャを起こす」という、最大の難関を突破しなければならないのである。
何だ、別に寝てる人を起こすくらい、なんてことないじゃないか、と。
思った、そこのお前。
さては、このアリューシャの寝穢さを知らないな?
まず、第一段階。
「…おい、起きろアリューシャ」
名前を呼んでみる。
「…zzz…」
当然、こんなことで起きるはずがない。
この程度でアリューシャが起きたら、むしろ「大丈夫か?眠れなかったのか?」と逆に心配になるレベル。
次、第二段階。
「起きろアリューシャ!」
肩を揺さぶってみる。
大抵の人間なら、これで起きる。
しかし、この歴戦の勇者は。
「…zzz…」
まぁ、この程度で起きるなら、俺も毎回苦労してない。
仕方ないので、第三段階。
携帯のアラームを、「ジリリリリリ!!」と爆音で流してみる。
もしかしたら、隣の部屋まで聞こえているかもしれない爆音である。
隣の人、起こしちゃったらごめんな。
と、俺は隣人の睡眠事情まで気にしているというのに。
目の前のアリューシャは。
「…zzz…」
それがどうしたとばかりに、眠り続ける。
人によっては、もう眠っているのではなく、死んでいるのではないかと疑うレベルに到達している。
じゃあ次、第四段階。
「…起きろって言ってるだろ、馬鹿アリューシャ!」
後頭部を、まぁまぁの勢いでひっぱたいてみる。
普通の人なら、「いった!何するんだ!」と怒るくらいの威力。
しかし。
歴戦の勇者は、そんなことでは目覚めない。
「…zzz…」
まだまだぐっすり、夢の中。
こうなってくると、もうそろそろ、諦めがつく。
起こすのではなく、自然に起きてくるのを待とう、と。
確かに、ここでいくらアリューシャを起こそうとしても、無駄な努力だ。
頭から水をぶっかけようが、耳元でフライパンをガンガン鳴らそうが、アリューシャが起きることは決してない。
ならもういっそ、そのまま放っておいて、自然の成り行きに任せる方が、余程時間を有効的に使えると言うものだ。
しかし。
今日の任務には、アリューシャが不可欠。
いつまでも放っておいて、時間を無為に過ごす訳にはいかないのだ。
ましてや、この洗脳国家ではな。
一秒たりとも、長居したくはない。
よって、俺はアリューシャを起こすという、無謀とも言える選択をする。
と言うのも。
この居眠り勇者には、致命的な弱点がある。
アリューシャの、本当の保護者であるアイズから、きちんとその「方法」を教わっている。
そして俺は、昨晩の夕食バイキングで、ちゃんとシェフの方に聞いてきた。
故に、準備は万端。
ここまでしても起きないアリューシャを、一体どうやって起こすのかと言うと。
大声を出すのでも、ひっぱたくのでもない。
ただ一言、こう囁やけば良い。
「アリューシャ。今朝の朝食バイキング、ジェラートが出るんだってさ」
「え、マジ?」
あっさりと。
ぱっちりと。
アリューシャは目を開けて、むくっ、と起き上がった。
音を出しても駄目、叩いても殴っても水をかけても駄目。
しかし。
食べ物で釣ると、めちゃくちゃあっさり起きるのが、このへっぽこ歴戦の勇者、アリューシャなのである。
思った、そこのお前。
さては、このアリューシャの寝穢さを知らないな?
まず、第一段階。
「…おい、起きろアリューシャ」
名前を呼んでみる。
「…zzz…」
当然、こんなことで起きるはずがない。
この程度でアリューシャが起きたら、むしろ「大丈夫か?眠れなかったのか?」と逆に心配になるレベル。
次、第二段階。
「起きろアリューシャ!」
肩を揺さぶってみる。
大抵の人間なら、これで起きる。
しかし、この歴戦の勇者は。
「…zzz…」
まぁ、この程度で起きるなら、俺も毎回苦労してない。
仕方ないので、第三段階。
携帯のアラームを、「ジリリリリリ!!」と爆音で流してみる。
もしかしたら、隣の部屋まで聞こえているかもしれない爆音である。
隣の人、起こしちゃったらごめんな。
と、俺は隣人の睡眠事情まで気にしているというのに。
目の前のアリューシャは。
「…zzz…」
それがどうしたとばかりに、眠り続ける。
人によっては、もう眠っているのではなく、死んでいるのではないかと疑うレベルに到達している。
じゃあ次、第四段階。
「…起きろって言ってるだろ、馬鹿アリューシャ!」
後頭部を、まぁまぁの勢いでひっぱたいてみる。
普通の人なら、「いった!何するんだ!」と怒るくらいの威力。
しかし。
歴戦の勇者は、そんなことでは目覚めない。
「…zzz…」
まだまだぐっすり、夢の中。
こうなってくると、もうそろそろ、諦めがつく。
起こすのではなく、自然に起きてくるのを待とう、と。
確かに、ここでいくらアリューシャを起こそうとしても、無駄な努力だ。
頭から水をぶっかけようが、耳元でフライパンをガンガン鳴らそうが、アリューシャが起きることは決してない。
ならもういっそ、そのまま放っておいて、自然の成り行きに任せる方が、余程時間を有効的に使えると言うものだ。
しかし。
今日の任務には、アリューシャが不可欠。
いつまでも放っておいて、時間を無為に過ごす訳にはいかないのだ。
ましてや、この洗脳国家ではな。
一秒たりとも、長居したくはない。
よって、俺はアリューシャを起こすという、無謀とも言える選択をする。
と言うのも。
この居眠り勇者には、致命的な弱点がある。
アリューシャの、本当の保護者であるアイズから、きちんとその「方法」を教わっている。
そして俺は、昨晩の夕食バイキングで、ちゃんとシェフの方に聞いてきた。
故に、準備は万端。
ここまでしても起きないアリューシャを、一体どうやって起こすのかと言うと。
大声を出すのでも、ひっぱたくのでもない。
ただ一言、こう囁やけば良い。
「アリューシャ。今朝の朝食バイキング、ジェラートが出るんだってさ」
「え、マジ?」
あっさりと。
ぱっちりと。
アリューシャは目を開けて、むくっ、と起き上がった。
音を出しても駄目、叩いても殴っても水をかけても駄目。
しかし。
食べ物で釣ると、めちゃくちゃあっさり起きるのが、このへっぽこ歴戦の勇者、アリューシャなのである。
…その後。
朝食の席にて。
「うめー!」
「良かったな…」
アリューシャは、釣られて起きたジェラートを、もぐもぐ食べていた。
「ルル公は食わねぇの?」
「あぁ」
「何でー?美味いのに」
「…」
そうだな。見た目はピンク色で、ストロベリージェラートみたいで美味しそうだが。
昨日、シェフに聞いたとき教えてくれたよ。良い笑顔でさ。
「明日のデザートは、シェルドニアガラガラヘビの肝を、たっぷり使ったジェラートですよ」と。
俺は思ったね。絶対食わねぇって。
アリューシャには、そのジェラートの正体は教えなかった。
教えたところで、アリューシャなら気にせずバクバク食べそうだがな。
まぁ、そんなことはどうでも良い。
「アリューシャ」
「うみゅ?」
俺は、ルティス語でアリューシャに話しかけた。
こうすれば、周囲がシェルドニア人ばかりの場所でも、気にせず会話が出来る。
…と言っても、そもそもアリューシャはシェルドニア語を知らないから、ルティス語で話すしかないんだけどな。
「お前、ここに何しに来たのか、ちゃんと分かってるな?」
「?ジェラート食べに来た!」
そういう意味じゃねぇ。
「ちげーよ。何でシェルドニア王国まで来たのか、そこを分かってるのかって聞いてるんだ。俺達の任務だよ」
「任務…?…。…分かってるよ!」
ちょっと考えただろお前。今。
本当に大丈夫なんだろうな?
スナイパーとしてはこの上なく信頼出来るが、如何せんオツムの方は信用ならない。
朝食の席にて。
「うめー!」
「良かったな…」
アリューシャは、釣られて起きたジェラートを、もぐもぐ食べていた。
「ルル公は食わねぇの?」
「あぁ」
「何でー?美味いのに」
「…」
そうだな。見た目はピンク色で、ストロベリージェラートみたいで美味しそうだが。
昨日、シェフに聞いたとき教えてくれたよ。良い笑顔でさ。
「明日のデザートは、シェルドニアガラガラヘビの肝を、たっぷり使ったジェラートですよ」と。
俺は思ったね。絶対食わねぇって。
アリューシャには、そのジェラートの正体は教えなかった。
教えたところで、アリューシャなら気にせずバクバク食べそうだがな。
まぁ、そんなことはどうでも良い。
「アリューシャ」
「うみゅ?」
俺は、ルティス語でアリューシャに話しかけた。
こうすれば、周囲がシェルドニア人ばかりの場所でも、気にせず会話が出来る。
…と言っても、そもそもアリューシャはシェルドニア語を知らないから、ルティス語で話すしかないんだけどな。
「お前、ここに何しに来たのか、ちゃんと分かってるな?」
「?ジェラート食べに来た!」
そういう意味じゃねぇ。
「ちげーよ。何でシェルドニア王国まで来たのか、そこを分かってるのかって聞いてるんだ。俺達の任務だよ」
「任務…?…。…分かってるよ!」
ちょっと考えただろお前。今。
本当に大丈夫なんだろうな?
スナイパーとしてはこの上なく信頼出来るが、如何せんオツムの方は信用ならない。
相変わらずサングラスをかけて、変装するような格好をした俺達は。
ホテルを出てすぐ、「任務地」に向かった。
ここからは、アリューシャとは別行動である。
仕事用のインカムで、連絡を取り合うことになる。
俺は指定のポイントについて、アリューシャに連絡を取った。
「アリューシャ。着いたか?」
『おけおけ。警備ガバだねーこの建物。びっくりするくらいあっという間に侵入出来たよ』
だろうな。
シェルドニア王国は、世界で一番犯罪発生率が低い国。
これだけ聞けば、なんて治安の良い国なんだろうと思うが。
俺達は、この治安の良さのからくりを知っている。
これら全てが、『白亜の塔』によるものだと。
そして。
生まれたときから、『白亜の塔』の影響下にあり、反抗したり犯罪を犯すことを知らない国民達は。
良くも悪くも、危機感というものを知らない。
国民全体の気質が穏やか過ぎるせいで、「まさか悪いことを企む人がいるはずがない」という空気が蔓延している。
だから、俺達はそこに付け入らせてもらう。
『そっちの様子は〜…っと…。おーおー。女王様が住むお城だってのに、警備は門番二人だけかよ。しょぼっ』
「あぁ。それはここからも見えてるよ」
まず、一般人である俺が、王宮の近くにこんなに接近出来るのがおかしい。
ルティス帝国の王宮だったら、まずここまで近づくにも一苦労だ。
それに比べ、シェルドニア王国の王宮は、今俺の目と鼻の先にあるも同然。
警備が手薄なのも、「王宮に手出しする国民がいるはずがない」と思い込んでいる証だ。
つい先日、王様が暗殺されたばかりで国が荒れたというのに、まるで何事もなかったかのように静かだ。
これも、全て『白亜の塔』の影響だ。
不自然に国王が変わろうと、国民は何の疑いも持たず、新しい国王を無邪気に讃える。
「警備はたかが二人だ。俺が…」
と、言いかけると。
『まぁ待て待て。ルル公は奇襲係なんだから。ここは分担していこうぜ』
「分担?」
『門番二人と、門のセキュリティはアリューシャがぶっ壊す。あと、門から建物までにあるカメラと…あれは自動迎撃マシンガンだな。あれもぶっ壊すよ』
…さすがアリューシャ。
スナイパーの「目」は、前線にいる俺なんかより、ずっと視野が広い。
「奴らも、一応襲撃の備えはしてるんだな」
『お粗末過ぎて笑えてくるけどな。大体、こんなベストポジションで王宮を狙える位置に、お誂え向きの建物がある時点でお察しだろ』
全くだ。
ルティス帝国王宮なら有り得ないな。
まぁ、それでもアリューシャは王宮の窓をぶち抜いていたが。
あれはアリューシャがチート過ぎるのだ。
「とはいえ、警戒は怠るな。位置がバレたら危ない。適宜移動しろよ」
『おいおい、スナイパーの基本をアリューシャに講釈か?』
「…そりゃそうか。悪かったよ」
俺が言うまでもなく、お前は誰より優秀なスナイパーだよ。
「よし、始めるぞ」
『あいよ』
と、言った瞬間。
アリューシャのライフルが、火を吹いた。
ホテルを出てすぐ、「任務地」に向かった。
ここからは、アリューシャとは別行動である。
仕事用のインカムで、連絡を取り合うことになる。
俺は指定のポイントについて、アリューシャに連絡を取った。
「アリューシャ。着いたか?」
『おけおけ。警備ガバだねーこの建物。びっくりするくらいあっという間に侵入出来たよ』
だろうな。
シェルドニア王国は、世界で一番犯罪発生率が低い国。
これだけ聞けば、なんて治安の良い国なんだろうと思うが。
俺達は、この治安の良さのからくりを知っている。
これら全てが、『白亜の塔』によるものだと。
そして。
生まれたときから、『白亜の塔』の影響下にあり、反抗したり犯罪を犯すことを知らない国民達は。
良くも悪くも、危機感というものを知らない。
国民全体の気質が穏やか過ぎるせいで、「まさか悪いことを企む人がいるはずがない」という空気が蔓延している。
だから、俺達はそこに付け入らせてもらう。
『そっちの様子は〜…っと…。おーおー。女王様が住むお城だってのに、警備は門番二人だけかよ。しょぼっ』
「あぁ。それはここからも見えてるよ」
まず、一般人である俺が、王宮の近くにこんなに接近出来るのがおかしい。
ルティス帝国の王宮だったら、まずここまで近づくにも一苦労だ。
それに比べ、シェルドニア王国の王宮は、今俺の目と鼻の先にあるも同然。
警備が手薄なのも、「王宮に手出しする国民がいるはずがない」と思い込んでいる証だ。
つい先日、王様が暗殺されたばかりで国が荒れたというのに、まるで何事もなかったかのように静かだ。
これも、全て『白亜の塔』の影響だ。
不自然に国王が変わろうと、国民は何の疑いも持たず、新しい国王を無邪気に讃える。
「警備はたかが二人だ。俺が…」
と、言いかけると。
『まぁ待て待て。ルル公は奇襲係なんだから。ここは分担していこうぜ』
「分担?」
『門番二人と、門のセキュリティはアリューシャがぶっ壊す。あと、門から建物までにあるカメラと…あれは自動迎撃マシンガンだな。あれもぶっ壊すよ』
…さすがアリューシャ。
スナイパーの「目」は、前線にいる俺なんかより、ずっと視野が広い。
「奴らも、一応襲撃の備えはしてるんだな」
『お粗末過ぎて笑えてくるけどな。大体、こんなベストポジションで王宮を狙える位置に、お誂え向きの建物がある時点でお察しだろ』
全くだ。
ルティス帝国王宮なら有り得ないな。
まぁ、それでもアリューシャは王宮の窓をぶち抜いていたが。
あれはアリューシャがチート過ぎるのだ。
「とはいえ、警戒は怠るな。位置がバレたら危ない。適宜移動しろよ」
『おいおい、スナイパーの基本をアリューシャに講釈か?』
「…そりゃそうか。悪かったよ」
俺が言うまでもなく、お前は誰より優秀なスナイパーだよ。
「よし、始めるぞ」
『あいよ』
と、言った瞬間。
アリューシャのライフルが、火を吹いた。
ぽすっ、ぽすっ、と。
連続して、可愛らしい音がして。
見張りに立っていた二人に、アリューシャの撃った弾が着弾していた。
門番の二人は、自分に弾が当たったことに、一瞬気づかなかったらしく。
「あれ?」みたいな顔をして、そして驚愕に目を見開いた。
そして、気づいたときにはもう遅い。
二人共、血飛沫をあげて倒れ…、
…は、しなかった。
いや、倒れたのは事実だが。
血飛沫をあげたりはしなかった。
アリューシャが撃ったのは、単なる麻酔弾。
殺す為の弾丸ではなく、身体を麻痺させ、無力化させる為の弾だ。
そして。
僅かな間を開けて、今度は実弾が命中した。
王宮を守る門の、セキュリティロックを破壊したのだ。
…今更ながら。
よく当てるよ。あんな小さな的に。
…さぁ。感心してる場合じゃない。
アリューシャが、己の役目を果たしたのだ。
なら、次は俺の番だ。
「っ!」
俺は物陰から走り出し、壊れた門を突き破って、王宮の敷地内に飛び込んだ。
倒れた門番達が、何か言おうとしていたが。
悪いが、構っている暇はない。
それに。
侵入者が現れるや、シェルドニア王宮の最低限の防衛システム、自動迎撃マシンガンが、俺をターゲットに捉えた。
だが、俺は意に介さなかった。
ルレイアじゃないが、ただ真っ直ぐ、真正面から突き進んだだけだ。
マシンガンごときで、俺を阻むことは出来ない。
何故なら。
マシンガンが俺に向かって発射される、その寸前。
バキンッ!と破砕音がして、マシンガンが呆気なく破壊された。
マシンガンは一つだけではない。
王宮入り口に向かうまでに、前後左右を取り囲むように張り巡らされた、自動迎撃マシンガンは。
一発も、俺に向かって弾を発射することが出来なかった。
理由は簡単だ。
マシンガンが俺を捉え、発砲する前に。
全て、アリューシャが狙撃でマシンガンを破壊しているからである。
一発も撃ち漏らすことなく、あっという間にマシンガンは沈黙した。
更に。
固く閉ざされた王宮の扉までも、門と同じくあっさり狙撃で破壊。
…アリューシャの狙撃の腕前は、最早言うまでもないが。
シェルドニア王宮の警備、いくらなんでもガバガバ過ぎないか?
連続して、可愛らしい音がして。
見張りに立っていた二人に、アリューシャの撃った弾が着弾していた。
門番の二人は、自分に弾が当たったことに、一瞬気づかなかったらしく。
「あれ?」みたいな顔をして、そして驚愕に目を見開いた。
そして、気づいたときにはもう遅い。
二人共、血飛沫をあげて倒れ…、
…は、しなかった。
いや、倒れたのは事実だが。
血飛沫をあげたりはしなかった。
アリューシャが撃ったのは、単なる麻酔弾。
殺す為の弾丸ではなく、身体を麻痺させ、無力化させる為の弾だ。
そして。
僅かな間を開けて、今度は実弾が命中した。
王宮を守る門の、セキュリティロックを破壊したのだ。
…今更ながら。
よく当てるよ。あんな小さな的に。
…さぁ。感心してる場合じゃない。
アリューシャが、己の役目を果たしたのだ。
なら、次は俺の番だ。
「っ!」
俺は物陰から走り出し、壊れた門を突き破って、王宮の敷地内に飛び込んだ。
倒れた門番達が、何か言おうとしていたが。
悪いが、構っている暇はない。
それに。
侵入者が現れるや、シェルドニア王宮の最低限の防衛システム、自動迎撃マシンガンが、俺をターゲットに捉えた。
だが、俺は意に介さなかった。
ルレイアじゃないが、ただ真っ直ぐ、真正面から突き進んだだけだ。
マシンガンごときで、俺を阻むことは出来ない。
何故なら。
マシンガンが俺に向かって発射される、その寸前。
バキンッ!と破砕音がして、マシンガンが呆気なく破壊された。
マシンガンは一つだけではない。
王宮入り口に向かうまでに、前後左右を取り囲むように張り巡らされた、自動迎撃マシンガンは。
一発も、俺に向かって弾を発射することが出来なかった。
理由は簡単だ。
マシンガンが俺を捉え、発砲する前に。
全て、アリューシャが狙撃でマシンガンを破壊しているからである。
一発も撃ち漏らすことなく、あっという間にマシンガンは沈黙した。
更に。
固く閉ざされた王宮の扉までも、門と同じくあっさり狙撃で破壊。
…アリューシャの狙撃の腕前は、最早言うまでもないが。
シェルドニア王宮の警備、いくらなんでもガバガバ過ぎないか?
ひとまず。
これで、侵入は成功した。
「アリューシャ。狙撃ポイントを移動しろ」
『ルル公一人で大丈夫かよ?』
「時間稼ぎが出来れば良い。『真打ち』が出てくるまでに、一度移動して、態勢を立て直してくれ」
『りょ』
アリューシャが、狙撃ポイントの移動を開始した。
だから、俺がやるべきことは。
事の次第を聞きつけて、『真打ち』が出てくるまでの間。
ここで、王宮内の警備兵を足止めすることだ。
「…さて」
ルレイア並みの、ダイナミック入室を果たした俺は。
立ち止まり、両手に拳銃を持って、周囲を見渡した。
いかに、ガバガバな警備とは言えど。
さすがに、王宮内の守りは、最低限固めているようで。
騒ぎを聞きつけたらしい警備兵達が、俺の周りに集まり始めていた。
…しかし。
「…相変わらず、全く怖くないな」
一応、訓練された警備兵なのだろうが。
前述の通り、シェルドニア王国は、『白亜の塔』の影響のせいで、平和に慣れ過ぎている。
それ故に、イレギュラーな事態に弱い。
警備兵達は、一応拳銃や刃物を持ってはいるが。
顔には、ありありと動揺と狼狽が浮かんでいた。
「言われたから来てみたけど、どうしたら良いのか分からない」って顔だな。
簡単に言うと、全員へっぴり腰なのだ。
一通りの訓練は受けているのだろうが、訓練と実戦は、天と地ほどの差がある。
平和な訓練を受けたことはあっても、本当の実戦は経験したことがない彼らから、全くプレッシャーは感じなかった。
こいつらは兵隊と言うより、ただの一般人だ。
一般人に重火器を持たせても、扱えないのと同じ。
皆、武装しているのに、ちっとも敵意を感じない。
これなら、『青薔薇連合会』の末端構成員の方が、まだ士気が高いぞ。
国が平和だと、いざイレギュラーな事態が起きたとき、即座に対処する能力が失われる。
そのように仕向けられているのだから、彼らには何の罪もないが。
これで、侵入は成功した。
「アリューシャ。狙撃ポイントを移動しろ」
『ルル公一人で大丈夫かよ?』
「時間稼ぎが出来れば良い。『真打ち』が出てくるまでに、一度移動して、態勢を立て直してくれ」
『りょ』
アリューシャが、狙撃ポイントの移動を開始した。
だから、俺がやるべきことは。
事の次第を聞きつけて、『真打ち』が出てくるまでの間。
ここで、王宮内の警備兵を足止めすることだ。
「…さて」
ルレイア並みの、ダイナミック入室を果たした俺は。
立ち止まり、両手に拳銃を持って、周囲を見渡した。
いかに、ガバガバな警備とは言えど。
さすがに、王宮内の守りは、最低限固めているようで。
騒ぎを聞きつけたらしい警備兵達が、俺の周りに集まり始めていた。
…しかし。
「…相変わらず、全く怖くないな」
一応、訓練された警備兵なのだろうが。
前述の通り、シェルドニア王国は、『白亜の塔』の影響のせいで、平和に慣れ過ぎている。
それ故に、イレギュラーな事態に弱い。
警備兵達は、一応拳銃や刃物を持ってはいるが。
顔には、ありありと動揺と狼狽が浮かんでいた。
「言われたから来てみたけど、どうしたら良いのか分からない」って顔だな。
簡単に言うと、全員へっぴり腰なのだ。
一通りの訓練は受けているのだろうが、訓練と実戦は、天と地ほどの差がある。
平和な訓練を受けたことはあっても、本当の実戦は経験したことがない彼らから、全くプレッシャーは感じなかった。
こいつらは兵隊と言うより、ただの一般人だ。
一般人に重火器を持たせても、扱えないのと同じ。
皆、武装しているのに、ちっとも敵意を感じない。
これなら、『青薔薇連合会』の末端構成員の方が、まだ士気が高いぞ。
国が平和だと、いざイレギュラーな事態が起きたとき、即座に対処する能力が失われる。
そのように仕向けられているのだから、彼らには何の罪もないが。
駆けつけた警備兵の数は、およそ20人ほど。
ルレイアなら、一刈りで一掃出来る数だな。
そして俺は、いつもそんなルレイアの横について、一緒に戦ってきたのだ。
今更、数の暴力にはビビらない。
ましてや、こんなへっぴり腰集団など、何人集まろうと数のうちに入らない。
俺は、最大限の殺気を放った。
恐らく、彼らが初めて経験するであろう、
本物の、マフィアの殺気だ。
「…来いよ」
敢えて、シェルドニア語でそう言った。
どれだけ国が違っていようと、これが何を意味するのかは分かるな?
別に、挑発したつもりはない。
こんな烏合の衆、怖くもなんともない。
束になってかかってこられようと、まとめて返り討ちにしてくれる。
しかし。
「ひっ…」
「う、うぅ…」
情けないことに。
シェルドニア兵は、立派な小銃やショットガンを持って、俺より20倍も数の優位を取っていながら。
俺に挑んで、前に出る者は一人もいなかった。
それどころか、俺の殺気に怯えて、後退りする始末。
20人全員が、「誰か先に行ってくれ」と無言で言い合っている。
…アシミムよ。
お前の軍隊は、全く軍隊として機能してないな。
気の毒になってくるが、しかし、これがお前の国のやり方なのだから。
同情する必要はない。
俺は、手前にいた、震える手で拳銃を握っている若い男性兵士に、拳銃を向けた。
「ひ、ひっ!」
銃口を向けられ、彼は反射的に拳銃を向けてきたが。
あんなへっぴり腰じゃ、当たるものも当たらない。
そんなことより。
「アシミム女王と、ルシード・キルシュテンをここに呼べ。『青薔薇連合会』の幹部が来たと伝えろ」
俺は、彼らにも分かるよう、シェルドニア語で伝えた。
「え、え…?」
「…もう一度言わせる気か?」
「ひっ…」
呆ける兵士に向かって、再び殺気を浴びせてやると。
彼は怯えた表情のまま、伝言を伝えに踵を返した。
…本当に、実戦慣れしてないにも程があるな。
突然侵入してきた、得体の知れない敵に、自分達の国王を連れてこいと命じられ。
素直に、それに従おうとするなど。
そこは普通、「武器を捨てて投降しろ」と、逆に脅しをかけるところだろうに。
まぁ良い。
「来客」が俺達であることを知れば、奴らは俺達を無視出来ないのだから。
ルレイアなら、一刈りで一掃出来る数だな。
そして俺は、いつもそんなルレイアの横について、一緒に戦ってきたのだ。
今更、数の暴力にはビビらない。
ましてや、こんなへっぴり腰集団など、何人集まろうと数のうちに入らない。
俺は、最大限の殺気を放った。
恐らく、彼らが初めて経験するであろう、
本物の、マフィアの殺気だ。
「…来いよ」
敢えて、シェルドニア語でそう言った。
どれだけ国が違っていようと、これが何を意味するのかは分かるな?
別に、挑発したつもりはない。
こんな烏合の衆、怖くもなんともない。
束になってかかってこられようと、まとめて返り討ちにしてくれる。
しかし。
「ひっ…」
「う、うぅ…」
情けないことに。
シェルドニア兵は、立派な小銃やショットガンを持って、俺より20倍も数の優位を取っていながら。
俺に挑んで、前に出る者は一人もいなかった。
それどころか、俺の殺気に怯えて、後退りする始末。
20人全員が、「誰か先に行ってくれ」と無言で言い合っている。
…アシミムよ。
お前の軍隊は、全く軍隊として機能してないな。
気の毒になってくるが、しかし、これがお前の国のやり方なのだから。
同情する必要はない。
俺は、手前にいた、震える手で拳銃を握っている若い男性兵士に、拳銃を向けた。
「ひ、ひっ!」
銃口を向けられ、彼は反射的に拳銃を向けてきたが。
あんなへっぴり腰じゃ、当たるものも当たらない。
そんなことより。
「アシミム女王と、ルシード・キルシュテンをここに呼べ。『青薔薇連合会』の幹部が来たと伝えろ」
俺は、彼らにも分かるよう、シェルドニア語で伝えた。
「え、え…?」
「…もう一度言わせる気か?」
「ひっ…」
呆ける兵士に向かって、再び殺気を浴びせてやると。
彼は怯えた表情のまま、伝言を伝えに踵を返した。
…本当に、実戦慣れしてないにも程があるな。
突然侵入してきた、得体の知れない敵に、自分達の国王を連れてこいと命じられ。
素直に、それに従おうとするなど。
そこは普通、「武器を捨てて投降しろ」と、逆に脅しをかけるところだろうに。
まぁ良い。
「来客」が俺達であることを知れば、奴らは俺達を無視出来ないのだから。
拳銃を向けて、怯え顔の兵士と、しばらく睨み合っていると。
『…ルル公。狙撃ポイントに着いた』
インカムから、アリューシャの声がした。
…よし。こちらの準備は整ったな。
『取り囲まれてんね、ルル公。何人か威嚇射撃でもしようか?』
「いや、そのまま待機だ。狙撃のタイミングは、俺が指示する」
俺は、ルティス語で答えた。
こうしてルティス語で話せば、シェルドニア人の兵士達には、俺が何を言ってるのか分かるまい。
ともかく、「真打ち」達が…ルシードとアシミムが来ない限りは、俺達も動かない。
向こうがアシミムを出し渋るのなら、威嚇も視野に入れるが。
『それは良いけどよ。ルル公が危ねーと思ったら、その前にアリューシャが撃つぞ』
「分かった。そうしてくれ」
『で、こんなルレ公じみた特攻やって、ルシード…ルシ公とアシ公は、本当に来るの?』
お前は、誰にでもその呼び方をしなきゃ気が済まないんだな。
まぁ、ルレイアなんて、もっと酷い呼び方してるから(ゲロ顔縦ロールお嬢様(笑)とか)。
それに比べれば、アリューシャは可愛いもんだ。
「来るよ」
『ふーん…。何で?』
「こう脅せば、奴らは俺達を無視出来ない…って、お前の大好きなアイズが言ってたからだ」
『成程。説得力あるわ〜』
アイズが言うんだから、間違いはないな。
俺は、ここで待っていれば良い。
そして。
「お前達、下がっていろ」
「る、ルシード隊長!」
シェルドニア兵士達の後ろから。
ひときわ背の高い、長い髪を後ろで一つに束ねた青年が現れた。
彼を見て、兵士達は救世主がやって来たと言わんばかりの表情。
それもそのはず。
華弦という、大事な戦力がいなくなった以上。
恐らくこの王宮で、最も実力を持った「戦士」は、この男を除いて他にいない。
「…久し振りだな。ルシード・キルシュテン」
「…ルルシー・エンタルーシアか」
アシミムの懐刀であり、俺達の仇敵でもある男。
ルシードが、この場にやって来た。
な?アイズの言った通りだったろう?
『…ルル公。狙撃ポイントに着いた』
インカムから、アリューシャの声がした。
…よし。こちらの準備は整ったな。
『取り囲まれてんね、ルル公。何人か威嚇射撃でもしようか?』
「いや、そのまま待機だ。狙撃のタイミングは、俺が指示する」
俺は、ルティス語で答えた。
こうしてルティス語で話せば、シェルドニア人の兵士達には、俺が何を言ってるのか分かるまい。
ともかく、「真打ち」達が…ルシードとアシミムが来ない限りは、俺達も動かない。
向こうがアシミムを出し渋るのなら、威嚇も視野に入れるが。
『それは良いけどよ。ルル公が危ねーと思ったら、その前にアリューシャが撃つぞ』
「分かった。そうしてくれ」
『で、こんなルレ公じみた特攻やって、ルシード…ルシ公とアシ公は、本当に来るの?』
お前は、誰にでもその呼び方をしなきゃ気が済まないんだな。
まぁ、ルレイアなんて、もっと酷い呼び方してるから(ゲロ顔縦ロールお嬢様(笑)とか)。
それに比べれば、アリューシャは可愛いもんだ。
「来るよ」
『ふーん…。何で?』
「こう脅せば、奴らは俺達を無視出来ない…って、お前の大好きなアイズが言ってたからだ」
『成程。説得力あるわ〜』
アイズが言うんだから、間違いはないな。
俺は、ここで待っていれば良い。
そして。
「お前達、下がっていろ」
「る、ルシード隊長!」
シェルドニア兵士達の後ろから。
ひときわ背の高い、長い髪を後ろで一つに束ねた青年が現れた。
彼を見て、兵士達は救世主がやって来たと言わんばかりの表情。
それもそのはず。
華弦という、大事な戦力がいなくなった以上。
恐らくこの王宮で、最も実力を持った「戦士」は、この男を除いて他にいない。
「…久し振りだな。ルシード・キルシュテン」
「…ルルシー・エンタルーシアか」
アシミムの懐刀であり、俺達の仇敵でもある男。
ルシードが、この場にやって来た。
な?アイズの言った通りだったろう?
この作家の他の作品
表紙を見る
彼らは夢を見る。毎晩、バケモノに襲われる悪夢を。
彼らは生贄。罪を犯した人間達が生み出したバケモノを、その手で殺すことを宿命付けられた生贄。
彼らは選ばれた。「普通」であることに選ばれなかった彼ら。
裁定者たる天使が振った賽に、選ばれてしまった彼らが辿る運命は。
そして、生贄に選ばれた彼らの抱える、辛く、苦しみに満ちた過去の記憶とは…。
表紙を見る
2019年に作者が携帯小説モバスペbookに投稿した作品を移植しました。
彼らの迎えた夜明けに、祝福の歌を。
表紙を見る
2021年にモバスペbookに投稿した作品を移植しました。
エロマフィア、記念すべき第5弾。
最果てにあるレゾンデートルを、お楽しみください。
※この作品に登場する宗教、教義、宗教組織は全てフィクションです。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…