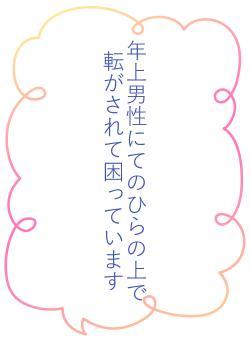「本当だ珍しい。バスで帰るのかな?」
「それは無いだろう、だって先輩はバイクで通学してるんだから。どこに隠してるのか知らないけど」
そんな二人の会話もそこそこに智成が挨拶をしてきた。
「よう谷口。栗岡も居たのか」
「お疲れッス」
「お疲れ様ッス」
「これ、お前のか?」
簡単に挨拶をすますと智成が智樹に見せてきたのは腕時計だった。
「いいえ、俺んじゃないッスよ」
そういう智樹の横でどこか見覚えがあると思考回路をフル活用していた美利。
あごに手を当てた美利に気付き、智成は時計を美利に向けた。
「誰かがつけていた気がするんだよなぁ」
喉まで出かかっている何かが出てこない。
「忘れ物ッスか?」
智樹が時計を手に取りベルト部分や裏側を確認し始めた。