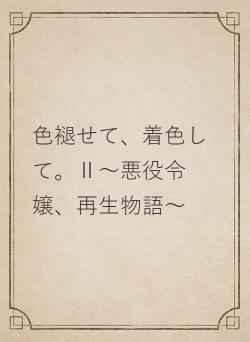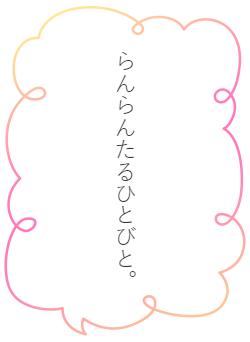半年も経てば、クリスはクリストファーにおかれる状況を何となく理解し始めた。
クリストファーはお手伝いさんと思われる50代の夫婦と3人で暮らしている。
最初は、クリストファーの祖父母なのかと思ったが、クリストファーのことを「坊ちゃま」と呼んでいるから、お手伝いさんというのに間違いない。
たまに、ドレス姿の女性がやってきて、すぐに帰ってしまう。
あの人はクリストファーの母親であろう。
髪の毛が長いときは、クリストファーは屋敷を出られないので、
こっそりとクリスが屋敷に行って遊ぶようになった。
そのうち、クリスが夜になると女の身体になってしまうことがバレた。
夕方だったから、安心していたのが災いした。
その日、クリストファーの髪の毛が短かったので、外に出て祖父と3人で遊んでいたときだった。
いつもは21時くらいに女の身体に変身するのに。
どういうわけかその日は夕方、女の身体に変身した。
身体がピカッと光ったかと思うと髪の毛が肩まで伸びた。
クリスは恥ずかしくなって泣いてしまったが、
クリストファーはクリスの姿を見て何も言わず、「帰ろう」と言って。
自分が被っていた帽子をクリスに被せた。
その日から、クリスはクリストファーが本当の友達だと考えるようになった。
そして、真実を話すことを決めた。
「7歳の誕生日に魔法をかけられたんだ」
信じてもらえないだろうなと思ったが、
クリストファーは驚いて、「私も」と大きく頷いた。
「ずっと女の子に生まれたかった。服だって、妹が着ているようなドレスが着たかった。でも、あの人に言ったら殴られた」
クリストファーは、母親のことを「あの人」と言う。
「お父さんは何しているの?」
「…さあ? 多分、お仕事だと思う」
クリストファーが怖い顔をしたので、クリスは聴いてはいけないのだと思った。
「誕生日に魔法をかけられてから、沢山、病院に行った。でも、原因がわからなくて、あの人は毎日叫んでた。そのうち、ここに連れてこられて…そんな感じ」
「さみしくないの?」
「全然。だって、毎日。気持ち悪いって言われてたんだよ? それが、今は自由だよ」
ニコッとクリストファーが笑うと頬にえくぼが出来る。
クリスは、可愛い人だなと思った。
クリストファーはお手伝いさんと思われる50代の夫婦と3人で暮らしている。
最初は、クリストファーの祖父母なのかと思ったが、クリストファーのことを「坊ちゃま」と呼んでいるから、お手伝いさんというのに間違いない。
たまに、ドレス姿の女性がやってきて、すぐに帰ってしまう。
あの人はクリストファーの母親であろう。
髪の毛が長いときは、クリストファーは屋敷を出られないので、
こっそりとクリスが屋敷に行って遊ぶようになった。
そのうち、クリスが夜になると女の身体になってしまうことがバレた。
夕方だったから、安心していたのが災いした。
その日、クリストファーの髪の毛が短かったので、外に出て祖父と3人で遊んでいたときだった。
いつもは21時くらいに女の身体に変身するのに。
どういうわけかその日は夕方、女の身体に変身した。
身体がピカッと光ったかと思うと髪の毛が肩まで伸びた。
クリスは恥ずかしくなって泣いてしまったが、
クリストファーはクリスの姿を見て何も言わず、「帰ろう」と言って。
自分が被っていた帽子をクリスに被せた。
その日から、クリスはクリストファーが本当の友達だと考えるようになった。
そして、真実を話すことを決めた。
「7歳の誕生日に魔法をかけられたんだ」
信じてもらえないだろうなと思ったが、
クリストファーは驚いて、「私も」と大きく頷いた。
「ずっと女の子に生まれたかった。服だって、妹が着ているようなドレスが着たかった。でも、あの人に言ったら殴られた」
クリストファーは、母親のことを「あの人」と言う。
「お父さんは何しているの?」
「…さあ? 多分、お仕事だと思う」
クリストファーが怖い顔をしたので、クリスは聴いてはいけないのだと思った。
「誕生日に魔法をかけられてから、沢山、病院に行った。でも、原因がわからなくて、あの人は毎日叫んでた。そのうち、ここに連れてこられて…そんな感じ」
「さみしくないの?」
「全然。だって、毎日。気持ち悪いって言われてたんだよ? それが、今は自由だよ」
ニコッとクリストファーが笑うと頬にえくぼが出来る。
クリスは、可愛い人だなと思った。