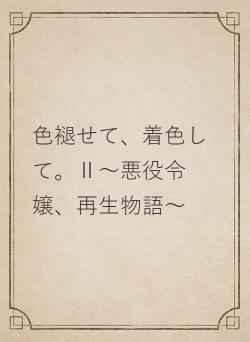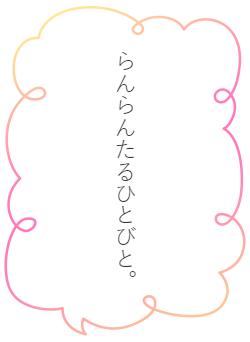その日は、いつものように漁をサボって。
渚は岩場で寝っ転がっていた。
心地よい暖かさに思わずウトウトしかけていると。
「こらー」という声がしたので、思わず飛び跳ねた。
見ると、ナンが立っている。
「また、仕事サボったでしょ。お姉さんたち怒ってたよ」
「サボってたんじゃないよ。休んでいただけ」
ナンを睨みつけると。
ナンは渚の隣に座った。
「マリクは本当に自由だよね」
急に疲れたような声でナンが言うので、渚は驚いた。
両親に置いていかれ、一人で生活しているナンを尊敬しつつも、
許嫁としてどう接していいのかわからなくなっていた時期だった。
「10年後、20年後、どうなってんのかなあ」
「急に何だよ」
ナンが大きな目でこっちを見つめる。
あと数年経てば、この女は自分の嫁になる。
それが、どうしても頭で理解出来ない。
2人きりになると、気まずくて、渚は立ち上がった。
が、ふと潮風に混ざった異臭に気づいた。
「…なんか、焦げ臭くないか?」
「えー、またオババが何か燃やしてんのかなあ」
オババは本業である、祈祷をする際、色んなものを燃やす。
枝や葉っぱだけじゃなく、神に捧げるものとして魚も燃やす。
ナンはのんきに、オババのせいじゃないかと言うが。
渚は嫌な胸騒ぎがした。
「ここから村まで結構離れてんのに、ここまで匂うか?」
「…確かに。マリクは見つからないために此処にいるんだもんね」
嫌味たらしくナンが言った。
「うっさい」と渚がナンに怒ったところで。
渚とナンは、あることに気づいた…。
「あっ・・・」
潮風と共に微かに、女性の悲鳴が聞こえたかと思えば。
村の方から煙が出ているのが目に入った。