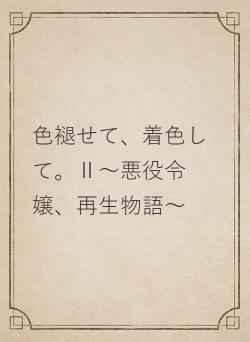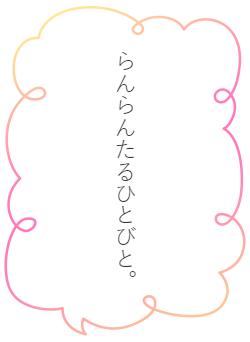男じゃなくて、女として生まれたかった。
サクラの心に、そんな感情が芽生えたのは妹のドレス姿を見た時だった。
妹は、甘やかされて育っていた。
母に似ていた。
妹とは、あまり顔を見合わせることがなかったが。
たまに、貴族のパーティーなどで一緒に行く機会があった際、妹のドレス姿を見て絶句した。
妹の平凡なる顔に煌びやかなドレスは見劣りしていた。
ドレスは妹を拒否しているように見えた。
「まあ、どこかのお姫様かと思っちゃったわ」
と母は、ベタベタと妹を褒める。
自分だったら、もっときちんとあのドレスを着こなすのにな…と感じた。
母も妹も、お洒落がわからないのかとサクラは思った。
どんなに豪華に着飾っていても、パーティー会場では母も妹も見劣りする存在でしかない。それでも、母はパーティーを満喫し貴族たちと喋ることで、自分を優位に感じていたのかもしれない。
母だとは、思えず妹も悪魔だと感じるようになってサクラは一人、孤立し始めた。
父は、あまり家には帰ってこなかった。
仕事で忙しいとはいえ、本当だろうかと疑う。
たまに、父と顔を見合わせることはあっても、何かを話すわけではない。
誰にも相談できない。
毎日、苦しみしかない日々を過ごすしかなかった。
勉強も剣術の稽古も、そこまで得意ではない。
苦痛に耐えながら勉学に励んでいたとき、祖父が遊びにやって来た。
祖父は、何冊かの植物図鑑と一冊の絵本をサクラに与えた。
「跡取りになるならば、きちんと本は読んでおくように」
いつも、植物図鑑しかプレゼントしてこない祖父が何故、絵本をくれたのかはわからない。
だが、その本はサクラの傷ついた心を支える絵本となった。
サクラの心に、そんな感情が芽生えたのは妹のドレス姿を見た時だった。
妹は、甘やかされて育っていた。
母に似ていた。
妹とは、あまり顔を見合わせることがなかったが。
たまに、貴族のパーティーなどで一緒に行く機会があった際、妹のドレス姿を見て絶句した。
妹の平凡なる顔に煌びやかなドレスは見劣りしていた。
ドレスは妹を拒否しているように見えた。
「まあ、どこかのお姫様かと思っちゃったわ」
と母は、ベタベタと妹を褒める。
自分だったら、もっときちんとあのドレスを着こなすのにな…と感じた。
母も妹も、お洒落がわからないのかとサクラは思った。
どんなに豪華に着飾っていても、パーティー会場では母も妹も見劣りする存在でしかない。それでも、母はパーティーを満喫し貴族たちと喋ることで、自分を優位に感じていたのかもしれない。
母だとは、思えず妹も悪魔だと感じるようになってサクラは一人、孤立し始めた。
父は、あまり家には帰ってこなかった。
仕事で忙しいとはいえ、本当だろうかと疑う。
たまに、父と顔を見合わせることはあっても、何かを話すわけではない。
誰にも相談できない。
毎日、苦しみしかない日々を過ごすしかなかった。
勉強も剣術の稽古も、そこまで得意ではない。
苦痛に耐えながら勉学に励んでいたとき、祖父が遊びにやって来た。
祖父は、何冊かの植物図鑑と一冊の絵本をサクラに与えた。
「跡取りになるならば、きちんと本は読んでおくように」
いつも、植物図鑑しかプレゼントしてこない祖父が何故、絵本をくれたのかはわからない。
だが、その本はサクラの傷ついた心を支える絵本となった。