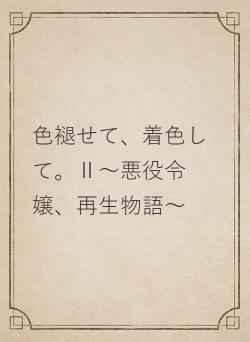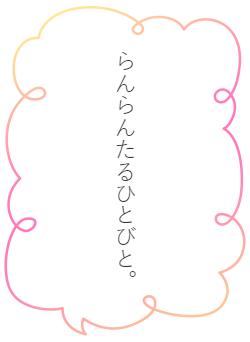「ローズさんが、人を殺していたんですか?」
あまりにも怖いことを言うので。
私はガタガタと震えだす。
「殺したのか、怪我を負わせたのか、俺にはわかりません。だけど…ローズは最強で、危険な奴なんですよ」
シュロさんの話を終えた後、ショックで頭が痛くなった。
家族に売られて、今でも家族のために懸命に働いているシュロさんを尊敬するし、どうしてそんな悲しいことが起きたのか理解が出来ない。
「俺が覚えているのは、その日までです。それからは、毎日、日記をつけることで何とか覚えようとはしています」
「日記?」
シュロさんはズボンのポケットから小さな手帳を取り出した。
「朝になったら、まず日記を読むようにはしてるんですけど…。全部読むのは面倒なので、誰かに説明してもらうことも多いみたいです」
手帳にはびっしりと文字が書かれている。
手帳をしまい込むと。
シュロさんは、ふぁぁとあくびをした。
「多分なんですけど、俺。カレンさんのこと昔から知っている気がします」
「えっ!?」
シュロさんとは、会うたびに「はじめまして」と自己紹介していたはずなのに。
初めて、そんなことを言われて驚いた。
「すいません。もしかしたら、前から会っているのに失礼なことを言っているのかもしれません」
「それは・・・」
「多分なんですけど、前も2人だけで話したことがなかったですか?」
「うぇ!?」
あまりにも驚きすぎて、大声を出した。
「覚えてるんですか?」
かつて、蘭と喧嘩した際、
私は屋敷の門の前で馬鹿みたいに号泣した。
そのとき、シュロさんが蘭の秘密を打ち明けてくれたことを今でも覚えている。
「…いえ、覚えているというか」
そう言って、シュロさんは頭をおさえこんだ。
「俺、おかしいんです。皆、俺のこと馬鹿だって言ってるけど・・・いてえ」
両手で頭をおさえこむシュロさん。
「シュロさんは、馬鹿じゃないですよ」
シュロさんの腕をつかむ。
「ごめんなさい、混乱させて…。私は蘭の妻です。だから、シュロさんとは会ってるし、2人で話したこともあります」
「やっぱり、そうですよね」
シュロさんの手を放すとシュロさんは、ふぅと苦しそうな表情をゆるめた。
「蘭と結婚してくれてありがとうございます」
あまりにも怖いことを言うので。
私はガタガタと震えだす。
「殺したのか、怪我を負わせたのか、俺にはわかりません。だけど…ローズは最強で、危険な奴なんですよ」
シュロさんの話を終えた後、ショックで頭が痛くなった。
家族に売られて、今でも家族のために懸命に働いているシュロさんを尊敬するし、どうしてそんな悲しいことが起きたのか理解が出来ない。
「俺が覚えているのは、その日までです。それからは、毎日、日記をつけることで何とか覚えようとはしています」
「日記?」
シュロさんはズボンのポケットから小さな手帳を取り出した。
「朝になったら、まず日記を読むようにはしてるんですけど…。全部読むのは面倒なので、誰かに説明してもらうことも多いみたいです」
手帳にはびっしりと文字が書かれている。
手帳をしまい込むと。
シュロさんは、ふぁぁとあくびをした。
「多分なんですけど、俺。カレンさんのこと昔から知っている気がします」
「えっ!?」
シュロさんとは、会うたびに「はじめまして」と自己紹介していたはずなのに。
初めて、そんなことを言われて驚いた。
「すいません。もしかしたら、前から会っているのに失礼なことを言っているのかもしれません」
「それは・・・」
「多分なんですけど、前も2人だけで話したことがなかったですか?」
「うぇ!?」
あまりにも驚きすぎて、大声を出した。
「覚えてるんですか?」
かつて、蘭と喧嘩した際、
私は屋敷の門の前で馬鹿みたいに号泣した。
そのとき、シュロさんが蘭の秘密を打ち明けてくれたことを今でも覚えている。
「…いえ、覚えているというか」
そう言って、シュロさんは頭をおさえこんだ。
「俺、おかしいんです。皆、俺のこと馬鹿だって言ってるけど・・・いてえ」
両手で頭をおさえこむシュロさん。
「シュロさんは、馬鹿じゃないですよ」
シュロさんの腕をつかむ。
「ごめんなさい、混乱させて…。私は蘭の妻です。だから、シュロさんとは会ってるし、2人で話したこともあります」
「やっぱり、そうですよね」
シュロさんの手を放すとシュロさんは、ふぅと苦しそうな表情をゆるめた。
「蘭と結婚してくれてありがとうございます」