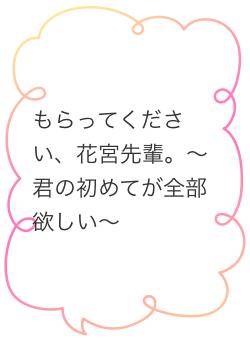高槻さんを好きになったきっかけ。それはとても単純なものだった。
「……なんだか、元気ないね。大丈夫?」
「────え」
そう彼女から声を掛けられた時、俺の精神状態は崖っぷちだった。
入社5ヶ月目、毎日毎日残業残業、取引先への営業、慣れない愛想笑い、疲れ切った頃に大きなミスをやらかし、上司から怒鳴られ取引先からは嫌味を言われ、ぎりぎり繋がっていた糸がプツリと切れるように、俺は決心した。
もう辞めよう。向いていないんだと。
この資料を届けたら、上に相談しよう。そう思い経理部を訪ね、対応してくれた高槻さんが心配そうに声を掛けてくれた。
その問いかけに対して返事をするでもなく、ただ曖昧に視線を落とすだけの俺を見て、それ以上なにも聞こうとはせず、高槻さんは資料に目を通しながら話を続ける。
「営業は大変だよね。私の同期も、新入社員の時よく悔し泣きしてたよ。係長すぐ怒鳴るし、嫌になっちゃうよね」
「…………はい」
「それでね、同期に教えて貰ったんだけど、どーーしても我慢ならないことがあったら、脳内で自分に不快な思いをさせてる相手をボコボコにするんだって。そりゃもう、ギッタンギッタンに」
「え」
「大切なことはちゃんと聞く、それ以外の言葉は聞き流す。流せなければボコボコ。これだけで結構楽みたい。もちろん私も試したよ」
「……ずいぶん物騒ですね」
「まぁ、とにかくね」
高槻さんは、書類をトントンと揃え机に置く。そして、引き出しから出した付箋に何かを書き込むと、俺のスーツにペタリと貼った。
「入社5ヶ月、今が踏ん張り時。半年やってダメならその時はその時」
「なんですか、この付箋」
「頑張れ、新人くん」
バクン。心臓が大きく鳴り響く。
高槻さんの浮かべた優しく包み込むような笑みが、俺の心の中の全てを持っていった。
スーツに貼られた付箋には、『頑張れ!』とキレイな文字が並んでいる。
この理由を聞く人間は、それくらいのことで落ちるか?と言うかもしれない。けど、弱っていた俺にいち早く気付いてくれた。俺は表情の変化があまりないから、察する人間も少ないのに。
もう、心を鷲掴みにされたように、とにかくキレイに撃ち抜かれた。この人を自分のものにしたい、振り向いて欲しい、そんな欲に駆られた。
「頑張り、ます」
今が踏ん張りどき、その言葉を信じてみようと思った。そして、半年、一年、俺は仕事にも慣れ、営業としての結果を残せるようになった。
そして────。
「小宮さん」
「なに?今度の取引先の件?」
「北海道土産、高槻さんの好み分かります?」
「……ついに動く時?」
「頃合いかと」
「へぇ〜……」
喫煙室で男物のタバコを吸う、キレイな顔の女上司に声を掛ける。小宮さんは高槻さんの同僚で、何かと二人でいるところを見かける。俺の発言に目を丸くし、一気にタバコを吸い込んだ小宮さんは頭を掻いた。
営業部では、俺が経理に書類を持っていくのが決まり事のようになっている。
まぁ、その原因は先輩が書類を持って行こうとした時に押し問答になり、そこで理由を言えとほぼ無理矢理、高槻さんのことを吐かされたからだ。
そして、一週間後には営業部内どころか経理にまで伝わる程の噂になっていた。周りから生ぬるい視線を向けられたけど、その不快感と天秤にかけても、俺は高槻さんに会える方を選んだ。
肝心の高槻さんは何も知らないようで、ずっと変わらず俺からの書類を受け取ってくれていたのが救いだ。
小宮さんは目を瞑り小さく唸った後、俺に視線を向けた。
「黒岩さぁ、あの子の年齢分かってる?」
「はい」
「アラサー、結婚を前提に同棲中の彼氏あり。そこに横槍入れる意味分かってる?」
「もちろん」
「真剣ってこと?」
「真剣でしかないです」
「……へぇ」
「好きなんです。あの人が」
俺の答えを聞いた小宮さんは、そう、と小さく返事をし、タバコを灰皿に押し付ける。そして口角を上げた。
「じゃあ、やるだけやってみれば?ちなみにあの子は六花亭のバターサンドが好き」
「了解しました。聞いて教えてもらえなければ、それを買ってきます」
「私は応援してるよ」
「え」
小宮さんは二本目のタバコを取り出し、火をつける。そして口を開いた。
「健闘を祈る」
※※※※
目が覚めると、隣に寝ていたはずの高槻さんの姿は消えていた。部屋中を探し、玄関に靴がないことで帰ってしまったことを知り、死ぬほど後悔をした。
小宮さんが原因とはいえ、高槻さんの可愛さと揺れているであろう態度を見て、強引にコトを進めた自覚はある。けど、そこまでしてでも手に入れたかった。心底嫌がられたらやめるつもりだった。
朝起きたらきちんと話そう、そう思い、行為後にすぐ眠ってしまった高槻さんの横で眠ってしまったのがいけなかったんだ。
────高槻さんは、後悔したのかもしれない。
所詮酔った勢いだった。帰りたくないと言った現実に戻っていったんだ。
黙って出て行ったということは、追われることを望んでいない。追おうにも、連絡先も知らない。会えるのは会社だけ。
「…………はぁ」
深い溜息が溢れる。付け入る隙は閉じられてしまったのに、愛しさは更に大きくなってしまった。
重なり合った昨日の夜が、遠い昔に感じる。
※※※※
────あの夜から一ヶ月。
私は、付箋を貼った書類を片手に営業部に向かい脚を進めていた。
ごくごく簡単な確認作業、いつもは電話で済ませてしまうのに、今日はそういうわけにいかなかった。
営業部に辿り着くと、私はドア付近で目当ての人物の名前を呼ぶ。
「すみません、黒岩さんはいらっしゃいますか?」
「────高槻さん?」
「わっ」
突然後ろから名前を呼ばれ、振り返るとそこには驚いた顔をした黒岩くんが。
彼と話すのは一ヶ月ぶりになる。この前の営業部の書類も黒岩くんでない人が持ってきたから、きっと避けられていたんだろう。
だから私は今日、ここに来た。
「今、時間ある?」
「……少しなら」
「そっか。じゃあちょっと書類の訂正お願いしたいんだ」
「了解しました」
「あと、彼氏と別れました」
「そうですか………え?」
「自分の幸せ考えてみたくなってね。揉めに揉めたけど、やっと落ち着いたから」
「……ちょっと、すみません。気持ちが追いつかないんですけど」
黒岩くんは口元を手で覆い、顔を真っ赤にした後、グイッと私の手を引き歩き出した。
私はあの夜を経験し、自分の中にあった本当の気持ちを隠せなくなってしまった。
他人の望む自分になり、与え続けても、辿り着くのは外から見た『幸せ』であって、私自身の幸せではないと、改めて気付かされてしまったから。
燻んだ日々より、自分の人生は自分のものであると言い切れる、きらめいた主役の日常を選びたくなったんだ。
別れを切り出した時、優斗は泣き縋ってきたけど、不思議と未練も後悔も感じられなかった。
「高槻さん」
辿り着いたのは、誰もいない会議室。パタンとドアが閉まり、黒岩くんが私の手首をゆっくりと放す。
そして、私の瞳をじっと覗き込んできた。
「嫌われたかと思ってました」
「そうなの?」
「連絡先も知らないから謝れないし、会社で話しかけるのも嫌かなと思って」
「そっか」
「……強引だった自覚もあります」
「……うん」
「けど」
頬に黒岩くんの指先が触れる。途端にそこからじわりと熱が広がっていく。
「別れたって伝えにきたということは、期待してもいいってことですか?」
シンとした室内に、二人分の呼吸音、縮まる距離、そして────。
「好きなんです。幸せ、保障させて下さい」
私の片手を取り、懇願するように眉を下げる彼。
たまらない幸せが、心に浸透していく。足りなかった部分が、溢れる程に満たされていく。
アラサー、結婚、世間体、もうどうでもいい。自分が自分であるために生きる。
「黒岩くん」
「はい」
「保障、してね」
私の答えと同時に、塞がれる唇。目を閉じて何度も重なるそれを受け入れながら、私は考える。
まずは連絡先を交換しないと。私の手に持っていた書類が、床にひらりと落ちる。
そこには、私の連絡先が書かれた一枚の付箋が貼られている。
『 正しい『幸せ』保証致します。 』おわり