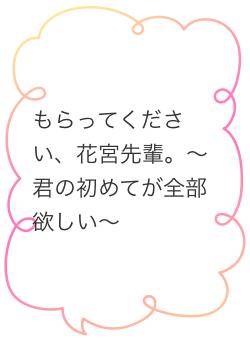心地よい揺れで意識が浮上した。
薄く瞼を開くと、ここはどうやら車内らしい。窓の外で街の夜景が流れていく。
美穂子と飲んでいたはずなのに、アルコールのせいで最後の記憶が途切れ途切れだ。いつもならそのまま泊まっていくのに、私が帰ると言ったのだろうか。
────というか、私が寄りかかってるのは誰の肩なんだろう。なんだか硬くて、寝心地が悪い。
「高槻さん、起きてますか」
「…………んぅ、だれ」
「黒岩です。小宮さんが高槻さんの住所教えてくれなかったんですけど、言えますか」
「……えーと、じゅうしょ、えへへ、どこだっけ」
「……ハァ、夜中に電話してきたかと思えばこんな状態で放り出すなんて、あの人何考えてるんだ」
「……これ、夢?」
私に肩を貸してくれていたのは黒岩くんだった。さっきから何かブツブツ言ってるけど、もう何が何だか分からない。
だっておかしい。夢でしょ、こんなの。黒岩くんがこんな夜中に私のことを迎えに来るはずなんてないもの。
なんだか楽しくなって肩を揺らして笑う。すると、そんな私に呆れたような、静かな声がした。
「何笑ってるんですか」
「えー……だって、黒岩くんがいるんだもん」
「それはいますよ。呼ばれたので」
「んん?よばれた?」
「はい。小宮さんが、高槻さんが俺を選んだとか訳が分からないことを言ってました」
「…………やっぱり、夢?」
「夢じゃない」
「やっぱ夢だよ、夢ならいいのかな」
私は黒岩くんの肩に寄りかかったまま、勝手に納得する。
もしこれが現実なら、今すぐにでもこのタクシーを降りて一目散に帰らなければならないけど、夢の中なら、アラサーで同棲してる彼氏がいるとか、理性的なこと考えて行動する必要もない。
あぁ、やだな。現実。
そう、私現実が嫌なんだ。
「待ってください。もう一度小宮さんに連絡しま」
「…………くない」
「は」
「────かえりたくない」
「っ……」
車内に、私の情けない本音が響く。
本当は、私がいないと汚れもゴミも放置され、家政婦のように手を動かし、無理に笑顔でいなければならない息が詰まるようなあの部屋に帰りたくない。
本当は、私のことを母親のように、居て当たり前だと思っている優斗の元に帰りたくない。
本当は、結婚しても心から『幸せ』になれないと分かっていながら、年齢と世間体を気にして手放せない、あの燻んだ日常に帰りたくない。
本当は、私が私を大切だと、主役だと言い切れる場所に、全てを捨てて走っていきたい。
「……言質、とりましたからね」
静かな声、妙な沈黙。そして、その空気を打ち破るように黒岩くんは身を乗り出した。
「運転手さん、行き先変更して下さい」
「黒岩くん……?なんれ」
「酔っ払いは黙ってろ」
ぴしゃりと遮られ、黒岩くんが運転手さんに住所を伝えるその声を聞きながら、私は再び瞼を閉じた。
※※※※
「────高槻さん」
「んんぅ……なに?」
「起きてください」
「……ねむい」
ぽすんと身体を柔らかいソファーの上に降ろされる。
どうやら背負われていたらしく、私を下ろした黒岩くんの背中がすぐそこにあった。程よく筋肉のついたかっこいい背中だな、なんて思ってると、蓋が外されたペットボトルを差し出される。
「はい、水どうぞ」
「……ありがと」
「外であまり飲まない方がいいですよ、高槻さんは」
「なんで……?」
「酔うと、いつもの数倍可愛いので」
「へ」
寝かされていたベッドから身体をゆっくり起こし、水を飲む私の顔を黒岩くんが覗き込む。その表情は、いつも通りの真面目な黒岩くんで、言葉とのギャップに困惑する。
可愛いなんて久しぶりに言われて、年甲斐もなく照れてしまう。夢ってすごいな。
黒岩くん、至近距離でもカッコいい……って、あれ?
待って、これ、夢だよね?夢にしてはリアルな気がする。このシーツの感触とか……。
「く、ろいわくん。これって夢」
「残念ですが現実です」
「…………は?」
「高槻さん、酔っていて家の場所も言いませんし、うちに連れてきました」
「えっ?!」
「小宮さんに聞こうにも、電話出ませんし」
ガバッと勢いよく起き上がると、そこは見知らぬアパートの一室だった。
綺麗に整頓されてはいるが、インテリアや干してある洋服から、男の部屋ということは分かる。夢じゃない、ここは完全に黒岩くんの部屋だ。冷や汗が背中を伝う。
な、なんでこんなことに……!!いや、私のせいなんだけど、けどまず美穂子が悪いでしょ!
とにかく私は動揺を隠し、ソファーの上に正座し、黒岩くんに頭を下げる。
「情けない姿を見せてごめんなさい」
「いきなり酔いが醒めるんですね。さっきまであんなにふわふわしてたのに」
「……だって、夢だと思ったから」
「……へぇ」
黒岩くんは床に座り、ソファーの上で正座した私を見上げる。意志の強そうな瞳に真っ直ぐ見つめられ、心臓がドキリと鳴った。
ダメだ、落ち着け、ときめいたらいけない。揺れたらいけない。私は視線を彷徨わせる。
どうしよう、早く帰らないと────。
「酔うと、本音が出ますよね」
「え?」
「貴方が帰りたくないって言ったんですよ」
その言葉に、私は黒岩くんに視線を戻す。相変わらず黒岩くんは私を射抜くように見つめていた。そして、その視線はさっきよりも熱く強くなっている。
確かに言ったかもしれない。けど、そんなの酔っ払いの戯言だと思って聞き流してくれたらいいのに。
自分を騙すことに慣れていたのに、お酒を飲んだくらいでこんな風に本音を知られてしまうなんて。いい歳して恥ずかしい。忘れてほしい。
「帰りたくないなら、やめればいいんです」
「やめるって、何も知らないのに勝手なこと言わないで」
「帰りたくない場所にいる相手と、結婚を前提になんて言われて、納得できない」
「納得って、私黒岩くんに連絡先も教えてないし、思わせぶりなことなんて何もしてないよね?そんなこと言われる筋合いない」
思わず言葉が強くなる。突き放すような私の態度に、黒岩くんは引き下がることなく食らい付いてくる。
もう放っておいてほしい。これでいいと思ったの。私の生き方はこれでいいと。
田舎の母親から、結婚はまだか孫はまだかと定期的にくる連絡の煩わしさ。周りがどんどん身を固めていく中、取り残されているような不安な感覚。世間は女性が自由であることに、思った以上に厳しい。
その全てを解決してくれるのが優斗の存在なの。
私さえ我慢していれば、そのうち結婚して、世間から見た『幸せ』に私もなれる。そう、私は幸せでなくとも。周りから、私は『幸せ』なんだと、思ってもらえる。
思考回路がグチャグチャだ。頑張ってきたのに、無理してきたのに、黒岩くんが私の前に現れたから、隠していた本音が出てきてしまった。
逃げるように両手で顔を覆った私に、黒岩くんは口を開く。
「筋合いならあります」
「ない」
「付け入る隙があるんです。貴方には」
「だから、ないって」
「だったら、なんで俺からのお土産を受け取るんですか」
「……断れないでしょ」
「本気で嫌だったら、なんとでも言い訳できる」
「じゃあ次から受け取らない」
「逃げるくせに、捕まえられたら満更でもなさそうに無防備に笑う。視線を送れば恥ずかしそうに逸らす」
ギシッとベッドのスプリングが軋む。目の前に黒岩くん引き締まった身体があって、私の横に手をついている。心臓がドクドクと鳴り響き、身体が熱を帯びていく。ダメだ、ダメ。こんなの。
「連絡先を受け取らないだけでなく、全て拒否すればよかったんだ」
「…………」
「同棲してる彼氏を愛してるって言えばいい。今が幸せだと」
「……それ、は」
「俺は本気なんです。本気だからこそ、好きな女の嫌なことはしない」
「だったら────」
「言ってください。彼氏を愛してるから、俺のことは好きになれないって」
ズルい。ここまで私の気持ちを好き勝手に暴いておいて、ここで判断を委ねてくるなんて。
私から優斗に対する、愛してるなんて気持ちはとうの昔に消え去っている。けど、人間は理性的な生き物だ。本能的に見えて、先のことをいつでも考えている。
────私って、なんなんだろう。
未来のために頑張って作り上げてきた日常、私の我慢の上に成り立つ生活、周りからの私の女としての評価。結婚し、『普通』に収まることが正解だと思い生きてきた。年齢も29になる。
『幸せ』になることで、私自身は幸せになれない。分かっていながら、情けない。
────本当は、黒岩くんのことが、もっと知りたいのに。
私は、唇を震わせる。
「私、は」
「はい」
「────幸せに、なりたいの」
「…………は?」
「どうしたらいいと思う?」
質問の答えになっていない。それどころか、私もズルい質問をしていると思う。感情が昂りすぎて視界が揺らめく。
黒岩くんは、驚いたように目を見開き、次に顔を伏せた。そして長い溜息をつく。
「そんなの、決まってるでしょう」
「……教えて」
「幸せ、保証します」
────そして、冒頭に至る。
黒岩くんに答えを求めておいて、やはり怖気付きそうになった私を見ても、彼は止まってはくれなかった。
キスがこんなにも気持ち良いものだと、この年齢で初めて知り、はち切れそうな脳内はパンクしそうになる。
「俺のものになればいい」
────そんなの、無理に決まってる。
だって私は、結婚がしたいんだから。世間でいう『幸せ』を手に入れ、安心したいんだから。
けどその反面、黒岩くんのものになりたいと叫ぶもう一人の自分がいる。
だって、外側の『幸せ』ではなく、私の幸せを保障すると言ってくれたんだもの。
指輪の抜けた薬指が軽い。きっとこれが答えだ。
部屋の隅に置かれた私の鞄から、スマホの小さな振動音が聞こえる。それを知りながら、私はそっと黒岩くんの背中に腕を回し、襲いくる快感に酔いしれた。