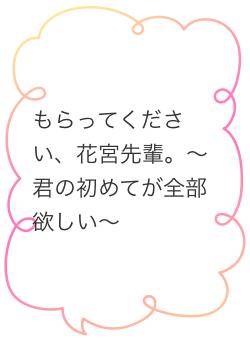────私の人生は、私のものである。誰かの人生の脇役じゃない。
そんなこと、当たり前と言われればそれまでだが。その言葉のまま生きるのは、簡単なように思えて意外に難しい。
いつか自分が物語の主人公のようにスポットライトを浴びるなんて、そんなことを望んでいたわけではない。
スポットライトを浴びる主人公の横でいい、普通の人生でいい。
もう、誰かの人生の脇役に甘んじていてもいいの。
世間でいう『幸せ』を手に入れたい、ただそれだけだった。
……なのに。
「何考えてるの」
────今、私に跨る体躯の良くて私よりずっと若い、整った顔の彼は、私の薬指に嵌る、年期の入り燻んだ指輪を無理矢理外すと、不機嫌そうにベッドサイドに投げ捨てた。そして、どろりと独占欲を孕ませた双眸でこちらを見下ろす。
「……体裁ばっかり気にするんですね」
「だ、だって……どう考えてもおかしいもの」
「何が」
「私、今年で30なのよ?黒岩くんは24でしょ……そんな若い人が」
「自分のこと、本気で好きになるわけないって?」
「っ」
「……よくそんなこと言えますね。俺がどんな気持ちか知ってるくせに、無抵抗に押し倒されておいて」
ドキリ、図星を突かれ気まずくて目を逸らす。すると、カサついた指先で輪郭を撫で上げられ、耳朶を遊ばれる。それだけで息が上がり、肌が粟立ってしまう。
普段は眉間に皺を寄せ、仕事のこと以外眼中にないような真面目な彼が、今は私の一挙一動全てを見逃さぬよう、じいっと私だけを瞳に映し、熱の籠った視線を送ってくる。
そして、行き場もなく自分の身体を抱き締めるようにしていた私の両腕を取り、あっという間にシーツに縫い付け、グッとお互いの呼吸が分かってしまうほど距離を詰めてきた。
そして、耳元に唇を寄せ、熱い吐息と共に、私の凝り固まった思考を溶かす言葉を吹き込む。
「俺のものになればいい」
────そんなの、無理に決まってる。
だって私は、結婚がしたいんだから。世間でいう『幸せ』を手に入れ、安心したいんだから。
そう続くはずだった言葉は彼の薄い唇に飲み込まれる。お互いの舌が触れ合い、性急に貪るように口内を蹂躙され、息も絶え絶えになった時にはシャツのボタンは全て外されていた。
彼がハァと深く息を吐き、ネクタイを雑に外してその辺にポイと投げる。そして、抵抗虚しく再び唇を重ねられ、私は諦めるのと同時にそっと目を閉じた。
※※※※
────不安定な恋なんて不必要、欲しいのは、安定した揺るぎない愛。つまりは『幸せ』
そんなことを頭の片隅で反芻させながら、今日も今日とてデスクワークをこなす。
私、高槻由紀乃は今年30になる。それなりに名の知れた会社に大学卒業と共に奇跡的に就職し、経理部に所属して早数年。ありきたりな日々は変わらない。
一日中同じ姿勢をしているせいで固まった背中を伸ばすべく、グッと逸らしてみるとゴキッといい音がした。そのままこめかみを揉み、再びパソコンに向かう。
入社当初若かった私も、いつの間にかアラサー。同期達は次々『幸せ』を掴み寿退社をしていった。
私はいつそれを掴めるのだろうか。日々妙な焦燥感を感じる。
「高槻さん、これ、よろしくお願いします」
「わっ……ありがとう」
「すみません驚かせて」
黙々と伝票入力していると、突如隣から低い声が降ってきた。肩をビクつかせながら視線をそちら向けると、毎月営業部から経理部まで書類を届けにくる、若きエース黒岩くんがこちらを見下ろしていた。
私は書類を受け取りながら、チラリと隣に立つ黒岩くんを見上げる。うん、何度見ても女の子達が騒ぐのも頷けるルックスだ。
180以上あるであろう身長、スラリとした長い脚、スーツの上からでも分かる、鍛えられた程よく筋肉質な身体。学生時代はきっと運動部だ。
そして顔もかっこいい。彫りが深く、くっきりとして整った目鼻立ちに、サッパリとした短い黒髪はワックスでセットされていて、清潔感もある。
そして仕事もできて真面目で若いんだから、女の子達が騒がない理由なんて見つからない。
私は頭の片隅でそんなことを考えながら、貰った書類を確認し、口角をキュッと上げ黒岩くんを見上げる。
「この付箋が貼ってあるのは、先輩のだよね。ここのところ毎月遅れてるから、ちゃんと提出するように伝えておいてね」
「はい」
「毎月お疲れ様。確かに受け取りました」
「…………」
もう戻っていいと言ったつもりだったんだけど、何故か黒岩くんはじっとこちらを見下ろし黙りこくっている。
私何か顔に付いてるのかな?さっき食べたチョコレート?30目前の女が、口に食べカスつけてるなんて恥ずかしい。可愛くない。思わず口元を手でサッと隠すと、黒岩くんはやっと薄い唇を開く。
「今度、営業で北海道に行くんです」
「えっ、そ、そうなんだ……?」
「お土産、何か欲しいものありますか」
お土産、お土産……?
その言葉を噛み砕き飲み込むまで、時間が掛かった。だって、私は黒岩くんにお土産を貰うほど仲良くもないし、ましてや会話だって月に一度、仕事上のこのやりとりのみだ。
なのに、お土産、私に?いや、多分、絶対違う。やっと理解できた。
「経理部は結構甘党が多いから、無難に白い恋人とか……みんな喜ぶと思うよ」
「高槻さんは」
「へ」
「高槻さんは、何が欲しいんですか?」
私の答えはどうやら間違えていたらしい。黒岩くんは表情を変えず、もう一度『私』にその答えを求めてくる。
お土産、欲しいもの、そんなに急に聞かれても……。
私が困ったように首を傾げると、黒岩くんは小さく息を吐いた。
「それじゃあ、俺が適当に選んできます」
「待って、大丈夫だよお土産なんて。気を遣わなくて」
「俺が高槻さんにあげたいので。それでは」
くるりと踵を返した黒岩くんを、呆気に取られながら見つめる私。
そして、気付いてしまった。黒岩くんの耳が赤く染まっていることに。
いや、まさか、そんな。
「(え〜〜〜……?)」
その後ろ姿が見えなくなるまで放心していると、後ろから肩をポンと叩かれる。振り返ると、後輩の朝井さんが楽しそうに微笑んでいた。
「先輩、鈍過ぎですよ〜」
「いや、鈍いとかじゃなくてね」
「毎月必ず先輩のところに来て、あれだけ熱視線送っても気付いて貰えないもんだから痺れを切らしたんでしょうね」
「………はい?」
「黒岩くんがモテるのは有名ですけど、それと同じくらい有名な噂があって」
「やめて、聞きたくない。頭が痛い」
私の静止なんてなんのその、朝井さんは言葉を続けた。
「黒岩くんが高槻さんに片想いをしてるって」
片想い、なんてパンチのある言葉なんだろう。私は椅子から転げ落ちそうになる。
あんなに若くてかっこいい、女の子選び放題な男が?三十路の私に?ぜひ辞めることを勧める。
朝井さんは言うだけ言って、それはもう楽しそうに自分の席に戻っていった。私は動揺を隠すように、さっき黒岩くんから預かった書類に視線を落とす。
すると、貼られた付箋の中に気になるものを見つけた。
「…………ふぅーーー」
そこには、電話番号とチャットアプリのID、そして黒岩くんの名前がキレイな字で書いてあり、頭を抱える。
あの子、真面目なのに一度動き出したら結構攻めてくるんだな。私はその付箋を剥がし、サッとポケットにいれる。
気付かなかったことにして、後で処分しよう。黒岩くんには申し訳ないけど、連絡をするつもりは毛頭ない。
この年齢で、新しい出会いなんていらないし刺激も欲してはいない。
求めるものは安定、安心。要するに、結婚に結びつかない浮ついた感情なんて、求めてはいない。
────求めてはいけない。
※※※※
「はぁ……」
私はアパートのリビングの電気をつけ、大きな溜息を吐く。
洗濯カゴがあるのに、その横に脱ぎ散らかされた裏返しの洋服、玄関で不揃いに並んだ靴、食べ終わりそのままシンクに置かれ、水につけられていない食器、水の飛び散った流し台。
寝室から微かに聞こえるイビキをBGMに、私はその一つ一つをリセットするように片付けていく。これが私の仕事から帰り毎日行うルーティンだ。
結婚を前提に同棲をしている彼氏、優斗は、仕事柄夜勤が多い職種に就いている。だから、私が夕方に帰ったとしても眠っていることも多い。
家事は最初は分担していたものの、今は私がほぼ全てをこなしている。言ったところで返事だけだからだ。
些細なことの積み重ね、しかし積まれれば積まれるほど、それは重く深く私の心の大部分を占めていく。
「私、何してるんだろ」
汚れのこびり付いた皿をゴシゴシと擦りながら呟く。
2年前、同棲したての時、直してくれることを願い注意した時期もあった。しかし返事だけで、何度も何度も繰り返す。そして毎回喧嘩になり、私は疲れ果て、諦めてしまった。
結婚は諦めが肝心。昔から母に何度も言われてきた台詞が脳内でリフレインする。結婚もまだしていないのにこれか。
けど、同棲もして『幸せ』を手に入れる目前なんだから、余計なことを考えるのは良くない。
私の人生は私のもの、誰かの人生の脇役ではないなんて綺麗事だ。
人は常に誰かの人生の脇役であって、歯車にすぎない。
それでいい、それでいいんだ。今更手放せない。きっとこの暮らしを、日常を手放したら、この先わたしが『幸せ』になれる未来がイメージできない。
「由紀乃……?おかえり」
寝室から寝起きの優斗が出てくる。私は軋んだ心を誤魔化すように笑みを作り、振り返る。
「ただいま」
※※※※
「高槻さん」
社員食堂で食事を終え、トイレで化粧直しをし、さぁオフィスに戻ろうというところで声を掛けられびくりと肩が跳ねる。
ギギギッと振り返るとそこには、ここ数日、声を掛けられそうになる度避けていた相手、黒岩くんが立っていた。
その表情はどこか不機嫌そうで。けど、私はそれに気付かないふりをし挨拶する。
「黒岩くん、お疲れ様」
「俺のこと避けてますよね」
「え」
「幾らなんでも分かりやす過ぎます」
「……そんなことないよ?」
「これ」
「……なにこれ」
黒岩くんは煮え切らない表情をしながらも、私に紙袋に入った何かを差し出す。
袋の中を覗くと、六花亭のバターサンドのパッケージが。うわうそ、これ。
「めちゃくちゃ好きなやつだ……!!」
「散々避けられたので、賞味期限ギリギリですよ」
「あ、そっか……北海道のお土産か」
「渡したいから話し掛けようとしてたのに、逃げ回りすぎです。連絡もくれませんし」
「……しないよ」
「して下さい」
「する理由がない」
黒岩くんは呆れたようにこちらを見つめる。
けど、逃げられても仕方ないと思う。だってあんな噂聞いて、尚且つ連絡先の書いてあるあの付箋、私だけに非があるわけでは絶対にない。
けど、黒岩くんのこちらを責めるような雰囲気のせいで、私は何も言い返すことができない。私は貰ったお土産を胸の前でぎゅっと抱きしめながら、視線を泳がせる。
「……だって」
「俺が高槻さんに片想いしてるって、聞いたから?」
黒岩くんの言葉に、わたしの肩はびくりと震える。反応してしまったせいで図星だとバレてしまったらしく、ジリジリと距離を詰められる。幸いこの場に人がいないからいいけど、この妙な光景を誰にも見られたくはない。
また新たな噂にでもなったとしたら────。
その時、ペタリと私の背中が壁にくっ付いた。逃げ場を失ったことに気付き、私は顔を青くする。黒岩くんはそんな私を人一人分の距離を空け、見下ろした。
「逃げないで下さい。追いたくなる」
「何その捕食者みたいな台詞」
「今更ですよ。みんなが知ってます。俺が高槻さんを────」
「私、結婚を前提に同棲してる彼氏がいるの」
私の言葉に黒岩くんは唇を閉じ、眉をピクリと動かした。
私に彼氏がいて同棲していることを、この社内の人達はあまり知らない。私が自分のことを話さないのもあるけど、まさかこんな場面で言うことになるとは。
けど、きっとこれで黒岩くんも引き下がってくれるはず。
「別に気にしません」
「…………はい?」
「まだ結婚してないんですよね」
「え、まぁ、そうだけど」
「俺、片想いは慣れてるんで」
黒岩くんは、なんて事ないという表情でこちらを見る。いやいやいや、おかしいでしょ。
「気にするのは私だから」
「なんでですか」
「彼氏がいるのに迫られたら困るでしょ?」
「嫌なら本気で抵抗すればいいですし、振り向かなきゃいいだけの話ですよね」
「……はぁーーーー」
「俺、引く気ないんですよ」
この子、こんなに聞き分けがなくてわがままだったんだ。というか、絶対こんなの遊びでしょ。こちとらもうすぐ30なのに。
私は黒岩くんをジロリと見上げる。
「アラサー騙そうったってそうはいかない」
「騙してません。本気です」
恐ろしいほど真っ直ぐな声だった。この前と同じように、黒岩くんの耳は赤く染まっている。
え?待って、その反応はズルくない?
迷惑だと思う反面、私の心は少しだけ揺れていた。不安定な恋愛などしない、欲していないはずなのに。
────どうしてだろう。
「ずっと、高槻さんに恋してました」
アラサーの私が欲しいのは、世間的に言う、『幸せ』なはずなのに。