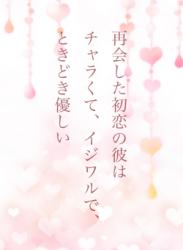「そういえば仰ってましたよね。他に好きな方がいると...」
「ああ。ん?アルマ、その手...」
アルマのケガに気づいて近づいたが、アルマは心配して欲しくないと思い、後ろに下がった。
「だ、大丈夫です。バラの棘でケガしただけなので」
「尚更手当てしないとダメだ!見せてみろ」
「ボクはメイドです。ケガくらい自分で手当て出来ます!」
「だったら何故、泣いているんだ!?」
涙?ボク泣いていたんだ。あんなに我慢していたのに。
ルイス様の声が優しくて愛おしくて...それで安心して涙が堪えきれなくなってたんだ。
「ケガなんてどうでもいいです。.....ルイス様ボクの話を聞いてくれますか?」
ルイスは無言で頷いた。
「ボクがお父様とパーニスに行かなかったのはルイス様。あなたの傍に居たかったから」
「ああ。ん?アルマ、その手...」
アルマのケガに気づいて近づいたが、アルマは心配して欲しくないと思い、後ろに下がった。
「だ、大丈夫です。バラの棘でケガしただけなので」
「尚更手当てしないとダメだ!見せてみろ」
「ボクはメイドです。ケガくらい自分で手当て出来ます!」
「だったら何故、泣いているんだ!?」
涙?ボク泣いていたんだ。あんなに我慢していたのに。
ルイス様の声が優しくて愛おしくて...それで安心して涙が堪えきれなくなってたんだ。
「ケガなんてどうでもいいです。.....ルイス様ボクの話を聞いてくれますか?」
ルイスは無言で頷いた。
「ボクがお父様とパーニスに行かなかったのはルイス様。あなたの傍に居たかったから」
これだけ言えればボクは満足。
「まだ、何か言いたいことがあるんじゃないのか?」
お見通しか。
「...はい。ルイス様の言う通り。まだ沢山言いたいことあります。聞きたいですか?」
「出来ることなら聞きたい」
「ひとつ、約束をして下さい。ボクが話す代わりにルイス様がボクのことどう思っているか聞かせて下さい」
こんな賭け。無意味だってよく分かってる。無意味だと分かっていてもボクはもう、こうしないと自分の気持ちを伝えられない。
「分かった。それで話してくれるなら。俺は、お前のことを...」
「妹みたいに思っている」
アルーシャ様!?どうしてここに。今の話もしかして聞かれていたかもしれない。
「アルーシャ、様...」
「そうでしょ?ルイス」
「はい....」
「アルマ聞いての通りよ。もうこれ以上、私たちの邪魔はしないでちょうだい。行きましょうルイス」
ルイスはアルマに背を向け、アルーシャと共にバラ園を出ていった。
一人の女性としてルイス様の心には居なかったことを知り、アルマはその場に泣き崩れた。
ルイスにとって、ボクは妹みたいな存在だった。一人の女性として見られなかったことがとても悔しい。
賭けなんてしないで正直に想いを伝えれば良かった。
もうボクにはルイス様を愛する資格は無くなったんだ。
「まだ、何か言いたいことがあるんじゃないのか?」
お見通しか。
「...はい。ルイス様の言う通り。まだ沢山言いたいことあります。聞きたいですか?」
「出来ることなら聞きたい」
「ひとつ、約束をして下さい。ボクが話す代わりにルイス様がボクのことどう思っているか聞かせて下さい」
こんな賭け。無意味だってよく分かってる。無意味だと分かっていてもボクはもう、こうしないと自分の気持ちを伝えられない。
「分かった。それで話してくれるなら。俺は、お前のことを...」
「妹みたいに思っている」
アルーシャ様!?どうしてここに。今の話もしかして聞かれていたかもしれない。
「アルーシャ、様...」
「そうでしょ?ルイス」
「はい....」
「アルマ聞いての通りよ。もうこれ以上、私たちの邪魔はしないでちょうだい。行きましょうルイス」
ルイスはアルマに背を向け、アルーシャと共にバラ園を出ていった。
一人の女性としてルイス様の心には居なかったことを知り、アルマはその場に泣き崩れた。
ルイスにとって、ボクは妹みたいな存在だった。一人の女性として見られなかったことがとても悔しい。
賭けなんてしないで正直に想いを伝えれば良かった。
もうボクにはルイス様を愛する資格は無くなったんだ。
バラ園を後にした二人はアルーシャの部屋から泣き崩れているアルマの姿を見ていた。
「これがあなたが見たかった光景ですか」
「えぇそうよ。私たちの邪魔をするアルマの哀れな姿を見たかった。あの子がルイスのことを好きになるなんて百年早いのよ」
紅茶を飲んで満足気な顔で本心を語ったアルーシャの姿はとても恐ろしく思えた。
「そこまでして俺と結婚なされたいのですかあなたは...」
「あら?お怒りね。でもルイス。あなたには選択肢がないのよ。あなたの父、ジャック様の言いつけを守らないとここには居られないんの忘れた訳じゃないわよね?」
唇を強く噛み、怒りを堪えた。ルイスはアルマの姿を見ていられず、アルーシャの部屋を出ていった。
城内の人気の無い場所に移動したルイス。階段を何度も拳で殴り、怒りをぶつけた。
落ち着きを取り戻すとその場に座った。
「あの人の言いつけは絶対...。俺は一体どうしたらいいんだ。...アルマすまない。俺にはお前を愛する資格はないんだ」
だからもう、俺のことは....。
「これがあなたが見たかった光景ですか」
「えぇそうよ。私たちの邪魔をするアルマの哀れな姿を見たかった。あの子がルイスのことを好きになるなんて百年早いのよ」
紅茶を飲んで満足気な顔で本心を語ったアルーシャの姿はとても恐ろしく思えた。
「そこまでして俺と結婚なされたいのですかあなたは...」
「あら?お怒りね。でもルイス。あなたには選択肢がないのよ。あなたの父、ジャック様の言いつけを守らないとここには居られないんの忘れた訳じゃないわよね?」
唇を強く噛み、怒りを堪えた。ルイスはアルマの姿を見ていられず、アルーシャの部屋を出ていった。
城内の人気の無い場所に移動したルイス。階段を何度も拳で殴り、怒りをぶつけた。
落ち着きを取り戻すとその場に座った。
「あの人の言いつけは絶対...。俺は一体どうしたらいいんだ。...アルマすまない。俺にはお前を愛する資格はないんだ」
だからもう、俺のことは....。
あれからルイス様とは必要最低限の会話しかしてません。式の準備も着々と進んでいます。
ボクは式の会場の掃除にバラの手入れをして一日を過ごしています。
「はぁ...。これでやって行けるのかなボク」
落ち込んで掃除をしているとある男性がアルマに話しかけてきた。
「君はここのメイドか?」
「はい。どちら様でしょうか?」
誰だろう。なんか見覚えのある顔をしているおじさんだな。
「私はジャック・バトラー。オリバーの弟で、ルイス・バトラーの父だ」
「え!?も、申し訳ございません。そうとは知らずに失礼な態度を...」
「構わんよ。それより、オリバーはいるかね?」
「はい。ご案内致します」
まさかルイス様のお父様がいらっしゃるなんて。ルイス様に似てとても気品がある方だ。
年齢はボクのお父様とそんなに変わらなそうなのにこんなに違うんだ。
ボクは式の会場の掃除にバラの手入れをして一日を過ごしています。
「はぁ...。これでやって行けるのかなボク」
落ち込んで掃除をしているとある男性がアルマに話しかけてきた。
「君はここのメイドか?」
「はい。どちら様でしょうか?」
誰だろう。なんか見覚えのある顔をしているおじさんだな。
「私はジャック・バトラー。オリバーの弟で、ルイス・バトラーの父だ」
「え!?も、申し訳ございません。そうとは知らずに失礼な態度を...」
「構わんよ。それより、オリバーはいるかね?」
「はい。ご案内致します」
まさかルイス様のお父様がいらっしゃるなんて。ルイス様に似てとても気品がある方だ。
年齢はボクのお父様とそんなに変わらなそうなのにこんなに違うんだ。
応接室に案内し、オリバーを呼びに行ったアルマ。話を聞いたオリバーは直ぐにジャックの元へ。
アルマは応接室には戻らず、厨房でお茶の準備をしていた。
お口に合うといいな。
「アルマ。父さんが来たって噂は本当か!?」
「ルイス様!え、あ、はい!今応接室に。オリバー様も一緒です」
「そうか。なんで今来るんだ....」
怒ってる?もしかして仲が悪いのかな?
「応接室だったな。それとアルマ。あの人は紅茶よりコーヒーだ。砂糖とミルクは必要ない」
「はい...!あ、あの!」
しかしそこにはルイスの姿はもうなかった。
アルマは応接室には戻らず、厨房でお茶の準備をしていた。
お口に合うといいな。
「アルマ。父さんが来たって噂は本当か!?」
「ルイス様!え、あ、はい!今応接室に。オリバー様も一緒です」
「そうか。なんで今来るんだ....」
怒ってる?もしかして仲が悪いのかな?
「応接室だったな。それとアルマ。あの人は紅茶よりコーヒーだ。砂糖とミルクは必要ない」
「はい...!あ、あの!」
しかしそこにはルイスの姿はもうなかった。
ルイス様...。もう少し話したかったな。
コンコンコン
「失礼します」
「ルイスか。久しいな」
「父さん。急にどうしたんですか...」
「そんな事より茶はどうした?客人に対してその態度はなんだ!」
「失礼します。オリバー様、お茶をお持ちしました」
コンコンコン
「失礼します」
「ルイスか。久しいな」
「父さん。急にどうしたんですか...」
「そんな事より茶はどうした?客人に対してその態度はなんだ!」
「失礼します。オリバー様、お茶をお持ちしました」
「おおアルマか。丁度いいタイミングだ」
重苦しい空気が入ってすぐに伝わってきた。震えて危うくお茶をこぼすところだった。
ルイスはアルマが持っていたトレイを受け取り、悲痛な思いを我慢しながら礼を言ってオリバーとジャックにお茶を差し出した。
「助かった」
「ジャック。この子はアルマ・ベイカー。覚えているか?私の友人。ライアン・ベイカーのお嬢さんだよ」
「ほお。あのライアンの...」
「アルマ・ベイカーです。以後お見知りおきを」
深々と頭を下げた。挨拶が済んだあと、応接室を出て厨房で休息をとった。
ジャック様とは挨拶だけで終わった。お父様のこと知っていたんだ。
オリバー様とお父様は友人関係だから知っていて当たり前か。
重苦しい空気が入ってすぐに伝わってきた。震えて危うくお茶をこぼすところだった。
ルイスはアルマが持っていたトレイを受け取り、悲痛な思いを我慢しながら礼を言ってオリバーとジャックにお茶を差し出した。
「助かった」
「ジャック。この子はアルマ・ベイカー。覚えているか?私の友人。ライアン・ベイカーのお嬢さんだよ」
「ほお。あのライアンの...」
「アルマ・ベイカーです。以後お見知りおきを」
深々と頭を下げた。挨拶が済んだあと、応接室を出て厨房で休息をとった。
ジャック様とは挨拶だけで終わった。お父様のこと知っていたんだ。
オリバー様とお父様は友人関係だから知っていて当たり前か。
緊張がほぐれて小腹が空いたアルマは部屋からクッキーを持ってきて空腹を満たした。
食器を片付けようとしていると厨房にルイスがやって来た。
「アルマ。茶を頼む」
「は、はい」
お茶を飲んで落ち着いたのか気が緩んで、いつも身なりを正しているルイスの服や髪が崩れていた。
「疲れた...。あの人と居るとほんと疲れる。話を段々と進めて、俺の気持ちなんてどうでもいいのか」
突如ルイスの口から本音がこぼれ始めた。驚いたアルマはルイスに声をかけたが話をやめなかった。
「二年前に決まった婚約だってそうだ。あれは絶対俺が生まれてから...いや、生まれる前から勝手に決めていたんだ」
今まで我慢していた本音が止まらなくなっていく。話している姿はとても苦しそうだった。
ボクはそれをただ、黙って見て、聞いているしかなかった。
食器を片付けようとしていると厨房にルイスがやって来た。
「アルマ。茶を頼む」
「は、はい」
お茶を飲んで落ち着いたのか気が緩んで、いつも身なりを正しているルイスの服や髪が崩れていた。
「疲れた...。あの人と居るとほんと疲れる。話を段々と進めて、俺の気持ちなんてどうでもいいのか」
突如ルイスの口から本音がこぼれ始めた。驚いたアルマはルイスに声をかけたが話をやめなかった。
「二年前に決まった婚約だってそうだ。あれは絶対俺が生まれてから...いや、生まれる前から勝手に決めていたんだ」
今まで我慢していた本音が止まらなくなっていく。話している姿はとても苦しそうだった。
ボクはそれをただ、黙って見て、聞いているしかなかった。
「あの人はいつも俺の気持ちなんて聞かない。何度だって逆らった。そしていつも怒られた。だから従うしかなかった。バトラー家の執事を命じられた時も父さんが勝手に決めたことだ....」
バトラー家の執事は代々、他の名家から雇うことになっている。だけど、テオ様とアルーシャ様に仕える執事はその年には生まれなかった。
だから同じバトラー家でお茶を様の弟のジャック様の息子であるルイス様が執事としてオリバー様の元に来た。
「お二人に仕える執事が生まれていれば俺はここに来ることはほとんどなかっただろうな。婚約は確実だっただろうけど」
「何故ですか?」
「父さんは昔バトラー家を勘当されている。何をやったかは知らないがな。お爺様が亡くなってから父さんはバトラー家の信用を取り戻そうとして俺とアルーシャを婚約させたんだ」
「オリバー様は反対してなかったんですか?」
バトラー家の執事は代々、他の名家から雇うことになっている。だけど、テオ様とアルーシャ様に仕える執事はその年には生まれなかった。
だから同じバトラー家でお茶を様の弟のジャック様の息子であるルイス様が執事としてオリバー様の元に来た。
「お二人に仕える執事が生まれていれば俺はここに来ることはほとんどなかっただろうな。婚約は確実だっただろうけど」
「何故ですか?」
「父さんは昔バトラー家を勘当されている。何をやったかは知らないがな。お爺様が亡くなってから父さんはバトラー家の信用を取り戻そうとして俺とアルーシャを婚約させたんだ」
「オリバー様は反対してなかったんですか?」
この作家の他の作品
表紙を見る
「また君か。今日はどこを怪我したの?」
「先生は何でいつも外を見ているの?」
*いつも無口な保健室の先生*
*いつも転んでばかりのドジな女の子*
「君は似てる。あの人に...」
「先生はなんであたしに優しくしてくれるんですか?」
☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*
ドジっ子高校生
杉原 奏
(すぎはら かなで)
無口な養護教諭
薬師寺 楓舞
(やくしじ ふうま)
☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*
一つのドジから生まれた運命と恋心
先生×生徒
。.:*・運命の出会いは人を変える.:*・。
‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧
2020年9月15日からオススメ掲載される事になりました
続編『恋の治療は保健室で〜秘密の遠距離〜』もありますので是非、ご覧下さい!
‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧
表紙を見る
真面目で優しくて
そんな彼は私の初恋。なのに....
「お前、地味だな」
その彼はチャラくて、イジワルな人になってました
それでも変わらないところが一つだけあった
「どれだけバカにされてたとしても、今のお前は昔のお前じゃない。自信もっていけ!」
優しいところはそのまま
あの頃の渉くんだった
。・:*:・゚☆地味に生きることにした隠れ美少女。・:*:・゚☆
小鳥遊 雅 Takanasi Miyabi
×
o,+:。☆.*・+。元真面目のS系男子o,+:。☆.*・+。
稲葉 渉 Inaba Wataru
もう一度あなたに恋、してもいいかな?
.*・゚ じれったすぎる初恋ストーリーをもう一度.*・゚
☆*。総合ランキング65位✩.*˚
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…