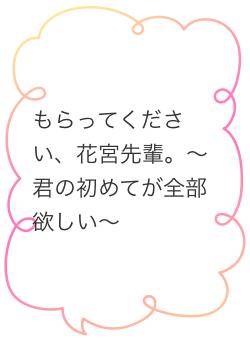「んで、どうしたんだよ」
「別に、話すことねーよ」
「そんな暗い顔してる、話すことしかないだろ」
「人に話すことじゃない」
「じゃあお前、悩んだ時今までどうしてたの?」
「…………」
高田の言葉に沈黙する。
今まで、正直ここまで誰かへの想いで悩んだことはなかった。
深入りせず、興味も持たず、平坦に生きてきたから。
「今まで悩んだことがない」
「は?!じゃあダメだ尚更話せよ!!」
「はぁ?なんで」
「誰かに聞いてもらうと、なんかスッとすんだよ」
「…………」
「なんか吹っ切れることもあるし。とりあえず話してみればいいじゃん」
高田のことは、馬鹿だと思っていた。だけど、コイツは人のいい馬鹿だ。
だから俺なんかに話し掛けて、周りの友達と話すきっかけをくれたり。
一応、信用できる奴だ。
俺はオレンジジュースの缶を開け、一気にごくごくと喉を潤す。そして、高田を見た。
「余計なことを言ったら殴って捨てる」
「物騒すぎだろ」
俺はゆっくりと口を開いた。
※※※※
「いやそれ奏多ダメだろ」
「…………なんでだよ」
「だってお前、自分のこと過大評価しすぎじゃね?」
「うっ」
「立ち直るのって、結局は自分の気持ちと時間薬だろ」
高田はあっけらかんと俺が話した愛理とのことを否定した。
もっとマヌケな答えが返ってくると思っていたから、正直驚く。
けど、まるで誰かを支えることを経験したような物言いだ。
「お前もさぁ、自分を犠牲にしてまでそれでいいの?」
「……しかたねーだろ」
「なにが?」
「愛理を一人にできない」
「違うな」
「は?」
「奏多がいたら、いつまでも先輩は一人だよ」
────どういうことだ?
意味が理解ができなくて黙ると、高田は下を向き口を開く。
「俺の大切な子もさ、昔すげー大変な事件に巻き込まれて」
「……大変な事件?」
「女の子はトラウマになるだろうっていう、理不尽な事件。すげー大騒ぎになってさ。俺小さいながらになんか大変なことがあったって心配で」
「…………」
「支えたいって子供ながらに思ったけど。最初は塞ぎ込んでたあの子も、時間共に強く元気になってさ。きっと本人にしか分からない傷もあるんだろうけど、俺の出る幕はなかった」
「…………」
「助けてほしいって言われたら別だけど。今奏多がしてることは、先輩が立ち上がる力を知らず知らずのうちに奪ってね?」
ズバッと、まるで当たり前のように自分の行動を切られ、自分より馬鹿だと思っていた高田の言葉で視界がやけにクリアになる。
確かに、俺が近くにいることで余計に愛理は俺なしでいられなくなっている。時間薬が上手く作用しなくなる。
そして、俺が差し伸べた手が、逆に愛理を泥沼に沈めてしまったのかもしれない。自分で立ち上がる力を奪ってしまったのかもしれない。
俺をじっと見ていた高田は、さらに話を続ける。そしてニッと笑った。
「先輩とのことちゃんとケジメつけてから片山さんにアタックし直せよ」
「…………」
「そんなごちゃごちゃの思考回路でされる告白なんて、俺でも絶対無理」
「うるせーよ」
「ちゃんとやり直せよ」
背中をバンと叩かれ、空の缶が地面に落ちる。
確かに、話したらなんだかスッとした。
「高田」
「なに」
「さんきゅな」
「……は」
高田が口を開けてポカンとしている。なんだよ、俺がお礼を言うのはおかしいのか?
けど、ちゃんと話そう。決めた。愛理が納得するまで、何度でも話す。
そして、それから俺がすることは────。
※※※※
もう、目で追うのをやめよう。そう思うのに、高田くんに引っ張られていく奏多くんを見つめてしまった。
バチッと合った視線を急いで逸らす。きっと不自然に思われた。
けど、こうやって徐々に他人になっていくしか忘れる方法はない。
放課後のホームルームの後、私は自分の席から立ち上がり、有菜ちゃんの席に向かう。
「凛子……平気?」
「うん、大丈夫だよ」
「……そっか」
有菜ちゃんには、夏休みのうちに電話で奏多くんとの関係を終わらせたことを話した。
その時も何度も大丈夫かと聞かれたけど、私は強がり大丈夫だとしか言わなかった。きっとそれもバレていただろうけど。
思った以上に、同じクラスに奏多くんがいるのは辛い。気持ちを変えるのは簡単じゃないと、改めて実感した。
有菜ちゃんが帰る準備を終え、立ち上がる。私達はそのまま二人で教室から出た。
下校する生徒でいっぱいの廊下を進み、下駄箱で上靴から靴を履き替えていると、後ろから声がした。
それは、今一番聞きたくないもので────。
「ねぇ、もう奏多って帰った?」
本当に、いつもこの人は奏多くんを探している。振り返るとそこには愛理先輩がいて、私をじっと見ていた。なんで私にそれを聞くのかが分からなくて困惑する。
私は一瞬躊躇ったけど、高田くんに引きずられていった奏多くんを思い出し、口を開こうとした時、私と愛理先輩の間に有菜ちゃんが割って入る。
「奏多くんは、」
「すいません。分からないですね」
「……あなたも奏多と同じクラス?」
「はい。けど同じクラスってだけで分からないので、自分で連絡した方が早いと思いますよ」
「そっか、そうだよね」
愛理先輩は有菜ちゃんにふわっと笑顔を向けた後、私に視線を戻す。
「これからは、自分で探すね」
「は、はい」
まるで、私が今後奏多くんに関わることを牽制するような言い方。
けど、もう私は自分で奏多くんへの気持ちに蓋をしようと決めた。もう先輩は何も心配する必要なんてない。
愛理先輩は私の答えを待たず、背中を向けて廊下の向こうに消えていった。
しばらくその背中を眺めていると、有菜ちゃんがくるっとこちらを向いた。その表情は明らかに機嫌を損ねている。
「凛子、本当にいいの?」
「……だから、いいんだって何度も」
「あんな風に人の恋路に口出して自分だけが楽で幸せな場所に行こうとしてる人間に、黙って自分の大切な人をあげちゃうの?」
「それは」
有菜ちゃんの目には、静かな怒りが籠っていて、私は話を続けることはできなかった。
そのまま手を引かれ、廊下の人気がない方へ進んでいく。そして立ち止まると、有菜ちゃんは口を開いた。
「奪わないでって言われて素直に従ってるけど、水瀬は先輩のものじゃない」
「けど二人は幼馴染で、今おばあちゃんが入院してて大変な先輩には奏多くんがいないとダメなんだから」
「じゃあ、水瀬には凛子がいなくて平気なんだ」
「…………」
「水瀬がどれだけ凛子を大切にしてたか、どれだけ男嫌いな凛子に頑張って予約してまでアタックしてたか、自分が一番分かってるでしょ」
ぐっと息が詰まる。
分かってる。私は今まで何度も奏多くんに助けられてきた。何度も想いを伝えてもらったし、こんな自分でもいいんだって、何度も何度も思わせてもらえた。
そこまでしてもらって、私がいなくても平気なんて言えない。
「けど、私がいるから奏多くんと愛理先輩のバランスが崩れるの」
「違う」
「奏多くんが悩んでるとこ見たくない。私がいなければ、先輩も安心していられる。今が辛くても奏多くんだって楽になれる」
「そうじゃないでしょ」
「大体、あの二人の方がずっとお似合いだし、そのうち奏多くんも気付くよ──」
「いい加減にしなよ!!」
突然怒鳴られ、びくりと肩が跳ねる。何で有菜ちゃんがそこまで怒るの?
有菜ちゃんは深いため息を吐くと、私の両肩を掴んだ。
「今凛子が話してること全部、水瀬と先輩の問題でしょ」
「…………それは」
「そんなの二人が解決すればいい話でしょ?凛子と水瀬の恋愛には、全く関係ない問題なの。なのに水瀬が凛子を待たせたりしたからいけないの」
「…………」
「凛子が水瀬と付き合おうと何しようと、先輩は立ち直るときは立ち直るし、ダメなときは自分でなんとかしなければいけないの。とにかく、凛子は関係ない」
────私は、関係ない?
「それに、楽になれるってなに?水瀬は会えなくても毎日凛子に連絡をくれてたんでしょ?」
「楽になれたら、幸せになれるの?」
「水瀬が一度でも、凛子に楽になりたいなんて言ったことあった?」
「何度でも聞くよ、凛子はどうしたいの?」
無理やり蓋をした気持ちをこじ開けるように、有菜ちゃんの言葉が次々と心に入り込んでくる。
あぁ、ダメだ、決めたのに。
あの日、奏多くんへの気持ち、貰った思い出は全部振り落としたはずなのに。
ずきずきと胸が痛む。この痛みがある限り、私はずっと、ずっと────。
「ない」
「凛子」
「言われたこと、ない」
「……うん」
「本当は、先輩に奏多くんを、あげたくない」
蓋が外れて、気持ちが弾けた。
もう、先輩が何と言おうときっと今の私は聞いてあげられない。
「私は、奏多くんが好き」
有菜ちゃんは嬉しそうに笑い、私をぎゅっと抱きしめた。
「知ってるよそんなこと」
「けど私……奏多くんにもうやめようって言っちゃった」
「そんなの簡単でしょ」
「え?」
有菜ちゃんはまるで当たり前かのように口を開いた。
「今度は凛子が予約すればいいじゃん。告白予約」
※※※※
(愛理side)
「奏多、もう少し積極的に友達作ったほうがいいよ」
「なんで」
「今日だって遊びに誘われてたんでしょ?」
「別に問題も起こしてないし、学校でも話す奴いるから平気」
あれは私達が中学生の頃。
夕日の茜色に照らされた住宅街、学校の帰り道に奏多を見つけ駆け寄ると、めんどくさそうに私の提案は却下される。
私が中学3年の時、2年だった奏多はいつもどこか無気力でとにかくクールだった。
昔から何を考えているか分からないこともあったけど、成長しここ数年、余計に奏多が分からない。
────けど、
「危ない」
奏多が私の腕を引いたと同時に、猛スピードで車が私の横を通過する。
そう、奏多は心根が優しいのを私は知っている。だから、何を考えているか分からなくても、根本を知っているからなんとも思わない。
こんな奏多の理解者は私だけ。いつかきっと、私は奏多の彼女になる。
奏多が今、私のことを家族としてみてることは分かってるけど、時間を掛けてそれが変わっていけばいい。
別に、急ぐ必要はないんだ。
────この時はそう思ってた。
※※※※
────本当は、あの子に酷いことをしてるって分かってる。
焦ってたことは確かだけど、奏多が心からあの子のことを想っていたのも分かっているし、急いででも奏多の気持ちを掴みに行かなかった自業自得だってことも、分かっていた。
けど、おばあちゃんがいなくなるかも知れない。お父さんは出張ばかりでなかなか帰ってこないし、友達にだって弱い私は見せられない。
だけど、奏多だけは私の弱さに気付いてくれた。
一人家に引きこもる私に、手を差し伸べてくれた。
私には、やっぱり奏多しかいない。強くそう思った。
「誰にも分かるはずない」
結局あの後奏多に連絡がつかなくて、一人で家に帰ってきた。
最近は奏多と連絡がつかないだけで不安になる。あの子がいつ奏多を奪っていってしまか、いつも意識がピリピリしている。
カバンを投げ出し、一人きりのリビングでぽつりと呟くと、テーブルの上のスマホが震えた。
そこには奏多からのメッセージがあって、私は家から飛び出した。
この作家の他の作品
表紙を見る
三つ子のお世話に明け暮れたことから
他人のお世話を焼くことが
生き甲斐のあかり。
末っ子気質で
他人にお世話を焼かれることに
抵抗のない総一郎。
そんな二人が出会った時
頭のネジのはずれた同居生活が
スタートする……?
クーデレ男子を愛育した結果、溺愛?
****
世話好きな恋愛に疎い系女子
日比野あかり(ヒビノアカリ)
×
末っ子気質クーデレ部活男子
与田総一郎(ヨダソウイチロウ)
****
「あかり可愛い」
「はいはい、分かったから」
2021/8/14〜2024/10/20 一章完結。
表紙を見る
憧れの姉の自慢の妹になりたくて
姉の卒業校を受験するも不合格。
そんな花絵が入学することになったのは
裏社会の跡取りの巣窟、不良ばかりの学校だった……。
そんな学校で
一人のヤクザの跡取りに魅入られた事で
花絵の平凡だった生活は一変していく。
*・゜゚・*:.。..。.:*・・*:.。. .。.:*・゜゚・*
モデルの姉に憧れる平凡少女
吉岡 花絵(よしおか はなえ)
×
組長の一人息子、美しい見た目で容赦ない
天宮 遥(あまみや はるか)
*・゜゚・*:.。..。.:*・*:.。. .。.:*・゜゚・*
「自分でした事の落とし前くらいしっかり付けろよ。それが此処の決まりだろ?」
「これから俺達は末長く、誰よりも深い仲で繋がるんだ」
「花絵、これからお前は俺の女で、共犯だよ」
この恋の落とし前、誰がつける……?
2023/03/17公開、完結
表紙を見る
正義感が強く、間違ったものに対して
黙っていられない奈湖。
しかし、そのせいで中学時代
無視の対象になってしまう。
そして、こんなに悲しい思いをするなら
もう黙っていよう、周りに合わせようと
変わることを決意する。
しかし、高校ではみんなが恋愛に夢中。
周りから浮きたくない奈湖は
無理をして初カレを作ろうとするが
同じ委員会の花宮先輩は
そんな奈湖がとてもとても心配で──?
****
正義感強め妹力抜群ガール
小森奈湖 (こもり なこ)
×
優しく穏やか執着系王子
花宮秀 (はなみや しゅう)
****
「ねぇ奈湖、俺に奈湖のはじめてを全部ちょうだい」
「大切に、大切に貰うから」
「恋人同士はキスをするんだよ。はじめてなんだから、ちゃんと覚えて」
「俺に抱きしめられてるのに、他の男の名前を出さないで」
「これからも俺と、たくさんはじめてを経験しようね」
──花宮先輩、溺愛注意報出てます。
2021/05/14〜07/21
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…