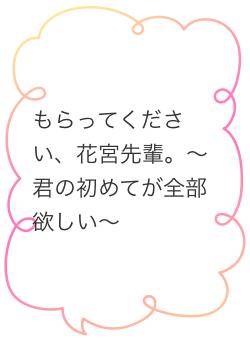「家族だと思ってるからとか、近くで支えなきゃ、とか。結局それって本人次第で」
「…………」
「手の差し伸べ方を間違えると、支えなしでは立てなくなって、取り返しつかなくなるんじゃないのかって」
「……奏多くん?」
「俺なら、不安定な時を支えられるって。けどそれは過大評価だったのかも」
────奏多くん、少し痩せた?
その言葉を聞き、奏多くんと合わせた視線から少しの躊躇いを感じた。そして、元から細かった身体がほんの少し細くなっている気がして、胸がざわつく。
奏多くんが言いたいのは、愛理先輩のことだ。
きっと、愛理先輩はずっと不安定なんだ。けど、そこにはきっとおばあちゃんのことだけではなく、私のことも入っている。
私が奏多くんのそばにいる限り、先輩が不安定になり、回り回って奏多くんが辛くなるんだ。
ずきずき、胸が痛い。何故か息も浅くなる。何にも言えない。
「あのさ、凛子」
「な、なに?」
「告白、していい?」
「────え?」
カシャッと音がして、気付くとブランコから立ち上がった奏多くんが私の目の前に立っていた。じっと真剣な目で、私を見つめている。
呆気に取られた私は、何も言葉を発することができなかった。今?なんで……?
「奏多くん、ま、待って」
「待ちたくない」
「ねぇ、先輩はっ」
「俺の気持ちは、俺のものだから」
────奪わないで。
脳内で愛理先輩の言葉が反芻する。
知ってるよ、分かってる。奏多くんの気持ちは奏多くんのものだし、私の気持ちは私のもの。それが大前提だ。
けど、それなら私達が足踏みする理由は何?大切なことなんじゃないの?奏多くんにとって。
だから、そんな苦しそうな表情なんでしょ?何かに抵抗するように、なのに手放さないように、ゆらゆらと揺れている。
「凛子、俺は」
その時、スマホから着信音が鳴った。それは私のものではなく奏多くんの物で。
けど、一向に奏多くんは電話に出ようとしはしない。
「奏多くん、電話」
「平気」
「ねぇ、奏多くん」
「俺は今、凛子と話したい」
「分かったからっ」
「凛子────」
「じゃあ、なんでそんなに辛そうなの」
着信が止まる。私の問いに、奏多くんはぐっと押し黙った。
私の胸に、一つの答えが浮かび上がる。ずっと目を逸らして、考えないようにしていた一つの答えが。
私は奏多くんの手首を掴み、顔を下から覗き込む。
そして、ひゅっと息を吸い込み、その考えを口にした。
「奏多くん、もう、やめようか」
「…………は?」
「私……奏多くんとは付き合えない」
────元より本当は、愛理先輩が座るべき席だったんだ。
そこに私が座ろうとするから、本来あったバランスが崩れて不安定になった。
私は、自分のせいで奏多くんが間接的に影響を受けて、想いの狭間で苦しんでいるのに耐えられない。自分のせいで痩せ細っていくことに、どうしても耐えられない。
好きだから健康でいてほしい、好きだから苦しまないでほしい、好きだから幸せでいてほしい。笑っていて、お願い。
こんなに風に誰かに対して、想い願う日がくるなんて思っていなかった。
私の声は震えていた。奏多くんは目を大きく見開くと、私の肩を掴む。
「嘘吐くな」
「本当だよ」
「じゃあなんで目を合わせないんだよ」
「合わせたく、ないから」
「俺達、同じ気持ちだっただろ?」
思わず頷きたくなる自分を止める。そして、私の肩に乗った奏多くんの手をゆっくりと下ろす。
バランスを崩したらダメだ。私の存在は本来奏多くんの中になかったはずなんだから。
あの日、私がたまたま人助けなんかして、偶然が重なってしまっただけで、本当は奏多くんみたいな素敵な人が、私のことを好きになるなんてこと、あるわけないことだったんだから。
「もう、好きじゃなくなった」
出来るだけ傷付けるように、わざと酷い言葉を選んだ。そして私の思惑通り、奏多くんは酷く歪んだ表情をした。
お願い、もう私を嫌いになった方が楽になれる。絶対に幸せになれるよ。
私は泣かないようぎゅっと拳を握りしめ、わざとへらりと笑顔を作る。
「好きになってくれて嬉しかった。ありがとう」
カシャンとブランコから立ち上がる。奏多くんは下を向き動かない。
早く行かなきゃ、この場からいなくならなきゃ。そうしないと、今にも泣きそうだ。
「ばいばい、奏多くん」
奏多くんは振り返らなかった。
私は奏多くんをとり残し、その場から駆け出した。気を抜くと振り返りたくなる身体を抑え、スピードをどんどん上げる。
駅前を抜け、住宅街を抜け、必死で走る。
好きという気持ちを振り落とすように、宝物みたいな思い出を、奏多くんがくれた優しい気持ちを、全て振り落として、忘れてしまうくらいに。
ぼろぼろと涙が溢れる。
苦しい、悲しい、好き、ダメ。ぐるぐると脳内を色んな気持ちが回る。
「はぁっ……はぁっ……」
やっと家の前に辿り着き、ただいまも言わずに自分の部屋に駆け込んだ。
そしてベッドにダイブして頭から布団をかぶる。
「忘れろっ……忘れてっ……」
傷つけたくなかった。好きだと言いたかった。
本当は、奏多くんが、好きだ。
けど、忘れなきゃならない。私は好きな人に幸せになってほしい、さっき自分で決断したんだから。
「……っ、……ふ、ぅ」
────忘れるんだ。
だから、今だけは泣かせて。
ばいばい、奏多くん。
※※※※
────有菜ちゃんや、友達からの誘いを断り、失恋の痛みに耐えるだけの長い夏休みが終わった。
あれから奏多くんからの連絡は途切れた。
自分が望んだこととはいえ、スマホを見ると連絡がきていないか期待をしてしまう自分がいた。
胸の痛みは一向に消えないし、気を抜くと涙が溢れてしまう時もあった。
失恋がこんなにも辛いなら、もう私は一生恋をしなくていいとさえ思う。
たくさんの生徒でごった返す朝の下駄箱で、上履きを履き、人気の少ない静かな階段から重い足取りで教室へ向かっていると、後ろから肩を叩かれた。
振り返ると陸くんで、わざわざ人気のない階段を選んだ私を追ってきたんだと思う。
「おはよう。お前後ろ姿から元気ねぇな」
「おはよう陸くん。そんなことないよ」
「……あれから何かあったか?」
「え」
「水瀬と」
────そうだった。
あの花火大会以降、私は陸くんからチャットがきて、奏多くんとのことを聞かれても曖昧に答えていた。
私はその場に立ち止まり、陸くんの腕を引っ張って廊下の隅に移動した。
「やめることにしたんだ」
「は」
「もう奏多くんのこと好きでいるの。ほら、奏多くんには私より合う人絶対にいるし」
「お前さ、本気でそれ言ってんのか」
「……本気だよ」
「下手くそな笑顔で、何我慢して嘘ついてんだよ」
「…………」
「俺の前で辛いのに笑われんの、ムカつくんだよ」
陸くんは、苛立ちを隠さず私に向けてきた。その瞳はゆらゆらと熱く揺れていて、思わずそらす。
なんでそんなこと言われなきゃいけないの?私は私の意思で終わりにしたの。辛いのに笑ってないと、今にも弱音を吐きそうなの。
もう放っておいてほしくて、その場から歩き出そうとすると、腕を掴まれ引き止められる。
ハッと陸くんの顔を見上げると、その表情は花火大会で見た、どこか切なさを含んだ物だった。
「俺の前では、強がらなくていいから」
その言葉が引き金だった。ずっと我慢していた涙が、私の目からはほろほろと溢れ、頬を伝う。
なんでそんなことを言うの?そんなに優しいことを言われたら、止まらなくなる。
両手で顔を覆った私の頭を、陸くんは優しく撫でる。そして、少しだけ苦しそうな陸くんの声が頭の上から降ってきた。
「頼むから幸せになって」
その時だった、キュッと床を踏みしめる音がその場に響く。
そして、私の頭の上に乗った陸くんの手が空に浮いた。
「────なに泣かせてんの」
その声は、私がずっと焦がれていた物で。反射的に顔を上げると、そこには陸くんの腕を浮かんで睨む奏多くんがいた。その目には怒りが滲んでいて、私は息を呑む。
なんでここに奏多くんが?
動揺する私を他所に、陸くんは一瞬目を見開いた後、自分の腕を掴む手を振り払い、冷たい言葉を吐く。
「関係なくね?」
「……泣かせるな」
「こいつとの約束断って、他の女と花火大会行ってた奴が何言ってんだよ」
「っ……」
バチッと奏多くんと視線が合う。私が二人を見てしまったことを、奏多くんは知らない。私は気まずくてその視線をすぐにそらす。
陸くんは怒りを込め、話を続ける。
「凛子がどんな気持ちでお前らのこと見てたか、知ってんのかよ」
「…………」
「大切な物一つ選べずに、凛子に決断させて辛い思いさせたくせに、口出してんじゃねぇよ」
「陸くん、やめて」
「今、俺の好きな女を泣かせてるのはお前だろ」
遠くの廊下で、生徒達の騒めく声がする。
その場が静まり返り、誰も声を発することはなかった。
それくらい私は驚いていた。奏多くんも同じなんだと思う。
好きな女?それって、待って────。
「陸くっ」
────グイッ
私の言葉を遮るように手を引かれ、奏多くんを置いてその場から駆け出す。
特別教室しかない階まで走り、音楽室の前でやっと陸くんは立ち止まる。そしてやっと陸くんは振り返った。
その表情はあまりにも真剣で、私の心臓が大きく鳴る。
「……ま、待って。陸くん、冗談だよね」
「冗談であんなこと言わねぇだろ。好きだから助けてたし、好きだから嫌がられてでも和解したかった」
「でもっ、それなら私……陸くんに色々話して……」
「俺は好きな女には幸せになってほしい」
「…………」
「本当は自分が幸せにしたいけど、今それが凛子の幸せに繋がらないって分かってるからな」
陸くんは私の手を握る手にぎゅっと力を込めた後、すぐにそれを離す。
そして、いつものように、なんでもないように笑った。
「俺はいつだって凛子の味方だ」
「…………陸くん」
「だから、凛子は余計なこと考えずに自分の気持ちに素直でいろよ。両想いなんだから」
「ねぇってば」
「煽ったから、どうにかうまく転がればいいんだけど」
「聞いて」
好きな人に幸せでいて欲しい。その気持ちは痛いほど分かる。
けど、自分にそんな思いを抱いてくれている人がいるなんて、思ってもみなかった。
私は陸くんの肩を掴み、陸くんの言葉を遮る。
「陸くん、ありがとう」
陸くんは私の言葉に驚いたように目を見開くと、切なそうに目を伏せた後、またなんでもないように笑った。
「顔、りんごみたいに赤いぞ」
この笑顔の反対側には、色んな想いがあったんだ。それを知り、私の心はどうしようもなく苦しくて嬉しくなった。
けど、私は陸くんを好きにはなれない。
好きな人に幸せになってほしい、私も同じなんだよ陸くん。
だから、私もその幸せを願ってこの想いに蓋をするしかないんだよ。
────校舎にチャイムが鳴り響いた。
※※※※
(奏多side)
────ドーン、パラパラ…
夏の夜空に上がる、色とりどりの花火。様々な色や形、上がるたびに上がる見物客からの歓声。
確かに、キレイだと思う。
けど、本当なら隣にいるはずだった人のことを考え、俺の脳内はずっと沈んでいた。
「……愛理?」
「…………」
「どうした。体調悪い?」
「……ううん、平気」
今隣にいるのは幼馴染の愛理で、凛子ではない。
愛理はばあちゃんが入院して、俺への執着が日に日に増している。夏休みは出来るだけ一緒に過ごしているが、気分の波は激しい。
今日、愛理の父さんに頼まれ花火大会に連れ出してはみたものの、最初は楽しそうにしていたのに、途中で一度はぐれてからずっと元気がない。
愛理は愛想がなくて人に対して興味のない俺が、周りから誤解されないよういつも見えないところで手を貸してくれていた。
だから、俺にとってこんな愛理を放っておくという選択肢はない。
────けど。
「(何も好転しない)」
この作家の他の作品
表紙を見る
三つ子のお世話に明け暮れたことから
他人のお世話を焼くことが
生き甲斐のあかり。
末っ子気質で
他人にお世話を焼かれることに
抵抗のない総一郎。
そんな二人が出会った時
頭のネジのはずれた同居生活が
スタートする……?
クーデレ男子を愛育した結果、溺愛?
****
世話好きな恋愛に疎い系女子
日比野あかり(ヒビノアカリ)
×
末っ子気質クーデレ部活男子
与田総一郎(ヨダソウイチロウ)
****
「あかり可愛い」
「はいはい、分かったから」
2021/8/14〜2024/10/20 一章完結。
表紙を見る
憧れの姉の自慢の妹になりたくて
姉の卒業校を受験するも不合格。
そんな花絵が入学することになったのは
裏社会の跡取りの巣窟、不良ばかりの学校だった……。
そんな学校で
一人のヤクザの跡取りに魅入られた事で
花絵の平凡だった生活は一変していく。
*・゜゚・*:.。..。.:*・・*:.。. .。.:*・゜゚・*
モデルの姉に憧れる平凡少女
吉岡 花絵(よしおか はなえ)
×
組長の一人息子、美しい見た目で容赦ない
天宮 遥(あまみや はるか)
*・゜゚・*:.。..。.:*・*:.。. .。.:*・゜゚・*
「自分でした事の落とし前くらいしっかり付けろよ。それが此処の決まりだろ?」
「これから俺達は末長く、誰よりも深い仲で繋がるんだ」
「花絵、これからお前は俺の女で、共犯だよ」
この恋の落とし前、誰がつける……?
2023/03/17公開、完結
表紙を見る
正義感が強く、間違ったものに対して
黙っていられない奈湖。
しかし、そのせいで中学時代
無視の対象になってしまう。
そして、こんなに悲しい思いをするなら
もう黙っていよう、周りに合わせようと
変わることを決意する。
しかし、高校ではみんなが恋愛に夢中。
周りから浮きたくない奈湖は
無理をして初カレを作ろうとするが
同じ委員会の花宮先輩は
そんな奈湖がとてもとても心配で──?
****
正義感強め妹力抜群ガール
小森奈湖 (こもり なこ)
×
優しく穏やか執着系王子
花宮秀 (はなみや しゅう)
****
「ねぇ奈湖、俺に奈湖のはじめてを全部ちょうだい」
「大切に、大切に貰うから」
「恋人同士はキスをするんだよ。はじめてなんだから、ちゃんと覚えて」
「俺に抱きしめられてるのに、他の男の名前を出さないで」
「これからも俺と、たくさんはじめてを経験しようね」
──花宮先輩、溺愛注意報出てます。
2021/05/14〜07/21
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…