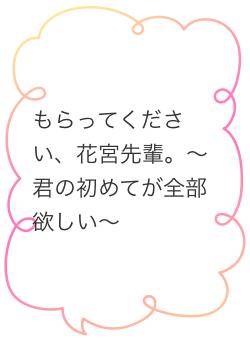ずっと今日見た二人のことを思い出し、モヤモヤと夏休みを過ごしながら、奏多くんと連絡を取るのは嫌だ。
だから、愛理先輩が不安定だから一緒に来たんだと、奏多くんの口から聞きたい。
私が奏多くんに向かい、足を踏み出したその時だった。
「────なにしてるの?」
突然背後から声をかけられ、振り返る。
そこには、冷たい視線をこちらに向ける愛理先輩が立っていた。
「……奏多くんに、用が」
「そっか。けど、その前に私と話そうよ」
「え?」
「あっち。人少ないから」
愛理先輩が先に歩いて行ってしまい、私は後に続くしかなかった。
辿り着いたのは、出店の後ろの人の少ない路地だった。
「……先輩、大丈夫なんですか?」
「ん?なにが?」
「奏多くんから、少しだけ事情を聞いて」
「あー、そうなんだ……大丈夫では、ないかなぁ」
先輩は視線を落とし、表情が読めない。前話した時と雰囲気が変わっていて、初めて名前を呼ばれた時のような明るさがない。
本当に、大丈夫ではないんだ。
「片山さんさ」
「……はい」
「お父さんも、お母さんも普通に揃ってるんでしょ?」
「……は、はい」
「私にはね、おばあちゃんが死んじゃったら、仕事ばかりで家に帰ってこないお父さんしかいないの」
一気に空気が重くなる。愛理先輩の悲しさが伝わってきて、何も言えない。
私が無言になると、先輩は話を続けた。
「学校に友達はいるよ?けど、心から私を理解してくれるのは、ずっと近くにいてくれた奏多だけなの」
「……奏多、くんが」
「片山さんは私にないものを持ってるでしょ?けど、私には……奏多しかいないの」
まるで、深い悲しみの底に引き摺り込まれるようだった。
そんな錯覚に陥ってしまうほどに、私は何も言えはしなかった。
先輩の家庭の事情は少しは知っている。そして、奏多くんのことを大切に思っていることも。
────けど、私だって奏多くんが好きだ。私が好きなのは、どこを探したって奏多くんしかいない。
「ご、めんなさい……けど、私」
言葉を続けようとした。けど、私と視線を合わせた愛理先輩の目から、大粒の涙が溢れたのを見て、私はぐっと言葉を飲み込んでしまった。
なんで、どうして、ずるい。なんで泣くの……?
けど、先輩はおばあちゃんを失いそうで、そして奏多くんまで近くからいなくなってしまったら、一体どうなってしまうの?
脳内をぐちゃぐちゃになった感情がぐるぐると回っている。私は、どうしたら────。
「お願い……」
「……え?」
「お願い、私から奏多を奪わないで」
愛理先輩の言葉はあまりにも悲しくて、あまりにも一人の女の子として弱々しくて、けど、私の心に突き刺すのには充分な強い言葉だった。
愛理先輩は、涙を拭いながら私の横をすり抜け、いなくなってしまった。
「なに、それ」
私は、その場に脚を縫い付けられたように動けないままだった。
胸が痛い、苦しい。どうして?なんで?伝えることさえ私は許されない?
スマホが鳴り、力の入らない手でそれをタップし電話に出る。
すると、すぐに怒ったような声が聞こえた。
『おい凛子!!おまえ今どこにっ』
「陸、くん」
『……は、待て、本当今どこにいるんだよ』
「出店の裏の、路地」
「…………5秒で行く」
通話が切れてすぐに、本当に陸くんは息を切らし、5秒程で来てくれた。
そして、その場に立ちすくむ私を見て、両肩を掴む。
「凛子、どうした。水瀬は?」
「……陸くん、私」
「なんだよ」
「私は、奏多くんに、好きって言ったらダメなのかな」
「は?」
「奪うってなに?奏多くんも私を好きって言ってくれた、私も奏多くんを好きになった……なのにっ」
「…………」
「私が奏多くんと付き合うことで、どうしようもなく悲しい思いをする人がいるのっ……」
ずっと我慢していた気持ちが決壊し、それが涙になって溢れ出す。
助けて、苦しい。初めて人を好きになったの。好きだって言われて幸せで、嬉しかった。奏多くんの彼女になりたかった。隣を歩きたかった。
けど、私のせいで愛理先輩は一人になるの?
どの選択をしたら正解なの?私だけが幸せになんて、なっていいの?
「落ち着け凛子」
突然、身体を引き寄せられ、大きな身体に包まれた。ぎゅっと力を込められて、それはまるで大丈夫だと私に言い聞かせているようで、余計に涙が溢れる。
「全部、決めるのはお前と水瀬だよ」
「…………」
「大丈夫だ。どんな道を選んでも、凛子は間違ってないし悪者じゃない」
ドンッと大きな音がした。花火が上がったんだ。その光は陸くんの顔を照らした。そして気付く。陸くんの表情が、どうしようもなく切なそうなことに。
「……絶対、何があっても、俺は凛子の味方だから」
ちぎれた恋心を拾い集めるように、陸くんは優しい言葉をくれた。
※※※※
「待って、なにそれ」
「言った通り」
「なんで先輩にそんなこと言われなきゃいけないの?恋愛なんて、本人達次第でしょ」
「……そう、なんだけどね」
夏休みも終盤に差し掛かった。
炎天下の中涼しい場所を求め、学校近くのファミレスに集合した私と有菜ちゃんは、ドリンクバーを頼み、最初は夏休みにあった楽しいことを話していたはずなのに、奏多くんの話になった途端とても暗い雰囲気になってしまった。
というより、有菜ちゃんはキレている。ミルクティーを勢いよく飲み干し、私をズバッと指さした。
「凛子も水瀬くんも両思いなんでしょ?というより、水瀬くんが頑張って凛子を振り向かせた」
「……うん」
「どんなに弱ってようと、どんなに相手を好きだろうと、他人の恋に水を差すって一番の罪だと思うんだけど」
「…………」
「凛子が、凛子の意思で選びなよ」
────陸くんも有菜ちゃんも、私の意思を優先してくれる。
私の意思で決めなきゃならないのは分かってる。けど、愛理先輩のあんなに悲しそうな姿を見てしまったら、どうしても踏みとどまってしまいそうになる。
きっと、有菜ちゃんならそんな言葉吹き飛ばして進んでいくんだろうな。
「水瀬くんとは?やりとりしてるの?」
「うん。毎日連絡くれるよ。電話もしてる」
「……水瀬の気持ちはブレてないじゃん。まぁ、先輩にお節介焼きすぎだとは思うけど」
奏多くんからは、会えない代わりに毎日連絡がくる。
なんでもないやりとりや、時折ドキッとするような気持ちをぶつけられたり、電話ではあれこれ楽しいことを話した後に、すごく会いたいと打ち明けられたり。
打ち明けることにブレーキが掛かる一方で、好きと言う気持ちは日々心に降り積もっていく。
喉元まで出る、奏多くんが好きと言う言葉を飲み込み、私はいつも曖昧に返事をすることしかできない。
もやもや、ずきずき、心の中がずっと落ち着かない。
随分前にりんごジュースを飲み終えたグラスで、氷が溶けてカランと音が鳴った。
「自分の傷を他人任せに癒してもらおうなんて、甘いんだよって言ってやりな」
「……言えるわけないでしょ」
「あーあ、もどかしい」
唇を尖らせる有菜ちゃんを見て眉を下げる。すると、テーブルに置いていた私のスマホの画面にチャットの通知が。
私はその画面を見て、目を見開いた。
※※※※
夕方5時、夏の日は長くてまだ空は暗くなる素振りを見せない。
私は家の最寄り駅前で、そわそわと人を待っていた。
すると、ちょうど電車が到着したらしく、サラリーマンやら夏休みの学生やらがどんどん駅から出てきた。
その人の波から、私はたった一人を見つけ手を上げる。
「奏多くん」
私が名前を呼ぶと、人混みの中、誰かを探すように周りを見渡していた奏多くんと視線が合った。
すると奏多くんは猫のような目を大きく見開き、嬉しそうに口角を上げながらこちらに歩いてくる。
「久しぶり。悪い待った?」
「ううん、全然」
「……すげー」
「え、どうしたの?」
「本物の凛子だ。うれしー」
口元を手で覆い、嬉しそうにする奏多くんに私まで嬉しくなってしまう。
今日の昼間、有菜ちゃんとファミレスにいるときにチャットがきて、突然今日会いたいと約束を取り付けられた。
とても嬉しかった反面、愛理先輩とのこともあったから、素直に喜びきれない自分がいた。
「6時には家に送るから」
「うん」
二人で横に並び、ゆっくりと歩き出す。久しぶりに電話ではなくちゃんと会って話すから、緊張して顔を見るのが恥ずかしい。奏多くんも同じなのか、少しだけ口数が少なかった。
そして、駅の近くに人気の少ない小さな公園を見つけ、どちらともなく中に入る。
ブランコに座る奏多くんを見て、同じように私もブランコに座った。
すると、私が座ったのと同時に奏多くんが口を開いた。
「まさか、こんなに会えないと思ってなくて焦った」
「えっ……まぁ、確かにそうだね」
「毎日電話してもチャットで話してても、足りない」
「…………」
「めちゃくちゃ会いたかった」
奏多くんは気持ちをストレートに伝えてくるから、こっちが恥ずかしくなる。ボボっと、赤くなる私の頬を見て、奏多くんは少しだけ満足そうに口角を上げる。
会えなくても、愛理先輩のが近くにいても、奏多くんの気持ちは少しも揺らいでいないんだ。それが透けて見えるくらい、奏多くんの言葉はまっすぐだ。
私は赤くなった顔を隠すように少し俯きながら口を開く。
「今日、突然大丈夫だったの?」
「うん。まぁ、平気」
「……そっか」
「……多分、俺が自分のこと過大評価してたのかも」
────過大評価?
どういうことだろう。私がその言葉の意味が理解出来ずに黙ると、奏多くんは話を続ける。
「家族だと思ってるからとか、近くで支えなきゃ、とか。結局それって本人次第で」
「…………」
「手の差し伸べ方を間違えると、支えなしでは立てなくなって、取り返しつかなくなるんじゃないのかって」
「……奏多くん?」
「俺なら、不安定な時を支えられるって。けどそれは過大評価だったのかも」
────奏多くん、少し痩せた?
その言葉を聞き、奏多くんと合わせた視線から少しの躊躇いを感じた。そして、元から細かった身体がほんの少し細くなっている気がして、胸がざわつく。
奏多くんが言いたいのは、愛理先輩のことだ。
きっと、愛理先輩はずっと不安定なんだ。けど、そこにはきっとおばあちゃんのことだけではなく、私のことも入っている。
私が奏多くんのそばにいる限り、先輩が不安定になり、回り回って奏多くんが辛くなるんだ。
ずきずき、胸が痛い。何故か息も浅くなる。何にも言えない。
「あのさ、凛子」
「な、なに?」
「告白、していい?」
「────え?」
カシャッと音がして、気付くとブランコから立ち上がった奏多くんが私の目の前に立っていた。じっと真剣な目で、私を見つめている。
呆気に取られた私は、何も言葉を発することができなかった。今?なんで……?
「奏多くん、ま、待って」
「待ちたくない」
「ねぇ、先輩はっ」
「俺の気持ちは、俺のものだから」
────奪わないで。
脳内で愛理先輩の言葉が反芻する。
知ってるよ、分かってる。奏多くんの気持ちは奏多くんのものだし、私の気持ちは私のもの。それが大前提だ。
けど、それなら私達が足踏みする理由は何?大切なことなんじゃないの?奏多くんにとって。
だから、そんな苦しそうな表情なんでしょ?何かに抵抗するように、なのに手放さないように、ゆらゆらと揺れている。
「凛子、俺は」
その時、スマホから着信音が鳴った。それは私のものではなく奏多くんの物で。
けど、一向に奏多くんは電話に出ようとしはしない。
「奏多くん、電話」
「平気」
「ねぇ、奏多くん」
「俺は今、凛子と話したい」
「分かったからっ」
「凛子────」
「じゃあ、なんでそんなに辛そうなの」
着信が止まる。私の問いに、奏多くんはぐっと押し黙った。
私の胸に、一つの答えが浮かび上がる。ずっと目を逸らして、考えないようにしていた一つの答えが。
私は奏多くんの手首を掴み、顔を下から覗き込む。
そして、ひゅっと息を吸い込み、その考えを口にした。
「奏多くん、もう、やめようか」
「…………は?」
「私……奏多くんとは付き合えない」
この作家の他の作品
表紙を見る
三つ子のお世話に明け暮れたことから
他人のお世話を焼くことが
生き甲斐のあかり。
末っ子気質で
他人にお世話を焼かれることに
抵抗のない総一郎。
そんな二人が出会った時
頭のネジのはずれた同居生活が
スタートする……?
クーデレ男子を愛育した結果、溺愛?
****
世話好きな恋愛に疎い系女子
日比野あかり(ヒビノアカリ)
×
末っ子気質クーデレ部活男子
与田総一郎(ヨダソウイチロウ)
****
「あかり可愛い」
「はいはい、分かったから」
2021/8/14〜2024/10/20 一章完結。
表紙を見る
憧れの姉の自慢の妹になりたくて
姉の卒業校を受験するも不合格。
そんな花絵が入学することになったのは
裏社会の跡取りの巣窟、不良ばかりの学校だった……。
そんな学校で
一人のヤクザの跡取りに魅入られた事で
花絵の平凡だった生活は一変していく。
*・゜゚・*:.。..。.:*・・*:.。. .。.:*・゜゚・*
モデルの姉に憧れる平凡少女
吉岡 花絵(よしおか はなえ)
×
組長の一人息子、美しい見た目で容赦ない
天宮 遥(あまみや はるか)
*・゜゚・*:.。..。.:*・*:.。. .。.:*・゜゚・*
「自分でした事の落とし前くらいしっかり付けろよ。それが此処の決まりだろ?」
「これから俺達は末長く、誰よりも深い仲で繋がるんだ」
「花絵、これからお前は俺の女で、共犯だよ」
この恋の落とし前、誰がつける……?
2023/03/17公開、完結
表紙を見る
正義感が強く、間違ったものに対して
黙っていられない奈湖。
しかし、そのせいで中学時代
無視の対象になってしまう。
そして、こんなに悲しい思いをするなら
もう黙っていよう、周りに合わせようと
変わることを決意する。
しかし、高校ではみんなが恋愛に夢中。
周りから浮きたくない奈湖は
無理をして初カレを作ろうとするが
同じ委員会の花宮先輩は
そんな奈湖がとてもとても心配で──?
****
正義感強め妹力抜群ガール
小森奈湖 (こもり なこ)
×
優しく穏やか執着系王子
花宮秀 (はなみや しゅう)
****
「ねぇ奈湖、俺に奈湖のはじめてを全部ちょうだい」
「大切に、大切に貰うから」
「恋人同士はキスをするんだよ。はじめてなんだから、ちゃんと覚えて」
「俺に抱きしめられてるのに、他の男の名前を出さないで」
「これからも俺と、たくさんはじめてを経験しようね」
──花宮先輩、溺愛注意報出てます。
2021/05/14〜07/21
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…